- ↑にメニューバーが現れない場合、
- ←クリックして下さい。
- パソコンの文化 2000.04.16記 更新 - 2007.12.02 (2016.06.21修正)
- 更新トピック(2007.04.28)
- → パソコンの文化21 パソコンを形作ったアプリケーションソフト(その7)
- - ATOK(ジャストシステム)
- お断り:
- 本記事は、以下に示す参考文献を元に書き著しました。
- 随所に参考文献からの引用をしています。営利行為ではないので許される範囲と考えています。
- この件お含みおきいただき、ご了承下さい。
- 本記事は、以下に示す参考文献を元に書き著しました。
-
- はじめに (2000.4.16)
- 自分は、パソコンオタッキーなのか?と時々自問することがあります。
- パソコンオタクは、自分でマザーボードをいじったりCPUを入れ替えたりする人たちだと思っています。
- 私はどちらかというと文書に凝ったり、ホームページ開いたり、データ整理するのにコンピュータの活用を見い出している人間ですので、コンピュータを「文房具」という意識で見ています。
- それでも、毎年2月に行われるマックワールドにはここ7年はかかさず参加していますので他の人に比べたらコンピュータに狂ってるかもしれません。なにせここ7年でコンピュータに投資したお金は300万円はくだらないんですから。
- 今年(2000.02)もMac World Expo/Tokyo2000に参加しました。
- マックの詳しい話はあまり興味が持たれないと思いますので、我々の世代のパソコン文化というものについて話してみたいと思います。
- 話の骨子は以下の通りです。
- ●パソコンは40代の米国オヤジたちが作り上げた文化
- ●コンピュータとパソコンは根本的に違う
- ●IBM - 巨大帝国
- ●マイクロソフトの急成長
- ●アップルのアップルらしさ
- ●日本のパソコン事情
- 自分は、パソコンオタッキーなのか?と時々自問することがあります。
- はじめに (2000.4.16)
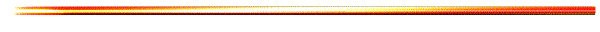
- ↑にメニューバーが現れない場合、
- ←クリックして下さい。
- ↑にメニューバーが現れない場合、
-
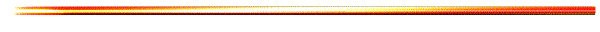
- ↑にメニューバーが現れない場合、
- ←クリックして下さい。
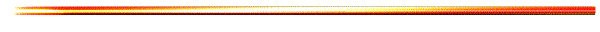
- ↑にメニューバーが現れない場合、
- ←クリックして下さい。
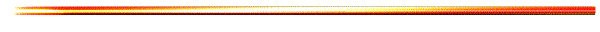
- ↑にメニューバーが現れない場合、
- ←クリックして下さい。
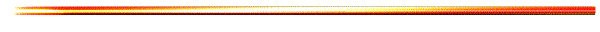
- ↑にメニューバーが現れない場合、
- ←クリックして下さい。
- 6. パソコンの文化6 (2000.06.02)
- 6-1. IBMのパソコン参入
- アップルの成功を横目で見ていたIBMは、当初パソコンの存在を軽く考えていました。決して自分たちの牙城 = 大型コンピュータを中心としたビジネスは崩れないと確信していました。
- IBMは逆に、コンピュータがパソコンの社会になることを決して望んでいなかったし、そうさせてはならないとも思っていました。そうならないためにあらゆる手を打ってもきました。
- 彼らの戦略は、メインフレーム(大型コンピュータ)の市場の安泰にあり、メインフレームにつながる端末としてパソコンを位置づけていました。当時のパソコンの性能ならば大型コンピュータを脅かす要素など何一つなかったのです。メインフレームのお客へのホンのサービスのつもりで、超大企業ビックブルー(IBM、会社のロゴが青い文字なので米国ではIBMのことをビックブルーと言っています)はパソコン市場に参入したのです。
- IBMは、できるだけ手間ひまかけず超特急でパソコンを作り上げるために、開発を100%外部に任せ、規格のほとんどを公開しました。規格を公開することによりいろいろなメーカが安い価格でものを作ってIBMに持ってくると考えたからです。
- パソコンを動かすオペレーティング・システム(OS)についてもそのように考え、2、3のソフトウェア会社に依頼を申し込んでいました。その要求にうまく取り入ったのが若き実業家ビル・ゲイツだったのです。そう、彼は実業家だったのです。彼は、パソコン用に移植が完了していたBASICとパッケージに加え、MS-DOS(マイクロソフト・ディスクオペレーティングシステム)をにわか作りでまとめ上げ、IBMに取り入ってしまったのです。
- マイクロソフト社のその後の急成長はご存じの通りです。IBMもマイクロソフトがここまで急成長をするとは思わなかったでしょう。
- そして自分自身が凋落することも・・。
- ■ IBMパソコン戦略の誤算
- IBMは、パソコンを開発するに当たってパソコンの仕様、技術資料をすべてを公開しました。CPUとデータのやりとりをするBIOS(基本入出力)のプログラムソースまでも公開しました。ただし、IBMは、これに罠をしかけました。公開したプログラムに著作権を与え法律的保護を加えたのです。そしてBIOSのチップは決して販売しませんでした。こうしておけばどんなコンピュータメーカもIBM互換機を作ることができないし、BIOSをコピーしようとしても、または一部を借用したとしても世界最大の法律専門部隊を持つIBMが違法であることをたちどころに暴き、多額の賠償金を求めることができると考えたのです。
- かくてIBMはパソコン市場にも君臨し、メインフレームへの道にも赤い絨毯(じゅうたん)が敷かれるはずでした。
- しかし、現実は、違う方向に舵が切られることになるのです。・・・
- (誰も想像してなかった)崩壊の時が来ました。
- この理由は、「コンパック(Compaq)」のところで述べます。
- 6-2. IBM - 巨大帝国
- ここで古き良き時代のアメリカのビジネスのやり方について見てみましょう。
- 巨大IBMとアップルなどに代表される東と西の会社のイメージを比較して見ることにします。
- ★煙突、摩天楼、半エーカーもあるマホガニーのデスク。
- 社用ジェット機、銀髪、タイムカードを押す顔のない労働者の集団が
- 巨大な工場で組み立てる製品。
- - これが成功した東海岸企業の昔ながらのイメージです。
- ★バレーボール、ジャンクフード(ハンバーガショップ等)、週100時間労働、
- だだっ広い事務所に代わる小さな仕切の部屋、Tシャツ、アジアでは見られな
- い働く人も動いている機械も見えない工場。
- - これが、現代のパーソナルコンピュータ業界(西海岸、シリコンバレー)
- における成功した企業のイメージです。
- ■ IBMの黎明
- 前にも述べましたが、再度IBM社についてその会社の成り立ち、体質について考えてみましょう。IBM社は、1970年代後半に台頭したパソコンの文化とはかなり違う会社であることに気がつかれると思います。
- コンピュータは今でこそ脚光を浴びた花形商品ですが、登場当初は地味な存在でした。今でこそコンピュータは小型化され、処理時間が短縮化され、省エネ化された「哺乳動物」程度に進化を遂げていますが、初期のコンピュータは文字どおり「恐竜」そのものでした。巨大で、鈍く、重く、しかも膨大な量の食糧(電力)を消費しました。恐竜が絶滅の道をたどったように、この初期のコンピュータも「絶滅」しました。
- 世界最初のデジタルコンピュータの開発は、1937年にハーバード大学の数学者ハワード・エイケンによって手がけられました。エイケンは学生の手を借りながら、IBM社(当時、IBMはコンピュータでなく穿孔カード・タブレータを作っていました)と提携し、1943年に「マークI」を完成させました。マークIは少なくともその図体からして見る人を圧倒する機械でした。長さが50フィート(15m)、高さが8フィート(2.4m)を超え、部品数は750,000個で、それぞれの部品は長さにして約500マイル(800km)の針金で接続されていました。マークIの「頭脳」は、3300個の電気的リレースイッチで構成されていました。初代マークIの考案、デザインには数年が費やされ、完成までに数千時間に及ぶ労働が投入されました。このマシンは、徹頭徹尾、電気技術者、金属工らによる手作業によって仕上げられたものだったのです。
- ■ IBMのビジネスのやり方
- IBMのメインフレーム・ビジネスは、コンピュータの性能や価格の安さではなく、「信頼できるサービス体制」の上に成り立っています。会計処理に使われているシステム370/168が故障すると、たとえブルードホー湾であろうとヒューストンであろうとIBMの人間は修理のためにすぐさま先方の会社に出かけ、システムをバックアップし再稼働させるのです。
- 顧客サービスが、世界で最も利益の大きな会社を作りだしたのです。
- 話はそれますが、コピーマシンで有名な米国ゼロックス社も顧客サービスで会社を成り立たせるという方法で成功しています。こうした新しいビジネス方法を考えるアメリカは柔軟だなって思います。
- しかし、IBMが採用した顧客サービスは、メインフレームという何十億円という投資する規模のビジネスではな成り立つものの、数十万円のパーソナルコンピュータに応用するとなると話は別です。オフィスの中にある1ダースのうちの1台、あるいは100台のうちの、もしくは1000台のうちのたった1台のパーソナルコンピュータが故障した場合にIBMのようなサービスが成り立つかどうかを考えたとき、白いつなぎを着て待機しているIBMの保守要員の30%ないし50%以上は維持できなくなって解雇せざるをえないでしょう。現実問題として、パソコン自体が安くなりすぎてエンジニアを派遣するよりもコンピュータを取り替えてしまった方がはるかにてっとり早いと考えるようなビジネスになっています。ハードディスクのフェイルセーフ(fail&safe)を考えたときも、二つか三つのハードディスクで自動的に同じ内容をバックアップして、故障の際に併走していた別のハードディスクがバックアップするというシステムが発達しました。機械が自動的に保守をするシステムです。このシステムをより高機能にしたものとしてRAID(Redundant Array of Independent Disks)と呼ぶ技術があります。
- ■ IBM社員の意識
- 年商600億ドルのIBMは、ほとんどの国家より大きなGNP(国民総生産)を持っています。IBMの従業員数は約38万人。そこに配偶者と一人当たり平均1.8人の子供を加えると、IBMは実に100万人以上の市民をかかえていることになります。
- 人口統計学的に見るとIBMはクウェートによく似ていますが、気質的にはスイスに近いと言われています。IBMはスイスに似て保守的で、いくぶん怠惰で、変化の速度は遅いのですが裕福です。どちらの国も、出ていく金より多くの金を手に入れる習慣があります。どちらも学習速度が遅く、自分のペースで周囲に適応して行きます。
- スイスもIBMもどんなことが起こっても生き残れます。
- と、少なくとも自分たちはそう信じています。どちらもノロマかもしれませんが、そうだからと言ってへたに干渉しない方がいいようです。両方とも自分たちのものを守るためなら戦うし、小突かれたりしようものなら汚い手を使ってでも仕返しするでしょう。スイスには自分たちの守るために各家庭にマシンガン(ライフルではなくマシンガンですよ)を持っていますし、永世中立国として国民皆兵の義務があり国を挙げて武装化しています。
- IBMの市民は、コンピュータを発明したわけではありません。最強のコンピュータを作ったわけでもありません。IBMの市民は、ほかの誰よりも多くのコンピュータを作っただけなのです。今でこそジーンズと言えば誰でもリーバイスを思い浮かべますが、リーバイスとは対照的にファッショナブルなジーンズをデザインするグロリア・バンダービルトと競っていた時代がありました。けれど、辛うじて生き延びたのはリーバイスのほうでした。こうしてリーバイスがジーンズの代名詞になったようにIBMもコンピュータの代名詞になりました。
- IBMの社員は独自の言語を持ち、それに固執しています。例えば、ミニコンピュータは、「ミッドレンジシステム」と呼びます。モニタは、「ディスプレー」です。外部記憶装置であるハードディスクは、固定されているわけでもないのになぜか「固定ディスク」と呼んでいます。カッコつけすぎの感じがしないでもありません。
- IBMの人間はやや独善的で、少々ノロマでいささか太りすぎています。IBMの社員はほとんどが新卒で入社するのでほかの会社で働いた経験がありません。彼らの生活スタイルは中流階級そのものであり、シリコンバレーの企業とは全く正反対なのです。なにか日本の大手企業に入社する若者たちに似てなくもありません。
- ■ IBMの体質
- IBMの全従業員は、明らかにマネージャになろうという野心を抱いています。会社側もマネージメントを唯一最大のビジネスにすることによって、従業員がそう望むことを奨励しています。IBMの重役が商品をデザインしたり、ソフトウェアを書いたりすることはありません。彼らは商品デザインやソフトウェア作成を管理するのです。彼らはいくつもの会議に出席します。そのため、労力の大半は仕事をマネージすること(外部、内部との折衝、管理)に費やされることになります。実際に仕事をする重役など、ほとんどいないのです。すなわち、IBMが作り出すマシンの大部分のハードウェアとほとんどすべてのソフトウェアは最下層の連中、つまり見習い社員が作っているといっも過言ではありません。その他の社員は全員、会議やマネージメント、マネージャになるための勉強であまりに忙しすぎて自分の専門知識をIBMの製品に活かすチャンスがほとんどありません。
- IBMという会社には何かの決定をくだすたび、修正するたびに、これをいちいちチェックし、確認するマネージメント階層が無数にあります。この巨大な安全ネットのおかげで、IBMは間違った決定がくだされることはまずありません。間違った決定どころか、どんな決定をくだすのもきわめて困難なのです。これがこの会社の最大の問題点であり、流れの速い業界に足を踏み入れたIBMにとってはいずれ決定的な没落の原因となると言われていました。日本の大きな会社にもよく当てはまる事です。
- IBMは、会社内組織がしっかり構築しすぎているため、きわめて高い地位にある人間を除けば、鈍重で反芻することしか能がない重役たちを生み出す原因にもなりました。彼らは命令のことしか頭になく、しかも何をいつやらせるかの指示は会社まかせです。例えば、新しい仕事にかかる前、IBMの人間はその仕事の遂行に必要だと会社が考えるあらゆる情報を与えられます。このブリーフィング(briefing:簡潔な指示書、書類)は、自分でそれ以外の資料を読んだり、独自の調査をしたりする社員がいないくらい徹底したものだそうです。もしIBMのマーケティング担当重役が自社のパーソナルコンピュータと他社の製品との違いを知っているとしたら、それはほぼ間違いなくブリーフィング資料で知ったことなのです。間違っても他社の製品を自分で調べることなどありません。自社製品(メインフレーム)だってそうなのです。
- IBMは古きよき時代の東海岸の大企業で、一流大学を出た若者が青いスーツを身にまとってブリーフィングによって仕入れた資料に基づいてミーティングとマネージメントに明け暮れるわけです。
- なにやら日本の大企業もこうした米国の大企業にあやかって同じシステムを導入しているような感じを受けます。まあ、ビジネスそのものが欧米からきたものですからしかたのないことでしょう。
- IBMの実体を知れば、よくもまあ、こんな大きな舵取りの必要な会社が流れの速いパソコンに参入したものだと思いになるでしょう。
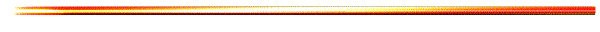
- ↑にメニューバーが現れない場合、
- ←クリックして下さい。
- 7. パソコンの文化7 (2000.06.11)
- 7-1. そんなIBMがパソコンを
- そんな企業風土(パソコンの文化 - その6)を持つIBMの人間の目にマイクロコンピュータ市場参入が魅力的に見えてきたのは、実は企業内競争があったからです。IBM社内では、社内のほかの部門と内戦をしながらメインフレームのマーケットシェアを苦労してもぎ取っていくのはもうウンザリという気運がありました。マイクロコンピュータ市場では社内のライバルに気を使う必要もなく、反トラスト法もありません。そして何よりも重要なのは、パソコンの顧客は、IBMにとってはまったくの新顔ばかりで過去にIBMのセールスマンと固い握手をかわした人間は一人もいないと言う事実でした。新しい世界、新世界だったのです。
- マイクロコンピュータ開発につぎ込まれる資金は、IBM自身がマイクロコンピュータを売らないかぎりIBMには入ってこない、だからマイクロコンピュータを売る。この考えには説得力がありました。マイクロコンピュータ市場に対する猛攻を指揮したIBMの重役たちは、この新しい戦場での成功こそが彼らを権力の源泉、すなわち、ニューヨーク州アーマンクにあるIBM本部へと導くこと(平たく言えば出世すること)であると理解したのです。スティーブ・ウォズニアクやスティーブ・ジョブズがパソコンを始めた動機と比べると、IBMはパソコンをビジネスとしてとらえていたのをはっきりと見て取ることができます。
- 1980年、マイクロコンピュータ市場には数多くの企業が参入していました。しかしIBMには、アップルもアタリもコモドールもラジオシャックも同じような雑魚(ざこ)に見えました。小人の国へ行くガリバーのような気持ちではなかったかと考えます。いずれもとるにたらない小さな会社ばかりというわけです。しかし、米国内におけるマイクロコンピュータの総売り上げは既に10億ドル(2,000億円)に達していましたから、それら小人を蹴散らして、10億のおいしい蜜を奪い取る(市場を占有する)価値は十分にあったのです。実際、IBMのパソコン分野への本格参入によってこの市場は爆発的な伸びを示したのです。
- 1983年私が初めてアメリカへ出張し、東海岸の会社に自社製品をもってPRに回ったとき、多くの会社のオフィスの秘書の机にIBM PCがあったのを鮮明に覚えています。IBMの電子タイプライターがこのパソコンに変わったんだ、ととても新鮮だったのを記憶しています。
- 7-2. IBMのパソコン開発
- 1981年8月に発売されたIBM PC(モデル5150)は、フロリダ州ボカ・レイトン(Boca Raton, Florida)にある反逆的な独立部門が作ったものだそうです。これはIBMで最初に開発されたパーソナルコンピュータではありませんでした。ボカで以前に作られたものを含めて少なくとも4種類がこれまでに設計され、アーマンク(Armonk、N.Y.本部)の経営陣に提出されています。こうした初期のものと最終的にIBM PCとなったものとの大きな違いは、
- 「1年後にIBM PCを市場に出す。」
- という大命題を課せられていたことです。ほかのプロジェクトは先行投資の意味合いが強く、期限などが決められていない言わばIBM時間での開発でした。それがホントの時間(時間を区切られてホントに出荷するというタイムスケジュール)で開発を命じられたのです。
- この命題が課せられたのは1980年7月のことで、その人物はエントリー・システムズ部(ESD)研究室長、ビル・ロウ(William C. Lowe)でした。
- IBMにとって、一年というのは時間と呼べるほどの単位ではありません。IBMは全てがゆっくりで4年経っても完成のめどが立たないプロジェクトもたくさんありました。既存のシステムに機能を追加するだけでも4年もかかるとしたら、コンピュータシステムを一年で作るなんて不可能としか言いようのないものでした。
- 実際のところ、1年でパソコンを開発するなんてとても不可能でしたし、ロウもそれをよく承知してました。他社のハードウェアとソフトウェアを組み合わせてシステムとして機能するものを作り上げ、外側にIBMのラベルを貼り付ける。IBMがとれる最前の方法は、それぐらいしか考えられなかったのです。
- そして、ビル・ロウ(William C. Lowe)はこの方法を選びました。
- ロウとその部下たちは、その後何度も繰り返すことになるルール破りの皮切りとして(そしてそれがIBMの恒常的な体質となるのですが)、全ての部品を下請け会社から買うことに決めましたた。そして手始めにソフトウェア探しにとりかかったのです。
- ロウは、安定した会社からオペレーティング・システムを買おうと考えました。彼はOSを考えた時、そのOSは天才プログラマー、ゲーリー・キルドールが開発した評価の高い『CP/M』しか頭にありませんでした。CP/M(Control・Program/Monitor、後Control Program for Microcomputers)というOSは、ゲーリー・キルドールが1975年にインテル8088用のCPUチップのために開発したもので、現在のパソコンの中にも組み込まれているBIOS = 「基本入出力システム」(Basic Input/Output System 略してBIOS)という考えを初めて導入したシステムです。BIOSは、マイクロソフト社が開発したMS-DOSにも踏襲されて(一説にはごっそりコピーしたと言われていますが)、Windows98の核にもこの痕跡がありました。
- IBM PCのOS決定までのくだりは面白いのでマイクロソフトのところで詳しく触れたいと思います。
- 7-3. IBM PCの波及効果
- パーソナルコンピュータ業界におけるIBMの成功は、まぐれ当たりでした。三年以下ではどだい何も作れない会社が、一年間でどうにかこうにかパーソナルコンピュータとそれに組み合わせるオペレーティングシステムを作り出したのです。それから18ヶ月後、IBMは少しばかり改良されたマシン、PC-XTを発表しました。さらに18ヶ月後、IBMはXTの五倍の性能を持つ真の第二世代の製品、PC-ATを発表しました。そして1981年から84年にかけて、IBMはパーソナルコンピュータの「標準」を確立しました。そのおかげでアメリカの企業社会がパーソナルコンピュータを本気で受けとめるようになり、現在にいたるパーソナルコンピュータの産業が生まれたのです。
- しかしながらIBMは、1984年以降この業界のコントロールを失ってしまいました。
- PC-ATの開発によって、エントリー・システムズ部門にもようやくIBMの現実がのしかかってきました。つまり、パソコンを売り始めた最初の頃は部門の責任で勝手に指揮をとっていても良かったのですが、この分野の波及効果を見て本部からIBMスケジュールで管理されるようになったのです。
- その結果、PC-AT以降のIBMは新しい製品系列を開発するのに三年以上かかるようになりました。メインフレーム(大型コンピュータ)の基準で考えれば、三年というのは悪い数字ではありません。しかし既に述べたように、IBMにとってメインフレームはコンピュータですが、パーソナルコンピュータは単なる集積回路の固まり(100%外注によって製作されたもの)でしかありませんでした。そしてパーソナルコンピュータは、半導体の価格対性能比の曲線に対応することになっています。つまり、製品の価格は、どんどん安くなっていくというパソコンの市場価格原理に突入していったのです。けれどもIBMにはそうした市場に対応できる力はありませんでした。IBMは、1986年までに業界を引っ張っていくような新しい製品系列を作るべきだったのにそれをやらなかったのです。
- 別の会社が支配権を握る番がやってきました。
- それが、コンパック・コンピュータでした。
- コンパックについては、項を改めて紹介しましょう。なぜクローンメーカが出てくるようになって帝国IBMが瓦解したのかも興味あるところです。
- コンパック・コンピュータは一年で8088ベースのIBM PCクローンを作り、半年で80286ベースのPC-ATクローンを作りました。IBMは1986年までに80386ベースのマシンを発表するべきだったのに、間に合わなかったのです。理由は、前にも述べた「東海岸の大企業」の体質でした。
- そしてビッグブルー(IBM)を待てなかったコンパックが、IBMを追い越してデスクプロ386を発表してしまいました。これに続いて他のクローンメーカーからもすぐに386マシンが発表されたのですが、面白いことに、これらはいずれもIBMのクローンではなくコンパックのマシンのクローンだったのです。
- 一方、ビッグブルーは性能曲線(パソコンは絶えず性能が向上しそれと共に価格が下がるという原理)から脱落し、二度と追いつくことはありませんでした。
- IBMの後ろを走っていたコンパックをはじめとするクローンメーカがペースがあがらないリーダを見限って追い越し先に走り出してしまったのです。
- IBMは、MS-DOSにオペレーティングシステムとしての特別な地位を与えました。これはマイクロソフト社を間接的に巨大企業として促成することになりました。
- IBMはまた、多くの会社が作る拡張カードが同じマシンでどういった用途に使えるかを決めるPC-ATの16ビットバスの『標準』を設定しました。
- 市場のリーダーが自社製品を市場にもっと浸透させるには、他のハードウェア会社やソフトウェア会社の助けが必要です。標準というのは、いわば市場のリーダーが自分を助けてくれる関連会社に与える慈悲(蜜)のようなものなのです。
- IBMの役割はそこで終わりました。
- IBMが性能曲線からはずれても、IBMが定めた標準は相変わらず指針として機能し続けました。市場の主導権を握る可能性はIBMが脱落した後、クローンメーカーの手にゆだねられ、実際にそうなって行きました。そしてIBMは、自社の市場占有率がゆっくり落ち始めたことに気づくことになります。
- ですが、1980年代後半のIBMは依然としてパーソナルコンピュータ業界の最大手であり、相変わらず技術的な大混乱を引き起こすだけの巨大な潜在能力を持っていました。なにせ米国の中枢とも呼べる優秀な法律家を自社で雇って法律問題に関して強い力を持っているのですから。そして、ビジネスブームをもっと楽なペースに落とす方法を他の会社よりはるかによくわかっていました。IBMは、以下の戦略を立てることによりこれからも業界を引っ張るという姿勢を具体的に示しました。
- 1. 製品ではなく方向性を示し、競合メーカに無駄な浪費をさせ、決してIBMの前には走らせない。
- 2. 製品の発売を予告し、実際の発売までにたっぷり時間をかけ競合会社をいたぶる。
- 3. ときには、製品を出さず、出すようなそぶりを示してじらす。
- 4. 独自の標準品を他社に強要する(OS/2)
- 5. 製品を発表し簡単に自社製品を否定する
- (PCネットワーク/PC-LANプログラム→トークンリング)
- しかし、1990年代にはいると凋落は誰の目にも明らかとなりました。IBMに変わってパソコンをリードし始めたのが、Windowsの移植を成功させたマイクロソフトでありCPU製造業者であるインテルでした。世間はこれらを総称して「ウィンテル」と呼び始めました。
- 7-4. それでもIBMが帝国である理由
- 1980年以来、IBM PC開発チームのリーダとしてドン・エストリッジ(Philip Don Estridge:1937.06.23 - 1985.08.02 )は、これまでのIBMの経営上考えられない方向を打ち出して来ました。彼のチームは、可能な限りIBMらしくなくなることによって成功を収めました。IBM PCは爆発的に売れたし収益は上がっていたのです。通常なら昇進するはずでした。ところが、エストリッジのやり方はIBMのやり方とは違うという理由で、彼は信頼性を失い、製造担当副社長のポストにしかつくことができませんでした。
- そんなとき、フロリダ州ボカ・レイトン(Boca Raton, Florida)にある彼の自宅にアップルの腕利きセールスマン、スティーブ・ジョブズ(当時28才、1983年)がリクルートに現れます。
- 小さな会社の重役が三菱重工業のような巨大企業のS製作所副所長の所に「100万ドルの契約金と200万ドルの引っ越し代、年俸100万ドル = 当時で合計9億円でうちに来ませんか?」とコンタクトをとるようなものです。
- エストリッジは閑職に追いやられようとしていましたし、IBMにいてもおそらくトップにはなれない。アップルとの相性は完璧だし、給料はとてつもない額を提示されたのです。しかし彼はしばらくの間悩み抜き、親しい友人達に相談した結果、この話を断わりました。内面の心的葛藤の結果でした。
- このエピソードは、エリートIBMマンの生き様が見えてとても興味深いものです。
- たとえアップルに社長のイスが用意され莫大な報酬が約束されても、ドン・エストリッジにIBMを辞められるわけがなかったのです。
- なぜならアップルはただの会社にすぎませんが、IBMは国家だからです。
- ドン・エストリッジは、1985年8月2日、不幸な一生を終えます。デルタエアラインに乗り合わせた彼は天候不良によって飛行機がマイクロバーストに合い、テキサス空港での着陸失敗の事故で夫人と共に他界してしまいました。ドン・エストリッジ48才のことでした。
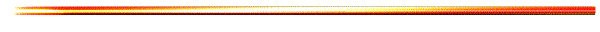
- ↑にメニューバーが現れない場合、
- ←クリックして下さい。
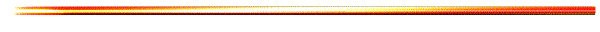
- ↑にメニューバーが現れない場合、
- ←クリックして下さい。
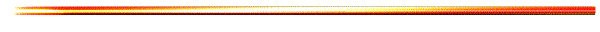
- ↑にメニューバーが現れない場合、
- ←クリックして下さい。
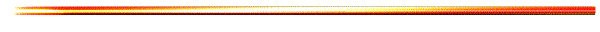
- ↑にメニューバーが現れない場合、
- ←クリックして下さい。
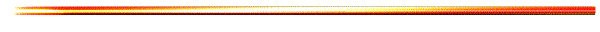
- ↑にメニューバーが現れない場合、
- ←クリックして下さい。
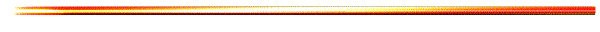
- ↑にメニューバーが現れない場合、
- ←クリックして下さい。
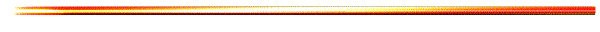
- ↑にメニューバーが現れない場合、
- ←クリックして下さい。
- 17. パソコンの文化17 (2001.06.03)
- 17-1. パソコンを形作ったアプリケーションソフト(その3) - 表計算ソフトVisiCalc
- 「コンピュータと言えばパソコン」と言えるまでにパソコンの地位を押し上げたアプリケーションソフトウェアがこれから紹介する表計算ソフトと呼ばれるスプレッドシートソフトです。このソフトのアイデアと使いやすさ、それに個人が持つことのできるコンピュータ(パソコン)で実行できる特徴が多くの知識人に受けパソコン市場を大きく前進させました。
- このソフトウェアはどのようにして開発されたのでしょう。
- ■ ダン・ブリックリンとボブ・フラクストン - 表計算ソフト
- ビジカルク(VISICALC)は、圧倒的魅力を持つアプリケーションでした。このソフトがコンピュータの購入動機になるくらい、非常に重要なアプリケーションだったのです。こうしたアプリケーションは、コンピュータをホビイストのおもちゃからビジネスマシンに変えるのに必要な最後の要素になります。コンピュータがどれほど強力な性能を持つことや、そしがどれだけ内部設計がすばらしいか、など全く関係ないのです。圧倒的魅力を持つアプリケーションソフトウェアのないコンピュータは決して成功しないのです。こうしたアプリケーションを買った当時の人々とはどんな人物だったかというと、メインフレーム(大型コンピュータ)は在庫管理や会計処理のためのマシンとしてみなし、そしてビジカルクを最初に搭載したアップルIIは、彼が個人的に使うパーソナルコンピュータであり、表計算ソフトを動かす「ビジカルクマシン」と見なしていました。
- ビジカルクと呼ばれるソフトウェアは、それ以前はどんなコンピュータにもなかった全く新しいアプリケーションでした。ソフトウェアをコンパクトにまとめてマイクロコンピュータで動かせるようにしたスプレッドシート(表計算)は、ミニコンピュータにもメインフレームにもなかったのです。マイクロコンピュータとスプレッドシートは、ほぼ同時期に誕生しました。それぞれが、お互いのために生まれてきたようなものというぐらいに相性が良かったのです。
- ■ 表計算ソフト VisiCalc - 発端
- ビジカルクは、これを開発したダン・ブリックリン(Dan Bricklin)がハーバード大学ビジネススクールに通っていたことがきっかけで生まれました。ブリックリンは、1951年米国フィラデルフィア生まれ、1973年MIT(マサチューセッツ工科大学)卒業後DECに入社、ワープロソフトWPS-8の開発リーダとして仕事に従事していました。1977年、彼は、自分のプログラマとしてのキャリアが終わりかけていると感じて再び大学に戻りハーバード・ビジネス・スクールに入りました。彼は、プログラムを書くことがどんどん簡単になり、やがてプログラムがまったく不要になって自分は仕事を失うと確信したのです。そこで1977年の秋、26才だったブリックリンはこのままではダメになってしまうのではないかと心配なり、新しいキャリアを求めてハーバード・ビジネススクールに入学したのです。ここでのスクールの学生は、1クラス80名。彼はそこで経営学を学びました。カリキュラムには、経営者が資本を投入して市場に影響を及ぼすと株価や物価、消費がどのように影響を与えるかという表計算のシミュレーションがあり、その講義には電卓が必須でした。
- ブリックリンは、ハーバードでほかの学生より有利な立場にありました。というのも彼は、財務計算を行うBASICプログラムぐらいなら、ハーバート大学のタイムシェアリングシステム(コンピュータ)を使って簡単に書くことができたのです。それよりもブリックリンを悩ませたのは、新しい問題にあわせて(パラメータが変わる毎に)その都度プログラムを書き直さなければならないことでした。そこで彼は、こうした計算を柔軟なフォーマットで処理できるような、もっと汎用的な方法はないものかと考えはじめたのです。この発想こそが実にユニークで非凡だと思います。
- ブリックリンが本当にほしかったのはマイクロコンピュータのプログラムではなく、専用のハードウェアでした。その当時、生産管理学の教授が一部の企業で生産計画に使われている大きな黒板のことを話していました。この黒板は何部屋にもわたるほど長いこともあり、列(ロウ)と行(コラム)からなるマス目に分割されていました。生産計画の担当者は、製品の製造に必要な時間、材料、人員、経費などに関係する各空間にチョークで書き込みをしていくのです。黒板上の空欄をセルと言い、セルの位置は列と行で指定できます。つまり、各セルは二次元の番地を持っていることになります。セルの中にはほかのセルと関連しているものもあります。そこで、たとえばセルF-7に書き込まれている製造品目が増加してセルC-3に書き込まれた必要人員が増えたとすると、それに比例してセルD-5の賃金総額も増やさなければなりません。一つのセルの値を変更すると、それとリンクしたすべてのセルを再計算しなければならなくなります。つまり、黒板を消して計算し直すという作業を繰り返さなければならないことになります。
- そうした作業をする担当者は、再計算が必要なセルを見落として総合的な結論を出し間違えることがないようにと、常にヒヤヒヤしているのです。
- ■ 表計算VisiCalcのアイデア - セル
- 黒板方式はブリックリンの財務計算機にとって格好の形態でした。何しろ、物理的な黒板をビデオスクリーンに置き換えるだけでいいのですから。ユーザーは各セルにデータや数式を一旦入れてしまえば、一つの変数を変更するだけでほかのすべてのセルは自動的に再計算され、データも書き替わります。リンクしたセルを見落とす心配もまったくなくなります。ビデオスクリーンは、実際にはコンピュータのメモリの中にあるスプレッドシートの一部を見せる窓を表示しているだけなのです。つまり箱に収まった仮想スプレッドシートは、どんな大きさにもできるのです。一度スプレッドシートを設定してしまえば、「もし部品一個につき10セント値上げをしたら、どれだけの増収が見込めるか」といった質問にもほんの数秒で答えてくれます。
- ブリックリンの生産管理の教授は、会計学の教授と同じように彼のアイデアをとても気に入ってくれました。しかし、別の教授、必要な計算を他人にやらせていた財政学の教授は、すでにメインフレーム用の財政分析プログラムがあるから、世界はダン・ブリックリンの小さなプログラムなど必要としないだろうと言いました。ところが必要としないのは財政学の教授だけで、世界中の人々は今はまだ名前も持たないブリックリンの小さなプログラムを必要としていたのです。
- 未来のビジカルク・ユーザーの大半がビジネススクール出身者だったことを考えれば、ビジカルクがビジネススクールでの体験から生まれたのは何ら不思議なことではありません。ビジカルク・ユーザーの中には、分析的な経営技術を学んで就職したMBAが数多くいましたが、経営技術を学んだことよりも重要なのは、彼らがタイピングを習得していた(タイプライターを自由に使いこなせる人々だった)ことです。つまり彼らは、タイプを打つことやコンピュータを扱うのにアレルギーがなかったのです。
- ビジネススクール出身のビジカルク・ユーザーは、適切な道具さえ与えられればすべて自分一人でこなせるコンピュータ・ビジネスマンの最初の世代だったのです。
- しかしながらMBAを取得した彼らに対して、このソフトを使いたい、使えるという技能と動機が十分にあったにもかかわらず、彼らが勤めるほとんどの会社ではコンピュータにアクセスすることができなかったのです。
- ブリックリンは、週末を使って、アイデアの概略を説明するためのデモンストレーション・プログラムを作りました。このプログラムはBASICで書かれているので処理が遅く、一画面分の列と行しか持っていませんでした。しかしながら、スプレッドシートが持つ多くの基本機能を見せることはできました。たとえば、何もせずにただ待っているというのも機能の一つでしだ。これはスプレッドシートの優れた特質で、このプログラムは何らかの指示によって動作(イベント・ドリブン)するのです。ユーザがセルを変更しないかぎり、何も起こらないのです。こんなことはたいしたことには思えないかもしれませんが、イベント・ドリブンであるおかげでスプレッドシート全体がユーザーに反応するようになっているわけです。ほかの多くのプログラムとは違った形で、ユーザーがすべてを管理できるのです。ビジカルクは、いわばスプレッドシート言語です。ユーザーは、気づかないうちに初歩的なプログラミングをしていることになるのです。
- ■ ビジカルクの開発
- ブリックリンのデモンストレーション・プログラムが動くようになったのは、1978年初めのことでした。ちょうどマイクロコンピュータの大衆向け市場のようなものが出現し、アップルII、コモドールのPET、ラジオシャックのTRS-80が競争をはじめた頃です。彼はそれまでマイクロコンピュータを使った経験もなく、特にどのマシンが好みということもありませんでした。そこでブリックリンと彼のMIT時代の古い友人で新しくパートナーになったボブ・フランクストンは、アップルII用のビジカルクを開発しました。
- 彼らは、表計算ソフト会社「ソフトウェア・アーツ社」を設立し、MITの大型コンピュータを使ってソフトを開発しはじめました。昼間は学校、夜に夜間使用料金でMITコンピュータを使用したのです。資金が不足していたので、フランクストンは夜、仕事をしました。夜間はコンピュータ使用料が安く、しかも利用者が減るからタイムシェアリングシステムの反応速度が速くなるのです。そして完成まで1年を費やしました。
- 完成は1979年10月。ブリックリンとフランクストンは、ミニコンピュータ上のアップルIIエミュレータを使ってビジカルクの最初のバージョンを開発したのです。彼らは、マイクロソフトBASICやCP/Mが書かれたのと、まったく同じ方法でこのプログラムを開発しました。これをアップルIIに搭載しました。ビジカルクはマウスで動くというおまけまでついて。
- ブリックリンは当時まだハーバード・ビジネススクールに在学中だったので、のちにマイクロコンピュータのプログラムを開発する際の標準となったやり方で仕事を分担することにしました。つまり、ブリックリンが「プログラムの画面デザインはこんな感じで、こんな仕様になっていて、こんなふうに機能する」といった具合に指示を出し、実際にプログラム内部の設計をするのはフランクストンの仕事、という具合です。フランクストンは1963年からソフトウェアを書いてきた人間だったのでこれはまさに打ってつけの仕事でした。フランクストンは自分の考えでいくつかの機能を追加していますが、その中の一つに「ルックアップ」(lookup)機能がありました。ルックアップはあらかじめ作っておいた一覧表から特定の数値を取り出す機能で、彼はこれを自分の税金を計算するために作ったのだったそうです。
- ボブ・フランクストンは後にロータス・デベロップメント社の主席研究員を務めました。彼は非常に心の優しい性格の持ち主で、ロータス社に勤めたとき、この会社の連中が、彼のために、「ロータス1-2-3」を作ってくれたのだと思っていました。ハードウェア会社であれ、ソフトウェア会社であれ、パーソナルコンピュータの会社では社長でさえ主席研究員をどう扱ったらいいのかわかっていないようです。一般に、主席研究員は何もしなくていいのです。彼らは競争相手に引き抜かれたくないと思うほど頭のキレる連中なのです。そこで彼らは会社から肩書きとオフィスを与えられ、会社のあらゆる式典に過去の栄光を代表して出席することを義務づけられています。主席研究員が何人もいてはまずいというので、アップルコンピュータでは彼らを「アップル・フェローズ」と呼んでいるのです。
- ボブ・フランクストンは変形おたくで、あごひげをはやし、この種の連中に不可欠なフランネルのシャツを着ています。彼は、主席研究員としての自分の役割がインチキなものであることに気づいていないようでした。彼にとってこの肩書きは決してインチキなものではなく、市場性などを無視して自己の内面を見つめ、深淵な思考をするには絶好のポジションだったのです。
- ブリックリンらの作っているソフトウェアは、一ヶ月もあればすべての仕事が終わるだろうと考えていましたが、実際には完成までに一年近くかかりました。その間、彼らはまだ数少なかったソフトウェア販売店やアップル、アタリといったコンピュータメーカーに、ビジカルクの発売前のバージョンを見せてまわりました。アタリは関心を示したが、まだ売るべきコンピュータがありませんでした。一方、アップルの反応は冷たいものでした。
- 1979年1月、彼らはアップルソフトBASICで書かれたカルクレジャー(ビジカルクの前身)を完成させその試作品をアップルに持ち込みマイク・マークラとスティーブ・ジョブズに見せました。ブリックリンらはこのソフトを100万ドル(2億4000万円)で売ろうとしましたがアップルは受け付けませんでした。彼らは当時このプログラムの重要性を把握できなかったのです。もっともこのプログラムの重要性を見抜けなかったのはアップルだけでなくビル・ゲイツでさえこのプログラムを買い取ることを拒否したといいます。
- 1979年5月にサンフランシスコのウェストコースト・コンピュータ・フェアでビジカルクと改名して衆目の前にスプレッドシートがお目見えします。その後すったもんだして1979年10月、アップルIIに搭載されマウスで操作できるまでになりました。
- 1979年10月、ビジカルクは100ドルの価格で発売を開始します。最初の100セットは、マサチューセッツ州ベッドフォードにあるマーブ・ゴールドシュミットのコンピュータショップに送られました。ダン・ブリックリンは定期的にこの店に出かけ、当惑する客に向かって製品のデモンストレーションを行ったそうです。しかし、売れ行きは思わしくありませんでした。ビジカルクの最初の画面を見てそれが未来を見ることだと気づかなかったとしても、当時のユーザーを責めるのはお門違いででしょう。なにしろ、こんな製品はいままで存在しなかったのですから。
- 当時のパーソナルコンピュータのソフトウェア開発者のほとんどは、自分たちが開発する財務関係の製品はどれも主に小企業(スモールビジネス)で働く人々がユーザーになるだろうと思って疑いませんでした。たとえばアップルのマークラが愛用していた会計システムは、タイムシェアリングシステムにアクセスするだけの余裕などなく、しかも会計会社に経理の仕事をまかせたくないので、小規模な販売業者や製造業者に使われる財務管理ソフトを使っていました。ブリックリンが開発したビジカルクスプレッドシートも、同じように小企業で働く人々が予算を組んだり商売の予測を立てたりするために使われるはずでした。メインフレームやミニコンピュータの導入で大・中企業のオートメーション化がはじまったように、小企業はマイクロコンピュータによってオートメーションの時代を迎えるはずだったのです。しかし、事は目論見どおりには運びませんでした。
- ■ VisiCalc出版元 ダン・フィルストラのパーソナル・ソフトウェア社
- ブリックリンとフラクストンがビジカルクを開発するにあたりアップルIIを使ったのは、彼らの出版元になるはずの人間がアップルIIを貸してくれたという単にそれだけの理由でした。機種の決定に、技術的にメリットがあるかどうかはまったく関係がなかったそうです。
- ダン・フィルストラと言う人がその出版元でした。彼は、1,2年前にハーバード・ビジネススクールを卒業したばかりの人間で、自宅でマイクロコンピュータ用チェス・プログラムの通信販売をして暮らそうと考えていました。フィルストラの会社「パーソナル・ソフトウェア社」は、マイクロコンピュータ用アプリケーションソフトウェア会社の原型と言っていいでしょう。マイクロソフトのビル・ゲイツやデジタルリサーチのゲーリー・キルドールは、オペレーティングシステムや言語の開発・販売が専門でした。どちらの製品も、システムソフトウェアというラベルで一つにくくることができます。また、いずれも直接ユーザーに売られるわけではなく、ハードウェアメーカーに販売されていました。しかしながら、フィルストラはこうした販売方法とは別のやり方で、アプリケーションソフトをを小売店やユーザーに直接売っていたのです。それも、たいていは一回に1セットという小さな販売形態でした。当時そうした販売をするの格好の手本にする会社がなかったので、フィルストラは自分自身で数多くの失敗を経験しなければなりませんでした。
- 見習うべきサクセス・ストーリーは他になく、金を稼ぐための原則を見つけだしたソフトウェア販売会社もない状況だったのです。そこでフィルストラはハーバードでのケーススタディーを引っぱり出し、マイクロコンピュータのソフトウェアビジネスに応用できそうな原則を持つよく似た業界を探すことにしました。
- 彼が見つけた中で最も近かったのは本の出版元でした。出版業界では著者に製品のデザインと提供(インプリメント)の責任があり、出版社は製造、流通、マーケティング、販売の責任を負います。これをマイクロコンピュータ業界に移し替えると、ブリックリンとフランクストンが作った会社ソフトウェア・アーツ社は、ビジカルクを開発し、その後のバージョンアップ、製品サポートにも責任を持つ。一方、フィルストラの会社パーソナル・ソフトウェア社は、フロッピーディスクをコピーしてマニュアルを印刷し、コンピュータ雑誌に広告を載せ、製品を小売店や一般ユーザに届ける責任を持つ、ということになります。ソフトウェア・アーツ(製造元)は、ビジカルク一部につき小売価格の37.5%、または卸売価格の50%の印税を受け取ることになりました。この高い印税がのちのち彼らの前途を暗くさせ新しい波を起こさせることになりました。
- ■ ビジカルクの市場
- スモールビジネス市場の問題は、小企業というものがビジネスにとってはたいていはあまりおいしくないマーケットであることです。小さな会社で働いている人々の大半は、自分がどんな仕事をしているのかわかっていませんでした。会計などというものは、明らかに彼らの手に負えないものだったのです。
- その当時、ホビイストやそのうちコンピュータゲームファンになるはずの連中に対するソフトウェアの売上はピークに達していましたが、小企業に対するビジネスソフトの売上はさっぱりでした。これは、アップルやその競争相手にとっては非常に深刻な問題でした。パーソナルコンピュータ革命がまるであと五年しか続かないように思えたようです。しかし、そうした危惧をしはじめたそのあとにビジカルクの売上が急激に増加しはじめたのです。
- マープ・ゴールドシュミットの店でビジカルクのデモを見た数多くの客の中に、わずかではありましたが大企業に勤めるビジネスマンが混じっていました。彼らはコンピュータマニアであり、なおかつビジネスの世界でも認められている例外的な人間でした。こうした連中の多くはアップルIIを買い、一行40文字しか表示できないディスプレーや小文字が使えないことに半ばあきらめをもちつつもそれでも実際の仕事に使いたいと思っていました。ビジカルクなら小文字が使えなくても問題がありません。また、このプログラムは大きな仮想スプレッドシートの一部をスクリーン表示するようになっていましたから、一行40文字の制約も思っていたほど問題になりません。それがわかった彼らは100ドルを払ってこのチャンスに飛びつき、ビジカルクを家に持ち込みました。こうして、アップルIIの真の市場は小さな企業の人達ではなく大企業のビジネスマンにあることがわかったのです。アップルIIを産業界に広めたのは、アップルIIのマーケッタではなかったのです。企業に勤める仕事熱心なビジネスマンの努力でアップルIIが産業界に広まったのです。
- 「スプレッドシートのすばらしい点は、大企業に勤める顧客たちが本当に頭が良くて、あのプログラムがもたらす利益を即座に理解できたことだ」と、アップル社でスモールビジネス戦略をまかされていたトリップ・ホーキンスは述懐しています。
- ■ VisiCalc 市場独占のミス
- 「ピッツバーグのウェスチングハウス社に行ったときのことだ。あの会社はアップルIIが自分のところには適していないと結論を出していたんだが、どういうわけか本社に1000台のアップルIIが届いてしまった。それで、小口の手持ち資金でビジカルクを全部買ってくれたというわけだよ。あの会社のインテリたちが、アップルIIを有名にしてくれたようなものだね」
- スプレッドシートはパーソナルコンピュータライフの新しい形態であり、ビジカルクはアップル社が大・中企業向けのマイクロコンピュータ市場に参入するために必要な道具となりました。そして、ビジカルクがあればこの市場を独占できるかもしれない、と、アップル社営業マンのホーキンスは、そのことに気づいた最初の一人でした。ビジカルクはその当時、販売されていた唯一のスプレッドシートでした。アップルII初のしかもアップルIIでしか使えないスプレッドシートだったのです。ビジカルクは、アップル社にとって戦略的な価値がありました。ブリックリンとフランクストンがラジオシャックのTRS-80のような他のマシンに移植しようかな、と考える前にしっかりつなぎ止めておかなければならない商品だったのです。
- 「最初のビジカルクをアップルのオフィスに持っていったとき、私はこれがアップルIIの成功に不可欠な重要なアプリケーションだと確信したんだ」と、アップル社のホーキンスは言っています。
- 「ラジオシャックやいずれは登場するのがわかっていたIBMのマシンに、あのソフトウェアを移植してほしくなかった。そこで私はダン・フィルストラを昼食に招いて、買い取りの話を持ちかけたんだ。100万ドル相当のアップル株の譲渡ということで話はまとまったよ。あとになれば、この100万ドルははるかに大きな価値をもつはずだからね。ところがアップル社の幹部であるマークラにこの取引を承認してもらおうとしたら、『ダメだ、高すぎる』と言われてしまったんだ。」
- マイクロコンピュータ・ソフトウェアビジネスの草創期、100万ドルといったらとても大変な額でした。多少なりとも金銭のことを考えた事があるプログラマなら、だれでも自分が作ったプログラムがかっきり100万ドルで売れるときのことを想像したことがあるでしょう。このプログラムの所有権を持っていれば、アップル社は何年にもわたってマイクロコンピュータのビジネス市場を独占できたはずなのです。ダン・フィルストラにとっても、この取引はすばらしい結果をもたらすはずでした。取引が成立していれば、彼は今頃自分のアパートでチェス・プログラムの通信販売をしていられたかもしれないのです。ただし、ダン・フィルストラではなくダン・ブリックリンとボブ・フランクストンがビジカルクの所有権を持っていたことを除けば、の話です。マサチューセッツにいる二人にはまったく知らされることなく、この取引は持ち上がり、そして消えていったのです。
- ビジカルクは、アップルIIのソフトとして99$で発売され、100,000本/年売れました。IBMはライバル会社のパソコンに搭載されている「ビジカルク」を見てパソコンを開発する決定をしたと言います。
- そして、同種類のソフト開発にIBMが動くのです。MS-DOSとIBMパソコンを不動にしたキラーソフト、「Lotus1-2-3」の登場です。
- 「Lotus1-2-3」は、ミッチーケーパとジョナサン・サックスが起こした会社ロータス社で開発された製品で、IBMパソコン用の表計算ソフトとして発売されました。1982.11月の発売と同時に300万$の注文を受け先陣のビジカルクを圧倒します。「Lotus1-2-3」は2,000万本を出荷し、ビジカルクはビジネスに失敗しました。 Lotus社についてはパソコンの文化18で詳しく述べます。
- 現在ダニエル・ブリックリンは自宅でソフトウェア・ガーデン社を経営しています。従業員3名。一時ロータスに顧問として勤めていましたが退社しています。
- 17-2. VisiCalc(ビジカルク)とビジコープ(VisiCorp)社
- IBM PC用に移植されたビジカルクが発売される頃には、IBM PCパーソナルコンピュータだけでなく人気のあるマイクロコンピュータのほとんどの機種ですでに使えるようになっていました。IBM PC版のビジカルクは、実は移植のまた移植でした。アップルIIのオリジナル版から移植されたラジオシャック版をさらに移植したものでした。ビジカルクはすでに二歳になり、少しばかり疲れていました。IBM PCは、最大640Kバイトのメモリを利用できるおうになっているのにビジカルクは依然として64Kバイトしか使えませんでした。しかも、アップルII版や「トラッシュ80」版同様の古くさい機能しか持っていなかったのです。これからコンピュータユーザーになろうとする人間にとって、もはやビジカルクでは圧倒的魅力はなくなっていました。彼らは何か新しいものを求めていたのです。
- ビジカルクがこれだけたくさんのマイクロコンピュータで利用できるようになった理由は、一つにはかってはパーソナル・ソフトウェア社(Personal Software)と呼ばれ、1976年にビジコープ(VisiCorp)と社名変更していたダン・フィルストラ(Dan Fylstra)の会社と、ダン・ブリックリン(Dan Bricklin)の会社ソフトウェア・アーツ社(Software Arts)との契約までさかのぼります。
- ビジコープ(ビジカルクの販売会社)は、ソフトウェア・アーツと(ビジカルクの開発会社)の契約から逃れたがっていました。ビジコープは、マサチューセッツ州のフィルストラのベッドルームで生まれ、やがて活気のあるカリフォルニア州に移って派手な家に落ち着きました。しかし、シリコンバレーで起きるありとあらゆる出来事の真っ只中にいながら、ビジコープはソフトウェア・アーツとの契約に苦しめられていました。ブリックリンとフランクストンにビジカルクを一部売るごとに依然として37.5%の印税を払っていたのです。ビジカルクの売上は、ピーク時には1ヶ月3万部までに達しました。ビジコープ社は契約に従って、1983年だけでソフトウェア・アーツ社に1200万ドル(29億円)支払わなければならなかったのです。どちらの会社も、これほどの額になるとは予想もしていませんでした。
- フィルストラは、会社の負担を軽くするために新しい契約を交わしたいと思っていましたが、彼には相手に変更を強いるだけの力はありませんでした。契約は契約なのです。それに、プログラミングの内部の厳密な規則を理解しそしてその規則に従うのがブリックリンとフランクストンの仕事の基本なのです。彼らのようなハッカーが自分たちの有利な立場(今回の契約)を放棄するはずがありません。契約のもとにビジコープが権利として持っている強制力は、ソフトウェア・アーツ(ブリックリンとフラクストン)に対してフィルストラが希望するすべてのコンピュータにビジカルクを移植させることしかありませんでした。
- そこでフィルストラは、ブリックリンにあらゆるマイクロコンピュータにビジカルクを移植させたのです。
- ビジコープにもソフトウェア・アーツにも互いに37.5%という印税率が高すぎることはわかっていました。現在でこそ、印税率は15%前後が一般的だと言われています。フィルストラはビジカルクの全権利を所有したかったのですが、二年間にわたってその交渉を続けたものの両社が合意に達することはありませんでした。
- ビジコープ社は、同じ印税でビジカルク以外の製品も販売していました。その中の一つに、ミッチー・ケーパー(Mitch Kapor:後のLotusの創設者、1950 〜)とエリック・ローゼンフィールドが書いた「ビジプロット/ビジトレンド」(VisiPlot/VisiTrend)があります。ビジプロット/ビジトレンドと呼ばれるソフトウェアは、ビジカルクの機能を拡張するプログラムでした。ビジElickカルクやほかのプログラムからデータを取り込んでグラフを作成し、統計学的分析を加えてデータから傾向を読みとることができるソフトウェアでした。これは株式市場の分析には格好のプログラムだったのです。
- ミッチー・ケイパーは1951年米国マサチューセッツ州に生まれました。経歴は少し変わっていてエール大学時代は主に心理学を専攻しラジオ局やコメディアンなどの職に就いていたそうですが点々と職を変えたようです。一時期宗教にも凝りその世界に入っていきますが、1978年、ビーコン・カレッジに入学し直し心理学を勉強する傍らコンピュータに魅せられて行きます。そうした中で、マサチューセッツ工科大学(MIT)の院生らの研究を手伝うようになります。
- 大学院の学生には、さまざまな研究が割り当てられます。ミッチー・ケーパーも、大学院にいた頃に数多くの研究を割り当てられていました。「ビジプロット/ビジトレンド」はその中で開発されたソフトウェアの一つでした。これはMITのスローン経営学研究室での研究の最中に書いたプログラムがもとになっていました。TROLLという計量経済学のために開発されたモデリング言語を使って、統計学の論文を書いていたケーパーの友人ローゼンフィールドは、MITのコンピュータシステムの使用時間を減らし、使用料を節約しようとしていました。そこでケーパーはこれに協力するために、彼が「タイニーTROLL」と呼ぶプログラムを書いたのです。これは、TROLLのマイクロコンピュータ用サブセットプログラムでした。このタイニーTROLLがのちにビジカルクのファイルが読み込まれるように書き直され、やがて「ビジプロット/ビジトレンド」となっていったのです。
- 高い印税率にもかかわらず、ビジコープ社は当時のマイクロコンピュータソフトウェア会社の中で最も成功した会社でした。成功した会社にとってソフトウェア商売というのは紙幣印刷のライセンスのようなものなのです。アプリケーションを書く費用を差し引くと、利幅は90%近くになるのです。たとえば、ビジプロット/ビジトレンドの価格は249ドル95セントですが、販売代理店にはその60%引き、つまり99ドル98セントで卸されます。ケーパーの印税はその37.5%ですから一部当たり37ドル49セントになります。ビジコープには62ドル49セント残り、ここからフロッピーディスクとマニュアルを製造費として15ドル程度を支払い、マーケッティングのコストに約25ドル払ってもまだ22ドル49セントの利益が残る計算になります。ケーパーとローゼンフィールドは1981年と82年の2年間で、ビジプロット/ビジトレンドの印税として約50万ドル(1億1000万円)の収入を得ました。このソフトウェアが、もともとスローン研究室のタイムシェアリングシステムの使用料を節約することから始まったものであることを考えれば、これは大きな金額でした。しかし、ダン・ブリックリンとボブ・フランクストンは、ビジコープの本当のドル箱であるビジカルクからその10倍の金を稼いでいたのです。
- ミッチー・ケーパーは、この違いにどんな意味があるのかよくわかっていました。
- ↑にメニューバーが現れない場合、
- ←クリックして下さい。
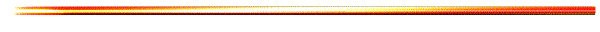
- ↑にメニューバーが現れない場合、
- ←クリックして下さい。
-
- ---- パソコンの文化 その22 おわり ------
 目次に戻る
目次に戻る
- ---- つづく ----
- 参考文献:
- ●『アップル-世界を変えた天才たちの20年』(上・下)
- ジム・カールトン、山崎理仁訳、早川書房、1998.9.30初版
- ●『アップル・コンフィデンシャル』
- Owen W. Linzmayer、林伸行、柴田文彦訳、(株)アスキー、2000.1.12初版
- ●『ノンストップ・コンピュータのしくみがわかる本』
- 麹町FTC研究会 著、日本タンデムコンピュータ(株)監修、1992.12.1初版、(株)工業調査会
- ●『次世代マイクロプロセッサ - マルチメディア革命をもたらす驚異のチップ -』
- 嶋 正利、1995.2.24、1版1刷、日本経済新聞社
- ●『マッキントッシュ物語』
- スティーブン・レヴィ(Steven Levy)著、翔泳社
- ●『コンピュータ帝国の興亡』上・下
- ロバート・X・クリンジリー、薮暁彦 訳、1993.3.21初版、(株)アスキー
- ●『スーパーコンピュータを創った男 - 世界最速のマシンに賭けたシーモア・クレイの生涯』
- チャールズ・マーレイ著、小林 達監訳、廣済堂出版 1998年4月30日初版
- ●『パソコンビジネスの巨星たち』米国パソコン界を創ったキーマンに聞く成功の戦略
- Tim Scannell(ティム・スキャネル)著、日暮雅道訳、ソフトバンク(株)1991.7.20初版
- ●『メガメディアの衝撃』(Megamedia Shakeout)
- ケビン・メイニー著、古賀林 幸訳、1995.11.30第一刷、徳間書店
- ●『ビル・ゲイツ』執念とビジョンの企業戦略家
- 中川 貴雄(なかがわ たかお)著、1995.7.5 初版 中央経済社
- ● NHKスペシャル『新・電子立国1巻〜6巻』
- 相田 洋著、NHK取材班 大墻 敦、1996.12.20第1刷、日本放送協会
- ●『ビル・ゲイツ未来を語る - Bill Gates The Road Ahead』
- 西和彦 訳、(株)アスキー、1995年12月11日初版
- ●『インターネット革命』
- 大前研一、1995.1.30初版、1995.2.28 第5刷、(株)プレジデント発行
- ●『暴走する帝国 - インターネットをめぐるマイクロソフトの終わりなき闘い』
- Overdirive - Bill Gates and the Race to Contorol Cyberspace、
- ジェイムズ・ウォレスJames Wallace、武舎広幸・武舎るみ、1998.3.30 初版 翔泳社
- ●『AT&TとIBM』
- 那野比古、講談社現代新書 1989.06.20初版
- ●『電脳のサムライたち〜西和彦とその時代』
- 滝田誠一郎、実業之日本社、1997.12.19初版
- ●『サン・マイクロシステムズ - UNIXワークステーションを創った男たち』
- Mark Hall/John Barry、オフィスK 訳、(株)アスキー、1991.5.1初版
- ●『実録! 天才プログラマー』
- スーザン・ラマース/マイクロソフトプレス、岡 和夫 訳、(株)アスキー、1987.2.11初版
- ●『僕らのパソコン10年史』
- SE編集部 編、翔泳社、1989.9.30初版
 目次に戻る
目次に戻る
- ---- パソコンの文化 その22 おわり ------