- 英語がカッコよく話せたらなぁ、と誰しも思う。思うこととできることは全く別次元で、この次元を取り持つのは、本人の才能とやる気にかかっている。
- 才能がある人はうらやましいと思う。比較的努力をせずに身についてしまうのだから。しかし、英語を習得するのは、プロ野球の一軍の選手になることでもなければ、オリンピックで金メダルを取るほどの難しいことでもない。英国に行けば3才の坊やだって英語を話しているではないか。肝心なことは自分の道具として英語が身につけることであり、自分の能力に応じて英語が話せればよい。米国人だってそうしている。日本人だって能力に応じて日本語を話している。所詮、自分の考えている世界以上のことは英語に置き換えられないのだ。英語がある程度話せるようになると、今度はそれを使って何を相手に伝えるのかが問われる。「おなかがすいた」、「疲れた」などの基本的会話は比較的簡単に憶えられる。問題はそれからである。
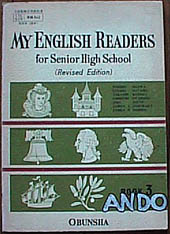
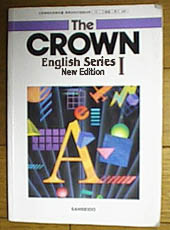 1998年、息子が使っている高校の英語の教科書を見た。我々が習った教科書より、一層米語寄りのカリキュラムになっていた。また、米口語を多用してより現実的な英語(アメリカ英語)を身につけさせているように見えた。息子の使用している教科書は、SANSEIDOの 「The CROWN English Series I」だった。我々のテキストより50%程度厚く、テキスト、写真、図がふんだんに盛り込まれていた。テキストの中には、17年前に我々が学んだ教科書にも載っていたイギリス自然科学者『ダーウィン Charles Darwin』のエピソードがあった。 ガラパゴス島の風景と進化論の着想のエピソードは時代を超えて興味ある題材のようである。また、テキストの内容には、学生から見た視点で書かれたものが多いように思えた。息子の高校2年の教科書には、赤毛のアン、動物たちのsupersense(超能力)、ビートルズ、2001年宇宙の旅、アウサン・スー・チーなどの話題が豊富に載っていた。高校2年にもなるとさすがに歯ごたえがあった。過日、わが愚息とこのリーダーで「赤毛のアン」の読み合わせを行った。小説は、多分に前置詞(on、at、in)を駆使して状況・情景を明確にしようと努めている。こうした前置詞の妙味を味わえるようになると英語が少し分かってくる。
1998年、息子が使っている高校の英語の教科書を見た。我々が習った教科書より、一層米語寄りのカリキュラムになっていた。また、米口語を多用してより現実的な英語(アメリカ英語)を身につけさせているように見えた。息子の使用している教科書は、SANSEIDOの 「The CROWN English Series I」だった。我々のテキストより50%程度厚く、テキスト、写真、図がふんだんに盛り込まれていた。テキストの中には、17年前に我々が学んだ教科書にも載っていたイギリス自然科学者『ダーウィン Charles Darwin』のエピソードがあった。 ガラパゴス島の風景と進化論の着想のエピソードは時代を超えて興味ある題材のようである。また、テキストの内容には、学生から見た視点で書かれたものが多いように思えた。息子の高校2年の教科書には、赤毛のアン、動物たちのsupersense(超能力)、ビートルズ、2001年宇宙の旅、アウサン・スー・チーなどの話題が豊富に載っていた。高校2年にもなるとさすがに歯ごたえがあった。過日、わが愚息とこのリーダーで「赤毛のアン」の読み合わせを行った。小説は、多分に前置詞(on、at、in)を駆使して状況・情景を明確にしようと努めている。こうした前置詞の妙味を味わえるようになると英語が少し分かってくる。

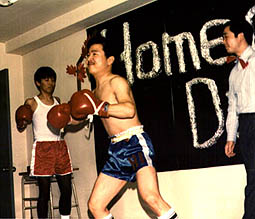





 道路を挟んだ町並みも古い外観を維持保存している。日本のようにどんどん壊して新しい建物を建てるようなことはしていない。斬新な建物はロンドンの中心ではなく郊外の新しい場所に建てられているのであろうか?何度かイギリスの地を訪れ、郊外も自動車で走ったことがあるが、高層ビルにはお目にかかったことがない。ロンドン市内も郊外も古い町並みを維持している感じを受けた。
道路を挟んだ町並みも古い外観を維持保存している。日本のようにどんどん壊して新しい建物を建てるようなことはしていない。斬新な建物はロンドンの中心ではなく郊外の新しい場所に建てられているのであろうか?何度かイギリスの地を訪れ、郊外も自動車で走ったことがあるが、高層ビルにはお目にかかったことがない。ロンドン市内も郊外も古い町並みを維持している感じを受けた。
 今年始めに新車発表されたローバーの乗用車の中では最高機種に属するものだという。イギリスは総じていろいろな車が走っている。イギリスの自動車産業が振るわなくなって輸入自動車が増えたためと思われる。日本の車も結構走っている。トヨタ、日産、ホンダ、マツダ、スズキが多い。特に日産とホンダはよく走っている。そのほか大衆車としてはFord、VW(フォルクスワーゲン)が多い。英国自動車はローバー、ジャガー、ロールスロイスであるがこれらはいずれも外国資本と提携してしまっている。ローバーは以前、ホンダと技術提携していたが最近ドイツBMWの傘下に入りエンジンはBMWを使っているという。私の好きな自動車評論家の徳大寺有恒さんは、このローバー75がお気に入りで日本で楽しく乗り回していらっしゃるという。イギリスの車の醍醐味はインテリアのまとめ方と足回りのしなやかさであろう。私はこの車でその良さを十分に堪能した。しかしエンジンの非力さを感じた。V6エンジン2.5リッタなのだが、出足の加速と、80Km/hから120Km/hに加速していく時にもたつきを感じた。エンジンが思ったより吹け上がらないのである。トランスミッションはオートマチックの5速と言われていてそれを知らないためにアクセルを十分に踏み込まなかったためシフトしなかったのかもしれない。そもそもがゆったり乗るミドルクラスの人向けのクルマであろうからオートマチックの味付けもそのようになっているのかもしれない。高速道路で80マイル/hで2,000rpmちょっとの回転数であったから5速のギアが効いていたのだろう。室内はいたって静かだった。
今年始めに新車発表されたローバーの乗用車の中では最高機種に属するものだという。イギリスは総じていろいろな車が走っている。イギリスの自動車産業が振るわなくなって輸入自動車が増えたためと思われる。日本の車も結構走っている。トヨタ、日産、ホンダ、マツダ、スズキが多い。特に日産とホンダはよく走っている。そのほか大衆車としてはFord、VW(フォルクスワーゲン)が多い。英国自動車はローバー、ジャガー、ロールスロイスであるがこれらはいずれも外国資本と提携してしまっている。ローバーは以前、ホンダと技術提携していたが最近ドイツBMWの傘下に入りエンジンはBMWを使っているという。私の好きな自動車評論家の徳大寺有恒さんは、このローバー75がお気に入りで日本で楽しく乗り回していらっしゃるという。イギリスの車の醍醐味はインテリアのまとめ方と足回りのしなやかさであろう。私はこの車でその良さを十分に堪能した。しかしエンジンの非力さを感じた。V6エンジン2.5リッタなのだが、出足の加速と、80Km/hから120Km/hに加速していく時にもたつきを感じた。エンジンが思ったより吹け上がらないのである。トランスミッションはオートマチックの5速と言われていてそれを知らないためにアクセルを十分に踏み込まなかったためシフトしなかったのかもしれない。そもそもがゆったり乗るミドルクラスの人向けのクルマであろうからオートマチックの味付けもそのようになっているのかもしれない。高速道路で80マイル/hで2,000rpmちょっとの回転数であったから5速のギアが効いていたのだろう。室内はいたって静かだった。
 イギリスの3日目は、ロンドン郊外、Oxford市の近くのThameという町で一泊した。この町は以前社用で来たことがありとてもすてきな田舎町という好印象を持っている。
イギリスの3日目は、ロンドン郊外、Oxford市の近くのThameという町で一泊した。この町は以前社用で来たことがありとてもすてきな田舎町という好印象を持っている。
 イギリスとフランス。良くも悪くも比較される老大国である。イギリスは、16世紀から19世紀にかけ世界を制覇した国。植民地政策を積極的に取り込み、産業革命の技術も後押しして莫大な富を手に入れた。フランスはローマ亡き後、(ヨーロッパ)大陸を支配してきたフランク王国の末裔である。ヨーロッパは諸国が群雄割拠した時代が長く続いたがフランク王国はその中で一番大きく強い勢力を維持していた。そのフランク王国がいくつかの革命を経て国民を中心とした国を一番早く作り上げ憲法も制定した。イギリスも議会民主主義を発展させてきたが、フランスよりは民族の出入りが少なく、国王の力が強く植民地政策もあって民主化は少し遅れた感じを受ける。パリには、ロンドンとは違う雰囲気がある。
イギリスとフランス。良くも悪くも比較される老大国である。イギリスは、16世紀から19世紀にかけ世界を制覇した国。植民地政策を積極的に取り込み、産業革命の技術も後押しして莫大な富を手に入れた。フランスはローマ亡き後、(ヨーロッパ)大陸を支配してきたフランク王国の末裔である。ヨーロッパは諸国が群雄割拠した時代が長く続いたがフランク王国はその中で一番大きく強い勢力を維持していた。そのフランク王国がいくつかの革命を経て国民を中心とした国を一番早く作り上げ憲法も制定した。イギリスも議会民主主義を発展させてきたが、フランスよりは民族の出入りが少なく、国王の力が強く植民地政策もあって民主化は少し遅れた感じを受ける。パリには、ロンドンとは違う雰囲気がある。
 ・彼らは日本の麺類は苦手。
・彼らは日本の麺類は苦手。