- ���οޤƲ����������־�β�����Ǥ�դ������X,Y�ˤȤ�����������ǻ�٤��D�ˤȤ��ޤ���
- �����Ѥ��Ƥ���������֤����顼�����Ͽ�Ǥ����Τʤ�С�ǻ�پ���ϡ����줾�쥫�顼����Ϳ����졢����3���������Ѥ�������ʤ��Db��Dg��Dr�ˡ� = �ġ��С��֡ˤ�3�Ĥξ�������뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���������ʿ�̾����ǻ�پ����3�����ξ����X,Y,D���������뤳�Ȥ��狼��ޤ����Dz襫���Τ褦�ˤ�������β����ƤǤ������֤�Ȥ��в�����˻��ä����־���Ϳ����졢�ǽ�Ū�ˤ���X,Y,D,T�ˤλͤĤξ�����Ϳ�����뤳�Ȥˤʤ�ޤ���
- ����°����γ�Ҥ��������ǻ��Ƥ���������פ��⤫�٤Ʋ��������������ǤϤ����������礭����γ�Ҥ�����������Ϥ��Ǥ��������̿��˻��äơ���İ���礭����¬�äƤ��ä�γ�¤Ȥ������٤�ɽ���ҥ��ȥ�������夲�뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ����Ƕ�Ǥϡ���������CCD���������դ���CCD�����β�����ľ�ܥ���ԥ塼���μ����ळ�Ȥ��Ǥ����������������������������եȤ�¨�¤˥ҥ��ȥ������뤳�Ȥ��Ǥ���褦�ˤʤ�ޤ�����
- ����ޤϡ�������ʬ���̣�����ݤΰ�ư����ʪ�Τ��ǤȤ館�ʤ⤷���ϰ����¿��Ϫ���ʤɤˤ�군�̿����Ƥ�Ԥ��ˡ��������ư����ʪ�Τ�®�٤������ˡ������ΤǤ���10ǯ�ۤ����������ѥӥǥ������ǡ���ư����ʪ�ΤΤߤ���ư����¿��Ϫ����������ˡ�����Ѥ��졢�ץ������Ѥǥԥå��㡼����嵰�פ�ɽ������Τ˻Ȥ��ޤ��������������ư�����Υ����Ф���������Ψ���θ���ʤ���ºݤ��Ѱ̤��������ʬ����®�٤���ޤ����ޤ���ư�٥��ȥ�ʤɤ���뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ�����®�٥����Ǥϡ�����������������ʤ��饿�����åȺ�ɸ��ԥ塼���˵��������ޤ���
- �����̤ˡ���������ʪ�Τ�ư�����ɤ��������ˡ�ϡ�γ������ˡ��PIV = Particle Image Velocimetry�ˤȤ�������ή�ι���ʬ���ȯŸ���ޤ�����
- ��
- ��


 ������ʪ�ΤƤ��븦��Ϻ����Τ��Ѥ�äƤ��ʤ��褦�˻פ��ޤ�������ष�����Ƕ�ϥߥ���Ū�ʹͻ����������������ʤɤγ�����طϤ��Ѥ�����®�ٻ��Ʊ��Ѥ������Ƥ���褦�˴����ޤ�����ʪ�θ���Τߤʤ餺����°�ù����ϼ͡�ʮ̸���桢�վ����桢�ץ饺�ޥǥ����ץ쥣�����Τ���γ��������ӥơ�����������åȥץ�ʤɡ������оݤ��ɤ�ɤ�ߥ���Ū�ʻ����˰ܤäƤ��봶��������ޤ���
������ʪ�ΤƤ��븦��Ϻ����Τ��Ѥ�äƤ��ʤ��褦�˻פ��ޤ�������ष�����Ƕ�ϥߥ���Ū�ʹͻ����������������ʤɤγ�����طϤ��Ѥ�����®�ٻ��Ʊ��Ѥ������Ƥ���褦�˴����ޤ�����ʪ�θ���Τߤʤ餺����°�ù����ϼ͡�ʮ̸���桢�վ����桢�ץ饺�ޥǥ����ץ쥣�����Τ���γ��������ӥơ�����������åȥץ�ʤɡ������оݤ��ɤ�ɤ�ߥ���Ū�ʻ����˰ܤäƤ��봶��������ޤ���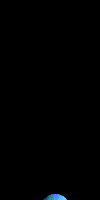 ������
������
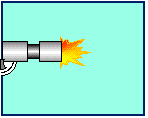 ������������������������������������
������������������������������������