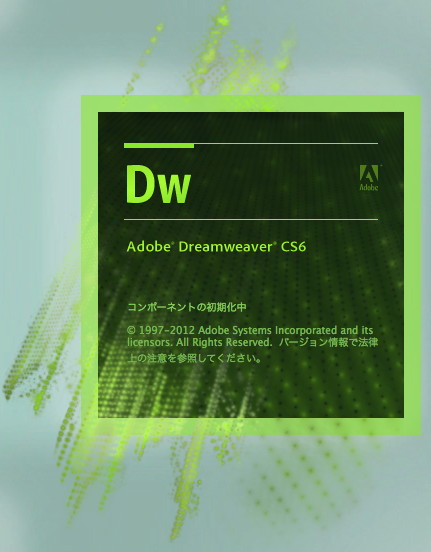
|
||||
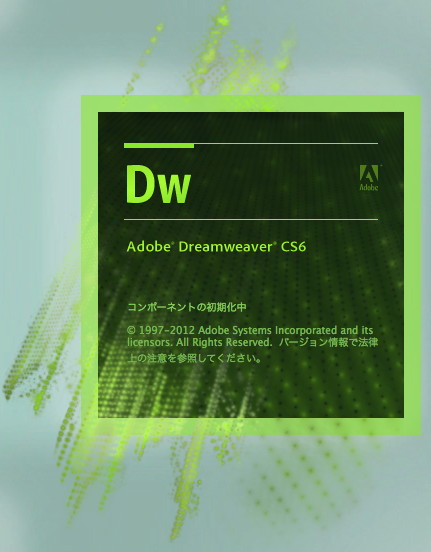 |
||||
| ���Υ���ƥ�Ĥϡ�Dreamweaver CS6������Ƥ��ޤ��� | ||||
��
��
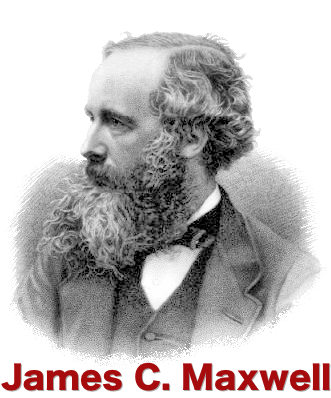
 ��ϡ��ɻ�¸������ť���åפ�Ȥä����Ť����ʲ����ȡˡ������15��ȥ�Υ�줿���֤˥�����Ǻ�ä���������֤������Ŵѻ���ԤäƤ��ޤ����������Ť����Ƽ����������Ť��������ȡ��������Υ���å����֤����Ť�������Τǡ�������ǧ���Ƥ����ˡ�
��ϡ��ɻ�¸������ť���åפ�Ȥä����Ť����ʲ����ȡˡ������15��ȥ�Υ�줿���֤˥�����Ǻ�ä���������֤������Ŵѻ���ԤäƤ��ޤ����������Ť����Ƽ����������Ť��������ȡ��������Υ���å����֤����Ť�������Τǡ�������ǧ���Ƥ����ˡ�
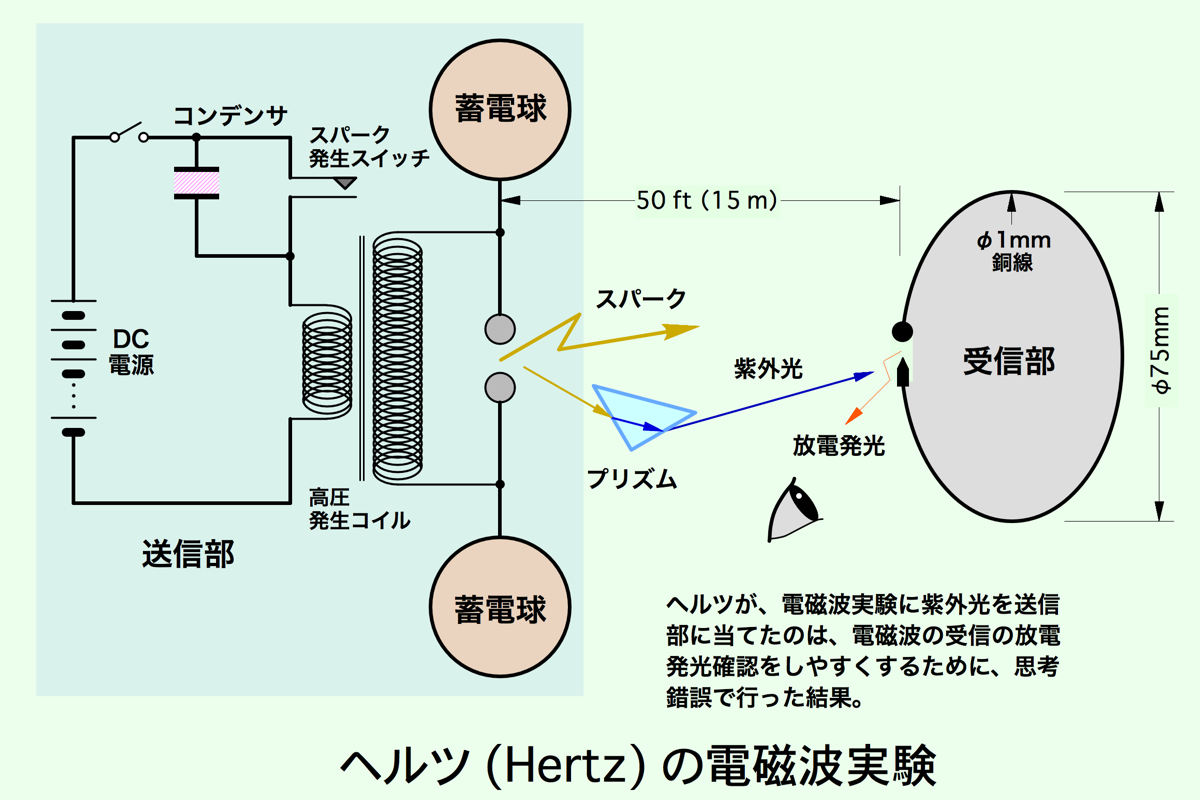
��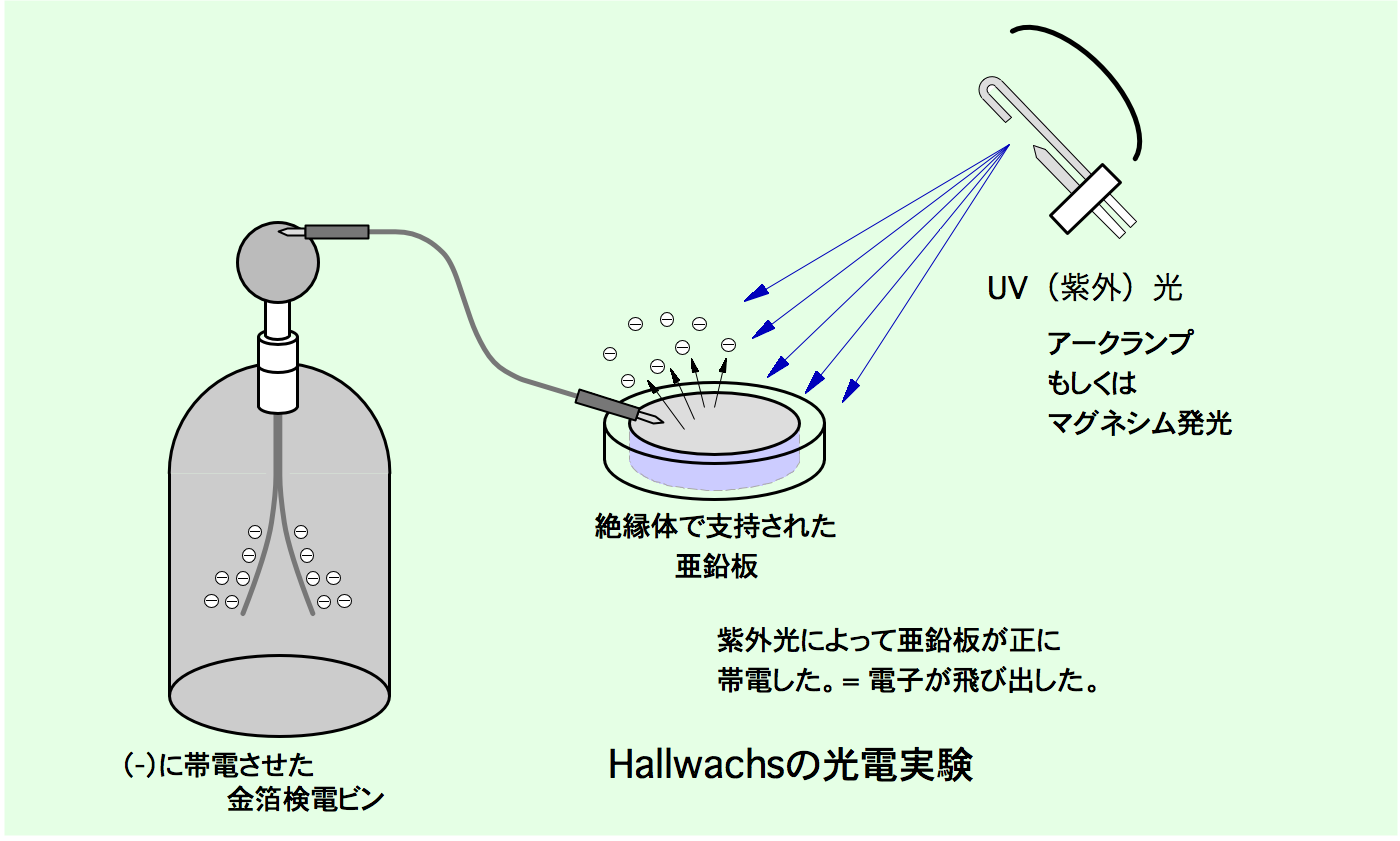 ��
��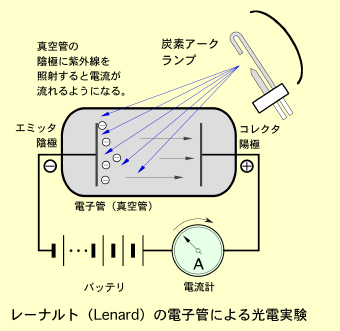
 ����ˡ�20ǯ���1902ǯ��Ʊ��Υե���åס��졼�ʥ�ȡ�Philipp Eduard Anton von Lenard��1862 - 1947���إ�Ĥ���ҡ�1905ǯ�Ρ��٥�ʪ���ؾ��ޡˤˤ�äơ���������=�Ż����ˤȸ��˴ؤ��뤵��ʤ붽̣�����������̤������ޤ����ʾ屦���ȡˡ�
����ˡ�20ǯ���1902ǯ��Ʊ��Υե���åס��졼�ʥ�ȡ�Philipp Eduard Anton von Lenard��1862 - 1947���إ�Ĥ���ҡ�1905ǯ�Ρ��٥�ʪ���ؾ��ޡˤˤ�äơ���������=�Ż����ˤȸ��˴ؤ��뤵��ʤ붽̣�����������̤������ޤ����ʾ屦���ȡˡ�
 �������̻���ι��ۤˤ����ơ����ȥ����Wilhelm Konrad Roentgen��1845-1923����1895ǯ��ȯ������X���ϡ�����¿��ʤ�ҥ�Ȥ�Ϳ���ޤ�����
�������̻���ι��ۤˤ����ơ����ȥ����Wilhelm Konrad Roentgen��1845-1923����1895ǯ��ȯ������X���ϡ�����¿��ʤ�ҥ�Ȥ�Ϳ���ޤ�����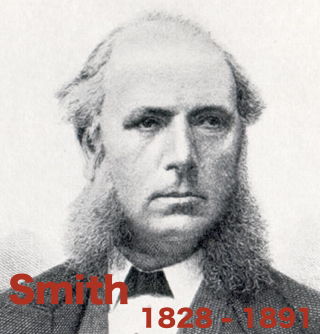
 ��ϡ�ͻ�������ꥳ���Ȥä���ʬŪ�˹���ٲ�������ˡ����Ѥ��ޤ���
��ϡ�ͻ�������ꥳ���Ȥä���ʬŪ�˹���ٲ�������ˡ����Ѥ��ޤ���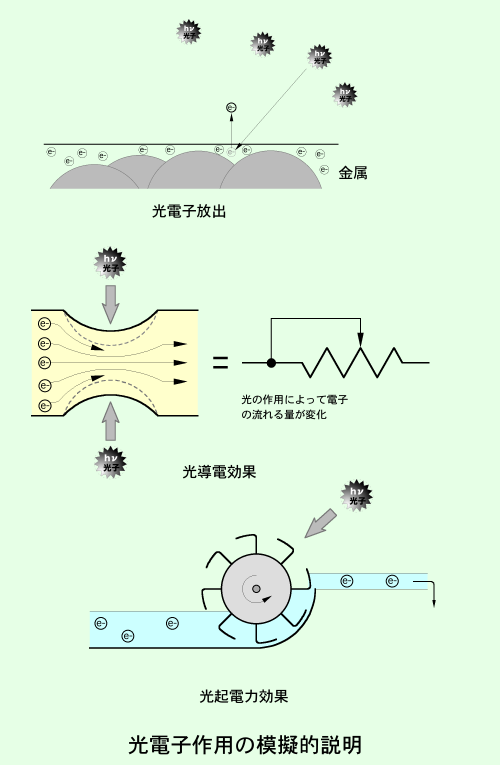 �� ��
�� �� 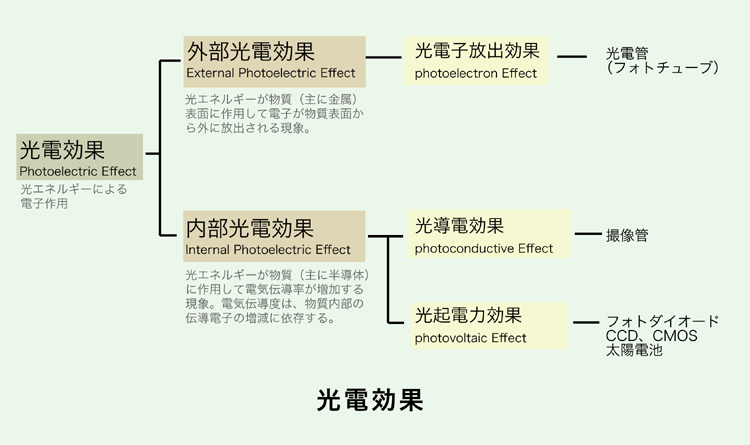
|
|||||
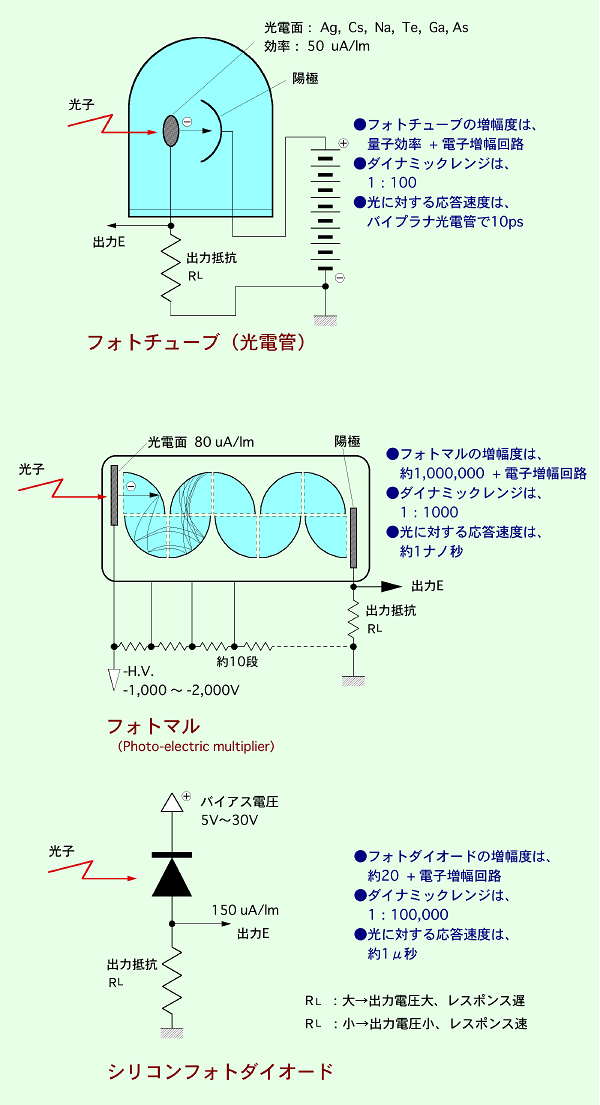 ��
�� 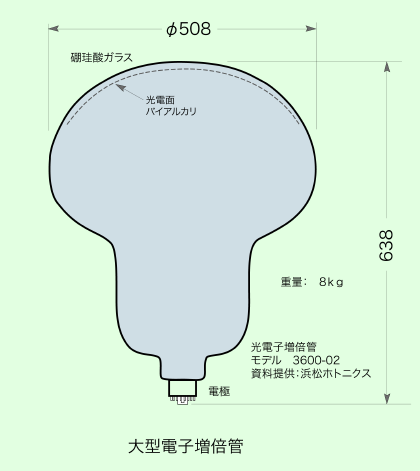 �ե��ȥޥ�λȤ��Ƥ�����ɽŪ�ʻ����Ҳ𤷤ޤ���
�ե��ȥޥ�λȤ��Ƥ�����ɽŪ�ʻ����Ҳ𤷤ޤ���
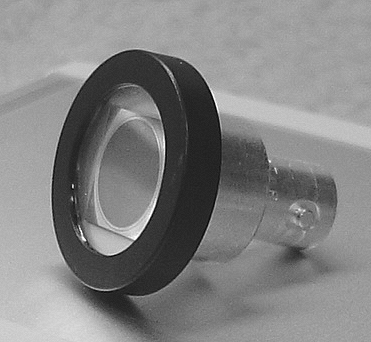 |
|||
�ե��ȥ��������ɡʻ��͡ˡ� �����Ϥ��������ʥ����פ����롣�̿��Ϻ����γ������α߷������ե��ȥ���������������ü�Ҥ�BNC�ˤʤäƤ��ƻȤ��䤹���� |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
��
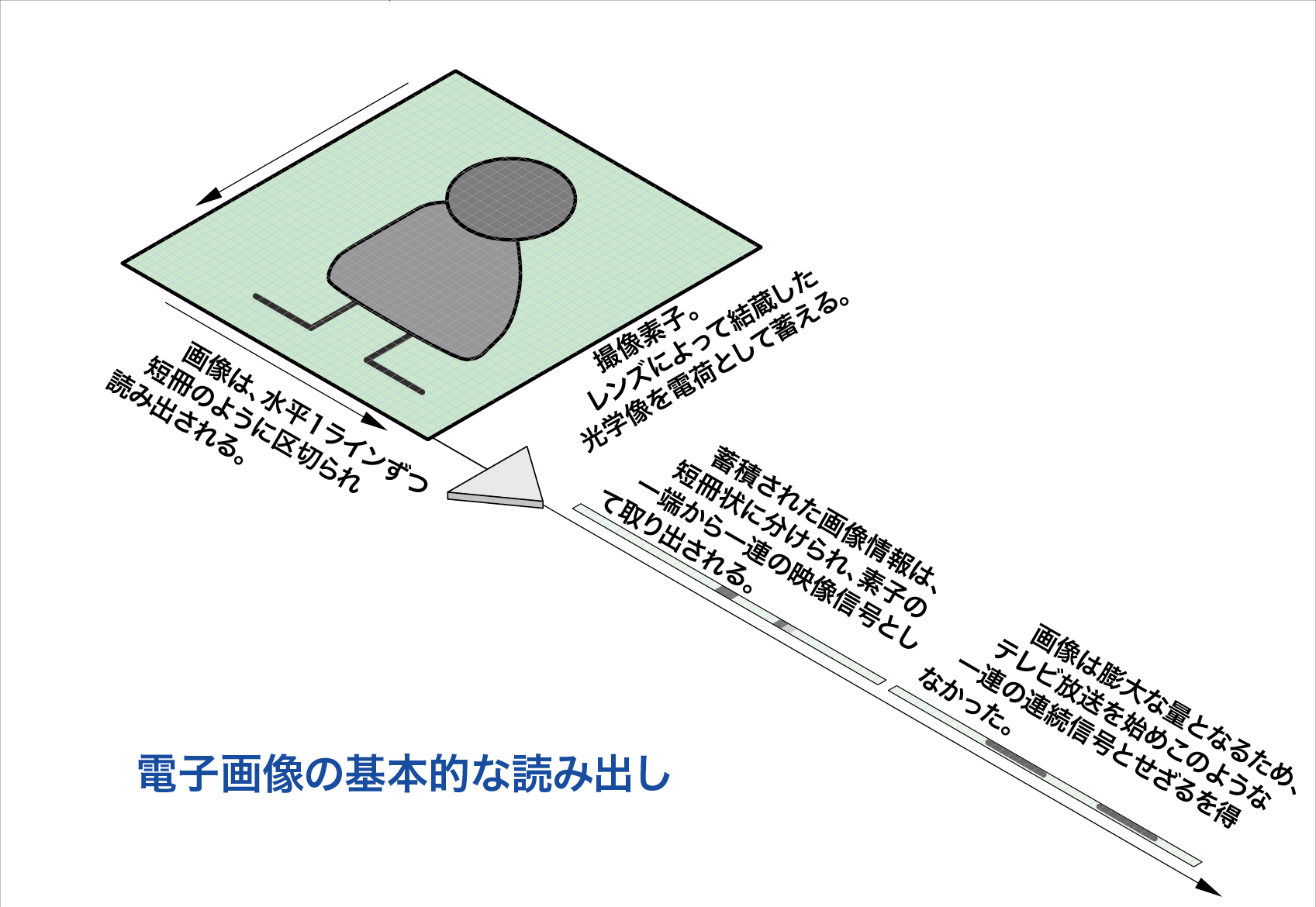 �Ż߲����ˤ����Ƥϡ�����Υե�����������ĤλؿˤǤ�����
�Ż߲����ˤ����Ƥϡ�����Υե�����������ĤλؿˤǤ�����
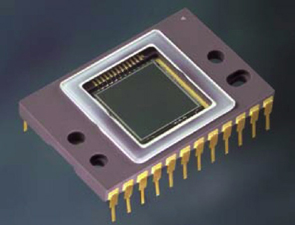
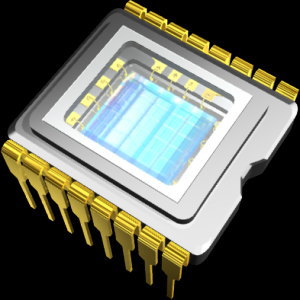 Ʊ���塢��Ω�����C-MOS�����פλ����ǻҤ���ȯ������β�����ޤ�����
Ʊ���塢��Ω�����C-MOS�����פλ����ǻҤ���ȯ������β�����ޤ�����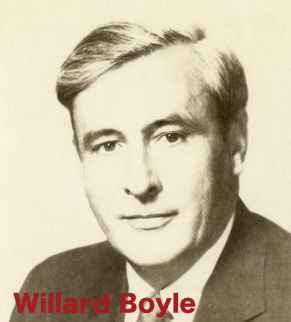 ������ޤ�����
������ޤ�����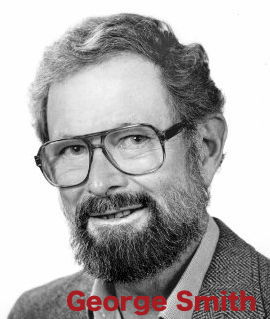 �˥ȥ�����Υ����å���ȤäƼ��Ф����ᡢ�����å��Υ�����¿�������줬�����˰��ƶ���Ϳ���ơ�S/N�椬���ޤ��ɤ��ʤ���CCDž����������٤��礭�ʥϥ�ǥ�����åפ�����äƤ��ޤ�����
�˥ȥ�����Υ����å���ȤäƼ��Ф����ᡢ�����å��Υ�����¿�������줬�����˰��ƶ���Ϳ���ơ�S/N�椬���ޤ��ɤ��ʤ���CCDž����������٤��礭�ʥϥ�ǥ�����åפ�����äƤ��ޤ�������
 ���ȤΥץ��������Ȥȸ����ΤϷäޤ줿�Ķ�����ǰ�Ƥ��ƴ��������Τ��ȡ��伫�ȤϻפäƤ��ޤ�����
���ȤΥץ��������Ȥȸ����ΤϷäޤ줿�Ķ�����ǰ�Ƥ��ƴ��������Τ��ȡ��伫�ȤϻפäƤ��ޤ�����
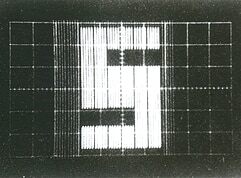 ���һ�ϡ������ʸ�����ɤ��CCD�λ����Τꡢ��̣��Ф����ȳؤ�CCD�θ���˼�꤫����ޤ���1970ǯ12��Τ��ȤǤ�����
���һ�ϡ������ʸ�����ɤ��CCD�λ����Τꡢ��̣��Ф����ȳؤ�CCD�θ���˼�꤫����ޤ���1970ǯ12��Τ��ȤǤ����� �����ʾ���48ǯ��1973ǯ�ˤΥ��ˡ��β�һ���ȸ����С����㡼�פ���ȯ����4�ӥåȥޥ�������¢���Żҷ�������ȯŪ�����Ԥ��Τ����������ơ�6ǯ����1967ǯ�ʾ���41ǯ�ˤ˳�ȯ����������ʤȤʤäƤ����ŵ������֥��Хå��� = SOBAX = Solid State Abacus���Żҥ����Х�פ����Ԥ����Ѥä���ߤ�Ǥ��ޤä������Ǥ�����
�����ʾ���48ǯ��1973ǯ�ˤΥ��ˡ��β�һ���ȸ����С����㡼�פ���ȯ����4�ӥåȥޥ�������¢���Żҷ�������ȯŪ�����Ԥ��Τ����������ơ�6ǯ����1967ǯ�ʾ���41ǯ�ˤ˳�ȯ����������ʤȤʤäƤ����ŵ������֥��Хå��� = SOBAX = Solid State Abacus���Żҥ����Х�פ����Ԥ����Ѥä���ߤ�Ǥ��ޤä������Ǥ����� ��Ĺ�δ�ֻ�ϡ����ʤⴰ�����Ƥ��ʤ������������˳�ȯ�Ӿ��CCD�����������ߡ���ʸ���äƤ��ޤ��ޤ�����
��Ĺ�δ�ֻ�ϡ����ʤⴰ�����Ƥ��ʤ������������˳�ȯ�Ӿ��CCD�����������ߡ���ʸ���äƤ��ޤ��ޤ�����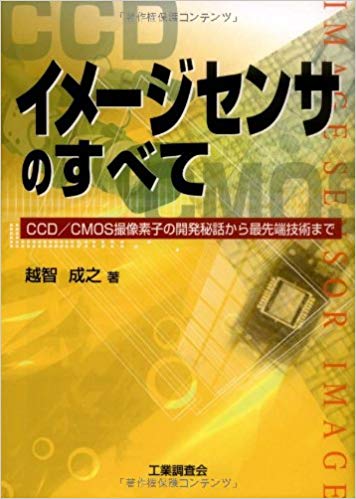
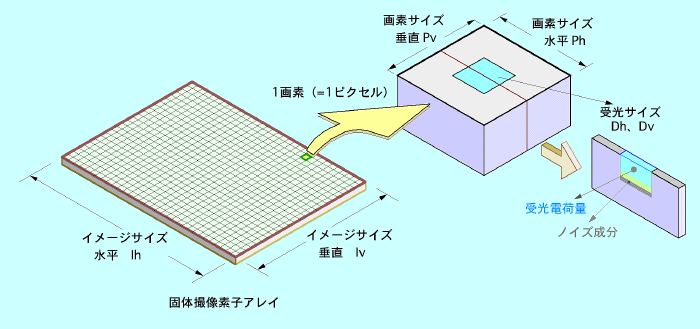 ������������ϡ������礭����ɽ����硢����Ū��1���������2/3���������1/2���������1/3��������Ȥ����������ǸƤӡ����θƾΤǤ����������礭�����狼��褦�ˤʤäƤ��ޤ���
������������ϡ������礭����ɽ����硢����Ū��1���������2/3���������1/2���������1/3��������Ȥ����������ǸƤӡ����θƾΤǤ����������礭�����狼��褦�ˤʤäƤ��ޤ���
|
|||||
��CCD�����ǻҤμ����
1.�������饤��ȥ�ե�������IT-CCD������-�������ߡ�����Ū�ʤ��
2.���ե졼�।���饤��ȥ�ե�������FIT-CCD����-���������ѤȤ��ƻȤ��Ƥ�����
3.���ե�ե졼��ȥ�ե��������������ʤ��ˡ�FF-CCD����-��CCD�ν���Τ��
4.���ե졼��ȥ�ե�����������������ˡ�FT-CCD����-���ե졼��ȥ�ե����β�����
5.���������ɤ߽Ф��ʥץ�����å��֥������˷���-�������饤��ȥ�ե��β��ɷ��ʥ����졼����Ԥ�ʤ���Ρ�
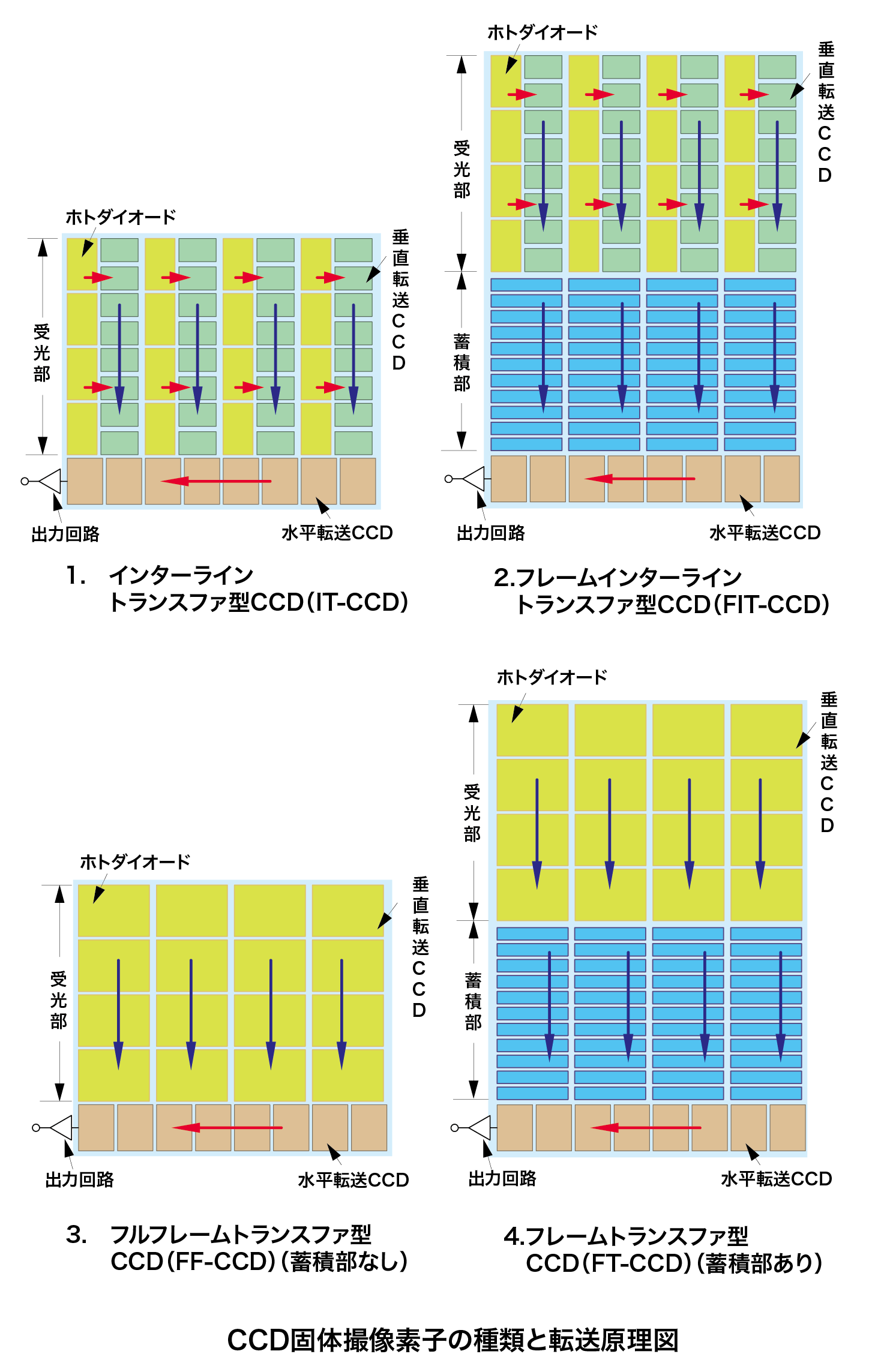
��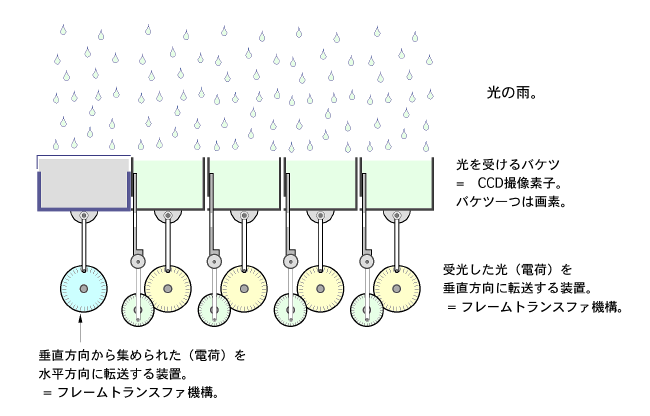
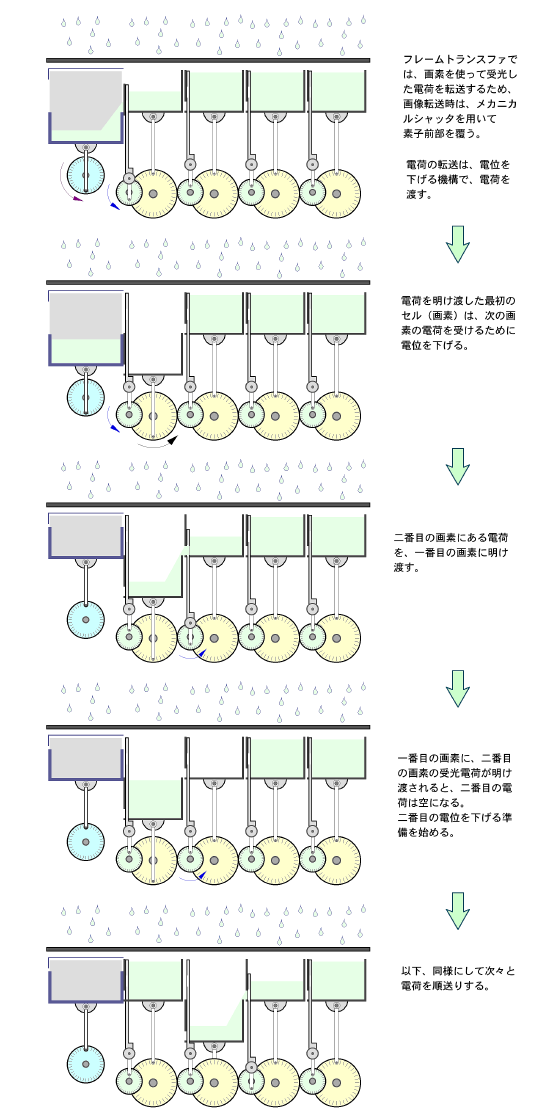 ��¤������ץ�ʤΤǡ�CCD�λ��Ȥߤ�����ˤϰ����ɤ������פ��Ȼפ��ޤ���
��¤������ץ�ʤΤǡ�CCD�λ��Ȥߤ�����ˤϰ����ɤ������פ��Ȼפ��ޤ���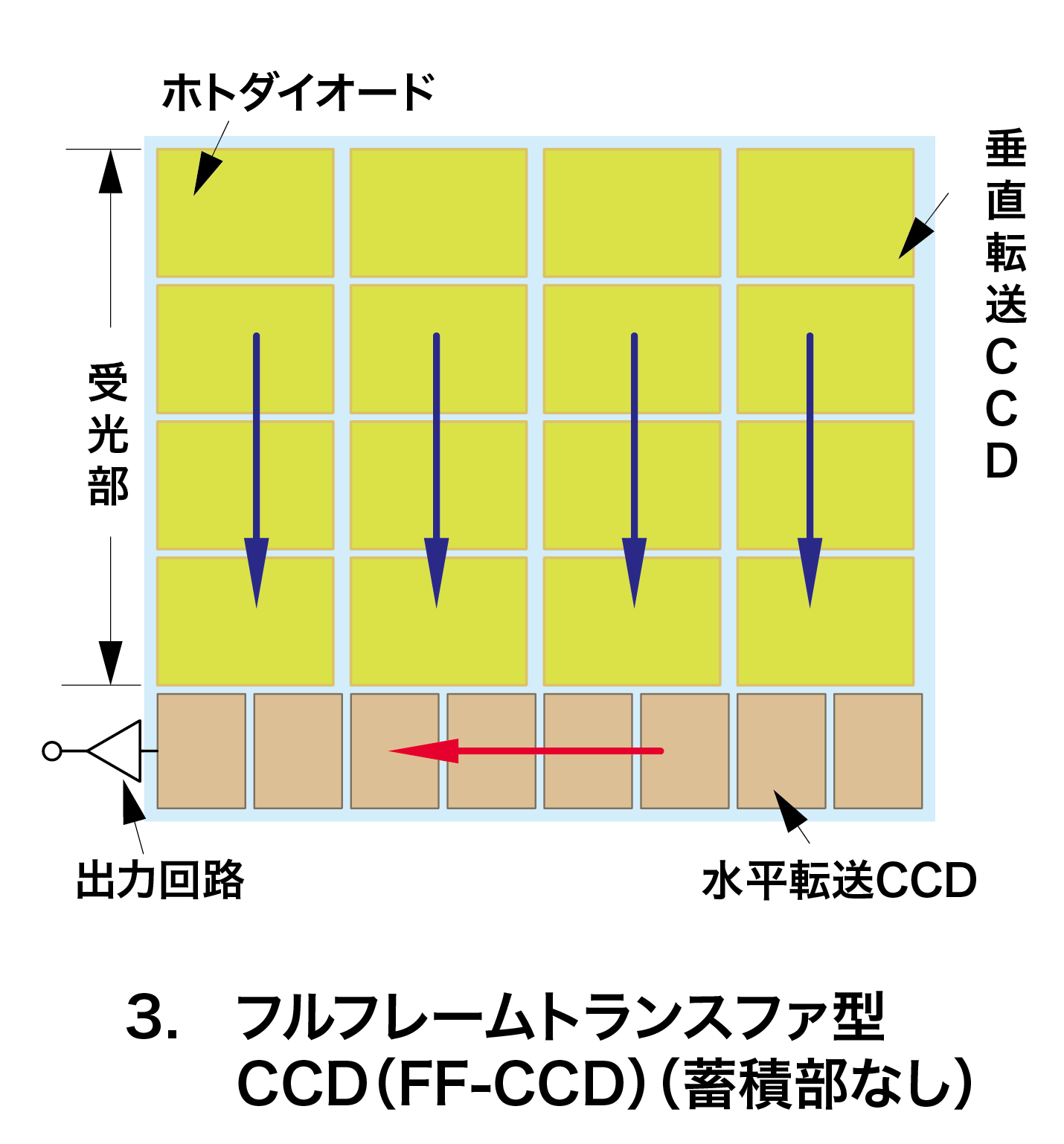 ��ž���λ��Ȥߡ�
��ž���λ��Ȥߡ�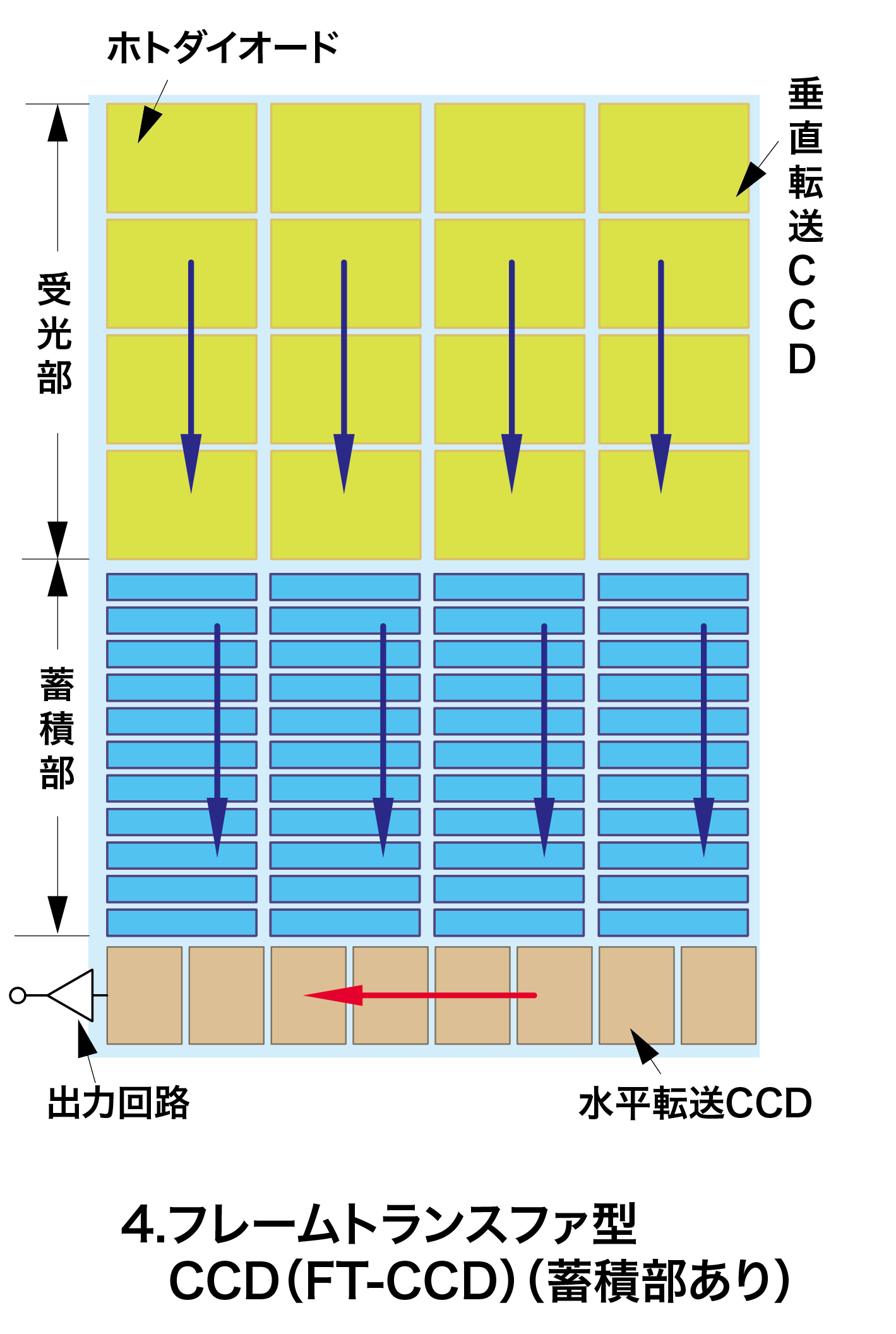 1��β������ɤ߽Ф��Τ�2.6�ä����뤳�Ȥˤʤ�ޤ���
1��β������ɤ߽Ф��Τ�2.6�ä����뤳�Ȥˤʤ�ޤ���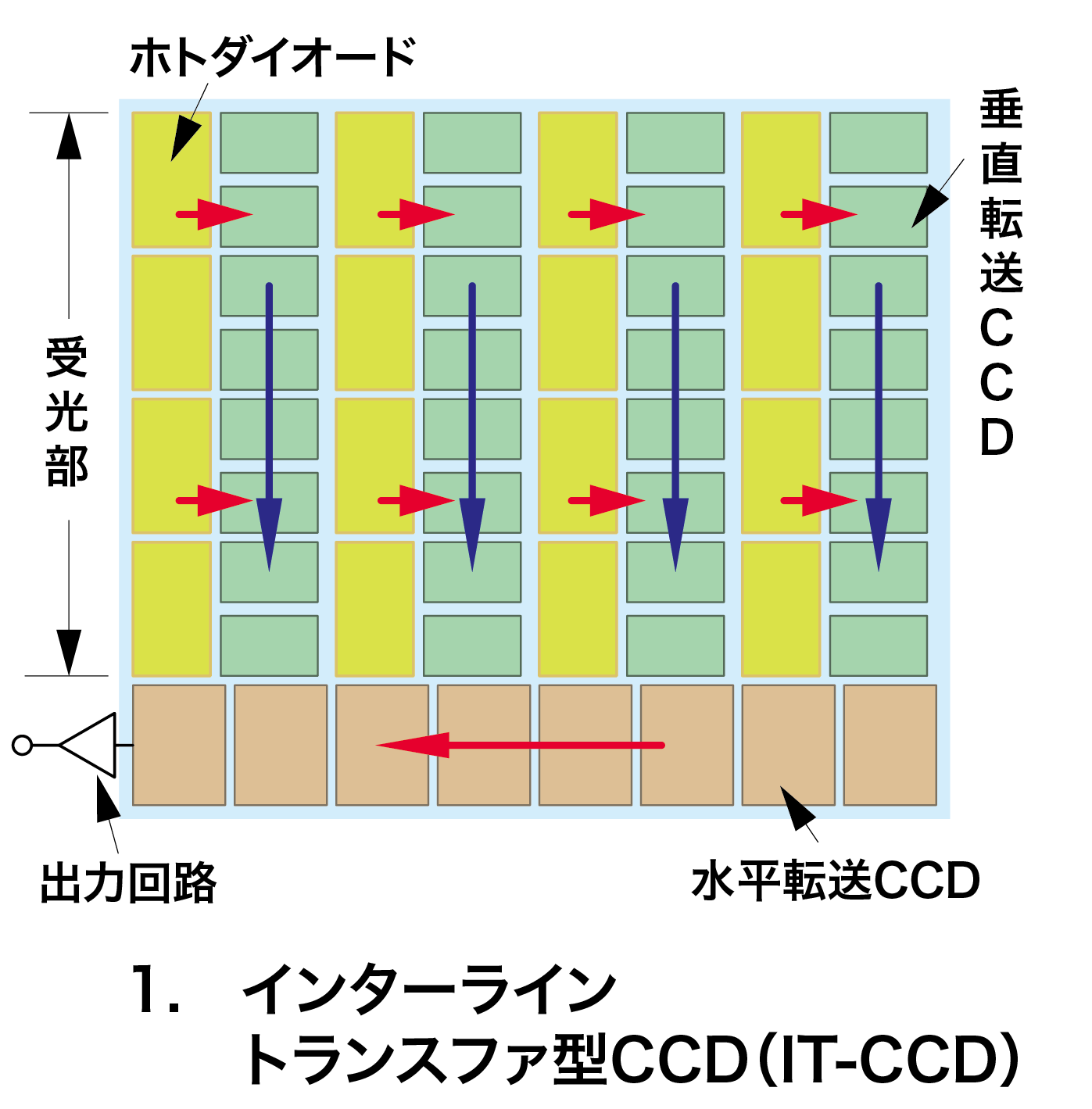 1.�Υ����饤��ȥ�ե�����CCD��IT-CCD�ˤϡ�CCD����̾��Ȥ�ƤФ����ɽŪ�ʤ�ΤǤ���
1.�Υ����饤��ȥ�ե�����CCD��IT-CCD�ˤϡ�CCD����̾��Ȥ�ƤФ����ɽŪ�ʤ�ΤǤ���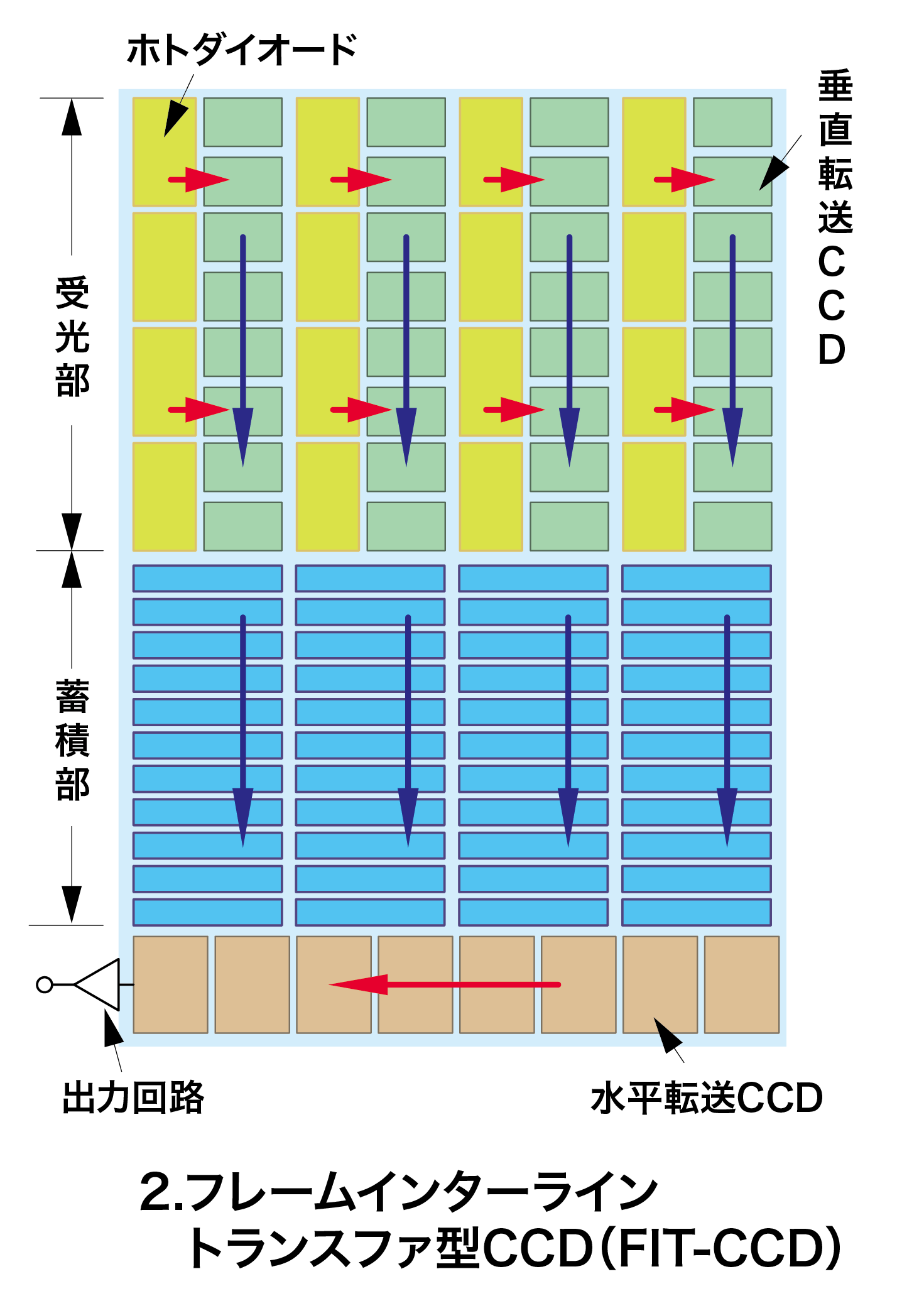 II.�Υե졼�।���饤��ȥ�ե�����CCD��FIT-CCD���ϡ������饤�Ǥ���ʤ�������������������CCD�Ǥ��ꡢ����Υ����饤��ꤵ��ʤ����ߥ��ʥ��ᥢ�������ɻߤΤ���˳�ȯ����ޤ�����
II.�Υե졼�।���饤��ȥ�ե�����CCD��FIT-CCD���ϡ������饤�Ǥ���ʤ�������������������CCD�Ǥ��ꡢ����Υ����饤��ꤵ��ʤ����ߥ��ʥ��ᥢ�������ɻߤΤ���˳�ȯ����ޤ�����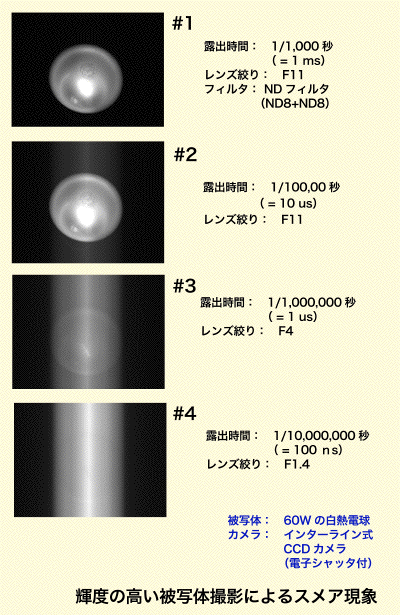
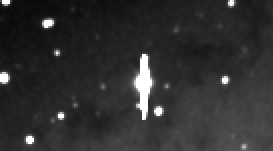
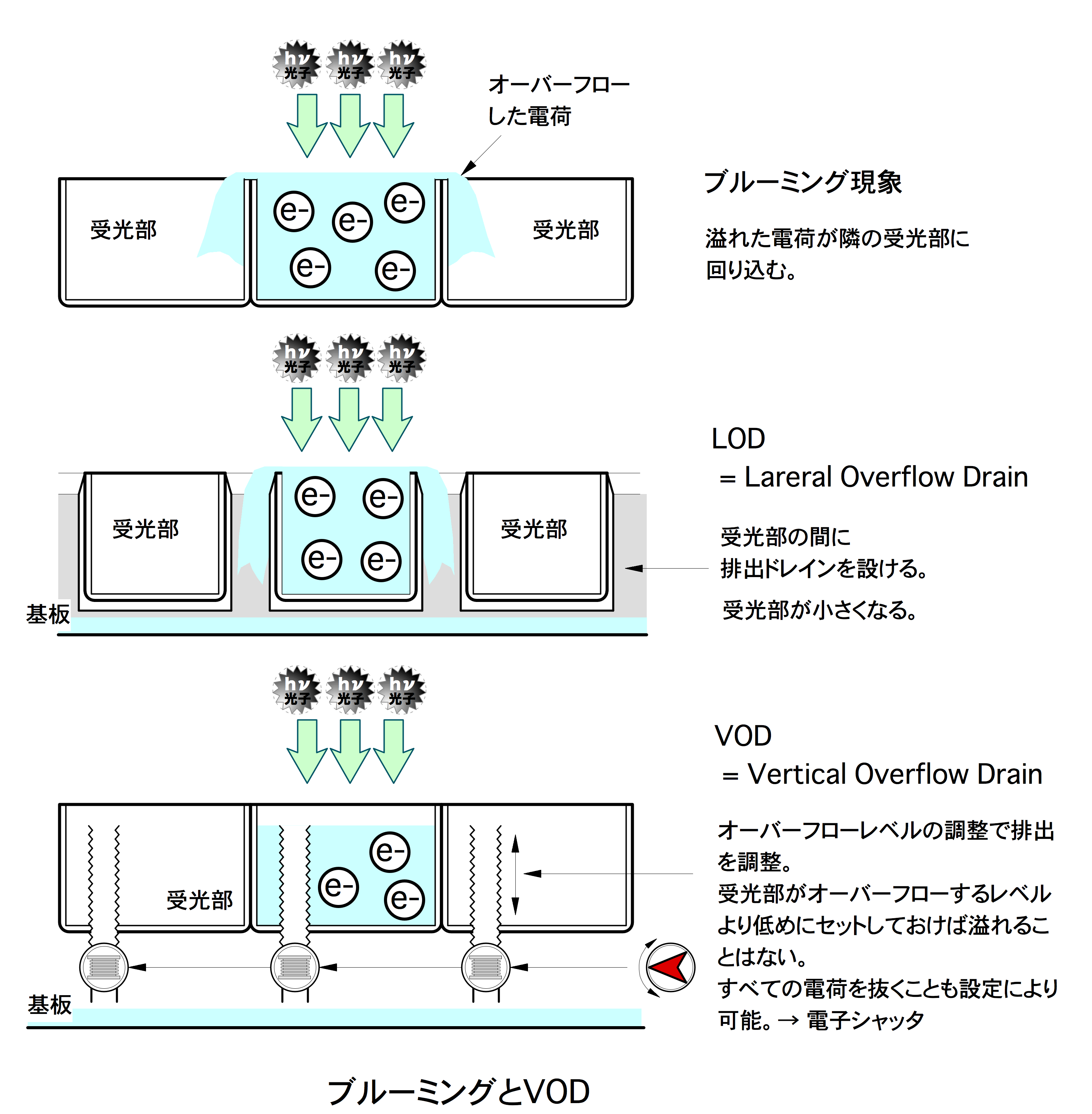 CCD�γ�ȯ����ˤ�Ҥ�Ȥ��Ƥߤޤ��ȡ�CCD�����ǻҳ�ȯ�ϥ��ߥ��ȥ֥롼�ߥȤ�Ʈ�����ä��褦�ʵ������ޤ���
CCD�γ�ȯ����ˤ�Ҥ�Ȥ��Ƥߤޤ��ȡ�CCD�����ǻҳ�ȯ�ϥ��ߥ��ȥ֥롼�ߥȤ�Ʈ�����ä��褦�ʵ������ޤ���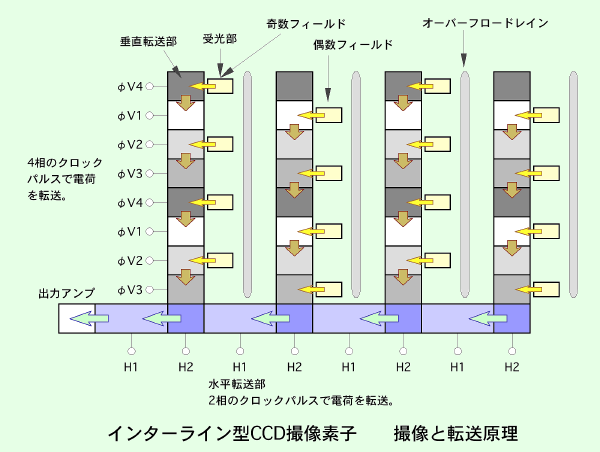
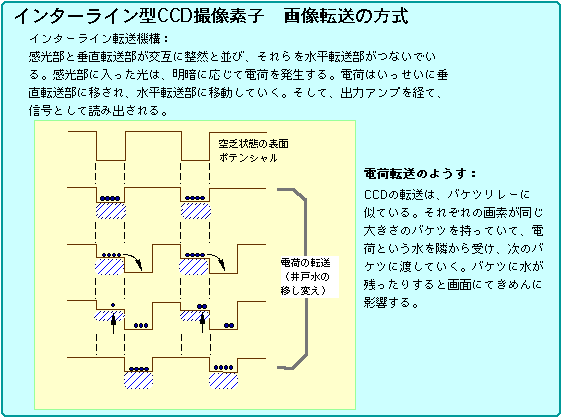
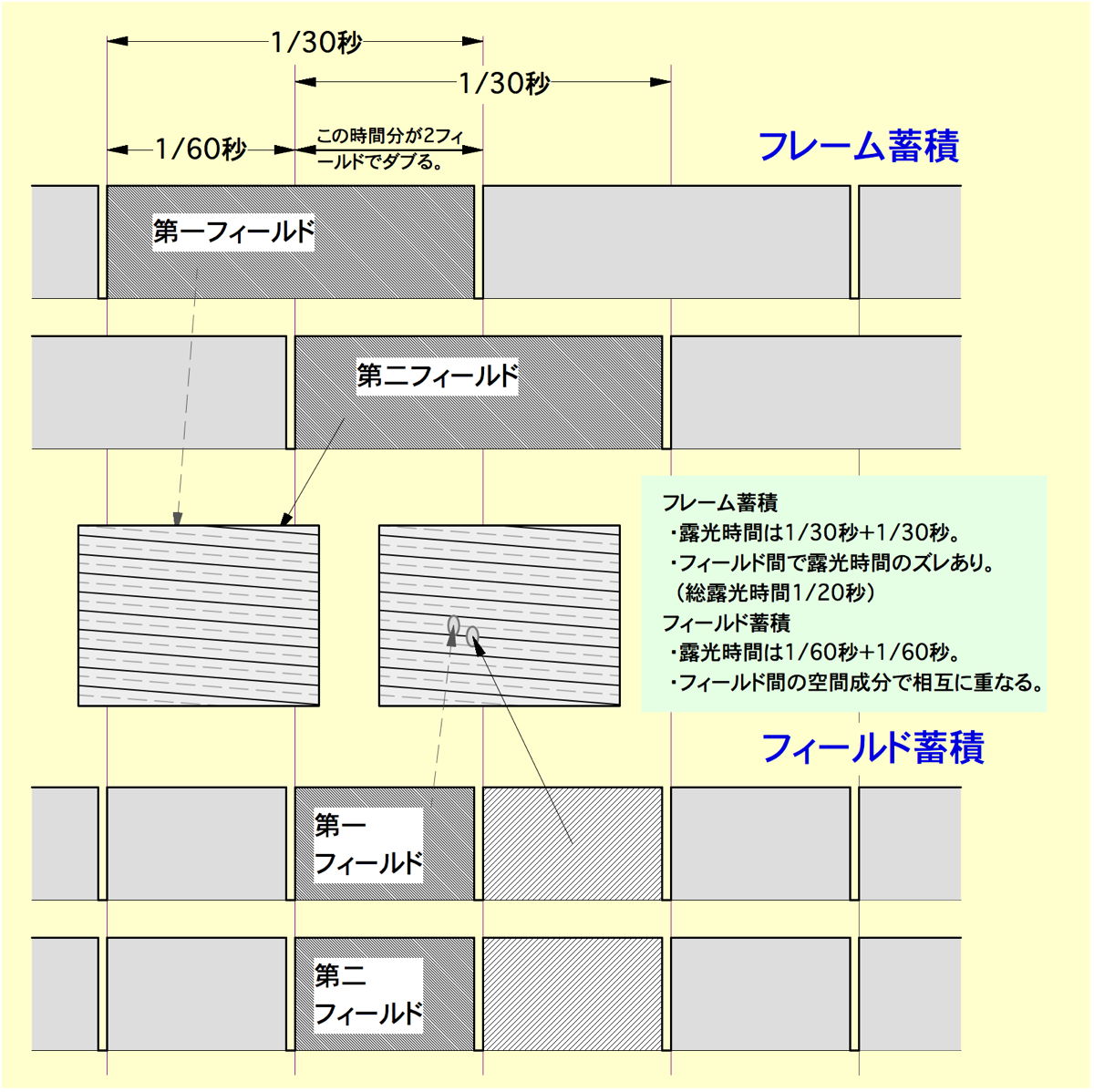 1990ǯ��ޤǤη�¬��CCD����������ȡ�CCD����ǽ����˥ե졼�����Ѥȥե���������ѤȤ�����ǽ����Ƥ��ޤ���
1990ǯ��ޤǤη�¬��CCD����������ȡ�CCD����ǽ����˥ե졼�����Ѥȥե���������ѤȤ�����ǽ����Ƥ��ޤ���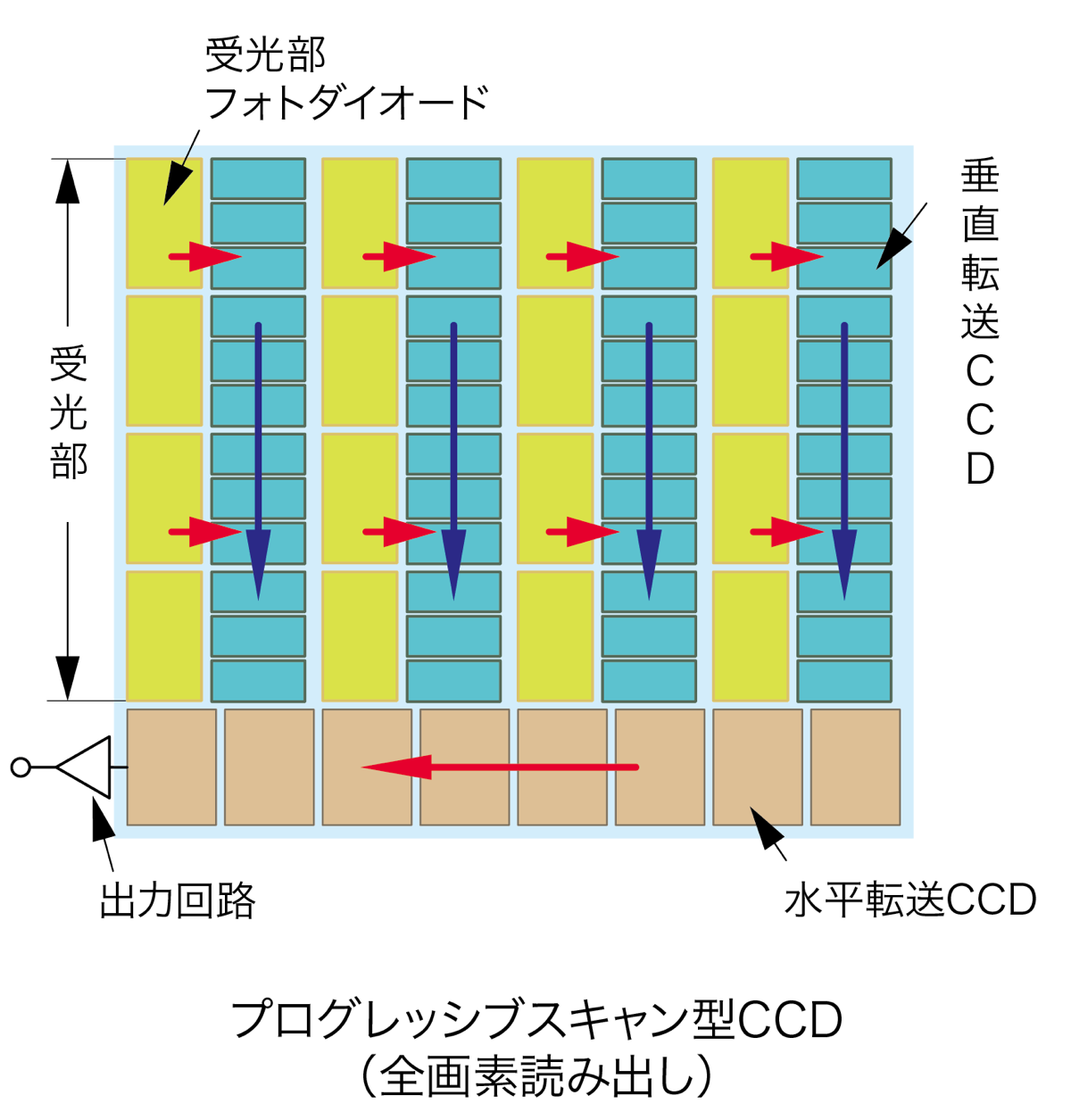
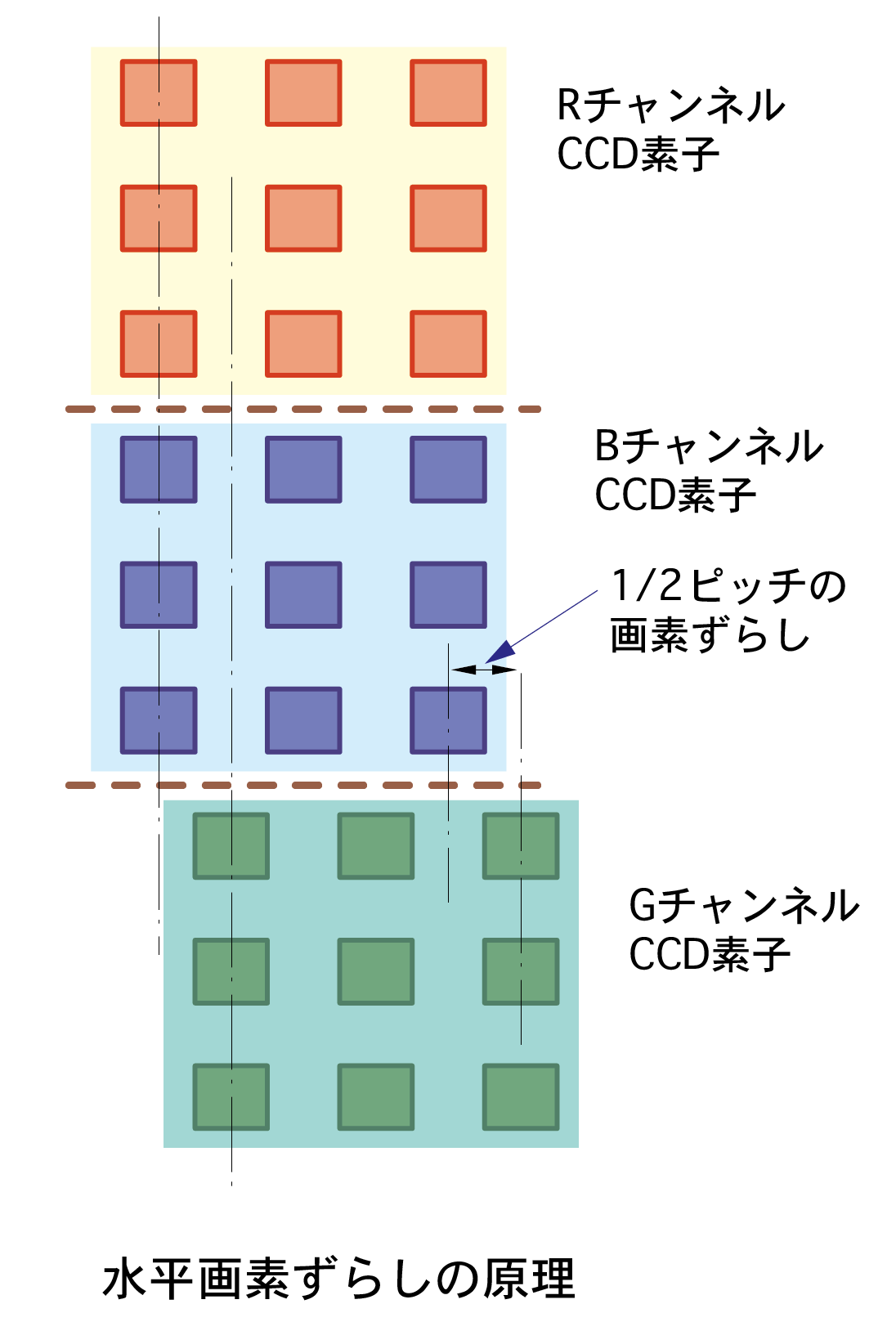 ���顼���������Τ褦��2��ʾ�λ����ǻҤ���Ѥ��Ƥ����硢�����ǻҤ��ʿ������1/2����ʬ���餹�ȶ��־�����֤Ǥ��ƿ�ʿ�����٤�夲�뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
���顼���������Τ褦��2��ʾ�λ����ǻҤ���Ѥ��Ƥ����硢�����ǻҤ��ʿ������1/2����ʬ���餹�ȶ��־�����֤Ǥ��ƿ�ʿ�����٤�夲�뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���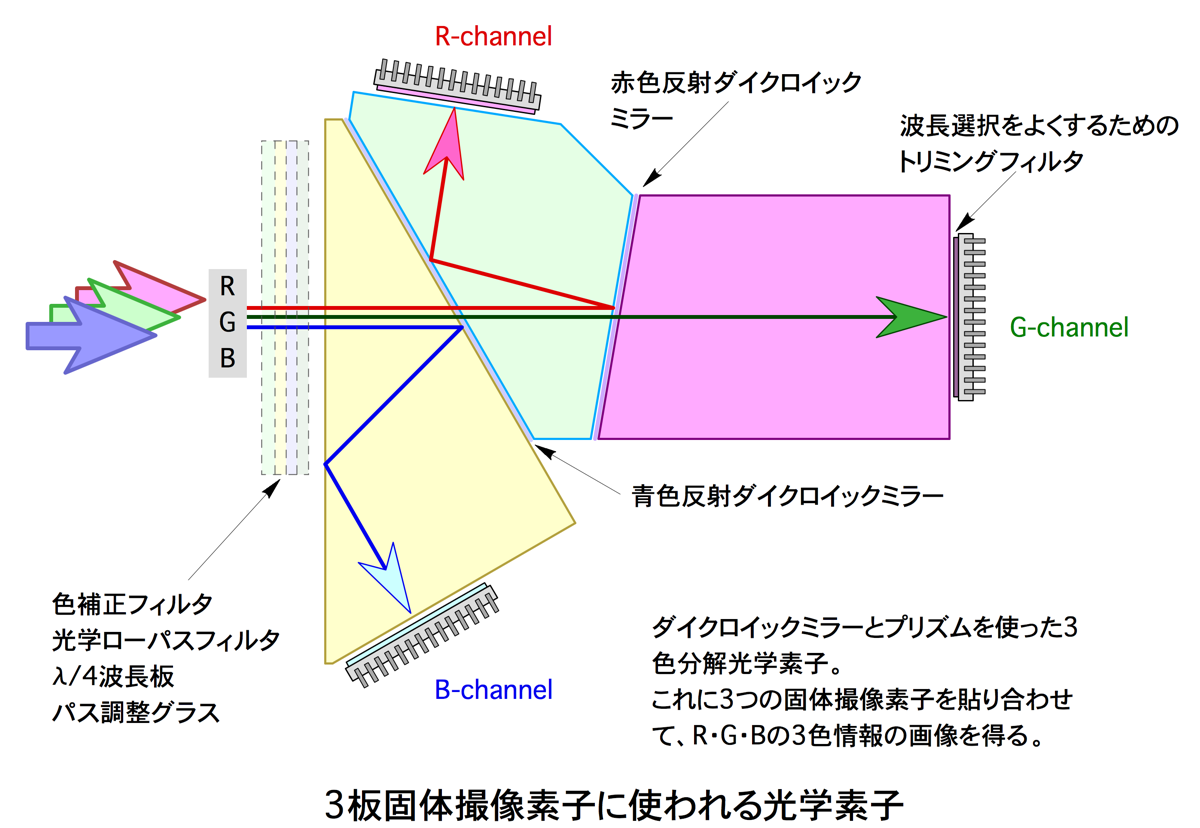 ���Υ쥤�����ȤǤϡ�3�Ĥ�CCD�ǻҤ�Ȥäƥ��顼�����R.G.B.�ˤ����Ƥ��ޤ���
���Υ쥤�����ȤǤϡ�3�Ĥ�CCD�ǻҤ�Ȥäƥ��顼�����R.G.B.�ˤ����Ƥ��ޤ���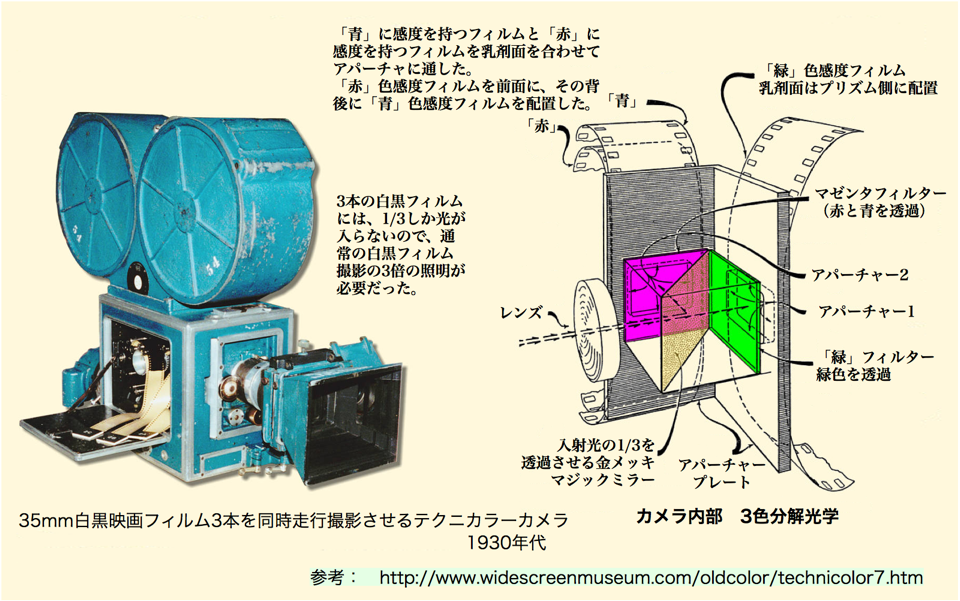
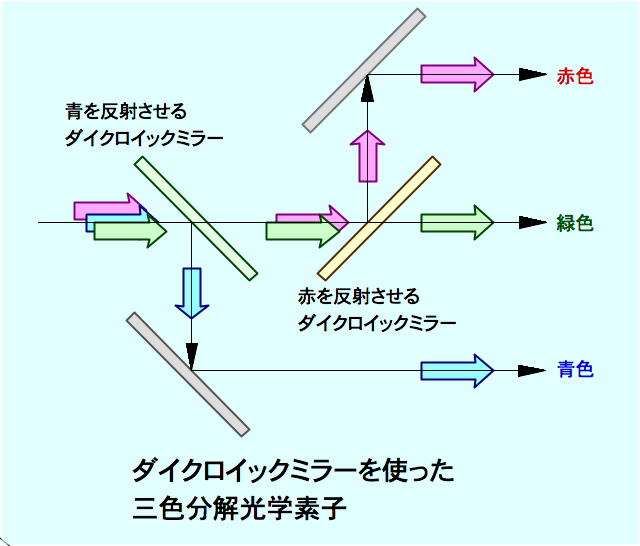
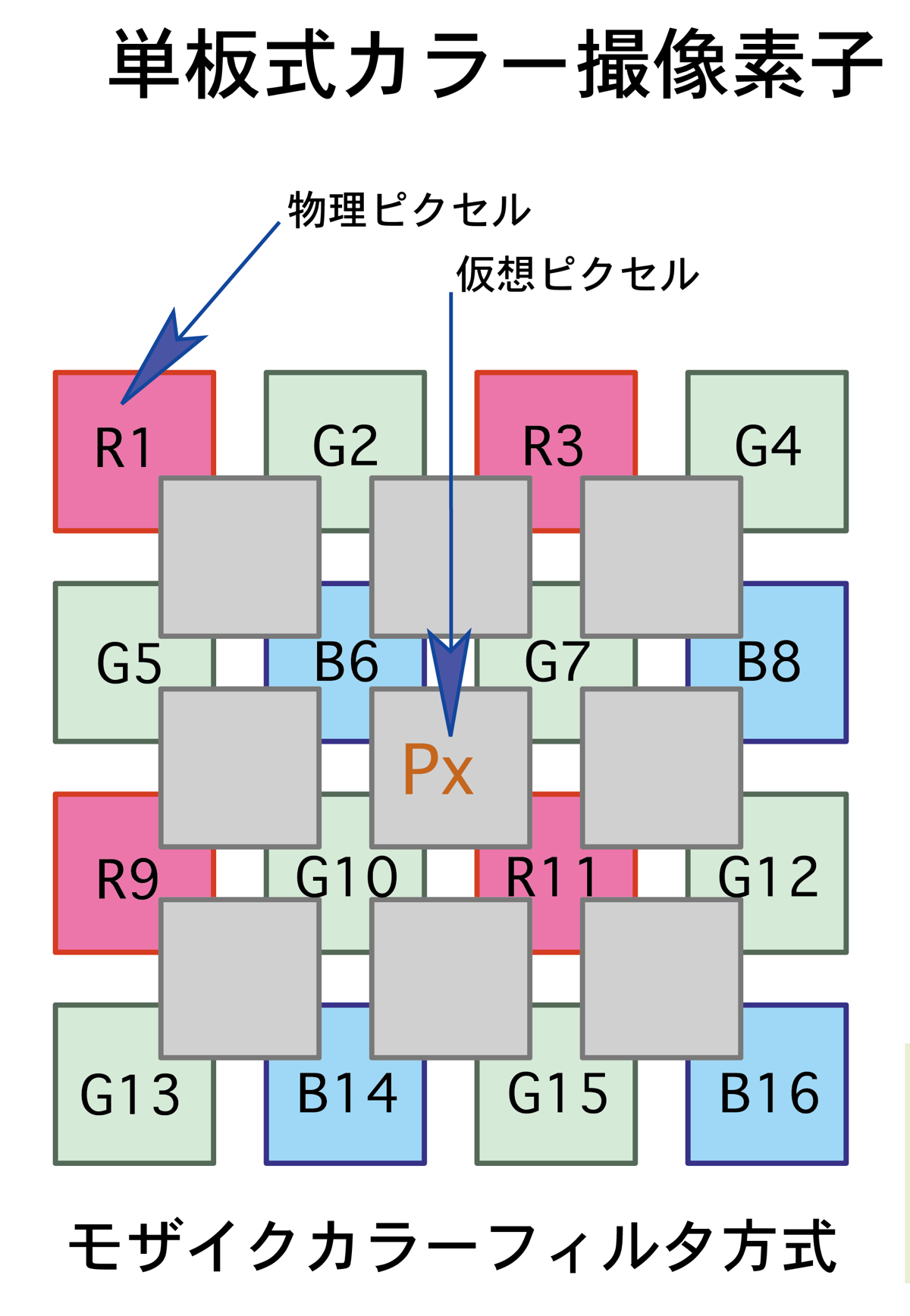 ���顼�����Υ������ɥå����ʤ�Τϡ���˽Ҥ٤�3��CCD�����Ǥ���
���顼�����Υ������ɥå����ʤ�Τϡ���˽Ҥ٤�3��CCD�����Ǥ���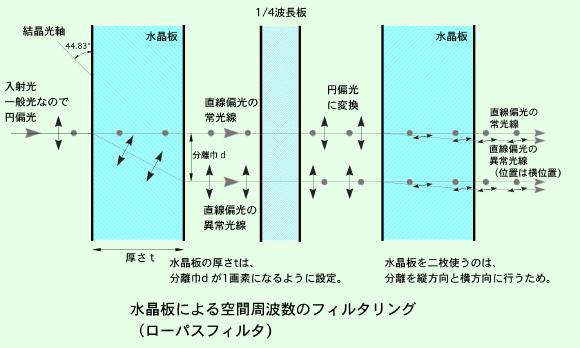 CCD�ʤɤθ��λ����ǻҤ��Ѥ�����⥢������к��Ǥϡ��徽�ˤ��뾽�ĤǺ��줿�����ѥ��ե��륿��Low Pass Filter�ˤ����ǻ��̤����˼���դ�����ˡ���Ǥ����Ū�Ǥ���
CCD�ʤɤθ��λ����ǻҤ��Ѥ�����⥢������к��Ǥϡ��徽�ˤ��뾽�ĤǺ��줿�����ѥ��ե��륿��Low Pass Filter�ˤ����ǻ��̤����˼���դ�����ˡ���Ǥ����Ū�Ǥ���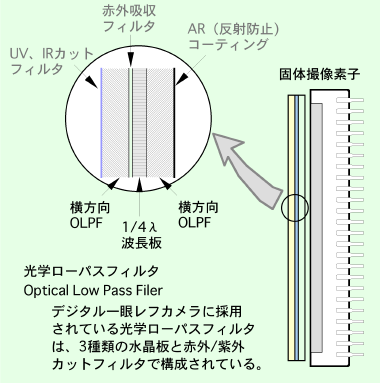
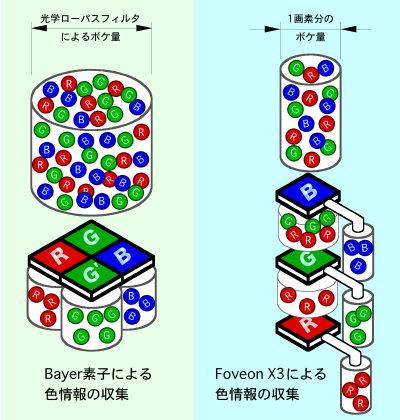 |
||||||
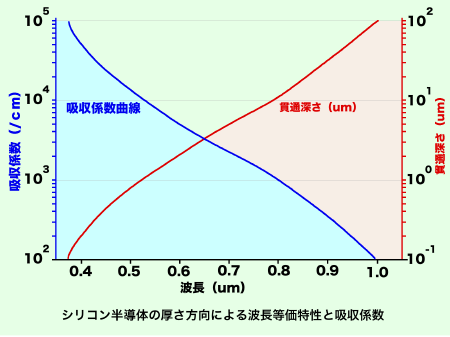 |
||||||
|
||||||
| ���͡�Richard F. Lyon, Paul M. Hubel, Foveon, Inc. ,"Eyeing the Camera: into the Next Century", 2003 | Bayer�ǻҤ�ʿ��Ū�˿�������������Τ��Ф���Foveon�Ͽ�ľ�˿������������롣���äơ�Foveon�Ͽ��Τˤ��ߤ��ʤ��� | |||||
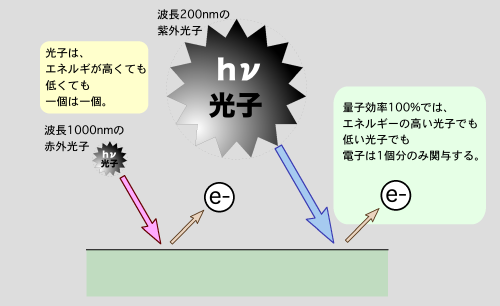 ����ϥܡ�����Niels Henrik David Bohr��1885.10��1962.11���ǥ�ޡ�����ʪ���ؼԡ�1922ǯ�Ρ��٥�ʪ���ؾ���) ���ͤ��������ǡ��ŻҤϸ��ҳˤβ������ε�ƻ�Dz�ꡢ�������饨�ͥ륮�������Ȱ�ij��ε�ƻ�˰ܤꡢ�ޤ������ͥ륮�������Ф���Ȥ�����¦�ε�ƻ�˰ܤ�Ȥ�����ΤǤ���
����ϥܡ�����Niels Henrik David Bohr��1885.10��1962.11���ǥ�ޡ�����ʪ���ؼԡ�1922ǯ�Ρ��٥�ʪ���ؾ���) ���ͤ��������ǡ��ŻҤϸ��ҳˤβ������ε�ƻ�Dz�ꡢ�������饨�ͥ륮�������Ȱ�ij��ε�ƻ�˰ܤꡢ�ޤ������ͥ륮�������Ф���Ȥ�����¦�ε�ƻ�˰ܤ�Ȥ�����ΤǤ���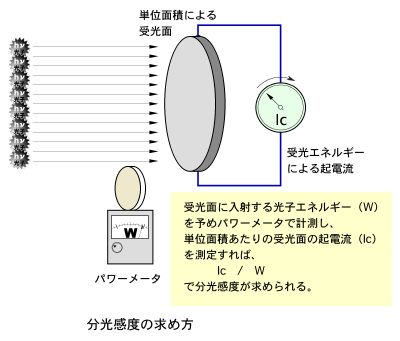
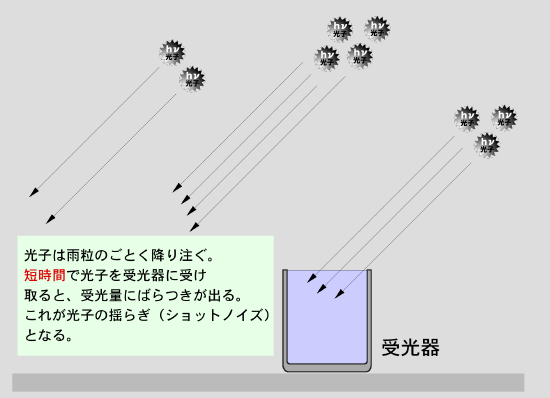 ����åȥΥ����ϡ�Ķ�ⴶ�٥�����Ȥäơ����Ūû���֤�Ϫ���Dz�����Ȥ館�������Ω���ޤ����ⴶ�٥����ϡ����Τ�����ҿ������ʤ��ΤǤ����������ݤ������˸���ޤ���
����åȥΥ����ϡ�Ķ�ⴶ�٥�����Ȥäơ����Ūû���֤�Ϫ���Dz�����Ȥ館�������Ω���ޤ����ⴶ�٥����ϡ����Τ�����ҿ������ʤ��ΤǤ����������ݤ������˸���ޤ���
N �� ���Nr2 + Nd2 + Ns2 �ˡ�����������Rec -15��
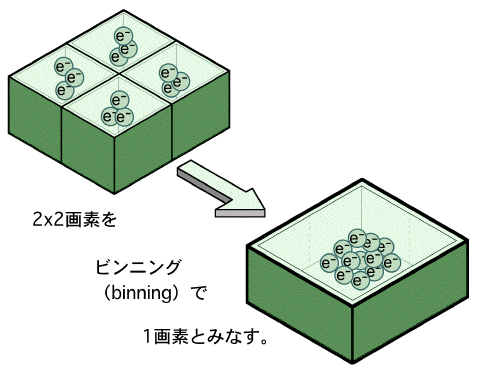 �����ӥ�˥�Binning)������2008.05.15)
�����ӥ�˥�Binning)������2008.05.15)
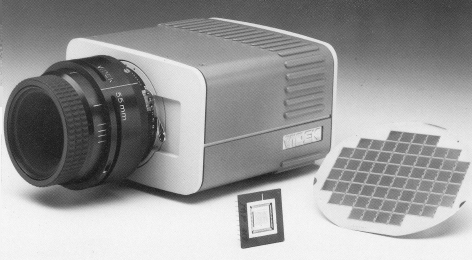 ���Υ�����̾���ϡ��ᥬ�ԥ������100�����ǡˤ�ο���������Ȥ������Ȥ���֥ᥬ�ץ饹��Megaplus�ˡפȸƤФ�ޤ�����
���Υ�����̾���ϡ��ᥬ�ԥ������100�����ǡˤ�ο���������Ȥ������Ȥ���֥ᥬ�ץ饹��Megaplus�ˡפȸƤФ�ޤ�����
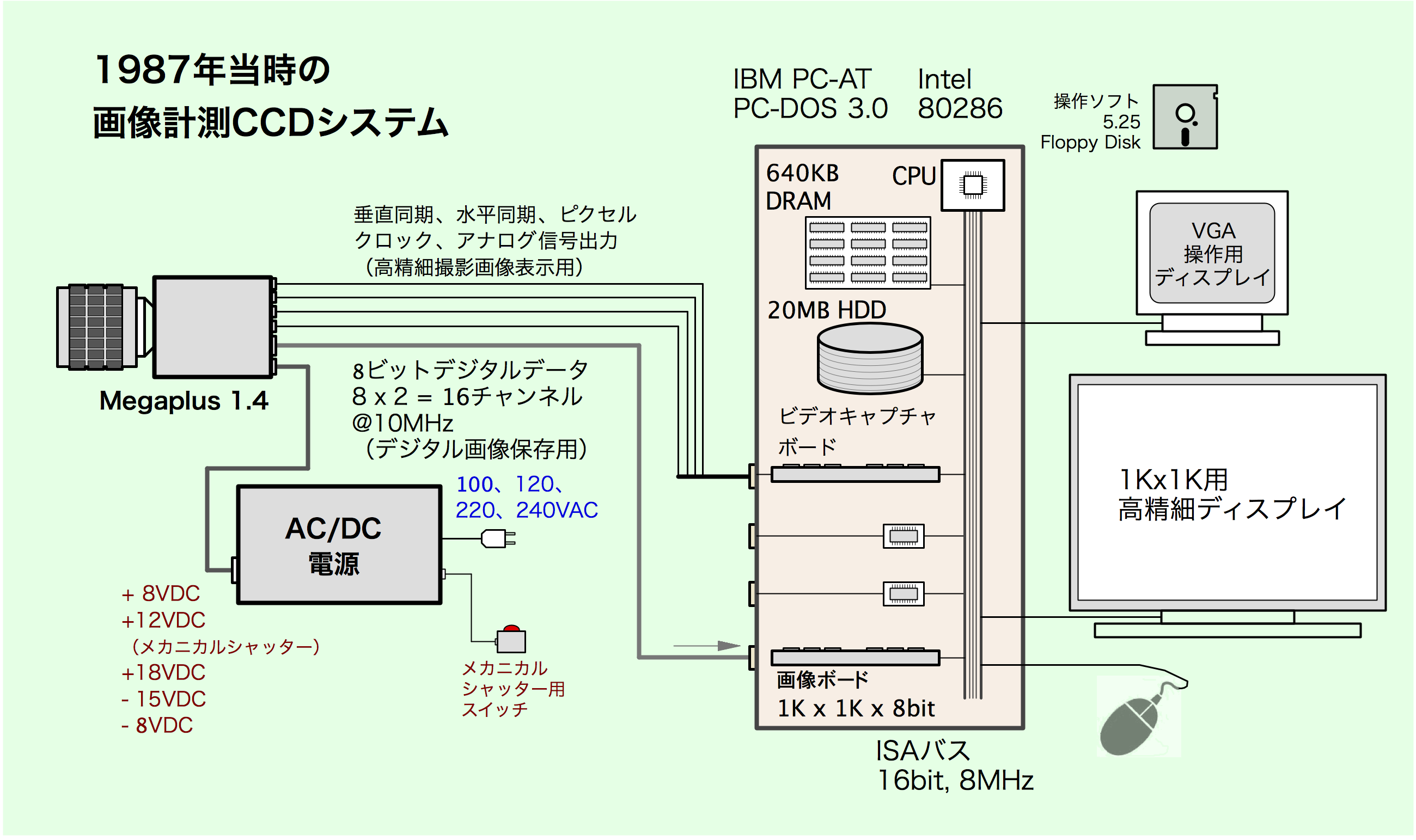
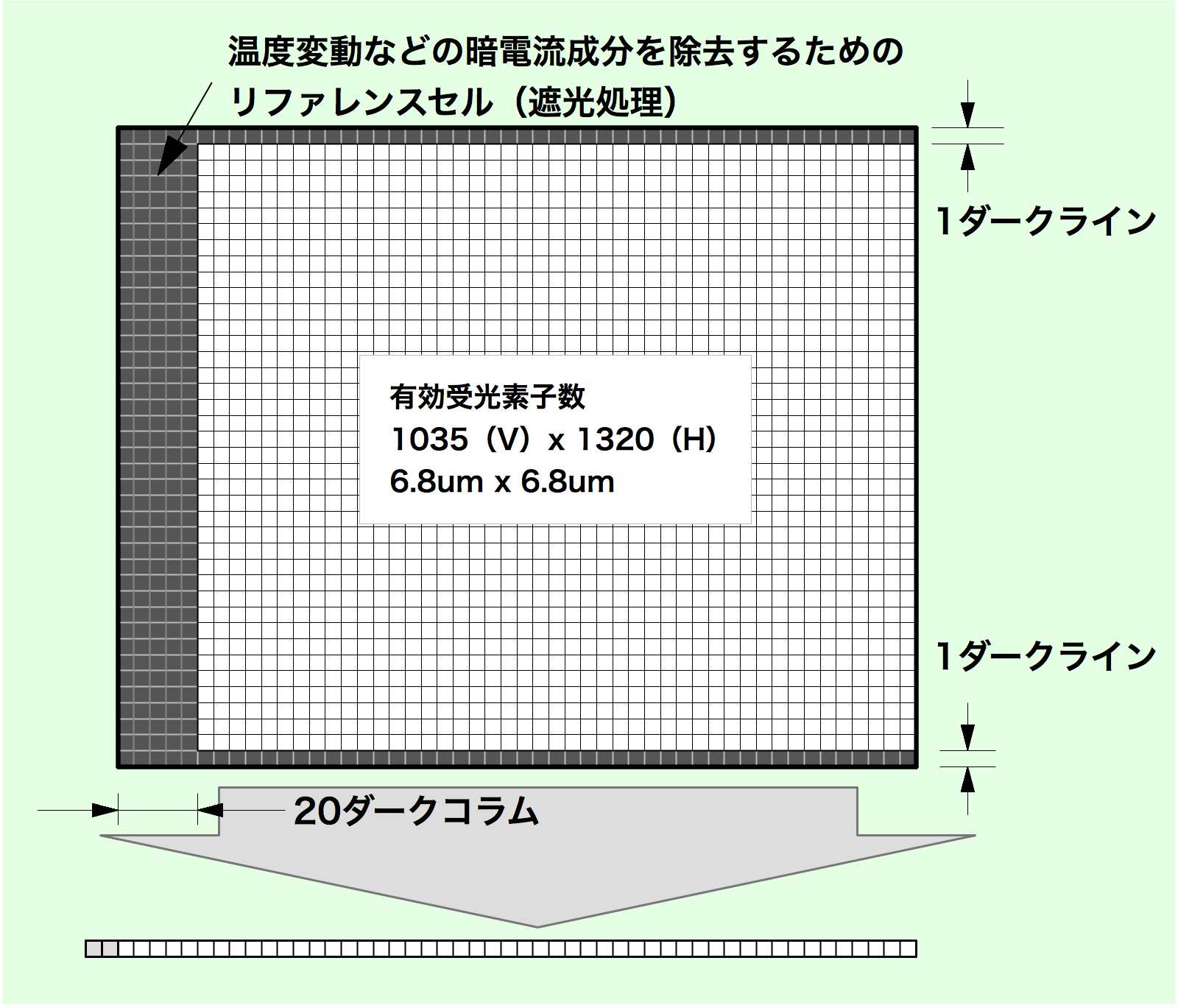 �Х��ǥå��˻Ȥ�줿CCD���ե�ե졼��ȥ�ե���CCD���λ����ǻҤǤ���
�Х��ǥå��˻Ȥ�줿CCD���ե�ե졼��ȥ�ե���CCD���λ����ǻҤǤ���
 ��¬��CCD�����Ͽʲ���뤲��1990ǯ���Ⱦ�ˤ�4,000x4,000���ǤΥ���餬�о줷�ޤ�����
��¬��CCD�����Ͽʲ���뤲��1990ǯ���Ⱦ�ˤ�4,000x4,000���ǤΥ���餬�о줷�ޤ����� 2005ǯ�ˡ��������CCD�����Ȥ��ơ����˼����褦���Ż���ѷ�����餬���ʲ�����ޤ�����
2005ǯ�ˡ��������CCD�����Ȥ��ơ����˼����褦���Ż���ѷ�����餬���ʲ�����ޤ�����
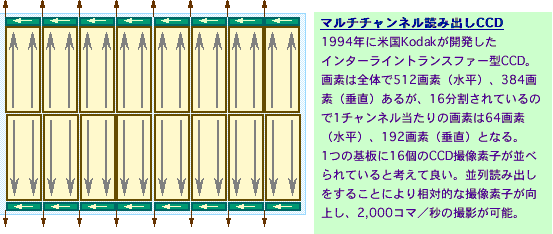 CCD��ž����100ns��1000��ʬ��1�áˤ��³��ȸ����Ƥ��ޤ����顢�������40�ܤ�®������ʤ��ƤϤʤ�ޤ���
CCD��ž����100ns��1000��ʬ��1�áˤ��³��ȸ����Ƥ��ޤ����顢�������40�ܤ�®������ʤ��ƤϤʤ�ޤ��� �Ȥ�����ħ����äƤ��ޤ�����
�Ȥ�����ħ����äƤ��ޤ�����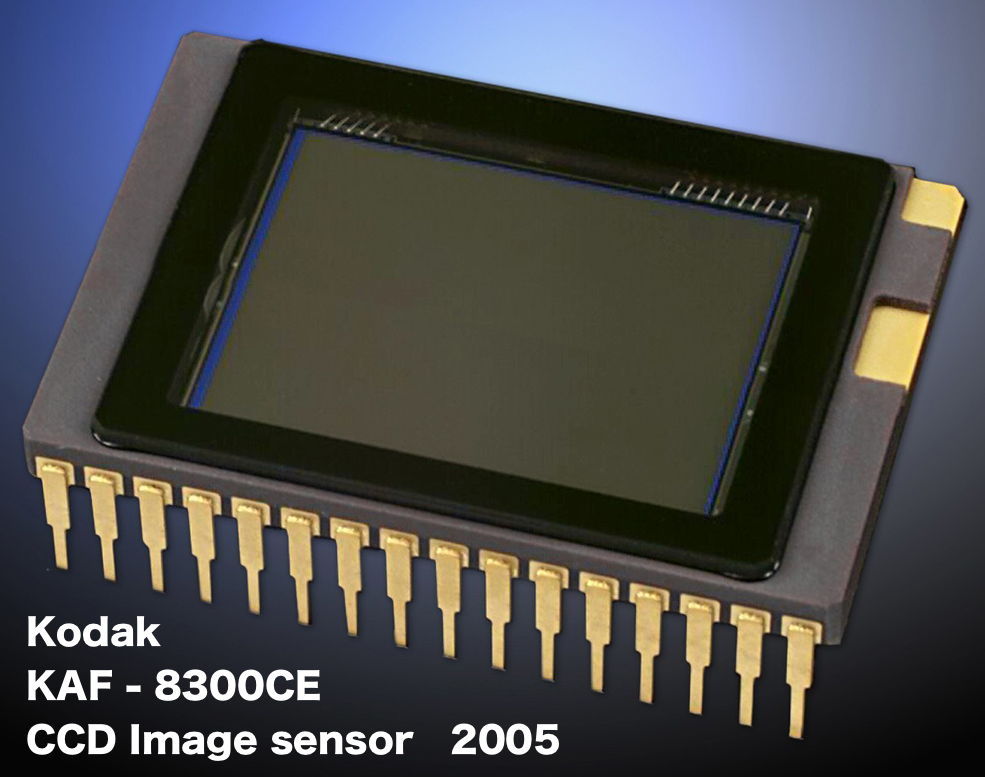 �̾��CCD���λ����ǻҤȤϼ��ۤˤ������ʳ��Ѥη�¬CCD�ǻҤ����Ƥ��ޤ���
�̾��CCD���λ����ǻҤȤϼ��ۤˤ������ʳ��Ѥη�¬CCD�ǻҤ����Ƥ��ޤ���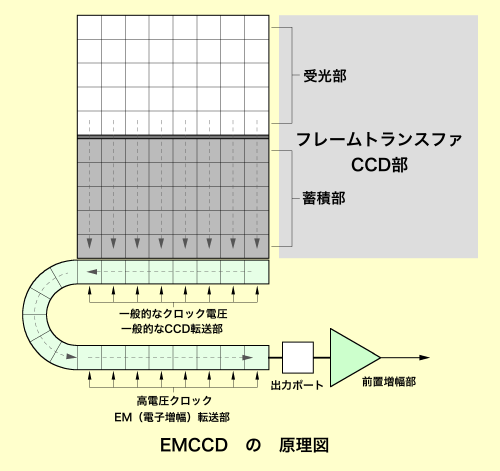 EMCCD��Electron Multiplying CCD�ˤȸƤФ����λ����ǻҤϡ�CCD����֤����ꡢ���˴��٤ι⤤�����ǻҤǤ���
EMCCD��Electron Multiplying CCD�ˤȸƤФ����λ����ǻҤϡ�CCD����֤����ꡢ���˴��٤ι⤤�����ǻҤǤ��� |
|||||
|
|
||||
|
|||||
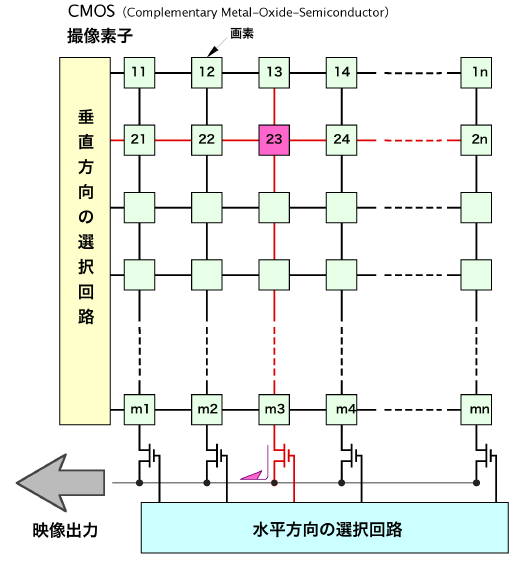 ��
��
 ��ϡ�CMOS�ǻҤ����������¢������CMOS APS��CMOS Active Pixel Sensor�˻����ǻҤ�ȯ���ޤ�����
��ϡ�CMOS�ǻҤ����������¢������CMOS APS��CMOS Active Pixel Sensor�˻����ǻҤ�ȯ���ޤ�����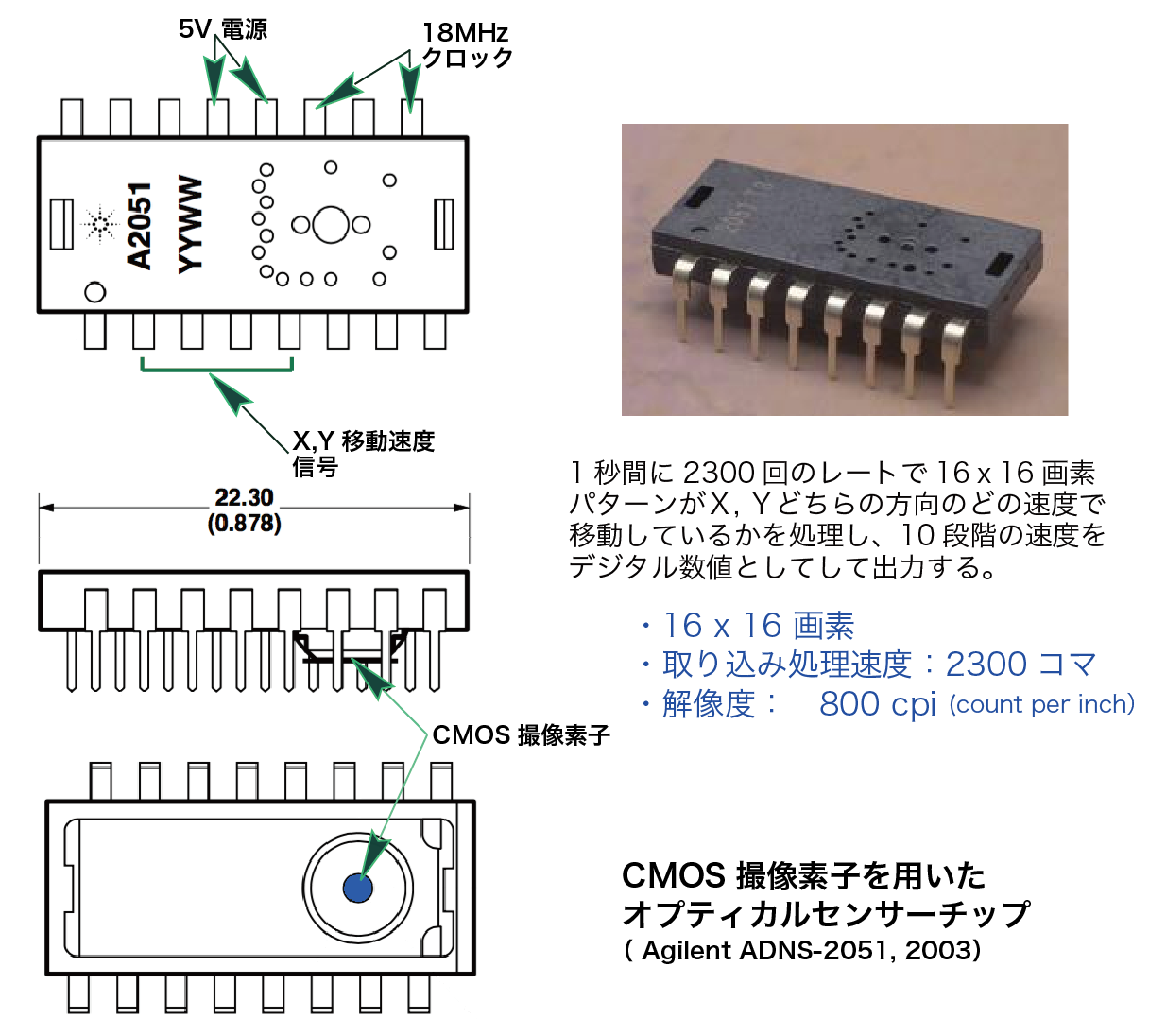 �ޤ���CMOS�����ϥ����δ�Ȥ��ƤǤϤʤ�����ԥ塼���˻Ȥ�����إޥ����Υ����Ȥ������Ѥ���Ƥ��ޤ���
�ޤ���CMOS�����ϥ����δ�Ȥ��ƤǤϤʤ�����ԥ塼���˻Ȥ�����إޥ����Υ����Ȥ������Ѥ���Ƥ��ޤ���
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||

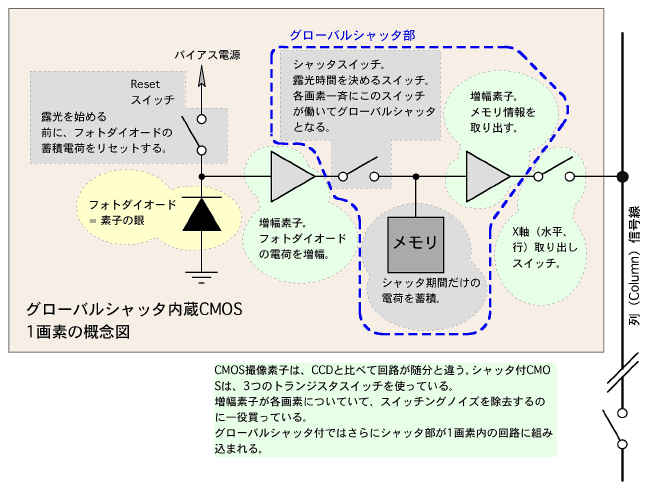 ��¬��CMOS�����ǻҤǤϡ��Żҥ���å���¢�Τ�Τ�����Ū�ˤʤäƤ��ޤ���
��¬��CMOS�����ǻҤǤϡ��Żҥ���å���¢�Τ�Τ�����Ū�ˤʤäƤ��ޤ���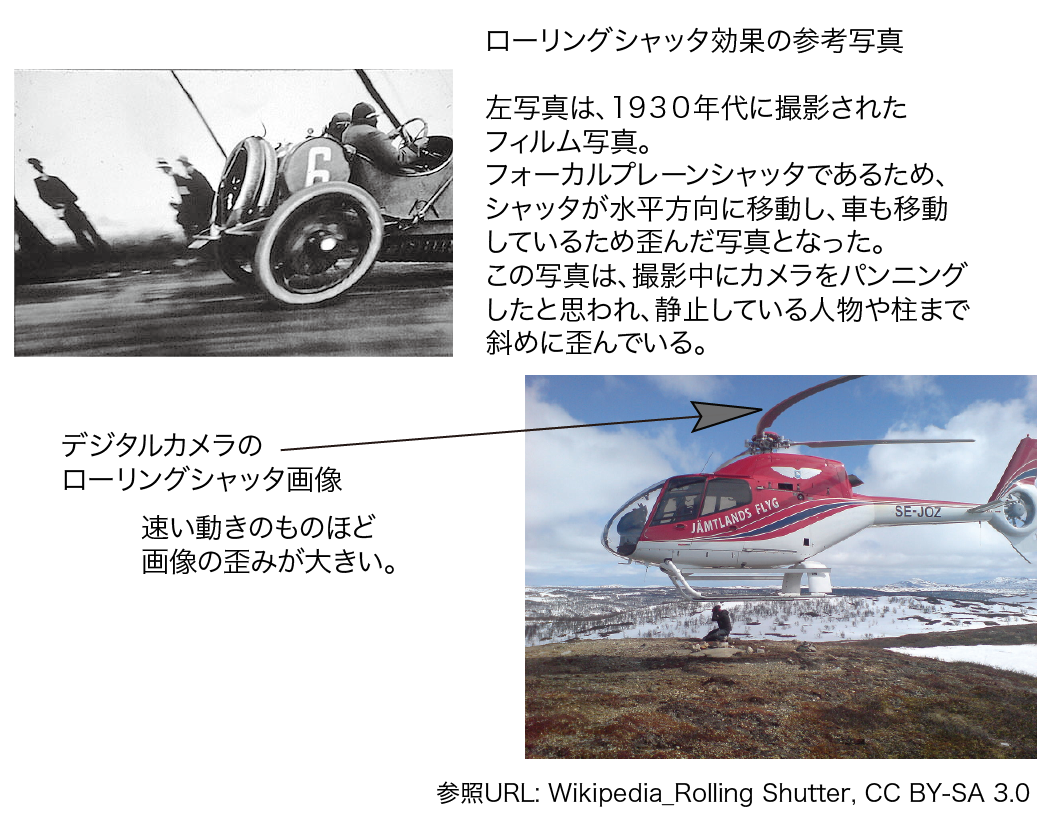
��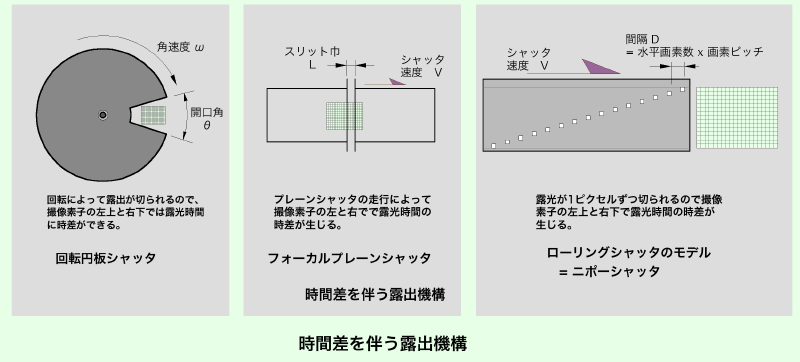
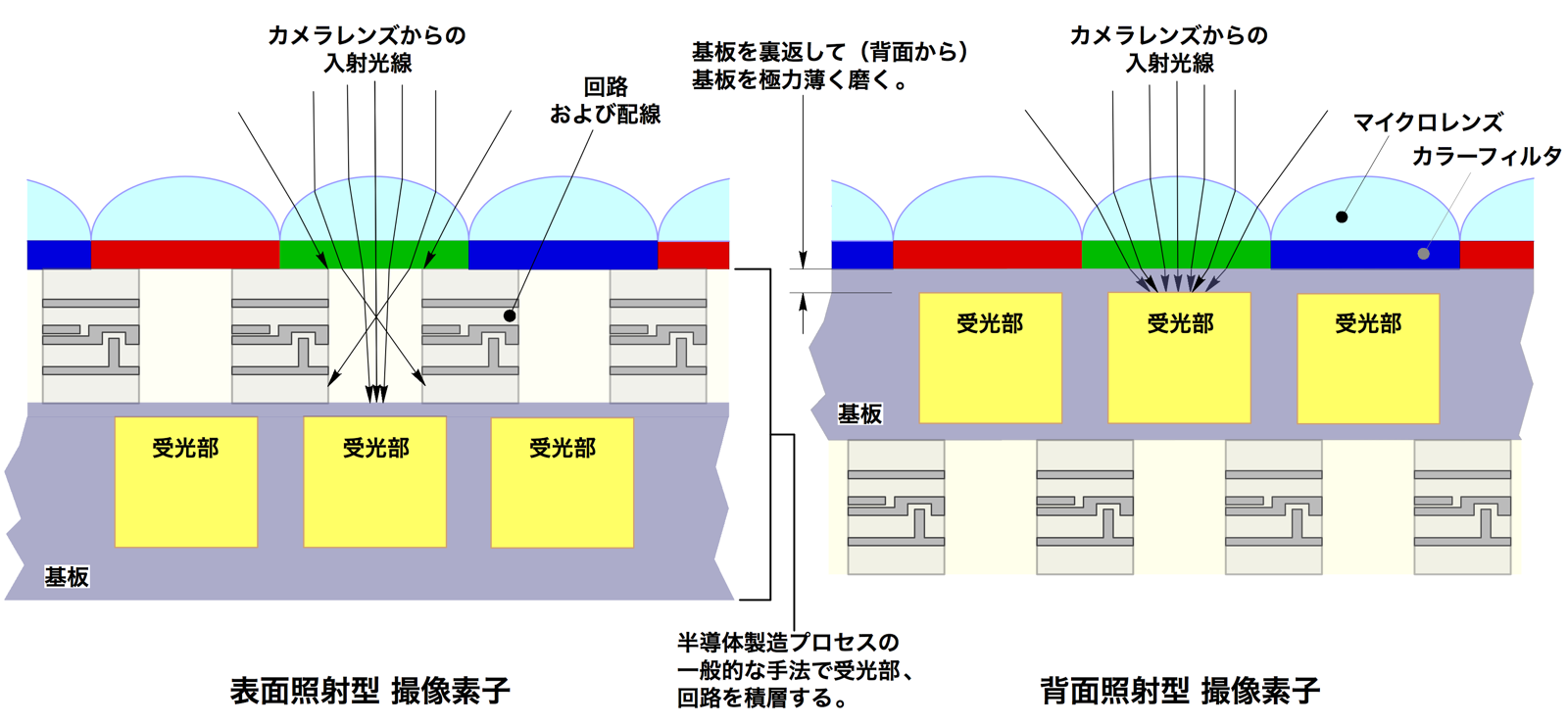 ���̾ȼͷ������ǻҤϡ����ޤ˼����褦�˼������������������֤����������Ȳ�ϩ�ǻҤ��������֤��������ǻҤǤ���
���̾ȼͷ������ǻҤϡ����ޤ˼����褦�˼������������������֤����������Ȳ�ϩ�ǻҤ��������֤��������ǻҤǤ���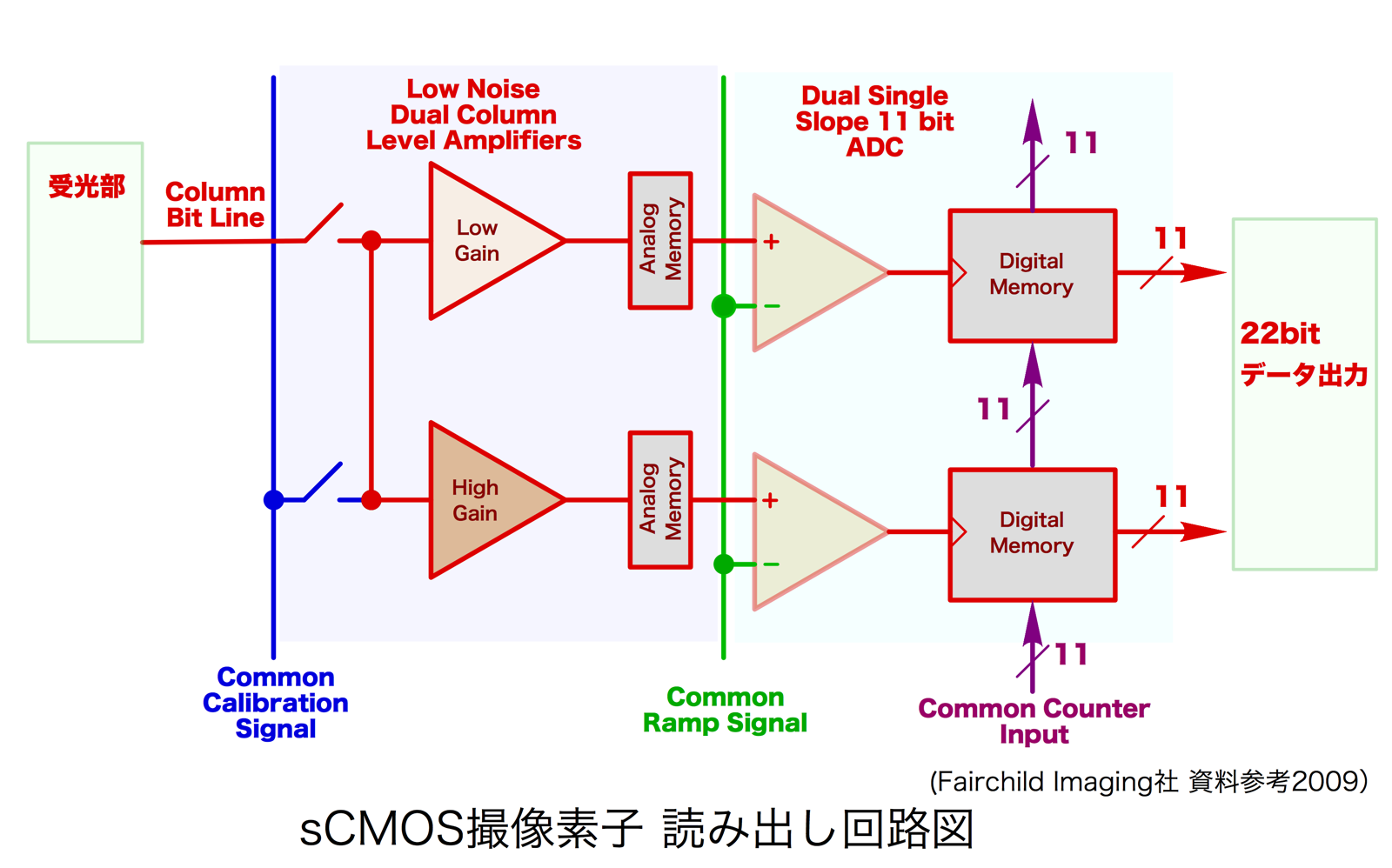
|
|||||
 |
|||
�� ![]()
|
|
||||||
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
��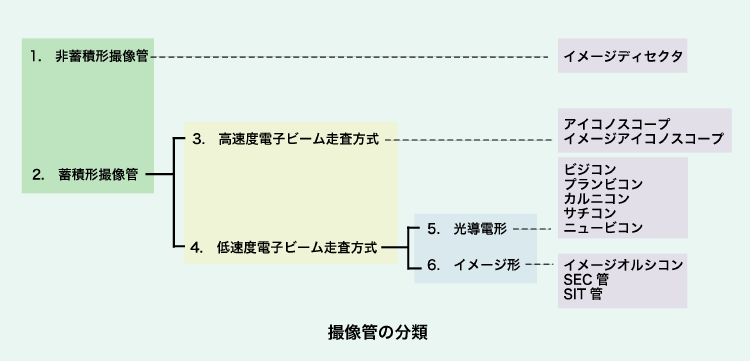
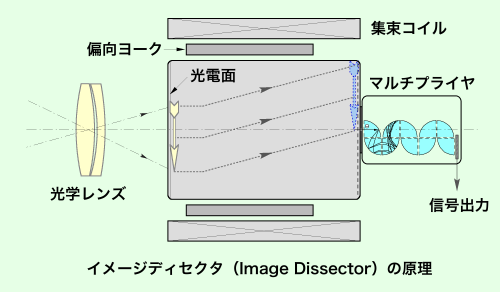 �����ѻ����ɤϡ��ƥ�ӥ����θ���Ū¸�ߤΤ�Τǡ�1931ǯ���ƹ��Farnsworth��1906 - 1971�ˤˤ�äƥ�����ǥ���������Image Dissector�ˤȸƤФ�뻣���ɤ���ȯ����ޤ�����
�����ѻ����ɤϡ��ƥ�ӥ����θ���Ū¸�ߤΤ�Τǡ�1931ǯ���ƹ��Farnsworth��1906 - 1971�ˤˤ�äƥ�����ǥ���������Image Dissector�ˤȸƤФ�뻣���ɤ���ȯ����ޤ����� |
|||
|
|||
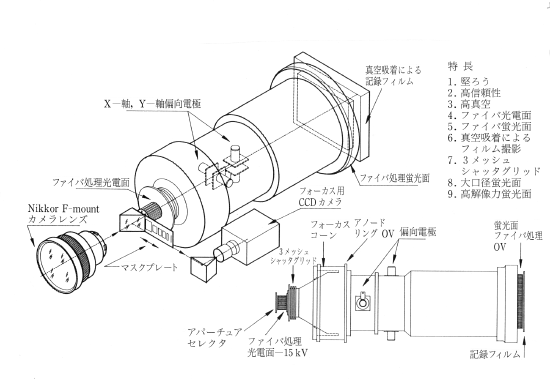 |
||||||
|
||||||
|
||||||
X���������ϡ��ʲ���3�Ĥ����̤�������Ω�äƤ��ޤ������ʤ����
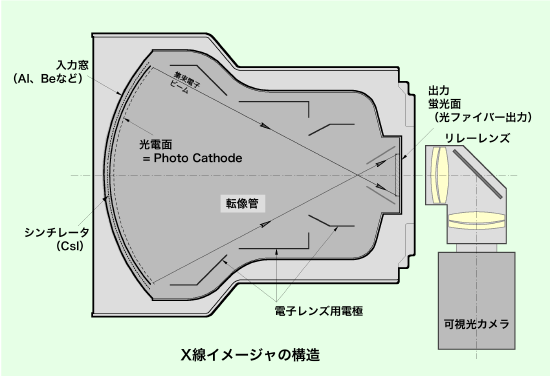 |
||||
 |
||||
|
||||
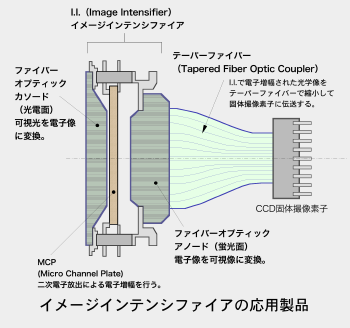 ���˼������ޤϡ���3����ζ��ܷ����������ƥե���������ե����С���CCD�ǻҤȥ��ץ�����ⴶ�٥����ι�¤�ޤǤ���
���˼������ޤϡ���3����ζ��ܷ����������ƥե���������ե����С���CCD�ǻҤȥ��ץ�����ⴶ�٥����ι�¤�ޤǤ���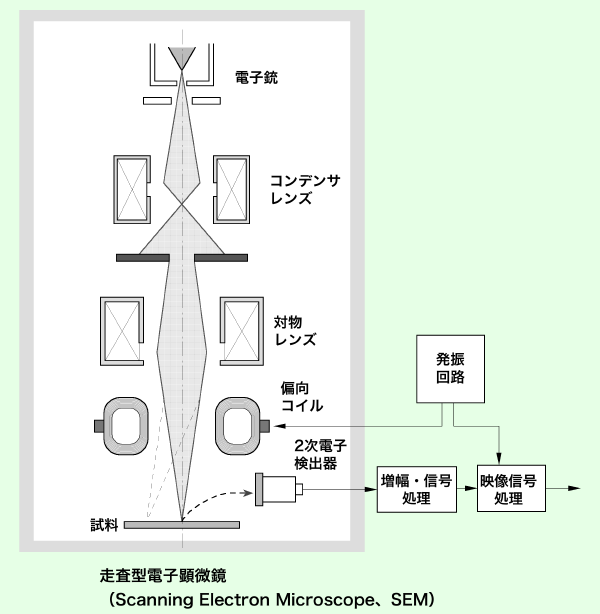 ������ˤ��Ƥ⡢��������Τ������ʬ��ȼ�������ϰ������Ȥ��Ǥ��ޤ���
������ˤ��Ƥ⡢��������Τ������ʬ��ȼ�������ϰ������Ȥ��Ǥ��ޤ���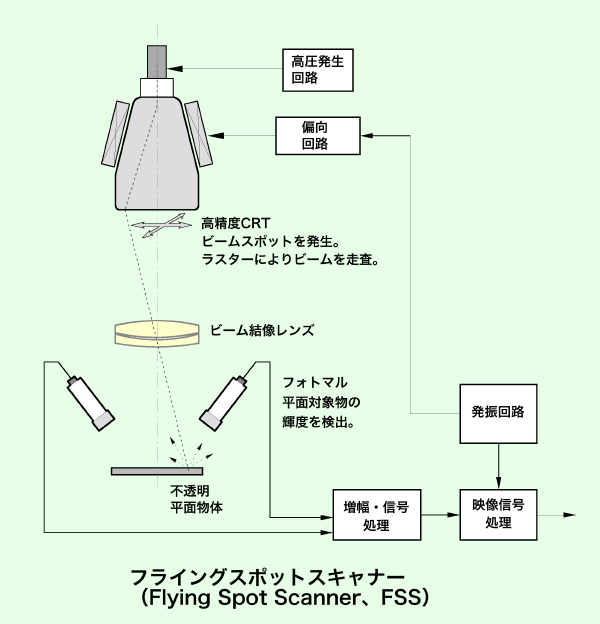 �������ŻҸ������θ����ե饤�����ݥåȡ�������ʡ���FSS�ˤ˸��뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
�������ŻҸ������θ����ե饤�����ݥåȡ�������ʡ���FSS�ˤ˸��뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ�����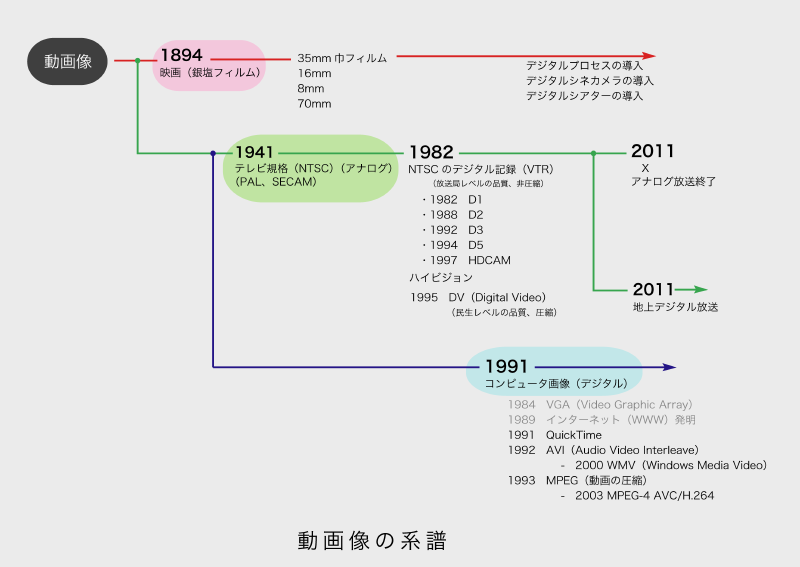
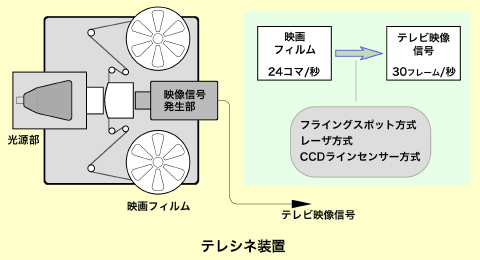 �ƥ쥷�����֤Ȥϡ��Dz�ե�����ƥ�ӿ�����Ѵ��������֤Ǥ���
�ƥ쥷�����֤Ȥϡ��Dz�ե�����ƥ�ӿ�����Ѵ��������֤Ǥ���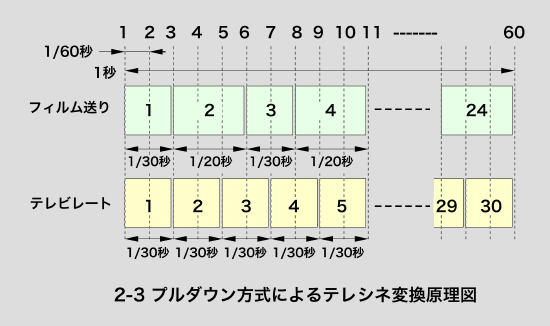 �ƥ쥷�ͤαǼ̵��Ǥϡ�1�����ܤ�2�����ܤ��ϡ�
�ƥ쥷�ͤαǼ̵��Ǥϡ�1�����ܤ�2�����ܤ��ϡ�
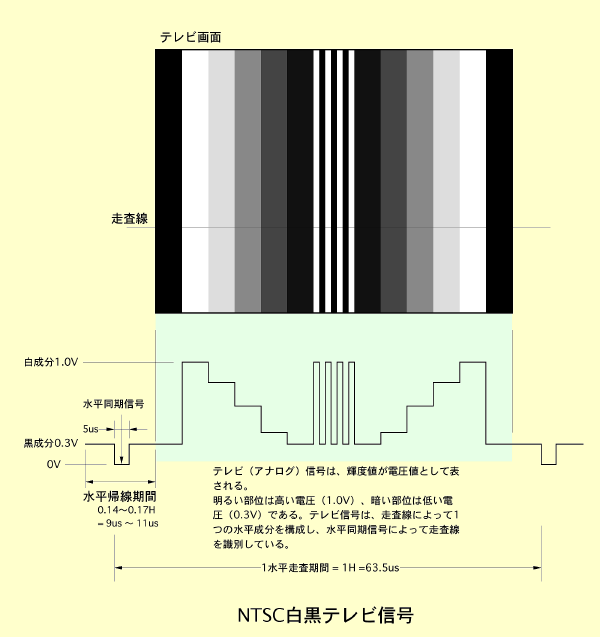 NTSC�ϡ�1941ǯ������Υƥ�ӥ�����������ʤ��Ǥ��Ф��ޤ���
NTSC�ϡ�1941ǯ������Υƥ�ӥ�����������ʤ��Ǥ��Ф��ޤ���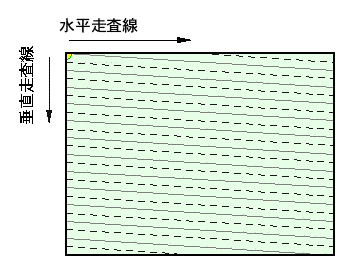 |
|||
 |
|||
��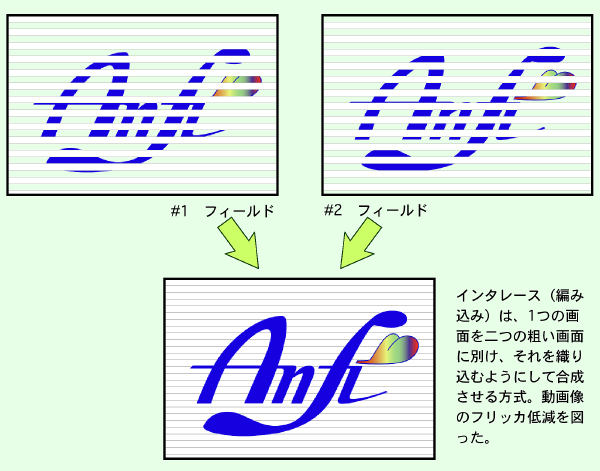
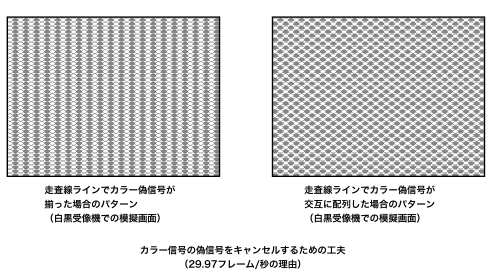
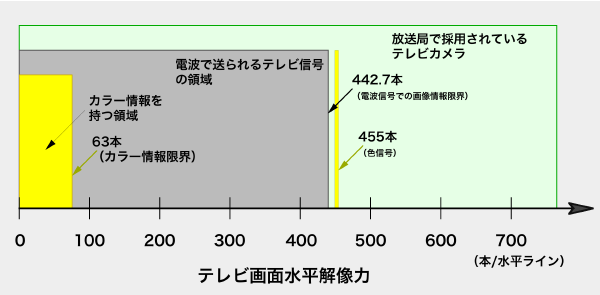
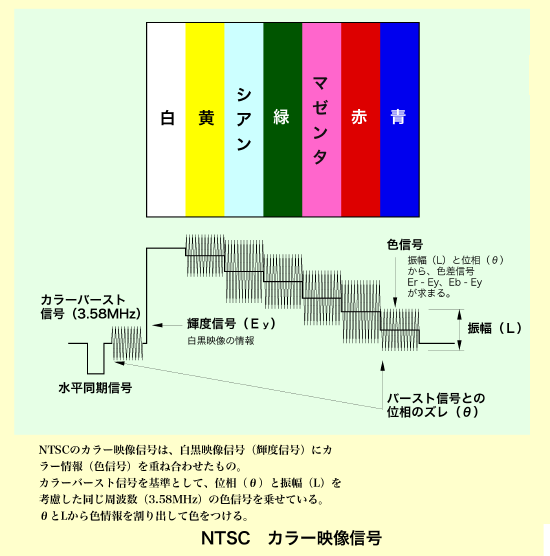
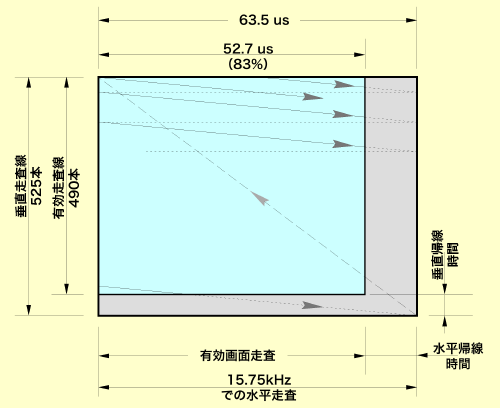 ������졢�����͡�3.58 MHz�ˤ����С����ȿ�����ȿ���fs�ˤκ���Ȥʤ�ޤ�����
������졢�����͡�3.58 MHz�ˤ����С����ȿ�����ȿ���fs�ˤκ���Ȥʤ�ޤ����� |
||||
|
||||
 ��
��
 |
||||
|
||||
|
|||||
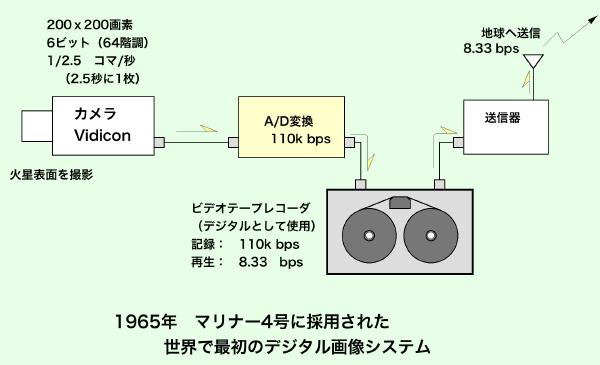 ����õ�������ޥ�ʡ�4���Mariner 4�ˤ���ܤ��줿�����ϡ��ե���५���ǤϤʤ������������Τ���ʤ��ƥ�ӥ����Ǥ�����
����õ�������ޥ�ʡ�4���Mariner 4�ˤ���ܤ��줿�����ϡ��ե���५���ǤϤʤ������������Τ���ʤ��ƥ�ӥ����Ǥ�����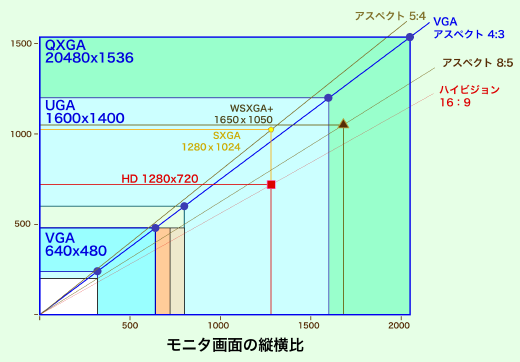
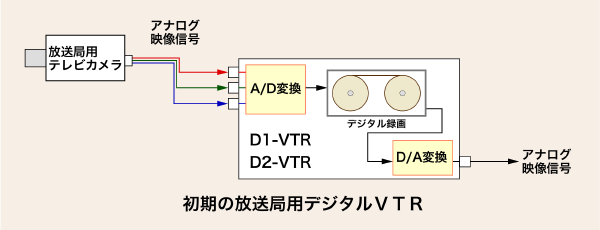 �����ǥ�����VTR��Digital Video Tape Recorder��
�����ǥ�����VTR��Digital Video Tape Recorder��
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
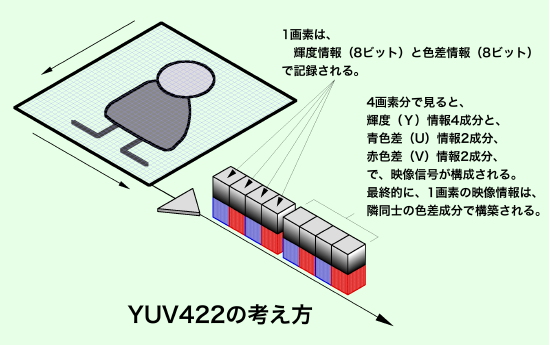 �ǥ����뿮��Ǥ���4:2:2����ݡ��ͥ�ȥǥ����뿮��ˤ����Ƥ⡢�����դ�����ˡ�ϥ��ʥ��������Ʊ���褦����������Ѥ������ٿ���ȿ������椫�鹽����������������ꡢ�٤������̤��Ф��ƤϿ����դ��ʤ���ˡ����Ѥ��ޤ�����
�ǥ����뿮��Ǥ���4:2:2����ݡ��ͥ�ȥǥ����뿮��ˤ����Ƥ⡢�����դ�����ˡ�ϥ��ʥ��������Ʊ���褦����������Ѥ������ٿ���ȿ������椫�鹽����������������ꡢ�٤������̤��Ф��ƤϿ����դ��ʤ���ˡ����Ѥ��ޤ�����
��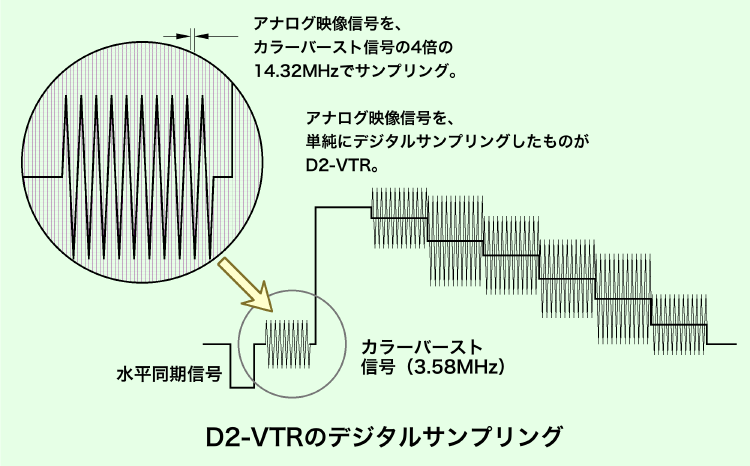
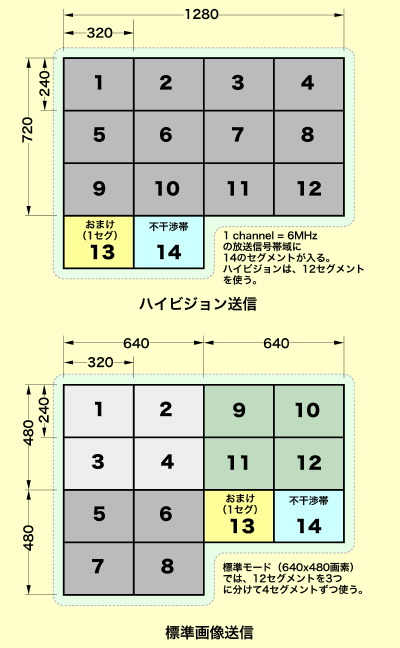 ������������������Segment Broadcasting������2009.02.03�ɵ���
������������������Segment Broadcasting������2009.02.03�ɵ���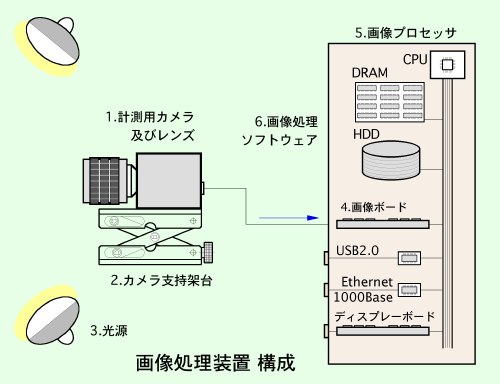 �����ܡ��ɤǥǥ�����������Ѵ����줿�ǡ����ϡ�����ԥ塼���Υǡ����Х��ˤ�äơ��������֡ʥץ����å��ˤ�DRAM�������ޤ���
�����ܡ��ɤǥǥ�����������Ѵ����줿�ǡ����ϡ�����ԥ塼���Υǡ����Х��ˤ�äơ��������֡ʥץ����å��ˤ�DRAM�������ޤ���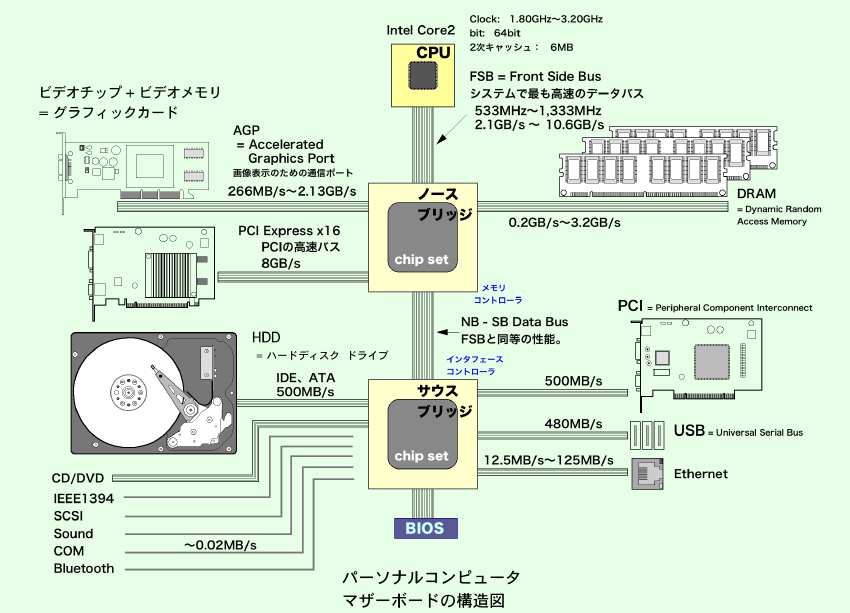
 |
|||
|
|||
 �ƹ�β��������������RCA��Radio Corporation of America�˼Ҥ���1940ǯ��˳�ȯ���������������³ü�����ͥ�����RCA���ͥ����ʱ��̿������Ѽ��ȿ��� 10M Hz�ˤȸƤ�Ǥ��ޤ���
�ƹ�β��������������RCA��Radio Corporation of America�˼Ҥ���1940ǯ��˳�ȯ���������������³ü�����ͥ�����RCA���ͥ����ʱ��̿������Ѽ��ȿ��� 10M Hz�ˤȸƤ�Ǥ��ޤ���
 |
 |
 |
||||||||
|
||||||||||
|
|
|||||||||
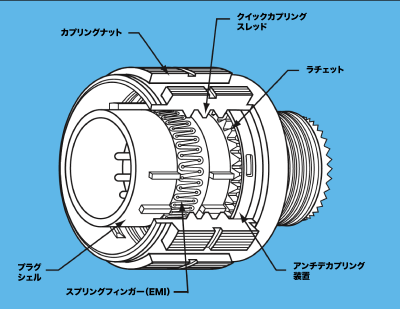 |
|||||
 |
|||||
|
|||||
��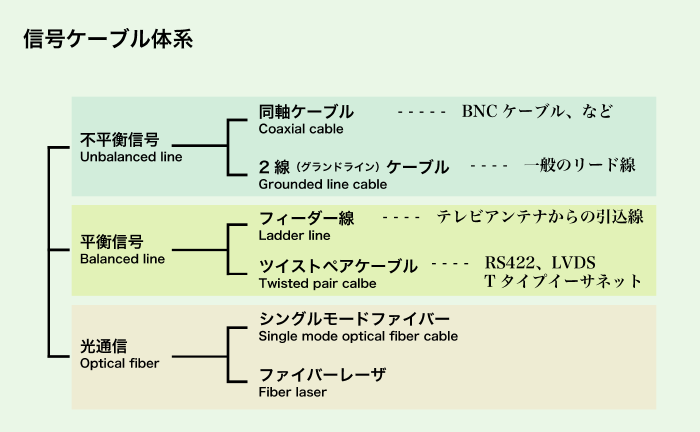
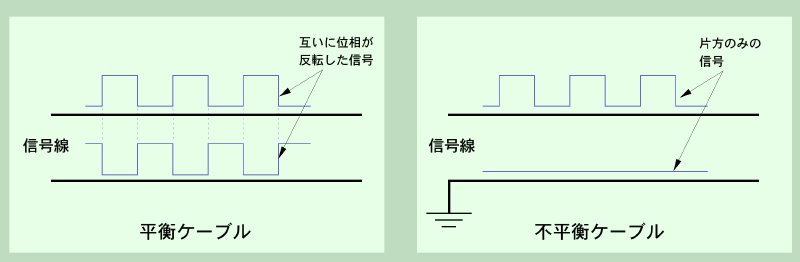 ��
��
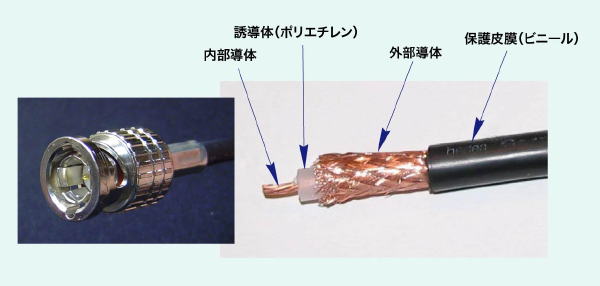 ��
��
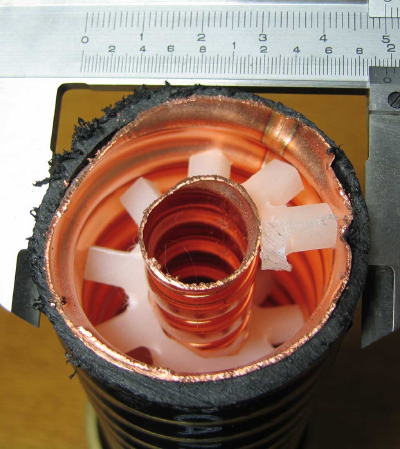 |
||||
�̿�����Miikka Raninen��
|
||||
��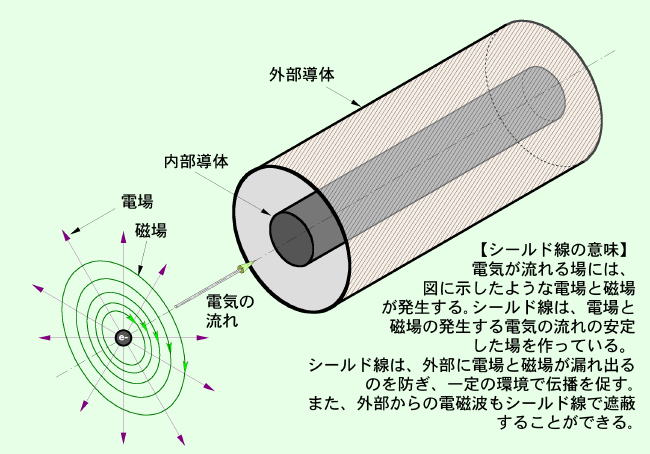
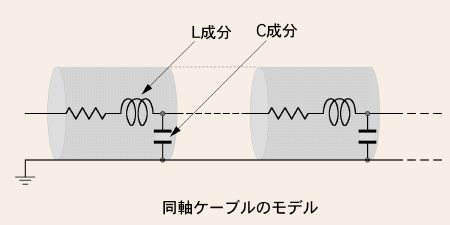 �⤤���ȿ��ο�����֥�������硢�����֥�ϰʲ�������ʬ������ޤ��� ��
�⤤���ȿ��ο�����֥�������硢�����֥�ϰʲ�������ʬ������ޤ��� ��
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ʊ�������֥��3C-2V��10C-2V�ˤ�����ɽ��
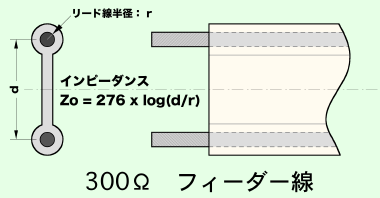
 ��ʬ�����դ�ʧ�ä�����Ǥϡ�����������Ʊ�������֥����ͥ��Ƥ��ޤ���
��ʬ�����դ�ʧ�ä�����Ǥϡ�����������Ʊ�������֥����ͥ��Ƥ��ޤ�����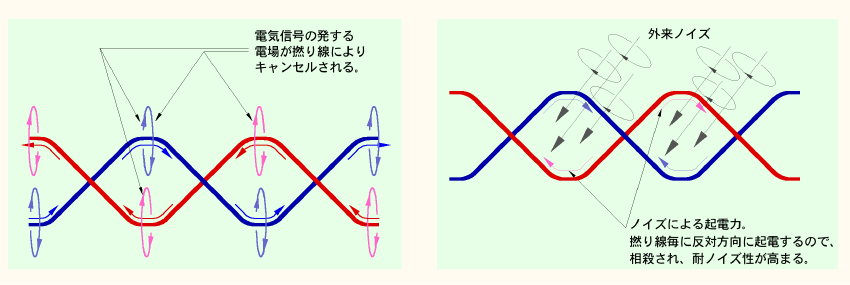
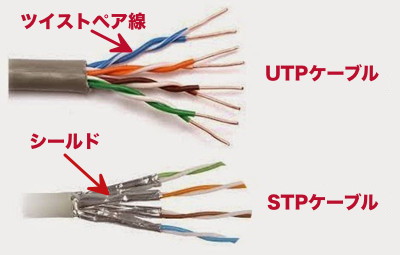 �ĥ����ȥڥ������֥�ϡ�����Ū�˥Υ����˶�����������äƤ��ޤ���������Ǥ⳰��������ż��Υ��������ۤ������ˡ������֥����Τ���ɽ��������ĥ����ȥڥ������֥��Ȥ����Ȥ�����ޤ���
�ĥ����ȥڥ������֥�ϡ�����Ū�˥Υ����˶�����������äƤ��ޤ���������Ǥ⳰��������ż��Υ��������ۤ������ˡ������֥����Τ���ɽ��������ĥ����ȥڥ������֥��Ȥ����Ȥ�����ޤ���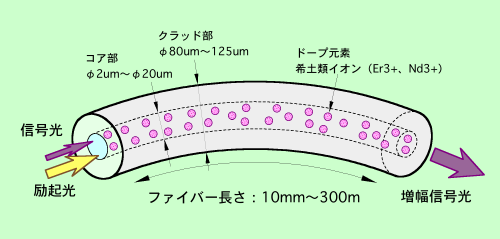 |
||||
|
||||
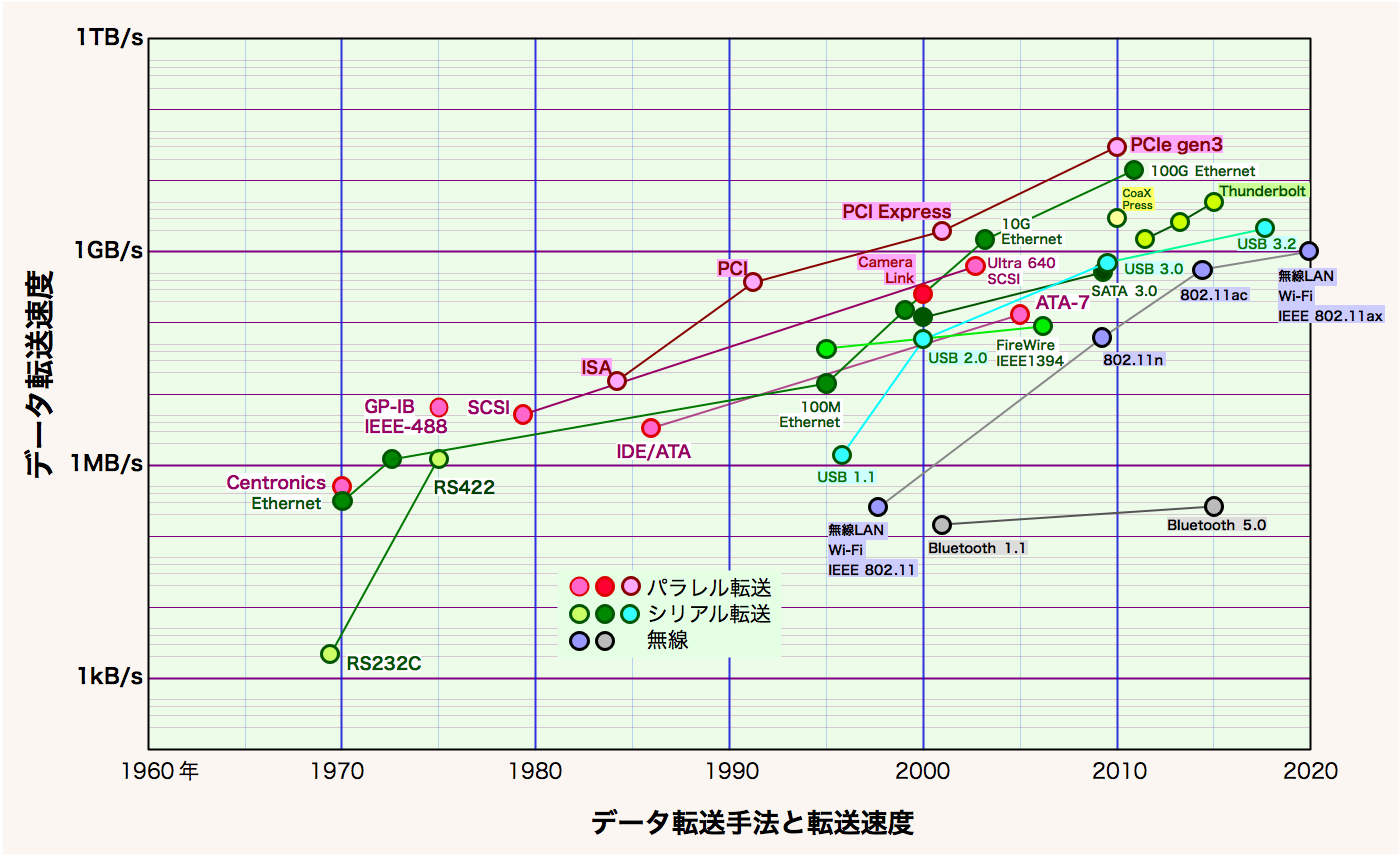 ��
��
 COM�Ȥ����Τϡ�Communication���̿��ˤ�ά�ǡ��̿��ݡ��Ȥΰ�̣�Ǥ���
COM�Ȥ����Τϡ�Communication���̿��ˤ�ά�ǡ��̿��ݡ��Ȥΰ�̣�Ǥ��� �������ץ顼�ȸƤФ�����֡����äμ��ô�ˤ��ФΤ褦�ʤ�Τ����դ��ơ�FAX������ݤΥ�����/��������Τ褦�ʲ����ǥǥ������̿���Ԥä����֡ˤ⡢����RS232C���ʤ���Ѥ��Ƥ��ޤ�����
�������ץ顼�ȸƤФ�����֡����äμ��ô�ˤ��ФΤ褦�ʤ�Τ����դ��ơ�FAX������ݤΥ�����/��������Τ褦�ʲ����ǥǥ������̿���Ԥä����֡ˤ⡢����RS232C���ʤ���Ѥ��Ƥ��ޤ�����
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
��
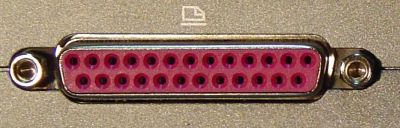
- * �ԥ�1��STROBE���ѥ����ǡ����������������Ȥ�ץ��������Ʊ�����档
- * �ԥ�2-9��DATA1 - DATA8��8�ӥåȤΥǡ������档
- ---------------------------------
- * �ԥ�10��ACKNLG���ץ���ǡ���������������Ȥ�ۥ��Ȥ�������Ʊ�����档
- * �ԥ�11��BUSY���ץ�����Υǡ���������Ǥ��ʤ����Ȥ����档
- * �ԥ�12��PE���ץ���ѻ�ν������Τ餻�뿮�档
- * �ԥ�13��SEL���ץ�����档
- * �ԥ�14��LF���ץ�ιԴ������档
- * �ԥ�15��ERROR���ץ�Υ��顼���档
- ---------------------------------
- * �ԥ�16��PRIME������ԥ塼���ν�������档
- * �ԥ�17��SEL������ԥ塼�������档
- ---------------------------------
- * �ԥ�18 - 25��GND��8�ܤΥ����ɿ������� ��
����
��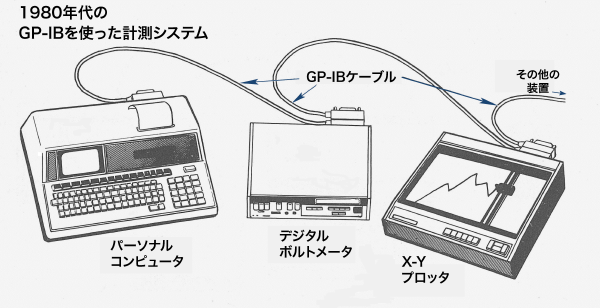
 |
|
 IDE�ϡ�SCSI ���֤������褦�ˤ���ȯŸ���Ƥ�����Τǡ��ϡ��ɥǥ�������HDD�ˤι�®�ǡ���ž������Ū�ˤ��Ƥ��ޤ�����
IDE�ϡ�SCSI ���֤������褦�ˤ���ȯŸ���Ƥ�����Τǡ��ϡ��ɥǥ�������HDD�ˤι�®�ǡ���ž������Ū�ˤ��Ƥ��ޤ�����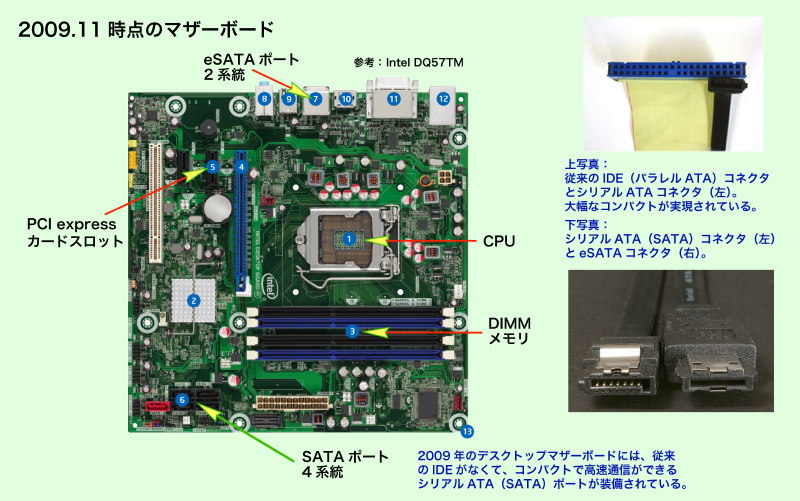 ��
�� 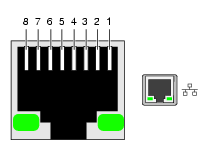 |
|||||||
|
|||||||
 |
|||||||
|
|||||||
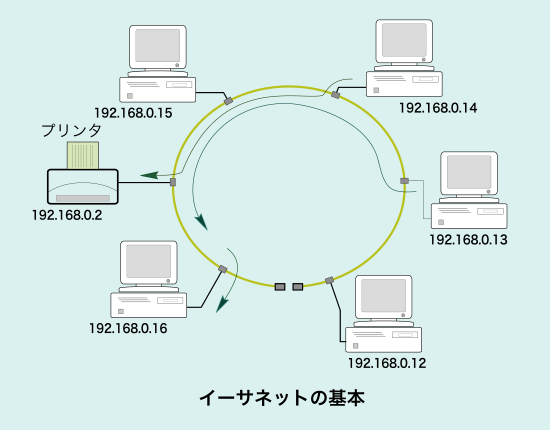 |
||||
|
||||
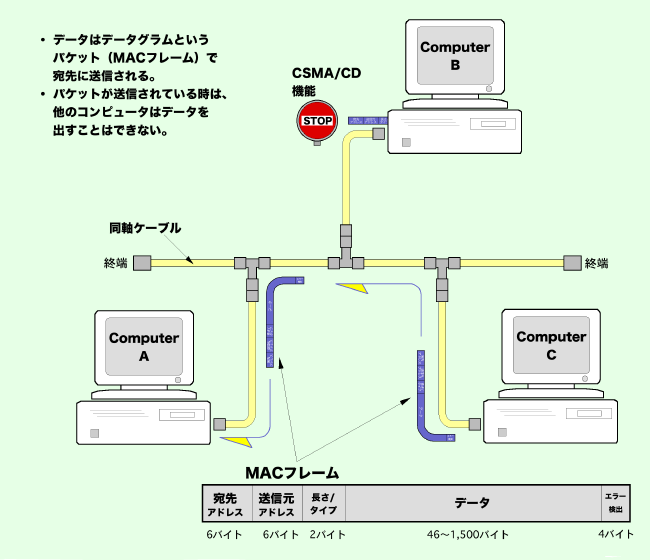 ��ȥ����դϡ��ǡ������̿����������Ȥ������äζ�Ʊ�������ʥѡ��ƥ��饤��ˤȤ�����ǰ��Ƴ�����ޤ�����
��ȥ����դϡ��ǡ������̿����������Ȥ������äζ�Ʊ�������ʥѡ��ƥ��饤��ˤȤ�����ǰ��Ƴ�����ޤ�����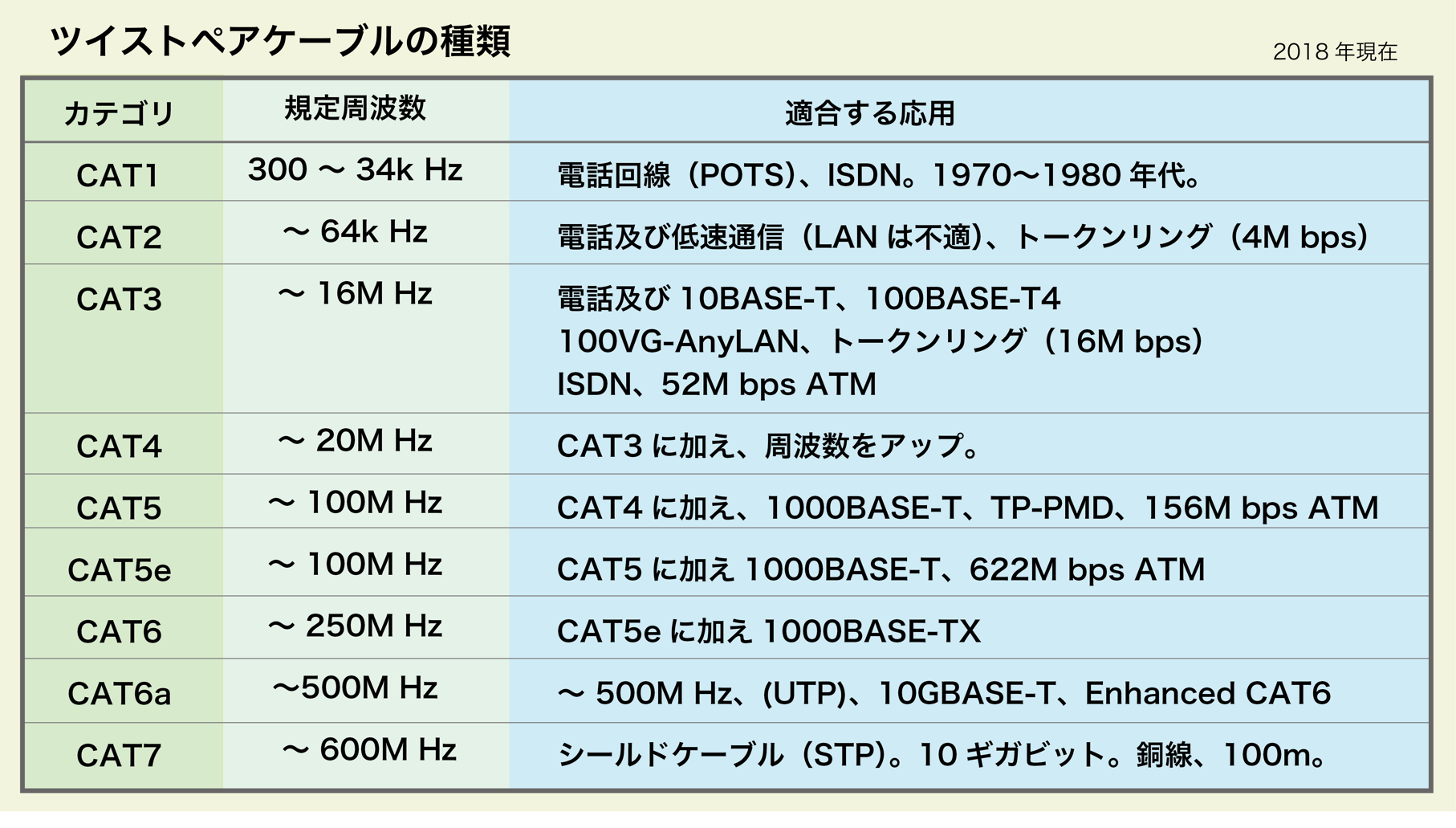
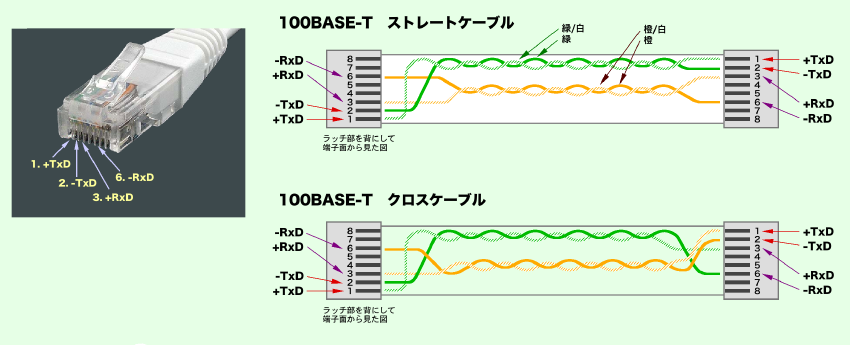 ��
��
- ��1000BASE-T�Ǥϡ���¸�Υĥ����ȥڥ������֥��Ȥäƹ�®�̿��뤿���4�Фο������٤Ƥ�Ȥä����������������Τ���ǡ����Ȥ��뤿���8�ӥåȾ����9�ӥåȤˤ���������4�饤���9�ӥåȾ����ʬ���뤿���5��ˡ�ǡ����Ȥ�������
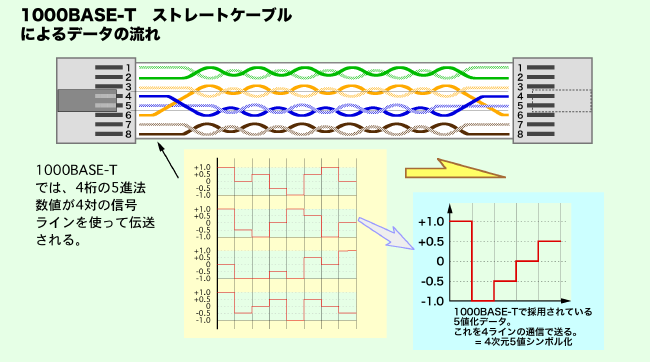
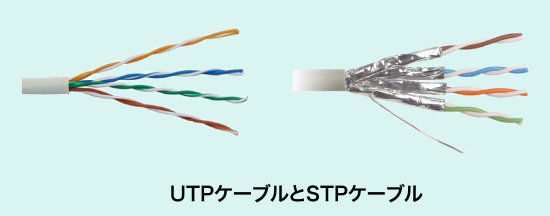 �ĥ����ȥڥ������פΥ������ͥåȥ����֥�ˤϡ���ǽ�̥��ƥ����ʬ����줿�����¾�ˡ���¤��2����Τ�Τ�����ޤ���
�ĥ����ȥڥ������פΥ������ͥåȥ����֥�ˤϡ���ǽ�̥��ƥ����ʬ����줿�����¾�ˡ���¤��2����Τ�Τ�����ޤ��� |
||||||
 |
||||||
|
||||||
 |
||||||
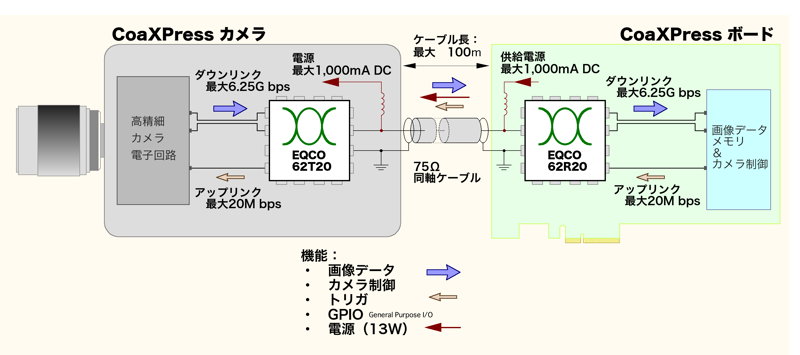 Ʊ�������֥�ϡ�Ĺ��Υ�̿������դǤ����Τ�̵��¢��Ĺ�����뤳�ȤϤǤ��ޤ���
Ʊ�������֥�ϡ�Ĺ��Υ�̿������դǤ����Τ�̵��¢��Ĺ�����뤳�ȤϤǤ��ޤ��� |
||||
 |
||||
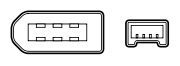 |
||||
|
||||
��
 |
|||||
 |
|||||
|
|||||
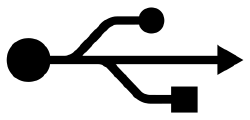 |
|||||
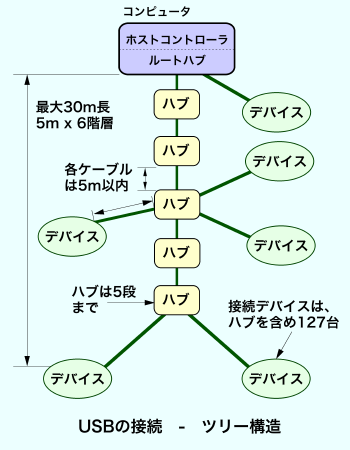 �ʥۥ��ȡˤˤ�������ɬ�פȤ��ޤ���
�ʥۥ��ȡˤˤ�������ɬ�פȤ��ޤ���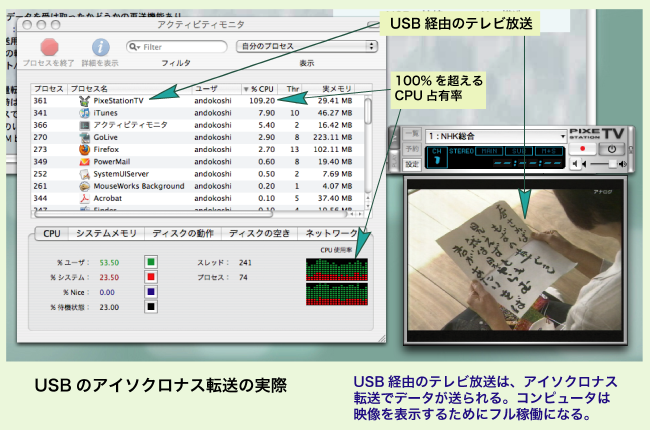
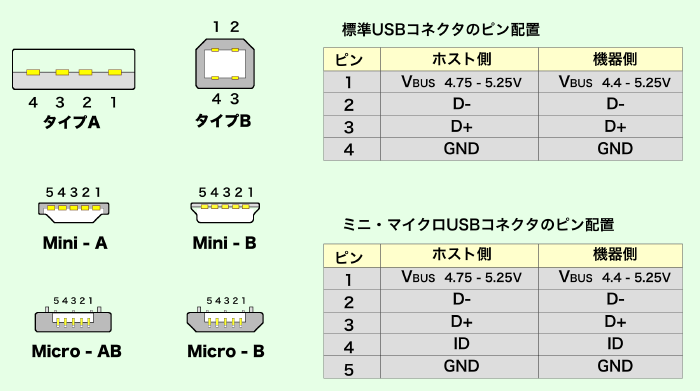 ��
��
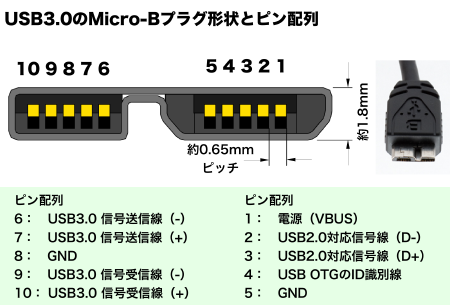 94�����®�̿����Ǥ�����ǽ�Ǥ���
94�����®�̿����Ǥ�����ǽ�Ǥ���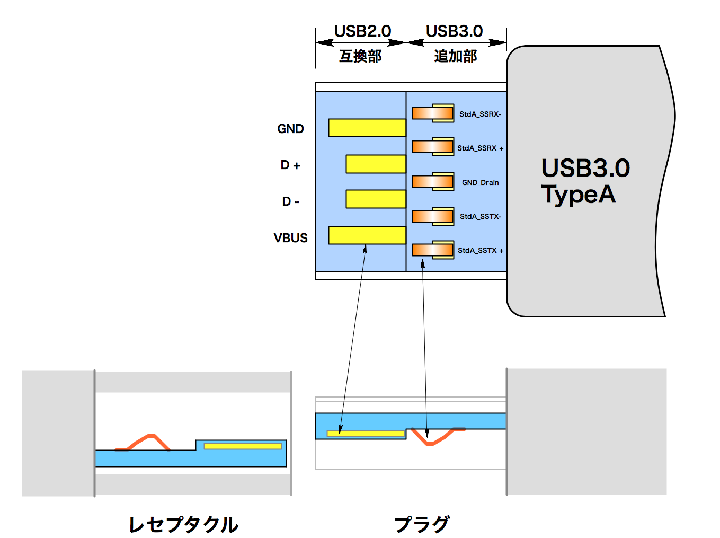
 ��
��
��

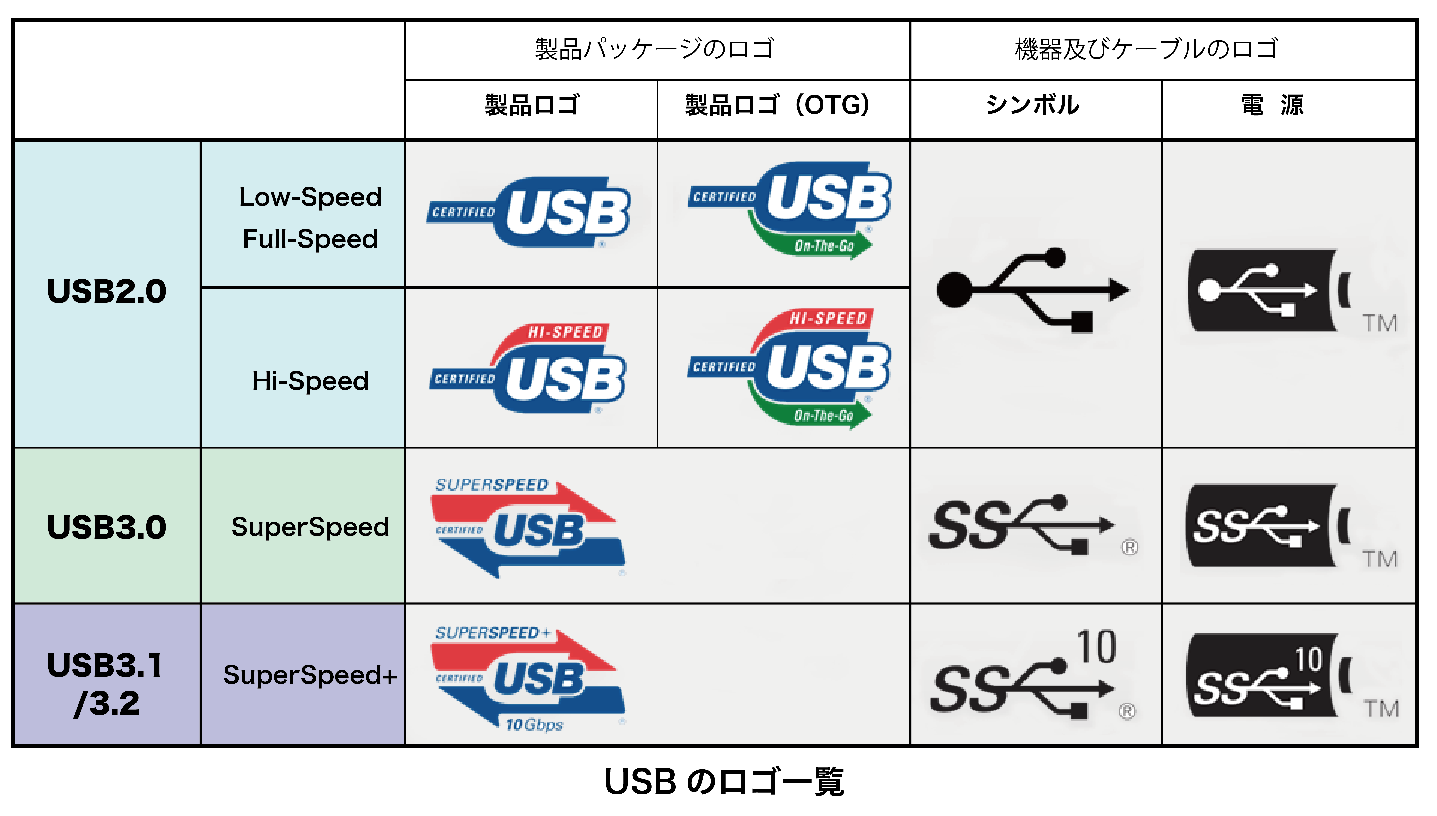 ��
��
 USB4�ϡ�2019ǯ8���USB Implementeres Forum��1995ǯ��Ω�ˤˤ�äƥС������1.0����������ޤ�����
USB4�ϡ�2019ǯ8���USB Implementeres Forum��1995ǯ��Ω�ˤˤ�äƥС������1.0����������ޤ����� USB3.0�ʹߤǤϡ����ͥ�������Thunderbolt3�ʹߤ���Ȥ��Ƥ���Ʊ��������USB-C�����֥뤬���Ѥ���Ƥ��ơ����ѼԤˤ�ξ�Ԥΰ㤤���狼�餺�����ޤͤ��Ƥ��ޤ���
USB3.0�ʹߤǤϡ����ͥ�������Thunderbolt3�ʹߤ���Ȥ��Ƥ���Ʊ��������USB-C�����֥뤬���Ѥ���Ƥ��ơ����ѼԤˤ�ξ�Ԥΰ㤤���狼�餺�����ޤͤ��Ƥ��ޤ�������USB���������2018.11.12�ˡ�2018.12.27�ɵ���
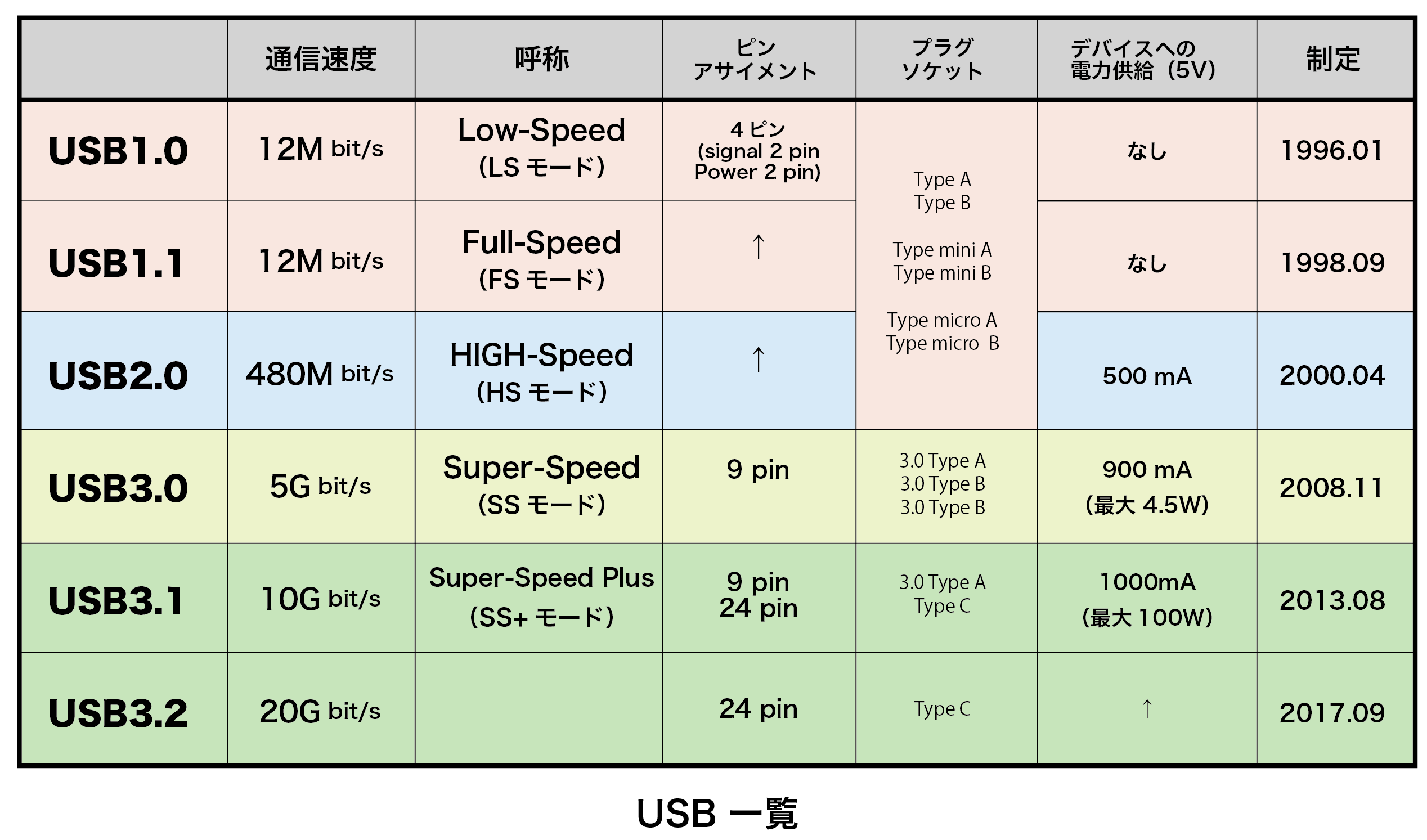 ��
��
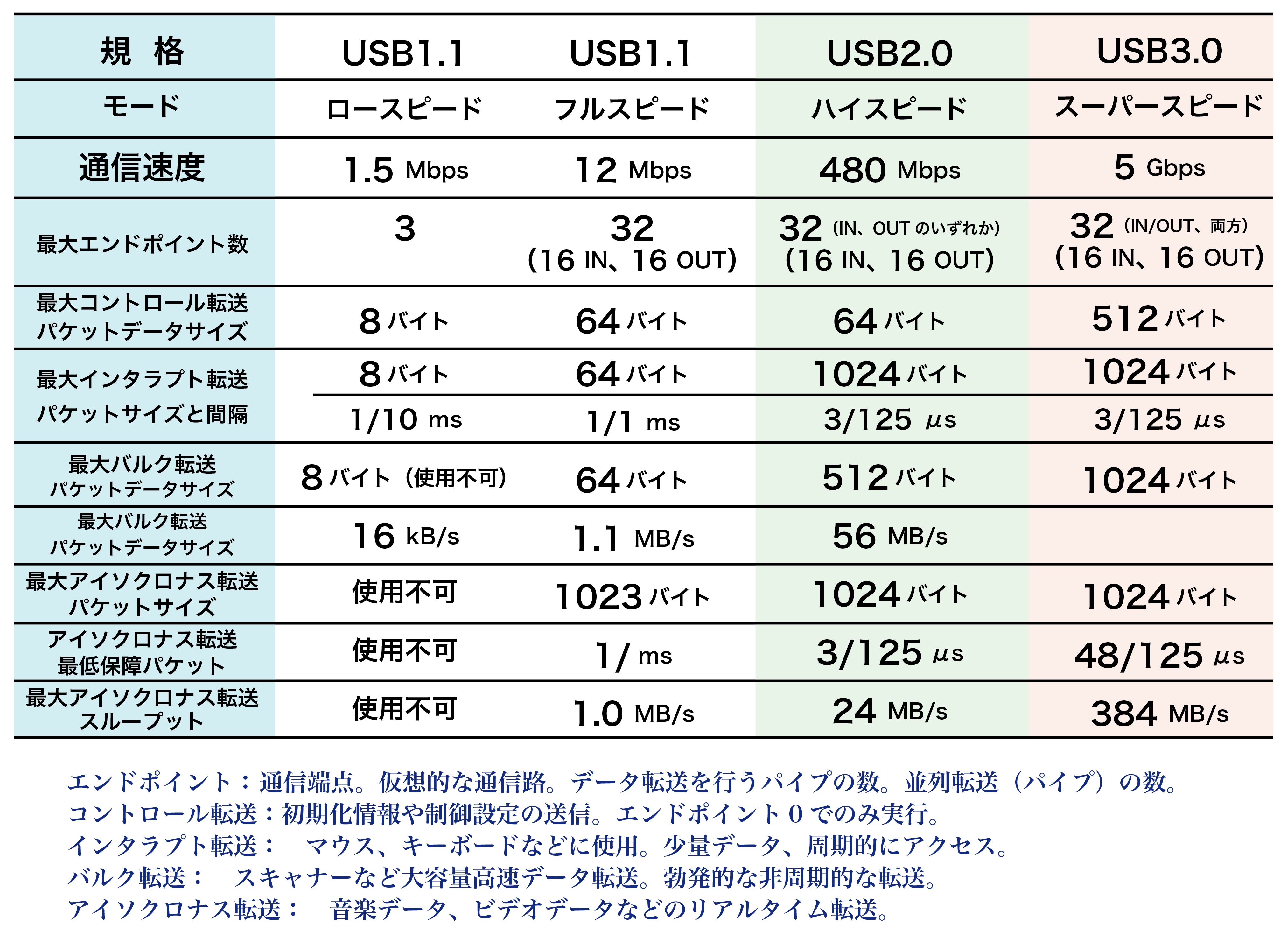 ��
��

��
 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
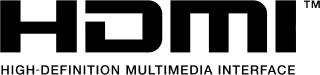 |
 |
|||
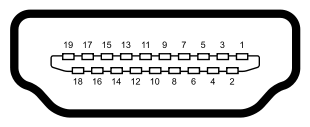 |
||||
 |
|||
| ���ʥ����ӥǥ�ü�ҡʾ�̿��ˤȥǥ�����ӥǥ�ü�ҡ�DVI�ˡʲ��̿���
�ǥ����ȥåץѥ�����Ǥϥǥ�����ӥǥ�ü�Ҥ���ڤ��Ƥ��뤬���Ρ��ȥѥ��������°��˥����Ϥ�վ��ץ�����������ü�Ҥˤϰ����Ȥ��ƾ�ޤΥ��ʥ���ü�Ҥ��Ȥ��Ƥ��롣 |
|||
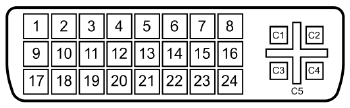 |
|||
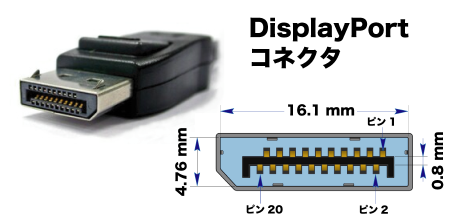 ����DisplayPort�ʥѥ����̿���
����DisplayPort�ʥѥ����̿���

 ��ư���������Ȥ��˻Ȥ��ڥ��ˤʤä�2�����ϡ��ߤ����ܿ�����Dz�ä��κۤˤʤäƤ��ޤ���
��ư���������Ȥ��˻Ȥ��ڥ��ˤʤä�2�����ϡ��ߤ����ܿ�����Dz�ä��κۤˤʤäƤ��ޤ�����
- �� �� �� �� ��
- ��


��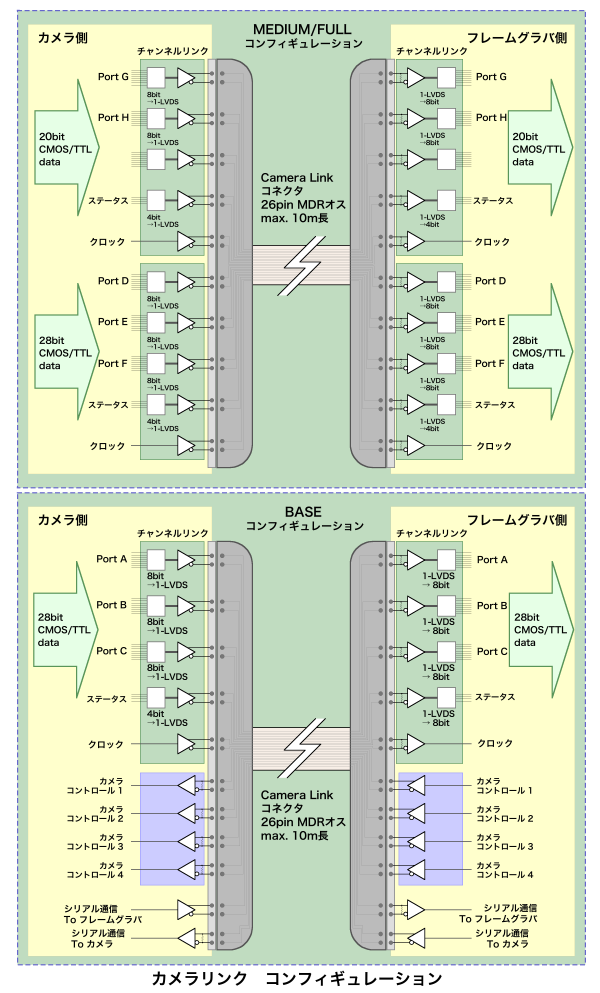

��
��
��

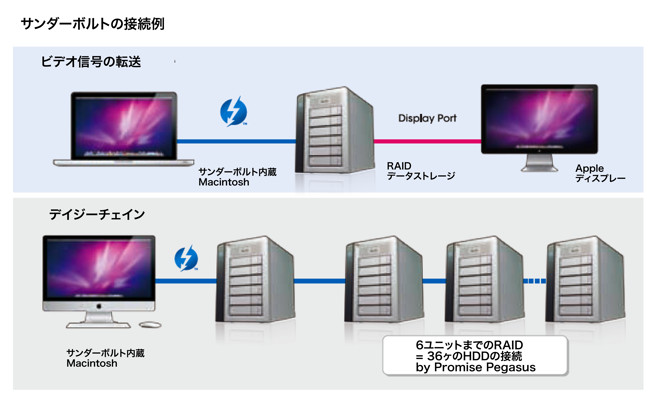

 3���ܤι��ܤ�USB PD��USB Power Delivery�˵�ǽ�Ȥϡ���³���줿������Ÿ�������Ԥ���ΤǤ���
3���ܤι��ܤ�USB PD��USB Power Delivery�˵�ǽ�Ȥϡ���³���줿������Ÿ�������Ԥ���ΤǤ��� Thunderbolt 4�ϡ�2020ǯ1��˥���ƥ�Ҥˤ��ȯɽ����ޤ�����
Thunderbolt 4�ϡ�2020ǯ1��˥���ƥ�Ҥˤ��ȯɽ����ޤ����� Thunderbolt4 ������Thunderbolt3�ϡ�USB4�˵��ʡ���ǽ��ܴɤ��Ƥ��ޤ��Τǡ�Thunderbolt4�б������֥���Ѥ���USB4�������³���뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
Thunderbolt4 ������Thunderbolt3�ϡ�USB4�˵��ʡ���ǽ��ܴɤ��Ƥ��ޤ��Τǡ�Thunderbolt4�б������֥���Ѥ���USB4�������³���뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
|
|||||
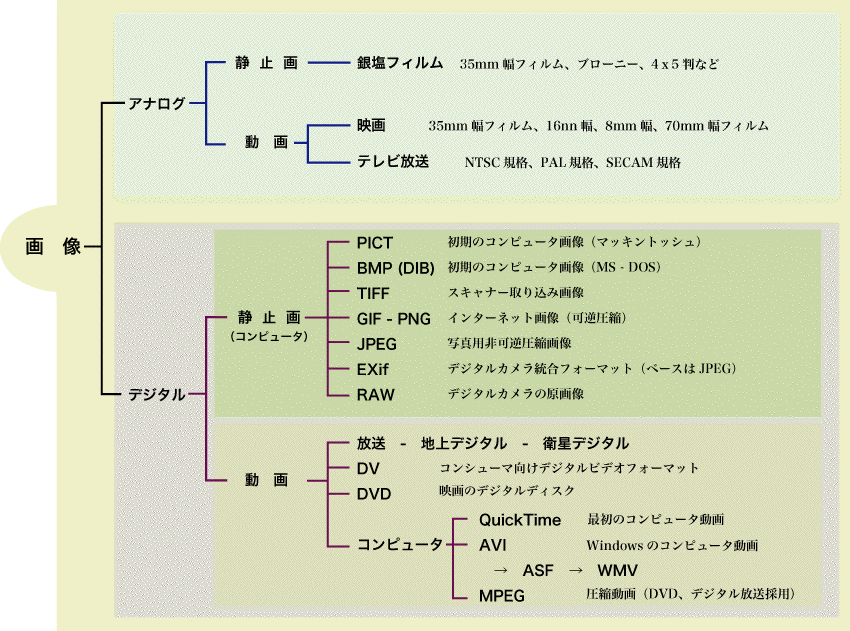
 TIFF�ϡ��Ż߲����Ȥ��ư���Ū�ʥե�����ե����ޥåȷ������������ǽ�Τ�ΤǤ���
TIFF�ϡ��Ż߲����Ȥ��ư���Ū�ʥե�����ե����ޥåȷ������������ǽ�Τ�ΤǤ���
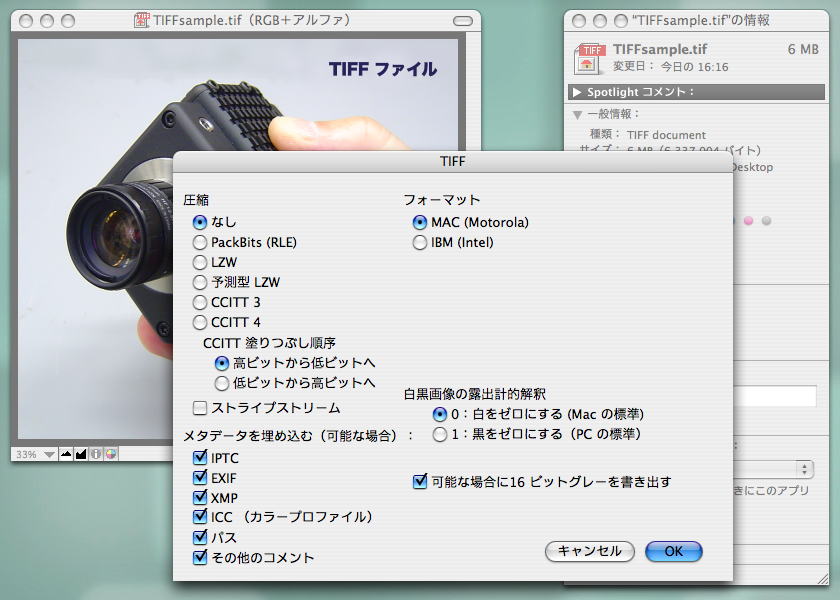 TIFF�ե��������¸�����硢���ץ����ܥ�����ȱ��˼����褦�ʥ��ץ�������꤬�Ǥ��ޤ���
TIFF�Ǥϰ��̤ˤ��ե�����������ǽ�ȤʤäƤ��ޤ���
TIFF�ե��������¸�����硢���ץ����ܥ�����ȱ��˼����褦�ʥ��ץ�������꤬�Ǥ��ޤ���
TIFF�Ǥϰ��̤ˤ��ե�����������ǽ�ȤʤäƤ��ޤ���
| �ե�����ե����ޥåȤˤ�����ΰ㤤 | ||||||
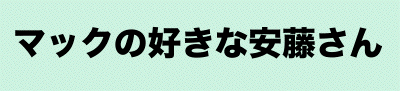 |
||||||
| TIFF��BMP��PICT�Υӥåȥޥåײ��������̤���Ƥʤ��Τ����̤��礭������������������ɹ��� | ||||||
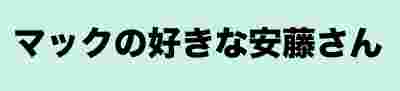 |
||||||
| ����Ψ10%��JPEG������JPEG���äΥΥ����ʥ⥹�����ȥΥ����ˤ�����롣ʸ���η�֤��طʿ������������褦�ˤʤäƤ��롣JPEG�Ǥϰ���Ψ�����ȡ��٤������ʤ��ʤ롣 | ||||||
 |
||||||
| ���10%�˰��̤���JPEG���������ɽ��������Ρ����̤ˤ������ιӤ줬��Ω�ġ��⥹�����ȥΥ������Ф�Τϡ�8����x8���Ǥǰ��̤�Ԥ����ᡣ | ||||||
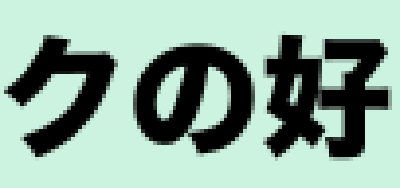 |
||||||
| ���̥ե�����Ǥ���GIF�β��������ɽ��������Ρ�GIF�����ϲĵհ��̤Ǥ��ꡢ�������ξ������Ϥʤ���ʸ���ʤɤϡ�GIF������JPEG���⤭�줤��Ʊ������������PNG�����롣GIF���õ������꤬���ä�����PNG�ˤϤʤ��� | ||||||
 |
||||||
| EPS�ե����롣EPS�Ͽ����Dz����Ҥ��Ƥ��롣�ӥåȥޥåפȰ�äơ�����������Ƥ��Ŭ�ʲ�����ɽ�������äƲ�������礷�Ƥ��餫��ɽ�����롣 | ||||||
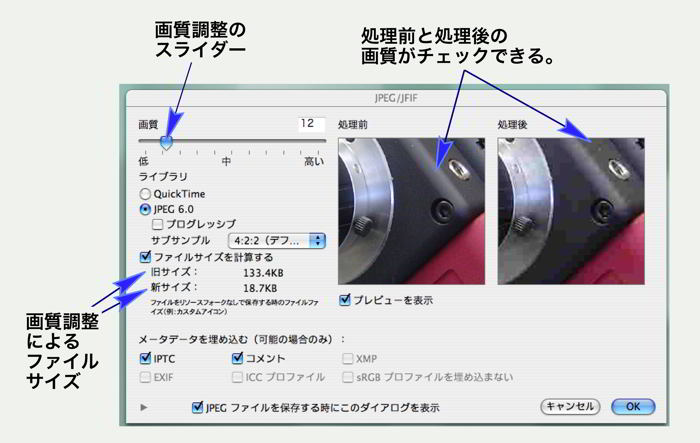 JPEG�ϡ�JFIF�Ȥ�ƤФ�Ƥ��ޤ���������������Ū�ˤ�JPEG�Ȥ���̾�����Ȥ��Ƥ��ޤ���
JPEG�ϡ�JFIF�Ȥ�ƤФ�Ƥ��ޤ���������������Ū�ˤ�JPEG�Ȥ���̾�����Ȥ��Ƥ��ޤ���
 JPEG 2000�ϡ�JPEG�θ�ѥե�����ե����ޥåȤǤ���2000ǯ12��˴��𤵤�ޤ�����
JPEG 2000�ϡ�JPEG�θ�ѥե�����ե����ޥåȤǤ���2000ǯ12��˴��𤵤�ޤ�����
- ��β����ϡ��ǥ�����ǻ��Ƥ���Exif�����Ȥ��β��������äƤ���Exif�ǡ����� �ǡ����ξܺ٤˼�����
- ���Υե����뤫�顢���Ƥ���ǯ�����Ȼ��֡����Ѥ�������顢���ƾ��ե��������̤ʤɻ��٤��ʾ���뤳�Ȥ��Ǥ��롣
- ���β����ϡ��ޥå���ȥå���β������������֥��եȥ�������Graphic Converter ver.5.9.5�פ���Ѥ��Ʊ����������̤Υ��ԡ��Ǥ��롣 ��2006.06��
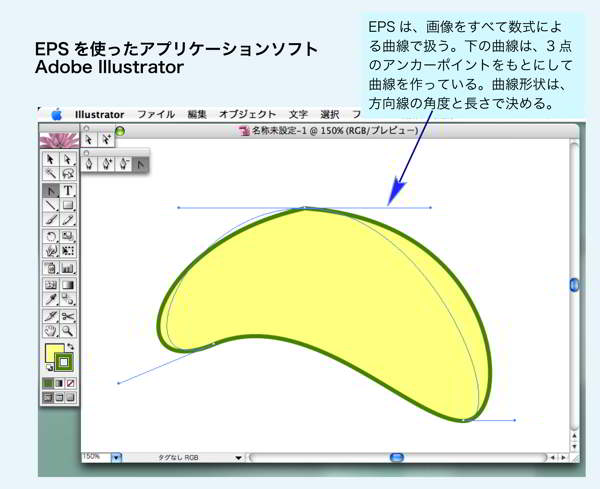 EPS�ե�����ϡ�ASCII �����Τ�Τȡ��Х��ʥ�����Σ����ब���ꡢ�Х��ʥ�����Τ�Τϥե����륵������Ⱦʬ�ˤʤ�ޤ���
EPS�ե�����ϡ�ASCII �����Τ�Τȡ��Х��ʥ�����Σ����ब���ꡢ�Х��ʥ�����Τ�Τϥե����륵������Ⱦʬ�ˤʤ�ޤ���

 |
||
- ̾������
- ������
- ������
- �� ��
- �ģ����ʲ����ϡ�
- ���ǿ�
- MB
- Base/16
- 128 x192
- 24.8 k����
- 0.07
- �ץ�ӥ塼������ͥ���
- Base/4
- 256 x 384
- 98.3 k����
- 0.28
- �����ͥå�Web��
- Base
- 512 x 768
- 393.2 k����
- 1.13
- ����ԥ塼���������
- �����ͥå�Web��
- 4Base
- 1,024 x 1,536
- 1.57 M����
- 4.50
- �������TV�������
- 16Base
- 2,048 x 3,072
- 6.29 M����
- 18.0
- ������
- 64Base
- 4,096 x 6,144
- 25.2 M����
- 72.0
- �ץ�����
- ��
- ���ε��ʤ��Ǥ���1990ǯ���Ⱦ��DPE����åפ˥ե����ͥ����������ȡ�Base/16���� 16Base �ޤǤ�5�Ĥβ�����1���åȤȤ���CD�˾Ƥ��Ƥ��줿����������ޤ���
- PhotoCD�Ǥϡ�CD1���100������Ͽ�Ǥ��뵬�ʤˤʤäƤ��ޤ�����
- Pro PhotoCD�Ǥ�4�ܤ��礭���ˤʤ�Τ�1���CD��25��β�������¸�Ǥ��ޤ�����
- PhotoCD��5�Ĥβ����Υե��������̤��פ����23.99MB�Ȥʤ�ޤ���
- CD1���100����ʬ��Ͽ�����2.4GB�Ȥʤ�ޤ���
- ����Ǥ�CD�˼��ޤ�ޤ���
- 650MB��CD��100���PhotoCD��Ͽ����Ȥʤ�ȡ�1�Ĥβ�����6.5MB�ʲ����ޤ��ʤ���Фʤ�ޤ���
- 16Base�β����Ǥ�18MB��������ΤǤ���
- ���äơ�PhotoCD�ϲĵհ��̼�ˡ���Ȥ��Ƥ��ޤ���
- ����ϡ�Image Pac�ȸƤФ������Ǥ�����
- ��
- ����������ѥå�������Image pac��
- PhotoCD�ϡ�16Base�� = 2,048 x 3,072���ǡˤβ����Ϥ����Ȥ���5�Ĥβ����Ϥ�ɽ���Ǥ�������ե������������äƤ��ޤ���
- ��Pro PhotoCD�ϡ�64Base��ޤ6����β����ե�������äƤ��ޤ�������
- ������ѥå��ϳ��ز���¤����ä���Τǡ����ܲ�����Base�˲��������ղþ���ˤ�ä�5����β����Ϥ���IJ�����Ǥ�դ˸ƤӽФ����Ȥ��Ǥ����ΤǤ���
- ���γ��ز����ѡ�hierarchical storage format�ˤϡ��ƹ��HP�ҡ�Hewlett-Packard�ˤ������ȸ����Ƥ��ޤ���
- ��˽Ҥ٤ޤ����褦�ˡ�PhotoCD��5�Ĥβ����Ϥ���IJ��������ǡ�����Τ�Τϡ�16Base��2,048 x 3,072���ǥե륫�顼�Ǥ���
- �����������β����ϥե��������̤�ñ��������18MB�Ȥʤ�ޤ���
- PhotoCD�Ǥϡ�Base�������δ��ܤȤʤäƤ��ơ�������٤β�������Ȥ��ˤϡ�Base��������ܤȤ��Ʋ��Ǵ֤��䴰����4�ܤξ�������4Base����ޤ���
- ����˹�����٤��᤹����ϡ�4Base�β����˲���������䴰����4�ܤξ�������16Base����ޤ���
- �ޤ���Base/4��Base/16�ξ����������ϡ����̤����ʤ��Τ�ľ�ܲ����ե�������ä���¸���Ƥ��ޤ���
- ��
- PhotoCD�δ��ܲ����ϡ�Base�Ȥ���512 x 768���ǤǤ��ꤳ�줫�����Ǥ��ۤ��Ƥ���������ȤäƤ��ޤ���
- ���ֹ⤤�����Ϥβ����ե����뤫��ְ������Ʋ��ǿ��餷�Ƥ����Τ����䤹����ΤǤ�����Base�Ȥ������Ū�����ʲ��Ǥǹ�����٤β������ۤ��Ƥ����Ȥ����Τ���ˡ���ߤƤ��ơ��ۥ�Ȥ˹����β�����������Τ��ȵ���˴����Ƥ��ޤ��ޤ���
- ����ϡ�Base��ǽ�Ū�˺��夲��Ȥ����ǽ��16Base�β����ǥǥ��������ʥǥ����벽�ˤ��ơ���������1/16��Base�ޤǽ̾����Ƥ������̾���������������Ĥ��Ƥ������餳���Ǥ�����ˡ���ä��ΤǤ���
- �̾�������ϡ�16Base�����˸��������Ǥ������Ǥ��ꡢ���ξ����˰��̡�Huffman�����ˤ�����¸����Ȥ�����ΤǤ�����
- 1990ǯ�������ϡ�������ˡ��������ѥ��ȤˤޤȤ�Ʋ����ȥ쥹�ʤ�ɽ�����ʤ����Ĺ�����٤ޤ��б����Ƥ���٥��Ȥ������Ǥ��ä��ȸ����뤫���Τ�ޤ���
- ������ѥå������Ѥ��Ƥ���������̤ϲĵհ��̤Ǥ��ꡢJPEG�Τ褦�ʲ���������������ޤ���
- �����Τˤϡ��٤�����ο������䰦�����پ��������Ĥ��ΤǴ����ʲĵհ��̤ǤϤ���ޤ����ۤȤ������ˤʤ�ޤ���
- ������ѥå��βĵհ��������δ��ܤϰʲ����̤�Ǥ���
- ��
- ����1.���ǽ�β����ʥե��������ˤ�16Base�����ʤ����2,048���� x 3,072���ǤΥե륫�顼��24�ӥåȡˤǼ����ࡣ
- ����2.�����β�����RGB��3�����ˤǤϤʤ���YCC�ʵ��٤ȿ�����YUV�Ȥ���������Ѵ����롣
- ��������YCC���������ΰ��̤��Ԥ��䤹��������Ū��Y�ʵ��١ˤϽ��פʤΤǤ��ξ���ϻĤ���
- ����������������ϡ��٤������̤˴ؤ��ƤϿͤ��ܤ��б����ʤ��ΤǴְ�����
- ���������ʤ���ϥƥ�ӤΥ��顼���Ѥ�Ʊ������
- ����3.����������1/4���Ѵ�����4Base�β������롣
- �����������λ��ˡ��Ѵ���������ե�����˻Ĥ��Ƥ�����16Base�β�������Ȥ��ν���䵤Ȥ��롣
- ����4.������ˡ�4Base��1/4���Ѵ����ơ�Base�ײ������롣ʻ���Ƥ����Ѵ���������ե�����˻Ĥ���
- ����������Base�ײ�������ܲ����Ȥ�����¸���롣������Ȥ�4Base��16Base����夲�롣
- ����5.��Base/4��Base/16�ϡ��������������Τ�ͽ���äƲ����ե�����Ȥ�����¸���롣
- ����6.��64Base�ϡ�Pro PhotoCD�ȸƤФ���Τǡ�����ϡ��ǽ��4,096���� x 6,144���Ǥ��ꡢ
- �����������Ʊ�ͤμ�ˡ�ǹ��6����β������ۤ��롣
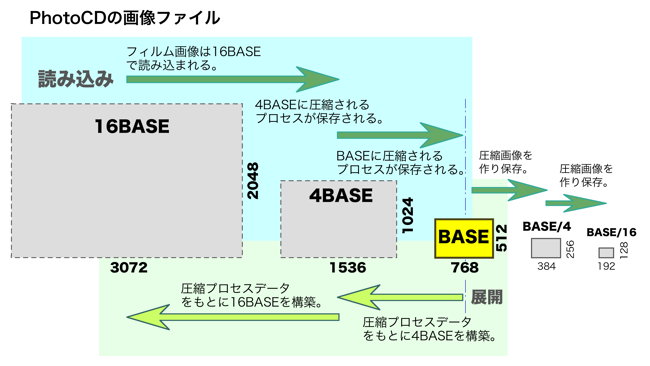
- ��
- 1990ǯ�塢4Base�β�����4.5MB�ˤ�ѥ�����dz�����Τϻ���ζȤǤ�����
- �������������30�����٤λ��֤������äƤ����ȵ������Ƥ��ޤ���
- ���ǿ������ޤ��ȡ�Base������2000ǯ�����˸���줿�ǥ����륫����640���ǣ�480���������ˤȤۤȤ��Ʊ���٤Ȥʤ�ޤ��������ä��ꤷ���ե��������������ǽ������ʡ���PhotoCD�˻Ȥ�줿������ʡ������ɴ���ߡˤǥǥ����벽���������ϡ���γ��γ·�äƤ�����1���ǤΥΥ��������ʤ��ˡ��̥����ɤ��ǥ���������������Ƥ��ޤ�����
- �ޤ���ñ��CCD�ǻҤ�����줿�ǥ�����������⥫�顼�����ä��ꤷ�Ƥ��ޤ�����
- ��������2010ǯ�ˤ��äƤϡ�3000���ǣ�2000���������Υǥ����륫��餬�²��˽в��褦�ˤʤ�ȡ����ǿ�������Ū�ʥѥ������Τǽ̾����ƻȤ��Хե��������ʾ�β�����������褦�ˤʤ�ޤ�����
- ����ˤ��谷�Τ褤�ǥ����륫��餬�ե���५������ष�Ƥ������Ȥˤʤ�ޤ�����
- ����
- ����Flashpix�ʥե�å���ԥ�����������2010.03.15�ˡ�2010.04.29�ɵ���
�����γ��ز����Ѥ������Τ�Flashpix�Ǥ���
- ���β����ե����ޥåȤϡ��������ȥޥ��å��Ҥμ�Ƴ�ǥҥ塼��åȥѥå����ɼҡ��饤�֥ԥ�����ҡ��ޥ��������եȼҤζ��Ϥ�����1996ǯ�˺��ꤵ��ޤ�����
- Flashpix�ե����ޥåȤϡ��饤�֥ԥ�����Ҥ���ȯ����IVUE�Ȥ��������뵡ǽ/�ޥ����롼�����ǽ��Ƨ�����Ƥ��ޤ���
- Flashpix�ϡ�Exif�ե����ޥåȤˤ��б����Ƥ��ơ��ǥ����륫��������줿Exif�ե����ޥåȲ�����Flashpix���Ѵ���¸���Ʊ������뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
- Flashpix�ϡ���®�˹��������ե����������������Ȥ����ᤫ�����ޤ�ޤ�����
- �������Ȥ��̤ˡ�96x96���ǤΥ���ͥ�����������Υե����ޥåȤ��Ȥ߹��ޤ�Ƥ��ơ������γ��פ�����˸�����褦�ˤʤäƤ��ޤ���
- ����˲ä������������ʬ�����ơʥ����뵡ǽ�ˡ��ɤΥ��ꥢ��ȴ���Ф�����ͳ�����֤��Ȥ��Ǥ��ޤ���
- �ޤ������ϰϤ�����硢�٤�������������ɬ�פϤʤ��ΤǴְ����������������ä��̿���ɽ������٤�ڸ������Ƥ��ޤ��ʥޥ����롼�����ǽ�ˡ�
- Flashpix�Ǥϡ��Ǿ�ñ�̤�64x64���ǤǴ�������Ƥ��ơ����β��ǥ֥��å��ʥ�˥åȡˤ���Ž��ι�¤�Τ褦�ˤ��Ƹ�����������Ƥ��ޤ���
- �����ϰϤ�Ȥ��ϡ�64x64���Ǥ������ɽŪ�ʾ�����夲����1���ǤȤ��Ʋ������ۤ���褦�ˤʤ�ޤ���
- �̾�β����ե����ޥåȤϡ�������ѥ�����ˤ��ä��������ǥѥ�������dz���䥹���������Ԥ��Τ����̤Ǥ�����������ˡ�����礭�ʲ����٤Ƽ����ޤʤ���Фʤ�ʤ��Τǻ��֤������ä����̿��֤䥳��ԥ塼������٤�������ޤ���
- �����Զ����θ���Ʋ������ʬ�����Ƴ�Ǽ������ͳ�ˤ��Ĺ�®���ɤ߽Ф����Ȥ��Ǥ���Τ�Flashpix�Ǥ���
- �ڥޥ����롼�����ǽ��
- Flashpix�ϡ����켫�Τ�ʪ��Ū�ʥե�����ե����ޥåȤ�������Ƥ���櫓�ǤϤʤ�����Ǽ����ǡ�������ˡ�ʤɤΥ롼������������ƥ�����Ǥ��ꡢ����Ū�ˤϤ��ޤ��ޤ�ʪ���ե����ޥåȤ˱��ѤǤ���褦�ˤʤäƤ��ޤ���
- �פ����JPEG�����Ǥ�TIFF�����Ǥ�Flashpix�ˤǤ���Ȥ������ȤǤ���
- Flashpix���礭����ħ�ϡ������� 64x64�ԥ������1�ĤΥ֥��å��Ȥ��ƴ����������Υ֥��å�ñ�̤�ɽ��������ʤɤΥ����������Ԥ��Ƥ��뤳�ȤǤ���
- ���äơ�������Ϥβ�����ɽ�����������������ˡ�ǽ�ϤΤʤ�����ԥ塼����ץ�Ǥ�ɬ�װʾ�ˤ�����������֤�û�̤����뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
- Flashpix�Ǥϡ�������ɽ����Ǿ�1/64�ˤ��뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
- ��������������ϡ�PhotoCD�Ȼ��Ƥ��ޤ���
- ��������PhotoCD�����ǿ��䥢���ڥ����椬BASE�Ȥ������ޤ�Ǹ��ꤵ��Ƥ���Τ��Ф���Flashpix�ϼ�ͳ�����֤��Ȥ��Ǥ��ޤ���
- ����ˤ��μ�ͳ�ʲ������������Ȥˤ��ơ����դ줾��1/2��1/4��1/8��4�ʳ��˲����������٤�������ƿ�®�˲���ɽ������Ϥ��Ǥ���褦�ˤʤäƤ��ޤ���
- �㤤CPU ǽ�Ϥ���ĥ���ԥ塼���Dz���������Ԥ��Ȥ��ϡ�������ְ����ƽ�����Ԥ����ץ��Ȥ���Ȥ��˻��֤��ƹ⤤�����Ϥǥץ��Ƚ��Ϥ��뤳�Ȥ�Ǥ��ޤ���
- �����֥ޥ����롼����� = MultiResolution��ǽ�ȸƤ�Ǥ��ޤ���
- ��
- �ڥ������ǽ��
- Flashpix�Τ⤦��Ĥ��礭����ħ�ϡ��֥������ = Tiling��ǽ�Ǥ���
- ��ۤɡ�Flashpix��64x64�ԥ���������Υ֥��å�ñ�̤Dz���������������Ƥ���ȸ����ޤ����������Τ��ޤ�����Ѥ��ơ����Τβ�������ɬ�פ���ʬ��������Ф��ʤ��줬���Τ���Ф��ʤ��Τǹ�®�˼��Ф���˵�ǽ������ޤ���
- �������Ȥ����ޤ���
- ���äơ������ǡ����Ϻǽ�����Τ�����ɤ��Ƥ���ɬ�פϤ���ޤ���
- �Ǿ��¤Υ��ȥ쥹�Ǥ��������ݴɤ���Ƥ����ǥ�����������ɤ��ʤ��顢�礭�ʲ����ǡ�����������뤳�Ȥ��Ǥ���ΤǤ���
- ���Υ�����ȥޥ����롼�������Ȥ߹�碌�ϥ����ߥǤ�ͭ���˵�ǽ���ޤ���
- ��������Flashpix����ħ�ϡ�������ʪ�ʤɤε��Ťʲ��λ�ե�������������ٲ����Ȥ����ݴɤ���ɬ�פ˱����ƴ�˾�����礭���Ǻ���ɽ��������Ū��ͭ���Ǥ���
- �㤨�п�ۤ˽�¢���Ƥ��볨��ʪ���ʸ���Flashpix��������¸���ơ����Ѥ����������Ԥ˥ͥåȥ�����̤���Viewer�Ǹ��Ƥ�餦�Ȥ�����ˡ�Ǥ���
- �������ϡ�1GB�ʥ����Х��ȡˤˤ�ã���뤳�Ȥ�����ޤ���
- Flashpix�Ǥϡ��ְ����������Τ���ɽ�������Ȥ������ä��ꡢ��������ʬ�����γ�����������뤳�Ȥ��Ǥ���Τǡ�ɬ����¤Υǡ����̤Dz����������Ǥ�ɽ�����ԡ��ɤ����åפ��ޤ���
- Flashpix����Ѥ���ˤϥ饤����ɬ�פǤ��ꡢFlashpix������ˤ����ѤΥӥ奢��ɬ�פʤ��ᡢFlashpix�Ȥ���̾����������˹����Ȥ��Ƥ���Ȥ������ȤϤʤ��褦�Ǥ���
- �������̥ե����롡-�������ˤ��ե��������̤ΰ㤤
- ���Ȥ��Ƥ�������ե�����ϡ����̤�����Ū�ˤʤäƤ��ޤ���
- ���̤�Ԥ����֤���Ū�ϡ������ե��������̤������뤳�ȤǤ���
- ���꤬����Ǥ��ä������ѥ��������ǽ���夬��ʤ��ä����塢����˥����ͥåȤ��̿�®�٤��夬��ʤ��ä�����ˤϤȤƤ⤢�꤬������ǽ�Ǥ�����
- �����������̤���ߤˤ�����ȴ��Ԥ�ź���ʤ���̤Ȥʤ�ޤ���
- �㤨�С�����Ψ�ι⤤�������¸���줿JPEG�����ϡ����줷�������Ȥʤ�ޤ���
- �������¬���ʤȤ��ư������ˤϡ����̥ե��������ħ�ȥե��������̤�������ʬ�����Ƥ������Ȥ�ɬ�פ��ȹͤ��ޤ���
- ���˼��������μ̿��ϡ�����BMP�ʥӥåȥޥåס˥ե�����ǡ�����JPEG��10��ޤǰ��̤��������ե�����Ǥ���
- ����ϰ��������ǡ�JPEG�������Ƥ�����Ω���ޤ���
- BMP�ե�����ϡ��̤Ǥ�������ǿ������Τޤޥե��������̤Ȥʤ�ޤ���
- 512x417����@8�ӥå�ǻ�٤Ǥϡ��ʲ��Υե��������̤Ȥʤ�ޤ���
- 512 ���� x 417 ���� = 213.5k ����/����������������Rec-38��
- �ڼ̿������ΰ��̡�
- ���˼�����JPEG�����Ǥϡ�10��˰��̤��Ƥޤ��Τǥե��������̤�1/37��5.7k�Х��ȤǤ���
- ξ�Ԥ���٤�ȡ��ե��������̤����ʤ꾮�����ʤä�ʬ����������ʤäƤ���Τ�����Ǥ��ޤ���
- Ʊ��������PNG�ե��������ȡ�155.7k�Х��ȤȤʤ�ޤ�������ϡ�BMP�ե������73�����٤������̤Ǥ��ޤ���
- ���Τ��Ȥ���PNG�ʲĵհ��̥ե�����ˤǤϼ̿��Τ褦�ʺ٤����������Ф��ƤϤ��ޤ����դǤϤʤ����Ȥ��狼��ޤ���
- �� �ڥ���ե��å������� ���β��˼���������ץ�����ϡ���ȹ����Ϥä��ꤷ��ñ��ʥѥ���������Ǥ���
- ���β����ǥե��������̤ޤ��ȡ�BMP�ե�����ϡ��̾�μ̿�������Ʊ��215.0kB�ȤʤꡢJPEG10%���̥ե������7.4kB��1/29�ΰ��̤ˤʤäƤ��ޤ���
- ���ܤ��٤��ϡ�PNG�ե�����ǡ�2.7kB�ȶð�Ū�ʲĵհ��̤ˤʤ�ޤ���
- PNG�ϡ����˥��ʸ���ʤɤΥѥ��������Τʤ�Τ��Ф����̲������Ѥ��ʤ��ʼ��ǹ⤤���̤��Ǥ��뤳�Ȥ��狼��ޤ���
- JPEG�ϡ�ʸ���䥰��ե��å������ΰ��̤Ǥϲ褬�����ʤ�ޤ��ʥ⥹�����ȥΥ������Ф�ˡ�
- �� �ڿ�����ʲ����� �Ǹ�˿�����ʲ����ˤĤ��ƹͻ����ޤ���������ʲ����Ǥ�BMP�ե�����ϲ��ǿ�ʬ�����Υե��������̡�215.0kB�ˤȤʤ�ޤ���
- JPEG�ϡ�8x8���ǤDz����Υѥ�����Ƥ����ޤ��Τǡ�1/(8x8) = 1/64�ʲ��ˤϤʤ�ޤ���
- ��������PNG�Ǥ�1.9kB�Ȥʤ�1/119�ΰ��̤ˤʤ�ޤ����ѥ�����ñ�㲽������Τۤ�PNG�ե�����ΰ��Ϥ�ȯ���Ǥ���ȸ�����Ǥ��礦��
����
- 512x417����8�ӥåȤ�����̿������Υե��������̤���ӡ� ������BMP�ե����롧215.0kB��-���庸�β����� ������TIFF�ե����롧215.0kB��-�����̤�Ԥ�ʤ�TIFF�ե������BMP��Ʊ���ե��������̤���ġ� ������PNG�ե����롧155.7kB��-���ĵհ��̥ե�����ʤΤǺ٤����̿������ΰ���Ψ�Ϥ褯�ʤ��� ������JPEG90%���̥ե����롧��51.9kB��-���ե��������̤�1/4���٤ˤʤä��������½���ʤ��� ������JPEG50%���̥ե����롧��18.6kB��-���ե��������̤�1/11���٤ˤʤä�������ϼ㴳�Ӥ�Ƥ��롣 ������JPEG10%���̥ե����롧��5.7kB��-���屦�β������ե��������̤�1/37��
- ������JPEG 1%���̥ե����롧��4.0kB��-���ե���������1/53������Ϥ��ʤ�Ӥ�롣
- 512x417����8�ӥåȤ�����ѥ���������Υե��������̤���ӡ� ������BMP�ե����롧�������� 215.0kB��-���庸�β����� ������PNG���̥ե����롧������ 2.7kB��-��1/79�ΰ��̤Ȥʤ롣�����½���Ϥʤ��� ������JPEG90%���̥ե����롧 16.0kB��-���ե��������̤�1/13���٤ˤʤä��������½���ʤ��� ������JPEG10%���̥ե����롧��7.4kB��-���ե��������̤�1/29���٤ˤʤä��������½���ʤ��� ������JPEG 1%���̥ե����롧�� 5.8kB��-���屦�β������ե���������1/36������ϹӤ���ʥ⥹�����ȥΥ������� ��
- �ѥ�������礭�ʲ����ϡ������ΰ���Ψ������礭�ʥե����밵�̤��Ǥ��롣������ͳ�ϡ�JPEG��8x8�ΰ��̥��르�ꥺ�ब���ѥ�����ΤϤä��ꤷ�������Ǥ�1/64�ˤ��뤳�Ȥ��Ǥ��뤿�ᡣ�ѥ�������Ƥ�������PNG������Ū��ͭ���ǹ⤤����Ψ�������롣
- 512��417����8�ӥåȤ� �����Υե������������ ����BMP�ե����롧 215.0kB��-�����β����� ����PNG���̥ե����롧 1.9kB��-��1/119���̡� ����JPEG 90%���̥ե����롧 3.6kB��-��1/59�� ����JPEG 50%���̥ե����롧 3.6kB��-��1/59�� �� ñ�����쿧�β����Ǥ⡢BMP�ե�����Ǥϲ���ʬ�����̤�Ϳ�����롣PNG�ե�����Ǥϡ�1/119�ΰ��̤�Ԥ���JPEG��갵��Ψ���ɤ�������ϡ�JPEG�Ȥϰ㤦���̥��르�ꥺ���ȤäƤ��뤿�ᡣJPEG�ϡ�8x8���Ǥ��ĤΥ֥��å��Ȥ��Ƥ��뤿�ᡢ1/64���٤��³��Ȥʤ롣ñ��ʲ����Ǥ����PNG����������Ψ���褤��
- ��
- ��¸�ե����ޥå�
- �̾�β���
- ����Υѥ��������
- ������ʲ���
- 512x417���� 8�ӥåȡ�256��Ĵ��
- ���

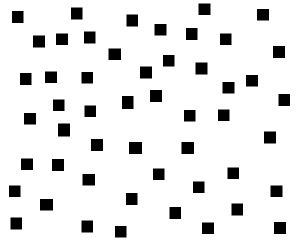

- BMP
- 215kB
- 215kB
- 215kB
- TIFF
- 215kB
- 215kB
- 215kB
- PNG
- 155.7��B
- 2.7kB
- 1.9kB
- JPEG��90%
- 51.9kB
- 16kB
- 3.6kB
- JPEG��10%
- 5.7kB
- 7.4kB
- 3.6kB
- JPEG��1%
- 4.0kB
- 5.8kB
- 3.6kB
�����ѥ�����ΰ㤤�ˤ��ե��������̤ΰ㤤�ΤޤȤ��ɽ��
- ���ɽ���顢JPEG�ϼ̿������˰��Ϥ�ȯ������ �ѥ�����ΤϤä��ꤷ�������Ǥ�PNG�����̤Τ��뤳�Ȥ�����Ǥ��ޤ�
- ��
- ��
- ��
- ��
- ����DNG��Digital Negative��������2018.11.07��
- DNG�ϡ��ƹ�Adobe�Ҥ�2004ǯ�˳�ȯ���������ե����ޥåȤǤ���
- �ǥ����륫���β������������8�ӥå�ǻ�١ʥ��顼������8�ӥå� x 3 = 24�ӥå�ǻ�١ˤ���10�ӥå�ǻ�١�12�ӥå�ǻ�٤���Ĥ�Τ������ơ��ƥ���������ȼ��Υե��������Ѥ��Ф������Ȥ��顢�������ե�����ե����ޥåȡ� �ե�����ˤ����줹����Ū�dz�ȯ����ޤ�����
- ̾�����֥ͥ��ƥ��֡פȤ��Ƥ���Τϡ��ե����Υͥ�����������Ƥ���Ȼפ��ޤ���
- DNG�ϡ�Adobe�Ҥ��꤬��������������եȥ�������Photoshop�פ��Lightroom�פؤΰܿ�����褯���ơ������Υ��եȤǤβ���������Ԥ��䤹�����Ƥ��ޤ���
- DNG�ϡ�TIFF/EP��TIFF�ե������2001ǯ���ɲ����ꤷ����Ρˤ�١����ˤ��Ƥ��ޤ���
- TIFF��Tag Image File Format�ˤϡ�1986ǯ�ˤǤ����Ť��ե����ޥåȤ��̤Ǥ���
- Aldus�Ҥ���ȯ��Adobe�Ҥ�Aldus�Ҥ������������TIFF��Adobe�Ҥν�ͭʪ�ȤʤäƤ��ޤ�����
- TIFF�ϡ�¾�β����ե�����ե����ޥåȤ����8�ӥåȡʥ��顼8�ӥå� x 3 =24�ӥåȡˤǤ��ä��Τ��Ф��ơ����16�ӥåȡ�2�Х��ȡˡ����顼48�ӥåȤ�Ϳ�����ÿ�����äƤ������ᡢAdobe�Ҥ�����TIFF�ե����ޥåȤ����Ϥ����ȹͤ��ޤ���
- TIFF/EP��Tag Image File Format / Electric Photography�ˤϡ����ꥸ�ʥ��TIFF�˥ǥ����륫������ڤ��Ƥ���Exif������Ȥ߹�碌����Τǡ��ǥ����륫���β����ե����ޥåȤ��ò�������ΤȤ���2001ǯ�����ꤵ��ޤ�����
- DNG�ϡ�TIFF/EP��˿ʲ������ƥե�����ե����ޥåȤ��ò�������8�ӥåȲ�����JPEG��PNG�ʤɡˤؤ��ڤ�Ф����ưפˤ�����տޤ�����ޤ���
- ����DNG�����ե�����ϡ��⾰����ǰ�Ǻ���ƤϤ����ΤΡ����꤫��14ǯ�����äƤ⤳�����Ѥ��Ƥ��륫��������ϥ����ޡ��饤�����ڥå����ʤɿ��Ҥǡ����Υ���������ϰ����Ȥ��Ƽ��ҤΥե��������Ѥ�³���Ƥ��ޤ���
- ��Photoshop�פ��Lightroom�פؤΰܿ�����ǧ�����Ф��β����ե�������礭���������Ƥ�����ΤȻפ��ޤ���
- ��
- ����HEIF��High Efficiency Image File Format��������2018.11.07��
- HEIF�ϡ�2017ǯ�����åץ�Ҥ����Ҥ�OS��macOS High Sierra�ڤ�iOS11�ˤǥ��ݡ��Ȥ�Ϥ�����ե�����ե����ޥåȤǤ���
- JPEG����������夵����Ʊ���ʾ���ʼ��ǥե��������̤�1/2���ޤ������ΤǤ���
- ���ޥۤ���Ѥ�������Ǽ̿�/ư�褬���������Ȥˤ�äƥե�������¸���̤��������뤳�Ȥˤʤꡢ��������ޤ�ޤ�����
- ���β����ե�����ϡ�����ư��ե������꤬����MPEG���ؤ�2013ǯ������ꤷ2015ǯ�˳�ȯ���ޤ�����
- H.265�Ȥ������������ʤΥ����ǥå�����Ѥ��Ƥ��ޤ���
- HEIF�μºݤα��Ѥϥ��åץ�Ҥ����ƤǤ��ꡢ�ޥ��������եȼҤϤޤ����ݡ��Ȥ���Ƥ��ʤ��Τǡ�Windows�Ǥϥե�������䥵���ɥѡ��ƥ��ˤ������������ץꥱ������եȥ����������Ѥ���ɬ�פ�����ޤ���
- HEIF���Ż߲����Ǥ�������Ȥ�Ȥ�H.265����Ѥ���ư��ե������HEVC��High Efficiency Video Codec���Ȥ������ʤ����졢������Ȥ��Ż߲�Υե�����ե����ޥåȤ����ʲ�����ޤ�����
- ���Υե����ޥåȤ�����ɸ��ˤʤäƤ������ɤ����Ϥޤ��狼��ޤ���
- ���ѿ���¿��iPhone��ɸ����������줿�Τǡ�ǧ�ΤϤ���Ƥ����Τ������Ȼפ��ޤ���
- ������iPhone�ϡ����ޤͤ����Ѥ���Ƥ���JPEG��º�Ť��ơ������¦������ˤ�äơ�HEIF �ե����ޥåȤǤϤʤ�JPEG����¸��������ˤ����ꡢ�֥饦����JPEG�ե�����˴�ñ���Ѵ�����¸�Ǥ���褦�ˤ��Ƥ��ޤ���
- ��
- ��
- �����ǥ����뵭Ͽ��ư������������2007.4.15�ɵ��ˡ�2010.05.19�ɵ��� �� ���ι�Ǥϡ�ư�����ˤĤ��ƿ���ޤ��� �� ���˥�ư��θ����������Ǥ���褦�ˡ��Ż߲����ּ����¤٤ƺ��������ư�����������ޤ���
- �ѥ������ư�����Ϥ���ȯ�ۤǺ���ޤ�����
- ư�������Τ�Τϡ��ѥ�����ȯã���������餢��ޤ�����
- �ƥ�������ȱDz�Ǥ���
- ����黰�Ԥϡ��ȼ��ο�Ÿ�ʤ��餷����ߤ��˱ƶ�����äƺ����˻�äƤ��ޤ�����ư���������Ū��ή������ȡˡ�
- �Dz��ƥ�Ӥ����ʥ���ư��Ǥ��ä��Τ��Ф����ѥ������ư��ϥǥ�����������饹�����Ȥ��ޤ�����
- ������������ư���������������NTSC��PAL���ʡˤ��龯�ʤ���̱ƶ�������Ƥ��ޤ���
- �ѥ������ȯ����IBM�Ҥ�MSDOS����ԥ塼����Ϳ����ɸ����̤ϡ�NTSC����������ϤȤ���640x480���Ǥ���VGA��Video Graphics Array�˵��ʤǤ�����
- ��
- ����ԥ塼����ư�����ϡ��Ż߲��Ϣ³���ƺ������뤳�Ȥ����ȯ���ޤ�����
- ���������˲���������ƥƥ�������Τ褦�ʻ��ȤߤȤ��ޤ�����
- ����ԥ塼����ư�����ϡ��ƥ�����������������������뤳�Ȥ��Ǥ����Τǡ�����������ư�����ե�����ե����ޥåȤ��Ǥ��ޤ�����
- ������������Υѥ��������ǽ���褯�ʤ��ä��Τǡ��ƥ��������٥�β���Ȳ���ͳ���ߤ���뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���Ǥ�����
- �ǥ�����������������Ѥ����⤷��NTSC������ɤŨ����褦�ˤʤ�ȡ��ǥ�����������ƥ�����������ĥ��褦�ʷ��Ȥʤ�ޤ�����
- ξ�Ԥϸߤ���ʸ������ʤ��顢�ѥ�����ǰ�ä�ư�����ե�����ȡ��ƥ�Ӥ��ݤ�줿�ƥ�ӱ���������˱Dz�Ǻ��Ѥ��Ƥ����Dz�ե����ޥåȤ������Ȥ�褦�ˤ��ơ��ǥ�����ư�����ե����ޥåȤ�������ƹԤ��ޤ�����
- ��AVI�ۡ�Audio Video Interleaved Format�ˡʤ����֤�����������2009.05.19�ɵ��ˡ�2022.04.19�ɵ���
- �桹��¬ʬ��ǺǤ��ɤ��Ȥ��Ƥ���ư��ե�����ե����ޥåȤ�AVI��1992 ǯ��ȯ��1997ǯ��ȯ��λ�ˤǤ���
- �Ǥ�Ť����ʤǤ��뤳�Υե����ޥåȤ�30ǯ�������ǻȤ��Ƥ���Τ϶ä��Ǥ���
- ������25ǯ��Ⳬȯ�������ݡ��Ȥ���ߤ��Ƥ��ޤä��ˤ⤫����餺�Ǥ���
- AVI�ե�����ϡ�Audio Video Interleaved Format��ά�Ǥ���
- �ޥ��������եȼҤ�1992ǯ��PC�Ѥ˳�ȯ�����ࡼ�ӡ��ե����ޥåȤǤ���
- AVI�ϡ�Windowsɸ���DIB��Device Independent Bitmap = BMP�˲�����Ϣ³�����ե����륷�����֤ˡ�WAVE�ǡ����ʲ����ǡ����ˡ�WAV�ե����ޥåȡˤ߹�����ե����ޥåȤȤ��ƽ�ȯ���ޤ�����
- ����2GB����������2022.04.19�ɵ���
- Windws95�dz�ȯ���줿Microsoft Internet Explorer�ˤϡ�AVI�ե�����ե����ޥåȤ�����饤��ࡼ�ӡ��Ȥ������Ѥ���Ƥ��ޤ����ʱ��ޡˡ�
- AVI�ե�����ϡ�WAVE�����ǡ����ȹ��Τ����Ƥ���ط���RIFF��Resource Interchange File Format�ˤȤ�������ʪ�����Ѥ��Ƥ��ޤ���
- ����RIFF������ʪ����32�ӥåȤ�ʸ�������������뤿�ᡢ�ե�����Υ�������32�ӥåȡ�4,294,967,296 = 4G�Х��ȡˤޤǤȤʤ�ޤ���
- �ޤ����ǡ����̤ˤ����¤��ä���졢16�ӥåȤ�AVI��1G�Х��ȤΥե����롢32�ӥåȤ�AVI��2G�Х��Ȥ����¤Ȥʤ�ޤ���
- �ե�����̤���2GB�ʲ��ˤ��Ƥ⡢AVI�ǤϺ��������̤�Ʊ���Υ����ΰ����ݤ���褦�ǡ����ΤȤ���2GB���̤�Ķ����ȥ��顼�Ȥʤ�������Ǥ��ʤ��ʤäƤ��ޤ��ޤ���
- ¿���Υޥ����ǥ����ǡ����ˤ����ơ�1��B��2GB�Υǡ����Ͻ�ʬ�����̤Ǥ��������ȥࡼ�ӡ��˴ؤ��Ƥϡ����θ¤�ǤϤ���ޤ���
- �ӥǥ��¤Υ�����ƥ��ǰ������Ȥ���ȡ����äȤ����֤˥�����ɤ��ͤ������äƤ��ޤ��ޤ���
- 2000ǯ�ʹߤι�®�٥����Ǥϡ�������2GB����4GB�Υ���ʻ��ˤ�16GB��32GB�ˤ���ܤ��Ƥ��ơ����Ƥ���������ѥ������ž�����Ƥ��Τޤ����ե�����Ȥ�����¸���褦�Ȥ��������ˤ���ޤ���
- 2022ǯ�����Ǥϡ������̤Υǡ�����RAW�ʳƥ�����ȼ��θ������ե�����ˤ���¸���뷹���ˤ���ޤ���
- RAW�ϡ�������ζ��뤹��ӥ��Ǥʤ��Ⱥ����Ǥ��ޤ���
- AVI�ե�����ϡ��ȤƤ�Ť����ʤǷѤ����Ѥ�����¸³���Ƥ��뵬�ʤǤ����顢4GB�Τ褦������ʥǡ�����AVI�ե�����������Ȥ���Ȥ��������ʾ㳲�������ޤ���
- ����ˡ���ȯ���Υޥ��������եȼҤϡ�1997ǯ��13ǯ�ʾ�����ˤ˥��ݡ��Ȥ���ߤ��Ƥ��ޤ��ޤ�����
- AVI�Ǥϡ��ɤ��ˤ��ĥ�����ʤ��Ȥ������ȤΤ褦�Ǥ���
- �ޥ��������եȤϡ�1996ǯ��AVI���Ѥ��ե����ޥåȤȤ���ASF��Advanced Streaming Format�ˤ��о줵������ڤ�Ϥ���ޤ�����˧������̤ˤʤ�ޤ���Ǥ�����
- �����ǡ��ޥ��������եȤϡ�WMV��Windows Media Video File�˥ե������2000ǯ���о줵����WindowsOS��ɸ��ư��ӥ奢�Ǥ���MediaPlayer��ɸ��ե����ޥåȤˤ��ޤ�����
- WMV�ݡ��Ȥ��븽�ߤ�MediaPlayer�Ǥϡ������������AVI�ե�������ɤ߹��ळ�ȤϤǤ��ޤ���
- �������ʤ��顢OS��AVI���Τ�Τε��ʤ��鳰�줿2GB�ʾ�����̤����AVI�ե�������Ф��Ƥϡ��桼��������Ǥ�ˤ����ƽ������ʤ���Фʤ�ʤ�����Ȥ��ƻĤäƤ��ޤ���
- �����ϸ��äƤ⡢��¬ʬ��Ǥ�ư������Ǥ�2020ǯ�����Ǥ�AVI�ϰ���Ū�˼�ή�Ǥ���
- ¿���η�¬��ư��������եȤ������ߤ�ʤ�AVI�ե�������ե�����ե����ޥåȤȤ���MPEG��WMV�ե�����ˤ��б����Ƥ��ʤ��Τ��¾�Ǥ���
- DVD�ʤɤαDz褬MPEG2�ε��ʤ�ư��������¸�������Ƥ��뤿�ᡢAVI���ΤϷ�¬����Ū�Ȥ���ʬ��˸¤���褦�ˤʤäƤ��ޤ�����
- �ʤ���AVI������Ȥ��Ƥ���Τ��ȸ����ȡ�AVI�ϰ������β�����ʬΥ������¸�Ǥ��뤫��Ǥ���
- ��������AVI�Υ����ǥå��ˤϡ�MPEG�䡢H.264�ʤɤλ��ְ���������ФƤ����Τǡʤ�������������Ψ���⤯�Ʋ�����ɤ��ˡ��������������ǥå�����ä�AVI���¬�˻Ȥ����ˤϡ�����ξQ�Ǥ����AVI�ϰ�����礬��Ω���������פȤ����ͤ����Ǥ��ʤ��ʤꡢ����������Ǥ�����ˤʤ뤳�Ȥ�����ޤ���
- ��AVI�ե�����ΰ��̡�-�����̥����ǥå���
�����ǥå���Codec�Ƚ�Compression & Decompression ��ά�Ǥ���
- ���̤���Ĵ�Ȥ�����̣�Ǥ���
- AVI�Ǥϡ��ǡ����ΰ��̥ᥫ�˥��ब�����ƥ��OS�ˤ��Τ�Τȴط��ʤ���Ω���Ƥ���Τǡ����̥����ǥå��ɥ饤�Ф����ȡ��뤵��Ƥ���С����������ʥ����פΰ��̤���ǽ�Ǥ���
- �դˡ�Ŭ�ڤʥɥ饤�Ф����ȡ��뤵��Ƥ��ʤ��Ȱ��̤��줿�ǡ������ɤ߽Ф������������Ƹ�����ޤ���
- ���Ѥ��Ƥ��밵�̥����ǥå��˴ؤ������ϡ��ӥǥ����ȥ��Υإå���4ʸ����ID�Τ������ǵ�Ͽ���졢�������˻��ꤵ�줿�ɥ饤�Ф��ɤ߽Ф��Ʊ�����Ƹ�����褦�ˤʤäƤ��ޤ���
- �����ǥå���ͭ̾�ʤ�ΤǤϡ�����ƥ뤬��ȯ����Indeo��1992ǯ���ˡ�SuperMac�Ҥ���ȯ����Cinepak��1992ǯ���ˡ��ޥ��������եȼҤ���ȯ����Microsoft Video1��1992ǯ���ˡ�MotionJPEG���̡�MPEG���̡�H.264���̤ʤɤ�����ޤ���
- ����ɽ�ˡ��Ƽ�Υ����ǥå�����¸����AVI�ե�����Ȥ������̤���Ӥ��ޤ�����
- ɽ�ΰ��ֺ���TIFF��Ϣ�֥ե������21��ι�פǤ���
- ��AVI��TIFF�ե�������������Τ�ΤǤ�����ե��������̤�Ʊ���Ǥ���
- ���ֱ���QuickTime��AVI�ե�����ǤϤ���ޤ���2010ǯ�����ǰ��ְ��̤��褯�Ʋ�����褤�Τǻ��ͤޤǤ���Ӥ�����ޤ�����
- AVI�Ϻ���Ť������פΥե����ޥåȤǡ�����ƥʤȤ�����̾����Ĥۤɡ��Ĥޤꡢñ�ʤ�Ȣ�Ȥ����ۤɤˤʤäƤ��ޤ��ޤ�����
- ����Ȣ�ˤ��������ʥ����ǥå���Codec�ˤ�ųݤ���AVI�ե�����Ȥ��Ƥ��ޤ���
- �Ǥ����顢�ҤȤ�����AVI�ȸ��äƤ�ɤΥ����ǥå��dz�Ǽ�������ä�����İ����Ƥ���ɬ�פ�����ޤ���
- ��2GB�ʾ�Υե��������AVI2.0��
- �ޥ��������եȼҤ����ݡ��Ȥ���ߤ���AVI�ե����ޥåȤ�Ȣ������褫���ơ����ߤǤ�Ȥ���褦�ˤ������ʤ�AVI2.0�Ǥ���
- ���ε��ʤˤϡ��ޥ��������եȼҼ��Τϴ�Ϳ���Ƥ��ޤ���
- ����ϡ�1996ǯ�˲����ܡ��ɥ����Matrox�Ҥ��濴�ˤʤäơ�OpenDML��Open Digital Media Language�ˤȤ������Ѥ��ꡢ���ε��Ѥˤ���OpenDML AVI��AVI2.0�ˤ���ޤ�����
- ����AVI�Ǥϡ�2GB�ʾ�Υե����뤬������褦�ˤʤꡢ�ޤ���MotionJPEGư���AVI�ե����ޥåȤǺ����Ǥ���褦�ˤ��ޤ�����
- Sony��VAIO�ϡ������ƥ�ˡ�DVgate�פȸƤФ��ư���Խ����եȤ�Ʊ������Ƥ��ơ������2GB��ۤ���AVI�ե�������뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
- �ޤ���ư��������ץ��㡼�ܡ��ɤäƤ��륫�Ρ��ץ��Ҥ�AVI2.0����¸�Ǥ���ư������¸���եȥ��������äƤ��ޤ���
- Adobe�Ҥ�ư���Խ����եȥ�������Premier�פǤϡ�ver.6.0����OpenDML AVI���б����Ƥ��ޤ���
- �����δĶ��Τ���ѥ�����Ǥ�2GB�ʾ��AVI�ե������������뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ�����¿���Υѥ�����ˤϤ��Τ褦�ʴĶ���������ʤ���礬¿���Τǡ�������������AVI�ե���������ۤ���Ȥ��ˤϡ����ä���꤬�����Ǥ��뤳�Ȥ��ǧ����ɬ�פ�����ޤ���
- �ޤ���2GB��ۤ���AVI�ե���������ˤĤ��Ƥϡ����ȷ�AVI��Reference AVI�ˤȤ�����Τ�¸�ߤ���ʣ����AVI�ե�������ڤ��ؤ��ʤ��������³���ơ���������2GB�ʾ���ɤ�ۤ�����ˡ���äƤ����Τ⤢��ޤ���
- ������ˡ����AVI�⡢������ˤ��μ��ư��ե����뤬�����Ǥ��뤳�Ȥ��ǧ�����ۤ�ɬ�פ�����ޤ���
- 2GB�ʾ�Υե���������ư�����ξ��ˤϡ�JPEG�ʤɤ�1��ñ�̤��Ż߲��Ϣ�֤ǰ�ĤΥե����������¸������ˡ���μ¤ȹͤ��ޤ���
- AVI�ǰ�ĤΥե�����ˤޤȤ��Τϡ��ǡ������������Ƥ��ޤ鷺��������¦�̤�����ޤ�������¬�Ȥ�����������ϡ���İ�Ĥ��Ż߲�Dz���������Ȥ����Τ����ܤʤΤǡ��Ż߲��Ϣ�֥ե����������ޤ���
- �ѥ�ݥ���Ȥ�ư������Ž���դ�����ϡ����Υե����뤫�顢ɬ�פ��ϰϤ�ȴ����ꡢɬ��ʬ�ʲ��ǥ��������Ѵ�����MPEG2�ʤɤΰ��̥ե��������¸������ˡ�����ޡ��Ȥ��ȹͤ��ޤ���
- ��64bit��AVI��32bit��AVI������2020.03.01�ɵ���
- AVI�ϡ�1992ǯ�˺��ꤵ�줿ư��ե����ޥåȤ�1997ǯ�˥��ݡ��Ȥ��ޤ�����
- ���äơ�AVI��32bit��CPU�dz�ȯ���줿��ΤǤϤʤ������ǥå���ۤȤ�ɤ�32bit�Ķ��dz�ȯ���줿���ᡢ64bit�Ķ��Ǥϻ��Ѥ��뤳�Ȥ�������뤳�Ȥ�Ǥ��ޤ���
- ��¬ʬ��Ǥϡ��Ť���Indeo�����ǥå����Ȥ�졢DivX��Xvid��VCM9��Cinepak��Ȥ��Ƥ��ޤ�����
- �����ϡ�32bit �б��Υ����ǥå�����
- 64bit�Ķ���AVI��������Τϡ��̡�uncomp�ˤ�microsoft��cinepak��3�������٤Ǥ���
- H264�����ǥå��ϡ����ߤΤȤ����Ǥⰵ�̤��⤯���IJ�����褤��ΤǤ���
- ����ɡ����Υ����ǥå���Windows7/Vista/8/10��ɸ��ǥХ�ɥ뤵��Ƥ��ʤ����ᡢ���ӥ��ȡ��뤹��ɬ�פ�����ޤ���
- ����ϡ���x264vfw download / SourceForge.net�פ������������ɤ��ޤ���
- ��WMV�ۡ�Windows Media Video�����֤�夨��֤�����2000.06�ˡ�2020.03.01�ɵ���
- �ޥ��������եȼҤ���AVI�ե�����ڤ�ASF�ե���������뵬�ʤȤ���2000ǯ��ȯɽ�����ǥ�����ӥǥ��ο������ץ�åȥե�����Ǥ���
- 2020ǯ�λ����ǤϤ��Υե����ޥåȤǤ�ư��Ϥ��ޤ�Ȥ��Ƥ��ޤ���
- ���ޥۡ�2009ǯ iPhone�ˤǤ�ư�����MP4( = MPEG-4)���Ȥ��ϤᡢYouTube�ʤɤΥ����ͥåȾ��ư��Ǥ�MP4�������Ȥ��Ƥ��뤳�Ȥ��顢���Υե�����ե����ޥåȤϻȤ��뤳�ȤϤʤ��ʤ�ޤ�����
- ���äơ�2010ǯ��ʹߤ�ư��ϤۤȤ�ɻȤ��Ƥ��ޤ���
- AVI�ե�����θ�ѥե�����Ȥ����о줷��WMV�ϡ�AVI����ٹ⤤����Ψ�������̲����ޤ��Ƥ��ޤ���
- ���Υե�����ϡ����ְ��̤Ƥ���Τ�AVI���ꥸ�ʥ��1��1�����¸��������ȤϤʤäƤ��ޤ���
- MPEG���̵��Ѥ���Ѥ��Ƥ��ޤ���
- MPEG���̤Ȥ��äƤ�ޥ��������եȼҤ��ȼ��˼��ä���MS-MPEG4�ʤΤǡ��ߴ���������ˤʤä����Ȥ⤢��ޤ�����
- ������ˤ����¬ʬ��ˤϻȤ��Ť餤�ե����ޥåȤǤ�����
- WMV�ե�����ϡ���ȯ����ϥ����ͥåȾ�ǽ����˿�Ʃ���Ƥ��ޤ�����
- Windows Media Player ��ɸ���ư��ե�����Ȥ����硹Ū�˺��Ѥ����а塢����ƶ��Ϥ��礭�ʤ�ΤǤ�����
- AVI�ե����뤬1997ǯ�˥��ݡ�����ߤ줿�塢��¿��������Ф�Windows��ư��Ϥ��Υե����ޥåȤ�����夭�ޤ�����
- ���������桹��¬ʬ��Ǥϰ����Ȥ���AVI�ե���������Ѥ�¿���Τ��¾�Ǥ���
- WMV�ե�����ϡ���¬�Ѥ�ư��������եȥ������Ǥ�ǧ�����ʤ��褦�Ǥ���
- ��¬ʬ��ˤʤ�WMV����Ʃ���ʤ��Τ��Ȥ����ȡ�WMV�κ��Ѥ��Ƥ��밵��������MS-MPEG4←MPEG4�ȼ㴳�㤦�ˤ���¬ʬ��ˤ�����ʤ�������ȹͤ��ޤ���
- ��¬ʬ��Ǥ�ư���1��1����Ω���Ƥ����ۤ�����¬��ط����Թ礬�ɤ��ΤǤ���
- ���ΰ�̣��AVI�ϡ��Ť����ʤʤ��餽�δꤤ�ˤ��ʤä��ե����ޥåȤʤΤǤ���
- ��QuickTime�ۡʤ����ä��������������2010.03.27�ɵ���
- QuickTime�ʤ����ä�������ˤϡ�����ԥ塼��ư��ե������Ϸ��Ū�ʤ�Τǥ��åץ�Ҥ�1991ǯ�˻��ͤ���ޥ����ǥ����ե����ޥåȤǤ���
- 20ǯ����ˤ�����ޤ���
- �ޥ��������եȼҤγ�ȯ����AVI�ϡ�QuickTime����˰ռ�����1ǯ�٤�ǥ������줿��ΤǤ�����
- QuickTime�ν���Τ�Τϡ����̥��르�ꥺ��Ȥ���SuperMac Technology����ȯ����CinePak����ܤ��Ƥ��ޤ�����
- �ѡ����ʥ륳��ԥ塼���Ǻǽ��ư��ä��ե����ޥåȤȤ�����ˤ˻Ĥ��ΤǤ���
- ���Υե����ޥåȤϡ�2010ǯ�ˤ��äƤ�Ƕ���ư��ե����ޥåȤȤ��ƻȤ��³���Ƥ��ޤ���
- QuickTime������Ū�ʥե������ĥ�Ҥϡ�mov���뤤��qt�Ǥ���
- QuickTime�ϡ��ࡼ�ӡ����������������갷�����ޤ����Ū��ñ�˥ࡼ�ӡ����뤳�Ȥ��Ǥ��뤿�ᡢ�����ͥåȤǤ���ɽŪ�ʥե����ޥåȤȤʤ�ޤ�����
- QuickTime�Ϥޤ����ӥǥ��ǥå��������桢�ӥǥ�����ץ��㡢�ǡ������̡���ǥ�����Ʊ�������ʤɤε�ǽ�Ȥ�������Ѥ��뤿��Υġ���ܥå����ʥ����ƥ�ˤ����Ƥ��ޤ���
- ���Υǡ����Υե�������QuickTime�ࡼ�ӡ��ե�����פȤ����ޤ���
- QuickTime��̾����ư���ѥե�����ե����ޥåȤȤ��Ƥ��ޤ�ˤ�ͭ̾�ˤʤäƤ��ޤ��ޤ��������ºݤˤϡ��Ż߲衢�ƥ����ȡ�������ɡ�MIDI�Ȥ��ä����ޤ��ޤʥ�ǥ��������Ȥ��Ǥ��������Υ�ǥ�������ּ����ɤä����椹�뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
- �����å�������ϡ���ȯ���顢AVI�Ȥ褯��Ӥ���ޤ�����
- ���������ޥ����ǥ����Ķ�����ּ��˽��ä�Ʊ������������������Ǥ�AVI�Ȥ���٤�Τˤʤ�ޤ���Ǥ�����
- 1993ǯ�ˤϡ�Windows��Ǻ������뤿��κ�������QuickTime for Windows��ȯɽ���졢Windows��Ǥ������ǽ�Ȥʤ�ޤ�����
- �����1998ǯ�ˤϡ�Java�ǤΡ�QuickTime for Java�פ�ȯɽ����ޤ�����
- QuickTime�ࡼ�ӡ��ե�����Ǥϡ�RIFF��Resource Interchange File Fomat�ˤΥ�������������Τȥ��atom�ˤȤ����ޤ���
- ����������ϡ�32�ӥåȤ�����դ������Ȥ��ư����Τǡ������Ǥ���ΤϺ���2G�Х��ȤޤǤǤ���
- �����AVI�Ǥ�Ʊ���Ǥ����Ƕ�Υե�����ϡ�2GB�ʾ�Υե��������̤С����뤿��˥�����쥹�˥ե�������ɤ߽Ф���ǽ���ɲä��Ƥ��ޤ���
- QuickTime�ϡ������ɤ��Ǥ��������ͥå��̿���ư��ե�����ǡ��Dz���ͽ���ԡ�Trailer�ˤǤ���ǽ�Ϥ���ʤ�ȯ�����Ƥ��ޤ��ʲ����ȡˡ�
- �ϥ��ӥ�����б���QuickTime�β���ϡ����˥��쥤�Dz����⥯�ꥢ�Ǥ���
- �ޤ������ͥåȾ��ư�������������ݤˡ��ǡ����̿��ʥ��ȥ�ߥˤʤ��������Ǥ��ޤ���
- ���ε�ǽ�ϡ�QuickTime��RealPlayer����Ĥ����ǤƤ��ޤ���
- ���åץ�Ҥϡ�2001ǯ��ȯ��Ϥ���iPod�������ˤ�ꡢiTune��ư��ե������QuickTime��ɸ�������������ꡢ�ǥ�����ư���Խ����եȡ�Final Cut Pro�פ�QuickTime��ɸ������Ȥ��Ƥ��ޤ���
- �����å�������ץ졼��ˤ��Dz��ư�襵��ץ�ν̾������� ���ꥸ�ʥ�ϡ�1280��532���ǤΤ�Τǡ�H.264�ǥ���������ѡ�
- �Dz��ѤΥȥ졼��Ǥϡ��ե�ϥ��ӥ�����1080p�ˤǤΥ���ץ����ۤ�ԤäƤ��롣
- ���ߤ�QuickTime��QuickTime7��2005ǯ�ˤϡ�MPEG4�˲ä�H.264/AVC��ɸ��ե����ޥåȤˤ��Ƥ��뤿�ᡢ�ߴ����ι⤤��ΤˤʤäƤ��ޤ���
- 2009ǯ�ˤϡ�MacOS���������ʤä����Ȥˤ���Mac OS ver.10.6 Snow Leopard�ˡ�H.264���̤��®��������QuickTimeX��ȯ�䤷�ޤ�����
- ����ϡ�iPhone���������줿ư��������Ѥ��Ѥ�����Τǡ������Υϥ��ӥ��������ȥ쥹�ʤ��Ѵ�ɽ����������¸�Ǥ��뵡ǽ���äƤ��ޤ���
- �����QuickTime7�Ȥϸߴ������ʤ���MPEG-4/H.264���ò�������ΤǸŤ�ư��ե�������ɤ߽Ф����Ȥ��Ǥ��ޤ���
- QuickTime7��QuickTimeX�϶�¸�Ǥ���Τ�ξ�Ԥ�ѥ�����˥��ȡ��뤷�ƻ��Ѥ��뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
- ���Ū�˸��ޤ��ȡ�QuickTime�ϰʲ��Τ褦�ʿʲ���뤲�Ƥ��ޤ���
- 1991��QuickTime1��������ԥ塼����ư���ǽ�Υӥǥ��ե����롣CD-ROMư�����κ�����Cinepak���̵�����ܡ�
- 1994��QuickTime2�����ե륹�����ӥǥ���Windows�б���MPEG-1�б���
- 1998��QuickTime3�����ꥢ�륿����ɽ���ʥ����ͥå��б��ˡ�Java�б���H.261��H.263�б�
- 1999��QuickTime4�������ȥ�ߥ��ѳ�ĥ��QuickTime TV��Macromedia Flash�б���
- 2001��QuickTime5����Sorenton Video3����ĥDV��Macromedia Flash4�б�
- 2002��QuickTime6����MPEG-4�б���3GPP��3GPP2�б���MPEG-2�����б���JPEG2000�б���iTunes��ɸ��������Apple Lossless codec���ѡ�
- 2005��QuickTime7����H.264�б����ե륹��������档
- 2009��QuickTimeX����iPhone OS��곫ȯ��H.264�ե�������®������
- ������������������������Mac OS ver.10.6��Snow Leopard�ˤ˥Х�ɥ롣
- ����������������������������ƥ�64bitCPU���б��������QuickTime�Ȥ��̥饤��Τ�Ρ�
- �������������������������Ť�Macintosh��Windows�ˤ��б����Ƥ��ʤ���
- ��Motion-JPEG�ۡʤ⡼��������ڤ��ˡ�����2010.06.29�ɵ���
- �Ż߲����ե����ޥåȤǤ���JPEG���®�ǿ�ĥ�������ơ�Ϣ³�������뤳�Ȥ�ư��˸��������������Ǥ���
- M-JPEG�ʤ��ࡦ�������ڤ��ˤȤ�ƤФ�Ƥ��ޤ���
- MPEG-2���ѥ�����ǥ��ȥ쥹�ʤ��Ȥ���褦�ˤʤ�ޤǤ褯�Ȥ��Ƥ�����ˡ�Ǥ���
- �������줿���������ΤǤϤ���ޤ���JPEG�����ʲ�����Ƥ���4ǯ���1996ǯ���˵��ʲ��ؤβ�礬��ȯ�ˤʤꡢ�ʸ塢�ӥǥ��Խ�����������¬����Ǥ褯�Ȥ���褦�ˤʤ�ޤ�����
- MPEG�����̽����˻��֤������ä��ꡢ�����˹���ǽ��CPU��ɬ�פȤ��Ƥ������ᡢ�����δĶ��������ޤǤδ֡�Motion JPEG�Ͻ�������ޤ�����
- 1996ǯ�����ϡ����Υե��������Τ��ƹ�Zoran�Ҥ�C-Cubed�Ҥ�2�Ҥ����뤹��Motion JPEG�Υ��åץ��åȤ�Ȥ��Τ��Ǥ⥹�ޡ��Ȥ��ä��Τǡ������ܡ��ɤˤ����Υ��åפ���ܤ���M-JPEG�������äƤ��ޤ�����
- 1996ǯ�����ϡ�ư���ѥ�����Ǹ���Ȥ����Ķ������äƤ��ޤ���Ǥ�����
- ����ԥ塼����ǽ�ϡ�CPU��RAM��HDD�����̡ˤ��ȤƤ����ϤǤ��ä����ᡢ��������ư������ˤϲ����ܡ��ɤ�Ȥäƽ������뤳�Ȥ�¿���Ԥ��Ƥ��ޤ�����
- MPEG��ѥ�����Ǻ�뤳�ȤʤɵڤӤ⤷�ʤ�����Ǥ�����
- ��������������ݤ�줿Motion JPEG�ϡ��ӥǥ��Խ�ʬ��ǽ�������2010ǯ�����Ǥ��Խ���ư��ե�����Ȥ��ƻȤ��Ƥ��ޤ���
- Motion JPEG�ϡ�MPEG�Ȱۤʤꡢ���������Ω���������Ȥ�����¸���Ƥ���Τǥե졼��ñ�̤��Խ�����Τ��Թ礬�ɤ��ΤǤ���
- ���θ塢����ԥ塼�������Υ��եȥ�����������M-JPEG�����������褦�ˤʤꡢAVI��QuickTime�Ǥ�Motion JPEG�Υ����ǥ��å�����ȯ����ޤ�����
- �ǥ����륫����ư��ե�����ˤϸ��ߤ�Ȥ��Ƥ��ޤ������Υǥ����륫���ϲ��ǿ���¿���ʤꤹ���������Motion-JPEG����¸����ȵ�Ͽ�������ô��������Τǡ����̸�Ψ���ɤ��ƹ�����H.264����Ѥ��륫��餬�����Ƥ��ޤ���
- Motion JPEG�Ϥޤ������ѤΥϡ��ɥ�������Ȥäƥǡ������̤�Ԥ��ʤ���ꥢ�륿�����ư��μ����ߤ��Ԥ��뤿�ᡢ�ѡ����ʥ�����Υӥǥ�����ץ��㡦�����ɤʤɤˤ��Υե����ޥåȤ����Ѥ���ư������˰��Ϥ�ȯ�����ޤ�����
- �ޤ���Motion-JPEG��MPEG�ǡ����ʤɤȰۤʤ�1���ޤ��Ż߲����Ȥ���¸�ߤ��뤿�ᡢǤ�դβս�Ǥ��Խ����ưפ˹Ԥ��ޤ���
- ����Ψ��1/5����1/20���٤Ǥ��ꡢ���̤���������Ƥ������Ȥʤ�ޤ�����ȯ���������ΰ��̲�����ȤäƲ�����¬��Ԥ����Ȥ����Ȥ��������̤��줿�ǡ�������ư����������Τʰ��־��������ޤ���Ǥ�����
- Motion JPEG��MPEG�ϡ�̾�������Ƥ��ޤ������ե����ޥåȤ��㤤�ޤ���������¬�Ѥ�Motion-JPEG�Ϥ��Ф��лȤ��ޤ�����MPEG���Ը����Ǥ���
- MPEG�ե����ޥåȤǤϲ������Żߤ������ꥳ�����ꤷ�����ž�������뤳�Ȥ������դǤ���
- �ʤ���������ǥե����ޥåȤ��äƤ��ʤ��Τǡˡ�JPEG�����Ǥⰵ�̤��ٹ礤�ˤ�äƤϷ�¬�϶줷���ơ��ɤ���ͤ����ΤǤϤʤ��ʤ�Ȥ�����Ŧ��¿������ޤ���
- ������¬�ˤϤ��ޤꤪ������Ǥ��ʤ��ե����ޥåȤǤ���
- �����ϸ��äƤ�2010ǯ�ˤ��äƤ�MPEG���������̤˽в�ꡢ����ȹ��ޤ���ˤ�����餺�����Ƥ��줿MPEG�������������¬�ʤ���Фʤ�ʤ�������¿���ʤäƤ��ޤ�����
- ��¬���٤Ϥɤ����줽����������ˤʤ�ޤ�������2010.05.25����
- ��MPEG�ۡ�Motion Picture Expert Group�ˡʤ���ڤ�������2009.05.04�ɵ��ˡ�2010.06.27�ɵ���
- MPEG�ϡ�Motion Picture Expert Group ��ά�Ǥ������Υե����ޥåȤϡ�1988ǯ����Ω���줿Ʊ��̾������ĥ��롼�פ�ư�����沽���Ѹ�����椫�����ޤ�ޤ�����
- ����Ū�ʳ�ĥ�Ҥϡ�mpg�����뤤��mpeg�Ǥ���
- WMV��Quick Time�ȰۤʤꡢISOɸ�ಽ���������ͤ���Ƥ��ޤ���
- DVD��ǥ����������ΰ��̥ե����ޥåȤ˺��Ѥ��줿���ᡢ2010ǯ�����ǤϤ�äȤ����Ū��ư�谵�̥ե�����ե����ޥåȤȤʤäƤ��ޤ���
- ����ư��ե����ޥåȤ���ˤ⤢�ꡢ���ʤ�ȯŸ��³���Ƥ���ư��ե����ޥåȤǤϤ���ޤ����������ϰϤ������ʤäƤ��ޤäơ��㤨�С�MPEG-4�Ǥ⤤�������ʥ��ƥ���� = �ץ��ե�����ˤ��Ǥ��Ƥ��ޤ���MPEG�Ȱ���˸��äƤ�����Ǥ��ʤ����������ǤƤ��Ƥ��ޤ���
- ���������ե졼��
- MPEG�ϡ���γ�ǰ�ޤ������Ƥ���褦�ˡ����٤ƤΥե졼��� = ���̡ˤˤ錄�ä���Ω��������������櫓�ǤϤ���ޤ���
- MPEG�Ǥϡ������ե졼��ȸƤФ�����Τβ�����������ե졼�ब���ꡢ����ʳ��ϡ������ե졼��֤�ư���Ƥ������̤�������¸��������������Ƥ��ޤ���
- ������ˡ��Ȥ��С�1�ե졼�ह�٤Ƥ���¸����������餫�˥ǡ����̤����ʤ��ƺѤߤޤ�����ñ�̻��֤����������ǡ����̤⾯�ʤ��Ƥ��ߤޤ���
- �Ĥޤꡢ�����������̿��Ӱ褬�����Ƥ⡢�Ӱ�ʾ�ξ������ı��������뤳�Ȥ��Ǥ���ΤǤ���
- ���οޤϡ�MPEG-2�����������ޤǤ���
- ������MPEG-2��������ħ�����뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
- ���β����ϱ߷��β�ž���Ĥ˻�Ⱦ�߷�����ݡ����ݤΥ������åȥޡ�����Ž���դ��Ʋ�ž�����Ƥ�������ΰ���Ǥ���
- ���β����γ���ޤ�ȡ��������åȼ�������̤����ȥ�ߥ���ƺ٤������Ǥ˶�ʬ�����졢ư���Ƥʤ��Хå������ɤ��礶�äѤ˽�������Ƥ��뤳�Ȥ��狼��ޤ���
- MPEG�γ�ȯ�ϡ����äơ��ǡ����̿�����٤�ڸ����뤿��˹Ԥ��ޤ�����
- ư������̤Υǡ�����Ϣ�ʤ�³���Τǡ�ư�������ͥåȲ����ʤɤ��̤�������������Ӱ�����Ȥ������꤬�����Ƥ��ޤ��ޤ���
�����Զ����ä������ƤȤ��ơ��ǡ����̤�������Ȥ�����ˡ�����Ѥ��줿�ΤǤ���
- �ǡ������̤ϡ�JPEG�Τ褦�˰���β��̤�̵�̤ʾ����ʤ����ְ��̤ȡ�ʣ���������Ϥä��Ѳ����Ƥ��ʤ��������������ʤ��Ȥ�����ְ��̤�����ब����ޤ���
- ���ְ��̤Ȼ��ְ��̤�2������Ȥ����Ȥˤ�ꡢ���̤�Ԥ�ʤ���AVI�ե��������1/100��1/200���٤ΰ��̤���ǽ�Ȥʤ�ޤ�����
- MPEG�ϡ�1990ǯ���Ⱦ����2000ǯ��ˤ����ơ�DVD�ˤ��Dz�䥤���ͥå��ۿ�������ȥǥ�����ƥ�������˺��Ѥ����褦�ˤʤꡢ���ߤ�ư��ե�����μ��ϤˤʤäƤ��ޤ���
- �������֤��٤�
- ���Υե�����ե����ޥåȤ����դ��ʤ���Фʤ�ʤ����Ȥϡ���Ĥˤϡ��ꥢ�륿����Ǥ��������������ȤǤ���
- �ե�����ι�¤�塢�����ե졼��֤�1�Ȥβ�����GOP = Group Of Pictures�ˤ�ñ�̤Ȥ��ơ�ư���Τ���Ȥ�����������Ф��ư��̽�����Ԥ��ޤ��ʲ����ȡˡ�
- GOP��MPEG�ե���������δ��ܤ����ޤ�Ȥʤ�ޤ���
- MPEG�����ˤ�����ͥ���ʥ�������ɬ�פǤ���
- �桹���ȤäƤ���PC�Υ��եȥ�������Ȥä�MPEG�ե�������ɤ���ˤ������ʻ��֤�������ޤ���
- �ƥ�������Ǥϥѥ�����Τ褦��ͪĹ�ʤ��ȤϤǤ��ʤ��Τǡ����ѤΥ��������֤�Ȥä�MPEG-2�������®�ǹԤ��������Ƥ��ޤ���������������ǽ�������֤�ȤäƤ�����֤Ǥΰ��̽�����Ԥ�ɬ�塢������ί������Ȥ�ޤ�Ƥ��ν����˻���Ū���٤줬�Ǥޤ���
- �������פ���ȡ����褽1��2�����٤��٤�Ȥʤꡢ�ºݤθ��ݤ���٤��������ϩ�����뤳�Ȥˤʤ�ޤ���
- �ޤ����������¦�Ǥ�ͥåȥ�����̿������������Ӱ���̿�®�٤��Ѥ��ޤ���
- ���ξ塢������륳��ԥ塼���Ǥ�MPEG����ɤ��ƺ��������������������ޤ��Τǡ������Ǥ⥭���ե졼��Ⱥ�ʬ��������ư�������ۤ��뤿��ν������֡��٤���֡ˤ�и礷�ʤ���Фʤ�ޤ���
- �Υƥ�������ϡ��ǥ����������ˤʤ�ޤ�������ɤ⡢MPEG����Ѥ��Ƥ���ط��奢�ʥ���������Ʊ�����Ȥȸ���٤��2�������٤�Ƥ��ޤ���
- �ʻ�����Ͽ�褷����Τϥǥ������٤�����������������äƤ���ɤ⤢�뤽���Ǥ�����
NHK������λ���ʤɤϡ��ΤΥ��ʥ���������饸�������Ǥ���л��֤��٤�ʤ�ɤۤȤ�ɵ��ˤ��������Ǥ����Τˡ��ǥ�����������MPEG-2�Ǥϥǥ������٤줬�ФƤ��ޤ��Τǥ����ӥ���ߤ�Ƥ��ޤ��ޤ�����
- �ǥ�����ʤɤȤ�������ǽ����̾��Τ褦�ʶ������������ˡ�����Ū���٤줬���ʤꤢ��Ȥ����Τ϶ä��Ǥ���
- ����Хåե��˲��������ί�����Ǻƹ��ۤ���ǥ������ˡ�Ǥ����̤�ʤ���ħ�Ȥʤ�ޤ���
- ����I�ե졼�ࡢP�ե졼�ࡢB�ե졼��
- MPEG�Ǥϡ�3����Υե졼�ब�Ȥ��Ƥ��ޤ���
- ����I�ե졼��
- ����P�ե졼��
- ����B�ե졼��
- ����3�Ĥ�GOP����˳�Ǽ����Ƥ��ޤ��ʾ���ȡˡ�
- �����ե졼��ϡ���I�ץե졼���Intra coded Frame�ˤȸƤФ�Ƥ��ޤ���
- ��ʬ��������ξ��������̾���ե졼����P�ץե졼���Predicted Frame��ͽ¬�ե졼�ࡢ�ǥ륿�ե졼��ˡ�����ӡ�B�ץե졼���Bi-Predicted Frame��������ͽ¬�ե졼��ˤȸƤ�Ǥ��ޤ���
- ��I�ץե졼��ϡ����ʴ��뷿�Υե졼��Dz������Τξ������äƤ��ޤ���
- ����ϡ������ե졼��Ȥ��ƻȤ��ޤ���JPEG�ʤɤ���ְ��̤�ۤɤ����ƤϤ����ΤΤ��켫�Τˤ��٤Ƥβ�������������碌�Ƥ���Τǡ�I�ץե졼�������ޤ���
- ��P�ץե졼��ϥǥ륿�ե졼�ࡢ�⤷����ͽ¬�ե졼��Ȥ�ƤФ졢ľ���Υե졼���I�ե졼��⤷����P�ե졼��ˤȤ����Ѳ����������Ȥ��Ƶ�Ͽ���Ƥ��ޤ���
- ��P�ץե졼��Ͻ�������ñ�Ǥ������Ѵ���Ȥ��Ԥ��䤹��ȿ�̡����̤ˤ�³������ꡢ����Ψ���Ū�˾夲�뤳�ȤϤǤ��ޤ���
- ��B�ץե졼��ϡ��������ե졼��ȸƤФ���Τǡ�ľ����ľ��Υե졼���I�ե졼���P�ե졼��ˤȤ��ƺ�ʬ��Ͽ�����ΤǤ���
- �Ĥޤꡢ����Υե졼������Υե졼�������κ�ʬ����¸���뤿�ᡢ��P�ץե졼����⤵���;ʬ�ʾ�������Ȥ����Ȥ��Ǥ����̤���뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
- ��B�ץե졼��ϡ�����������ʣ���ˤʤ�ޤ����顢���̡�����ˤϽ������֤���٤�������ޤ���
- ��
- ����������¬�Ȥ��Ƥ�MPEG
MPEG�Ǥ⤦������դ��ʤ���Фʤ�ʤ����Ȥϡ���¬��Ū�Τ����MPEG��Ȥ��Τ���Ŭ���Ǥ��뤳�ȤǤ���
- ���Υե����ޥåȤϡ����衢�¤�줿�̿��Ӱ��ư����������Ȥ�����Ū�Ǻ��줿��ΤǤ��ꡢ�ƥ�Ӥ�Dz�ʤɤ��̿����������뤳�Ȥ���Ū�Ȥ��Ƥ��ޤ�����
- �ޤ�MPEG-2�Ǥ�4.7GB�����̤�DVD�˱Dz����¸�������뤳�Ȥ�����ʻ�̿�Ȥ��Ƥ��ޤ�����
- DVD�ˤ��Dz�վޤϡ�Ϣ³������ǰƬ�ˤ���ޤ�����¬�Ѥ�ư�����ϡ��Żߤ������ꥹ����������Ԥä����ž������Ԥ��ޤ���
- ���Τ���������������礫��ʪ�Τ��Ѱ̤���ꡢǻ�٤����٤褯��¬���ޤ�������������Ū�ˤ�MPEG���Ը����Ǥ���
- MPEG�ǤϾ�ǽҤ٤��褦�˥����ե졼���Ĥ��ä�Ϣ³�������ۤ��뤳�Ȥ˽������֤��Ƥ��ޤ����쥳������䥹���å�������ž������Ԥ���硢�������٥����ե졼���õ���ơ�GOP��ˡ˴�˾�����ϰϤǤ�Ϣ³�������ۤ�����Ϣ��ư�������ۤ��ޤ�����������������Ф��������������ϼ����������ʤ���ΤȤʤ�ޤ���
- �����ȳ����Խ���Ȥˤϥ֥��å�ñ�̡�GOPñ�̡ˤǤ��Խ��������餤�����MPEG���Ѥ��Ƥ��餺���ǽ������ʤȤ��ƤΤ��Ѥ��Ƥ��ޤ���
- ���������������顢MPEG�Ϥ���������ʬ�����ƻ��Ѥ���ɬ�פ�����ȸ����ޤ��礦��
- �������ɤǺ��Ѥ���Ƥ���MPEG-4 Studio Profile�Ȥ������ʤϡ��Խ���ǽ��ʬ�˹�θ�������ʤΤ褦�Ǥ�����
- ��
- ���ޤˡ�MPEG-2�ե������ȤäƲ�ž�Τ�Ž�դ����������åȥޡ������Ѱ̤�ץ��åȤ����ޤ��ޤ���
- �ץ��åȿޤϡ������˥ե졼�ࡢ�ļ��˲�ž���륿�����åȤ�Y�����ʿ�ľ�����ˤ��Ѱ���ʬ���Ƥ��ޤ���
- �о�ʪ�ϲ�ž��ư�Ǥ�����Y����ʬ��ñ��ư�ʥ������֡ˤˤʤ�Ϥ��Ǥ���
- �ޤƤߤޤ��Ȥ��⤷�������Ȥ˵��Ť��ޤ���
- 15�ե졼����˥��֤Τ褦����ʬ������Ƥ��ޤ���
- MPEG-2�ե�����Υ��ꥸ�ʥ�ե������AVI�Ǥ���
- AVI����MPEG-2�ե��������ޤ��������ꥸ�ʥ�ե������AVI�ե������Ʊ�ͤβ��Ϥޤ��ȡʲ��ޡ����ʡˤ����������֤ϸ�������ޤ���
- MPEG-2�����Ǥɤ����Ƥ��Τ褦�ʥ��֤���ʬ�����Ф����Τ���Ĵ�٤Ƥߤơ����Τ褦�ʤ��Ȥ��狼��ޤ�����
- MPEG-2�����ϡ�GOP��Group Of Pictures�ˤ�ư���դ����Ԥ��Ƥ��뤳�ȤϤ��Ǥ˽Ҥ٤ޤ�����
- ������Ѥ���MPEG-2�����ϡ�15�ե졼��ʬ��GOP��1�֥��å����������Ƥ��ޤ���
- 15�ե졼���1�Ĥ�ư���뤵���Ƥ��ޤ���
- �����Ǥ�����ϡ�GOP�Υ֥��å��֤ΤĤʤ��ܽ��������ޤ����äƤ��ʤ����Ȥ˵������Ƥ��ޤ���
- 15���֤�ư���դ��Ϥ��ޤ��Ԥ����ΤΡ�GOP��ޤ����Ǽ��κǽ�Υե졼�ब���ԥ�����ʬ��֤Ǥ��Ƥ��ʤ�����������ޤ�����
- ��������β�褬����Τ��ɤ����Ϻ��ΤȤ����狼��ޤ���
- MPEG-2�Υ������饤�����줿�ե����ޥåȤ�Ȥ��ȡ������������꤬�����Ƥ��ޤ����Ȥϻ��¤Τ褦�Ǥ���
- �����������褹�뤿��ˡ�MPEG-2�ե��������ݤˤ��٤Ƥβ���ʬ���ɤ߹������֥ե�������äơ�������������Ȥ�����ˡ������ޤ���
- ��ޤβ��ϤǻȤä�MPEG-2�ե������TIFF��Ϣ�֥ե�������Ѵ���¸���ơ�Ʊ�ͤβ��Ϥ�Ԥä��Ȥ������֤��Զ��Ϥʤ������줤��ñ��ư�ȷ��������ޤ�����
- �����������Ȥ��顢MPEG-2�������ܼ�Ū�˲��Ϥ��Ը����Ǥ��뤳�Ȥ�����Ǥ��ޤ���
- ��¬��Ū�ˤϤǤ������MPEG-2�ϻȤ鷺��TIFF��JPEG��Ϣ�ֲ������Ѥ��뤫��AVI�ե�������Ѥ��뤳�Ȥ����ȥ쥹�ʤ���ˡ���ȹͤ��ޤ���
- ��������MPEG-2�Ǥ��������ե����뤬����Ǥ��ʤ����ϡ����Υե�������öAVI�ե����뤫TIFF�ե�������֤������Ʋ��Ͻ����˲��Ȥ�̵����ȹͤ��ޤ���
- MPEG-2�ե�������礭����ħ�Ǥ���2���֡�220,000���720x480���ǡˤˤ�錄��Ĺ����Ͽ��ե��������Ϥ�������硢�����쵤�˲��Ϥ���ͭ���ʼ���ƤϺ��ΤȤ�������ޤ���
- ���ξ��ˤϡ�Ĺ����Ͽ�褵�줿�ե��������Dz��Ϥ�ɬ�פ��ϰϤ���������AVI��TIFF�˥ե������Ѵ����ơ����Υե�����ǽ�����Ԥ��Τ���ñ�ǰ²�����ˡ���Ȼפ��ޤ���
- ��¬�����ˤ�äƤϡ�Ĺ����Ͽ���PC�Υϡ��ɥǥ�������ľ�ܽ���Ǥ�����Τ����ꡢ����������Τ��Ż߲��������¸�����Τ�¿���Τǡ���¬�ϥ��ࡼ���˹Ԥ����Ȥ��Ǥ��ޤ���
- ��
- �� MPEG-1��
- MPEG-1�ϡ�MPEG�ե����ޥåȤκǽ�ε��ʤǤ��ꡢ1993ǯ�˵��ʤ����ꤵ��ޤ�����
- ����MPEG-1�ϡ�ž��®�٤�1.5M�ӥå�/�äǡ�������������352 x 240 ���ǤǤ��ꡢ30�ե졼��/�ä�Ͽ�褬�Ǥ��ޤ�����
- �����鸫��ȿ�ʬ�����������Ǥ������β����������ϥƥ�Ӳ�����1/4�Ǥ��ꡢ�ƥ�Ӥ�ο���Ȥ�����ǽ�ǤϤ���ޤ���Ǥ�����
- MPEG-1�����줿��1993ǯ���������ǡ����̿���ѥ�����ν���ǽ�Ϥ�ͤ����顢���ε��ʤ������դ��ä��Τ����Τ�ޤ���
- MPEG-1�Υǡ���®�٤ϡ�����Ǥ������Υ����ͥåȤ˾褻�뤳�ȤϤޤä����Բ�ǽ�Ǥ�����
- 1990ǯ����Ⱦ���̿������ϥ��ʥ������õ��β������ۤȤ�ɤǡ������1.5M�ӥå�/�äΥǥ������̿���Ԥ����Ȥ��Բ�ǽ���ä��ΤǤ���
- �����Υ������륢�åײ������̿�®�٤�28.8k�ӥå�/�ä��ǹ���ǽ�Ǥ��ꡢMPEG-1���᤹��1/52����ǽ��������ޤ���Ǥ�����
- ���äơ�MPEG-1�ϡ�CD-ROM��ư������Ͽ������ʤȤ��Ƴ�ȯ���졢Video-CD�ʤɤ˻Ȥ��ޤ�����
- CD�ξƤ�����®�٤����Υ졼�ȤǤ�����
- MPEG-1�ϡ�2010ǯ�ˤ��äƤϤ���������MPEG-4���Ȥ���褦�ˤʤ�ޤ�����
- MPEG-1�Υ����ǥ����ե�����Ǥ����MPEG-1 Audio layer-3�פ����ϡ�MP3�Ȥ���2010ǯ�Ǥ�¿���Ȥ��Ƥ��ޤ���
��
- �� MPEG-2��
- MPEG-2�ϡ�1995ǯ�����ꤵ��ޤ�����
- ����ϡ�HDTV�ʥϥ��ӥ����ƥ�ӡˤޤǥ��С�����ǥ�����ӥǥ��Ѥε��ʤǤ�����
- ���ε��ʤǤϡ�MPEG-1�˲ݤ����ӥåȥ졼�Ȥ����¤���ž��®�٤�4Mbps��24Mbps�Ȥ��ޤ�����
- ��갷��������ϡ�720 x 480 �� 1920 x 1080�Ȥʤꡢ�ƥ�Ӳ������ʼ���ռ����ƥϥ��ӥ����ˤ��б��Ǥ����ΤȤ��ޤ�����
- �֥����ɥХ�ɤΥ����ͥåȤˤ��б��Ǥ���褦�ˤ������ᡢMPEG-2�ϥͥå��ۿ��Ǥ���ư�����γθǤ����ϰ̤��Ω���ޤ�����
- �ޤ���DVD�˺��Ѥ��줿���ᡢ�Ǥ�ͭ̾�ʵ��ʤȤʤ�ޤ�����
- ��
- �� MPEG-3��
- ��MPEG-3�ϡ�¸�ߤ��ޤ���
- ���Υץ��������Ȥϡ�1080�ܥ����졼��������20 Mbps - 40 Mbps�ˤ��HDTV���������ѤȤ��Ƶ��ʲ����Ϥޤ�ޤ�������MPEG-2����������ǽ��ʬ�˻��äƤ���Ȥ��ơ��Ĥޤꡢ����������MPEG-2��Ʊ���Ǥ��뤿�ᳫȯ�ΰյ����ʤ��ʤꡢ����������Ⱦ�Ф�1992ǯ��MPEG-2�˵ۼ�����ޤ�����
- ���ʤߤˡ����ڥե������ͭ̾��MP3�ϡ�MPEG-3�ǤϤʤ���MPEG-1�Υ����ǥ������ʤȤ��ƽ�ȯ������Τǡ���MPEG-1 Audio layer-3�פ�ά�ΤǤ���
- ��
- �� MPEG-4��
- 1998ǯ�����ꤵ�줿��ư���̿��ѵ��ʤǤ���
- ���ʲ����줿����������ե����ޥåȤϡ�176 x 120 �� 352 x 240 �Ⱦ��������̿�®�٤�64kbps �� 512kbps���٤���ΤǤ�����
- ���ε��ʤϡ�QuickTime��ASF�ʤɤΥѥ�������ư���ޥ����ǥ��������Ѥ��ޤ�����
- ���θ塢MPEG-4�ϼ�갷�����Ƥ������ʤꡢ�ѡ��ȤȤ�������¿�����������ʤ����ޤ졢�̿�®�٤��®�ˤʤ����ǹ��ʰ̤ε��ʤˤʤäƤ����ޤ�����
- 2010ǯ�ˤ��äƤϡ���MPEG�פȤ����Ȥ��Υ��ƥ����ؤ����Ȥ�¿���ʤäƤ��ޤ����������ϰϤ����ޤ�˹����Τ��������Τ���¤Ǥ���
- MPEG-4���Ȥ��Ƥ�����Ѥˤ���1������QuickTime7��iPod��iPad��AppleTV��HD DVD��Blu-ray�ʤɤ����ꡢ�����˺��Ѥ���Ƥ���ư��ե����ޥåȤϡ�MPEG-4 AVC/H.264 �Ȥ������ʤǤ���
- ��
- �� MPEG-7��
- MPEG-7�ϡ������MPEG�ε��ʤȼۤʤ�ޤ���
- ���ε��ʤϡ��ޥ����ǥ���������ƥ�Ĥ˴ؤ��뤵�ޤ��ޤʾ���ε�����ˡ��ɸ�ಽ���ơ�������Ԥä���ե�������ǽ�ˤ��뵬�ʤȤʤ�ޤ�����
- MPEG-7�ϡ�1996ǯ�˥������Ȥ���2000ǯ����ɸ�˵��ʲ���Ȥ��ʤ���ޤ�����
- ��������10ǯ��Ф�2010ǯ�ˤ��äƤ�MPEG-7��̾���Ϥ��ޤ�ʹ���ޤ���
- ���ʤμ�ݤϡ������ͥåȤο�Ÿ��ȼ���������ͥåȥ�ǥ�����ʸ��ե����ޥåȡˤ����줵���Ƹ�����������ưפˤ����褦�Ȥ������������ä��褦�Ǥ���
- ����������̤Ϥ���ۤ�˧������ΤǤϤʤ��ä��褦�Ǥ���
- ư�����˴ؤ���¤�MPEG-7�Ǥ����Ϥ���ۤ��礭���ʤ���2010ǯ�ˤ��äƤ�MPEG-4����ή�Ǥ���
- ��
- ��MPEG-4 AVC/H.264��
- AVC�ϡ�Advanced Video Coding��ά�Ǥ���MPEG-4�Υѡ���10�θƤ�̾�Ȥ���AVC���դ����ޤ�����
- �����ˤϡ���MPEG-4 Part 10 Advanced Video Coding�פȸƤ֤Τ��������ΤǤ�����Ĺ���Τ�ñ��AVC�ȸƤ֤��Ȥ⤢��ޤ���
- �ޤ�����ȯ�������ؤ�º�Ť���H.264���դ��Ƥ��ޤ���
- AVC�ϡ�MPEG-4�Υ��ƥ�������H.264���ʤ�����ơ�Part10�˥饤�åפ����Ȥ������֤Ť��Ǥ���
- AVC�ϡ�2003ǯ�����ꤵ��Ƥ�������˻Ȥ���褦�ˤʤꡢ2010ǯ�ˤ��äƤϤ�äȤ�ͥ�줿ư�������̥ե����ޥåȤȤʤ�ޤ�����
- ��갷���������礭���ϡ�320 x 240���Ǥ���1920 x 1080���Ǥȹ��ϰϤǡ��̿��졼�Ȥ�320kbps��10Mbps���Ͼ�ǥ������������ʤ����ƤϤޤ�褦�ˤʤäƤ��ޤ���
- ���ε��ʤǤϡ�ư������Τ���Υ֥��å���������16x16���Ǥ���4x4���Ǥޤ����֤��Ȥ��Ǥ��٤��������ޤ������������Ǥ��뤿�ᡢ�֥��å��Υ�����⥹�����ȥΥ�����ȯ�����ޤ��뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
- ��
- ����H.264����
- H.264�ϡ�ư�谵�̥ե�����ε��ʤǤ���MPEG��ISO��IEC���ȿ��β��ǵ��ʲ����줿�Τ��Ф���H.264�ϡ�ITU�ʹ���ŵ��̿�Ϣ�硢International Telecommunication Union�����Ȥ�CCITT�ˤβ����ȿ��Ǥ���ITU-T��Video Coding Experts Group (VCEG)�ˤ�äơ�2003ǯ5��˺��ꤵ��ޤ�����
- �ǽ�ε��ʤǤ���H.261�ϡ�1990ǯ�ˤǤ��Ƥ��ޤ���
- ����ǯ�������иŤ����ʤȸ����ޤ���
- ���줬�ʲ���³����H.264�ˤʤ�ޤ�����
- ���ε��ʤ�MPEG�ˤ���Ѥ���뤳�ȤˤʤꡢMPEG-4�Υѡ���10�Ȥ���������ꤷ�ơ�MPEG-4 AVC/H.264�Ȥʤ�ޤ�����
- MPEG��H.264�ϡ����賫ȯ���Ƥ��뵡�ؤ���äƤ����ΤǤ��������̥��르�ꥺ���Ʊ���Ǥ�����H.264�ϡ�����ͥ���ʥ��르�ꥺ��Ǥ��ꡢ����Ψ���⤤��˲�����������ʤ��ä������MPEG���������Ѥ��ޤ�����
- ISO/IEC�Ǥϡ���MPEG-4 Part 10 Advanced Video Coding�פȤ��Ƶ��ꤷ��̾�������H.264�����äƤ��ޤ���
- �����������Ƥ�H.264���Τ�ΤǤ��뤿�ᳫȯ���ؤ˷ɰդ�ɽ���ƤĤ��˼����褦��ʻ������褦�ˤʤ�ޤ�����
- ��H.264/AVC�� ��H.264/MPEG-4 AVC��
- ��MPEG-4 AVC/H.264��
- ����VC-1��Video Codec 1��
- H.264�Υ饤�Х�ϡ��ޥ��������եȼҤ�VC-1��Video Codec 1�ˤǤ���
- ξ�Ԥϡ�����Ψ������ۤ�Ʊ���Ȥ����Ƥ��ޤ���
- VC-1�ϡ��ޥ��������եȼҤ��ȼ��˳�ȯ����MS-MPEG�Ѥΰ��̥����ǥå��Ǥ��ꡢWindows Media Video 9 ��WMV9�ˤȤ���Windows Media Player�˼�������ޤ�����
- ���줬2003ǯ���ƹ�Dz�ƥ�ӥ���Ѷ����SMPTE = the Society of Motion Picture and Television Engineers�ˤ˿������졢2006ǯ�˵��ʲ�����ޤ�����
- VC-1������̾�Τϡ�SMPTE 421M video codec standard�Ǥ������������̾����Ĺ���Ф����餤�Τǡ����ڤ�������ä�VC-1�θƾΤ������Ȥ��Ƥ��ޤ���
- DVD�ե������Ǥϡ����Υޥ��������եȼҤγ�ȯ����VC-1��H.264�Ǥ���MPEG-4 AVC��ξ�Ԥ�ɬ�ܥ����ƥ�Ȥ��ƾ�ǧ�������ᡢ�ʸ塢������Ĥ�ư�谵�̥ե�����Υ���������ɤȤ��ƻȤ���褦�ˤʤ�ޤ�����
- VC-1�ϡ�HD DVD��Blu-ray�ǥ�������Windows Media Video 9���ޥ��������ե�Silverlight�˺��Ѥ���Ƥ��ޤ���
- ��
- ��DV-AVI�ۡʤǤ��֤������֤�������
- DV-AVI�ϡ�Digital Video AVI ��ά�Ǥ����ǥ�����ӥǥ����ʤΥǡ����Τޤ�AVI�Ȥ�������ʪ�����줿�ե����ޥåȤǤ���
- ��˽Ҥ٤�AVI���ޤ���Ȣ�ˤʤäƤ��ޤä��Ȥ���ŵ��Ū����Ǥ���
- DV-AVI�ϡ�AVI�Ȥ���Ȣ�������Ф���������ư�襽�եȤǺ����Ǥ���Τ������Ǥ���Ȥ�������������졢�ǥ�����ӥǥ�����餫���ư��ե��������Τ���ڤ��ޤ�����
- �ǥ�����ӥǥ������Ͽ�褷��DV�ơ��פ�ѥ��������¸����Ȥ���DV-AVI���Ȥ��ޤ���
- MPEG���Ѵ���������Խ����ڤȤ�����ͳ����Ǥ���
- �������������ʤ���ե��������̤�2GB���ɤ�����ޤ���
- DV-AVI�ե�����κ��ܤϡ��ʲ��˽Ҥ٤�DV�����Ǥ�������DV���ʤ�Motion JPEG����ܤȤ��Ƥ��ޤ�������¬�Ѥ�ư�����������եȤǤϤ��Υե����ޥåȤ��б����Ƥ��ʤ���Τ�¿������ޤ���
- ��
- ��DV�ۡʤǤ���������������2010.07.10�ɵ���
- DV�ʥǥ����롦�ӥǥ����ǥ������ˤϡ�Digital Video��ά�Ǥ���
- �����1995ǯ�˷���줿̱����Υǥ�����ӥǥ����ʤǡ�����Υ��ʥ����ӥǥ��ơ��������������ؤ��ơ��ǥ���������ǡ����Ȥ��Ƽ����ơ��פ˵�Ͽ���뤿��˵��ʲ�����ޤ�����
- �ǥ�����Ͽ��Ǥ����顢����Υ��ʥ�������VHS�ӥǥ��ơ��ץ쥳�����Ȱ�ä��Խ���ʣ����ȼ�����������������ޤ���ʡ��ǥ�����ӥǥ������DV�����ȡˡ�
- ���ε��ʤ��Ǥ��������ˤϡ��ƥ�������Υǥ����벽�ȥѥ��������ڤ��������ޤ���
- 1980ǯ�塢VTR����ڤˤ�ꥢ�ʥ����ӥǥ�����ˤ��ӥǥ����郎������˹����Ԥ��Ϥ�褦�ˤʤ�ޤ�����
- �ʥ��ʥ����ӥǥ�����ˤĤ��Ƥϡ�NTSC��Q23.NTSC�äƲ������ͤˤ��Ƥ�����������
- ���Υ��ʥ����Υƥ�ӡʥӥǥ��˿����ǥ����벽������Τ�DV�ե����ޥåȤǤ���
- ���äơ�DV�ˤ�NTSC����α�����������ϳ�餵���ǥ�������֤�������տޤ�����ޤ�����
- �ӥǥ������ǥ����벽�������Ȥˤ�ꡢ���ԡ��ˤ��������������ʤ��ʤ�ޤ�����
- ����ޤ���ڤ��Ƥ���8mm�ӥǥ��ơ��ץ쥳�����⡢�����˥ǥ�����ӥǥ��ơ��פ��ؤ�äƤ����褦�ˤʤ�ޤ�����
- ������������DV�⡢2000ǯ��Ⱦ�����о줷��80mm�¤�DVD��1�������25.4mm��HDD��ȾƳ�Υ����SD�����ɡˤ�Ͽ���ΤȤ���ӥǥ������γ�ȯ�ˤ�ꡢ�Ծ���Υ����˾���褦�ˤʤ�ޤ�����AVCHD�����ˡ�
- ���������ӥǥ������Ǥϡ�DV�ǤϤʤ�MPEG-4���Ȥ��ޤ�����
- MPEG���������̤��⤤����Ǥ���
- �����������٤�Ҥ٤Ƥ��ޤ������Խ�����Ū�Ȥ����̳�Ѥ�ʬ��Ǥ�Motion-JPEG��١����Ȥ���DV������̥��Ū�Ǥ��뤿�ᡢ��������ʬ��Ǥ�2010ǯ�ˤ����Ƥ�DV���ʤΥǥ�����ӥǥ��ơ��פ����Ѥ����ӥǥ�����餬�Ȥ��Ƥ��ޤ���
- ��
- ����DV - Motion JPEG��¸
- DV���ʤǤ����̥������ϡ�720��480�ԥ�����ǡ��ե졼��졼�Ȥ�30fps������Ψ����1/5�ȤʤäƤ��ޤ���
- ���̥������ϡ�NTSC�����ǥ�����ˤ��뤿���ɬ�פ��Ľ�ʬ�ʲ��ǤȤ��Ƥ��ޤ���
- 30����/�äȤ���Ͽ�衦����®�٤�ӥǥ�����ε��ʤΤޤ�Ƨ�����ޤ�����
- �����ϡ�Motion-JPEG�ˤ��ե졼���ⰵ�̤���Ѥ��Ƥ��ơ�MPEG�Ȥϰ㤤���������Ż߲����¸���Ƥ��ޤ���
- MPEG�ϡ������ְ��̤�Ԥ�����˥����ɽ������ȤƤ�ʣ���Ȥʤꡢ1995ǯ�����Ϥ�����ǽ�ˤ���²���MPEG���������åפ��ʤ��ä����ᡢ���ޥ��奢���������ʤˤ���ܤǤ��ޤ���Ǥ�����
- Motion JPEG�ϡ�ȿ�̡������Խ����ڤˤǤ��ޤ�����
- �����ϡ�����ץ���ȿ�48kHz���̻Ҳ��ӥåȿ�16bit�Υ�˥�PCM2ch����32kHz��12bit�ΥΥ��˥�PCM4ch�ȤʤäƤ��ޤ���
- Ͽ����֤�ɸ�५���åȤ�270ʬ���ߥ˥����åȡ�Mini DV�ˤ�60ʬ��80ʬ�Τ����줫��Ͽ�褬��ǽ�Ǥ���
- DV�ˤϾ�˽Ҥ٤������ѤΤ�Ρ�SD�ˤȡ��ϥ��ӥ�����ѡ�HD���ѤΥե����ޥå�HDV���ʤ�����ޤ������ǥ�����ӥǥ����� ���ȡ���
- ��
- ����DV��MPEG-2
- �ǥ�����ӥǥ��ơ��פ���¸����DV�ȡ�DVD�˺��Ѥ���Ƥ���MPEG-2����٤�ȡ�DV�Υӥåȥ졼�Ȥ���25Mbps�Ǥ���DVD��8Mbps����٤�3�ܶ��Υǡ����̤ˤʤ�ޤ���
- DV�ϻ��ְ��̤ʤ�Motion JPEG���Ȥ��Ƥ���Τǡ��ǡ����̤�¿���ʤ�ޤ���
- ȿ�̡����ְ��̽�����Ԥ�ʤ��Τǽ������֤�®������������ľ�˹Ԥ����Ȥ��Ǥ��ޤ���
- 2010ǯ������̱���ѥǥ����륫���λԾ�Ƥߤޤ��ȡ�DV�ơ��פ�Ȥä��ǥ�����ӥǥ������������ϤۤȤ�ɹԤ��Ƥ��餺��HDD��ե�å�����ꡢDVD���Ѥ���MPEG-2Ͽ��Υӥǥ�����餬��ή�ȤʤäƤ��ޤ���
- ����ή��ϡ�MPEG-2����/���ब���ȥ쥹�ʤ��Ԥ���ޤ����֤ι�®�����ʤ�����Ȥȡ����Ѥ��뵭Ͽ��ǥ����������������ꥳ��ԥ塼����DVD���֤Ȥ��������褤���ȡ���Ͽ���֤�����Ū��Ĺ���Ȥ��褦�ˤʤä����Ȥ������ͳ�ȹͤ��ޤ���
- ��HDV��High-definition Video�ˡ�
- HDV�ϡ�2003ǯ��DV���ʤ������Ȥ��ƺ��줿�ϥ��ӥ����Ͽ��ΤǤ��뵬�ʤǤ���
- HDV�ˤĤ��Ƥϡ��ϥ��ӥ����ǥ�����ӥǥ���HDV�˿����ν�Ǥ�ܤ�������Ƥ��ޤ���
- DV�����ʲ������Ȥ��ˡ��ϥ��ӥ���������̱���ӥǥ�������Ȥ߹��ळ�Ȥ���θ����Ƥ��ơ�DV���ʤdz�ȯ���줿�ǻҤ�ơ��פʤɤ����¤����Ѥ��뤳�Ȥ�������ޤ�Ƥ��ޤ�����
- ���äơ����Ѥ���DV�ơ��פ�Ʊ����Τ�Ȥ����Ȥ�����Ǥ�����
- ��������˽��äƥϥ��ӥ�����б����ޤ��ޤ�����
- ���Τ�����礭�ʵ��ʤȤ��ơ�Ͽ��ե����ޥåȤ�MPEG-2�����Ѥ���ޤ�����
- DV��Motion-JPEG����Ѥ��Ƥ����Τ��Ф���HDV�Ǥ�MPEG-2����Ѥ��ޤ�����
- �ϥ��ӥ����ˤ�Motion JPEG�ե����ޥåȤǤϲ٤��Ť����ޤ�����
- 2010ǯ�ˤ��ä�HDV���ʤΥӥǥ��������ϡ����ߥץ����Ѥ��̳�Ѥι���ʵ�������˸¤�졢�²��ʥ�ǥ�ϰʲ��˼���AVCHD���ʤΥӥǥ�����������ή�ȤʤäƤ��ޤ���
- ��
- ��AVCHD��Advanced Video Codec High Definition�ˡۡ���2010.07.10����
- AVCHD�ϡ�HDV�����Ѥ��Ƥ���DV�ơ��פε�Ͽ��ˡ�ˤ�����뤳�Ȥʤ������ޤ��ޤʵ�Ͽ��ǥ������б������ⰵ�̡������Υϥ��ӥ���ʤǤ���2006ǯ�˥ѥʥ��˥å��ȥ��ˡ��ζ�Ʊ�Ǵ��ܻ��ͤ����ꤵ��ޤ�����
- AVCHD�δ��ܹ��Ҥϡ�ư�����ե����ޥåȤ�H.264/MPEG-4 AVC����Ѥ��������ǡ�����ѥ�����Υե���������Τ褦�ʥĥ��¤�Ȥ��Ƥ��뤳�ȤǤ���
- �ơ���Ͽ�������Υ����Ͽ��Ȥϰۤʤä���¸�����Ǥ���
- ���Τ��ᵭϿ����������PC�Ǻ������Խ�����Τ��Թ��ɤ��Ǥ����ޤ���
- MPEG-4 AVC�ϡ�2010ǯ�ˤ����ƤϺǤ��Ψ�Τ褤��Ͽ�ե����ޥåȤǤ���
- ��Ͽ��ǥ����ϡ�����Ū�ˤ�80mm�¤�DVD�Ǥ��ꡢ���Τۤ���SD�����ɤ�HDD�ʤɤ��б��Ǥ���褦�ˤʤäƤ��ޤ���
- 2010ǯ���ߡ�̱���ѥӥǥ����ॳ�����ΤۤȤ�ɤϤ��ε��ʤΤ�ΤȤʤäƤ��ޤ���
- �����ʤ���720x480���Ǥ�NTSC���ʤ�4:3�β��̥����ڥ�����ˤʤ�Τ���������2007.04.15���ˡ�2010.07.10�ɵ���
720 : 480 = 4 : 3 �ˤʤ뤫�����Ȥ�������Ǥ���
- ����Ϥʤ�ޤ���
- 720 �� 480 �ϡ�3 �� 2 �Ǥ��ꡢ4��3�ˤʤ�ޤ���
- ����ʤΤˡ�4:3�β��̥����ڥ��������DV���ʤǤϤʤ�720���ǣ�480���ǤˤʤäƤ���ΤǤ��礦����
- �������Ѥʼ���������륵���ȤϤʤ��ʤ�����ޤ���
- �����ԻĤʵ���ϡ�NTSC���������ʤ��ǥ�����˰ܹԤ���Ƥ��������Ǥ���̯�ʥ��줫����Ƥ��ޤ���
- �ޤ���NTSC�ϡ����̥����ڥ����椬 4 : 3 �ȸ��ʤ˷����Ƥ��ޤ���
- ��������������525�ܤǤ��뤳�Ȥ�����Ƥ��ơ����줬�Ĥβ����Ϥ���ꤷ�Ƥ��ޤ���
- �Ĥ�525�ܤβ����Ϥ��鴹�����ơ������ڥ����椫�鲣�β����Ϥ�����700�ܤȤʤ�ޤ���
- CCD����餬�������Ѥ˺��줿�Ȥ���CCD����ϡ����ε��ʤ�ʻ���������ǻҤ������Ȥ����Ϥ��Ǥ���
- ���������ǽ餫�餳�Τ褦�ʹ���Ǥ�CCD���뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���Ǥ�����
- �������β��Ǥ�525�ܤ���������ͤ����525�Ĥβ��Ǥ�ɬ�פ��Ȥ��Ƥ⡢�������Ϥ��������������Ǥ����֤�������ε��Ѥ�����ޤ���Ǥ�����
- ���ˡ���1980ǯ�˺ǽ�˺�ä�CCD�ϡ�381���ǣ�525���ǡ�20�����ǡˤ��ä��ΤǤ���
- ���������NTSC�Υ����ڥ��������������ˤϡ�381�Ĥ����ʤ��������β��Ǥ�Ĥβ��ǥ���������٤�1.38�ܤۤ�Ĺ�����ʤ���Фʤ�ޤ���Ǥ��������������аޤ�Фơ������Ϥ���ޤäƤ����Ȳ��ǿ���ɤ�ɤ����䤻��褦�ˤʤꡢ�������β��Ǥ�¿��CCD�������褦�ˤʤ�ޤ�����
- �Ĥβ��Ǥ�525�Ĥȷ����Ƥ���Τǡ���������䤹���ȤϤǤ��ޤ���
- ���äơ����β��Ǥ����䤷�ƿ�ʿ�����Ϥ������Dz���̤����ƹԤä��ΤǤ���
- ����ϡ��ͤޤ�Ȥ�����1�Ĥβ��ǤΥ����ڥ��ȥ쥷������ʿ�����Ϥ�����ʲ��ǿ��������Ƥ������ȡˤˤ�ä��Ѳ����Ƥ��ä����Ȥ�ʪ��äƤ��ޤ���
- ���Ǥ����ǽ�ϲ�Ĺ���ä��Τ˹���Dz��ˤʤ�˽�����Ĺ�ˤʤäƹԤä��ΤǤ���
- CCD����餬��¬�Ѥ˻Ȥ���褦�ˤʤäơ����Ǥ�1:1�Τ�Τ��Ǥ��Ƥ���褦�ˤʤ�ޤ�����
- �����ʻҷ������ǻҤȤ�����ΤǤ���
- ����ԥ塼����ȯã�ȤȤ�ˡ�����ԥ塼����Dz�������褦�ˤʤ�ȡ�����ԥ塼���˹�碌�����ǿ���CCD�Υ�������������褦�ˤʤꡢVGA�����˹�碌��640x480���Ǥ������ʻҡ�1���ǤΥ����ڥ����椬1:1�ˤ������褦�ˤʤ�ޤ�����
- VGA�Ǥβ��̤Υ����ڥ������4 �� 3 �Ǥ���������ԥ塼���������ϡ�VGA�ϡˡ������ڥ�����Ȥ��褽�β��ǿ���NTSC�����ޤ�������1���Ǥ��礭���������ʻҤȤ��ޤ�����
- ��1���� = �����ʻҡס����줬����ԥ塼�������λϤޤ�Ǥ��ꡢ�����β��̤�����Ω���Ȥ��礭���ۤʤ����Ǥ�����
- �����ʼ����ˤ��DV���ʤϡ���¬�ѡʥ���ԥ塼���ѡˤȤ��̤�ƻ�����Ǥ��ޤ�����
- �Ĥޤꡢ�����ͥ�褷1���ǤΥ����ڥ������1:1�Ȥ��������ǿ���ͥ�褷��720x480���ǤȤ��ޤ�����
- ����ˤ⤫����餺�����̤Υ����ڥ������4:3���ݤ��ޤ�����
- �Ȥ���ȡ�1���Ǥ���ˡ�νIJ��椬1:0.889�Ȥʤ�ޤ���
- ���ε��ʤ��¬�ѤȤ��ƥѥ�����˼������硢�ɤΤ褦�ʤ��Ȥ�������ΤǤ��礦��
- DV���ʤǤ�1���Ǥ��������Ȥߤʤ��Ƥ��ޤ��ȥ����ڥ����椬�Ѥ�ꡢ������ˡ���ºݤ���12.5%��Ĺ��ɽ������Ƥ��ޤ��ޤ���
- ����Ǥϡ����β���������ˡ���Ѱ̡�®�١����٤ʤɤ���뤳�Ȥ��Ǥ��ʤ��ʤ�ޤ���
- ����ϡ����̤α���������¬�Ѥ˻Ȥ��Ȥ������դ��ʤ���Фʤ�ʤ����פʥݥ���ȤǤ���
- ��¬�ѤˤϷ�¬�Ѥ�CCD�����ꡢ�����Ѥ䥢�ޥ��奢�ѥƥ�ӥ����ˤϷ�¬�ѤȤϰ㤦��ˤ��ʤ��ʤ���������β����ͥ�褷����CCD�����ä��Ȥ������ȤǤ���
- ��
- ��DVD-video�ۡʤǤ��֤��Ǥ��ӤǤ���������2010.7.10�ɵ���
- DVD-video�ϡ�DVD�˺��Ѥ���Ƥ���ư��ե�����ե����ޥåȤǤ���
- ���ʲ����طʤˤϡ���ǽҤ٤�DV�ʥǥ�����ӥǥ��ˤ�DVD�˵�Ͽ����Ȥ�����Ū������ޤ�����
- 2010ǯ�����ǡ��Dz衢�ƥ�ӥ���ƥ�Ĥ�DVDϿ���ǥ����Ȥ��ƺǤ�褯�Ȥ��Ƥ��������Ǥ���
- DVD�ϡ�CD��Ʊ��ľ�¤ȸ����ǡ�CD����7�ܤξ����Ͽ�Ǥ���ǥ������Ǥ���
- ����1�ؤ�4.7G�Х��Ȥα�����8Mbps��MPEG-2�ե�����ξ��ϡ���1����ʬ��4Mbps��MPEG-2�ե�����ξ����� 2����ʬ�ˤ�Ͽ�Ǥ��ޤ���
- ����2�ؤǤ��ܤε�Ͽ�Ȥʤ�ޤ���
- �����ε�Ͽ���֤ϤҤȤĤ��ܰ¤ǡ������μ��Ȱ��̤��ٹ礤�ˤ���Ѥ��ޤ���
- DVD-video�ϡ��ɤ߽Ф����Ѥ�DVD-ROM��DVD�ץ졼�䡼�Ǥκ�������ǽ�ǡ����٤��������DVD-R�����٤�����ΤǤ���DVD-RW�ʤɤ�����ޤ���
- DVD�Υ��ץꥱ������ʤǤϡ� �ʲ���3���ब����ޤ���
- ��
- ��������DVD-Video
- ��������DVD-VR(Video Recording)
- ��������DVD-Audio
- ��
- DVD-Video �ϡ������� MPEG-2 ����Ѥ��������������ѵ��ʤǤ����Dz���DVD�Ȥ��ƺǤ����Ū�ʤ�ΤǤ���
- DVD-VR(Video Recording)�ϡ�DVD-RW �� DVD-RAM ����Ѥ��ƱDz�ʤɤα�����Ͽ����ӥǥ��쥳���ɤε��ʤǤ���
- DVD-VRF�Ȥ�ƤФ�Ƥ��ޤ���
- �����ڤ��Ͽ�褬��ǽ�ǡ������٤�ʣ����480x480��544��480�ʤɡˤ����Ƥ��졢DVD-Video����ˤ����ʤǤ���
- DVD-VR�ϡ����ܤδ�Ȥ���ä��ȼ��ε��ʤǤ��ꡢ�����ʵ��ʤǤϤ���ޤ���
- DVD-Audio�ϡ������ǥ���CD��DVD�ǤǤ���������Ū�ǤϤ���ޤ���
- DVD�ӥǥ���DVD-Video�ˤϡ�ư�谵�̤�MPEG-2��Ȥ���133ʬ�α����Ȳ�������Ͽ���줿�ӥǥ��ǥ������Ǥ���
- ���ǿ�720�ԥ�����×480�ԥ����롢��ʿ��������500�����٤���ʵ��ʤǤ���
- �����ϡ��ɥ�ӡ��ǥ������AC-3�˥��饦��ɤȥ�˥�PCM�Τɤ��餫�Ǽ�Ͽ����ޤ���
- ���Τۤ��˥��ץ����ե����ޥåȤȤ��ơ�MPEG�����ǥ�����ǧ����Ƥ��ޤ���
- ����DVD-Video�Υե����빽��
DVD�ӥǥ���DVD-Video�˥ե�����ϡ�PC�ʥ���ԥ塼���ˤǸ��뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ��ʱ��̿����ȡˡ�
- DVD�ɥ饤�֤�DVD�ӥǥ��μ��ޤä�DVD�ǥ����������졢�������ץ�����dz����ȡ�
- ��
- ����[AUDIO_TS]��
- ����[VIDEO_TS]
- ��
- �Ȥ����ե��������ǧ�Ǥ��ޤ���
- [VIDEO_TS]�ե�����ˤϡ�
- ��
- ������IFO��
- ������BUP��
- ������VOB��
- ��
- �Σ���Υե����뤬���äƤ��ޤ���
- ��IFO�פϥ�˥塼�����ޥ������ʤɤ��������ե�����Ǥ���
- ��BUP�פϡ�IFO����Υե����뤬��»�������ΥХå����åפǡ���IFO�פ�Ʊ���ե����뤬���äƤ��ޤ���
- ��VOB�פˤϱ����䲻��������ʤɤμ¥ǡ��������äƤ��ޤ���
- �̾�ϡ�PC��DVD�����������ȼ�ưŪ��ǧ�����ƺ�����Ԥ��ޤ���
- ��
- �ڥǥ������������ʡ�
- ���ε��ʤϡ��ƥ������ʬ��ǵ��ʲ�����Ƥ����ƥ�ӱ����Υǥ����뵬�ʤǤ���
- �ǥ������������ʤϡ��ƹ��͡��ʻ��Ǥ����ߥǥ����뵬�ʤ˾��Ф����Τ�1950ǯ��Υƥ��������Ʊ���������쵬�ʤȤϤʤ�ޤ���Ǥ���������������������Segment Broadcasting�����ȡ���
- ���ܤΥǥ������������ʤϡ�ISDB��Integrated Services Ditital Broadcasiting������ǥ��������������ӥ��ˤȤ�����Τǡ��������礭����4�Ĥβ����ʤ�1�ĤΤ��ޤ��ˤ����٤�褦�ˤʤäƤ��ޤ���
- 4�Ĥβ����Ȥϡ��ʲ��Τ�ΤǤ���
- 1.��480i����NTSC�α������������Ȥˤ���720x480���ǥ����졼������
- 2.��480p����720x480���ǥץ�����å�������
- 3.��720p�����ϥ��ӥ��������Ǥ���1280x720���ǥץ�����å�������
- 4.��1080i�����ϥ��ӥ��������Ǥ���1920��1080���ǥ����졼������
- �ʤ��������Ͼ�ǥ����������Ǥϡ��Ӱ�δط���1440x1080i�����ꡢ����¦��1920x1080i�˰�����Ф��Ƥ��롣��
- ���ޤ�5.��1��������320x240����ʬ�α���
- ���ε��ʤϡ��ǥ����������ȱվ�/�ץ饺�ޥƥ�Ӥ���Ƭ�ˤ�äƵӸ�����Ӱ���Ū�ˤʤ�ޤ�����
- �ʤ���ISDB�ˤϡ��Ͼ�������ǥ�����������ISDB-T�ˡ��Ͼ�ǥ����������ˤȱ�������������ǥ�����������ISDB-S�ˡʥǥ�������������ˤ�����ޤ���
- �ޤ����Ͼ��Ȥˤ���ư���̿������Υǥ�����������ISDB-T SB�ˤ䥱���֥�ƥ�Ӹ����Υǥ������������ʡ�ISDB-C�ˤ⤢��ޤ���
- �ǥ������������ʤϡ�����ԥ塼��ʸ�������Ǥ���AVI��QuickTime�ʤɤ�ư��ե�����ȤϾ����ۤʤäƤ��ޤ���
- �ƥ�������Ǥϡ��̿��Ӱ��30�ե졼��/�äκ���®�٤��Ǥ���פʻ��ͤǤ��ꡢ�����1945ǯ�˷���줿���ʥ�����NTSC�������椫��©�Ť��Ƥ����ΤǤ���
- ���������ϡ�30�ե졼��/�äλ��ơ�����®�٤�ݻ����Ƥ����˹��ߤ˲�����ɤ�Ͽ��Ⱥ�����Ԥ��������Ѥο����Ǥ��ꡢ���Τ���ˤ��������ʰ��̵��Ѥ���ȯ����ޤ�����
- ���䥳��ԥ塼��ư��Ǥϡ��Ż߲��ư���դ�����꤫���ȯ���Ƥ��ޤ���
- ���ǿ������®�٤�ʤ��«�������ΤϤ���ޤ���Ǥ�����
- �ޤ����ƥ��������2����Ͽ�����������ʤ���ư�赭Ͽ��������Ƥ���Τ��Ф�������ԥ塼��ư��Ϥ�������10ʬ���٤���������Ƥ��ޤ�����
- �ʤ�û���Τ��ȸ����С�����ԥ塼���κ���ǽ�ϡ���¸ǽ�ϡ�ž��ǽ�Ϥ��ɤ��Ĥ��ʤ��ä�����Ǥ���
- �����ƥ����������β�����¬
- �ƥ�������ϡ��ӥǥ�Ͽ�����֡ʥӥǥ��쥳������DVD�쥳������BD�쥳�����ˤ��ߤ��뤳�Ȥ���ǽ�ǡ������DVD��Blue-ray�ǥ�������MPEG-2�ե����ޥåȤȤ�����¸���뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
- ������¬�ѤȤ��ƻȤ��뤫�Ȥ������Ѥʵ��䤬�來�ޤ���
- MPEG-2�β�����¬�ؤθ³��Ϥ��Ǥ˽Ҥ٤ޤ���������������¬�Ȥ��Ƥ�MPEG �ˡ�
- �ƥ�������ˤϡ������Υ��졼��������䡢�����ڥ��ȥ쥷�������ꡢ���ԡ�������ʤɤ�������äƤ��ơ������ν������ʬ�˹�θ����������ɬ�פǤ���ȹͤ��ޤ���
- ��
- ��HEVC��High Efficiency Video Coding�ˡ�������2018.11.07��
- HEVC�ϡ�H.265/MPEG-H Part2�θƤ�̾�ǡ�AVC��MPEG-4 AVC/H.264���θ�ѤȤʤ�ư��ե�����Ǥ���
- 2103ǯ��JCT-VC��MPEG & VCEG Joint Collaborative Team on Video Coding�˥��롼�פˤ�ä����ꤵ��ޤ�����
- AVC�����2�ܤΰ��̸�Ψ��Ʊ���̿��Ӱ��2�ܤβ����ϡˤ������8192 x 4320���ǤޤǤ��б���ǽ�Ȥ���4K����8K�������ǰƬ�ˤ��줿��ΤǤ���
- HEVC����������פ�OS�ˤϡ�Widnows10��Mac OS High Sierra, iOS 11���б����� �ޤ���
- HEVC�ϡ��õ������������꤬ʣ��������Ǥ��ơ�H.264�Τ褦��ñ�쵡�ؤؤ��õ�ȯ���ȤϤʤ餺��ʣ���γ�ȯ���Τ������ԻȤƤ��뤿����Ѥˤ����äƤϤ��줾������Τ��õ���������ɬ�פȤʤ�ޤ���
- ���줬���ꥢ�ˤʤ�ʤ�����ڤ����ȴ����ޤ���
- ��
��
- ���˥�˥塼�С�������ʤ���硢
- ������å����Ʋ�������
- ��
- �� �� �� ��
- �����������ŻҲ����ˤε�Ͽ����������2007.09.11�ˡ�2010.08.08�ɵ���
- �ŻҲ����ʥӥǥ������ˤ�Ͽ�������ΤˤϤɤΤ褦�ʤ�Τ����ä��ΤǤ��礦����
- ���ι��ܤǤϡ��ŻҲ����˻Ȥ��Ƥ�����Ͽ���ΤˤĤ��ƽҤ٤����Ȼפ��ޤ���
- �ŻҲ�����Ͽ�������Τ���ɽŪ�ʤ�Τϡ�Ŵ�μ����Ρ��ץ饹���å��פ�Ȥä�����Ͽ��ȾƳ�Υ����3�Ĥ�����ޤ���
- ������3�Ĥε�Ͽ���Τ�ȯã�������ˤϥե����ʶ��������ˤ��Ȥ��Ƥ��ޤ�����
- ��
- �����ե����λ���
- �ƥ�ӥ���餬��ȯ���줿�����1940ǯ��ˡ��ƥ�Ӳ�����Ͽ�褹�����ƤϤ���ޤ���Ǥ�����
- �ƥ�������ȸ����С����Ƥ�Ʊ���˱���Ϥر������������饤�ֱ������ۤȤ�ɤ��ä��ΤǤ���
- ������1960ǯ���ޤǡˡ�������Ͽ�������������Ƥȸ����С�ͣ���Ͽ�����ΤǤ��ä��ե����ʶ���ˤ����ʤ��ä��Τǡ��饤�֤ˤǤ��ʤ������ϱDz襫���ǰ�ö���Ƥ��Ƶ�Ͽ���������ե��������ˤʤä���Τ��ƥ쥷�����֤Ȥ����������ü�ƥ�ӥ����=�ե饤�����ݥåȡ�������ʡ����ǥƥ�ӿ����ľ�����������Ƥ��ޤ�����
- ���������ˤ�������ϡ�2005ǯ������ޤǹԤ��Ƥ��ޤ�����
- ���ޡ������ե����ϡ�35mm�Dz襫���ǻ��Ƥ��ơ������ƥ쥷�ͤȤ������֤ˤ������������Ƥ��ޤ�����
- �ޤ������������ʤɤǥƥ�ӥ�����Ȥä�����������Τ�Ͽ��¸���������ˤϤɤ����Ƥ������ȸ����ȡ��Dz�ե�����ȤäƤ��ޤ�����
- �������֤ϡ��ե������������ɤ��ü�ָ��̤���ä��Ĥߤξ��ʤ��ƥ�ӥ�˥��ʥ֥饦��ɡˤ˥ƥ�ӱ�����Ǥ��Ф���������ü�ʥե���५���ʥ��ͥ쥳���� = Kinescope Recording�ˤǥե����˻��Ƥ��Ƥ��ޤ�����
- ���ͥ쥳���֤Ȥ����Τϡ����ߤǤ⤵����˻Ȥ��Ƥ��ޤ���
- �Ƕ�αDz��CG�ˤ���ŻҲ�����¿���������ե����˾Ƥ��դ���ݤ˥ǥ����뿮�椫��졼����Ȥäƥե�����ľ�ܾƤ�����Ǥ��ޤ���
- ��Ͽ�λ����ϡ��ե������٤��졼���ӡ����������ʥ�����ˡ��ƥ�Ӳ�����ɽ���Ȼ����褦���������̵�Ͽ���Ƥ��ޤ���
- ���ߤαDz�θ��ܤϥǥ��������¸����Ƥ��ơ�����Τ褦�˥��ꥸ�ʥ�ͥ��ե�������¸����Ȥ����ΤǤϤʤ��褦�Ǥ��� ����→���ե����ˤ�뵭Ͽ�عԤ���
- ��
- ��
��
- �� �� ��
- ���������Τˤ�뵭Ͽ
- �ƥ�ӱ�����Ͽ���Żҵ�Ͽ�ˤ���ƹԤä��Τϡ�����Ŵ�ˤ�뼧���ơ��פε�Ͽ���֡����ʤ���ӥǥ��ơ��ץ쥳������VTR = Video Tape Recorder�ˤ���ȯ���줿1956ǯ�Ǥ���
- ����ʴ�Τ��ŵ�����ε�Ͽ�˻Ȥ���Ȥ���ȯ����1898ǯ�ˤ����ä�VTR���о�ޤǡ�58ǯ��ǯ��ФäƤ��ޤ���
- ��������Ͽ����Ȥ����Τϡ��ȤƤĤ�ʤ����ѳ�ȯ���ä��Τ˰㤤����ޤ���
- ���ι��ܤǤϡ������Τ�Ȥä���Ͽ���Ρʼ����ơ��ס��ե��åԡ��ǥ��������ϡ��ɥǥ������ʤɡˤ���ɤäƾҲ𤷤����Ȼפ��ޤ��� →���ּ����Τˤ�뵭Ͽ�פعԤ���
- ��
- �������ˤ�뵭Ͽ
- 1980ǯ�夫��ϡָ��פˤ�뵭Ͽ�������졼����Ȥä���Ͽ��ȯŸ���ޤ���
- �졼����ȯ���ʤ����Ƹ��ߤα�����Ͽ����ˤϤ������ޤ���Ǥ�����
- �졼����ȯ���ȥ���ԥ塼����ȯã�ʥǥ����뵻�ѡˤ����ε�Ͽ����٤���Ĺ�����ޤ�����
- ���ι��ܤǤϡ��졼����Ȥä��������֡ʥ졼���ǥ������ˤ���CD��MO��DVD��Blu-ray����ħ��Ҳ𤷤����Ȼפ��ޤ���
- �����ָ��ˤ�뵭Ͽ�פعԤ���
- ��
- ����ȾƳ�Τˤ�뵭Ͽ
- ȾƳ����¤���Ѥ���®��ȯŸ��뤲���桢�ȥ������Ͽ���ΤȤ����ˡ���ͤ��Ф��졢ȾƳ�Υ���Ȥ������ܤ��褦�ˤʤ�ޤ���
- ȾƳ�Υ��꤬�����Ӹ�����Ӥ��Τϡ��ե�å��������о줫��Ǥ��礦��
- ����ޤǤϡ�ȾƳ���ǻҤ�Ȥä���Ͽ�Υ����ǥ��Ϥ����Τα�����Ͽ�����ǥ����Ȥ��ƻ��Ѥ���ˤϡ��礭������ʤ�Ȥ���������Ū�ǤϤ���ޤ���Ǥ�����
- �ե�å�����꤬��ȯ���������ȾƳ�Υ���ϡ�����ԥ塼���˻Ȥ��Ƥ���DRAM�˸�����褦�ˡ��Ÿ����ڤ�ȥ������Ƥ��ä��Ƥ��ޤ���ΤǤ����� �ե�å������ϡ��Ÿ���̵���Ƥ�ǡ������ݻ���³����Ȥ����礭����ħ����äƤ��ޤ����� ������ȾƳ�Τˤ�뵭Ͽ���عԤ��� �� ��
- ��
- �� ��
- �����Τˤ�뵭Ͽ
- ������Ͽ�Ȥ���������ʤ���®�������̤Υǡ������Ż�Ū����¸�����ˡ�ϡ�����Ŵ�ˤ�뼧���Τμ�����Ͽ�ˤ������ޤ���
- ����ޤǤϡ��ʱDz�˥ե����ʶ���̿�������ˤǤʤ���ФǤ��ʤ����ȤǤ�����
- ������Ͽ���뼧���Τϡ��ӥǥ��ơ��פ�ȯ������Ϥޤ�ޤ���
- ����ϡ������ơ��פ��Ǥ��Ƹ��24ǯ�Фä�1956ǯ�Τ��ȤǤ���
- �ӥǥ��ơ��ץ쥳������ȯ���¿�ζ�ϫ������ޤ�����
��
- �� ��
- �ڼ����ơ��ס� ��2008.08.17�ɵ��� ��2008.12.07�ɵ���
- ��
- ���������ơ��פγ�ȯ
�ӥǥ��ơ��פϡ������ѥӥǥ��ơ��ץ쥳������VHS�ơ��פʤɤǹ����Τ��Ƥ���褦�ˡ������Ρʵ�Ͽ���Ρˤ����Τ褤�ݥꥨ���ƥ�ե����ʻٻ��Ρˤ����ۤ�����ΤǤ���
- �ӥǥ��ơ��פϡ������ѡʥ����ǥ����˥ơ��פ����������ޤ�����
- �����ǥ����ơ��פγ�ȯ�ϡ�1930ǯ����ɥ���BASF�ҤǻϤ��졢�ӥǥ��ơ��פϡ�1950ǯ���Ⱦ���ƹ�3M�Ҥ���Ω���ޤ�����
- 1970ǯ�夫��ϡ����ܤΥ���������ơ��׳�ȯ����¤�μ���ˤʤ�ޤ�����
- 2000ǯ�ʹߤμ����ơ��פϡ��ǥ�����ơ��פȤ��Ƥΰ��֤Ť����礭���ʤäƤ��ޤ���
- ���������ơ��פ����
- �����ơ��פγ�ȯ�����Ū�˸��Ƥߤޤ��ȡ������Τ��ŵ�����ε�Ͽ���ΤȤ��ƻȤ���ˡ��1898ǯ���ǥ�ޡ�����Valdemar Poulsen�ʥݡ��륻��1869 - 1942�ˤˤ�äƳ�ȯ����ޤ���
- ��ϡ���������Ĺ�������Ӥ�Ͽ���Τ˻Ȥä������磻���쥳������ȯ�����ޤ�����
- �ơ��פǤϤ���ޤ���
- �����ϡ������ץ饹���å��ե������뵻�Ѥ��ʤ��ä��ΤǤ���
- �������Ρʼ����磻��ˤϡ��������ʤ��顢��Ͽ̩�٤��㤯�ƻ�����¿����1970ǯ��Υ����ǥ����ơ��פ���٤�1000�ܶ���äƤ����ȸ����Ƥ��ޤ���
- �ݡ��륻��ϡ�����ꥫ�Υ�������ȯ�������߲�����Phonograph��1877ǯ�ˤȥ٥뤬ȯ���������õ���Telephone��1876ǯ�ˤ����ۤ����ơ����õ���Ͽ���ѤȤ��Ƥ������֤�ȯ�����õ�����ޤ�����
- ���Ͽ�����ϡ����äơ�Telegraphone�סʥƥ쥰��ե���ˤȸƤФ�ޤ�����
- ����Ͽ�����ϡ��ŵ������郎�ʤ��ƿ��椬�夯��������ɬ�פʻ��˿����ɤ�ȯ���ϡ�30ǯ���1906ǯ�Ǥ����ˡ�����˥磻�������ޤä��ꤷ��Ͽ���ο��������㤤��ΤǤ�����
- �������֤ϡ��õ����ڤ��1918ǯ�ޤǤ���ۤɤ���ڤ���1924ǯ����¤����ߤ��ޤ���
- ����ꥫ�Ǥϡ�1950ǯ���溢�ޤǷ����濴�Ȥ��Ƽ����磻��������Ͽ�������Ȥ��Ƥ����褦�Ǥ���
- ��
- �����ɥ��ĤΥơ��ץ쥳������ȯ
- �ڼ����ơ��פγ�ȯ��
- Ͽ�����θ��泫ȯ�ϡ���Telegraphone�פ��õ����ڤ��1918ǯ�ʹߺƤӻϤޤꡢ1932ǯ�˥ɥ��ĿͤΥ��˥� Fritz Pfleumer�ʥե�åġ��ե����ޡ���1881.03�� 1945.08�ˤ��ơ��������ˤ��Ͽ������ȯ�����ޤ���
- �������֤ϡ����顢��ơ��פ�ȤäƤ��ơ�����˻���Ŵ�μ�����ʴ���å������Ϥ��������ۤ�����ΤǤ�����
- �ץ饹���å��ơ��פϡ������ε��ѤǤ������ƶ��٤Τ����Τ����ʤ��ä��ΤǤ���
- ��ϡ��洬�����Х�����������Ѥ���äƤ����褦�ǡ����ε��Ѥ���Ѥ����褦�Ǥ���
- ��ϡ�������������õ���ɥ��Ĥ�AEG�ҡ�Allgemeine Elektrizitats-Gesellschaft���������ɥ��ĤκǤ��礭���ŵ����)�����ޤ���
- AEG�Ҥϡ�������Magnetophon�ʥޥ��ͥȥե���ˡפȤ�������̾�ˤ��ơ��ơ��ץ쥳���������˽Ф��ޤ�����
- ���Υơ��ץ쥳�����ϲ��ɤ��Ťͤ�졢BASF�ҡ�Farben�һ���)�ζ��Ϥˤ�꼧���ơ��פ���ɤ���ơ����������ȥ�α��դ������ڤ�Ͽ���˻Ȥ���ޤǤˤʤ�ޤ�����
- BASF�Ҥ��礭�ʲ��ع��Ȳ�Ҥǡ����β�Ҥˤϥơ��פλٻ��ΤǤ��륢���ơ��ȥե�����Acetate film��1920ǯ����������1924ǯ�֥�ƥ��å��塦����ˡ����ҹ��Ȳ��ˤ���¤���ѤȽ��٤ι⤤������ʴ���ʥ����ܥ˥�Ŵ��Fe(CO)5��Carbonyl Iron�ˤ��뵻�Ѥ���äƤ��ޤ�����
- �����ơ��פ���¤�ˤϡ��ɼ��ǰ��ꤷ���ե����١�����ɬ�פ��ä��ΤǤ���
- �����ơ��פ�ɸ��ٻ��ΤȤʤä��ݥꥨ���ƥ�ե�����Polyester film��1941ǯ�ѹ�ꥳ�ץ�����ҳ�ȯ��1953ǯ�ƹ�ǥ�ݥ���õ������ˤϡ���ˡ���������ˤ�Ƥ褯��������פʤΤǸ��������������ե������ơ��פ��뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
- �������������Ϥޤ����κ����Ϥ���ޤ���Ǥ�����
- �ݥꥨ���ƥ�ե������о�ϡ�1960ǯ�ʹߤǡ����κ������Ǥ���ޤǤϥ����ơ��ȥե���ब��ή�ȤʤäƤ��ޤ�����
- AEG�ҤΥޥ��ͥȥե���������ˤϡ�BASF�Ҥμ����ơ��׳�ȯ�θ��Ӥ��礭���ä��ȸ����Ƥ��ޤ���
- �����Τϡ������ܥ˥�Ŵ����ޥ��ͥ����ȡ�Fe3O4�ˤ��夨���ơ����ɤ��פ�Ĥ��ޤ���
- ��
- ����AC�Х�������Ͽ��AC bias method��
- �ޤ����������Τؤ�Ͽ�����Ѥˤ���ɤ��ä����ơ����������夷�ޤ�����
- ���β��ɤȸ����Τϡ�������������Τ˵�Ͽ���������β��ɤǤ���
- ������Ͽ�ϡ�ľή�Х�������DC bias�ˤȸƤФ���ˡ��Фơ���ή�Х�������AC bias��ˡ����ȯ����ޤ���
- ����ˤ�ꡢ����������Ū�˸��夷�ޤ�����
- �ޥ������ۥ齦�ä���������Τޤ����Τ˵�Ͽ������ˡ�ϡ�������Ͽ�������Ǥ������餫����Ƥ��ޤ�������˧������̤�Ĥ��ޤ���Ǥ�����
- �����Τˤϡ��ҥ��ƥꥷ���Ȥ������������ꡢ���Ϥο�����Ф������������㤷����Ͽ���Ǥ��������������Ͽ�����ʬ���ߤäơʤʤޤäơˤ��ޤ��ޤ��ʱ��ޡ��̾�μ���Ͽ�����ȡˡ�
- ����ʿ���Ǥϡ������Τ˽�ʬ�ʼ��Ϥ�Ϳ���뤳�Ȥ��Ǥ��ʤ��ΤǤ���
- �����Τ˽�ʬ�˼����Ǥ�������μ�«���ͥ륮����Ϳ������ˡ�Ȥ��ơ��ŵ������ͽ�������Ű���Ϳ���Ʋ��̤�����������ˡ�ʥХ�����������ˡ�ˤ��ͤ��Ф���ޤ����ʡ�DC�Х�����ˡ�ˤ�뼧��Ͽ�����ȡˡ�
- ������ˡ����Ѥ���ȡ�����ʿ��椫���礭�ʿ���ˤ����빭���ϰϤ����Τλ��ĥ�˥���ľ������ʬ�˼���뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
- ������ˡ�ϡ�Ͽ���������Ͽ���˰�����Ű���ä����Τ�ľή�Х�������DC bias��ˡ�ȸƤФ�ޤ�����
- ��
- �����Х�����ˡ DC
- �Х�����ˡ�ϡ�1907ǯ���ǥ�ޡ�����Valdemar Poulsen�ʥݡ��륻��ˤ���ȯ���ޤ���
- �ǥ�ޡ��������õ��դǤ��ä���ϡ���ʬ��ȯ������Ͽ�����ǥӥ��ͥ������������褦�ȥ���ꥫ���Ϥ�ޤ��������Ԥ˽����ޤ���
- �������������DC�Х�����ˡ��ͰƤ��ơ������Τ�Ȥä�Ͽ����ˡ�ˤ������٤��ܽ�Ƥޤ�����
- DC�Х������ˤ�뵭Ͽˡ�ϡ��ɥ��ĤΥơ��ץ쥳���� Magnetophon�ʱѸ�̾��Magnetophone�ˤˤ���Ѥ���ޤ�����
- �������������֤μ��ȿ������ϡ�50Hz �� 5kHz�ǡ������ʥߥå����40dB����Ψ��5%���ä������Ǥ���
- �����ʥߥå����40dB�Ȥ����Τ�1:100�Ǥ��ꡢ���β�����Ͽ�Ǥ������Ȥˤʤ�ޤ���
- 1:1000��= 60dB�����٤ˤʤ�ȡ��ʤ�Ȥ���Τˤʤ��ͤǤ����顢������Ͽ�����Ϥޤ��ޤ������������ä��ȸ����ޤ��礦��
- ���ˡ��ޥ��ͥȥե���ȯ���줿������AEG�ҤϤ�������������˻Ȥä��ߤ����Ȥ�����˾����äƤ��ޤ�������������78��ž�Υ쥳���ɡ�SP�� = Standard Player Disk�ˤ���٤ƤϤ뤫�˲����������ä����ᡢ���Ѥ���ޤ���Ǥ�����
- �ޤ���DC�Х�����ˡ�ˤϡ�����Ū�ʷ���������ޤ�����
- ���μ�ˡ�ϥХ������Ű��Ĥ����ˤ����Ƥ���Τǡ�����̵���Ȥ��Ǥ⼧���ơ��פˤϰ�����Ű����ä�ä�Ͽ������뤳�Ȥˤʤꡢ̵���Ǥ���Ϥ��ν�Ǥ⥸���Ȥ������������Ȥ����ҥ��ƥꥷ���Υ�������äƤ��ޤ��ΤǤ���
- ��
- ������ή�Х�����ˡ
- ����Ͽ���ʼ����Ѥ����Τ�����ή�Х�����ˡ��AC bias method�ˤǤ���
- AC�Х������ϡ�1935ǯ�˥ɥ��Ĥ�BASF�Ҥdz�ȯ����Ƥ��ޤ���
- ���줬��ȯ���줿����ϡ����ʲ��ˤϤۤɱ���ǽ�Ǥ��ä�����BASF�ҤϤ��θ�������Ǥ��ޤ���
- AEG�Ҥ�BASF�ҤȤ��̤δ�������Ʊ��ȯ���ޤ�����������Τˤʤ�ޤ���Ǥ�����
- 1940ǯ�ˡ��ɥ���������Ҥ�RRG�ҡ�Reichs- Rundfunkgesellschaft�ˤ�������ˡ����ٻ�ߤƴ����������ޥ��ͥȥե���˰ܿ��������ʲ��ˤ����失�ޤ���
- �ޥ��ͥȥե���˺��Ѥ��줿AC�Х�����ˡ�ϡ������ơ���Ͽ����ǽ������Ū�˸��夵���ޤ�����
- AC�Х������ˤ��ơ��ץ쥳�����μ��ȿ������ϡ�50Hz �� 10kHz�ޤǿ��ӡ������ʥߥå���� 65dB�� = 1:1780�ˤȤʤꡢ��Ψ��3%�˲�������ޤ�����
- 65dB����ǽ�Ϥ�äѤʿ��ͤǤ���
- AC�Х�����ˡ�ȸ����Τϡ�100kHz���٤οʹ֤μ��ˤ�ʹ�����ʤ�����Ȥ������Ͽ���˽Ť�碌�ơʽž������ơ˼������Τ�Ͽ���������ΤǤ���
- ������ˡ�ˤ��ȡ�100kHz�ι������ʬ�Υ���٥�����������������¦���ӡˤ�2�Ĥβ������椬�������졢�ҥ��ƥꥷ������������¦�����¦�ˤޤ����ǵ�Ͽ����ޤ��ʱ��ޡ�AC�Х�����ˡ�ˤ�뼧��Ͽ�����ȡˡ�
- 2�Ĥε�Ͽ����ϡ���������Ŭ�ڤʽ������ܤ����ȡ��϶�������Ȥʤꡢ�Υ�����ʬ�����Ǥ���褦�ˤʤ�ޤ��� �ޤ���̵���ξ�硢2�Ĥβ���������ʬ�ν����ˤ�ä�̵�Ű����椬������Τǡ�DC�Х�����������ˤʤä��ҥ��ƥꥷ���Υ��������Ǥ�����åȤ�ФƤ��ޤ��� AC�Х�����ˡ�ϡ��Х����������100kHz�Ȥ��������μ����ơ��פˤϵ�Ͽ�Ǥ��ʤ��⤤���ȿ���ȤäƤ��ޤ��� ����ϡ������Τ��Ȥʤ����������ϵ�Ͽ�Ǥ��ޤ��� ��οޡʾ庸�ˤˤ⼨�����褦�ˡ������ơ��פε�Ͽ���ȿ���M Hz�ˤϡ��ǽ�Ū�ˤϼ������Τε�Ͽ̩�٤˱ƶ�������ΤΡ���������δ���Ū����«�Ȥ��ơ������إåɤΥ���åס�d mm�ˤȥơ������ԥ��ԡ��ɡ�V m/s�ˤǴ���Ū��Ͽ�����ȿ�����ޤ�ޤ��� ��
- M = V / ��2 x d�ˡ���������������Rec -39��
- M������Ͽ���ȿ���Hz V�����ơ���®�١�mm/s
- d���������إåɥ���åס�mm
- ����Ū�ʡ������Υ����ǥ����ѡ˼����إåɤζ���ʥ���åסˤϡ�10um��40um�Ǥ��ꡢ�ơ��פ�����®�٤� 45mm/s��190mm/s�Ǥ���
- ���ξ�狼��Ƴ���Ф���뵭Ͽ���ȿ��ϡ�560 Hz��9.5 kHz�ȤʤꡢAC�Х�����ˡ���Ѥ�����100kHz�μ��ȿ��ϤȤƤϿ�Ǥ��ʤ��ͤȤʤ�ޤ���
- ���äơ�AC�Х�����ˡ�Ǥϡ�����٥����ס��������ˤ������ơ��פε�Ͽ�ϰϤ��äѤ��˵�Ͽ����뤳�Ȥ�ͤ�ä���Τȹͤ��ʤ���Фʤ�ޤ���
- ������Ū�Τ���ˡ���Ͽ���ȿ��˱ƶ���Ϳ���ʤ��Ϥ뤫�˹⤤�ʵ�Ͽ���ȿ���5�ܰʾ�˸�ή���äƲ�������ȽŤ�碌�ơ���Ͽ��������������Τȹͤ����ޤ���
- ��ή�Х�����ˡ��AC bias method�ˤϡ��ɥ��ġ�����ꥫ�����ܤ�Ʊ���������̡���ȯ�����줿�褦�Ǥ���
- �ʾ��ޤȤ��ȡ�AC�Х�����ˡ��DC�Х�����ˡ����١��ʲ���ͭ���ʲ������ߤȤ���ޤ��� ��
- ��AC�Х�����ˡ����ħ��
- �������������
- ��������S/N����
- ���������ҥ��ƥꥷ���Υ������㸺
- ���ܤˤ�����AC�Х�����ˡ�γ�ȯ�ϡ�1938ǯ��������ؤαʰ���Ʊ��ؤ�´�Ȥ�����Ω�ŵ��θ���������ˤ�äƹԤ�졢���ܤǤ��õ�������Ƥ��ޤ���
- �����õ��ϡ���塢���ˡ�������������̿����ȳ�����ҡˤ��������ơ������Ȥä��ơ��ץ쥳��������ȯ����ޤ�����
- �����õ��Τ������ʤȥȥ�������Ѥγ�ȯ�ˤǡ����ˡ��ϲ���Ͽ�����������ƼԤˤʤäƹԤ��ޤ�����
- ��
- �����ƹ������
- Magnetophon�ʥޥ��ͥȥե���ˤϡ��������������桢�ɥ��ķ��ʥ����ν��פ���ά����Ȥʤꡢ�ʥ����δɳ�����饸��������¿�Ѥ����褦�ˤʤ�ޤ�����
- �������ʥ��ξ�����ƻ뤷�Ƥ���Ϣ�緳�Ǥ��������ʤ����ơ��ץ쥳������¸�ߤ��Τ餺���饸���������������������쥳�����ס�SP�סˤ�û����Ͽ�������ȿ����Ƥ����褦�Ǥ���
- ���äơ�SP�װʾ����ǽ����ä�Ͽ���ʤɤ��ꤨ�ʤ��ȿ���������ʡ�Ĺ�����ջ��֡ˤʤɤ������դ��ȿ����Ƥ����褦�Ǥ���
- �ƹ�Φ���̿����U.S. Army Signal Corps�ˤ�Jack Mullin�ʥ���å����ޥ��1913 - 1999�ˤ�������ֺݤ�1945ǯ�˥����ĥ������˼����줿�����Ѥ�AEG�Ҥ�Magnetophon��2��ȡ�BASF�����μ����ơ���50�������ꤷ�ޤ�����
- Mullin�ϡ�����Ͽ������ꥫ�˻��äƵ��ä�Ű��Ū��Ĵ�١����ɤ�ܤ��ƿ�����Ͽ��������ޤ�����
- ����Ͽ������ȯ�˴ؤ�ä��Τ����ƹ�AMPEX�ҤǤ���
- �����ơ��פ˴ؤ��Ƥϡ�Ʊ���3M�ҡ�Minnesota Mining and Manufacturing Company�ˤ� BASF�Ҥ�����ʤ���Τ�ȯ���ơ�Scotch�Υ֥��ɤ������Ϥ�ޤ�����
- AMPEX�Ҥϡ�VTR�ʥӥǥ��ơ��ץ쥳�����ˤγ�ȯ��ͭ̾�ˤʤä���ҤǤ���������ꥫ�Ǻǽ�˹��ʼ��Υ����ǥ����ơ��ץ쥳�������ä���ҤǤ⤢��ޤ���
- ���β�Ҥϡ������ǥ����ơ��ץ쥳������ȯ��¤�β��Ϥ����ä��Τǡ�VTR��ȯ�ˤ����Ǥ��ޤ�����1952ǯ�ˡ�
- ��������AMPEX�Ҥ������ǥ����ơ��ץ쥳������ȯ�����Ȥ��οͿ��ϡ����ä�6̾�Ǥ�����
- AMPEX�Ҥϡ�1944ǯ����Ω���줿��Ҥǡ���Ω����ϡ������⡼����ȯ�ŵ����äƤ��ޤ�����
- AMPEX�Ҥϡ��������ƹ�Φ���̿���λŻ��Ƥ����Τ�Mullin�Ȥ��̼������ꡢ�����Ϥι⤵��������ब�������ä��ޥ��ͥȥե��������Ĵ���ȹ쥳�����γ�ȯ��Ǥ���줿�ΤǤ�����
- �����ʤ��ƹ�ϡ��ɥ��ĤΥơ��ץ쥳������¸�ߤ��Τ�ʤ��ä��Τ�
- ��ŵ����Wikipedia Commons
- ��������������˥ɥ��Ĥdz�ȯ���줿�����ǥ����ơ��ץ쥳������Magnetophon�ˡ�1939ǯ�ˡ�
- �饸�������ɤǻ��Ѥ���Ƥ�����
- ���֤��ơ������Էϥᥫ�˥���䥹���å������֤ʤɤ�ȡ��������줿���ã���Ƥ��뤳�Ȥ����Ƽ��롣�ŻҲ�ϩ�����������ɤ�ȤäƤ�����
- �����ǡ����Ѥʵ��䤬�來�夬��ޤ���
- 1943ǯ�ޤǤδ֡�����ꥫ�������ƥե�������ꥹ�ʤɤ�Ϣ�緳�ϡ��ʤ�����ǽ�ʥɥ��Ĥμ����ơ��ץ쥳������¸�ߤ��Τ�ʤ��ä��ΤǤ��礦����
- �ޤ����ɥ��Ĥ����Ū�Ƥ����ä����ܤˤ����Ƥ⡢1930ǯ���Ⱦ����1940ǯ����Ⱦ�ˤ����ƥɥ��Ĥ�Magnetophon���Ѷ�Ū��͢�������Ȥ������¤ϸ�������ޤ���
- ���������ε�Ͽ��Ͽ���ˤȸ����С��쥳�����ס�SP�� = Standard Playing Disk��78��ž/ʬ�ˤ���ή�Ǥ��ꡢ����������1945ǯ�ˡ�����ŷ�Ĥ���̱�˸����äƥ饸���������ʤ����̲������ˤ�SP�פ�Ͽ��������Τ�ȤäƤ��ޤ�����
- ŷ�Ĥθ���դϡ��饸�����������Ǥ⼧���ơ��ץ쥳�����ˤ��Ͽ�������Ǥ⤢��ޤ���Ǥ�����
- �Dz�������Ǥ�̵���Dz褫��ȡ�������Talkie��1927ǯ�ˤʤä����˺��Ѥ��줿Ͽ�����֤ϡ����ؼ�Ͽ���ʱDz�ե�������ü�˲����˱�����ǻø����Ƥ��դ������������������פǸ��ζ��پ�����ŵ�����˴�����Ʊ�����������ˤǤ�����
- ���λ��¤�¦�ˤϡ������ơ��ץ쥳�������ʼ���1930ǯ���Ⱦ�ˤʤ�ޤǤ��ʤ갭���ä����Ȥ�Ǥ碌�Ƥ��ޤ���
- 1930ǯ���Ⱦ����1940ǯ����Ⱦ�ˤ����ơ�Ͽ�����֤���ǽ��ɥ��Ĥ���®���ɤ����ƹԤä�������ƹ�ϥꥦ�åɤ��ܤ�ܤ��Ƥߤ�ȡ��ϥꥦ�åɤϡ��쥳���ɤȸ���Ͽ���˴ؿ���Ƥ��ޤ�����
- �ɥ��Ĥǥơ��ץ쥳������ȯã���뤳�λ����ϡ�����Ū�ˤϥʥ�������Ƭ���ҥåȥ顼���濴�Ȥ��Ʒ�������礷����������������������ƹԤä�����Ǥ�����
- ����Ū��¦�̤���ͤ���ȡ����λ���������ꥫ��衼���åѤ⡢����������ܤ�Ͽ�����˼����Τ�Ȥ��Ȥ�����ˡ�����Ƥ��ơ���äѤ����Ͽ���ʱDz�ե���� = ������ɥȥ�å�Ͽ���ˤ����⤷���ϡ��쥳�����פ�Ȥä�Ͽ�����ܤ��������Ƥ����褦�Ǥ���
- �������ˡ������μ���Ͽ���ϲ����������ä��Τǡ�Ĺ����Ͽ���Ȥ���ñ��Ͽ��������
- �����Ʒ��Ӥ������Ȥ��������ʳ��ˤϡ��쥳���ɡ�SP�סˤ�����ͥ��Ƥ����褦�Ǥ���
- �ϥꥦ�åɤǥơ��ץ쥳���������ܤ����Τϡ����AMPEX�Ҥ��ɥ��Ĥ�Magnetophon��ʣ�����Ƥ���Τ��ȤǤ���
- �������ƹϡ�Marvin Camras��1916 - 1995������Υ�������ض�����Armour Research Institute������ˤ���ȯ���������磻���ˤ��Ͽ������¿�����Ѥ��Ƥ��ޤ�����
- ����ꥫ�Ǥϡ��ǥ�ޡ�����Valdemar Poulsen�ʥݡ��륻��1869 - 1942�ˤ���ȯ������Telegraphone�פ��������ޤ�Ƥ����Τǡ�����ή�줬�Ǥ��Ƥ����褦�Ǥ���
- �����磻���쥳�������ϡ������Ǥⷳ�����濴��1,000��ʾ��������졢����1956ǯ���ޤ�������³���Ƥ��������Ǥ���
- �ɥ��ĤǤϡ������ơ��פˤ��Ͽ��������®��ȯŸ���Τ��Ф�������ꥫ��Ͽ�����ϼ����磻���ΤޤޤǤ�����
- ����ꥫ�ˤϡ������������ץ饹���å��ե�����ȤäƼ����ơ��פ��뵻�Ѥ�����ޤ���Ǥ�����
- �����ꥹ�ϡ�1935ǯ��Marconi�ʥޥ륳���ˡ��ſ���Ҥ�ͭ̾�ʲ�ҡˤȤ��λҲ�ҤǤ���BBC�ʱѹ�������ҡˤ��濴�ˤʤäơ�����Ŵ�ơ��סʥե����ǤϤʤ�Ŵ���ˤ�Ȥä�Ͽ������ȯ���Ƥ��ޤ�����
- ����Ŵ�ơ��פϡ�3mm����50um�θ��������ꡢ1.5m/s���Ԥ�30ʬ�֤�Ͽ�����Ǥ��ޤ�����
- 30ʬ��Ͽ�����Ǥ���Ŵ�ơ��פϡ�60cm��ľ�¤Ȥʤ�9kg�νŤ����ä������Ǥ���
- 1.5m/s�Ȥ������ԡ��ɤϤ��ʤ�®��®�٤Ǥ���
- 9kg�νŤ��Υơ��ץ�פ�Τˤ��ʤ��礭�ʶ�ư�⡼����ɬ�פ��ä��Ǥ��礦��
- ����ˡ�Ŵ���Υơ��פǤϡ����ԥΥ�������ž�Υ������������ä�����������ޤ���
- �������ʤϡ����̤����Ф���뤳�ȤϤʤ������������1950ǯ��ޤǻȤ��Ƥ����ȸ����Ƥ��ޤ���
- �����������¤Ƥߤ�ȡ�1930ǯ����1940ǯ�ˤ����Ƥμ���Ͽ�����Ѥϡ��ɥ��Ĥ��ͽФ�����ȯ�Ϥ���äƤ����ȸ����ޤ��礦��
- ���������ƹ�Ϥʤ����ؿ����ޤ���Ǥ�����
- �������ʤ��Ȥˡ�AEG�Ҥ�BASF�Ҥ���AC�Х�����ˡϿ�������ȥ����ơ��ȥե����ơ��פ�Ȥä�Ͽ������Magnetophon�פ�ȯ����1941ǯ�������ʥ����Ϥ������ʤ���̩�ˤ��ޤ���Ǥ�����
- �ˤ⤫����餺���������ʤ�ꥫ¦��̵�뤷�Ƥ��ޤ�����
- �������ʤϡ�1941ǯ�Υ٥���ο�ʹ�ˤ�Ǻܤ���ޤ�����
- �������郎��ȯ��������������ꥫ��6����֤ϻ��碌��������٥���ˤ����Ƥ��ޤ�����
- ������̣���д�ñ�˼������뤳�Ȥ��Ǥ����ܹ�����뤳�Ȥ�Ǥ����ΤǤ���
- �ˤ⤫����餺�����ϡ����ο����ʤ��Ф��Ƥϡ��ʤ���̵�ؿ��Ǥ�����
- ������̵�ؿ��Ǥ����桢�ɥ��Ĥ϶ˤ�ƹ���ǽ�ʥơ��ץ쥳������ȯ���ƹԤ��ޤ�����
- �����ơ��פˤ����ʼ�Ͽ������ǽ�ˤʤä��Τϡ��ʲ���3���˽���ޤ���
- �ڹ��ʼ�����Ͽ������ͳ��
- ����1.������ʼ����ơ��פγ�ȯ��
- ����2.��AC�Х�����ˡ�ˤ����ʼ���Ͽ��������
- ����3.����ǽ���ɤ��⡼���Ȼ��˿����ɤ�Ϥ���Ȥ����ŵ����ʤ�ȯã��
- �����ɥ��ĤΥơ��ץ쥳�����õ��Ϥɤ��ʤä���
- �������������Τɤ�������ʶ��ơ��Ȥ�����������Ŭ�ڤ��ɤ����狼��ޤ�������ꥫ�ϥɥ��Ĥǽ������줿�ơ��ץ쥳�������ܹ�˰ܿ�����Ʊ����Τ��äƤ��ޤ��ޤ���
- �ɥ��ĤǤϡ��ơ��ץ쥳�����γ�ȯ�ˤ����ä��õ������������¤�Ƥ����Ϥ��Ǥ�����
- �ƹ�ϡ���塢�ɥ���AEG�Ҥ�BASF�Ҥ��Ф��ƥơ��ץ쥳������ȯ�Τ�����õ�����ʧ�ä��ΤǤ��礦����
- �ɥ��Ĥϡ���������μ��żԡ������Ȥ�����ͳ�ˤ�ꡢϢ���¦������������������������ʤ��õ�̵��������Ϥ���Ƥ��ޤ�����
- ���äơ��ơ��ץ쥳������ȯ����AEG��BASF��Agfa�ƼҤϡ���塢��餬��ȯ�����õ���������פ����뤳�ȤϤǤ��ޤ���Ǥ�����
- ����������ǡ�����ꥫ�ϡ�������ɥ��Ĥε��Ѥԡ����ơ�AMPEX��3M������ǽ�Υơ��ץ쥳�����ȼ����ơ��פ�ȯ���ޤ�����
- ���Υơ��ץ쥳�����γ�ȯ�⡢����ꥫ�����Ȥ��礭�ʻ��ܤ�Ȥäƿʤ�Ȥ������⡢Jack Mullin ������괬�������ʲ�Ҥ�Magnetophone�ʥɥ���̾��Magnetophon�ˤ����路�ƺ��夲�����Ȥ��������������������褦�Ǥ���
- ����ꥫ�Ǻ��ľ���줿�ơ��ץ쥳�����ϡ�����ꥫ�Υ������ʤ��ʤ��117VAC���Ÿ�������������������ʡˤǺ��ľ����ޤ�����
- �ޤ�����ư��������ĥ⡼����ɥ��Ĥ�220VAC��ư�����ƹ�ξ����Ÿ��Ǥ���117VAC���ѹ������ɥ��Ĥ�50Hz���Ÿ����ȿ���ư������ץ�����ʥơ��פ����®�٤����������ˤ⥢��ꥫ��60Hz����������ž����褦���ѹ�����ޤ�����
- �����ơ��פϡ��ɥ��Ĥ����Ѥ���6.5mm�������ľ����1/4�������6.35mm�ˤȤ��ޤ�����
- �ơ��ץ��ԡ��ɤ�ɥ��Ĥ�77cm/s�˶�Ť���30�����/�á�76.2cm/s�ˤȤ��ޤ�����
- ���ε��ʡ�1/4������ơ��ҡ��ơ�������30�����/�áˤ������ơ��פ�ɸ�൬�ʤȤʤäơ���塢�ܲȤΥɥ��Ĥ⤳�ε��ʤ˽������Ȥˤʤ�ޤ�����
- �����ơ��ٻ���
- �ơ��ץ쥳�������ɥ��Ĥ������������Τϡ��ץ饹���å��������ե���ब�Ǥ�������Ǥ���
- ������Ͽ�ϡ�1898ǯ�˥ݡ��륻����Ƥ��ưʸ塢�����磻�������������ġ���ơ��ס��ץ饹���å��ե����ʤɤ�������Фơ��������ȻȤ��������夵���ޤ�����
- 1934ǯ��BASF�Ҥϡ�30um���Υ����ơ��ȥ١�����20um���Υ����ܥ˥�Ŵ��Fe(CO)5��Carbonyl Iron�����٤ι⤤Ŵʴ��1925ǯ��BASF�Ҥ�ȯ���ˤ��ƥ������ơ��פ�ȯ���ޤ�����
- ���Υơ��פϡ�6.5mm����1m/s�Υơ���®�١�25ʬ�֤�Ͽ�����Ǥ��ޤ�����
- ���äƥơ��פ�Ĺ���ϡ�1,500m�Ȥʤꡢ�ơ��ץ���ľ��30cm�Ȥʤ�ޤ�����
- �ޤ���1938ǯ�ˤϡ������ӥˡ����poly vinyl chloride�ˤ��Ѥ����ơ��פⳫȯ���졢�����ꤷ�������ơ��פ�����Ǥ���褦�ˤʤ�ޤ����� 1950ǯ��Ⱦ�Фˡ��ƹ��Du Pont�Ҥȱѹ�ICI�ҡ�Imperial Chemical Industries�ˤ��ݥꥨ���ƥ��Polyester��Mylar�ˤ�ȯ����ȡ����Υե���ब�����ơ��ץե����Ȥ��ƻȤ���褦�ˤʤ�ޤ�����
- PET�ܥȥ�Ǥ褯�Τ���PET��Polyethlene Telephthalate���ݥꥨ�����ƥ�ե��졼�ȡˤϥݥꥨ���ƥ�ΰ��Ǥ���
- 1989ǯ��VHS�����κ��˻Ȥ��Ƥ�������Ū�ʥӥǥ��ơ��פϡ��ե����١�����14.7um���ޥ�������ȼ������ظ�4.3um�η�19um���Τ�ΤǤ�����
- �ơ��ٻ��Υե����ϡ�����ȤȤ�������ʤäƹԤ���DVCAM�Υơ��פ�6.3um�Υ١�����������7.0um�ˤȤʤ�ޤ�����
- �����ؤϲ���0.3um�Ǥ���
- �����ơ��פ��Ǻ�Ȥ��Ƥϡ���˽Ҥ٤�PET�ȡ�PEN�ʥݥꥨ�����ʥե��졼�ȡ�Polyethylene Naphthalate�ˤ��Ȥ��Ƥ��ޤ���
- PEN��PET����2�ܶ�Υ��Ψ�����ꡢ���פ���������äƤ��ޤ���
- ��
- ��������������2010.09.23�ɵ���
- �����ơ��פΰ���Ū�ʤ�ΤǤ���ե��饤�ȼ����Τϡ�����Ŵ�����ʬ�Ȥ�������ߥå����Ǥ���1927ǯ��1930ǯ��ˤ����Ƴ�ȯ����ޤ�����
- �����ơ��פ���ȯ���줿�����μ����Τϡ������ܥ˥�Ŵ��Fe(CO)5��Carbonyl Iron�ˤǤ��ꡢ�����1925ǯ�˥ɥ��Ĥ�BASF�Ҥdz�ȯ����ޤ�����
- �����ܥ˥�Ŵ�ϡ���Ŵ�ΰ���ʴ���Τ�ΤǤ��ꡢ�ơ��פ����ۤ���Τ�����ͭ���Ǥ�����
- ���μ����Τϸ�ˡ�Fe3O4�ʥޥ��ͥ����ȡ�magnetite��ŷ���μ�Ŵ�ۤμ���ʬ�ˤ��Ѥ��ޤ�����
- 1950ǯ�ˤϡ��ƹ�Υ�������ؤ�Marvin Camras��1916 - 1995�ˤ��˾�γ�ҤΥ����-�إޥ����ȡ�γ-Fe2O3��mag hematite�ˤ��Ѥ��������ơ��פ�ȯɽ���ޤ�����
- ����ϡ������Υ��Ӥΰ��λ���Ŵ�Ǥ��뤿�ᡢ������˻��Ӥ뤳�Ȥʤ����ꤷ�Ƥ���Τ���ħ�Ǥ�����
- ��¤�����Ȥ�²��ʤ��ᡢ�����ơ��פΥ���������ɤȤʤä���ΤǤ���
- �����Τϡ����θ�¿���θ��椬�Ԥ�졢�����������������ࡢ1961ǯ��Du Pont��ȯ�ˤ��Ѥ�����Τ䡢��Ŵ�����Х�ȡ�Avilyn��1973ǯ��TDK��ȯ�ˤʤɤ�Ȥä���Τ���ȯ����ޤ�����
- ��̩�ٵ�Ͽ���Ǥ��뼧���ΤȤ��Ƥϡ�1960ǯ�ˡ�Fe-Ni-Co�ʥ˥å��륳�Х�ȼ����Ρˤι��γ�Ҥ���ȯ���졢1968ǯ�ˤϡ�CrO2�ʥ��������⼧���Ρ˹��ʴ������ȯ����ޤ�����
- �����ϡ�γ-�إޥ����Ȥ���3�ܤε�Ͽ̩�٤���äƤ��ޤ�����
- �������������ϼ����ݻ��Ϥ���ä��Τǡ��Х������Τ�������ü�����ˡ������Ȥϰۤʤ��ΤȤʤ�ޤ�����
- �ޤ��������μ��Τ��Ť��Τǥإåɤ����פ��㤷���������μ����Τ�Ȥ����ϡ������إåɤ�Ŭ�ڤ�����ɬ�פ�����ޤ�����
- �����Τϡ�1980ǯ�夫����ơ��פλ���ˤʤ�ޤ���
- ���ơ��פϡ���Ŵ��ȤäƤ��ޤ���������λ���Ŵ���Ѥ��������Τ���١���Ŵ�������ݻ��ϤϹ⤯�²��ˤǤ��ޤ���
- ��Ŵ���Ѥ�������Ͻ�Ŵ�λ����Ǥ��ꡢ���Ѥȶ��˻������ʤ�ǽ����ǽ���������뤳�Ȥ��Ǥ��ʤ��ʤ뤳�ȤǤ�����
- ���Τ���ˡ���Ŵ�λ������ɻߤ���Х�������ε��Ѥ�¿�ز��ε��Ѥ��ʤߤޤ�����
- �ޤ�����Ŵ��¾�ˤ������°�Ȥ��ƥ��Х�Ȥ��忩�ɻ��ѤΥ˥å�����Ѥ���1um�ʲ�����γ�Ҥˤ��ơ���������ۤ���Ȥ������Ѥ���Ω����ޤ�����
- 1980ǯ��ν����ˤϡ���뼧���Τ���嵻�Ѥˤ�ä��������뵻�Ѥ��ʤߡ�������ơ��פȤ���8mm�ǥ�����ӥǥ���DVCAM�����Ѥ����褦�ˤʤ�ޤ�����
- ���ơ��פϡ�����ε��Ѥ�����۷���MP��Metal Particulate�˥ơ��פȾ��嵻�ѤǺ��ME��Metal Evaporated�˥ơ��פ�2���ब����ޤ���
- ���������ϡ����ߡ�2010ǯ�ˤΥǥ�����ӥǥ��ơ��פμ�ή�ˤʤäƤ����ΤǤ���
- ξ�Ԥ���Ӥ�����硢ME�ơ��פ�������������¿���ε���Ū����ħ����ä��о줷�ޤ�����
- ME�ơ��פϡ��Х��������Ȥ鷺��Co-Ni���μ����Τ�ơ��פ�ľ�ܾ��夵����Τǡ��ˤ�������ƹ⤤��Ͽ̩�٤���ļ����ơ��פȤʤ�ޤ���
- MP�ơ��פϡ�ME�ơ��פ�����˳�ȯ���줿��ΤǤ������ٻΥե���ब�ȼ��ε��Ѥ�ȤäƥʥΥ����٥��¿�������������ơ��פ�ȯ���Ƥ���ϡ�����ͥ���������ܤ���Ƹ��ߤ���ơ��פ���ɽ�Ȥ��ƻ��Ѥ���Ƥ��ޤ���
- MP�ơ��פϡ�ME�ơ��פ���٤�������Ψ���⤤������¤�����Ȥ��¤������ѻ����ѵ�����⤤���ḽ�ߤ�⤤ɾ��������Ƥ��ޤ���
- �� ��
- �����������
- �����ơ��פǤϡ������κ��������ڤʤ��顢�����Τ�ٻ��ե����˰��ꤷ�Ƹ��ꤵ����Ĥʤ��ʥХ�������ˤ����ѽ��פʰ�̣����äƤ��ޤ�����
- �����Τ����Ǥϡ��ٻ��ե����ˤ��ޤ�����Ǥ������ꤷ����Ͽ���Ǥ��ʤ��ΤǤ���
- ����μ����ơ��פϡ������ΤȥХ����������Ψ��3��7�ǡ��Х��������������������ޤޤ�Ƥ��ޤ�����
- �Х�������ε��Ѥ��ʤߡ������ɥ����ƥ����Ѥ�ʤ�ȡ���������Ȥ����Х�ȤΤ褦�ʹ���ʺ�����Ȥ�ʤ��Ƥ⡢�Х�������餷�ƽ�Ŵ�������ͭ��������������Ф�褦�ˤʤä��Τǡ�����Ǽ�갷��������������ơ��פϻԾ줫��Ѥ�ä��Ƥ����ޤ�����
- �����Τ�ٻ��ե��������ۤ�����夫����夹�������Ѥ��ȡ��Х�������ΰ�̣�Ϥʤ��ʤäƤ��ޤ���
- �ӥǥ��ơ��פϡ������ơ��פ��������˹⤤���ȿ��ǡ��ʤ�����S/N�褯��Ͽ���ʤ���Фʤ�ʤ��Τǡ�DV���ʤΥ��ॳ�����˻Ȥ��뼧���ơ��פϡ��Х���������ӽ���������ơ��ס�ME�ơ��סˤ�����������ޤ�����
- ������2010ǯ�ˤ��äƤ�Х��������Ȥä�������۷��ơ��ס�MP�ơ��סˤ����Ѥ���Ƥ��ޤ���
- ME�ơ��פ�������Ψ�������������������Ǥ��������ȹ���ä�����Ǥ���
- ME�ơ��פ���ȯ����Ƥ�MP�ơ��פϥХ�������β��ɤ��ʤߡ�ME�ơ��פˤҤ�����ʤ�����ǽ�ʤ�Τ��Ǥ��Ƥ������ᡢMP�ơ��פ�ME�ơ��פ�������¸�ߤ��Ƥ��ޤ���
- MP�ơ��פ˻Ȥ���Х�������ϡ���뼧��ʴ��Ѱ��ʬ�������Ƶ��夵����Ư����¾�ˡ������ɻߡ���ꡢ�����䶯��Ư������äƤ��ޤ���
- ME�ơ��פϡ��Х������Ȥ鷺�˥ơ��פ˥�뼧��ʴ����夵���Ƥ��ޤ���
- ���Τ���˥١����ե����Ȥξ�������褯����ɬ�塢ͽ��ɤ��ؽ�����ܤ��Ƥ����Ƥ�������ԤäƤ��ޤ��ʾ���ȡˡ�
- ME�ơ��פϡ������ؤ��ơ��פ��������줿�꼧���إåɤȤ��ܿ��������פ��Զ�礬���ä����ᡢ�����إåɤ��ܿ������̤�ú�����ǤΥ����ե�����¤�ι��������ܤ����ݸ��ؤ�⤦���Ƥ��ޤ���
- �����DLC��Diamond Like Carbon�ˤȸƤ�Ǥ��ޤ���
- ���ν����ϥ��������ɤΤ褦�˹Ť���¤����äƤ��뤿��ME�ơ��פ�����Ǥ��ä������ؤ���������Żߥ⡼�ɤǤΥơ��פ����פ��ޤ��뤳�Ȥ��������ޤ�����
- ���������ơ��ס�-�����ʥ�������ǥ������
- �����ơ��פϥɥ��Ĥ�ȯ�����졢Ͽ�������ȯŸ�˸Ʊ����ƥɥ��ġ��ƹ����ܤǿʲ����ޤ�����
- ���ܤǤΥ����ǥ������ӥǥ��ơ��פ�ȯŸ���ܤ�ĥ���Τ�����ޤ�����
- ���ˡ���Ϥᡢ�����ʸ��ѥʥ��˥å��ˡ�TDK����Ω�ޥ����롢�ٻΥե���ࡢ�Х���������Ѥβֲ����١����ե��������ʤɡ�ͥ�ɤʥ�����ʼ����ɤ������ơ��פ�ȯ�����������˶��뤷�ޤ�����
- ���ܤΥ���ˤ�뼧���ơ��פ��ʼ����ɤ��Τϡ������κ�����ȯ��ͥ���ʵ��ѼԤ����ޤäƤ������Ȥȡ���¤�ʼ��ˤ����Ƥ��त���ʵ��Ѥ�ͭ���Ƥ������Ȥˤ��ޤ���
- �������������ơ��פ⡢1990ǯ���Ⱦ�����꤫��ž������ޤ��ޤ���
- ����ο����ˤ�ꡢ����Υ����ǥ������Ӥμ����ơ��פ���CD��HDD���ե�å�������å��졢VHS���濴�Ȥ����ӥǥ�Ͽ���ʬ��ˤ����Ƥ�DVD�ʤɤΥݥꥫ���ܥ͡��ȵ�Ͽ���Τ���ڤ���������פ��������Ƥ��ޤä��ΤǤ���
- ���ߡ�2008ǯ�ˤμ����ơ��פϡ��ǥ����륫�ॳ�����Υǥ����뼧���ơ��ס�DV�ˤ䡢��������Ͽ��ơ��ס������ơ�����ԥ塼��ʬ��Υ��ȥ졼���ǡ����ơ��פ˼��פФ��Ƥ���˲�������פ������̤ϸ��äƤ��Ƥ��ޤ���
- �����ơ������ơ��פ�ǥ�����λ����ޤ��뤳�Ȥˤʤ�ޤ�����
- �� ��
��
- �������ε�Ͽ
- �����ӥǥ��ơ��ץ쥳�����γ�ȯ - �ƹ�AMPEX��������2010.08.20�ɵ���
- �ŵ�����ˤ���������¸�ϡ��ӥǥ��ơ��ץ쥳������ȯ���Ǹ�����ߤޤ���
- ���ε��Ѥϡ�����Ͽ�����֤α�Ĺ���ˤ����Τǡ�1956ǯ�ʹߤΤ��ȤǤ���
- �����ǥ�����Ͽ�ȥӥǥ���Ͽ�Ǥ��ᤵ��뵻�Ѥ���㤤�˰ۤʤ�ޤ�����
- �ӥǥ��ơ��ץ쥳�����γ�ȯ�ˤ�¿���ε���Ū���꤬���ꡢ������褹�뤿��¿�ۤγ�ȯ��Ȼ��֤�������ޤ�����
- ���κ������ۤ��������ǽ��ƥӥǥ��ơ��ץ쥳������ȯ�����Τϡ��ƹ�AMPEX�ҤǤ�����
- ��
- ������ž�ɥ��إå�
- ����Ŵ�����Τ�Ȥä��ơ��פ�Ȥäơ��������Ż�Ū�˵�Ͽ�Ǥ���褦�ˤʤä��Τ�1956ǯ�Τ��ȤǤ���
- �ƹ��AMPEX�ҡ�1944ǯ��Ω���ƹ�ե���˥�����������ˤ����ƥ�ӥ����ǤȤ館���ŻҲ�����ơ��פ�Ͽ�褹�����֤γ�ȯ�����������ΤǤ���
- �����Ͼ���¿�����ᡢ�����ǥ����ơ��פΤ褦�ʵ�Ͽ�����ǤϤȤƤ�������������Ͽ���뤳�ȤϤǤ��ޤ���
- AMPEX�Ҥϡ�Ͽ��إåɤ�14,400rpm��240Hz���ӥǥ�����Υե�����ɲ���60�ե������/�ä�4�ܡˤDz�ž�����ơ����Υإåɤ�ơ��פ������������Ф��ƿ�ľ�˥������Ȥ���������ͤ��Ф��ޤ����ʲ������ȡˡ� �̾�����ǥ����˻Ȥ��Ƥ���Ͽ���������إåɤϡ���ư�������ž������Ϥ��ޤ���
- ����Ǥ���
- ����إåɤξ���ơ��פ����Ԥ��Ʋ��������Ͽ����������Τ�����Ū����ˡ�Ǥ�����
- ���������ӥǥ�����Ͼ���¿���Τǡʵ�Ͽ���ȿ����⤤�Τǡˡ�������ˡ����äƤ����ΤǤϤȤƤ���ȿ��Ӱ����ݤ��뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���Ǥ�����
�����إåɤ��ž������ȯ�ۤϡ���ȴ�ʤ�Τ��ä��ȸ����ޤ��� ��Ͽ���ȿ���夲����ˡ�Ȥ��Ƥϡ��إåɤ�ʣ�����֤��ƥơ���®�٤�夲�ƥޥ�������ͥ뵭Ͽ����ȸ����Τ�������ʤǤ��ʸ��ߤΥ���ԥ塼���μ����ơ������֤Ϥ��Τ褦�ˤ��Ƥ��ޤ���MT�����ˡ�
- �������������ϸ��äƤ�ơ������Ԥ�10m/s�����餻�ơ����ξ塢���Υ��ԡ��ɤ����ˤ�����Ȥ������Ѥ������Ǥ��ʤ��ä��ΤǤ��礦��
- 10m/s�Ȥ����ΤϤ��ʤ��®�٤Ǥ���
- ���Υ��ԡ��ɤ�10ʬ���٤β�����Ͽ�褷���Ȥ�����ɤΤ��餤�����̤ˤʤ�Ǥ��礦��
- 6,000m���Ĺ���ˤʤ�ޤ���
- VHS�ơ��פ�240m�Ǥ�����VHS�ơ��פ��⤵���25�ܤ��Ĺ����ɬ�פȤʤꡢ����Ĺ���Ǥ�10ʬ����Ͽ��Ǥ��ʤ��ΤǤ���
- ����������ˡ���⡢��ž�ɥ��˥إåɤ����դ��ơ��ơ��פȼ����إåɤ�����®�٤�夲�Ƽ��ȿ��Ӱ����������긽��Ū����AMPEX�Ҥε��ѼԤϹͤ��ޤ�����
- �����إåɤ���ž���Ƽ����ơ��פ˾����Ͽ���������ϡ���Ͽ��Ȥ���Ȥ���˹Ԥ����Ȥˤʤ�ޤ���
- �������ƥ�Ӥα���������������Dz��̤������Ƥ����Τǡ�������1��ʬ��إåɤ��ơ��פ������֤ˤ��Ƥ���������Ȥʤ�ޤ���Ǥ�����
- ���ιͤ������Ȥˤ��ơ�������VTR�ǰ���Ū�ˤʤ�VHS��١�����U-matic�⤹�٤Ʋ�ž�ɥ����������Ѥ���褦�ˤʤ�ޤ����� �١���������VHS�����Ǥϡ�����˼��ȿ��Ӱ��夲�뤿��˼Ф�˥ơ��פ����إꥫ�륹�������������Ѥ��ޤ�����
- VHS�ϡ�������ˡ�ˤ�äƥơ��פȥإåɤ�����®�٤�5.8m/s�Ȥ��Ƥ��ޤ���
- ���ʤߤˡ������ǥ����ơ��פ�1/4�������6.35mm���ˤΥơ��פǡ�30�����/�á�76cm/s�ˤǤ����Ԥ��ǹ�Ǥ����� �ơ��פ��������ԤǤϡ�1m/s��®�٤��ѵ�����ޤ���Ѿ�θ³����ä��Τ��⤷��ޤ���
- ��ž�ɥ��ˤ�뼧����Ͽ��ǽ�˳�ȯ����AMPEX�Ҥϡ��ơ������Ԥ��Ф��ƥɥ�ब��ľ�˲��ڤ�С��ƥ����륹������vertical scanning, transverse scanning����������Ѥ��ޤ�����
- ����ϡ���ž�ɥ��μ���90°���4�Ĥμ����إåɤ����֤��ơ��ɥ�ब90�ٲ�ž���뤴�Ȥ˥ơ��פ��إåɤθ����֤��������ư����褦�ˤ���4�ĤΥإåɤΤ����줫����������ơ��פ˥����Ȥ���褦�˹ͰƤ���Ƥ��ޤ�����
- ���Ѥ��������ơ��פϡ�2�������50.8mm�����Τ���������ΤǤ�����
- ���Υӥǥ��ơ��ץ쥳�����ϡ�2 inch Quadruplex Videotape Recorder�ȸƤФ�ޤ�����
- �ơ������Ԥȥɥ��إåɤβ�ž��14,400rpm�ˤˤ�äƺ����إåɤȥơ��פ�����®�٤�40m/s�Ȥʤ�ޤ�����
- ����إåɤǤϤ���®�٤ϤȤƤ�ã���Ǥ��ʤ��ͤǤ���
- ���ε�Ͽ®�٤ˤ�äơ���13MHz�ο����Ͽ�������Ǥ���褦�ˤʤ�ޤ�����
- 2�������50.8mm�˶ҤΥơ��פϡ�ξü�˥����ǥ����ȥ�å��ȥ���ȥ�����ȥ�å����桢����˥֥���ΰ����ݤ���ط��塢1 - 4/5 �������48.26 mm�˶Ҥ�������Ͽ���Ǥ���1�饤��� = �ȥ�å��ˤȤʤ�ޤ���
- �ºݤϡ�4�ĤΥإåɤ����֤˥ȥ�å������ä����Τǡ�1�إåɤ�1�ȥ�å��˵�Ͽ����Ĺ���ϡ�1 5/8 �������41.275 mm�ˤȤʤ�ޤ���
- ��ž�ɥ���1�ô֤�240��ޤ��ޤ��Τǡ��إåɤ�1�ô֤�960��ȥ�å���ʤ��äƹԤ��ޤ���
- �ƥ�ӱ�����1�ô֤�30���ޤα������äƤ���Τ�1���ޤΥƥ�ӱ����ϡ�32�ȥ�å��ǹ�������뤳�Ȥˤʤ�ޤ���
- ��AMPEX�ҳ�ȯ��VTR��ά���͡�
- �������ѥơ��ס���2������ҡ�50.8mm�˼����ơ��ס�4800ft��1500m�ˡ�1����Ͽ��
- ���������إåɡ�����ž�ɥ�༰
- ������ž�ɥ��¡���φ52.55mm�ʥإåɡ��ơ��ץ��ԡ��ɤ�껻�С�
- �����إåɿ�����4
- ���������������������ľ��������vertical scan������
- �����ɥ���ž������240 Hz��14,400 rpm��
- �����إå� - �ơ�������®�١���1,560�����/�á�39.6 m/s��
- �����ơ�������®�١���15�����/�á�0.381 m/s��
- �������浭Ͽ�Ӱ衧��13MHz���ʥإåɥ���åפ�1.5um�Ȥ��ƴ�����
- ������Ͽ��������FM�ʼ��ȿ���Ĵ������ �����ȥ�å��ҡ���10 mil��254 um��
- �����ȥ�å��ԥå�����15 mil ��381 um�� �� ��
�ڥӥǥ��ơ��ץ쥳�����γ�ȯ�طʡ�
- �ӥǥ��ơ��ץ쥳��������ȯ���줿ľ�ܤ�ư���ϡ��ƹ�Υƥ�������λ��ֺ��ˤ���ޤ�����
- ����ꥫ�Ϲ��ڤ��������ᡢ�˥塼�衼���Τ����쳤�ߤȥ������륹�Τ��������ߤǤ�4���֤λ���������ޤ���
- �ץ饤�ॿ����ʥ�����ǥ�ˤǥ˥塼�����Ȥ�ή�����ꡢ����줿�ȡ������Ȥ��������Ƥ�4���֤λ����Τ���ȿ��¦�ǤϿ�����ˤʤäƤ��ޤä��ꡢ�ޤ��͡���Ư���Ƥ�������Ӥ��ä��ꤹ��櫓�Ǥ���
- �����������ֺ���������뤿��ˡ��������ߤ��ƥ�������ή�����Ȥ��Ǥ����������������Ϲͤ��ޤ�����
- ����������˱����뤿��AMPEX�Ҥ���ȯ�˾��Ф���1956ǯ11��30����CBS�Ρ�the Douglas Edwards with the News�סʥ����饹�����ɥ���Υ˥塼���ˤˤ����ƥӥǥ��ơ��ץ쥳������Ȥä���������ƹԤ��ޤ�����
- ���������������Ǥ�����
- ����λ���Υӥǥ��ơ��ץ쥳���������˹���Ǥ�����
- ����ʾ�ˡ������ʤǤ���2������ơ��פ��ȤƤ����Ǥ��ä��ȸ����Ƥ��ޤ���
- 1���֤�Ͽ�褬�Ǥ��륪���ץ��뼰2������ӥǥ��ơ��פ����������ܤ�100�����������������Ǥ���
- ��������´�Ԥν�Ǥ�뤬1��2���ߤ��ä����Ȥ�ͤ���ȡ����ߡ�2009ǯ�ˤβ��ʤˤ���1500���������ˤʤ�ޤ���
- 1���֤�Ͽ���1500���ߤ���Ȥ����ΤϤȤ�Ǥ�ʤ��ä��ä��˰㤤����ޤ���
- ���Τ���ˡ������ϥӥǥ��ơ��פ�Ȥ��ơ�Ͽ�褷�ƤϾä��ơ����Ͽ���ԤäƤ��ޤ�����
- ���η�̡�1960ǯ��Υƥ�ӱ�����¿���ϡ�Ͽ��Ϥ��줿����ɤ⼡���Ⱦä���Ƥ��ޤ�����Ͽ�Ȥ��ƻĤ��ʤ��ä��Ȥ�����ǰ�ʤ��Ȥˤʤ�ޤ�����
- �ޤ���AMPEX��VTR���֤������礭���ƽŤ����Ҥ�1m50cm���⤵��1m60cm���ä������Ǥ���
- �礭����ê�Τ褦�ʥ���ӥͥåȤ����֤ǡ������˽Ť�5.5kg�⤢��ӥǥ��ơ��פ��ú¤��Ƥ��ޤ�����
- �ӥǥ��ơ��פ����ؤ���Ȥ��ϡ�ξ��ǥơ��פι⤵�ޤǻ����夲�����ˤ���ڥ���ǥХ��塼����å����Ƽ���ؤ��Ƥ��������Ǥ���
- �����Ƥޤ�����ž����ӥǥ��إåɤΥ��饤����Ĵ�����ȤƤ⥷�ӥ��ǡ����Ѥ��������ϰ���β��٤ȼ��٤��ݤ��ʤ��������ư��ʤ��ä��ȸ����Ƥ��ޤ���
- ��ž�إåɤϾ����ʤǡ��ơ��פȤ����פǥإåɤ��ܵͤޤꤷ���ꥢ�饤���Ȥ����ä��ꤷ�ޤ���
- ������������Ĵ���ϤȤƤ����Ƹ���ǤϤǤ��ʤ��Τǡ��ƥ�Ӷɤϥإåɥ�����֥�����ݴɤ��Ƥ��ơ���ɬ�פʻ��˥�����֥�����Ƥ����ȸ����ޤ���
- ����������ǡ����ˡ����ȥ������Ȥä�������2������ơ��ץӥǥ��ơ��ץ쥳������ȯ����1961ǯ�ˡ�3/4������ơ��פ��åȤ����줿U-matic��ȯ����1970ǯ�ˡ�1/2��������Υ١��������Υ١��������ȯ��1975ǯ�ˤ��ƹԤ��ޤ�����
- ���֤⥳��ѥ��Ȥˤʤ꿮���������������Ѥ���ơ��פ�ɤ�ɤ�²��ˤʤäƤ����ޤ�����
- 1980ǯ���Ⱦ�ˤϡ������ơ��פ�Ȥä��ǥ�����Ͽ�����Ǥ���褦�ˤʤ�ޤ�����
- ��
- �����ɥ�ӡ���Ray Milton Dolby��1933 - 2013�˻�Τ���
- AMPEX�Ҥ�VTR��ȯ�������˥��ΰ�ͤ�Ray Dolby����ޤ���
- ����ʬ��Ǥϡ��ɥ�ӡ���Ray Dolby��1933.01���˻�ζ��ӤϤ���ۤɹ⤯�Ϥʤ�������ʬ��ǥΥ��������������ƥ��ȯ�����ͤȤ��ơ��ɥ�ӡ������ƥ��̾���Ǥʤ��ߤ������Ȼפ��ޤ���
- ���Υɥ�ӡ���ϡ��嵭��AMPEX�Ҥ˹���奢��Х������Ȥ��ơ������ƲƵ٤ߤˤ�Ĺ���Υ���Х��ȤȤ������ǥ����ǥ����ơ��ץ쥳�����γ�ȯ������äƤ��ޤ�����
- ��ϡ����쥴�ݡ��ȥ��ɤ����ޤ�ƥ���ե�����ǰ���ޤ�����
- �ޤ����ब������ե�������ء�1951-52��1953 - 1957�ˤ����ä�����AMPEX�Ҥȴؤ��³��������Х��Ȥη���AMPEX�ҤΥӥǥ��ơ��ץ쥳�����γ�ȯ�˴ؤ��ޤ�����
- ��ϥ�����ե�������ؤ��ŵ����زʤ�´�Ȥ����ѹ���Ϥäƥ���֥�å���ؤ��̤�ʪ���ؤ���ι��������ޤ���
- ����֥�å���ؤ�Ф���ϡ���������ܤξ����ǵ��ѥ��ɥХ������Ƥ��ޤ�������1965ǯ�˱ѹ�����ɥ�ӡ�������Dolby Laboratories�ˤ���Ω���ޤ���
- ��Ω����ǯ�ˡ������ΥΥ������������������Ǥ���ɥ�ӡ�������ɥ����ƥ��ȯɽ���ޤ�����
- ���������ϱDz�β��������ƥ�˺��Ѥ�����礭��ȿ����Ƥӡ���β������ؤ��Ф��뵻�Ѥ��ɤ뤮�ʤ���Τˤ��ޤ�����
- �䤬����������ˤ������Τϡ��ɥ�ӡ������ƥ�Τ��ȤǤϤʤ��������μ�����Ͽ���֤˴ؤ�ä��㤭���Υɥ�ӡ���Τ��ȤǤ���
- AMPEX�ҤΥӥǥ��ơ��ץ쥳�����γ�ȯ��1952ǯ�˻Ϥޤ�ޤ��� ������ǯ1956ǯ�����̤ä�4ǯ���˥ץ��������Ȥ��������Ȥ��ޤ�����
- 4ǯ�γ�ȯǯ�Ĺ���ȸ���٤��ʤΤ������ȸ���٤��ʤΤ��Ϥ褯�狼��ޤ���AMPEX�Ҥμ�������ץ��������Ȥ����Ǥʤɤ����ä�4ǯ�Ȥ����з��䤵��ޤ�����
- �㤭���˥��Υɥ�ӡ����ä�äƤ��ʤ���С�AMPEX��VTR�����Ϥ�����٤�Ƥ����������ȸ����Ƥ��ޤ���
- AMPEX�Ҥ�1944ǯ�����ߤ��졢�����⡼����ȯ�ŵ������ҤȤ��ƥ������Ȥ��ޤ�����
- 6�ͤβ�ҤǤ�����
- Ʊ�Ҥϡ��ƹ�Φ���̿�����ȼ�������ä��ط��ǡ��Ʒ�������������˥ɥ��Ĥ���������ä��ơ��ץ쥳�����ι��������졢1947ǯ���鳫ȯ��Ϥᡢ1ǯ���1948ǯ�˴�������ABC���ƹ��������ҡˤ˺��Ѥ���ޤ�����
- ���Ϳ��ε��ѽ��ĤǤ����������ϤϹ⤫�ä��褦�Ǥ���
- ��������AMPEX�Ҥϥơ��ץ쥳������¤��ҤȤ���ȯŸ��³�����������ѤΥơ��ץ쥳�����Τߤʤ餺���Ʒ��η�¬�ѥơ��ץ쥳�����䡢�ϥꥦ�åɤαDz費�������ƥ��꤬����褦�ˤʤ�ޤ�����
- �ɥ�ӡ���ϡ�AMPEX�Ҥ������ǥ����ơ��ץ쥳�����γ�ȯ��Ϥ���餫�饢��Х��ȤȤ���Ʊ�Ҥ˽����ꤷ���������ؤ��μ���ƹԤä��褦�Ǥ���
- AMPEX�Ҥ��ӥǥ��ơ��ץ쥳�����γ�ȯ��Ϥ1952ǯ�ϡ��ɥ�ӡ��������ե�������ؤ�2ǯ���Ǥ�����
- 19�ͤγ����Ǥ�����ޤ��ޤȤ�ʥ��˥���ηи��ȼ��Ӥ�˳�����ä��Ȼפ��ޤ���������Ū���ץ�������ȯ�ۤκͤ˽��ǤƤ����褦�ǡ��֤��֤˥ץ��������Ȥ���ˤȤʤäƹԤ��ޤ���
- ��ϡ����λŻ��ˤΤ����ߤ�������ؤ����ष�Ƥ��ޤ��ޤ��� �����������������ŵ�Ǥ���ʼ����Ƚ����ڤ�Ƥ��ޤ���1953ǯ��3���ħʼ����Ƥ��ޤ��ޤ�����
- �बħʼ�˽ФƤ���֡�AMPEX�ҤΥץ��������Ȥϡ���ʰ�����֤����ޤ�AMPEX�Ҥ��Τ�Τηб����ˤ��Թ�ǡ����Υץ��������Ȥ����ê�夲��������Ǥ⤷�ޤ�����
- 1954ǯ1��˥ץ��������Ȥ��Ƴ����졢1955ǯ�νդ˥ɥ�ӡ��ʼ�鵢�ä���ޤ�����
- ����1ǯ��˥ӥǥ��ơ��ץ쥳�����ϴ������ޤ���
- �ɥ�ӡ���ϡ����٤���ؤ��̤��ʤ��饢��Х��ȤȤ������ǥץ��������Ȥ˻��ä���FM��Ĵ��ϩ�ʼ��ȿ���Ĵ�������饸��������FM���������˻��������ˤ��Ѥ�������ץ벽�߷פ�ǽ�Ϥ�ȯ�����ޤ�����
- �ӥǥ������ơ��פ�Ͽ�褹���ǡ�FM�ˤ�뿮�浭Ͽ��Ͽ��ˤϰ�Ĥε��ѳ��Ǥ�����
- ���ε��Ѥˤ�äƹ⤤���ȿ��α��������Ͽ�褷�����Ǥ���褦�ˤʤ�ޤ�����
- �� �� ��
- ����FM��Ͽ��Frequency Modulation Recording����������2010.08.21���ˡ�2010.08.24�ɵ���
FM��Ͽ�ϡ�AMPEX�Ҥ��ӥǥ��ơ��ץ쥳������ȯ�˺��Ѥ��������ơ��פؤο��浭Ͽ�����Ǥ���
- ����Υ����ǥ���Ͽ�����Ѥ�Ȥä��ΤǤϤȤƤ����ʱ�����Ͽ���Ǥ��ʤ�����ˡ����μ�ˡ����ȯ����ޤ�����
- VTR�γ�ȯ�ˤ����äƤϡ����Ӱ迮�浭Ͽ��Ԥ�����ˤޤ������إåɤι�®�����ޤ��ޤ�����
- ��ž�����إåɤκ��Ѥˤ�ꡢ�ơ��פȥإåɤ�����®�٤�1,560�����/�á�39.6 m/s�ˤȤ��ƹ��Ӱ�Ͽ����б������ޤ�����
- AMPEX����ȯ�����ӥǥ��ơ��ץ쥳�����ϡ�13MHz�ο����Ӱ��Ͽ��Ǥ���ǽ�Ϥ���äƤ��ޤ�����
- ����Ͽ�迮���Ӱ�ȥơ��ס��إå�����®�٤��顢�إåɥ���å�Ĺ�����ȡ�1.52um�Υ���å�Ĺ�Ȥʤ�ޤ���
- d = V/��2 x F�� = 39.6E6 um / ��2 x 13 MHz�� = 1.52 um
- AMPEX�ϡ����������ˤ�äƹ��Ӱ��Ͽ����ǽ���������ޤ�����
- ��VHS�����μ����إåɤǤϡ�����˶���0.3um�Υ���å�Ĺ�ˤʤäƤ��ޤ�����
- NTSC����ο����Ӱ�Ƥߤޤ��ȡ����ʤ�4.2MHz�ȷ����Ƥ��ޤ���NTSC���ʤο�ʿ�����ϻ����ˡ�
- AMPEX�ҤϤ����Ӱ��3�ܶ�����ļ����إåɤȥӥǥ��ơ��פγ�ȯ��Ԥä����Ȥˤʤ�ޤ���
- �ʤ������ͤ��С�����褦�ʳ�ȯ��Ԥä��ΤǤ��礦����
- ����ϡ������ǥ����ǻȤ��Ƥ���AC�Х�����ˡ�������Ͽ���Ѥ���ȡ��Ӱ褬�����������ơ�������㤤���ȿ��ΰ�Ǥ��Ĥߤ��礭���ʤäƤ��ޤ����꤬���ä�����Ǥ���
- ���Τ褦����ͳ���顢AC�Х�����ˡ������Ƽ��ȿ���Ĵ�ˤ�뵭Ͽˡ��FM��Ͽ�ˤ���Ѥ��뤳�Ȥˤ����ΤǤ���
- FM��Frequency Modulation�ˤȤϡ����Ͽ���ʿ�������ˤ���ȿ����Ѵ������ˡ�ǡ��������礭����Τϼ��ȿ���⤯���ƾ�������Τϼ��ȿ����㤯���뿮���Ѵ���ˡ�Ǥ���
- ���ʥ����ƥ�������Ǥ⤳����ˡ�Ϻ��Ѥ���Ƥ��ơ�FM����ˤ����������̵����Ȥä��������Ƥ��ޤ���
- �饸�������ˤ�FM���������ꡢƱ�ͤ��������äƤ��ޤ���
- FM��Ͽ�ϥ饸��������ʹ���Ƥ狼��褦�ˡ��Υ��������ʤ����ʼ��Ǥ���
- ���������Ӱ����뤳�Ȥ��Ǥ����Υ����˶����Ȥ����Τ�FM��Ͽ����ħ�Ǥ��� AMPEX�Ҥϡ�FM��Ͽ��Ԥ��ˤ����äƴ��ܼ��ȿ��������� = carrier�ˤ�8.6MHz�Ȥ��ޤ�����
- ���μ��ȿ����濴�Ȥ������Ͽ����岼��¦���ӡ�±4.2MHz�ˤ�褻��ȡ�
- ����4.4MHz <��8.6MHz�� < 12.8MHz
- �������ơ��פ˵�Ͽ�������ȿ��Ӱ�Ȥʤ�ޤ���
- �����ơ��פˤϡ���������ϰϤμ��ȿ�����Ͽ����뤳�Ȥˤʤ�ޤ���
- AMPEX�Ҥ�13MHz�ε�Ͽ�Ӱ���ܻؤ�����ͳ�������ˤ���ޤ��� �ƥ�Ӳ����μ��ȿ���ͤ���Ȥ�����Υȡ�������̤���٤������̤ޤǤβ������ȿ���30Hz��4,200,000Hz�Ȥʤ�ޤ���
- ���Υ�ϡ�1��140,000�Ǥ��ꡢ103dB���������ޤ���
- ���Υ����ʥߥå���С����뼧����Ͽ�ʤ������Ǥ��Բ�ǽ�˶ᤤ�ͤǤ�����
- ¿�����Żҵ���ϡ�60dB��1:1,000�����٤ε������Τ���äȤǡ�100dB��1:100,000�ˤ�ۤ����Τγ�ȯ�ϸ��������ˤ��˳�����ȸ��虜������ʤ��ä��ΤǤ���
- ���Υƥ�Ӳ����μ��ȿ���FM��Ͽ�ˤ���ȡ�4.4��12.8 = 1:2.9�� = 9.3dB�ˤȤʤꡢ���������ʥߥå���Ǥ⽽ʬ�˱�����Ͽ�Ǥ��뤳�Ȥˤʤ�ޤ���
- FM��Ͽ���礭����ħ�������ˤ���ޤ�����
- FM��Ĵ�ϡ����ȿ��Υ������������Ƽ��ȿ���ʬ�Υ����ʥߥå�������微���������ˡ�Ǥ�����
- ���μ�ˡ�ϡ��ʹߡ�VHS������VTR�ˤ���Ѥ���ƹԤ��ޤ�����
- ���ʥ�����������ε�����Τ褦��¸�ߤ�FM��Ͽ���ä��ΤǤ���
- �� �� �� �� �� ��
- ����MT��Magnetic Tape��- ����ԥ塼���ѥǥ����뼧���ơ�������2008.08.18�ɵ��ˡ�2010.12.12�ɵ���
- �����ơ��פ�Ȥä���Ͽ���֤ˤĤ��ơ����٤ϱ������������饳��ԥ塼�����������ܤ�����Ƹ��뤳�Ȥˤ��ޤ���
- �����ơ��פϡ����ʥ�����Ͽ���饹�����Ȥ��ޤ�����
- ���ʥ�����Ͽ�Ǥϡ�����ζ��٤��ζ����Ȥ��Ƶ�Ͽ���Ƥ��ޤ�����
- �ǥ����뵭Ͽ��������Ǥ��륳��ԥ塼���ѳ�����Ͽ�Ȥ��Ƥ⼧���ơ��פ����Ū��������ܤ���Ƥ��ޤ�����
- ����IBM726
����ԥ塼���Ѥγ����������֤Ȥ��Ƴ�ȯ���줿�ǽ�μ����ơ���Ͽ���֤ϡ�IBM�Ҥγ�ȯ������ǥ�726�Ȥ�����ΤǤ���
- ��ǥ�726�����������Τϡ�1952ǯ�Τ��ȤǤ����顢�����ơ��סʥ���������������ơ��ȥ١����ˤ��ƹ�����䤵���褦�ˤʤäƤ����ˤ������֤γ�ȯ�����ä�����������ޤ���
- 1952ǯ�ȸ����С��ޤ��ܳ�Ū���Żҷ����ϻ��β�����Ƥ��ޤ���
- �������Żҷ����Ϥޤ����ΰ��ФƤ��ʤ��ä��ΤǤ���
- IBM�⡢�����������緿�������äƤ��餺����ߥ�ȥ���ɼҡʸ塢��˥����ҡˤ��Żҷ����ҤΥѥ�������ɤ��Ȥ߹�碌����äƤ��ޤ�����
- ����IBM�Ҥ����Ҥ��Żҷ�����IBM701�ˤ�ȯ���������IBM726���Ȥ߹�碌�����䤷���ΤǤ���
- �������IBM726�Ͽ��������֤Ǥ����顢����Ǥ��꿮������狼�äƤ��ʤ��ä��Τǡ�Ĺ�餯���ѥ�������ɥ����ƥ���PCS = Punch Card System��URE = Unit Record Equipment�ˤ���ή�κ¤����ƹԤ��ޤ���
- ��������1952ǯ�����Ū�ᤤ�����ˡ������ơ��פ�Ȥä��ǥ�����ǡ����������֤�ȯ�����Τ���ɮ���٤����Ȥȸ����ޤ��礦��
- �緿�����������ȥ١����˾�äƤ���¸�ߤ��Ω����Τϡ�1964ǯ��IBM360����Ǥ���
- ���λ���ˤ��äƤ�ǡ��������������֤μ�ή�ϥѥ�������ɤǤ�����
- �ѥ�������ɤ������²��ǻȤ��䤹���ä��ΤǤ���
- ��ǥ�726�Υ�������ݡ��ͥ�Ȥϡ������ơ��פǤ��ꡢ��®�ǰ��ꤷ���ʼ����ݤĤ��ᡢIBM��3M�Ҥ˥���ԥ塼���ѥ��ȥ졼�����ѤΥơ��פ���ʸ���ޤ�����
- �ơ��פ�ɽ�̤ˤ鷺���ΰ�ʪ�������ǧ�᤺������ϡ��ޥ�ϥå���ȥݥ��ץ����ʥ˥塼�衼�����˴֤�96km��ƻϩ��鷺���ξ��Ф��ǧ��ʤ��ʼ��Ǥ��ä��ȸ����Ƥ��ޤ���
- ���Τ��ᡢIBM�Ҥϥݥ��ץ����˥����롼���������������ơ��ץ����ƥ��������ߤ����ʼ��θ�����ؤ�ޤ�����
- ��̩�ʸ�����Ф���¤����뼧���ơ��פ϶ˤ�ƹ���ʤ�ΤǤ�����
- ������Ͽ���֤Ȥ��Ƥμ����ơ��פ����ʥ�����Ͽ���ä��Τ��Ф���IBM�Ϻǽ餫��ǥ����뵭Ͽ��Ԥ��ޤ�����
- �����������Υǥ����뵭Ͽ�Ϥ���ۤɹ�®���Ĺ�̩�٤ˤǤ����櫓�ǤϤ���ޤ���Ǥ�����
- IBM726�ϡ�45,000�ӥå�/�ä��ɤ߽�ǽ�Ϥ���äƤ��ޤ�����
- ���ߤβ�����CD�ε�Ͽ®�٤�4M�ӥå�/�áʥǡ����¸��ͤ�1.4112Mbps�ˤǤ���Τǡ�IBM726�ε�Ͽ®�٤�CD����ǽ��1/31���٤Ǥ�����
- ���ξ塢��Ͽ���֤�3ʬ���٤Ǥ�����
- ���λ��¤ϡ����λ���μ����ơ��פDz����ǥ�����Ͽ���뤳�Ȥʤ������Բ�ǽ�Ǥ��ꡢ�������Ѥ����Ӱ�ι����������Ѥγ�Ω�Ϥۤɱ��Ȥ�ʪ��äƤ��ޤ���
- IBM�ϡ������ơ��פ�Ȥä���Ͽ���֤�ȯ���Ƥ����ˤ����ꡢ�ơ�������1/2�������12.7mm�ˤȤ��ޤ�����
- ����ϡ����ߤˤ�����ޤǽ��ϰ�Ӥ�����ΤǤ��ꡢ�����ץ��뤫�饫���ȥ�å����ͤؤȳ������Ѥ�äƤ�Ʊ���ơ������Τ�Τ��Ȥ�³�����Ƥ��ޤ���
- ������ǥ�726�Υǡ�����������
- ��ǥ�726�ϡ��ơ�����1/2�������12.7mm�ˤ�7�ȥ�å���6�ӥå� + 1�ѥ�ƥ��ˤε�Ͽ��������Ѥ��ޤ�����
- �ơ��ץ����礭����ľ��300mm�Ǥ��ꡢ�ơ��פ�Ĺ����1,200�ե����ȡ�366mĹ�ˤǤ�����
- ξ�Ӥǻ����夲�Ƥ�����Ȥ���Ť��Ǥ�����
- ��Ͽ̩�٤ϡ�600BPI��bit per inch�ˤǤ��ꡢ75�����/�á�1.905m/s�ˤΥơ���®�٤ǽ��ߤ�Ԥ��ޤ�����
- ������ǽ���������ȡ���Ͽ®�٤�45,000�ӥå�/�á�5.6KB/�áˤȤʤꡢ1,200�ե����ȡ�366mĹ�ˤΥơ��פˤ���3ʬ�ˤ錄�ä�1.08MB�Υǡ�������¸�Ǥ��뤳�Ȥˤʤ�ޤ���
- CD�����̤�1/600�ˤ������ʤ��������̤Ǥ⡢1950ǯ��ε�Ͽ���ΤȤ��ƤϤ����������礭�ʤ�ΤǤ�����
- ��ǥ�726�����ơ������֤ˤϡ��礭����ħ������ޤ�����
- ����ϡ��ơ��פ��礭��U���ˤ���ޤ��뵡���Ǥ�����
- �屦�ޤ˼����褦�ˡ������ơ��פ����Է�ϩ�Ǥ�300mm�¤μ����ơ��ץ�뤫�鼧���إåɤ�Ƴ���������ˡ�500mm���٤Υơ��פΤ���ߤ��륹�ڡ������äƤ��ޤ���
- �ޤ��������إåɤ��鴬�������ʥƥ������åץ��ˤ˹Ԥ�����ˤ�Ʊ�ͤΥ��ڡ������ߤ����Ƥ��ޤ���
- �ơ��פ�U�����Τ���ߤϡ������ݥ�פ�Ȥäƥơ��פ�ۤ��ƺ�äƤ��ޤ�����
- �ʤ������Τ褦���礭�ʤ���ߤ��ä����Ȥ����ȡ������μ����ơ��פϥǡ��������ˤ˽�������ɤ߽Ф����ꤹ�����֤Ǥ��ä����ᡢ�ơ��פ����ˤ˥ǡ��������������ʤ��졢�������٥ơ��פϥ��ȥå�&��������ߤ����ԡˤ������֤���ޤ�����
- ���Τ��ᡢ�ơ������Է�ϩ�ˤ��������˾סʥХåե�������ߡˤ��ߤ��ʤ��ȥơ��פ�쥹�ݥ��ɤ���®��ư�������Ȥ��Ǥ��ʤ��ä��ΤǤ���
- ���ߤβ桹���ͤ��뼧���ơ������֤ϡ������ƥ�ΥХå����åפȤ��ư쵤�˥ǡ������������ɤ߽Ф����ꤹ���Τȹͤ������Ǥ��������������٥ǡ������ɤ߽������֤��ä��ΤǤ���
- ��ǥ�726�ϡ����������ˤ�äơ�1/100�äǥǡ������������뤳�Ȥ��ǽ�ˤ��ޤ�����
- �ơ��פ�1/100�ä�0.5�������12.7mm�˿ʤ�Τǡ����δ֤ϥǡ�����Ͽ���뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
- ��ǥ�726�Ǥϡ��ǡ�������ڤ�ˤ�����¸���뤿�ᡢ�ǡ����֥��å��֤Ϥ���ʬ�����Υ��ڡ������ߤ��Ƥ��ޤ�����
- 1960ǯ�夫��1980ǯ����緿�������ˤϡ�����ʼ����ơ������ַ����ú¤��Ƥ��ơ���®�ǥ��ȥå�&�������֤��ʤ���ǡ������������Ƥ��ޤ�����
- ����ư�����ܿ������ä�����ˡ������ơ������֤Ȥ���ư��������ԥ塼�����Τ�Τ���̾��Τ褦�˥�ǥ����˼��夲���Ƥ��ޤ�����
- �� ��
- LTO���ʤΥǡ������ȥ졼���ơ��ס� 1�������Υ����åȤ˼�Ǽ����Ƥ��롣
- ��������/�ɤ߽Ф����֤��������ƻ��Ѥ��롣
- ����LTO��Linear Tape-Open��Ultrium������2010.12.12�ɵ���
- �����ơ��פϡ�����ȶ��˥ޥ���إåɤˤ���̩�ٹ�®��Ͽ���Ǥ���褦�ˤʤ�ޤ�����
- 2009ǯ�����ˤ��äƤ�1/2�������12.7mm�˼����ơ��פϡ��ᥤ��ե졼����緿����ԥ塼���ˤΥХå����å�Ͽ���֤Ȥ��ƻȤ��³���Ƥ��ޤ���
- �����������ơ��פϡ�LTO��Linear Tape-Open��Ultrium���ʤˤʤäƤ��ޤ��ʱ��ޡ������ȡˡ�
- ���ε��ʤϡ�1998ǯ��IBM��HP��Seagate��3�Ҥ����ꤷ�������ץʤǤ���
- ���ε��ʤδ��äȤʤäƤ���Τϡ�IBM��1980ǯ������Ѥ��Ƥ��륫���ȥ�å�3480�Ǥ���
- ���衢����ԥ塼���ǡ������ȥ졼���μ����ơ��פˤ϶��̤ε��ʤȤ�����Τ��ʤ��ä����ᡢ�����褤�β����ȤʤäƤ��ޤ�����
- �����桼�����Ȥ��䤹���褦�˵��ʤ�����ľ���������ץ����Τ����ε��ʤǤ���
- ���ε��ʤϻ���ȤȤ�˿ʲ�����LTO-1����LTO-5�ޤ�ȯŸ����2010ǯ�ʹߤ�LTO-6��3.2 TB���̡ˡ�LTO-7��6.4TB���̡ˡ�LTO-8��12.8TB���̡ˤλ��ͺ��꤬��������Ƥ��ޤ���
- 2010ǯ�˺��ꤵ�줿LTO-5���ʤ�ʲ��˼����ޤ���
- ��ȯ��������2010ǯ
- �������ȥ�å���ˡ����102.0 x 105.4 x 21.5 mm
- ����¸���̡���1.5TB
- ���ơ��ҡ���1/2�������12.7mm��
- ������ǡ���®�١���140MB/s
- ���ơ�������®�١���3.8m/s �� 7.5m/s
- ���ơ��פθ�������6.6um
- ���ơ���Ĺ������846m
- ���ơ��פΥȥ�å�������1,280
- ������ü�ҿ�����16
- ���Х��������Υ�å�����20
- ����Ͽ̩�١���15,142��bits/mm
���ǡ����̿����ե���������Serial-attached SCSI (SAS)
- ���ε��ʤǤϡ������ȥ�å����ơ������1.5TB�Υǡ�������¸���뤳�Ȥ��Ǥ�������140MB/�äε�Ͽ®�٤���äƤ��ޤ���
- �ޤ������ε��ʤϥơ��פ�4�Х�ɤ�ʬ���ơ�1�Х��������16ch�Υإåɤ�Ȥäƥơ����20��Ԥ����10�����ˤ��ơ��ǡ��������/�ɤ߽Ф���ԤäƤ��ޤ���
- 16ch�μ����إåɤϡ��ơ��פα����˥ߥ�����ñ�̤ΰ��������Ԥ�����Ŭ�ʥȥ�å����֤ǤΥǡ����ɤ߽�ԤäƤ��ޤ���
- ���ޤ˥ơ��פΥȥ�å��ѥ�������ޤ���12.7mm���Υơ��פˤϡ�1,280�ȥ�å������ꡢ�ơ��פ�ξü�ˤ�������Τ���Υ����ܡ�����˿��椬��Ͽ����Ƥ��ޤ���
- �ȥ�å����ʬ������5um���٤Ȥʤꡢ�����ޥ�������ͥ뼧���إåɤ�Ȥä��ɤ߽�ԤäƤ��ޤ���
- �����ȥ�å���Υơ��פϡ��ǡ����ɤ߽Τ���˥����ȥ�å�����Ф������ä���η����֤����ѻ��˹Ԥ����Ȥˤʤ�ޤ���
- ��serpentine recording = �����ڥ���ˡ�������ڥ���ϼؤμعԱ�ư�ΰ�̣�ˡ�
- ���Υ��ԡ��ɤϡ�3.8m/s��7.5��/s�ȤȤƤ�®���������ơ��פ����ԤǤϺ�®�Ǥ���
- ���Υơ��פλ��ĥǡ������̤�¤ꡢ�������ܤ���ӤƤ���DVD��HDD����Ӥ��ƤϿ���̤䵭Ͽ®�١���ǥ����β��ʤʤɤ����ǰ����Ȥ��Ƽ����ơ��פΥ��åȤ����뤳�Ȥ˵��Ť�����ޤ���
- LTO-5�Ǥϡ�����140MB/s�ε�Ͽ®�٤�����ޤ�������®�٤�HDD��4�ܤε�Ͽ®�٤��������ޤ���
- ��ǥ�����1.5TB��1����������15,000�����٤Ǥ���
- 1.5TB���̤ϡ�100�����٤�DVD����320��ɬ�פǤ����顢��ۤˤ���32,000�ߤۤɤˤʤꡢ�ݴɤ����ѤǤ�����LTO�Υ��åȤϽ�ʬ�ˤ���ޤ���
�������������Τ��Ȥʤ��顢�ơ��פ�Ϣ³������Ϣ�ε�Ͽ�����դǤ��ꡢǤ�դ����̤���Ф�����ե�����������ؤ�����ʥ����ॢ�������ˤ��뤳�ȤϤǤ��ޤ���
- ���äơ�����ʥǡ�����Хå����åפ�����Ū�˰��Ϥ�ȯ�����ޤ���
- ���������ơ��פΥǥ����뵭Ͽ�ȥӥǥ�Ͽ��
- ����ԥ塼���˻Ȥ��Ƥ��������ơ������֤ȡ��ƥ��ʬ��ǻȤ��Ƥ���������Ͽ���뼧���ơ��סʥӥǥ��ơ��ס����֤ϡ����줾���̡�����Ū����äƳ�ȯ���줿��Τǡ����줾��Υ��˥�������������dz�ȯ��³���Ƥ�����ΤǤ���
- ������Ͽ���ܼ��ϰ㤤�ʤ���ΤΡ���Ͽ�������ۤʤäƤ�������˳�ȯ�Ϥ��줾����Ω����ƻ�����ǹԤ��ޤ�����
- ξ�Ԥ��礭�ʰ㤤�ϡ���ȯ�����ǥ����뵭Ͽ�����ʥ�����Ͽ���Ǥ���
- �����ơ��ǥ����뵭Ͽ�ϥ���ԥ塼���Υǡ�����¸����ȯ���Ǥ��ꡢ���ʥ�����Ͽ�ϱ����ʤ⤷���ϲ����˵�Ͽ����ȯ���Ǥ�����
- ����ԥ塼���μ������֤Ȥ��Ƥμ�����Ͽ�ϡ��ǥ����뵭Ͽ��������ʤΤǤ���Ͼ�������Ǥ��ޤ���
- ����ӥǥ�Ͽ���NTSC���ʤ���ɽ�Ȥ���ӥǥ�����ε�Ͽ��������Ǥ��ꡢ�������餫��2011ǯ��������λ�˻��ޤǥ��ʥ�������Ǥ���
- �����ơ��ӥǥ������1�ô֤�30�ե졼�ࡢ��������525�ܤȤ����礭�ʷ�ޤ꤬���ꡢ����С����뵭Ͽ��������Ԥ�ʤ���Фʤ�ޤ���
- �ӥǥ�Ͽ��ˤϡ���ȯ���餫����ȿ��Ӱ�ι⤤��ǽ��Ĺ���ֵ�Ͽ��ǽ�������Ƥ��ޤ����������ǥ�����ǹԤ����ʤ������Բ�ǽ�Ǥ�����
- �ƹ�AMPEX�Ҥ��ӥǥ��ơ��ץ쥳������ȯ����1956ǯ���Ż����ʤȸ����С������ɤ������λ���Ǥ�����
- ���λ���ˡ�9MHz�α��������ơ��פ˵�Ͽ���ƺ�������Ȥ������֤������ʤ���Фʤ�ޤ���Ǥ�����
- ���α��������ǥ����뿮���ľ������¸����Ȥ���ȡ�1�����8�ӥåȡ����256��Ĵ�ˤȤ��Ƥ�72M�ӥå�/�äο��������ɬ�פȤ��ޤ���
- ���̤ʤɻפ�����ʤ�����Ǥ����� ���ȿ��ι⤤�ƥ�ӿ���ˤ��äƤϡ�������Ȥ�����������ε��Ѥ��ǥ����뿮������ˤϤʤ����ɤ��Ĥ����Ȥʤ�����Ǥ��ʤ����;���礭�ʾ㳲�Ǥ�����
- ���ʥ����ϥǥ��������٤ƹ�®�������Ǥ�����åȤ����ä��ΤǤ���
- ���������ʥ��������ϥΥ���������������Ǥ�����¿����ž���䥳�ԡ����֤�����ʼ����������ޤ���
- �ǥ���������ϡ�����Ū�˿�������������ޤ���
- ���������ǥ���������ˤ����֤��Żҽ�������٤������ˤ�����ޤ���
- ��®��Ͽ�δ�����������ȡ����ʥ����������ǥ��������®���Ԥ����Ȥ��Ǥ��ޤ�����
- �����������夬Ĺ��³�����ΤǤ���
- �����Υǥ�����Ͽ���ϡ�1982ǯ��D1�Ȥ������ʤǸ���ޤ���
- ����ϡ������ɤ�VTR�˺��Ѥ��줿���ʤǤ���
- VHS�ӥǥ�����ȯ���줿1976ǯ��6ǯ��λ��Ǥ���
- 1970ǯ�夫��1980ǯ�塢VTR���������������äƵ����Ϥ���ƹԤä����Ȥ����Τ��Ȥ�������Ǥ��ޤ���
�� ��
- �����ӥǥ��ơ��ץ쥳������-��VHS vs �١���
- �����ǡ��ӥǥ��ơ��ץ쥳��������ɽŪ���ʤȤʤä�VHS���ʤȥ١������ʤˤĤ��ƿ���ޤ���
- VHS���ʤΥӥǥ��ơ��ץ쥳�����ϡ�1976ǯ�����ܥӥ������ˤ�äƳ�ȯ����ޤ���
- VHS�ϡ�Video Home System��ά�ȸ����Ƥ��ޤ�������ȯ�����Video Helical Scan��ά�Ǥ��ä��ȸ����Ƥ��ޤ���
- �ƹ�AMPEX�Ҥ�2�������50.8mm�����μ����ơ��פ�Ȥäơ���ž�ӥǥ��إåɤ��ľ�˥�������transverse scanning�ˤ��뵡���Υӥǥ��ơ��ץ쥳�������������Τ�����Ȥ��ơ���ꥳ��ѥ��Ȥ�1/2�������12.7mm�˥ơ�������Ȥä������åȤ˼����ӥǥ�Ͽ�����֤���ȯ����ޤ�����
- �������ѤǤϡ�3/4�������19.05mm�����ơ��פ��åȤ����줿U-matic��1970ǯ��ȯ���糫ȯ�ϥ��ˡ����ե��ߥ�Ͼ����Ŵﻺ�� = �ѥʥ��˥å������ܥӥ�����������5�ҡˤ�����Ū�Ǥ��ä��Τǡ��ơ��Ҥ�˾���������1/2�������12.7mm�ˤΥ����åȥơ��פ�Ȥä����塼���ѡ�̱���ѡˤȤ��Ƴ�ȯ����ޤ�����
- �����ơ��פˤ�����Ͽ��ϡ�����ڥå����Ҥ�VTR��ȯ�ʹߡ������إåɤ���ž���륹��������������夷�ޤ���
- ���ˡ����������Ѥ�1976ǯ�˳�ȯ����1�������25.4mm��VTR�ϡ�ľ��134mm�β�ž�ɥ��Τۤ�������354°�ˤ��դ����C�ץե����ޥåȡʤ⤷���ϥ��ᥬ = Ω �����ˤǤ�����
- �� �� ��
VHS�ȥ١����Υӥǥ�����ϡ��桼����������㤷����������å��Ǥ������ʥӥǥ����衧1976ǯ��1988ǯ��
- VHS�ե����ޥåȳ���
- * ��ȯǯ����1976ǯ
- * �糫ȯ����������ܥӥ�����
- * �رġ��������Ŵ�ʸ��ѥʥ��˥å��ˡ�
- ������������Ω����ꡢ��ɩ�ŵ������㡼�ס�
- �����������ְ��ŵ�
- * ��Ͽ�������إꥫ�륹���������
- * ��Ͽ�إåɿ���2
- * �إåɥɥ��ľ�¡�62mm
- * �إåɥɥ���ž����29.97Hz ����1,800rpm��
- * �����åȥơ��ץ�����: 188mm×104mm×25mm
- * �ơ�������1/2�������12.7mm��
- *�ơ�������®�١���33.34mm/s(ɸ��)
- * ��Ͽ�ȥ�å�������58um(ɸ��)
- * �������� ����VHS����
- �����������桧���ȿ���Ĵ (FM)
- �����å�3.4MHz
- ��ԡ�����4.4MHz
- �������桧����Ѵ�����
- S-VHS����
- �����������桧���ȿ���Ĵ(FM)
- �����åס�5.4MHz
- ��ԡ�����7.0MHz
- �������桧����Ѵ�����
- �����������桧2�����ͥ�Ĺ��������Ͽ
- �ʥΡ��ޥ벻���ȥ�å��ξ���
- �١����ե����ޥåȤγ���
- * ��ȯǯ����1975ǯ
- * �糫ȯ����������ˡ�
- * �رġ�����ǡ������ŵ��������ŵ�������� �����������ѥ����˥�
- * ��Ͽ�������إꥫ�륹���������
- * ��Ͽ�إåɿ���2
- * �إåɥɥ��ľ�¡���74mm
- * �إåɥɥ���ž����29.97Hz ����1,800rpm��
- * �����åȥơ��ץ�����: 156mm×96mm×25mm��
- * �ơ�������1/2�������12.7mm��
- * �ơ�������®�١���40mm/s
- * ��Ͽ�ȥ�å�������58um
- * ����������
- �����������桧���ȿ���Ĵ (FM)
- �����åס�3.6MHz
- ��ԡ�����4.8MHz
- �������桧����Ѵ�����
- �����������桧2�����ͥ�Ĺ��������Ͽ
- �ǽ�Ū��̱���ѤΥӥǥ����֤ϡ�VHS���������ޤ�����
- ���Ѥι⤵�ȥޡ����åƥ��ι��ߤ���Ϣ��Ϣ����³���륽�ˡ��ˤ������˼��ˤ����̤Ǥ�����
- ���������ξ�����Ĥ��δ֡����ʤ뿷�������� = �ǥ������������Ƭ�ˤ�ꡢ���ʥ�����Ͽ�Ǥ���VHS���֤⽪��λ�����ޤ��ʤ���Фʤ�ޤ���Ǥ�����
- 2008ǯ1��ˡ�VHS�ˤ��VTR�����������ƽ�λ���ޤ�����
- VHS�ϡ�32ǯ����ˤ��ä��ȸ������Ȥ��Ǥ���Ǥ��礦����
- ���ʥ�����VTR�ϻѤ�ä��ޤ��������ǥ����������ˤ��VTR�ϡ����ߤ��ή�ǻȤ��Ƥ��ޤ���
- 1/4�������6.35mm�����Υ��ơ��ס�miniDV�ˤ���Ѥ����ǥ�����ӥǥ������ˤϡ���ž�ɥ��إåɤˤ��ǥ����뵭Ͽ��������Ѥ��Ƥ��ޤ���
- �������ѤΥǥ�����ӥǥ��������ˤ�ǥ�����ӥǥ��ơ��פ��Ȥ��Ƥ��ޤ���
- 1/2����������å������Υӥǥ�Ͽ�����ֳ�ȯ�ϡ���������ˤ��礭���פ�Ĥ��ޤ�����
- ����ϡ����˥ӥǥ��λ���������𤲤���������ä��ȸ��äƤ����ǤϤʤ��Ǥ��礦��
- ���̲�������ڤ��뤳�Ȥ�����ۤɤθ��̤�⤿�餹�Τ����Ȼפ��Τ餵�줿������Ǥ����� �ޤ���̱���Ѥ�VTR����ڤ�ȼ�äƥӥǥ���Ϣ���֤�����Ū��ȯŸ����CCD�����ν�����¥���ޤ�����
- CCD�����Ⱦ����ӥǥ��ơ��ץ쥳������8mm�ӥǥ��ˤγ�ȯ�������ϡ��֥ӥǥ��ס���CCD�פȤ������դ���������դޤ����夵���������Ӥ���礵�����Τߤʤ餺���������������Ѥ����פ��������ѤΥ�����ӥǥ��ơ��ץ쥳�����شԸ����뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ�����
- �Ծ�γ���ˤ�ꡢCCD�����ϳ��ʤ˰¤��ʤꡢ��ڤ˥ӥǥ����������Ȥ��Ǥ���褦�ˤʤ�ޤ�����
- ����ԥ塼����CPU�ˤ�ȯŸ�ϡ��ǥ�����������Ѥˤ������֤��ޤ�����
- ����ԥ塼����ȯŸ�ʤ����ơ����Υǥ����������ȯŸ�Ϥʤ��Ǥ��礦��
- �����α����������Ƥ⡢��ñ�˸��뤳�Ȥ��Ǥ��ʤ�����Ѳ��ͤ��ʤ�����Ǥ���
- �� �� ��
- ����DV���ʤȥ��ơ���
- �����ơ��פϡ��ӥǥ�Ͽ�����ΤȤ���ȯŸ��뤲��1982ǯ�ˤ�VHS�ơ��פ����Ѥ���200����/�äι�®�٥ӥǥ�����餬���ޤ�ޤ�����
- 1984ǯ�ˤ����Ѥι�̩�ټ����ơ��פ�Ȥä�2,000���ޡ��äι�®�٥����⸽��ޤ�����
- �����ơ��פ�Ĺ���֡���®Ͽ��Ȥ�����˸����˱�������Ͽ���ΤǤ�����
- ���ߤ��������ѤΥǥ�����ϥ��ӥ�����Ѥα�����Ͽ���Τˤ⼧���ơ��פ��Ȥ��Ƥ��ޤ���
- �������������ơ��פȸ��äƤ���Ȥ���ʬ�Ѥ��ޤ�����
- �����ơ��׳�ȯ���礭�ʵ��ѳ��ϡ���Ͽ���������ʥ�����Ͽ����ǥ�����ˤʤä����Ȥȡ������ơ����Τ�����ѥ��Ȥˤʤ������ơ��פ����Ѥ��줿���ȤǤ���
- �桹�λȤ�������̤���ǤϤ狼��ʤ����ε��ѤȤ��ơ������γ�ȯ�Υ֥졼�����롼�⤢��ޤ����� ����ޤǤμ����Τϡ�����Ŵ��Х�������ȸƤФ��ٻ��Τ˺����Ƥ����ơ��פ����ۤ��Ƥ��ޤ�����
- ���������������夨�Ƽ����ΤΤޤޥơ��פ˾��夹�뵻�Ѥ���ȯ����ޤ�����
- ���줬������ơ��ס�ME = Metal Evaporated�˥ơ��פȸƤФ���ΤǤ���
- ���ơ��פˤϡ�������Ͽ�˴�Ϳ���ʤ��Х��������̵���Τǥơ��פ��������뤳�Ȥ��Ǥ�����Ͽ̩�٤���夵���뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ�����
- ������������ȯŸ����ǡ������ơ��פϡ�
- 2������ơ�������50.8mm�ˤΥ����ץ���
- → 1�������25.4mm��
- → 3/4�������19.05mm��
- → ��8mm��
- → 1/4�������6.35mm��
- → 1/2�������12.7mm��
- �Ⱦ������ʤäƤ����ޤ�����
- �⤤���ȿ��Ӱ�ޤǽ�ʬ����ǽ�������Ƥ���ȡ�������ǥ�����ǵ�Ͽ�Ǥ����ǽ�����ФƤ��ޤ�����
- 8mm�ǥ�����ӥǥ������ϡ����ơ��פΥ���ѥ��Ȥ��ȵ�Ͽ̩�٤ι⤵�ˤ�äƼ¸��Ǥ����ȸ����ޤ���
- DV�����ϡ���ˤ�Ҥ٤�NTSC���ʥ��������ǥ������ľ�������ʤǡ����ޥ��奢�����Υӥǥ�����˹������Ѥ����褦�ˤʤä���ΤǤ��� ��������
��
- �� ��
- �ڥե��åԡ��ǥ�������Floppy Disk = FD�ˡ�������2009.10.18�ɵ��ˡ�2010.12.22�ɵ���
�ե��åԡ��ǥ������ϡ��Ŀ���Ū��ޤ��2005ǯ���ޤǤΥѡ����ʥ륳��ԥ塼���ΰ���Ū�ʵ�Ͽ���ΤǤ��ꡢ����ѥ��Ȥ��Ȱ²��Ǥ��뤳�Ȥ������ˤ褯�Ȥ��Ƥ��ޤ�����
- ��������2005ǯ�ʹߡ����Υ�ǥ������Ȥ��뤳�ȤϤۤȤ�ɤʤ��ʤ�ޤ�����
- ���ξڵ�ˡ�2000ǯ�ʹ�ȯ�䤵���ѥ�����ˤϥե��åԡ����֤���������ʤ��ʤ�ޤ�����
- �ե��åԡ��ǥ������ϡ��������ե������ѵ�Ͽ���ΤȤ��Ƥ����Ѳ��ͤϤʤ�����äѤ�ɥ�����ȥե��������¸�˻Ȥ��Ƥ��ޤ�����
- ���Υ�ǥ����ϡ��������̤����ʤ��ƥǡ�������������®�٤��٤��Τǡ������ǡ������ˤ��Ը������ä��ΤǤ���
- �ե��åԡ��ǥ������ϡ���ڤ˻������٤����Τ�²��Ǥ��ä��Τˡ�2000ǯ�ˤ��Ƶ�®�˻Ծ줫��Ѥ�ä��Ƥ��ä���ͳ�Ȥ��ưʲ��Τ�Τ��ͤ����ޤ���
- �����ѥ�����ΰ����ǡ������̤��б��Ǥ��ʤ��ʤä����ʲ����ե��������Ƭ��OS�����粽��
- �����ե��åԡ��ǥ��������ɤ߽�®�٤��٤��ä��� ����125k�ӥå�/s��
- ����CD-R/RW����ڤ��ơ����줬�ѥ������ɸ�������Ȥʤä���
- �����ե�å���������ڤˤ�ꡢ��ڤ������̤Υǡ����� �Хå����åפǤ���褦�ˤʤä���
- �����ѥ��������Τ�USB��ɸ���������졢��ڤ˼��յ����CD��DVD��HDD��USB����ˤ���³�Ǥ���褦�ˤʤä���
- ������ȯ
- �ե��åԡ��ǥ�������IBM�Ҥϥǥ������å� = diskette�ȸƤ�Ǥ����ˤϡ���������77um���Ρ˥ݥꥨ���ƥ�ե������ƹ�Du Pont�Ҥγ�ȯ�����ޥ��顼�ե���� = Mylar�ˤα��ġ�floppy = �ե��åԡ��ˤ˼����Τ����ۤ����ݸ���������줿��Τǡ�������ɤ߽����֤��������ƥǡ������ɤ߹�����ꡢ�Ф���ԤäƤ��ޤ�����
- �ե��åԡ��ǥ��������ɤ߽�Ԥ������إå���¢���֤�ե��åԡ��ǥ������ɥ饤�֡�Floppy Disk Drive = FDD�ˤȸƤ�Ǥ��ޤ�����
- �ե��åԡ��ǥ��������ƥब�ǽ�˳�ȯ���줿�Τϡ�1967ǯ�Τ��ȤǤ��� �ѥ������1981ǯ�ˤ��о줹��Ϥ뤫�����Τ��ȤǤ��� �������֤ϡ�IBM�ҤΥ��˥��������F�����奬���ȡ�Alan Field Shugart: 1930.09 - 2006.12�ˤ��ѥ�������������ѤȤ��Ƴ�ȯ���ޤ�����
- �����Υե��åԡ��ǥ����ε�Ͽ���̤ϡ�8�������φ203mm�ˤ��礭��������ˤ⤫����餺���鷺��256KB�Ǥ�����
- IBM�Ҥϡ���������餬��ȯ�����ᥤ��ե졼��Ǥ���IBM370�Υ����ƥ�������ѤȤ��ơ���갷�������ؤʳ����������֤���Ƥ��ޤ�����
- �������ѤȤ��Ƴ�ȯ���줿�Τ���8������ե��åԡ��ǥ��������ä��ΤǤ���
- �ե��åԡ��ǥ������ϡ����äơ������Τ��Ȥʤ��鳫ȯ���餫��ǥ����뵭Ͽ���ΤǤ�����
- 8������ե��åԡ��ǥ������ϡ�Memorex�Ҥ������䤵��ޤ�����
- Memorex�Ҥ���Ω�ϡ�1961ǯ�Ǥ���
- ���β�Ҥϡ�VTR��ȯ����AMPEX�Ҥ������3̾�ˤ�äƼ����ơ�����¤����Ū�Ȥ�����Ω���졢IBM�Ҹ����μ����ơ��פȼ����ǥ���������¤����Ĺ���ޤ�����
- Ʊ�Ҥϡ�2006ǯ��Imation�Ҥ˵ۼ�����ޤ�����
- ��
- ����IBM�ѥ�������ɡ�IBM 80 Column Punched Card Format��
- 1928ǯ�˳�ȯ���졢1970ǯ��ޤǼ�ή�Ǥ��ä�IBM �ѥ�������ɡ� �� �����ɤ��礭���ϡ�7 -3/8 x 3 -1/4�������187.3mmx82.55mm�ˡ� �����ϡ�0.007�������0.178mm�� = 143���1�������25.4mm�ˡ�
- �������緿�����ϡ����Υ����ɤ��ɤߤäƥХå���«�˽������줿��
- IBM����ȯ�����ե��åԡ��ǥ������ϡ������������֤μ�ή�Ǥ��ä��ѥ�������ɤ�¿ʬ�˰ռ����Ƥ��ޤ�����
- �פ���ˡ��ѥ�������ɤ��֤���������Ū�ǥե��åԡ��ǥ���������ȯ���줿�ΤǤ���
- �ѥ�������ɤˤ����������1800ǯ�夫�餢�ꡢ����ԥ塼�����Ǥ���������餢��ޤ�����
- �ѥ�������ɤ�ǽ�˻Ȥä��Τϡ��ե��ȯ���ȥ��祼�ա��ޥ�����㥫�����Joseph Marie Jacquard�ˤǡ��बȯ��������ʪ��ʸ�ͤ��������֡ʥ��㥫���ɿ����ˤ˺��Ѥ��줿�ȸ����Ƥ��ޤ���
- ������ꥹ�ο��ؼԥ��㡼�륺���Х٥å���Charles Babbage��1791ǯ - 1871ǯ�ˤ������ز��Ϥ�Ԥ��������Ȥ߹��ळ�Ȥ�1800ǯ���Ⱦ�˹ͰƤ�������ԥ塼���ؤ����������֤Ȥ������ܤ���ޤ�����
- ����ԥ塼�����Τ�1940ǯ��Ⱦ�ˤʤ�ޤǼ���Ū�ʤ�Τ����줺���ѥ�������ɤ����̤Υǡ���������ɬ�פȤ���ʬ��˻Ȥ�졢1890ǯ���ƹ����Ĵ�����ƹ��ȯ���ȥϡ��ޥۥ�ꥹ��Herman Hollerith��1860ǯ - 1929ǯ�ˤ���ä��������֥��ӥ�졼�ƥ��ޥ����Tabulating Machine�ˤ˻Ȥ��Ƥ��ޤ�����
- �ƹ�IBM�ҡ���Ω��1911ǯ�ˤϡ��ۥ�ꥹ�ζ�����Tabulating Machine Company�����Ρ�¾��2�ҡ���3�Ҥι�ʻ��ҡˤȤ��ơ����ӥ�졼�ƥ������֡ʥѥ�������ɥ����ƥ�ˤ���¤���䤹���ҤȤ���ȯŸ���ޤ�����
- �ѥ�������ɤ�IBM�ο�¡�����ä��ΤǤ���
- IBM�����Ѥ����ѥ�������ɤϡ�1928ǯ�˳�ȯ����IBM 80��ѥ�������ɡ�IBM 80 Column Punched Card Format�ˤ�ͭ̾�ǡ��ʸ夳�Υ����ɤ��Żҷ����λ���ˤʤäƤ�1980ǯ��Ⱦ�ФޤǤ���60ǯ���ϤäƻȤ�³�����ޤ�����
- IBM 80�� �ѥ�������ɤ���ħ�ϡ��ʲ����̤�Ǥ���
- ������η�����Ĺ������
- ����1��Υ����ɤ�80��1���12�ꡣ
- �� ���Ĥޤ�1��Υ����ɤ�12�ӥå�80����饯������Ͽ��= 960 bit = 120B��
- ���������ɤΥ������ϡ�7-3/8����� x 3-1/4�������187.325mm x 82.55mm�ˡ�
- ����������1�ɥ��ʾ���礭�����ʸ��ߤ�1�ɥ��ʾ�ϡ�������IJ�20%�������ʤäƤ��롣��
- ���������ɤθ����ϡ�0.007�������0.178mm�ˡ�1������θ�����143��Υ����ɡ�
- ���������ɤϡ���갷�����ڤʤ褦��ɽ�̤ࡼ�������������ľ��פ�����ݡ�
- ������®�����뤿�ᡢ1964ǯ���饫���ɤζ���ݤ�������
- ���������ɤˤ����Ѥμ�ǼȢ�����ꡢ2000��Υ����ɤ��Ǽ��
- ����1��12��ξ���ϡ�������12�����ξ夫��3���ܡ�12���ܤ�0����9�ˤ��ơ�
- ������ʸ���ϡ����־夫�黰��ʬ��Y��X��0�ˤΥ�����ѥ�����ꥢ���Ȥ߹�碌�����ʾ屦���ȡ�
- ����12���ηꤢ���ϡ��Żҷ����˻��Ѥ����ݤ�
- ����EBCDIC = Extended Binary Coded Decimal Interchange Code
- ���������˽�Ʒ���֤�����줿��
��οޤ����狼��褦�ˡ��ѥ�������ɤ����Ϥ���ʸ���ȥѥ����Υ����ǥ��ϴʷ�ǡ����߲桹��ǧ���������ˡ���äƤ��ޤ���
- �ʹ֤��ѥ����γ�������Ƚ�Ǥ��䤹����ˡ�ȤʤäƤ��ޤ���
- �ѥ�������ɤϡ�����ԥ塼�����Ǥ���������餢�ä��Τǡ��ʹ֤�ǧ�������餤���ˡ���Τ�Τηꤢ���Ϻ��Ѥ��ʤ��ä���ΤȻפ��ޤ���
- ��οޤǤϿ����ȥ���ե��٥å���ʸ�����ü�ʸ����ޤ213ʸ����������Ƥ��ޤ���
- �ºݤϡ�EBCDIC�ʳ�ĥ��ʲ�����ˡ�ˤ˽��Ȥ��ˤ����ʸ�����ɲä���ơ��ǽ�Ū��256ʸ���Ȥʤ�ޤ�����
- �ѥ�������ɼ��Τ�12��Ǥ���Τǡ���������ˡ�ˤ��Ƥ��ӥåȤ�ľ���ȡ�212 �����4,096����ˤε���Ƥ뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
- ���������ѥ�������ɤ����Ū�ʷаޤ���ͤ�ǧ�����ˤ���2��ˡ�����ǥ��ˤ��뤳�ȤϤ��������Τ褦����ˡ���ä��ȹͤ��ޤ���
- �ѥ�������ɤϡ��꺢�ʥǥ����뵭Ͽ���ΤǤ��ꡢ�ǡ������ɲä�õ�¤��ؤ�����ñ�ˤǤ��ޤ�����
- �����ػ����1970ǯ���Ⱦ�ˤΤ��Ȥ�פ��Ф��ȡ�����������ԥ塼���������˿��椷���ʤ�������Ƕ�Ĵ���������ä���ʪ���緿�Żҷ������ˤ���Ƥơ��������緿����ԥ塼�������֤��ƶ�Ʊ���Ѥ��뱿����ˡ���äƤ��ޤ�����
- �緿����ԥ塼���Υץ���������¸�ϡ��ѥ�������ɤǤ�����
- 1970ǯ��ΰ²��ʥǥ����뵭Ͽ���Τȸ����С��ѥ�������ɤ���ơ��פ��ä��ΤǤ���
- ���ѼԤϥѥ�������ɤ�«��Ȥ��Ʒ����������ꡢ�����ɥ���ǥѥ�������ɤ��ɤ�餻�ơ��������ٳ����Ʒ���̤���˹ԤäƤ��ޤ�����
- �ѥ�������ɤ�1980ǯ���ޤǻȤ��Ƥ��ޤ�����
- �ե��åԡ��ǥ��������о�ˤ�äơ����ؤǵ������̤��礭���ǥ����뵭Ͽ���Τλ���ˤʤ�ޤ�����
- �ե��åԡ��ǥ�����������Ū�˻Ȥ���褦�ˤʤä��Τ�1980ǯ�夫��ȵ������Ƥ��ޤ���
- �� ��
- �����ȥ�å��ȥ�������Track, Sector��
- �ե��åԡ��ǥ������˺��Ѥ��줿��Ͽ���Τϡ��쥳�����פΤ褦�˥�����˵�Ͽ���������ǤϤʤ������ڤ�˴ֻ��ڤꤷ�ơ������ॢ���������ǽ�Ȥ��ޤ�����
- ���ڤ�κǾ�ñ�̤ϡ������褯�Ȥ��Ƥ����ѥ�������ɡʱ���̿��ˤε������̤�����Ф���ޤ�����
- IBM���������Ѥ��Ƥ����ѥ�������ɤϡ�12���12�ӥåȡˣ�80�� = 960bit��120�Х��ȡˤ����̤���äƤ����Τǡ�8������ե��åԡ��ǥ������Ǥ�1���������������ˤ�ӥåȤ��ڤ���ɤ�128�Х��ȡ�27�ˤȤ��ޤ�����
- ��1�������ϡ����θ� 512�Х��� = 29�Х��� ��ɸ��Ȥʤ�ޤ������ǥ������������̲��ȤȤ�˥��������礭���ʤꡢ2011ǯ�ˤϥե�å�������1��������4096�Х��� = 212�Х��ȤȤʤ�ޤ�������
- ������ʬ��ˤ��ǥ�������Υǡ�����¸�ϡ�������26ʬ���ʬ������˥ǥ��������;��˲��ڤ�ȥ�å�����77�ȥ�å��ˤ�ʬ�䤷�ޤ�����
- �������뤳�Ȥˤ�ꡢ8������ե��åԡ��ǥ������ϡ�77�ȥ�å� x 26ʬ�� = 2002��������������꤬�Ǥ��ޤ������ʱ������ȡ�
- 1�������ϡ������ɥѥ����1��ʬ�ε�Ͽ���̤ʤΤǡ�����Υե��åԡ��ǥ�������256KB�ˤϡ�2002��Υѥ�������ɤΥǡ�������¸�Ǥ������Ȥˤʤ�ޤ���
�������ѥ�������ɤ�2,000����Ǽ����ѥ�������ɥܥå�����������ݴɤ���Ƥ����Τǡ��ѥ�������ɥܥå���1Ȣʬ��8������Υե��åԡ�1��ˤ��Τޤ������ؤ�뤳�Ȥˤʤ�ޤ�����
- �ե��åԡ��ǥ������ϡ��ǥ������β�ž�������ˤ��ƥǡ������ɤ߽���������CAV = Constant Angular Velocity�����ˤʤΤǡ��ե��åԡ�����¦�ȳ�¦�Ǥ���®�٤��ۤʤꡢ��¦�Υ���������¦�Υ���������٤Ƶ�Ͽ�ʼ�������Ȥ������꤬����ޤ�����
- ���äơ��ե��åԡ��Υǡ������̤ϡ���¦�Υ������Υǡ������̤�ɸ��ˤ��Ʒ����ޤ�����
- �����ѥ��������ܡ�-��CP/M
- �ե��åԡ��ǥ��������֤ϡ��ѥ�������Ū�ѤȤ��ƤǤϤʤ��緿����ԥ塼���ѤȤ��Ƴ�ȯ���줿���ȤϺ��Ҥ٤��Ȥ���Ǥ���
- IBM-PC��ȯ�䤵�줿1981ǯ���7ǯ������1974ǯ�ˡ��ޥ���������ԥ塼����8������ե��åԡ��ǥ����ɥ饤�֤�Ĥʤ�����ʪ�����ޤ���
- ���줬�����������ɡ����Gary Arlen Kildall��1942.5.19��1994.7.11�ˤǤ���
- ��ϡ�����ƥ�Ҥ���ȯ����8�ӥåȤΥޥ���������ԥ塼����i8080�ˤ�Ȥäơ��ǡ�����ޥ�����˥��åץ����ɤ����������������ɤ������ꤹ������ץ�������OS = Operating System�ˤ���ޤ�����
- ���줬���ѡ����ʥ륳��ԥ塼����OS�θ��ĤȤ����CP/M�� Control Program for Microcomputers���ޥ���������ԥ塼���Τ��������ץ��������Ǥ�����
- CP/M�ϡ��ޥ��������եȼҤ�ȯ�䤵�줿MS-DOS��MicroSoft Disk Operating System�ˤθ�����ʤ���ΤǤ�����
- CP/M�ˤϡ��ޥ���������ԥ塼���˥ǡ����������Ϥ�����BIOS��Basic Input/Output System�ˤȸƤФ�뿴¡�������ꡢ���ο�¡�����礭����䤬8������ե��åԡ��ǥ������������ä��ΤǤ���
- �������ե��åԡ����֤β��ʤ�1��������500�ɥ����15���ߡˤ⤷���Τǡ����μ�νФ���ʪ�ǤϤ���ޤ���Ǥ�����
- �����ǡ���ϥե��åԡ��ǥ������ɥ饤�֤Υ�������奬���ȡ������������ļҡ�Shugart Associates��IBM�Ҥθ�Manager���奬���Ȥ�1972ǯ����Ω������ҡˤ��������ơ��������֤��ѵץƥ��Ȥ�����ä��Ȥ��Ť��Υɥ饤�֤��Ǽ�����졢�������������CP/M�פȤ������ڥ졼�ƥ������ƥ��ȯ�����ΤǤ���
- ���Υ��ԥ����ɤ��鲿���狼�뤫�Ȥ����ȡ���������ȯ�ԤΥ����������ɡ���ˤȤä�500�ɥ뤬�ȤƤ��������Ǥ��ä����Ȥ��顢CP/M�ϸĿͥ١����dz�ȯ���줿�Ȳ��Ǥ��ޤ���
- �ѥ�����ʥޥ����åȡˤϡ�1970ǯ���Ⱦ�ˤ��äƤϸĿͤμ�̣�ǡʤ⤷���������Ǽ�ʬ�Υ���ԥ塼�����Ѥ������뤿��ˡ˺���Ƥ����ΤǤ���
- ����ο�¡���Ȥ������ܤΥӥ�����Ҥ���������4�ӥåȥޥ������ƥ�˺�餻��1971ǯ�������ޥ��������ǽŪ������Ⱦü�Ǥ��ꡢ��ȯ��������ƥ�Ǥ�������Ѥ��������ˤ��ޤ�����
- ���������Żҹ��ؤ������ʼ�ԤΥ���������٤��ä��ΤǤ���
- ����ƥ�ϡ�8�ӥåȥޥ������i8080�ˤ�ޤȤ��ư��������δĶ����եȤ�ȯ���뤿��ˡ������������ߤγ��������ر��ǥ���ԥ塼���������ζ����Ƥ��������������ɡ���Ѹ���ʥѡ��ȥ�����ˤȤ��Ƹۤ��ޤ�����
- ��ϡ������ݵ����ä��褦�ǡʤ���Ǥ���ŷ��Ū�ʥץ�����ޡ����ä��ˡ�����ƥ�λ�̳��˼֤ǽи����Τ�����Ǽ����������ä��Ż��褦�ȹͤ��ޤ�������2022ǯ�θ��ߤǤϡ������������ǻŻ���Ȥ����Τϡ������ͥåȤΤ����������̤ˤʤäƤ��ޤ���������ǧ�Ĥ����Ż����֤Ǥ���������2022.04.19�ɵ���
- �����ǡ������8�ӥåȥޥ������ץ����å�i8080��ư�����եȤ�夲�뤿�����ŤΥե��åԡ��ǥ������奬���ȼҤ�����������BIOS�θ����Ⱥǽ�Υѥ�������OS�Ǥ���CP/M����夲�ޤ�����
- ���Υ��եȤ�ƥ�˻���������ΤǤ���������ƥ�Ϥޤä����ؿ����ޤ���Ǥ�����
- ����ǡ���ʬ�Dz�ҡʥǥ�����ꥵ�����ҡ�Digital Research, Inc.�ˤ���1976ǯ��CP/M�ʥ���ƥ�i8080��OS�ˤ����䤹��褦�ˤʤ�ޤ���
- ���줬���ޥ��������եȼҤ�MS-DOS�����ΤǤ���
- �ޥ��������եȼҤ�IBM�Ҥ���ä�MS-DOS�ϡ�CP/M����ȡʥ����ǥ��ˤ��ۤȤ��Ʊ����Τ��ä��ȸ����Ƥ��ޤ���
- ������MS-DOS�ϥ���ƥ��16�ӥå�CPU i8086�˹�碌�ƥ����ǥ�����Ƥ��ޤ�����
- �ʸ塢IBM-PC����ȯŪ�ҥåȤϼ��Τ��̤�ǡ��ѥ�����˥ե��åԡ����������������Τ��Ȥʤ�ޤ�����
- 8������������Υե��åԡ��ǥ����ϡ�1976ǯ��5.25�������5 - 1/4������˥������ξ����ʤ�ΤȤʤ��礭����ڤޤ���
- ���ܤǰ��Ƥ����Ӥ��������ŵ���16�ӥåȥѥ�����PC-9801F��1983ǯȯ��ˤˤϡ�2���5.25�����2DD�Υե��åԡ��ǥ������ɥ饤�֤��Ĥ��Ƥ��ơ������ˤ�MS-DOS�Υ����ƥ�ե��åԡ����������졢�⤦�����ˤϥǡ�����¸�ѤΥե��åԡ��������Ǥ���褦�ˤʤäƤ��ޤ����� ����HDD�ʥϡ��ɥǥ������ɥ饤�֡ˤϤȤƤ������ä��Τǡ�����ԥ塼���ˤϥ����ƥ����¸���Ƥ�����Ͽ���Τ���äƤ��ޤ���Ǥ�����
- �����ƥ��ե��åԡ�����Ω���夲�Ƥ����ΤǤ���
- �����Ϥ������٤����̤ǥ����ƥब�Ǥ��Ƥ����ΤǤ���
- ����ˡ�1982ǯ�ˤϡ����ܤΥ��ˡ����ϡ��ɥ��С���ʤ�ä�3.5������Υե��åԡ��ǥ�����280kB�ˤ�ȯ���ޤ���
- ���θ塢���������ʥ����Ʊ��ε�Ͽ���Τ�ȯ���Ƥ����ޤ���������Ū�˸��ơ����ˡ��γ�ȯ����3.5������Υե��åԡ��ǥ����ʲ����̿��ˤ����֤����������褦�˻פ��ޤ���
- ���ˡ��Υϡ��ɥ��С�3.5������ե��åԡ��������������װ��ϡ�
- ����1984ǯ�Υ��åץ�ҥޥå���ȥå����ɸ���������줿���ȡ�
- ����1985ǯ�ˤϡ�������䥳��ɡ����³���ƥѡ����ʥ륳��ԥ塼����ɸ��Ȥ��ƹԤä����ȡ�
- �����ǥ������åȤ��ץ饹���å����С���ʤ��졢�ǥ������̤⼫ư���ĤΥ��饤�ɥ��С���ʤ���Ʒȹ������ɤ��ä����ȡ�
- �����ǡ������̤⽽ʬ���礭���ä����ȡ����ʤο��������⤫�ä����ȡ�
- �ʤɤ����ޤ���
3.5�����FDD�Ͽʲ���Ȥ���
- ������→����ȯ�����1982ǯ�ˤ����̤�280KB�Ǥ��ä���Τ���
- ��������→��ξ����̩�١�2D��360KB��
- ������������→��ξ����̩���ܥȥ�å���2DD��720KB��1984ǯ��
- ����������������→��ξ�̹�̩�١�2HD��1.44MB��1987ǯ��
- ��ȯŸ���Ƥ����ޤ�����
- ����������¸�ѤΥե��åԡ��ǥ�����
- �ե��åԡ��ǥ�������������¸�Ѥ˻Ȥ�줿���Ȥ�����ޤ���
- 1981ǯ�����ˡ���CCD����顢�ޥӥ���Mavica�ˤ�ȯ�����Ȥ��ˡ������ε������ΤȤ���2������Υե��åԡ��ǥ���������Ѥ��ޤ�����
- ��¸�����ϡ��ǥ�����ե�����ǤϤʤ�FM��Ĵ�������ʥ�����Ͽ�ǡ�570x490���������β�����50����¸���ޤ�����
- �����ϡ�NTSC���ʥ�������ˤ���ɤ߽Ф��ǡ���¸�Υƥ�ӥ�˥��Υӥǥ�ü�Ҥ˥����֥����³���Ƹ���褦�ˤʤäƤ��ޤ�����
- 1981ǯ�������Ż߲�����Ͽ���륫���ȸ����Хե���५��餬����Ū�Ǥ�����
- �����ϡ��ǥ�����ե����ޥåȤˤ���������������Ƥ��ޤ���Ǥ�����
- ��¬�Ѳ����ե������ͭ̾�ˤʤ�TIFF���Ǥ���Τ���1986ǯ�Τ��ȤǤ���
- ���̲�����ͭ̾��JPEG�ϡ�1992ǯ�γ�ȯ�Ǥ���
- ���äơ����λ���ˤ��äƤϲ�������¸�ʥ����Ǥ���ե��åԡ��˵ͤ������Τϲ��Ū�ʤ��ȤǤ�����
- ���ˡ��ϡ��ե��åԡ��ǥ����γ�ȯ���Ǥ��ä����Τ˥ե��åԡ��˼��夷���ǥ�����ޥӥ���Ф���1990ǯ���3.5������ե��åԡ��ǥ�������Ȥä��ǥ����륫�������䤷�Ƥ��ޤ�����
- 1999ǯ��ȯ�䤷���ǥ�����ޥӥ�MVC-FD88K�ϡ�130������CCD����ܤ���4��®�˿ʲ�����3.5������ե��åԡ��ǥ�����JPEG������4���1280x960���ǡˡ�40���640x480���ǡ�ʬ����¸�Ǥ���褦�ˤ��Ƥ��ޤ�����
- ���Υ����ϡ��ѥ�����ȤΥǡ��������Ϥ����ñ�ˤǤ��뤳�Ȥ����ä���ΤǤ��������ե�å���������Ƭ�ȤȤ�ˡ���Ͽ���̤Ƚ���®�١�����˼谷��������뤳�Υ����פΤ�ΤϽ���λ���ޤ���˻��ޤ�����
- �����ե��åԡ��ǥ���������ǽ�³�
- 2000ǯ��ۤ�������ꡢ�ѥ��������ǽ����ȤȤ�˥����ͥåȤ���ڤ��Ʋ�����������̿���������ˤʤ�ȡ����ˤ˰����ǡ��������̤�ž��®�٤��ե��åԡ��ǥ�������������ǽ��Ķ���Ƥ��ޤ��褦�ˤʤ�ޤ�����
- ���衢�ƥ����Ȥ����Ǥ��ä��ѥ������ʸ������ˡ�������Ž���դ����褦�ˤʤ�ȡ�ʸ������̤���㤤���礭���ʤ�ޤ�����
- A4��������40ʸ����45�Ԥ�����ʸ���äƤ������ϡ�4KB���٤Υե����륵�����ǺѤ�Ǥ����Τˡ�300dpi������80mm��60mm�Υ��顼������BMP�ˤ�Ž���դ���褦�ˤʤ�ȡ�����������2MB����¸���̤�ɬ�פȤʤ�ޤ���
- �������̤�3.5�����2HD�Υե��åԡ��ǥ������ε�Ͽ����1.4MB��椦��Ķ���Ƥ��ޤ��ޤ���
- �ޤ����ե��åԡ��ǥ������ϡ��ǡ�������Ф��Τ˻��֤�������ޤ���
- ž��®�٤ϡ�125k�ӥå�/s���٤Ǥ��뤿�ᡢ1.4MB���äѤ�����¸���줿�ǡ������ɤ߽Ф��ˤϡ�90�����٤�����ޤ���
- �ѥ�ƥ��ʤɤΥ��顼�����å��䥻�����֤ΰ�ư���֤�ͤ����3ʬ���٤Υ����������֤�и礷�ʤ���Фʤ�ʤ��Ǥ��礦��
- �����������Ȥ��顢�ѥ�����������Ǥϡ��ե��åԡ����������̤Ǥ���®�˥��������Ǥ��롢CD�ʥ���ѥ��ȥǥ������ˤ䡢HDD�ʥϡ��ɥǥ������ɥ饤�֡ˡ�MO��DVD���ե�å������ؤȵ�Ͽ���Τμ缴���ܤäƹԤ��ޤ�����
- ��
- �����ե��åԡ��ɥ饤�֡�FDD�˥������ű���ư����®������2009.07.28�ˡ�2010.07.10�ɵ���
- 2009ǯ7��27���դ�ī����ʹ�Ǥϡ��ե��åԡ��ǥ�������ư���֡�FDD�˥������3���ҡʥƥ����å����磻���������ǡ��������ˡ��ˤ���¤��λ����������Ĵ�������äƤ���Ȥ���������Ǻܤ��Ƥ��ޤ�����
- �ե��åԡ��ǥ������κ��綡���ҤǤ��ä����ˡ���2009ǯ9��˶�ư���֤���¤�Ͻ�λ�������ǥǥ���������¤��ԤäƤ��ޤ�����
- �����2011ǯ3����Ǥ��ڤ�FDD���Ȥδ���ű����ȯɽ���ޤ�����
- 3.5����FDD��1984ǯ���饳��ԥ塼������ܤ���Ϥ��ᡢWindows95��ȯ�䤵���1995ǯ��FD���פΥԡ����Ǥ��ä������Ǥ���
- ���������С��䤬�ǽ�˥ѥ��������ä�1993ǯ���ޥå���ȥå����LCIII�ˤˤ�3.5���Υե��åԡ��ɥ饤�֤��Ĥ��Ƥ��ơ�15��Υե��åԡ��������ؤ������ؤ�����OS�����줿����������ޤ���
- ���λ����Ϥޤ���CD���ѥ������ɸ�����ܤ���Ƥ��ʤ��ä��ΤǤ���
- ����FDD��2009ǯ�ǤϺ�������1/30�ˤޤ��������Ϥ�̾����ơ����פϴ�ȸ����Υ��ץ����˸¤��Ƥ��ޤä������Ǥ���
- 1967ǯ�Υե��åԡ���ȯ����43ǯ��Фơ�����̿���������ޤ�����
- �� �� ��
- ��Jaz��Zip��Bernoulli�ʤ��㤺�����äס��٤�̡����ˡ�
- �ե��åԡ����������ȤʤäƤ���1990ǯ��Ⱦ���ᥬ�Х��ȥ��饹�Υ�ࡼ�Х֥��ǥ��������ޤäƤ��ޤ�����
- ���������о줷���Τ����ƹ��IOmega�Ҥγ�ȯ���� Jaz��Zip��Bernoulli �Ǥ���
- �������ᥬ�Ҥϡ��ƹ�ե���˥�������ǥ������Ԥ�1980ǯ����Ω���줿����ԥ塼�����յ���β�ҤǤ���
- 2008ǯ4���EMC���������ޤ�����
- IOmega�Ҥ���ȯ���������ǥ��������ʤ�ǯ����֤ϡ�
- Bernoulli ��1983�� → Zip��1994�� → Jaz��1995��
- �Ȥʤ�ޤ���
- ���ߤǤϡ�������̾����ʹ�����Ȥ⾯�ʤ��ʤ�ޤ�������1990ǯ��ˤ��äƤϡ��������ݥåȤ���Ӥ���ǥ����Ǥ���
- �������ʤ��顢�������ʤ�²��ǿ��������⤤CD��DVD�Ȥζ����ͫ���ܤˤ��������ߤϰ����Υ桼�����Ȥ��ΤߤȤʤ�ޤ�����
- 2008ǯ�λ����Ǥϡ�Bernoulli��Jaz�⤢��ޤ���
- CD��DVD������ԥ塼����ɸ���ǥ����Ȥʤä����Τ�ľ����¢�����褦�ˤʤä��Τ��Ф������������ʤ�ɸ�������Ȥʤ뤳�ȤϤʤ������յ���Ȥ��Ƥΰ��֤Ť��˽��Ϥ��ޤ�����
- �ե��åԡ��ǥ���������ˤ�ߤƸ���ȡ�8�������128kB�Υե��åԡ��ǥ�������1970ǯ��IBM�ҤΥ����F�����奬���Ȥˤ�äƳ�ȯ����ơ�13ǯ���1983ǯ�˥������ᥬ�ҡ�IOmega�ˤ������̤Υե��åԡ��ǥ�������Bernoulli�ˤ�Ф������Ȥˤʤ�ޤ���
- Ʊ������1982ǯ�ˤˤϡ��ȳ�ɸ��Ȥʤ�3.5������Υϡ��ɥ����������ä��ե��åԡ��ǥ�������280kB�ˤ����ܤΥ��ˡ�����ȯ�䤵��ޤ���
- ���λ����˥������ᥬ�Ҥϡ�50�ܤΥǡ������̤���ĥե��åԡ��ǥ����������������ΤǤ���
- ����Jaz��1GB�Υ�ࡼ�Х֥�ϡ��ɥǥ�������
- Jaz�ɥ饤�֤ϡ�IOmega�Ҥ�1995ǯ�˳�ȯ����1GB���̤Υ�ࡼ�Х֥�ϡ��ɥǥ������Ǥ���
- 1998ǯ2��ˤϡ�2GB��ȯ�䤵��ޤ�����
- ��������4ǯ���2002ǯ����¤����ߤ��ޤ�����
- Jaz��Zip�Ȥΰ㤤�ϡ�Zip���ե��åԡ��ǥ������١����Ǥ��ä��Τ��Ф���Jaz�ϥϡ��ɥǥ������Ǥ��ä����ȤǤ���
- Jaz�ɥ饤�֤ϡ���¤���ϡ��ɥǥ������ʤΤ�Ʊ�����MO��Zip����ɤ߽����ʤ�®���Ԥ��ޤ����� 1995ǯ�����ϡ�OS��Windows95�ˤʤ�ѥ�����Υ����ƥब���粽���������ͥåȻ�����������ƥᥬ�Х������̤Υ�ǥ��������ޤäƤ��ޤ�����
- ����˸Ʊ�����褦�ˡ����������ʥ�ǥ�������ȯ������ƤäƤ��ޤ�����
- �������ˤ��äơ�CD�Ⱦ����ϡ��ɥǥ��������Ծ����ष�ƹԤä����ᡢJaz��ű���;���ʤ�����ޤ�����
- Jaz�ɥ饤�֤ϡ��ϡ��ɥǥ�������������ܤȤ��ơ�������ץ�å�����ȴ����������Ȥ��������ʥإåɤϸ������֤���¢�ˤΤ��ᤫ����������˳�������ȥ�֥뤬¿���ƻ��Ѥ˺�����꤬����ޤ�����
- Jaz�ϡ��ץ�å�ɽ�̤˥��ߤ����夹����������⤤��ࡼ�Х֥�ǥ����ǡ�5,400rpm��ι�®��ž�ˤ�äơ�1um�ε�Υ���֤��줿�إåɤȥץ�å��Υ��ꥢ�������פʤ���������Ȥ������䤬�來�ޤ���
- ���ʤߤˡ��Ƽ��ǥ����β�ž����Ӥ٤Ƥߤ�Ȱʲ��Τ褦�ˤʤ�ޤ���
- ����Jaz����5,400 rpm
- ����Zip����2,945 rpm
- ����Bernoulli Box����3,000 rpm
- �����ե��åԡ��ǥ������ɥ饤�֡���360 rpm
- ����MO����3,600 rpm��6,700 rpm
- ����CD����200 rpm��5,300 rpm
- �����ϡ��ɥǥ������ɥ饤�֡���4,200 rpm��15,000 rpm
- �졼������ԥå����åפ˻Ȥä���ǥ����ϡ��ԥå����åפȤΥ��ꥢ������Ū��������ΤDz�ž����夲�Ƥ�����Τ褦�ʵ������ޤ������إåɤȥץ�å����ε�Υ���ˤ�ƶᤤ�����ǥ������Ǥϡ��ۥ����⡼���ο�ư���������ʤɤ��к��ä���ȹԤ�ɬ�פ�����褦�˻פ��ޤ��� IOmega�Ҥˤ��äƤϡ�Jaz�ο���������夵���������ˤϸ����鷺�����ʤ������ȥåפ������ե��åԡ�������Zip�˼���ܤ��Ƥ�������������ޤ���
- ����Zip�ʥե��åԡ����Ф������̥ǥ�������
- Zip�ɥ饤�֤ϡ�IOmega�Ҥ�1994ǯ�˳�ȯ������곰����ǽ�ʼ����ǥ������ˤ���ǥ��������ƥ�Ǥ���
- �ե��åԡ��ǥ�������Ʊ�ͤδ��ФǼ�갷����������ǡ������̤�¿���Τ���ħ�Ǥ�����
- �ǥ��������礭���ϡ�3.5������Ǥ��ꡢ������3.5������ե��åԡ��ǥ������˻��Ƥ��ޤ���
- ��ȯ����Υǥ������ϡ�100MB�Ǥ��ä���Τ������250MB��750MB�������ޤ�����
- �ǡ�����ž��®�٤�1MB/�äǡ������������ब28ms�Ǥ��ꡢ1.44MB�Υե��åԡ���62.5KB/�á�������0.2�áˤ˳Ӥ�1��ʾ�ι�®�����������Ǥ��ޤ�����
- Zip�����ƥ�γ�ȯ�����Ȥˡ��٥�̡����ǥ�������Bernoulli Box system�ˤ�����ޤ�����
- �����٥�̡�����Bernoulli�ˡʺǽ�Υ�ࡼ�Х֥�ǥ�������
- Bernoulli Box System�ϡ��ƹ�IOmega�Ҥ�1983ǯ�˳�ȯ������ࡼ�Х֥뼧���ǥ�������5.25�������10MB�ˤǤ���
- ���ܤˤϤۤȤ��͢������ޤ���Ǥ��������ƹ�ǤϷ빽�Ȥ��Ƥ����褦�Ǥ���
- 1980ǯ�塢�����̤Υ�ǥ����Ϥ���ۤ�¿���μ��ब���ä��櫓�ǤϤʤ��ä��Τǡ����Υ�ǥ����Ͻп��Ǥ�����
- ���Υ�ǥ����ϡ�3.5������Υե��åԡ��ǥ������ȳ��Ѥϻ��Ƥ��ޤ��������礭����5.25������Ǥ����ʶ�136mm x Ĺ140mm x ��9mm�ˡ�
- ���Υ�������35MB��230 MB�����̤�ܤ��Ƥ��ޤ�����
���Υ�ǥ���������ϡ��ڥ�ڥ�Υݥꥨ�����ƥ�ե��졼�ȡ�PET�����ե��åԡ��ǥ��������®�Dz�ž�����ơ�3,000rpm�ˡ���®ή�β��˵����뵤ή�α��������Ѥ��Ƹ���إåɤ˵ۤ��դ�����ʤ������ܿ����ʤ��˵����������줿���ȤǤ���
- �إåɤȥե��åԡ��δ֤ϡ���ή����ߤ��뤿��˷褷���ܿ�����1�ߥ�����δַ��������ޤ���
- �ϡ��ɥǥ������ɥ饤�֤����إå������ܿ����֤��鵤ή�����ȡ�0.03um�ˤ����Ƥ���Τ��Ф����٥�̡����ܥå����ϥǥ������Ѷʤ����ƶ�Ť��Ƥ��ޤ���
- �ǥ������β�ž���ߤޤ�е�ή���ߤޤꡢ�ե��åԡ��⸵�ΰ��֤����ΤǸ���إåɤȤε�Υ�ϼ�ưŪ��Υ��빽¤�ˤʤäƤ��ޤ�����
- ���äơ��٥�̡����ܥå����Ǥϥϡ��ɥǥ������ɥ饤�֤�ɬ�ܤǤ��ä���ȥ饯�ȡʥإåɤ�ץ�å�������Υ�������ˤ�ɬ����������ޤ���Ǥ�����
- ���������ϡ�����������������ŷ�Ϳ��ؼԥե��ߥ�ΰ�ͤǤ�����˥��롦�٥�̡�����Daniel Bernoulli��1700.02��1782.03�ˤ�ȯ�������٥�̡�����ˡ§����Ѥ��Ƥ��ޤ���
- ���Τ����ǥ�����̾����٥�̡�����̾�Ť����ޤ�����
- ���Υ�ǥ����������ܤǤʤ���ڤ��ʤ��ä��Τ��Ϥ褯�狼��ޤ����٥�̡������о줷��Ʊ���������ܤǤ�MO�ʸ������ǥ������ˤ���ȯ���줿����ˡ����ܤǤϤ����餬�ٻ����줿��Τȹͤ����ޤ���
- ����Ū�ˤϰ��ꤷ�Ƥ��빽¤�Ǥ��������ºݤϡ��ɤ߹����Υȥ�֥뤬���ʤꤢ�ꡢCD�δ��ؤ��Ȱ¤��ˤ������Ǥ��Ǥ��ޤ���Ǥ�����
�� �� ��
- �ڥϡ��ɥǥ������ɥ饤�֡�HDD�ˡ�������2007.11.25�ˡ�2008.10.24�ɵ���
�ϡ��ɥǥ������ɥ饤�֡�HDD = Hard Disk Drive�ˤϡ��ե��åԡ��ǥ������ɥ饤�֤����Ф������֤Ȥ����о줷�ޤ�����
- �ե��åԡ��ǥ��������֤Υ��ڡ������ŵ�����ʥǡ�������ˤ˸ߴ���������ơ����֤��ñ�������ؤ�����褦���߷��ۤ���äƤ��ޤ�����
- �ϡ��ɥǥ������ε�Ͽ���Τι�¤�ϡ��ե��åԡ��ǥ������Τ褦�������ƥڥ�ڥ�μ����Υǥ������Ȱ�äơ��ǥ������˶��̲ù���ܤ�������ߴ��ġ��⤷���ϥ��饹���ĤˤʤäƤ��ơ�����ɽ�̤�����Ŵ�����Τ����ۤ�����Τ�ȤäƤ��ޤ���
- ��ȯ���Ǥ��ä�IBM�Ҥϡ������HDD�����ǥ�������Fixed Disk�ˤȸƤ�Ǥ��ޤ���
- �ϡ��ɥǥ������ɥ饤�֤ϡ������̤ε�Ͽ���ΤȤ��Ƴ�ȯ����ȯŸ������ޤ�����
- ����γ�ȯ�ϡ��緿����ԥ塼���Ѥγ�����Ͽ�ѤǤ��������ѥ������ȯŸ�ȶ��˾��������̲�����®���������ʤɤ��ǽ�ˤ������ʤ����β�����ޤ�����
- HDD�ϡ����ߡ�2010ǯ�ˤˤ��äƤ�ѥ���������ơ������ˤ�����Ƕ��ε������֤Ȥ��Ʒ��פ��Ƥ��ޤ���
- ����ԥ塼���Υǥ����뵭�����֤Ȥ������ޤ줿HDD�ϡ������̡���®�����������²��Ǥ�����ħ��ǧ���졢�ӥǥ������ε�Ͽ���֡������ӥǥ��쥳�����ε�Ͽ���֡������ʥӥ��������ε�Ͽ���֡������Ѳ��ں������֤Ȥ��Ƴ����ξ��Ȥ��Ƥ��ޤ���
- ���������ǥ�����
- �ϡ��ɥǥ������ι�¤�ϡ��ե��åԡ��ǥ�����������Ʊ���Ǥ���
- �����ǥ������̤˼�����Ͽ���줿�ǡ������إåɤ�Ȥä��ɤ߽���Ȥ����������Ѥ��ޤ���
- ��������HDD�ϥե��åԡ��ǥ������ɥ饤�֤ȳӤ٤ơ��ǡ����Υ�����������㤤��®�������̤��礭���ư��������ѳڤǤ���
- ����ʬ����ȯ����¤�������㤤�Ǥ��ä��Ȼפ��ޤ���
- ���ѳ�ȯ����ΰ�Ĥϡ������إåɤȼ����ǥ������ʥץ�å�����platter�ˤΥ���åפǤ���
- ξ�Ԥϡ����ܤ��ƹ�®������������Τǿ��������ѵ������礭�ʲ���Ǥ�����
- �������������ѵ������������夷�ơ���ư��⤬�ä����Ӳ��ڥץ졼��ˤ⼫ư�֤Υǡ����������֤ˤ���ܤ����褦�ˤʤ�ޤ�����
- �����ǥ��������֤ϡ�1980ǯ�ޤǤ��緿�����γ����������֤Ȥ����礭�ʥ�å����Ȥ߹��ޤ�������ϥ⡼����ȤäƱ��Ѥ���Ƥ��ޤ�����
- ����Τ�Ρ�1970ǯ�ޤǡˤϡ������ɥ�����֡�Magnetic Drum Memory�ˤǤ�����
- �����ɥ��ϱ������Υɥ���̤˼��������ƥ���ܤ��ƥɥ���̤��������줿ʣ���μ����إåɤǥǡ������ɤ߽����ΤǤ���
- �����إåɤϡ��ϡ��ɥǥ������ɥ饤�֤Τ褦�˥�����������ˤ�äƲ��Ѥ����ΤǤϤʤ�����ȤʤäƤ��ơ��ɥ���������ž���ƥǡ������ɤ�äƤ��ޤ�����
- ��¤�ϥ���ץ�Ǥ��������ɥ�ब�礭���Ƥ��γ�ˤ�3MB���٤����̤�������ޤ���Ǥ�����
- ���θ塢������Ͽ�̤ϱ�����������ǥ������������Ѥ�ꡢ���줬�����Ťʤä������ǥ��������Ѥ��ޤ�����
- �������֤ϡ�800MB���٤ε������̤��äƤ��ޤ�����
- ���äơ��緿���������������줿����ӥͥåȥ�å���¿���ϡ����μ����ǥ��������֤Ǥ�����
- ������礭�ʼ����ǥ��������֤������ʿ�˺ܤ뤰�餤�Υ���ѥ��Ȥʤ�Τˤʤä��ΤǤ���
- ����ѥ��Ȥ��߷��ۤΥХå������ɤˤϡ��ե��åԡ��ǥ������γ�ȯ���Ѥ����ä����Ȥ��ݤ�ޤ���
- �����ǽ�ξ����ϡ��ɥǥ������ɥ饤��
- ���ߤޤ�³���Ƥ��뾮��HDD�θ����ϡ�1980ǯ�˳�ȯ����ޤ�����
- ����HDD�ϡ��ե��åԡ��ǥ�������ȯ����IBM�Ҥθ���¤����Υޥ͡�����Ǥ��ä�Alan Shugart����ȯ���ޤ�����
- ��ϡ��ե��åԡ��ǥ��������뤿��� 1973ǯ��Shugart Associates�ҡ�1977ǯ Xerox�Ҥ�����ˤ����ߤ������٤ϡ�HDD���뤿���Ʊ�Ҥ���Ҥ��ơ�1979ǯ����֤�Finis Conner��1943.07���ˤ�Shugart Technology�Ҥ���Ω���ޤ�����
- �ǽ�β�Ҥ⡢2���ܤβ�Ҥ⼫ʬ��̾�����ޤ�����
- Shugart Technology�Ҥϡ�����Shugart Associates�Ҥ���"Shugart"�Ȥ���̾����ʶ��路������ȤäƤϤʤ�ʤ��ȸ������졼���Ĥ���줿�Τǡ�Ʊǯ�����̾��Seagate Technology �Ȳ���Ƥ��ޤ���
- �ǽ��HDD�ϡ�ST-506�ȸƤФ줿����HDD�Ǥ�����
- ST-506�ϡ�5MB�Υǡ������̤���äƤ��ƥե��åԡ��ǥ��������֤�Ʊ�����ե����������椹�뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ�����
- ����ϡ��ѡ����ʥ륳��ԥ塼���˼�������Τ����˳ڤ��߷��ۤǤ�����
- �ե��åԡ����֤��֤������ơ����Υ��ڡ�����HDD���Ȥ߹���Ф��Τޤޥѥ�����ǻȤ����ΤǤ���
- ST-506�Υϡ��ɥǥ�������platter�ˤϡ�5.25�������133.35mm�ˤ��礭���ǡ��ե��åԡ��ǥ�����Ʊ���礭���Ǥ�����
- �ϡ��ɥǥ������ɥ饤�����֤⡢�ե��åԡ��ǥ������ɥ饤�����֤Ȥۤ�Ʊ���礭���˻����ƺ��졢����θߴ������ɤ����ޤ�����
- �����Τ��Ȥ��顢Seagate Technology�Ҥϡ��ե��åԡ��ǥ������ɥ饤�֤ʤ�ռ����ơ����Ѥ�FDD��Ƨ�������ȹͤ����ޤ���
- ��äȤ⡢�ե��åԡ��ǥ�������ϡ��ɥǥ�������Ʊ��Shugart����ۤ��Ƴ�ȯ������ΤʤΤǡ�Ʊ�����ץȤˤʤ�Τ������Ǥ���
- ST-506�Υǡ���ž��®�٤ϡ�����625KB/�äǤ�����
- ����®�٤ϡ��ե��åԡ��ǥ������ɥ饤�֤�40�ܤ�®�٤���äƤ��ޤ�����
- ���Υǡ���ž��®�٤ϡ���������ʬ��®�٤���äƤ�������ˡ��֤��֤˵������Τμ�ή�Ȥʤ�ޤ�����
- �ϡ��ɥǥ������ɥ饤�֤ϡ��������̤��礭������ʬ���������ή�Ǥ��ä������ơ�����������٤ơ������ॢ�������Ǥ��������礭�ʶ��ߤǤ�����
- �ǡ����ե�������ɵ�����¸�����ꡢ�ɤ߽Ф����Ȥ��ڤˤǤ���ΤǤ���
- ���Υϡ��ɥǥ������ɥ饤�֤���®�ǥǡ����ɤ߽Ǥ��뤳�Ȥ��ǽ�ˤ����Τϡ���®�ǡ���ž�������ʥ��ե������ˤγ�ȯ�Ǥ���
- ���Ϥ�����Ū�Τ���ˡ�1981ǯ��Shugart Associates System Interface��SASI�����SCSI = Small Computer System Interface�������������Ȥ������ե�������ȯ���ޤ���
- ���������ϡ������Х��ȥ١����Υ������ͥåȤ�USB2.0���о줹��2000ǯ�ޤǤι�®�ǡ����̿����ե���������̾��Ȥʤä���ΤǤ���
- �ϡ��ɥǥ������ɥ饤�֤ϡ����顢�ǥ��������¤�5.25�������������133.35mm�ˤΤ�Τ���Ϥޤꡢ8�������203.2mm�ˤΤ�ΤⳫȯ����ޤ���������ȯ��ή��Ͼ��������¤˸�������3.5�������88.9mm�ˤ���ή�ȤʤäƤ����ޤ���
- ����ˡ������˾������˰ܹԤ��ơ�2.5�������88.9mm�ˡ�1.8�������45.7mm�ˡ�1.3�������33mm�ˡ�1�������25.4mm�ˤޤǾ������ʤäƤ����ޤ�����
- �����ˤʤ�ȡ���¸���̤⾮�����ʤ�ޤ���
- ���äơ������̡�����HDD�Ǥϡ���ǯ��ȯŸ��������ȾƳ�Υ���ʥե�å��������ȶ��礹�륱�����������Ƥ��Ƥ��ޤ���
- �����ϡ��ɥǥ������ɥ饤�֤Υ��ꥢ���ʤ���Фʤ�ʤ�������
- �ϡ��ɥǥ������ɥ饤�����֤�������®���ˤʤ�ˤĤ�ƥ��ꥢ���ʤ���Фʤ�ʤ����ΰ�Ĥˡ���ư���ʤ������������ι⤤�ࡼ�ֵ����κ��Ѥ�����ޤ���
- �ơ��ץ쥳�������ե�å����������äƤ��Ƥ���Τ⡢�����������ʤ��Ƹξ㤬���ʤ���������ѥ��ȡ��²��ˤǤ��뤫��Ǥ�����
- �ե�å������ϡ����ߡ�2009ǯ�˵�®�˥���������礷�Ƥ��ޤ���
- ��������100GB�ʾ�Υ������̤��ᤵ�����Ū�䡢���ʡ��ѵ����ʤɤδ�������ϡʥե�å������Ͻ��߲����������ˡ�̤��HDD�μ��פ��礭���ȸ����ޤ���
- �ϡ��ɥǥ���������ȯ���줿����ϡ��ξ㤬¿������ޤ�����
- �ϡ��ɥǥ������Υ���å���ϡ����̻��Τ�����ι��ΤΤ褦�ʴ��Фǰ��äƤ��ޤ�����
- �����줤�Ĥ�����ʬ�Υѥ�����ˤ⤽�������Զ�礬������ΤǤϤʤ����ȶ��ݤ������ʤ��顢���ڤʥǡ����ΥХå����åפ�¾�Υ�ǥ����ˤȤäƤ���줿����¿���Ȼפ��ޤ���
- ���������������ϡ��ɥǥ������ɥ饤�֤ǤϤ����ΤΡ���¤�塢�ѵ����˴ؤ��Ƥ��ޤ������¿���Τ��¾�Ǥ���
- �֥ϡ��ɥǥ������ϲ�����Τ����顢����ǧ�����б������������äƤ����ס��Ȥ����Τ�����Ū�ʸ����Τ褦�Ǥ���
- �伫�ȡ��ϡ��ɥǥ������ɥ饤�֤�Ȥä��ѥ����������³����25ǯ��ʤ�ޤ���2020ǯ�����ˡ�
- �ե��åԡ������ǥѥ������Ω���夲�Ƥ�������˳Ӥ٤�ȡ�Ω���夲��ǡ����Υ�����������ʬ�ȳڤˤʤ�ޤ�����
- ���ޤǡ�20�ĤۤɤΥϡ��ɥǥ������ɥ饤�֤ˤ����äˤʤä��褿�Ǥ��礦����
- �����ʤ��Ȥˡ������Υϡ��ɥǥ������Ϥ��٤ƽ�Ĵ�˵�ǽ���Ƥ���ޤ�����
- �����楳��ԥ塼����ư����³���Ƥ���֡��ϡ��ɥǥ������⤻�ä��Ȳ�äƤ��Ƥ��줿�Ϥ��Ǥ���
- �����3ǯ�δ֡ʤ�������3ǯ�ǥ���ԥ塼�����Ť��ʤ�ΤǸ��Ƥ����ˡ����äȲ��³���ƥ���������³���Ƥ���ޤ�����
- ���������ѵ��Ϥ���ǽ�ȸ���ͤФʤ�ޤ���
- �֤����Ե��˾�äƻ����⤤���Ρ��ȥѥ�����Ǥ⡢�ϡ��ɥǥ����������줿�и��Ϥ���ޤ���
- �Ρ��ȥѥ�����ξ�硢HDD����ǥ����ץ쥤������뤳�Ȥ�¿���ä��ȵ������Ƥ��ޤ���
- �ޤ������åץ뤬ȯ�䤷���ϡ��ɥǥ�������¢��iPod��2001ǯ11��ȯ�䡢5GB HDD�ˤ������ϡ��ϡ��ɥǥ������η�ϴ���ȿ������䤬��ˤ���ȸ����ޤ��礦��
- ��������1����ʾ��iPod�����ޤ�����
- �������Ⱦʬ�ʾ夬�ϡ��ɥǥ�������¢���ʤ��Ȼפ��ޤ���
- iPod����ڤˤ�äơ�HDD���ѵ������¾ڤ��줿�ΤǤ���
- �礷�����Ȥ��ȸ��虜������ޤ���
- ��äȤ⡢iPod��3ǯ���٤ǥ�ǥ뤬���ä���Хåƥ�μ�̿���褿��ǡ�����ʾ�ȤäƤ����ǽ�����㤤�Τǡ��ϡ��ɥǥ������θξ㤬�礭������뤳�Ȥ����ʤ��Τ����Τ�ޤ���
- �����顢iPod�ϥϡ��ɥǥ������ˤȤäƤ��Ϥ�����Τ褦�ʴĶ����⤷��ޤ���
- �伫�ȡ�iPod��ȾƳ�Υ���Υ�ǥ뤷�����äƤ��ޤ�����²�Τ�Τ��οͤ��ä�ʹ���¤ꡢ�ϡ��ɥǥ����������줿�Ȥ����ä�ʹ���ޤ���Ǥ�����
- iPod�ξ�硢�Хåƥ꤬��äƽ��Ť˻��֤�������褦�ˤʤꡢ��ǥ��Ť��ʤä��Τ��㤤�����륱�������ۤȤ�ɤǤ�����
- �ѥ�����Υϡ��ɥǥ������˴ؤ��Ƥϡ�ͧ�ͤ��Ҥ���֤��θ���ä���ȡ��ϡ��ɥǥ������Υ���å���������������ʹ���ޤ�����
- ���äơ��ϡ��ɥǥ������Υ���å���ϡ������˸��̻��Τ���������褦�ʤ�Τǡ����ļ�ʬ�ν�˹ߤ꤫���äƤ���Τ��狼�餤�Ȼפ��褦�ˤʤ�ޤ�����
- ���������ʰո������礷���ꡢ��ʬ�ηи���������ȡ��ϡ��ɥǥ������μ�̿��5ǯ�����٤Ǥ��ꡢ����˿������ϡ��ɥǥ������˥ǡ�����ܤ��ؤ��뤳�Ȥ�˾�ޤ����ȸ����ޤ��礦��
- �ޤ����ϡ��ɥǥ�����������Ƥ�Хå����åפ��Ȥ��RAID�ʥ쥤�ɡ�Redundant Arrays of Inexpensive Disks����Ŀͥ桼���ǤǤ�������Ӥˤʤä��Τǡ�����������ǽ����ϥѥ��������������Τ������ȸ����ޤ���
- �����إåɤȥץ�å����δֳ�
- �ϡ��ɥǥ������ɥ饤�֤Υץ�å���ɽ�̤ˤϡ������ξ�˥饤�ʡ��ȸƤФ����ޤ����ۤ���Ƥ��ޤ���
- �饤�ʡ��ϡ������إåɤ��ץ�å������ư����Ȥ�����Ω�Ĥ�ΤǤ���
- �����إåɤϡ��ǥ���������ž���Ƥ��ʤ��Ȥ��ϥץ�å������ܿ����Ƥ��ޤ���
- �إåɥ�����ϥХͤˤ�ä�ͽ�����������ץ�å��˲����Ĥ����Ƥ��ޤ���
- �ǥ���������ž���Ƥ��Ф餯�δ֡��إåɤϥץ�å����äƤ��뤳�Ȥˤʤ�ޤ���
- ��ž���夬��˽��äơ��ץ�å��Ȱ��˲�ž���뵤ή�ˤ�äƥإåɤ����Ȥ���褦�ˤʤ�ޤ���
- ���δַ�ʥإåɥ���åס��ե����ƥ��ϥ��ȡ��ե饤�ϥ��ȡˤϡ��鷺��10nm��30nm�ȸ����Ƥ��ޤ���
- ����ϸ�����Ĺ����������û���ַ�Ǥ���
- ���δ֤˥ۥ��꤬���ä���ץ�å��˥ۥ��꤬���夷����ҤȤ��ޤ��ʤ���Υ�Ǥ���
- �ϡ��ɥǥ������ɥ饤�֤�Ĺǯ�ȤäƤ���ȡ��ץ�å���ɽ�̤Υ饤�ʡ������������إåɤ��ץ�å������ܿ������ͤ���Ȥ������֤�ȯŸ���ޤ���
- ���줬������ȡ��ǥ������ϥ���å��夷�Ƽ�̿���Ԥ��뤳�Ȥˤʤ�ޤ���
- �ͤ��������Ƕ����������ȤǤ������ϡ��ɥǥ������ǤϤ����쵯���뤳�ȤǤ���
- �ϡ��ɥǥ������Τ⤦��Ĥ�����Ȥ��ơ��إåɤȥץ�å���ĥ���դ��Ƥ��ޤ���ĥ���դ��פȤ������꤬����ޤ���
- �ץ�å����������٤褯�ᤫ�줿���̤ˤʤäƤ��ơ��إåɤ�Ʊ�ͤ˶��̲ù�����Ƥ��ޤ���
- ξ�Ԥ��Żߤ������֤��ܿ�����ȡ�ʬ�Ҵֺ��ѤǶ������帽�ݤ������ޤ���
- �ϡ��ɥǥ������ν���κ���1980ǯ��ˤϡ����̿�������ȥإåɤ��ץ�å��������뵡�����Ĥ����Ƥ��ޤ�������������������ˤ����¤�����㸺���顢���ε�������������Ƥ��ޤ��ޤ�����
- ��������ȡ��إåɤϥץ�å����֤��줿�ޤ��Ÿ����ڤ�뤳�Ȥˤʤꡢ�֤Ϥ�Ĥ��פ�������褦�ˤʤ�ޤ�����
- ��������������褹�뤿��ˡ��ѥ�����Ρ�OS�פ���ϡ��ɥǥ�����������̿������ä��ꡢ�ϡ��ɥǥ�����¦�ǥإåɤ�ưŪ�������ΰ���᤹�������Ƥ����褹��褦�ˤʤ�ޤ�����
- ����������
- �ϡ��ɥǥ�������Ϣ³����Ĺ���ֲ��³���Ƥ��ƿ��ۤˤʤ�Τϡ��ץ�å���٤��Ƥ��뼴�������ѵ��������������ε�ή���٤ξ徺�Ǥ���
- �ץ�å���٤��뼴�����ϡ��ܡ���٥������ή��ư��������Fluid Dynamics Bearing��FDB�ˤ�2�Ĥ����������ꡢ�Ƕ�Τ�Τ�ή��ư����������ή�Ǥ���
- ή��ư�������ϡ������������ݻ�������ˡ�ǡ���®��ž�Τμ����ˤ褯�Ȥ��Ƥ��ޤ���
- ������ϡ����β�ž�ȶ��˼���������ήư��Ϥᡢ�������ήư���ϡ�ư���ˤˤ�äƼ����������⤫���褦�ʹ�¤�ˤʤäƤ��ޤ���
- ��ž���ʤ��Ȥ��ϡ�ư����Ư���ʤ��ΤǼ��ϼ������˥���ܿ����Ƥ��뤳�Ȥˤʤ�ޤ���
- �ޤ�������β��٤�夬�äƤ����Żߤ��Ƥ���Τ�Ǵ�����⤯���ϡ��ɥǥ�������ư���ˤϥ⡼���˶����ȥ륯��ɬ�פȤʤ�ޤ���
- �⤷���⡼��������������������Ǵ���������ǵ�ư���˶����ȥ륯�������ʤ����ϡ��ϡ��ɥǥ����������ʤ��ʤ�Ȥ����Զ�礬�����ޤ��� �ϡ��ɥǥ�������Ĺ���ֺ�ư�����Ƥ���ȡ������ʤ���Ǯ��ȯ�������ޤ��� Ǯ��ȯ�����ϡ��ǥ���������뵤ή��ȯǮ���⡼���β�žȯǮ������������ȯǮ���������٤ˤ���Ǯ�ʤɤ��ͤ����ޤ���
- �ϡ��ɥǥ�������ϥۥ�����ä˷����ޤ����顢��������ۥ��꤬����ʤ��褦��̩�Ĺ�¤�ˤʤäƤ��ޤ���
- ����������̩�Ĥˤ���ȵ�ή�β��٤ˤ�ä��������Ϥ��Ѥ��إåɤȥץ�å��֤Υ���åפ��Ѳ����ФƤ��ޤ���
- ���������Զ���ʤ�������ˡ��ϡ��ɥǥ������ˤϰ�ս���������ʶ�������������⤦���ơ��ǥ�������ΰ��Ϥ����ˤ�����θ���ʤ���Ƥ��ޤ���
- �� �� ��
- ����������Ͽ���� ��-����ʿ������Ͽ����
- �����⼧����Ͽ������Longitudinal Magnetic Recording��LMR�ˤ� ������ľ������Ͽ������Perpendicular Magnetic Recording��PMR��������2010.07.30���ˡ�2010.08.20�ɵ���
- ��ľ������Ͽ�����ϡ������������פμ����Τι�̩�ٵ�Ͽ�����Ǥ���
- �ǥ����뵭Ͽ�����Ȥ��ơ�HDD�ʥϡ��ɥǥ������ɥ饤�֡ˤ˺��Ѥ���Ƥ��ޤ���
���������ϡ�1976ǯ�˴��Ӱ���1926.08��������������ŵ��̿������ˤ���Ϥᡢ 2005ǯ����Ǥ�����HDD��1.8��HDD��80GB����������54mm x 78.5mm x t8mm�����̡�62g�ˤǤμ��Ѳ����������ޤ�����
- 2011ǯ�ˤ��äƤϾ���HDD�ΤۤȤ�ɤ�������������Ѥ��ơ���̩�ٵ�Ͽ�Υϡ��ɥǥ������ɥ饤�����ʤ����䤷�Ƥ��ޤ���
- ����μ�����Ͽ�ϡ���ʿ��Ͽ������Longitudinal Magnetic Recording, LMR�ˤȸƤФ���Τǡ����ˡ�S�ˤ�N�ˡˤ������̤˳Ȥ��äƵ�Ͽ����Ƥ��ޤ����ʱ��ޡˡ�
- ��ľ������Ͽ������Perpendicular Magnetic Recording, PMR�ˤǤϡ�S�ˤ�N�ˤ��ľ���֤ǵ�Ͽ���Ƥ��ޤ���
- �ʤ����ġ���Ͽ���ݥåȤ⾮�������Ƥ��ޤ���
- ���äơ���ľ������Ͽ��������Ͽ̩�٤�3�����ٸ��夵���뤳�Ȥ��Ǥ���Ͽ���̤����䤹���Ȥ��Ǥ��ޤ���
- �����Τ˼��ˤ�Ĥ��Ǥ����ࡢ�Ȥ����Τ����ε�Ͽ��ˡ�Υ����ݥ���ȤǤ���
- ��ʿ������˼�����Ͽ�Ǥϡ���̩�ٵ�Ͽ��Ԥ����Ȥ���ȡ�Ǯ��餮�ס�superparamagnetic effect�����꤬��夷��������Ͽ���ü����Ƥ��ޤ��Զ�礬����ޤ�����
������Ͽ���֤ι�̩�ٲ���ã�����Ƥ�����ǡ���ľ������Ͽ��ʡ���Ȥʤ�ޤ�����
- ��������ľ��Ͽ�ϥǥ����뵭Ͽ�˸����Ƥ��ꡢ�����ǥ����Τ褦�ʥ��ʥ�����Ͽ�ǤϽ���ο�ʿ������Ͽ�������������ɤ��Ȥ���Ƥ��ޤ���
- ��ľ������Ͽ�ϡ���̩�٥ǥ����뵭Ͽ�˸����ƤϤ����ΤΡ����Ѳ��ˤ�Ĺ��ǯ�������ޤ�����
- ���Ѳ����礭�ʾ㳲�ϰʲ��Τ�ΤǤ�����
- 1.����̩�٤ǿ�ľ�˼�����Ͽ��Ԥ����Ѥγ�Ω
- �� ������-���������פμ����Τγ�ȯ�ȡ���ľ�����إåɤγ�ȯ��
- 2.���Υ����Ȥ��襤
- ��������-����ľ������Ͽ�ϼ����Τλ����Υ�����¿���ä���
- �� ���������������פμ����Τγ�ȯ��
- 3.�����ѥ����Υ���
- ��������-����ľ������Ͽ����ͭ�κ�������ȯ������Υ�����
- �� ���������������פμ����Τγ�ȯ��
- 4.�����襤�졼����WATER; Wide Area Track ERasure��
- ��������-����Ͽ���ˡ���Ͽ�إåɼ缧�ˤ���������ʿ���
- �����������������ߥ������Υ�줿�ȥ�å����椬����ޤ���
- �������������ü����Ƥ��ޤ����ꡣ
- �������������������פμ����Τ���ȯ��
- ����PMR�Ѽ����إå�
- ��ľ������Ͽ��Ԥ��ˤϡ������餷�������إåɤ�ȯ����ɬ�פ�����ޤ����ʱ����ȡˡ�
- ��ľ������Ͽ�Ѥμ����إåɤϽ���Τ�Τ���٤ƹ�¤���礭�ʰ㤤�������ޤ���
- ����ο�ʿ������Ͽ�إåɤϡ���إåɤȸƤФ���Τǥ���åפ�ȯ�����뼧���κ��ѤǼ�����Ͽ�̤������Ƥ��ޤ�����
- ��ľ������Ͽ�Ǥϡ���Ͽ���ľ�˹Ԥ��ط���إåɤ�ñ�˹�¤�Ȥ��Ƽ������ľ��ȯ�������Ƥ��ޤ���
- ���μ����إåɤϤȤƤ⾮������Τ����ٲ����Ѥ���Ω����ƽ��Ƽ��Ѳ�����ޤ�����
- ����PMR�Ѽ�����
��ľ��Ͽ�ˤϡ������������פμ����Τγ�ȯ���Բķ�Ǥ�����
- �����Τ�1960ǯ�夫���°����ˡ����ȯ����Ƽ�ή�ȤʤäƤ����ޤ���
- ��뼧���Τϡ��ٻ����Ρʥ����ơ��ȥե���ࡢ����ߴ��ġ����饹���ġˤ˼����ζ�°�����ѥå��ˤ�äƾ��夵�����ΤǤ���
- ������ˡ�ϡ������������������������뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
- ��ľ������Ͽ�Ǥϼ��ˤ�Ĥ�������ط��塢��«���ľ�˷������ʤ���Фʤ�ޤ���
- ���Τ���ˡ�������Ͽ���ΤϤ���ޤǤΤ�ΤȤϹ�¤���ۤʤä���Τ������ޤ�����
- ���ޤ���ľ������Ͽ���Τι�¤�ޤǤ���
- ���οޤ����狼��褦�ˡ����ε�Ͽ���Τ���Ĥμ�������ǹ�������Ƥ��ޤ���
- ��Ĥ���ľ������ȸƤФ���Τǡ��⤦��Ĥ������Ǥ��ء����������졢SUL = Soft Under Layer�ˤȸƤФ���ΤǤ���
- ������0.8um�ο�ľ������ϡ������ȸƤФ������η뾽��¤�ΤǷ������졢�����ʼ��Ф����äƤ��ޤ���
- �����ϡ�8nm��10nm�¤��礭�����ä���Τ�Co�����ʬ�Ȥ��Ƥ��ޤ���
- ������ϡ����Х�ȡ�Co�ˤȥ������Cr�ˤ�Co:Cr=4:1�γ����۹礷RF���ѥå���Radio Frequency Sputter�ˤˤ�äƾ����ܤ����Ȥˤ�äơ����Τ褦�ʷ뾽��¤������夬�뤽���Ǥ���
- ���ι�¤�ϡ���ľ������Ԥ��Τ˶ˤ���Թ���ɤ���¤�Ǥ�����
- �����ϡ������ζ���Co�η뾽�ǽ���Ƥ��ơ����μ����������Cr�����Ϥ¤�ȤʤäƤ��뤿�ᡢ�����Ͼ����ʼ��ФȤʤ�ޤ���
- �����Ǥ��ء�����������ˤϡ���ľ��Ͽ����ݤ˼�������ꤵ����Ư��������ޤ���
- ���줬�ʤ��ȼ����إåɤ�Ͽ���Τ˶��ޤʤ���Фʤ�ޤ���
- ���Τ褦�ʼ����إåɤϼ��Ѿ��Բ�ǽ�˶ᤤ�Τǡ��������ľ���Ǥ�����Ǥʤ����İ��ꤵ���뤿��ι��ס����ʤ�������Ǥ��ؤ�ɬ�פ��ä��ΤǤ�����
- �� ��
- ����RAID�ʥ쥤�ɡ�Redundant Arrays of Inexpensive ��or Independent�� Disks��
�ϡ��ɥǥ������ϲ�����Ρ��Ȥ���������Ω�äơ��ǥ����������Τˤ�äƲ���Ƥ�Хå����åץϡ��ɥǥ������Ǿ㳲�����줹�륷���ƥब���ۤ���ޤ�����
- ���줬RAID�ȸƤФ�륷���ƥ�Ǥ���
- ���Υ����ǥ��ϡ�1988ǯ������ե���˥���إС����졼����David Patterson�ˤ�ä����줿��ΤǤ���
- ���Υ����ƥ�ϡ��ϡ��ɥǥ�������2��ʾ�Ȥäƥǡ�����ʬ����¸������1��Υϡ��ɥǥ�����������å��夷�Ƥ��̤Υǥ���������¸���줿�ǡ�����Хå����åפȤ��ƻȤ��Ȥ�����ΤǤ���
- RAID�ϡ��ǡ�����ʬ����������ܻ��ۤȤ��Ƥ��뤿�ᡢ�ǡ����ΰ�����¸�δ����ȡ��ǡ����ι�®������Ԥ����Ȥ���Ū�˻Ȥ��Ƥ��ޤ���
- RAID�ϡ��ϡ��ɥǥ������ι����ʥϡ��ɥ������ˤȥǥ�������������륽�եȥ�������������Ω�äƤ��ơ��桼�����᤹���٥��ä�7�ʳ���ʬ����Ƥ��ޤ���
- �Ǥ��ñ��RAID�����ƥब��RAID0��RAID1�ȸƤФ���ΤǤ��� �� ��
- ������
- �ϡ��ɥǥ�������
- �á���ħ
- RAID 0
- 2���
- RAID 1
- 2���
- RAID 5
- 3���
- RAID 0 +1
- 4���
- RAID 0�Ǥϡ���®�ɤ߽Υ����ƥ�ȤʤäƤ��ơ�ʬ�����ƥǡ������ɤ߽ޤ���
- ���Υ�٥�Τ�Τϡ��ǡ�����2�Ť���¸���ʤ��Τǡ��㳲����Ȥ��Ƥε�ǽ�Ϥ���ޤ���
- �㳲�������Ū�Ȥ����Хå����åץ����ƥ�ϡ�RAID 1���Ǥ�ñ��ǡ�2�Ĥ�HDD��Ʊ���ǡ�������¸���뵡ǽ�ˤʤäƤ��ޤ���
- RAID���ۤ���ˤϡ��ϡ��ɥǥ������ɥ饤�֤�������륽�եȥ�������ʣ���Υϡ��ɥǥ�������������ޤ���
- �����ʤǤϡ����ޤ��ޤ�RAID�����ƥब���뤵��Ƥ��ơ��������եȤ�HDD���Ȥ߹�碌���ѥå����������䤷�Ƥ��ޤ���
- HDD�ϥ⥸�塼��ǸǤ���褦�ˤʤäƤ��ơ��Զ�礬��������硢�������եȥ��������ٹ��Ф��ơ���������Τȸ�¥���褦�ˤʤäƤ��ޤ���
- �����������Ȥ���⡢�ϡ��ɥǥ������ɥ饤�֤ϡ����ߡ�2009ǯ�ˤ⡢��®�������̡��Хå����åץ���Ȥ��Ƹ���ǻȤ��Ƥ��뤳�Ȥ�����Ǥ��ޤ���
- �� �� ��
- �ڼ����ǥ������Υե����륷���ƥ��FAT��NTFS��HFS�ˡ�������2010.05.20���ˡ���2010.06.23�ɵ���
- ����ԥ塼�����ä˥ѡ����ʥ륳��ԥ塼������ڤ�ȼ�äƥե��åԡ��ǥ�������ϡ��ɥǥ������ʤɤμ����ǥ��������֤���������ȯ����Ƥ��ޤ�����
- �����������֤ϡ�����ԥ塼����OS�ʥ��ڥ졼�ƥ������ƥ�ˤǴ���������Τǡ���¸�����ε��ʡʥե����륷���ƥ�ˤ�OS��˺���Ƥ��ޤ�����
- �ǥ�������ʪ��Ū�ʳ�꿶�����������sector���ȸƤФ����ڤ�ε���ñ�̤ǹ�������ޤ��������Υ�������ե�����ȤɤΤ褦�˴ط��Ť��ƴ�ñ���ɤ߽Ǥ���褦�ˤ��뤫��OS��Operating System�ˤ����κǤ��礭�ʰ�ĤǤ�����
- �ѡ����ʥ륳��ԥ塼���˻Ȥ��Ƥ���OS���礭��ή��ϡ��ޥ��������եȼҤ�MS-DOS��Windows�����åץ�Ҥ�MacOS�������UNIX������ޤ���
- ����ή��˱�ä�¿���Υե����륷���ƥब���ʲ�����ƻȤ��Ƥ��ޤ�����
- �桹���Ȥ�����ԥ塼����Windows��Mac�Ǥ���Τǡ����ι�ǤϤ��������ѡ����ʥ륳��ԥ塼�����ɤ��Ȥ��Ƥ���3����ε��ʡ�FAT��NTFS��HFS�ˤˤĤ��ƽҤ٤����Ȼפ��ޤ���
- ����FAT��File Allocation Table��
- FAT�ʤդ��äȡˤϡ��ޥ��������եȼҤ�OS����Ϥ1970ǯ��ˤǤ�����Τǡ�MS-DOS��Windows�������ˤ�äƺ����ޤǻȤ��Ƥ���Ǥ�ͭ̾��ɸ��ե����ޥåȤǤ���
- ���Υե����ޥåȤ˽��äơ�MS-DOS��Winodws��ư������ԥ塼���Υϡ��ɥǥ�������ե��åԡ��ǥ������Υե����빽¤�����졢�ǡ����ν��ߤ��Ԥ��Ƥ��ޤ�����
- �ǥ������˥ǡ������Ǽ�����ˡ�ϡ�IBM���ե��åԡ��ǥ������åȤ�ȯ���������ι�¤�ȴ���Ū�ˤ��Ѥ��ޤ���
- FAT�ϡ���������ʪ��Ū�ʥե����ޥåȤ��Ȥˤ��ơ��ǡ����ե���������ΨŪ�˹�®��ijμ¤��ɤ߽Ǥ�������ץ���������Ģ�ˤǤ�����
- ����ԥ塼���ι���ǽ���ȼ�갷���ǡ������̤������̲���ȼ�äơ��ʲ���4����γ�ĥ���ʤ���Ƥ��ޤ�����
- ����FAT ��= FAT12�ˡ�-��1977ǯ
- ����FAT16���� - 1987ǯ
- ����FAT32����-��1996ǯ
- ����exFAT��-��2006ǯ
- ����FAT12
- FAT�ϡ��ѡ����ʥ륳��ԥ塼���˻Ȥ�줿���ֺǽ�Υե����륷���ƥ�ǡ��ӥ롦�����Ĥȥޡ������ޥ��ɥʥ�ɤˤ�ä�1977ǯ�˳�ȯ����ޤ�������IBM-PC��ȯ�䤵�줿1981ǯ��4ǯ���Τ��ȤǤ�����
- �ޥ��������եȼҤ���DISK-BASIC�δ������ͤ���Ǽ������ʤǤ���
- ���ε��ʤǤϡ�12�ӥåȥ�����ȤΥ��饹����cluster�ˤǥǡ�����������Ƥ����Τǡ��ǥ�������4,084�ĤΥ��饹���ǹ�������Ƥ��ޤ�����
- ���衢12�ӥåȥ�����ȤǤ���4,096�Ĥδ������Ǥ��ޤ���
- ���Τ�����12�Ĥϴ����Ѥ˳�����Ƥ��뤿�ᡢͭ���ʥǡ�����������4,084�ĤȤʤ�ޤ�����
- ���饹����OS����������ǥ������ǡ����Ρ֤ޤȤޤ�פǤ��ꡢ����ǥ������ϥ������ȸƤФ�뵭��ñ�̡ʾ������ˤ���äƤ��ޤ���
- ���饹���ϡ��������ʾ������ˤΤ�����礭�ʤҤȤޤȤޤ�Ȥ������֤Ť����ɤ��Ǥ��礦��
- �������������Ȥ��ޤ���礭�ʥ�����ȿ��ˤʤäƤ��ޤ����ᡢ��������«�ͤ륯�饹���γ�ǰ��Ƴ�����Ƶ������̤��羮�ˤ�ꥯ�饹�����礭�����Ѥ���OS�δ����Ǥ��륫����ȿ��ˤ����ΤǤ���
- ���饹�����ϡ���̾��������������˥åȥ�������allocation unit size�ˤȤ�ƤФ졢�ޥå���ȥå����HFS��HFS+�ˤǤϤ��θ�������ȤäƤ��ޤ���
- ���饹���ϡ�OS���ե������������뤿���1�֥��å��Ǥ��뤿�ᡢʸ�������ե�������礭���ˤ�ä�ʣ���Υ��饹����������Ƥ��ޤ�����
- 1�ĤΥ��饹���ˤϡ�Windows9x�ξ�硢512�Х��ȡ�32kB�� = 32,768 B��64������ʬ�ˤ��Ȥ߹���ޤ����ʥ����������ʤΤǡ�512 x 2n��n = 0��6 ���������Ӥ��ͤȤʤ�ޤ�����
- ���饹����1�������Ǥ��뤳�Ȥ⤢�ꡢ64�������Ǥ��뤳�Ȥ⤢��ޤ�����
- �ǥ������ˤϡ�ʪ��Ū��������ꤵ��Ƥ��������������ꡢ�����512�Х��ȡ� = 29 �Х��� = 29 x 23 = 212 �ӥåȡˤȷ����Ƥ��ޤ���
- 1�������ϡ��ե��åԡ��ǥ������åȤ���ȯ���줿�Ȥ��ˡ��ѥ��������1��ʬ�ξ����̡�128�Х��ȡˤȷ����Ƥ��ޤ�������MS-DOS�λ����512�Х��ȤȤʤꤽ�줬ɸ�൬�ʤȤ���Ĺ��³���ޤ�����
- �ե�å�������2011ǯ1���ȯ�䤵����ΤˤĤ��Ƥϡ�����������������4096�Х��Ȥ��礭�����ơ������䲻�ڥե�����Υ��������䤹������褦�ˤʤäƤ��ޤ���
- ����ϥ��꤬�����̲����ƥե����륵�������礭���ʤäƤ��Ƥ��뤳�Ȥؤ��б��Ǥ���
- ���饹�����礭���ϡ��ǥ����������̤ˤ�äƺ�Ŭ�ʥ����������������ޤ���
- ���饹�����������������ȥǥ��������̤��礭�����뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
- ���饹�����������礭�����ɤ߽�®���ʤ�ȿ�̡����̤ξ������ǥ������Ǥ������饹������¿����뤳�Ȥ��Ǥ�������������Υե��������¸�Ǥ��ʤ��ʤ�ޤ���
- ���η�礤�ǥ��饹���������Ϸ����ޤ���
- 1990ǯ��˻Ȥ��Ƥ����ե��åԡ��ǥ������ξ��ϡ�1���饹����1�������� = 512�Х��ȡˤȤʤäƤ��ޤ�����
- OS�ˤ��ǥ��������ϡ�CPU��16�ӥåȤξ��ˤ�����������216 = 65,536�ޤǤ��������Ǥ�����1��������512�Х��ȤǤ����顢�������̤�33.5MB�ޤǤȤʤ�ޤ���
- ���줬16�ӥå�CPU�Ǵ����Ǥ���ǡ������̤θ³��Ǥ���
- ���Υ��������Ⱥ������̤��������ǡ�12�ӥåȥ�����Ȥˤ�륯�饹���������Ԥ��ޤ�����
- 1980ǯ������33.5MB�����̤Ͻ�ʬ�ʤ�ΤǤ�����������ȶ��ˤ��Υǡ��������Ǥϼ궹�ˤʤä�����FAT16�����ʤ���ޤ�����
- FAT12�ǰ����ե�����̾�ϡ�8ʸ���αѿ����ȳ�ĥ��3ʸ���ǹ�������ޤ�����
- ���Υե����ޥåȤϡ���˥ե��åԡ��ǥ������ǻȤ��ޤ�����
- �������������ǥ�����������Ū�ˤʤäƤ���ȡ�����Ǥϼ궹�ˤʤ�ޤ�����
- �����ե饰���ơ�������fragmentation��
- �������֤ؤΥǡ�����¸������ǽҤ٤��褦�ʥ��饹���ȸƤФ�����ǹԤ��뤿�ᡢ8��������= 4kB�ˤ�1���饹���Ȥ��ƹ�������뼧���ǥ������Ǥϡ�FAT12�������16.73MB���̤Ȥʤ�ޤ���
- ���μ����ǥ�������1kB���̤Υǡ����������硢�ե������1���饹��ñ�̤Ǥ�����¸�Ǥ��ʤ��Τǡ������ǥ������ˤ�1���饹�� = 4kB��������Ƥ��ޤ���
- 100kB�Υǡ����ˤ�25���饹�������Ƥ��ޤ���
- ���Τ褦�ˤ��ƥǡ����饹����ñ�̤dz�꿶�뤿��ˡ������ʥե������õ���礭�ʥե������Ͽ���褦�Ȥ���Ⱦõ���������ե����������ʤ��ʤ�ޤ���
- ���ξ�硢�̤��礭�ʵ����ΰ褬����Ф����˥ǡ�������¸����ޤ������ʤ����ˤ϶��������饹���Ĥ����̡�����¸���ޤ���
- �ޤ����ǥ�������ˤϤ��ޤ��ͤ����ʤ��ä������ʶ��������饹�������ߤ���褦�ˤʤ�ޤ���
- ���줬���Ҳ��ʥե饰���ơ������ˤǤ���
- ���Ҳ���������ȡ��ե�������ɤ߽Ф��Ȥ��˻��֤�������褦�ˤʤꥢ���������٤��ʤ�ޤ���
- ���Τ褦�ˤ���ʬ�������Ƥ��ޤä���Ϣ�ǡ����Υ��饹�����Ψ�褯�����֤���Τ��ǥե饰��defragmentation�ˤǤ���
����FAT16
- FAT16�ϡ�1987ǯ��DOS3.31�Ǵ����Ǥ���ե����ޥåȤȤ��ƺ���ޤ�����
- �ǡ�����������륢�ɥ쥹�������12�ӥåȤ���16�ӥåȤȤʤ�ޤ�����
- 16�ӥåȤȤʤä����Ȥˤ�ꡢ�����饹����65,517�ĤȤʤ�FAT12���16�ܤ������ޤ�����
- ���饹���ϡ�FAT12��Ʊ����512�Х��ȡ�32kB�� = 32,768B�ˤǤ�����ȤʤäƤ��ޤ�����
- �ǥ��������Τϡ�16�ӥåȵ��ʤdz�꿶���ޤ��Τǥܥ�塼��Ϻ���2GB�� = 32kB x 216�ˤȤʤ�ޤ���
- �Ĥޤꡢ2GB�ʾ�Υϡ��ɥǥ������Ϥ��Υե����ޥåȤǤ�ǧ���Ǥ��ʤ����Ȥˤʤ�ޤ���
- FAT16�ϡ�Windows95�ޤǻ��Ѥ��졢Windows98�����32�ӥå��б���FAT32�Ȥʤä����ᡢ �ʹߡ�Windows�Υǥ�����������FAT32�����ϤȤʤ�ޤ�����
- FAT16�θ���ˤϡ��ե�����͡��ब����αѿ���8ʸ�����ä���Τ���255ʸ���ޤǻ��ѤǤ��뵬�ʤˤʤ�ޤ�����
- ���ܸ�ʤɤ�2�Х��Ȥ���Ѥ���̾���ˤĤ��Ƥϡ�16ʸ���ޤǻ��ѤǤ��ޤ�����
- ���ε�ǽ���Ȥ���FAT16��VFAT��Virtual FAT�ˤȸƤ�Ǥ��ޤ�����
- ����FAT32
- FAT32�ϡ�1996ǯ��Windows95�ʹߤǴ����Ǥ���ե����ޥåȤȤ��ƺ���ޤ�����
- �ǡ�����������륢�ɥ쥹��32�ӥåȡʼºݤϡ�4�ӥå�ʬ��ͽ��˳�����Ƥ���Τ�28�ӥåȡˤȤʤ�ޤ�����
- ���Τ��ᡢ�ϡ��ɥǥ�����������Ǥ���ܥ�塼�ब2TB�ޤdz�ĥ�����褦�ˤʤ�ޤ�����
- FAT32�ϡ�Windows95��Windows98��WindowsMe�Ǥ褯�Ȥ��ޤ�������Windows2000/XP�Ǥϰʲ��˽Ҥ٤�NTFS����ή�Ȥʤ�ޤ�����
- NTFS�ϡ�WindowsNT�dz�ȯ���줿�ե����ޥåȤǤ������������䵡ǽ������������ͥ��Ƥ��뤳�Ȥ���FAT32����NTFS���Ȥ��뤳�Ȥ�¿���ʤ�ޤ�����
- USB�����פΥե�å������ˤ�FAT�����Ѥ��졢�����̤Τ�Τ�FAT16��16GB�ʤɤ������̤ˤ�FAT32�����Ѥ���Ƥ��ޤ���
- ���������κ��Ѥˤ��Macintosh�Ǥ�WindowsXP/Vista/7�Ǥ������ǻȤ���褦�ˤʤäƤ��ޤ���
- ���ʤߤˡ�WindowsXP��ɸ����Ѥ���Ƥ���NTFS�ϡ�Macintosh��Mac OSX�ˤ���Ǥ�ľ�ܥ����������Ǥ��ʤ�������ɤ߹��ߤϤǤ��뤬�����ߤϤǤ��ʤ��ˡ��ǡ����ν��ߤϥͥåȥ����ͳ�ǹԤ�������öFAT�ˤ��ǥ������ʥե�å������ˤ˽���ǽ���������ˡ������Ƥ��ޤ���
- ����exFAT��extended File Allocation Table��
exFAT�ϡ������̲�����ե�å��������������ե����ޥåȤȤ���2006ǯ�˺���ޤ�����
- ����ϡ�Windows Embedded CE�ʷ�����ü�����֡˸����˳�ȯ���줿��ΤǤ���
- ������ü�����֤�OS�����˵��ʲ����줿��ΤȤϤ�����64�ӥå��б��Ǥ��뤿�ᡢ������ǡ������̡ʥե����륵�����ˤϺ���16EB�ʥ������Х��ȡˡ�16E18�Х��� = 264�Х��ȡˤ˵ڤӤޤ���
- exFAT�Ǥϥܥ�塼�����Τ����ե����륵�����ˤ��Ƥ뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ��Τǡ�����ܥ�塼�ॵ������16EB�ʥ������Х��ȡˤȤʤ�ޤ���
- ���饹����������������2255�������ޤ�����Ǥ����������1���饹����32MB�� = 225 B�ˤޤǤȤ��뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
- �����礭�ʥ��饹������ݤ��뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
- exFAT�ϡ�WindowsVISA�ˤ�Ƴ������ޤ�����
- WindowsXP�ˤϴ���Ū�ˤ��б����Ƥ��餺��Windows XP SP2/SP3�ˤƥޥ��������եȤ��������Ƥ���exFAT�б��ι����ץ�������Ŭ�Ѥ���ɬ�פ�����ޤ���
- ���åץ�Ҥ�Macintosh����Υ���������Ǥ��ޤ���
- �ޤ������Υե����륷���ƥ�ϡ���¢�ϡ��ɥǥ������ˤ��б����Ƥ��ޤ���
- ����NTFS��NT File System��
- ���Υե����ޥåȤϡ�WindowsNT�Ѥ˺��줿�ե����ޥåȤ�1993ǯ�˵��ʲ�����ޤ�����
- Ʊ���ޥ��������եȼҤγ�ȯ�ʤǤ���Τ�FAT�Ȥθߴ����Ϥ���ޤ���Ǥ�����
- �Ĥޤꡢ���Υե����ޥåȤǴ������줿�����ǥ�������MS-DOS��Windows95��ܤΥѡ����ʥ륳��ԥ塼���ǤϻȤ��ʤ��ä��ΤǤ���
- ���Υե����ޥåȤϡ��ޥ��������եȤ������С��ʤɤδ�OS�Ǥ���WindowsNT��ȯ�����Ȥ��ˤ��ΰ�ӤȤ��Ƶ��ʲ�������Τǡ��ѡ����ʥ륳��ԥ塼����OS�Ǥ���Windows95/98�ȤϤޤä�����ʪ�Ǥ�����
- �����������Υե����ޥåȤ����餫�������̤ǤΥǥ����������������Ǥ�����������FAT���⤫�ä��Τǡ�Windows2000/XP�ǻ��Ѥ����褦�ˤʤ�ޤ�����
- �ʹߡ�NTFS��2000ǯ���Ⱦ��WindowsXP��WindowsVista��Window7��ɸ��ե����ޥåȤȤʤ�ޤ�����
- ���ޤ�2004ǯ�˹�������WindowsXP���Dell�Ρ���PC�Υϡ��ɥǥ������Υץ��ѥƥ��ǡ������ȥե����륷���ƥबNTFS�ˤʤäƤ��뤳�Ȥ��狼��ޤ���
- �ܥ�塼��
- ������
- �������������
- ��˥åȥ�����
- > 512MB
- 512B
- 512MB - 1024MB
- 1kB
- 1024MB - 2048MB
- 2kB
- 2GB��<
- 4kB
- WindowsXP�Ǥ�NTFS�ե����ޥåȤ˻��Ѥ���륯�饹���������ʥ�������������˥åȥ�������
- ��NTFS����ħ��
- �����¥ĥ��¤�κ��ѡ�
- �����������¥ĥ�ϡ�Binary Tree��ά�ǡ�2ʬ�ڤ�ά����롣
- �����������ĥ���Υǡ�����¤�Τ��ḡ����®�����������䤹����
- ������ ����B�ĥ��Macintosh�Υե����륷���ƥ�ˤ���Ѥ���Ƥ��롣
- ���������̲�
- ����������1�ե��뤬1�ܥ�塼��ݤ���������̤ˤޤdz�ĥ���줿��
- ����������1�ե�����κ������̤�2TB�� = 241 B�ˡ�
- ��������������ϡ�1�ե�����κ��礬2GB�� = 231 B�ˤǤ���FAT32���������̡�
- ��������������Ū�ˤϡ�1�ܥ�塼��Ϻ���16EB
- �����������ʥ������Х��ȡ�16E18 B = 264 B�ˤޤDz�ǽ��
- �������㡼�ʥ�ե����륷���ƥ��Journaling File System��
- �������������ε�ǽ�ϡ��ǥ������ؤΥǡ�����¸�ʤɤ��Ÿ����Ǥʤɤ��Զ�礬
- �� ���������������ݤˡ�ɬ����¤Υ�����ǥǥ��������뵡ǽ��
- �������������ε�ǽ���ʤ����ϡ��ϡ��ɥ��������ΤΥ���å���˴٤롣
- �������������ε�ǽ�ˤ�äơ�FAT��꿮�������⤯�ʤä���
- �������������ε�ǽ����Ѥ��Ƥ���Τϡ�NTFS��¾��UNIX��MacOS�� = HFS+�ˡ�
- �������������ε�ǽ�ϡ�����ԥ塼�����ե����������Ԥ�����༡������Ĥ��Ƥ���
- ����������CPU�ΰ۾���ߤʤɤǥե�������������Ǥ����Ȥ��Ƥ⡢���Υ���������
- ������������®�˥ե�����ǡ��������줵����Ȥ�����Ρ��ե�������¸���Ϥ���ʬ���֤������롣
- �������̵�ǽ
- �����������ġ��Υե������ե�������⤷���ϥܥ�塼�����Τ̤��뤳�Ȥ���ǽ��
- �����Ź沽��ǽ
- �����������ġ��Υե������ե�������Ф��ưŹ���뤳�Ȥ��Ǥ��롣
- �����������ƥ��θ���
- �����������ġ��Υե������ǥ��쥯�ȥ��ACL��Access Control List�ˤˤ�륢���������������ƻ�����꤬�Ǥ��롣��
- ����Windows9X�ϡ�Macintosh�Ȥο��������ʤ���
- ����HFS��Hierarchical File System��
- ���Υե����륷���ƥ�ϡ����åץ�ҤΥޥå���ȥå��夬���Ѥ�����Τǡ�1985ǯ�˳�ȯ����ޤ�����
- ��Mac OSɸ��ե����ޥåȡפȤ�ƤФ�Ƥ��ޤ���
- ���åץ뤬1985ǯ�����ޤǺ��Ѥ��Ƥ����ե����ޥåȤϡ�MFS��Macintosh File System�ˤȸƤФ�Ƥ�����Τǡ�Ȣ�ʥǥ������ˤ���˥ǡ����Τޤ��������褦�ʥե�åȤʹ�¤�Ǥ�����
- �����ĥ��¤�ʥե�������Ǵ������빽¤�ˤ��Ѥ������ᡢ���ز���Hierarchical�ˤȤ������դ��Ȥ��ޤ�����
- �ĥ��¤��Bʬ�ڡ�Binary Tree�ˤȸƤФ졢����ԥ塼���Υǡ��������δ���Ū�ʤ�ΤǤ��ꡢ��������¸�Τ���δ������ưפʹ�¤�Ǥ���
- Bʬ�ڤϡ�B+�ڡ�B + Tree�ˤ��*�ڡ�B* - Tree�ˤ���Ĥ���������Macintosh�Ǥϣ�*�ڹ�¤�����Ѥ���Ƥ��ޤ���
- Windows�������Ǥϡ�NTFS��Bʬ�ڤ���Ѥ��Ƥ��ޤ���
- �ޥå��Υե����륷���ƥ���礭����ħ�ϡ�2�ĤΥ���ݡ��ͥ�Ȥ���ĥե�������¤�ˤ���ޤ���
- HFS+�Ǥϡ���İʾ�Υե���������Ĺ�¤�Ȥʤ�ޤ�����
- �ե������Ȥϥ���ԥ塼���Ѹ�ǥץ������������Ȥ�����̣�ǡ������˻Ȥ��ե������Τ褦�˺��ܤ���ʬ�����Ƥ����ͤ���̾�դ����ޤ�����
- HFS�Ǥϥե����뤽�Τ�ΤǤ���ǡ����ե������Τۤ��ˡ����������ե������°���������������ե�������2�ĤΥե������ǥե����뤬��������Ƥ��ޤ�����
- ���åץ���Τ���ե�����̾�˳�ĥ�Ҥ�Ĥ��ʤ��Ƥ�ե������°�����狼�ä��ꡢ�ե������ե�����������ɽ���Ǥ����Τϡ�������ե������˽����������ä�����Ǥ���
- 1998ǯ�ˤϡ�HFS+��Mac OS��ĥ�ե����ޥåȡˤȤ����ե����ޥåȤ�����Mac OS8.1���Ȥ߹��ޤ�ޤ�����
- MacOSX�Ǥϡ�HFS+��ɸ��ե����ޥåȤˤʤä����ᵯư�ǥ������Ȥ���HFS�ϻ��ѤǤ��ʤ��ʤ�ޤ�����
- HFS+���礭����ħ�ϡ��ե�����Υ֥��å���4kB��=��������������������饹�����������ˤȤ�������ե����륵������4EB�ʥ������Х��ȡˤȤʤꡢ����ܥ�塼�ॵ������16EB�ޤǰ������Ȥ��Ǥ���褦�ˤʤä����ȤǤ���
- �������������֥��å��ϡ��������Τ������̤ˤ�ä��Ѥ�ꡢ�ʲ��Τ褦������ȤʤäƤ��ޤ���
- �ե�����ʸ����255ʸ���ޤ��б����Ƥ��ޤ���
- �ޤ������㡼�ʥ��ǽ��������Ƥ��ޤ�����
- ������HFS+�ϡ�NTFS����ǽ���ɤ����Ƥ��뤳�Ȥ��狼��ޤ���
- �פ���ˡ��ե����륷���ƥ�ϻ���ȤȤ�������̲���������������夵���ƻȤ��䤹���ʤäƤ����ȸ����ޤ���
- HFS+�ϡ�iPod�ˤ���Ѥ���Ƥ��ޤ���
- �ܥ�塼��
- ������
- �������������
- ��˥åȥ�����
- > 256MB
- 512B
- 256MB - 512MB
- 1kB
- 512MB - 1GB
- 2kB
- 1GB��
- 4kB
- HFS+�ե����ޥåȤ˻��Ѥ���륢������������˥åȥ������ʥ��饹����
- ����HFS���
- ��������������ǯ����1985ǯ
- �����������ե���������2
- ������������¤����B*��
- �����������ե����륵������������ 2GB���� = 231�¡�
- �����������ե��������������65,535���� = 216��
- �����������ե�����̾��������31ʸ������ = 25��
- �����������ܥ�塼�ࡧ������2TB���� = 241�¡�
- �������������㡼�ʥ����̵��
- ����HFS+���
- ��������������ǯ����1998ǯ
- �����������ե����������ޥ���ե�����
- ������������¤����B*��
- �����������֥��å�����������4kB���ꡡ�� = 212 B��
- �����������ե����륵�����������硡8EB���� = 263 B��
- �����������ե��������������̵��
- �����������ե�����̾��������255ʸ����Unicode�б���
- �����������ܥ�塼�ࡧ������16EB���� = 264 B��
- �������������㡼�ʥ뵡ǽ����ͭ�� �� �� �� ��
- ↑�˥�˥塼�С�������ʤ���硢
- ←����å����Ʋ�������
- ��
- �� ��
- ���ˤ�뵭Ͽ����2009.07.26�ɵ��ˡ�2011.03.03�ɵ��ˡ�2022.04.10�ɵ���
- ������Ͽ�������Τϡ�1830ǯ��ζ��������������Ϥޤꡢ100ǯ���1930ǯ��˳�ȯ���줿����Ŵ�ˤ�뼧���Ρ�����ե����ˤ��礭���������ޤ�����
- ����Ŵ�����Τˤ�������Ͽ�ϡ��Żҵ�Ͽ���ǽ�ˤ����ΤǤ�����
- 1980ǯ��ˤʤ�ȡ�����������������Ŵ�����ΤȤ������ΰۤʤ����Ȥä���Ͽ���֤��о줷�ޤ���
- ���θ���Ͽ���졼������������ޤ���
- ��
- �����졼�������
- ���ǥ������ȸƤФ�뵭Ͽ��ǥ����ϡ��졼����ȯ����ȯŸ�ˤ�괰���ޤ�����
- �졼����ȯ������Ƥ��ʤ���С������˽Ҥ٤���ǥ�������ǥ����������ܤʤ��ä����ȤǤ��礦��
- ����ۤɤ˥졼����ȯ���ϲ��Ū�ʤ��ȤǤ�����
- �졼�������ǥ�������Ͽ���礭�ʹ�����ͳ��ޤ��� ��
- 1.���ߥ�����ñ�̤Υӡ��ॹ�ݥåȤ��ưפ������롣
- 2.�����ͥ륮��̩�٤��⤯�������⥨�ͥ륮�����Ϥ����椷�䤹����
- 3.��ñ����Ĺ�Ǥ��뤿�ᡢ�Υ�������������䤹����
- 4.�����̤�·�äƤ��롣���Ĥ������䤹������Υ�����ʬ�����䤹����
- 5.���и������ѤǤ������渡�Ф��Ԥ��䤹�����졼�������и��������碌�Ƥ���Τ��и������Ѥ������طϤ����䤹����
- ��
- �������ǥ������μ���
- ���ǥ���������ɽ�����Τϡ�CD�ʥ���ѥ��ȥǥ������ˤǤ���
- CD�����ΤȤʤäơ�DVD��Blu-ray�ǥ������ؤ�ȯŸ���ޤ�����
- �ޤ����졼�����λ��Ĺ�̩��Ǯ���ͥ륮�������Ѥ���Ǯ�ˤ�äƼ������Ѳ����뼧���κ�������ȯ���졢MO��MD�γ�ȯ���Ԥ��ޤ�����
- �����Ǥϡ��졼����Ȥä����ǥ������ˤ������ʥǡ����˵�Ͽ���Τ�Ҳ𤷤ޤ���
- ��
��
- �� ��
- �ڸ������ǥ�������Magneto - Optical Disk = MO�ˡۡ�����2007.11.30�ˡ�2011.03.03�ɵ���
- ��
- ����MO�����θ��ǥ�������-���졼���ǥ�������LD��
- MO�ʸ������ǥ������ˤϡ�1980ǯ���Ⱦ���о줷�ޤ���
- MO�ϡ�����ԥ塼���Ѥε������֤Ȥ��Ƥΰ��֤Ť����������ʤǤ�����MO���Ф�������θ���ǥ����ˤϸ��ǥ�����������ޤ�����
- ����ϡ��졼���ǥ�������Laser Disc�ˤȤ���̾���Τ�Τǡ����ܤΥѥ����˥���1981ǯ�˻��β����ޤ�����
- �졼���ǥ�������LD = Laser Disc�ˤϡ��ǥ�����ǤϤʤ������ʥ���Ͽ��Ǥ�����
- �졼���ǥ���������ȯ���줿1981ǯ��������®�ǥ����뵻�ѤϿʤ�Ǥ��ʤ��ä��Τǡ���Ͽ���Τϸ��ǥ������Ǥ��äƤ⥢�ʥ������������NTSC����ˤ����Ĵ���ơ�30cm�������Υǥ������ʱ����ӥˡ����LP��Ʊ���礭���ˤ˱�����������Ǥ��ޤ�����
- ���λ����ϡ������Ѥ�VHS�ȥ١����ޥå����������ʶ���Ƥ��������Ǥ���
- ���λ����˳�ȯ���줿���졼���ǥ������ϡ����νФ�쥳���ɤȤ������Ф���ޤ�����
- ���Υ�ǥ�����Ȥäơ����饪���������դ��Ȥʤꡢ�Dz褬�ǥ������˾Ƥ�ľ�����9,000����������ʤ�����Ϥ�ޤ�����
- ��������1990ǯ�ǡ���81��������䵬�Ϥ����ä������Ǥ���
- 1998ǯ�ʹߡ�DVD��ȯŸ�ȤȤ�˿��ष�����ʤγ�ȯ�����ȥåפ���2009ǯ3��˥ѥ����˥�����¤��ߤˤ�äƼ�̿�������ޤ�����
- ���졼���ǥ��������������줿�Τϡ��ʲ����װ������ä�����Ǥ���
- �������졼���ǥ�������30cm�Ȥ����礭����LP�쥳�����פ��礭���ˤǤ��ä����ȡ�
- �������ʥ�����Ͽ�Ǥ��ä����ȡ�
- �����²��ˤʤ�ʤ��ä����ȡ�
- �����������Ѥ��ᥤ��Ǥ��ꡢ��Ͽ��ǽ�����֤Ϲ���Ǥ��ä����ȡ�
- ����DVD��CD����ǥ���ʬ��ȥ���ԥ塼��ʬ��˵�®�˿�Ʃ���ƹԤä����ȡ� ��
��LaserDisc VP-1000�λ��͡�1980ǯ�ѥ����˥��ҡ�
- ���ǥ���������ľ��30cm�����������
- ����Ͽ�̡�������߾���
- ���ԥåȡʵ�Ͽ����ˡ����ԥåȶ�0.4um������0.1um���ȥ�å��ԥå�1.6um
- ����Ͽ���������쥯��FM��Ĵ�ˤ�륹�饤����������Ȥˤ��NTSC���浭Ͽ�ʥ��ʥ�����
- ���������֡���CAV�ˤ�����30ʬ��CLV�ˤ�����60ʬ
- ���⡼����ž������CAV�ʲ�ž������ˤˤ�1,800 rpm��
- �� ����������������CLV����®�ٰ���ˤˤ�1,800 rpm����¦�ˡ�600 rpm�ʳ�¦��
- ���졼�������إꥦ��ͥ����졼��������1��W��ȯ����Ĺλ = 632.8 nm
- ���ӥǥ����ϡ���NTSC�ʥ��ʥ����ӥǥ��˿���
- �������ϡ���CAV�⡼�ɤˤơ������336�ܡ�������440�ܡ�ʿ��400�ܡ�
- ������������CLV�⡼�ɤˤ�336�� ����S/N����42dB�ʾ�
- �����������������ǽ����1��ž���ӥǥ�����1�ե졼���������
- �����ե�������ǽ��������
- ���Ÿ�����AC100V����95W
- ����ˡ����550W x 142H x 405D����17.5 kg
- �� �� ��
- ����VHD��Video High Density Disc�������������������Ǥ���
�� ��2009.11.17��- �졼���ǥ��������о줷������ˡ�LD�ʥ졼�����ǥ������ˤ��й������ӥǥ��ǥ�����������ޤ�����
- �����VHD�ȸƤФ줿��Τǡ�1983ǯ�����ܥӥ���������ȯ���ޤ�����
- ���Υӥǥ��ǥ������ϸ��ؼ��ǤϤʤ��������̼��Υԥå����åפ���äƤ��ơ�26cm�Υǥ������������Ǥ�����LD��30cm�¤Ǥ�����
- �������Ф��ԥå����åפϥǥ��������ܿ����Ƥ��ơ��ǥ������̤˵�Ͽ���줿�������̤ˤ��������Ф������ȤʤäƤ��ޤ�����
- ������ʥ��������Ǥ��� �ǥ������̤ˤϹ¤Ϥʤ���900rpm�ΰ����ž�Dz��CAV�����Ǥ�����
- �ǥ��������ԥå����åפ��ܿ�����ط��塢�ǥ������ϥ���ǥ��ʥ����ȥ�å��ˤ�������Ƥ��ޤ�����
- �ۥ������ä��ΤǤ���
- ��������LD�ϡ�����ǥ�̵���Υ٥��ǥ�������CD��DVD��Ʊ���ˤǤ�����
- ��̣���뤳�Ȥˡ�����VHD��VHS�ӥǥ��ơ��ץ쥳������ȯ�������ܥӥ��������꤬���ơ����������˻����������ˤϾ����Ŵ�ʥѥʥ��˥å��ˡ����Ρ������ŵ������㡼�ס���ɩ�ŵ��ʤ�15�Ҥ�̾��Ϣ�ͤ�Ȥ��������ȥ͡���Х�塼�Ǥϥ饤�Х���ݤ��Ƥ��ޤ�����
- �졼���ǥ����������ϡ��ѥ����˥��ΰ�ҤǤ�����
- ���ˡ��ʤ���Ω�ˤϡ����顢�ʤ���������οرĤˤ��Ȥߤ�������ˤʤäƥ졼���ǥ������˻������ޤ�����
- ���λ��¤ϡ�����Ū�˹ͤ��Ƥߤޤ��ȡ������졼�������ϤȤƤ����Ǥ��ꤽ��˰�����������⤢�ä����ᡢ¿���Υ����LD�˻�������Τ����������ΤǤϤʤ����ȹͤ��ޤ���
- 1980ǯ��Ƭ��ȾƳ�Υ졼���ϡ�CD�Ѥ��ֳ����������ϤΤ�ΤϤǤ��Ƥ�����ΤΡ�������Ͽ���������������û��Ĺ���ֿ��ˤǹ���ϤΤ�ΤϤޤ��Ǥ��Ƥ��ޤ���Ǥ�����
- �����ϡ�VHS�����������ܥӥ��������濴�Ȥ��Ƥ������������äƤ��ޤ������顢���οرĤ���ȯ���뿷���ʤ���ƻ�ϳȤ���Ȥ�פä��Τ����Τ�ޤ���
- ������γ��νФ�쥳���ɤγ�ȯ���äƳƼҤ��㤷���������ǡ��졼�������椹�뵻�Ѥ���������ѥ����˥���VHD�رĤ�������ʲ��ˤ����失�ޤ�����
- VHD��LD��Ʊ������ȯ�䤹��ͽ��Ǥ��ä��Τ������ѳ�ȯ���٤�������ˤ������1983ǯ�Ȥʤ�ޤ�����
- VHD�ϡ��������ʤ��顢��ʿ�����Ϥ�240�����٤�VHS���٤��㤵�Ǥ��ꡢ������ԥå����åפΥ��ƥʥ�Ԥ�ʤ���Фʤ�ʤ����ᡢ������ή�ˤʤ�ĤĤ��ä��ơ���������VHS�������Ȥ����꤬�ɤ��ä����Ȥ⤢��ʰ²������ӥ����ԡ����Ǥ���ˡ�����ۤɼ��פ�����ˤϤ�����ޤ���Ǥ�����
- �ޤ����Ȥ����꤬�褯�����ͥ���졼���ǥ��������礭��������뤳�Ȥˤ�ʤ�ޤ�����
- VHD�ϡ����̤������Ȳ����Ӥ������줬¿�����ä������Ǥ���
- �졼���ǥ�������LD�����֤�CD���ɤ߹����褦�ˤʤä� CLD-9000��ȯ���1984ǯ�ˤ���VHD��©�κ���ߤ��������ä��ȸ����Ƥ��ޤ���
- ���Τ���VHD�ϡ���˥ۡ���ӥǥ��Ծ줫���ű�ष�ơ����饪���Ծ�˼���ܤޤ�����
- �������������2003ǯ6����äƻԾ줫��ű�ह�뤳�Ȥˤʤ�ޤ�����
- ���� ��
- ����MO��Magneto Optical Disc���������ǥ������ˤγ�ȯ������2010.07.10�ɵ���
- ����ԥ塼���������֤Ȥ��Ƥ�MO��= Magnet Optical Disc�ˤϡ�1988ǯ��5.25���ʥ�����ˤθ������ǥ������Ȥ����о줷�ޤ���
- 3.5���ʥ�����˥����פ�MO��2HD�ե��åԡ��Ȥۤ�Ʊ���礭���Ǹ�����2�ܰʾ夢�ä����ϡ��ɥ����åȤ˼�Ǽ����Ƥ��롣
- ���θ塢����Ū�ˤʤ�3.5���ʥ�����˥�����128MB��MO�ϡ�1991ǯ�˽в٤���ޤ�����
- �����ϡ��ѥ�����ε�®��ȯŸ��ȼ�ä�FDD�ʥե��åԡ��ˤε������̤˸³����Ƥ��������Ǥ��ꡢ�ե��åԡ��ǥ��������Фǥǡ�������¸���õ�Ǥ���������ǥ�������MO�ˤ��о�ϡ������������ʬ����������ΤǤ�����
- MO�ϡ�CD���Ⳬȯ���٤����٤ʵ��Ѥ�ɬ�פȤ��Ƥ��ޤ�����
- MO�β��Ū�ʽ�ϡ��ǡ������õ�Ǥ����������������ɤ߽��Ǥ��뤳�ȤǤ�����
- �ǡ������̤�3.5���ʥ�����˥����פǤϡ�128MB��230MB�����䤵�졢540MB��640MB�ȿʲ����Ƥ����ޤ�����
- ���θ塢2.3GB���̤�MO�� = GIGAMO�ˤ����ʲ�����ޤ�����
- ��ǯ��CD�����ڥ�ǥ������饳��ԥ塼���Υǡ�����ǥ����˿ʽФ��Ƥ��ơ�����ԥ塼���Υǡ�����Ͽ��ǥ����μ�ή�Ȥʤä��Ȥ���MO������Ȥʤ餶������ޤ���Ǥ�����
- CD���ѥ������ǥ����μ�ή�ˤʤä�����CD�Υǡ�����Ͽ�������ե��åԡ���ϡ��ɥǥ�������MO�Τ���ȤϰۤʤäƤ���������礤�˸��Ǥä����Ȥ����Ƥ��ޤ���
- CD�ϡ��٤��ʥե�������ɤ߽��Ǥ������������CD�ˤ˰쵤�˽��ߤ�Ԥ�ʤ���Фʤ�ޤ���Ǥ�����
- ����ϡ�CD���ǡ������ɤ߽��Ѥ˳�ȯ���줿�ΤǤϤʤ������ڤ�������뤿��˺��줿���Ȥ˵������Ƥ��ޤ���
- ����Ͽ���ϡ�LP�ʱ��ӤΥ쥳���ɡˤ˸�����褦�˲�������Τ褦�ʱ��������˰��ܤι¤�Ϣ�ʤȵ�Ͽ���Ƥ�����ΤǤ���
- �ǡ�����������������Ǥ������ڤ��Ͽ���ǤϤʤ��ΤǤ���
- ���ڤΥ쥳���ɤ����ѤȤ��Ƴ�ȯ���줿CD�Ǥ���������ǥ������̤��礭���ȥǥ�����ñ���ΰ¤�����ѥ�����ȳ����礤�˼���������ƹԤ��ޤ�����
- 2000ǯ��Ⱦ��MO�ϡ�CD�ڤ�DVD��ȾƳ�ΤΥ��ƥ��å������ȯŸ�˱���Ƥ��ޤ���������ο������Բ�Ǥ��ʤ��ʤ�ޤ�����
- ������ͳ�����ϡ�MO��ǥ����ʥǥ������ˤ�MO�ɥ饤�����֤�������ä����ȤǤ���
- MO��128MB�����̤���ä��о줷���Ȥ��ˤϡ�CD�Ϥ��Ǥ�5�ܤ��礭��650MB�����̤���äƤ��ơ��ǥ��������ʤ�1/20�ʲ��Ȱ²��Ǥ�����
- �ޤ����������ι⤤CD/DVD�ɥ饤�����֤�����ԥ塼����ɸ��I/O�����������֡ˤȤ�����������ƹԤä��Τ��Ф���MO�ϺǸ�ޤdz��դ��μ������֤Ǥ��ä����ᡢ���Ȥ����MO���㤦ɬ�������ʤ��ʤäƤ��ޤ��ޤ�����
- CD��DVD�����ǡ����ξõ�Ƚ�ľ�����Ǥ���褦�ˤʤä��ꡢ��®�˥ǡ������̤����䤷�ƹԤä����Ȥ⡢MO����Ƴ����å���ʤ��ä��װ��Ȥʤ�ޤ�����
- �ޤ������ܤǤϤ��������μ��פ굯�������Τ��Ф������ƤǤΥޡ����ƥ���˧������ΤǤϤ���ޤ���Ǥ�����
- ����MO�ε�Ͽ����������
- MO�ξ���Ͽ�ˤϡ�����Ŵ�μ����ΤȰۤʤꡢ���٤˰�¸���뼧���Τ�ȤäƤ��ޤ���
- ��Ͽ�̤��ö�ⲹ���ݻ�150�١�180�١ˤ�Ǯ���Ƽ������֤����������٤��䤨�Ƽ�����������������ǡ��������鼧�Ϥ�Ϳ���Ƽ���������Ȥ���������ȤäƤ��ޤ���
- �������줿��Ͽ�̤ϡ��ﲹ�ǤϤ��ξ�����ݤ�³���ޤ���
- �Ǥ����顢MO���̾�ξ��֤Ǽ��Ф��Ť��Ƥ⼧������뤳�ȤϤ���ޤ���
- �����ν꤬������Ŵ�����Τ�Ȥä��ե��åԡ��ǥ������伧���ơ��ס��ϡ��ɥǥ������ɥ饤�֤Ȱۤʤ����Ǥ���
- ʪ�������������٤����ȸ����ޤ��� ���Υ���������ã������Τˡ����ͥ륮��̩�٤ι⤤�졼������Ȥ��ޤ���
- ����Ū�ˤ��ֿ��졼�����Ȥ��Ƥ��ޤ�����
- ���Τ褦�ˡ�MO��CD/DVD�Ǥϵ�Ͽ�������ۤʤä���ΤˤʤäƤ��ޤ���
- MO��������Ͽ����ܤȤ��Ƥ���Τ��Ф���CD/DVD�ϼ�����Ͽ��������Ѥ��Ƥ��ޤ��� ��Ͽ����������CD-R�ϡ�ͭ�����Ǻ������Ѥ���MO��궯���졼�����ǥԥå��̤�Ƥ��ڤ���Ǹ���Ū�ʵ�Ͽ�ޤ���
- CD-RW�Ȥ��������פϥǡ������٤�õ�Ƶ�Ͽ�Ǥ��������Ǥ��ꡢ�������Ǥ�MO�Ȼ��Ƥ��ޤ���
- ��������CD-RW�ʤ����DVD�Υ�饤���֥�ˤǤϥ����ե�����°���Ѥ��ơ������̤�졼����Ǯ���ͥ륮���ˤ�äƷ뾽��¤���Ѥ��ޤ���
- ���λ��˷뾽��¤�̤�ȿ��Ψ���Ѥ�뤿�ᡢ����ȿ��Ψ���Τ��ƥǡ������ɤ߽Ф�������ȤäƤ��ޤ���
- ���������ǤϤʤ��ΤǤ���
- ��
��
- MO�Ǥϡ�CD/DVD�ε�Ͽ��ˡ�Ȥϰۤʤ꼧���Ȥ������ǵ�Ͽ����ޤ���
- �ǡ������ɤ߽Ф����ˤϡ��������줿�̤��и��Ȥ����������ä����ͤ��������и�ȿ�ͤ�����Τǡʼ������إ������̡ˡ���Ͽ������夤�졼���������Ƥ��и����ٹ礤�Ф��Ƶ�Ͽ�����������Ф��ޤ���
- ����������Ͽ���ǽ�ˤ��뵭Ͽ�����ˤϡ��������R�ˤ����ܶ�°���ǡ�TM�ˤˤ���⥢���ե���������ޤ���
- ���κ�����ݥꥫ���ܥ͡��ȴ��Ĥξ�˥��֥ޥ���������θ����ǿ�����������������ˤ����Ƥ��ޤ���
- �������ǥ������ϡ�����Ǯ�ˤˤ�뵭Ͽ��������ܤȤ��Ƥ���Τǡ��ǥ�������¤�ˤϰ��ꤷ����Ͽ�ݻ����Ǥ��뵭Ͽ����γ�ȯ�����ڤʲ���Ǥ�����
- ����MO��¸�߲���
- MO�ϡ�2011ǯ�����Υ���ԥ塼�����յ�Ͽ���֤���ˤ��äơ�CD��DVD�˼�Ƴ����å���Ƥ��ޤäƤ��ޤ���
- ��������MO�ˤ�MO�ʤ�ǤϤ��礭������������ޤ���
- ������ѵ����Ǥ���
- MO�Υǡ����ݻ������̿��50ǯ�Ȥ�100ǯ�Ȥ����졢��Ͽ�����1000����ȸ����Ƥ��ޤ���
- �����ѵ����ϡ��ϡ��ɥǥ�������ե�å������ʤɤȳӤ٤Ʒ�㤤����ǽ�Ǥ���
- ���δ������顢MO�����ڤʥǡ�����Ĺ����¸��������˽�ʬ�˱����뤳�Ȥ��Ǥ��������ߤ⺬�����ٻ������Ƥ��ޤ���
- MO���⤤�ѵ������������Τϡ��ʲ��Τ褦�����Ǥˤ���ΤǤ���
- 1.��MO�ǥ���������ϴ�ʥ����ȥ�å��˼�Ǽ����Ƥ��뤿�ᡢ ��������Υ����ۥ��ꡢ�����ߤ����˶�����
- 2.��MO�ǥ������ϡ�CD��DVD�ǥ������˳Ӥ٤�2�ܤۤɤθ��������ꡢɽ�̤�����ݥꥫ���ܥ͡��Ȥ�ʤ���Ƥ���Τǥ����˶�����
- 3.��MO�˻��Ѥ����졼�����ϡ��夤���Ϥ��ɤ߽�Ԥ��Τǥǥ������ؤΥ���������ʤ���
- 4.���ﲹ�Ǥμ��Фˤ�뼧�����ʤ���
- 5.�����ܿ����ʤΤǡ��ϡ��ɥǥ�������ե��åԡ��ǥ������Τ褦�˥ǥ����������פ��ʤ���
- 6.��CD-R��DVD-R�ε�Ͽ��ǥ�������糰�����Ф��ƶ�������ǯ�Ѳ��˶�����
- MO������Ū����ڤϤ���ޤ���Ǥ����������ܤǤ����Ū��Ĵ�˥�������ݻ����Ƥ��ơ�����ģ�ʤɤǤ�Ĺ����ʸ�����¸����ɬ�פΤ��뵡�ؤ䡢���Ǵط��ǤϺ��������פ���äƤ��ޤ�����
- �ޤ���5.25������Τ�Τϰ���³����ȯ���Ԥ�졢�Ļ�졼�����Ѥ���200GB���̤Υǥ�������ȯ���Ԥ��Ƥ��ޤ���
- 2011ǯ�ˤ��ä�MO�ǥ������ɥ饤�֤���¤���Ƥ������Ϥ���ޤ���
- ��ǥ�����¤�ϡ�2009ǯ9��������Ω�ޥ����뤬��¤��λ����Ʊǯ12�����˻�ɩ���إ�ǥ����������λ���ޤ����� ��¤��³���Ƥ������ˡ���2018ǯ�������λ���ޤ�������2022.04.20�ɵ���
- ��
- �� ����
��CD = Compact Disc��
- ��Disc�ϱѹ�ɽ�����̾��Disk�Ǥ��뤬���ˡ���Disc����Ͽ��ɸ���Ѥ�������2009.09.17�ˡ�2009.11.20�ɵ��ˡ�2020.05.10�ɵ���
CD�ʥ���ѥ��ȥǥ������ˤ�������1982ǯ�Ǥ���
- CD���о�ϡ��ǡ�����ǥ����˰����̿��⤿�餷�ޤ�����
- 650MB�ε������̤���CD�ϡ������ǥ�����ǥ�����˥ѥå���������Τ˽�ʬ�Ǥ��ꡢ�ѥ�����Υǡ�����¸�ˤ⽽ʬ�Ǥ�����
- CD����ȯ���줿������1982ǯ�ϡ�IBM���ѡ����ʥ륳��ԥ塼������ȯ���줿ǯ�Ǥ��ꡢ�ޤ��ե��åԡ��ǥ�������ϡ��ɥǥ������ɥ饤�֤���ȯ���줿ǯ�Ǥ⤢��ޤ���
- CD�ϡ����δ��Ф��餹��ȥ���ԥ塼���Υǡ�����ǥ����Ȥ��Ƴ�ȯ���줿���ݤ�����ޤ���
- ���������ºݤϲ����ѤȤ��Ƴ�ȯ����ޤ�����
- ���������ӥˡ���Υ쥳���ɡ�LP = Long Play Record Album���礭��φ12����� = 30.5cm�� ξ��Ͽ�������ʥ�����Ͽ�ǥ������ˤ�����ǥ�����ǥ������Ȥ��Ƴ�ȯ���줿�ΤǤ���
- CD�ϡ��ϡ��ɥǥ������ɥ饤�֤Τ褦�˥���ԥ塼���ѥǡ�����¸�ѤȤ��Ƴ�ȯ���줿�櫓�ǤϤ���ޤ���
- CD�ϡ����ˡ�����Ω�����ܥ�����ӥ��ˤ�äơ��ǥ����륪���ǥ����ǥ������Ȥ���ȯ�䤵��ޤ�����
- ����ԥ塼���ѥ�ǥ����Ǥ���CD-ROM��Compact Disc Read On Memory�ˤϡ�������CD��ȯ�䤵�줿3ǯ���1985ǯ�˺���ޤ�����
- �ǡ����ե������PC��ȤäƵ�Ͽ��¸�Ǥ���CD-R�ϡ�1989ǯ�˥��ˡ��ȥե���åץ��ˤ�äƳ�ȯ����ޤ�����
- CD-ROM��CD-R�ʸ�ǯ��CD-RW�ˤϡ��ѥ������ȯŸ��̵���ƤϤʤ�ʤ���ΤȤʤ�ޤ�����
- ������CD�ϡ�����Ū�ʥǥ�����Ͽ����ǥ����Ǥ��ꡢ�ʼ����褯�Ƽ�갷����ڤʤ��Ȥ���Ծ�˵�®����ڤ���ȯ��7ǯ���1989ǯ�ˤϤ���ޤǼ�ή�Ǥ��ä��쥳�����ס�LP�ˤ��Ф�����奷������90%�Ȥ��ޤ�����
- 2007ǯ������LP�λѤ�ŹƬ�ˤ���ޤ���
- CD�ϡ�1982ǯ��ȯ��ʹ�28ǯ����ˡ�2010ǯ�����ˤ���Ĥ��Ȥˤʤ�ޤ���
- ��ʬ��Ĺ���ֲ��ڥ������Ȥ��Ʒ��פ����褿�褦�˻פ��ޤ���
- ���ʤߤˡ����ƥ쥪�Υ쥳�����פ�1958ǯ�˳�ȯ����ޤ�����
- 24ǯ���1982ǯ�˥ǥ����륪���ǥ����θ��ĤǤ���CD��ȯ�䤵��ޤ�����
- 1982ǯ�ϡ��ǥ����륪���ǥ�����ǯ�ȸƤФ�Ƥ��ޤ���
- CD���й��ϤǤ����졼���ǥ�������LD���ϡ�1972ǯ���������ե���åץ��Ҥdz�ȯ����ޤ�����
- ���Υǥ������ϡ����ؼ��ӥǥ��ǥ������Ǥ������ǥ�����ǤϤ���ޤ���Ǥ�����
- 1977ǯ�ˡ����Υӥǥ��ǥ���������ܤȤ��������ǥ����ǥ������������ˡ�����ɩ���ƥ����å�����Ω�����ܥ�����ӥ�����ȯ�䤵��ޤ�����
- �ʤ���CD�ϡ�2001ǯ��iPod��ȯ��������MP3���ڥե����뤬��ή�Ȥʤꡢ�����ͥåȤ������������ɤ����褦�ˤʤ�ȵ�®�˼��פ餷�Ƥ����ޤ�������2020.05.10�ɵ�����
�������ǥ�������ɸ��Ȥʤä�120mm�¡�����1.2mm����
- 1979ǯ���ե���åץ��Ҥϸ��ߤ�CD�θ����Ȥʤä�ľ��11.5cm�Υ���ѥ��ȥǥ�������ȯɽ���ޤ���
- ���Υ������κ���ϡ��ե���åץ�����ȯ���������ǥ��������åȤ��г���������Ф����������ȸ����Ƥ��ޤ���
- ���Υǥ������������ǡ�14�ӥåȤ��̻Ҳ��ˤ��60ʬ�Υǥ�����Ͽ�����Ǥ����߷פˤʤäƤ��ޤ�����
- �����������λ��ͤ������ʤ��ä����ˡ��ϡ��١��ȡ��٥��������ʤ����ä�������67ʬ��Ͽ����16�ӥåȤ��̻Ҳ�����Ƥ�������ˡ��ǽ�Ū��12cm��ľ�¤Ȥʤ�ޤ�����
- 12cm�¤�CD�ϡ�75ʬ��Ͽ������ǽ�Ǥ�����
- 1980ǯ�ˤϡ��ե���åץ��ȥ��ˡ��ˤ�äƥ���ѥ��ȥǥ������ε�������ι�դ��ʤ��졢�ܳ�Ū��CD���夬���褷�ޤ�����
- CD����ȯ����ưʹߡ����ǥ������ι�®�����̲��ε��Ѥ��ʤߡ�DVD��HDDVD��Blu-ray����ȯ����Ƥ����ޤ���
- ���������������ǥ������Υ�������12cm�α߷��Ǥ��ꡢ������1.2mm��Ʊ����ˡ�ˤʤäƤ��ޤ���
- ����MO��ե��åԡ��ǥ�������FDD�ˤ�ϡ��ɥǥ��������֡�HDD�ˤϡ�8�������5.25�������3.5�������2.5������¤Ȥ����ƹ���ͤǼ������ޤ�����
- CD��FDD��HDD�ˤϡ��ǥ����뵭Ͽ�Ǥ���ʤ����̡���ʬ��鳫ȯ���Ԥ��ơ�����ԥ塼���Υ��ȥ졼���ʥǡ�����¸��ʬ��˺��դ��ƹԤ��ޤ�����
- ��
- ����CD���
- �ڻ��͡�
- ��ľ�¡���12cm�ʤޤ���8cm��
- ����������1.2mm�� ����������ݥꥫ���ܥ͡���
- ����®�١���1.2m/s��1.4m/s
- ����ž������500rpm���濴���ˡ�200rpm�ʳ�������
- ���ȥ�å��ԥå�����1.6um
- ���Ǿ��ԥå�Ĺ����0.87um
- ���ɤ��졼������λ=780nm�ֿ�ȾƳ�Υ졼��
- ����ʪ�����������N.A. = 0.45
- ���������̡���640MB��650MB��700MB
- ���ɤ߹���®�١���1.2M bps��1411.2k bps ����®������72��®��
- ���������ǥ���CD�ε�Ͽ���ȿ���44.1kHz
- CD��ȯ�κ��ܻ��ͤΰ�Ĥˡ���Ͽ���ȿ�������ޤ���
- ��Ͽ���ȿ�������Ǥ���Τϡ��ǥ�����Ͽ����ΤǤ����������ȸ����������Ǥ���
- ����ǥ����벽�����硢�ɤ����٤μ��ȿ��ǥǥ������Ѵ�����и����˶Ͽ���Ǥ��ơ�������谷���ڤ��Ȥ����߷��ۤˤ��äơ�44.1kHz�����ꤵ��ޤ�����
- �ͤβ�İ���ȿ��ξ�¤�20kHz�ȸ����Ƥ��ޤ��Τǡ������ܤ�40kHz�ˤ����20kHz�ޤǤβ�����¤˺Ƹ��Ǥ���Ȥ����Τ�����Ǥ�����
- �ޤ������μ��ȿ��˹�碌�Ʋ���16�ӥåȡ�65,000��Ĵ�ˤ��̻Ҳ����Ƥ��ޤ���
- �����礭����65,000��Ĵ��ʬ�����Ȥ������ȤǤ���
- ��������CD�ˤ�벻���Υǥ�����Ͽ���ϡ����������줾��44.1kHz�Υ���ץ�졼�ȤȤ���16�ӥåȤˤ�ä��̻Ҳ�����ޤ�����
- Ͽ�����ʳ��Ǥϡ�16�ӥåȤ�8�ӥåȤ���2�Ĥ�ʬ���Ƥ��ޤ���
- ����8�ӥå�ʬ��1����ܥ�ȸƤӤޤ��� ���äơ��̻Ҳ����줿1����ץ�� = 1/44,100��ñ�̡ˤβ��ϡ�16�ӥå� = 2����ܥ�Ȥʤ�ޤ��� CD-ROM��1985ǯ��ȯ�ˤΥǡ����ɤ��®�٤ϡ�����CD��Ʊ��®�٤�����줿����1.2M�ӥå�/�á����Τˤϡ�1,411.2k bps�ˤȤʤäƤ��ޤ���
- �� ����44.1k Hz x 16 bit/ch x 2 ch = 1411.2k bps����������Rec -39b��
- �������®��1��®�ˤȤ����ǡ����ι�®ž����ȼ�ä�®�٤��夲��졢x2��x4��x8��x48�ȸƤФ���®�ɤ߽Ф����Ǥ���褦�ˤʤ�ޤ�����
- 2006ǯ�ˤϡ�x52��®����CD����ȯ����ޤ�����
- ��
- ����EFM��Ĵ���� ��Eight to Fourteen Modulation��
- �ǥ����륪���ǥ�����Ͽ�������ǡ�CD����ǽ�����Ť���EFM��Ĵ�����ˤĤ��ƽҤ٤ޤ���
- ����ȯ���ˤ�äƥǥ����륪���ǥ����μ��Ѳ�������Ť���줿�ȸ��äƤ����ǤϤ���ޤ���
- ���ڤϡ��Ԥä��ʤ���Ĺ���֤ˤ錄�겻���ǡ�����ή��Ƥ��ޤ���
- �����ǥ������֤ϡ��ְ㤤��Ǥ���������ʤ����Ƴμ¤˥ǡ������ɤ߽Ф��ʤ��ƤϤʤ�ޤ���
- �ǥ�����ǡ����γμ¤ʹ�®�����Ϥ����ǽ�ˤ����Τ���EFM��Ĵ�������ä��ΤǤ���
- CD��Ͽ���Ǥϡ������ǡ�����1����ܥ� = 8�ӥåȤ�14�ӥåȤ��Ѵ�����ޤ���
- 8→14�ʤΤǡ������EFM��Eight to Fourteen Modulation�ˤȸƤ�Ǥ��ޤ���
- ���ε�ˡ�ϡ��������Υե���åץ��� �βʳؼ�Kees A. Schouhamer Immink��1946.12���ˡʥ����������ۥ��ϥ�롦���ߥˤˤ�äƳ�ȯ����ޤ�����
- �ʤ���8�ӥåȤβ������虜�虜14�ӥåȤ��Ĥ�ޤ��Ƶ�Ͽ������ΤǤ��礦��
- �ǥ�����ǡ����ϡ����̵��Ѥ�ȤäƤɤ�ɤʤ����Ƥ��뷹��������Τˡ�CD���ܶᤤ�ǡ������Ĥ�ޤ��ơ�����������8�ӥåȤΤޤ����֤��Ƥ���Ȥ����Τϡ������ˤ�Ǽ���Ǥ��ʤ����ȤǤ���
- ���������������ʤ��ȥǡ�����μ¤����뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���Ǥ�����
- �ɤߴְ㤨�ʤ��������ˡ�Ǥ�����
- EFM�ϡ��ǡ�����μ¤��ɤ�뤿������̤뤳�ȤΤǤ��ʤ���Ĵ�������ä��ΤǤ���
- �㤨�С����������ʤ���0�פ�ͤ��Ƥߤޤ��礦��
- ���λ���8�ӥåȤβ�����ϡ�0000000�Ȥʤäơ�0�פ�8���¤Ӥޤ���
- ���ξ�硢CD�ץ졼�䡼�Ϥ����ȡ�0�פ�8�ĤȤ����ɤ�äƤ����Ǥ��礦����
- Ʊ�����椬Ϣ³����³�����Ȥ���CD�Υԥå����åפ��ɤ��������ǥ������β�ž��顢CDɽ�̤α��졢��١��ǥ����������ߤ䷹���ʤɤ�������������ɤ߹��ޤʤ���ǽ������ʬ�˽ФƤ��ޤ���
- ���������ɤ�������ʤ�������ˡ�8�ӥåȤδ֤ˤ��餿�˾�����ʬ��6����������Ĺ��³��Ʊ��������ʬ�åȤ�������ʤ����ƾ�����ɤ�����٤���ΤǤ���
- 8�ӥåȾ���ˤ�����256����ˤϡ�ͽ��14�ӥåȾ�����Ѵ�����ơ��֥��ɽ�ˤ������Ƥ��ơ������Ѵ��ơ��֥�˽��ä�14�ӥåȲ����������CD�˽��ߡ�CD�����ɤ߽Ф�����14�ӥåȤξ����Ƥ��Ѵ��ơ��֥��Ȥä�8�ӥåȤ��᤹�Ȥ������Ȥߤ���Ѥ��ޤ�����
- �ʤˤ��Ź�ʸ�ΰŹ沽/���沽�Τ褦�Ǥ���
- �� ���ʤ���CD�Ϥ���ۤɤޤǤ˥ǡ������ɤ��Ťˤ��Ƥ���ΤǤ��礦�� ��
- ¾�ε�Ͽ���Ρ��㤨�Хե��åԡ��ǥ�������ϡ��ɥǥ������Ǥ�Ʊ���褦�������ǥǡ�����Ͽ���Ƥ���ΤǤ��礦����
- �����ϥΡ��Ǥ��� CD�ϡ�CD�ʤ�ǤϤΥǥ����벻���ǡ����ɤ߽Ф��λ��𤬤���ޤ�����
- ����Ȥϡ�67ʬ�֤��Ĺ����Ϣ�ʤȥǡ�����Ф�³���ʤ��ƤϤʤ�ʤ�����Ǥ���
- ����ϡ�ʸ��ե�����ʤɤΥǡ������ϼ��ȤϷ���Ū�ʰ㤤�Ǥ���
- �Ԥä��ʤ��Υǡ������Ϥ��Ф��Ƥϡ������ɤ������Τ˥ǡ�������Ф�ɬ�פ����ꡢ������������Ťˤ⤷�ƥǡ����ο���������빩�פ��ʤ��줿�ΤǤ���
- ʸ��ե�������Ż߲����ե�����ǡ����ʤɤϡ������ޤǸ��������ʤ��Ƥⲿ�٤Ǥ��ɤߤ˹Ԥ����ɤ��Τdzڤ����Τ�ޤ���
- �Dz�Τ褦��ư�����Ȥʤ�ȡ�����Ʊ���Ԥä��ʤ��α�������ˤʤ�Τǡ����������Ϥ���˽��פȤʤ�ޤ��� ���äơ�DVD�Ǥ�Blu-ray�Ǥ�Ʊ�ͤθ���������ǽ�ʤ������äȹ�̯�ʵ�ǽ�ˤ��Ĥ����Ƥ��ޤ���
- ����17�ӥåȤ�1����ܥ�ǡ���
- ��˽Ҥ٤��褦�ˡ�44.1kHz�ǥ���ץ���줿��Ĥβ���2����ܥ�ǹ�������ޤ���
- �����EFM�ˤ�ä�14�ӥå�1����ܥ�Ȥ��Ƥ���Τǡ����ΰ�Ĥ�28�ӥåȤΥǡ����Ȥʤ�ޤ���
- �����Ǥϲ����ΰ�ñ�̤���ǡ�pixel�ˤȸ��äƤ���Τˡ����δ��ܤϤʤ�ȸ��äƤ���ΤǤ��礦��
- ���ǡʤ��� = aucel�ˤʤɤȤ���������������ΤǤ��礦����
- �Ѥʵ���ϤȤ⤫����CD�˵�Ͽ���줿���δ���ñ�̤�44.1kHz��2����ܥ�Ȥ������Ȥˤʤ�ޤ���
- �ǥ�����Ͽ������벻�Ǥ�28�ӥåȤˤʤ�ޤ��������ΰŹ沽���礭���ʤäƤ�������ʤΤǡ������Τ�16�ӥåȤ��Ѥ�꤬����ޤ���
- ���μ�ˡ��EFM�ˤϡ����Ū�ˤϲ��Ū�ʼ�ˡ�Ȥʤ�CD�κƸ������ɤ���θä����Τˤ��ޤ�����
- ���������ˤ�ꡢDVD�γ�ȯ�ˤ����Ƥ�Ʊ����������Ѥ���EFMplus�����Ѥ��졢Blu-ray Disc�Ǥ�1-7pp��Ĵ�����Ѥ���ޤ�����
- ���Τ褦�ˤ��ơ�������Ĵ�����ϥǥ�������ǥ�����̵���ƤϤʤ�ʤ���ΤȤʤ�ޤ�����
- ����ˡ�EFM��14�ӥåȤˤ��줿1����ܥ�β��ϡ�3�ӥåȤΤĤʤ��ӥåȤ����������17�ӥåȤȤ���ΤǤ��줬1����ܥ�ñ�̤Ȥʤ�ޤ���
- �Ĥʤ��ӥåȤ���Ū�ϡ���Ͽ�ȷ���ľή��ʬ�ʤ����뤳�Ȥˤ��ꡢĹ�����֤Ǥߤ�HIGH��LOW���������ʤ�褦�ˤ��Ƥ��ޤ���
- 14�ӥåȡ�1����ܥ���ȷ���HIGH�ˤʤäƤ���ФĤʤ��ӥåȤ�LOW�ˤ��ƥȡ������0�ˤʤ�褦�ˤ��Ƥ��ޤ���
- ���ε�ǽ���ǡ����˷�٤����ä��������ǡ�����ľ���ʤ���Фʤ�ʤ��Ȥ�����Ω���ޤ���
- �Ĥʤ��ӥåȤ�ľή��ʬ���㤯�ޤ���ˤϡ�DSV��Digital Sum Value�ˤȤ������ͤ���Ƚ�Ǥ��ƹԤ��ޤ���
- �Ĥʤ��ӥåȤϡ���Ͽ���������������ˤʤ�褦�ʵ��⤷�ޤ������ºݤˤϤ���ʾ�Υ��åȤ�����ޤ���
- Ϣ�ʤ�³�������Ԥä��ʤ��ǺƸ����ƹԤ��ˤϡ��������������������Ѥߤ˶�Ȥ��Ƥ���ɬ�פ����ä��ΤǤ���
- ������ɡ������������Reed Solomon Coding��
- CD�˺��Ѥ��줿����ܥ��ñ�̤Ȥ��Ƹ���������Ԥ���ˡ���ɡ����������������Reed - Solomon Coding�ˤȸ����ޤ���
- ��ɡ�����������ϡ�1960ǯ�˳�ȯ����ޤ�����
- ��ɡ�Irving S. Reed: 1923���ˤȥ�������Gustave Solomon: 1930 - 1996�ˤϡ��ƹ�ο��ؼԤ�MIT�ʥޥ����塼���åĹ�����ء˽пȼԤǤ���
- 1960ǯ�ϡ��ǥ������������ʬ��ȯã���Ƥ��ʤ������ʤΤǡ����μ�ˡ�ϥǡ��������ΰ�ӤȤ��ƿ��ؾ�Υơ��ޤdz�ȯ���줿��Τȹͤ��ޤ���
- ���줬��������λ���ˤʤäơ�����θ��������ζ��Ϥʼ�ˡ�Ȥ��Ƽ��夲��졢CD��DVD�ε�Ͽ�䡢�����ǥ������̿��ʤɤ˼��������ޤ�����
- ������沽�ϡ������֥��å����ʬ���ʥ���ܥ벽�ˤƥ���ܥ���θ���������Ԥ����Ȥ���ħ�Ȥ��Ƥ��ơ��ǡ����η�»��Ϣ�ʤ�³����ǽ���Τ����������˰��Ϥ�ȯ�����ޤ�����
- ����ϡ�CD��DVD�ʤɤ�Ϣ�ʤ�³���ǡ��������������ˤϤ��äƤĤ��Ǥ�����
- ������������ʣ���ʤΤǡ����������⤤�ץ����å��������ޤǤϸ���̣���ӤӤޤ���Ǥ�����
- 1980ǯ���Ƭ���������������ѴĶ����Ϥ����������ä��Τ�������Ǥ��ޤ���
- ����CD�Υǡ�������
- CD�ϡ�Ĺ���֤β����ǡ������������ɤ߽Ф���ޤ���
- CD������ɤ߽Ф��ϡ��ե��åԡ��ǥ���������¸���줿���̤�ʸ����¸�Ȥϼۤʤ�ޤ���
- �ǡ����ϸ夫�餢�Ȥ���ɤ�ɤ�ФƤ��ޤ��Τǡ�®�䤫���ɤ߽Ф���Ԥ�������μ¤Ǥʤ���Фʤ�ޤ���
- ���Τ���˥ǡ������μ¤��ɤ߽Ф���褦�ѥ�ƥ����Ȥ߹��ޤ졢�ޤ���Ϣ³����Ʊ������ǡ�����³���ʤ��褦�ˡ�8�ӥåȥǡ�����14�ӥåȤ��Ѵ�����������ʤ���Ƥ��ޤ���
- ��������Ͽ�����ǡ��������������Τ���ο��椬�Ȥ߹�蘆��Τǡ��ºݤβ����ǡ�������礭���ʤ�ޤ���
- ����1�ե졼��ñ�̤β����ǡ���
- CD�ε�Ͽ�ˤϡ��ǡ����θ��ꡢ��»�β����������Ȥ��ơ�1�ե졼��ñ�̤ǥǡ�������Ǽ����Ƥ��ޤ���
- �ե졼����ȿ��ϡ�7.35kHz�ǡ������ͥ�ӥåȿ���4.3218MHz�� = �ե졼����ȿ���588�ܡˤȤʤäƤ��ޤ���
- �ե졼�����ϡ��ʲ��Τ褦�ʹ����ȤʤäƤ��ޤ���
- �ե졼�����γ�ǰ�ޤϲ��ޤȤ��Ʋ�������
- ��1�ե졼��Υӥåȿ���588�ӥåȤǤ��롣���������ϡ�
- �� �ե졼��κǽ�ϡ�24�ӥåȤ�Ʊ������ + �Ĥʤ��ӥå�3�ӥåȡ�
- �� �������濮��Ȥ��ơ�14�ӥåȡ�1����ܥ�� + �Ĥʤ��ӥå�3�ӥåȤ����Ƥ��롣
- �� ���˥ǡ����Υ���ܥ뤬12������17�ӥå� x12��
- �� ���������ѥѥ�ƥ��ӥåȤ�4����ܥ롣��17�ӥå� x4��
- �� ���Υǡ�������ܥ�ȥѥ�ƥ����⤦���Ĥʤ����17�ӥå� x16��
- ��˽Ҥ٤������ˤ�äơ�1�ե졼�ढ���ꡢ588�ӥåȤβ��Ȥʤ�ޤ����ʲ����ȡ� ��
- �� 24 bit/Ʊ������ + 3 bit/�Ĥʤ� �� + 14 bit/���濮�� + 3 bit/�Ĥʤ�
- ������������+ ��17 bit/�ǡ��������� x��12 + 4�� �ǡ��������� ��x 2 = 588 �ӥå�������������Rec -40��
- 1�ե졼���588�ӥåȡ˥ǡ���������ϡ��ʲ��οޤΤ褦�ˤʤäƤ��ޤ���
- ���β���1�ե졼��ˤ���Ф��ơ�����˸��꤬�ʤ����ɤ���������å��������顼������Ф�����������ƺ����ʤ�����ޤ���
- �ޤ���狼��褦�ˡ��ǡ�������¸����Τˡ���ʬ�ȿ��Ť˥��顼�����å���ǽ���Ȥ߹��ޤ�Ƥ���Τ��狼��ޤ���
- 1 �ե졼��ˤϾ嵭��������겻���ǡ�����24��ʬ���뤳�Ȥ��狼��ޤ���
- CD�����ǡ����ϡ�������L.R��2�����ͥ뤢�ꡢ�ޤ��������ǡ�����2�ĤΥ���ܥ�ǣ��Ĥβ���ñ�̤������Ƥ���Τǡ�1�ե졼��ˤϡ�24�ĤΥǡ�����2�ʺ����ˣ�2�ʥ���ܥ�� = 4�dz�ä�6�Фκ����β����ǡ�������Ǽ����Ƥ��뤳�Ȥˤʤ�ޤ���
- ��
- �� ��
- 1�ե졼��6�ФΥǡ�����1�ե졼�ब�������졢���줬 7.35kHz�dz�Ǽ����뤿�ᡢ1�Ĥβ����ϡ� ��
- 7.35 kHz x 6 = 44.1 kHz��������������Rec -41��
- 44.1kHz�β�������ץ���ȿ���Ͽ������Ƥ��뤳�Ȥ��狼��ޤ���
- CD�ε�Ͽ���̤�����Ƥߤޤ��� CD�ϡ�1�ե졼��Ȥ���ñ�̤ǵ�Ͽ����Ƥ��뤳�Ȥ���˽Ҥ٤ޤ�����
- ����ϡ�588�ӥåȤβ��Ǥ��ꡢ�����7.35kHz�ǵ�Ͽ���Ƥ������ᡢ
- 588 �ӥå� x 7,350 Hz = 4.3218 M�ӥå�/��������������Rec -42��
- �ε�Ͽ�Ȥʤ�ޤ��� ���줬74ʬ��³���ȡ�CD-ROM�ε������̤ϡ�
- 4.3218 M�ӥå�/�� x 60 ��/ʬ x 74 ʬ = 19,188.792 M�ӥå��� = 2,398.599 MB�ˡ�����������Rec -43��
- �Ȥʤꡢ��פ����19.2G�ӥåȤȤʤ�ޤ���
- ���η��ͤϡ��̾�����Ƥ���CD-ROM�ε�������650MB��3.6�ܤˤ�����ޤ���
- �Ĥʤ������������������������ΤΥǡ����ϡ�
- 14 �ӥå� x 2 ����ܥ� x 2 �����ͥ� x 44.1 kHz x 60 x 74 /8 �ӥå���= 1,370.628 MB��������������Rec -44��
- 1.37GB�Ȥʤ�ޤ��� ����ϡ����̤˸����Ƥ���CD-ROM�����̤�2�ܤε�Ͽ���̤ˤʤ�ޤ���
- �̾CD�ϥ���ץ���ȿ���44.1kHz�ǡ�16�ӥå��̻Ҳ�������2�����ͥ륵��ץ��74ʬ�ε�Ͽ��Ԥ��ޤ����顢FEM�Ѵ����θ���ʤ���������ϡ�
- 16 �ӥå� x 2 �����ͥ� x 44,100 Hz x 60 �� x 74 ʬ /8 �ӥå� = 783.216 MB������������Rec -45��
- 783MB�Ȥʤꡢ����Ū�˸����Ƥ���CD�����̤ο��ͤȤʤ�ޤ���
- �Ĥޤꡢ�����Ǹ��������Τϡ�CD�ε������̤ϡ����ΤΥǡ������̤�3.6�����٤��롢�Ȥ������ȤǤ���
- CD�ˤϡ���Ͽ�ǡ����ΰ�������¸�Τ���˿����ʥ����å��ǡ����ӥåȤ��ä����Ƥ���Ȥ������Ȥ��狼��ޤ���
- �����ޤǤ��ʤ��ȡ��ޤȤ�˥ǥ����벻������ε�Ͽ�������Ǥ��ʤ��ä����Ȥ��Ƥ���Ƥ��ޤ���
- �ǥ����뵭Ͽ���Τ���ˤ��֤äƸ���ȡ������ޤǴ��Ťˤ��������������ܤ�����Ͽ�����Ϥʤ��ä��褦�˻פ��ޤ���
- ��ơ��פˤ��Ƥ�ե��åԡ��ˤ��Ƥ��ñ�ʥѥ�ƥ������ǥǡ�������¸���Ƥ��ޤ�����
- �ϡ��ɥǥ������Ǥ���¸�ϡ���������˥ǡ����γ�ǧ���Ԥ�졢���ޤ���Ͽ�Ǥ��ʤ����Ϻ��ٽ���Ȥ����������äƤ��ޤ�����
- ��������CD�ξ��ϡ�����ʲ����ǡ�����Ϣ�ʤ�ή���ʤ���Фʤ�ʤ������塢�ޤ��ǥ��������Ĥߤ䷹�����ǥ�����ɽ�̤α���ʤɤ��θ�����ɤ�ꥨ�顼�����äƤ������Ǥ���褦�ˡ����Τ褦���������ä���Τȹͤ��ޤ���
- ��
- �����ǡ�������
- CD�˵�Ͽ�����ӥåȤϡ�1����������230�ʥ��äλ��ֳִ֡�= 1/4.3218M bit/s�ˤǵ�Ͽ����ޤ���
- �ӥåȤϡ�0.5um�ζҤ��礭���ǡ��ȥ�å��ֳ֤�1.6um�ԥå��Ǻ���Ƥ��ޤ��ʱ����ȡˡ�
- �ԥåȤ�Ĺ���ϡ�9���ढ�ꡢ��®�٤�1.25m/s�ξ�礽�줾�졢
- 0.87um��1.16um�� ��1.45um
- 1.74um�� ��2.02um��2.31um��
- 2.60um��2.89um�� ��3.18um
- �ȷ����Ƥ��ޤ���
- ����Ĺ���ϡ���®�٤ȥԥåȤλ��ֳִ֡�231.385�ʥ��áˤ�ͤ���碌��ȡ�0.87um�Υԥå�Ĺ�Ǥ�3�ӥå�ʬ�����������ʲ�1�ӥå�ʬ����Ĺ���������Ƥ�����3.18um�Υԥå�Ĺ�Ǥϡ�11�ӥå�ʬ�ξ���ˤʤ�ޤ��� CD�ε�Ͽ�ϡ����Υԥå�Ĺ���Ȥ߹�碌�ƥȥ�å���˥ԥåȤ����äƤ��ޤ���
- �ԥåȤ�11�ӥåȰʾ��Ĺ���Ϥʤ����Ȥˤʤ�ޤ���EFM��Ĵ���ȡˡ�
- �ǡ������ɤ߽Ф��졼���ˤĤ��ƹͤ��Ƥߤޤ���
- ���Ѥ��Ƥ����ֳ��졼���ӡ���ʦ�=780nm�ˤȥԥå����å��إ�γ�������N.A. = 0.45�ˤ��顢�ӡ���Υ��ݥåȷ¡�D�ˤϰʲ��μ��ˤ�äơ�
- D = 0.89λ/N.A.����������Rec - 46��
- ������D�����ӡ��ॹ�ݥåȷ�
- ������λ�����졼����Ĺ
- ������N.A.�����졼���������֤γ�����
- 1.54um�Ȥʤ�ޤ���
- ���Υӡ���¤ϡ��ԥåȤ��礭�������礭����3�ӥå�Ĺ�ΥԥåȤ���߹���Ǥ��ޤ��礭���Ǥ���
- �����礭�ʥӡ���¤Ǻ٤��ʥԥåȿ����ɤΤ褦�ˤ��Ƽ��Ф��Ƥ��뤫�Ȥ����ȡ��ԥåȤ����ȿ���������Τ��ƿ������Ф��Ƥ��ޤ��ʱ�����ȡˡ�
- CD�������줿�ԥåȤϡ������å������4.3218MHz�ˤ�Ʊ�����ƥԥåȿ��������������������Фƥǥ��������ˤ��Ƥ��ޤ���
- ��¸���줿�ǡ�������0�פ��1�פ�Ϣ�ʤ�Ĺ��³���ȥ�����ȥ��顼�������䤹���ʤ뤿�ᡢĹ��Ʊ������³���ʤ����פȤ�����˽Ҥ٤�EFM��Ĵ������Eight to Fourteen Modulation�����ͰƤ���ޤ�����
- CD���ɤߤȤ�ϡ�CLV��Constant Linear Velocity�ˤȸƤФ����®�ٰ����������ɤߤȤ��ޤ���
- ���̤Υ���ԥ塼���ǡ����ǥ������ϡ���¤���ñ�ˤ��뤿�ᡢ�ǥ������β�ž�������ˤ���CAV��Constant Angular Velocity������������Ū�Ǥ��������ڥ�ǥ����ξ�硢����Υǡ����̤�����ʤ���Фʤ�ʤ��ط��塢CLV�����ˤʤäƤ��ޤ���
- ���äơ���¦�ȳ�¦�Ǥϲ�ž�����Ѳ���������®�٤������ݤĤ褦�ˤ��Ƥ��ޤ���
- ������ͳ�ˤ�ꡢ�ǥ�����ž���ϥԥå����åפΰ��֤ˤ�ä��Ѥ�ꡢ��600��200rpm�β��Ѳ�ž®�٤Ȥʤ�ޤ���
CD���礭���ϡ�ľ��120mm���濴��φ15mm�η꤬�����Ƥ��ơ�φ50mm��φ116mm�Υɡ��ʥå��ΰ衢�Ĥޤ�Ⱦ������33mm�ζҤ���Ͽ�ΰ�Ȥʤ�ޤ���
- CD�ϡ�Ϣ�ʤȲ������椬³��Ͽ���ѤȤ��Ƴ�ȯ���줿�Τǡ��ե��åԡ��ǥ����Τ褦�˺��ڤ�Υǡ����ΰ�������Ƥ�Ȥ���ȯ�ۤϤ���ޤ���Ǥ�����
- ���äơ�CD��ǡ����Ѥ˻Ȥ����Ȥ���ȡ����ڤ�˥ǡ������Ǽ�Ǥ��ʤ��Τǡ���ɮ�ǰ쵤�˵�Ͽ����Ȥ�����ˡ��Ȥ餶������ޤ���Ǥ�����
- Ʊ���������ǥ������Ǥ⡢MO�ϡ��ե��åԡ���ϡ��ɥǥ������γ�ǰ������Ѥ��Ǥ��ޤ��Τǡ���Ͽ�ΰ�ϥ�������ʬ����Ƥ���Ǥ�դΥǡ�����¸�Ⱦõ��ǽ�Ǥ��ʱ����ȡˡ�
- �� ��
- ����CD��MD��MiniDisc����2022.04.10�ɵ���
- CD �����̤ϡ�75ʬ��650��700MB�Ǥ���
- MD��Ʊ�����֤Υ����ǥ���Ͽ�����Ǥ��ޤ���
- â�����ǡ������̤ϡ�CD�λ������̤�1/5��140MB�Ǥ���
- MD = MiniDisc��Disc�ϱѹ�ɽ�����̾��Disk�Ǥ��뤬�����ˡ���Disc����Ͽ��ɸ�Ȥ����ˤϡ�1992ǯ�˥��ˡ��ˤ�äƳ�ȯ����ޤ�����
- MiniDisc�ϡ�CD�Υ��������ꥳ��ѥ��Ȥˤ���Ͽ������������ñ�ˤǤ��빽¤�Ǥ�����
- ��������MD�ε�Ͽ������CD�ε�Ͽ�����Ȥϰ㤤��MO��Ʊ����������������Ѥ��Ƥ��ޤ���
- MD��Mini Disc�ˤϡ�ľ��2.5�������φ64mm�ˡ�����1.2mm�θ��ǥ������ǡ������72mmH x 68mmW x t5mm�Υ����ȥ�å��˼�Ǽ���ƻȤäƤ��ޤ���
MD�Υ�����ɤϡ�CD�ȤۤȤ���Ѥ�餺��44.1kHz��16bit�����ƥ쥪�ե����ޥåȤˤʤäƤ��ޤ���
- ������MD�Υ���ԥ塼��Ū���̤�140MB�Ǥ��ꡢ�����CD����1/5�����̤ˤ����������ޤ���
- ����ϡ�MD��ATRAC��Adaptive Transform Accoustic Coding�ˤȤ�����ĵհ��̵��Ѥ�������ơ�CD�Υǥ�����ǡ�������1/5�˰��̤��Ƥ��뤿��Ǥ���
- ���ʤߤ�CD�ϥǡ����̤��Ƥ��ޤ����ʵդ��Ĥ�ޤ��Ƥ��뤯�餤�Ǥ�����
- ATRAC �ϰ��Υޥ������̡ʥǡ������̡ˤǡ��㤨�С��礭�ʲ��Ⱦ����ʲ����ŤʤäƤ���ȡ������ʲ����礭�ʲ��ˤ����ä���Ƥ��ޤ����Ȥ����Ѥ��ƥޥ�����Ԥ��ޤ���
- ��˹ⲻ���㲻����ʬ�ǥޥ�����Ԥ���1/5�ΰ��̤�ԤäƤ��ޤ���
- ����ä�İ���������ǤϤ狼��ʤ�MD�β��⡢�����ˤ褯İ���Ƥߤ�Ȥ�䲻��������Ƥ��뤳�Ȥˤʤ�ޤ���
- MD�ϡ�CD�ۤɤ���ڤϤߤƤޤ���
- CD���ڥ������ԡ����ƻȤ����ޥ��奢�����Ȥ������֤Ť��ǡ��������٤�ȯŸ��뤲�ޤ�������MP3�γ�ȯ��ȾƳ�Υ���νи��ˤ�äơ�2001ǯ��iPod�ʤɤη��Ӳ��ں������֤���Ƭ�ˤ�äơˡ������ˤ��ΰ��֤��ĤĤ���ޤ���
- ��MD�ϡ�2011ǯ���ä�������λ���ޤ�������2020.05.10�ɵ��ˡ�2022.04.10�ɵ�����
- �� ��
- �����ӥǥ�CD��Video CD��View CD��Compact Disc digital video��
�ӥǥ�CD�ϡ����費���ѤǤ��ä�CD��ӥǥ��������ΤȤ��ƻȤ�����˵��ʲ����줿��ΤǤ���
- ����ϡ�1993ǯ�˥��ˡ����ե���åץ������������ܥӥ������ˤ�äƵ��ʲ�����ޤ�����
- ��������DVD���礭��������������ˡ��ӥǥ�CD��¸�ߤ�˺����줿��Τˤʤ�ޤ�����
- ���ε��ʤ��Ǥ����Τϡ�CD��Ȥä�ư�����¸�������Ȥ���������Τ��Ȥʤ��餢�ä����Ȥ��Ƥ���Ƥ��ޤ���
- �ӥǥ�CD���Ф�1993ǯ�����̤ä�6ǯ����1887ǯ�ϡ�CD�ӥǥ���CDV��CD Video�ˤȤ������ʤ���ȯ����Ƥ��ޤ���
- CD�ӥǥ��ϡ����ʥ����α���Ͽ��ʥ����ǥ������ϥǥ�����ˤǤ�����
- ���������ӥǥ�CD�ϡ������ǥ�����Ǥ�����
- ���äơ��ӥǥ�CD�ϡ�������äȤ���ڤ��Ƥ���VHS�ӥǥ��ơ��ױ����ȳӤ٤Ʋ�����������ʤ������⤢��ޤ���Ǥ�����
- ��������������352x240���ǤȾ��������ᡢ�������ˤϲ��Ǥ���֤����ܤˤ����720x480���ǡ������Ȥ��Ƥ��ޤ�����
- CD�ϱ�������¸����ˤϥǡ������̤�������ž���졼�Ȥ��㤤�Τǡ��ʲ��˼�����ǽ�����٤Ǥ��ä��Τ����Τ�ޤ���
- �ڥӥǥ�CD�ε��ʡ�
- ���������١���352 x 240���ǡ�NTSC��4��3�Ȥϼ㴳�ۤʤ��
- ���������ΰ��̡���MPEG-1
- ��������®�١���29.97�ե졼��/��
- �����ǡ�����1150kbps
- �����ӥåȥ졼�ȡ��������ǥ���CD��Ʊ��
- ������Ͽ���֡���74ʬ
- ������Ͽ���Ρ���CD-ROM
- �ӥǥ�CD�ϡ��²�����¤�Ǥ��뤳�Ȥ��顢DVD����ڤ���ޤǤδ֡���������ʹ�����ե���ԥ�ˤʤɤǻȤ��ޤ�����
- �������ʤ��顢�ӥǥ�CD�ϡ��̾�Υѥ������CD�ɥ饤�֤ǤϺ����Ǥ��ʤ���Τ�¿���ä��褦�Ǥ���
- �ӥǥ�CD��¸�ߤ����Τ�ʤ��ͤ⤤��Ȼפ��ޤ���
- ��
- �� �� ��
- ��DVD�ۡ�Digital Versatile Disc����ȯ����ϡ�Digital Video Disc������2009.04.15�ɵ���
- DVD�ϡ�CD��Ʊ�������Ƥ��ʤ������̩�ٲ���ޤä����ǥ�������1992ǯ�˳�ȯ����ޤ�����
- CD�γ�ȯ����10ǯ��Τ��ȤǤ�����
- DVD�ϡ��ϥꥦ�åɤ��濴�Ȥ����ƹ�αDz�ȳ����ֱDz��¤α���������Ǽ�ڤ˳ڤ���Ǥ�餤�����פȡ���Ǥ��濴�Ȥ������ܤΥ���˵��ѳ�ȯ����������Ƥ����Τ��Ϥޤ�Ǥ���
- ���ǥ��������֤ε��Ѥ����ܤΤ��ȷݤǤ��ä����ᡢ���ܤΥ�������𤬤��ä��褦�Ǥ���
- DVD�δ��ܻ��ͤǤ������̰��ؤ�����133ʬ�ֺ����Ǥ���ǽ�Ϥϡ��ϥꥦ�åɤ���ʸ�Ǥ�����
- �Dz�ϤۤȤ�ɤ�100ʬ�����Ĺ���Ǥ��뤿�ᡢ���̰��ؤ˼���뤳�Ȥ������ޤ�����
- DVD�γ�ȯ�⡢CD��ȯ��Ʊ�͡�����ԥ塼���Υǡ�����¸�Ȥ�������Dz��ѤΥ�ǥ�����VHS�ơ��פθ�Ѿ��ʡˤ���Ū�˳�ȯ���ʤߤޤ����� ���ڤȤ����Dz�Ȥ�������ǥ������פϥ���ԥ塼�����յ�����������ʤ������Ϥ뤫�˹⤤���Ȥ��γ�ȯ����ˤ϶����Ƥ���Ƥ��ޤ���
- ��
- ����CD��DVD�ΰ㤤
- DVD�ϡ�CD�ε��Ѥ���Ѥ�������̩�٤ǥǡ������̤ι⤤�ǥ��������֤Ǥ���
- CD�ȥǥ�������ˡ������Ʊ���ˤ��ʤ��顢�ɤΤ褦�˹�̩�ٵ�Ͽ��ã�������ΤǤ��礦��
- �Ǥ��礭�ʵ��ѳ��ϡ������ʥ졼���ˤ�����Ĺ��û����Τ��Ѥ������ȤǤ���
- CD����780nm���ֳ�ȾƳ�Υ졼����ȤäƤ����Τ��Ф���DVD�Ǥ�650nm���ֿ�ȾƳ�Υ졼����Ȥ��ޤ�����
- �ޤ����Ѥ�����N.A.0.45����N.A.0.6���礭��������Ĺ�Ȥη�礤�ǥӡ��ॹ�ݥåȤ�1.5um����0.96um�Ⱦ��������뤳�Ȥ��������ޤ�����
- �ӡ�����꾮�����ʤ���ळ�Ȥ��Ǥ���褦�ˤʤä��Τǡ��ǥ������̤˵�Ͽ����ԥåȤ⾮�������뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
- ���Τ���ԥåȤκǾ�Ĺ����0.87um����0.4um�ޤǾ��������뤳�Ȥ��Ǥ����ȥ�å��ԥå���1.6um����0.74um��Ⱦʬ�ʲ��˶���뤳�Ȥ���ǽ�Ȥʤ�ޤ�����
- �������뤳�Ȥˤ�äơ�Ʊ��12cm�¤Υǥ�������������4.7GB��CD����7�ܡˤΥǡ������̤���ݤ��뤳�Ȥ��Ǥ���褦�ˤʤ�ޤ�����
- DVD�ϡ��ޤ������餫�鵭Ͽ�̤�2�̻����߷פˤʤäƤ����Τǡ�2�ص�Ͽ�Ǥ�8.54GB�Υǡ������̤��Ĥ��Ȥ��Ǥ��ޤ�����
- �ڰ��̵��ѡ�
- DVD�˵�Ͽ����ư��ˤϡ�MPEG-2�ȸƤФ�밵�̵��Ѥ��Ѥ����Ƥ��ޤ���
- ���ڤ�CDϿ���Ǥϰ��̤�Ȥ�ʤ��ä��Τˡ��������˱����ǤϤ����⤤�������̵��Ѥ�Ȥ�ʤ���12cm�Υǥ������˱Dz褬���ޤ�ޤ���Ǥ�����
- DVD�α����ϡ�720���� x 480���ǡ�30�ե졼��/�ä����ܤȤʤäƤ��ޤ���
- ����ư���133ʬ��Ͽ����Ȥ���ȡ�ñ����ǡ�
- 720���� x 480���� x 3�Х���/���� x 30�ե졼��/�� x 60��/ʬ x 133ʬ = 248.2 GB
- 248.2GB�����̤�ɬ�פȤʤ�ޤ���
- DVD��4.7GB�����̤ʤΤǡ�ñ�����1/53�˰��̤�ɬ�פ�����ޤ���
- ���ΰ��̤Τ����MPEG-2�����Ѥ���ޤ�����
- MPEG�ϡ�Motion Picture Expert Group��ά�ǡ��Dz�ʤɤ�ư�����ΰ��̤�Ƥ���뤿��ƹ������Ȥ���ä��Ѱ���Ǥ���
- MPEG�ϡ�1993ǯ��MPEG1�Ǻǽ�����꤬�����ʤ��ޤ�����
- �ǡ����ΰ���Ψ����1/30�Ǥ�����
- ���ε��Ѥϡ����顢���饪��CD�Ǽ��Ѳ�����ޤ�����
- �Dz�ʤɤ����ӥǥ�CD�Ǥϡ�MPEG-1����Ѥ��ƺ���74ʬ�֤μ�Ͽ���ʤäƤ��ޤ�����
- ��������MPEG-1�����Ǥβ����Ϥϡ�VHS�ӥǥ��¤Ǥ��ꡢ�ȤƤ⽽ʬ�ʲ���Ȥϸ����ޤ���Ǥ�����
- �����ǡ������Ϥ�720x480�������ٳ��ݤ��뤿���MPEG-2�ε��ʤ����졢1995ǯ�ƤˤޤȤ���ޤ�����
- MPEG-2�ϡ��ϥꥦ�åɱDz�ʤɤ�DVD���ʤˤʤ��ƤϤʤ�̱����ե����ޥåȤȤʤ�ޤ�����
- ���������ؼ���
- �������ؼ���DVD�ϡ�ĥ���碌��ǥ�������ξ���˥ԥåȤ��äƤ���ޤ���
- Ž���碌��2��Υǥ������ΰ����ˤϽ����̤ꥢ��ߤ�����դ����⤦����ˤϸ�������Ʃ�����̤��ʤɤ������Ĥ��Ƥ����ޤ���
- ��������ԥåȤΤ���¦�˸����������ɤ��Ԥä����Ž���碌�ޤ���
- �ǡ������ɤ߽Ф��ݤˡ���������Ʃ�����̤�ȾƩ���ؤˤĤ��Ƥϥ졼���θ��ξ������˹�碌��ȿ���Ф��ޤ���
- ���β����ء�Ž���碌���⤦����Υǥ������ˤ˵�Ͽ���줿�ǡ������ɤߤȤ�ˤϡ��졼�����Υ���֤���̯�ˤ��餷�ޤ���
- �졼�����ϡ�ȾƩ������̤�ȴ���Ƥ⤦����Υǥ������Υ�������ȿ�ͤ��Ƥ���Ф���褦�ˤʤäƤ��ޤ���
- �ڻ��͡�
- ����ľ�¡���12cm
- ������������0.6mm���Υץ饹���å���2��ĥ���碌�ʸ�����1.2mm��
- �����ȥ�å��ԥå�����0.74um��CD�ϡ�1.6um�� �����Ǿ��ԥå�Ĺ��0.4um��CD�ϡ�0.87um��
- �����ɤ��졼������λ=650nm�ֿ�ȾƳ�Υ졼����CD�ϡ�780nm���ֳ��졼����
- ������ʪ�����������N.A. = 0.6��CD�ϡ�N.A. = 0.45��
- �����ǥ�������ž������600 rpm �� 1,400 rpm
- ������®�١���3.49m/s
- �����������̡���4.7GB��17GB��DVD-5��DVD-9��DVD-10��DVD-17��
- ����������������DVD-5�����̺����������أ��ء�4.7GB
- ����������������DVD-9�����̺�����������2�ء�8.5GB
- ����������������DVD-10��ξ�̺�����������1�ء�9.4GB
- ����������������DVD-17��ξ�̺�����������2�ء�17GB
- ������Ͽ��������DVD-R���饤�ȥ�ʰ��٤������ߡ�����3.8GB��ξ��7.6GB
- ����������������DVD-RAM�������С��饤�ȡ����Ѳ������ˡ�����2.6GB��ξ��5.2GB
- ������ʿ�����ϡ�500�ܡ�S-VHS400�ܡ�LD400�ܡ�
- �����ǡ������ɤ߽Ф�����CD-ROM��10�ܡ�4��®���ܰʾ��
- ����CD�Ȥθߴ�����ͭ���CD�ϲ��ڤ�60-70ʬ���դǤ�����Ū�Ǻ��줿��
- ��
- DVD�ե�����बǧ�ꤹ�������
- DVD-R��DVD-RAM��DVD-RW�����������°���롣
- DVD+RW���饤����ǧ�ꤹ�������
- DVD+R��DVD+RW���������°���롣
- ����Ĥ�DVD�����ȿ���
- ������DVD�ˤϡ��ʲ���2��ή�줬����ޤ�����
- ����DVD-RAM��侩�����DVD�ե������ץ��롼��
- ����DVD+RW��䤹��DVD+RW���饤���ץ��롼��
- DVD��ǥ�����ȡ����Τ褦�ʥ�����������Ƥ��ޤ��� ����餬��Ĥ����Τ��������Ǥ���
- ����Ū�ˡ��ǽ��DVD���ʤ�1995ǯ�ˡ�DVD����������٤Ȥ������Τ��Ǥ��ơ�1997ǯ�ˡ�DVD�ե������٤˰����Ѥ���ޤ�
- ��DVD+RW���饤���٤ϡ�4ǯ���2001ǯ�ˤǤ��ޤ���
- ����ξ�ԤϤ�¿ʬ��ϳ�줺�������褤�η�̡����Τ褦�ʿ��Ȥʤ�ޤ�����DVD�ϡ���Ȥ�Ȥϡ�CD����ȯ���줿�塢���������ǥ������ˤ���̩�ٵ�Ͽ���Τ���ȯ����ޤ��� 1990ǯ����ϡ����ˡ��ȥե���åץ��γ�ȯ����MMCD��MultiMedia Compact Disc�ˤȡ���ǡ��������ʡ����ѥʥ��˥å��ʤɤ��ʤ�Ƥ���SD��Super Density Disc�ˤ���Ĥ�ή�줬����ޤ�����SD�ϡ��ե�å�������SD��������̾����ͳ��Ȥ�ʤ�ޤ���������2020.03.24�ɵ�������ή����ĤˤޤȤ��ư����IBM�ˤ�äƤʤ���ơ����줬��DVD����������٤Ȥ������ˤʤ�ޤ����� �����DVD�ȳ��ϰ��ܲ��Ǥ���Ȼפ��ޤ�������DVD-RAM�ε��ʤ��Ф���MMCD�������ƤƤ������ˡ��ȥե���åץ����۵Ĥ���ʪ�̤�ˤʤꡢ2001ǯ�ˡ�DVD+RW���饤���٤���Ω����ޤ�����
- ����DVD�ե�������1997ǯ��Ω�˻��ô��
- *��� ��*�ѥʥ��˥å��ʾ����ˡ�*��Ω����� ��*���㡼�� *IBM
- *Intel ��*�ޥ��������ե� ��* LG ��* Walt Disney Pictures and Television
- * Warner Bros. Entertainment Inc.
- ����DVD+RW���饤����2001ǯ��Ω�˻��ô��
- *���ˡ� ��*�ե���åץ� ��*�ǥ� ��*�ҥ塼��åȥѥå�����
- *��ɩ���إ�ǥ��� ��*�ꥳ�� *�ȥॽ��
- ��˽Ҥ٤�DVD����Ĥ��礭��ή��ϡ�2000ǯ����2008ǯ�ޤ�³�����褬�Ԥ��ޤ�����
- 2�ĤΥ��롼�פ����DVD-R��DVD-RAM��DVD+R��DVD+RW��DVD-Video�ʤɤ�10����ۤɤ�DVD�ǥ�������������˽в��ޤ�����
- ����ˡ�����˲ä��ơ��ϥ��ӥ�����б���HD DVD�ȥ֥롼�쥤�ǥ�������Blu-ray Dics�ˤ�ή�줬�Ǥ��ޤ�����
- �ϥ��ӥ�����б�DVD�˴ؤ��Ƥϡ�2008ǯ��Blu-ray�˽���ޤ�����
- 2008ǯ�ˤʤ����ĤΥ��롼�פζ���������夤�ơ�DVD�ե�����൬�ʡ�DVD-R��DVD-RAM�ˤΥǥ�����������������褦�ˤʤ�ޤ�����
- ��������������DVD���֤Ǥϡ��ۤȤ�ɤμ����DVD�ǥ������ʤ�������Blu-ray���̡ˤ��ɤ߽Ф����Ȥ��Ǥ���Τǡ��ä��礭������ˤϤʤäƤ��ޤ���
- ������������դ����б������ǥ�������Ȥ�ɬ�פ�����ޤ���
- �����������ߤˤ����Ƥ⡢ξ����DVD���Ȥ������֤���¿���в�äƤ���Τǡ�����ۤɿ��м��ˤʤ�ʤ��Ƥ��ɤ��褦�Ǥ���
- ��λ��ô�ȤĤȡ�DELL��HP�ʤɳ����PC�����DVD+RW���롼�סʥ��ˡ���Ƴ�ˤ�뿷�������롼�סˤ�°������Ǥ�ѥʥ��˥å��ʤ����ܤΥ���ϡ�DVD�ե������ʺǽ�Υ��롼�סˤ�°���Ƥ���褦�Ǥ�����
- ���������鸫��ȡ����Ū���طʤ���DVD-R/-RW������¿���Ȥ��Ƥ���褦�Ǥ��� ���ƤǤϡ�DVD+R/+RW�������褯�Ȥ��Ƥ����ʹ���ޤ���
- 2009ǯ4����Ѥ����äƽ��ո��˽Фơ����ǥ���������ȥ��ȥ���ˬ��ޤ�����
- ������DVD��ǥ������֤��Ƥ��륳���ʡ��˹Ԥäơ��ɤ�ʼ���Υ֥�ǥ��������֤��Ƥ���Τ����Ƥߤޤ�����
- �ä������Ȥˡ�DVD-R��Ϥ�Ȥ���DVD�ե������ο�ʤ���ǥ�����������Ū���������Ѥ����Ƥ��ޤ�����
- DVD+RW�ǥ�������õ���Τ�5ʬ����10ʬ�ۤɤ����ä��Ǥ��礦����
- ����ۤɡ��ɤ�ê�Ƥ��-�סʥ��å���ˤΤĤ���DVD�ǥ����������֤��Ƥʤ��ä��ΤǤ���
- DVD+RW�ǥ������ϡ��ǥ������������Ѥ�5��������ʤ��褦��ê�ˤҤä�����֤���Ƥ��ޤ�����
- ¾��ê�Ƥ⡢�ޤ���ϩ�ˤ����줿���Ф��Υ若���ʡ��Ƥ⡢���٤�DVD-R��DVD-RW�Ǥ�����
- ���ˡ��Ǥ����⡢DVD-R�ǥ������ҥ֥��ɤ���äƤ����Τˤϥӥå��ꤷ�ޤ�����
- 2005ǯ�����ޤǤϡ����Τ褦�ʸ��ݤ�̵���ä��Ϥ��Ǥ��� ���ʤ��Ȥ�ξ�Ԥ��ɹ����Ƥ��ޤ�����
- �ɤ����Ƥ��Τ褦�ˤʤäƤ��ޤä��Τ��褯�狼��ޤ���
- �衼���åѤǤϡ�+�פΥ����������ܤ��⤤��ʹ���ޤ���
- ���ܤǤϡ���Ź��ê����Ƚ�Ǥ���Τˡ�+�פ�5���ʤ��褦�˴����ޤ�����
- �桼�����ܤ���ߤ�ȡ�ξ�Ԥ����̤ʵ���Ūͥ�����������餫�ˤ���Ȥϻפ��������٤Ƥε��ʤ�DVD���ɤ߽Ǥ�����إԥå����åפ�Ǥ����Τǡ�������������Ƥ��봶��������ޤ�����
- ����ʤ�С�DVD�κǽ�Υ����פǤ���DVD-R��Ȥ��С��ߴ��������ֹ⤯�ơ����ʤ�²�������Ǥ���Ȥ����ͤ�������Ū�ˤʤäƤ���褦�Ǥ���
- ����ˡ������������DVD����Blu-ray���Ѥ����Ĭ�ˤ��ä��Τǡ����Ȥ��餳��ʬ��Ƕ���ʤ��Ƥ��ɤ��Ȥ��������Ƚ�Ǥ⤢��褦�˴����ޤ�����
- 2009ǯ6��˺���Ʊ������Ź��ˬ��ޤ�����
- DVD�����ʤ�2����δ֤������ؤ����ʤ��졢1/3�����Ѥ�Blu-ray Disc���Ѥ�äƤ��ޤ�����
- �����ˤϡ���Ϥ䡢��+�פΤĤ���DVD�֥�ǥ������Ϥʤ�����-�פΤߤȤʤäƤ��ޤ�������2009.06.27�ɵ���
- ��Blu-ray Disc������2007.12.09�ˡ�2009.08.31�ɵ���
- Blu-ray Disc��BD���֥롼�쥤�ˤϡ�DVD��5�ܰʾ�Υǡ������̡�1��25GB��2��50GB�ˤ����ľ��12cm�������Υǥ������Ǥ���
- ������ư��ʥϥ��ӥ����ƥ�ӡ�������Ρ���¸�������ѤȤ���1999ǯ7��˥��ˡ��ȥե���åץ��dz�ȯ����ޤ�����
- 2ǯȾ���2002ǯ2��ˡ������ʸ��ѥʥ��˥å��ˡ��ѥ����˥�����Ω��LG�Żҡ����ॹ���㡼�ס��ȥॽ���RCA�ˤ�7�Ҥ��ä�ꡢBD���ʤ�����夬��ޤ�����
- Blu-ray Disc�ϡ�������DVD�Ȥ�ƤФ졢�Ͼ��ȥǥ����������ȥե�ϥ��ӥ����ǥ����������μ��Ѥ�ȼ����������Ѥ�������¸��ǥ����Ȥ������ܤ���ޤ�����
- Blu-ray Disc�Ǥϡ��Ͼ�ǥ�����������1440×1080i��16.8Mbps�ˤ�3�������١�BS�ǥ�����������1920×1080i��24Mbps�ˤ�2�������٤Υϥ��ӥ����Ͽ�褬�Ǥ���褦�ˤʤ�ޤ�����
- �إ֥롼�쥤�ǥ������αѸ�ɽ���ϡ�Blue-ray Disc �ǤϤʤ���Blu-ray Disc�Ǥ����ĤΡ�Blue�פΤޤȤäƤ��ޤ�����Blue-ray�פȤ���Ȱ���̾��˶�ʤäƸ�ͭ̾��Ȥ��Ƥ�ǧ�Τ�������ɸ�Ȥ��Ƹ�ǧ����ʤ������줬���ä����ᤳ��ɽ���Ȥ��������Ǥ�����
- ����ɽ������Web��ۣ��Ǥ��ä����Ȥ�T.I.���餴��Ŧ������ޤ����������˽����������ޤ���T.I.����ɤ��⤢�꤬�Ȥ��������ޤ�������2009.08.31��
- ���ε��ʤ����ʤ��Ϥ�����䤵�줿�Τ�2003ǯ�ǡ����ˡ���BD��Blu-ray Disc�˥쥳������BDZ-S77�פȤ�����ΤǤ���
- ��BDZ-S77�λ��͡�
- ����Ͽ�⡼�ɡ���1080i��720p �ˤ���2���֡�24M bps max.��
- �������������������Τۤ�480p��480i�����ʥ���Ͽ�衣
- ���ǥ����뿮�����ϡ����ǥ�����BS����ü�ҡ�IEEE1394��S200 = iLink��
- �����ʥ����������ϡ���S���� x2������ݥ��å�x2
- ���������ϡ����ǥ�����BS����ü�ҡ�D4 x1��S���� ��2������ݥ��å� x2
- ����ˡ����430W x 398D x 135H
- �����̡���14kg ���������ϡ���65W
- �����ʡ���450,000��
- �������ȥ�å��ǥ�������������1��23GB��3,500�ߡ�
- 3ǯ���2006ǯ�ˤϡ����ˡ��Υ����ൡPS3��PlayStation3������59,800�ߡˤ�BD��ɸ���������졢�֥롼�쥤�ǥ������ˤ�륲���ॽ�եȤ����䤬���Ϥ���ޤ�����
- ����ǯ����BD������Ū������褦�ˤʤä������Ǥ���
- ����ޤǤϥϥ��ӥ��������Υ����������������ڤ��Ƥ��餺��������DVD����٤Ƴ�ⴶ�����ä����ᡢ����ۤ���ڤ˲�®���Ĥ��Ƥ��ޤ���Ǥ�����
- 2006ǯ�ϡ�������DVD�θ�ǯ�Ȥ������٤�ǯ���⤷��ޤ���
- �ѡ����ʥ륳��ԥ塼���ǡ�2007ǯ������BD����ܤ��Ƥ����Τϥ��ˡ��ΤߤǤ���
- PC�������֤Ǥϡ������ʸ����ѥʥ��˥å��ˤ�BD-R��Blu-ray Disc Recordable�˥ɥ饤�֤�2007ǯ7��˳�ȯ����PC���յ�����¤��������Υ⥸�塼���Ȥä���¤����Ϥ��ޤ�����
- 2009ǯ�Ǥϡ�CD/DVD�˲ä���Blu-ray���ɤ߽Ǥ�����¢/���դ����֤����뤵�졢�̾�δ��Ф�Blu-ray�ǥ��������Ȥ���褦�ˤʤ�ޤ������ʤ��θ��PC��ɸ���BD�ɥ饤�С����������뵤���ϤǤ����������ͥåȤȥ��饦�ɤε�®����ڤ⤢�ä�2017ǯ�������PC�ˤ�CD/DVD�Υɥ饤�С����������ʤ���Τ������Ƥ��ޤ�������2020.05.10�ɵ�������
- ��
- ����HD DVD����High Definition Digital Versatile Disc��
- �֥롼�쥤�ǥ�������Ʊ�ͤΥ�ǥ����ˤϡ���ǡʤ�NEC�ˤ���ȯ����HD DVD��High Definition DVD�ˤ�����ޤ�����
- HD DVD�ϥ֥롼�쥤�ǥ������Ȥۤ�Ʊ�����ƥ�������ʤǡ�ξ�رĤϼ�����DVD���Ƹ�����äƥ����������ˤ��Τ����äƤ��ޤ�����
- ���ʲ����Ƹ����褦����ϡ��ۡ���ӥǥ����֤�VHS vs �١����ζ���˻�����Τ�����ޤ�����
- ������DVD�γ�ȯ����ϡ���ǿرĤ�HD DVD����Ԥ�������ꥫ�ϥꥦ�åɤαDz��ҤΤۤȤ�ɤ���ǵ��ʤι��ʼ�DVD��ٻ����Ƥ��ޤ�����
- ���줬��2005ǯ���������꤫����Ԥ������䤷���ʤꡢHD DVD����Blu-ray�ؾ�괹����Dz��۵��Ҥ������Ф��ޤ�����
- 2007ǯ12��Υ��ꥹ�ޥ�����Ǥ�BD�رĤ˷��ۤ��夬�ꡢī����ʹ��2007ǯ12��6��ī��12�̡ˤϡ���BD�쥳�����Υ�������98%��DVD���ΤǤ�21.1%�Υ������ˡפ���ƻ���ޤ�������ǯ��2008ǯ2��19������Ǥ�������ű����������Ф���ޤ�����
- 2009ǯ���Ծ�ˤ�HD DVD�λѤϤ���ޤ���
- ����Blu-ray����ħ
- BD�� HD DVDʬ��Ǿ��������װ��Ϥʤ���ä��ΤǤ��礦����
- ���������ʸ������ͤ����ޤ�����BD�ϥǡ������̤��礭���ä����Ȥ����ˤ�������Ȼפ��ޤ���
- HD DVD��1��15GB�ˤϡ�BD��1��25GB�ˤ�6�䤷����Ͽ���̤�����ޤ���Ǥ�����
- ���줬�ϥꥦ�åɱDz�ȳ��Ǥ��ڤ����������������ȹͤ����Ƥ��ޤ���
- �ޤ���TDK����ȯ�����ϡ��ɥ����ƥ����ѡ�DURABIS�ˤ���Ѥ����֥롼�쥤�ǥ������ϡ������ȥ�å��쥹������������갷���Ȳ��ʤ�̥��Ū�ʤ�Τˤ��ޤ�����
- �ϥꥦ�åɱDz�ȳ������Ƥ�BD�ˤʤӤ������Ȥˤ�ꡢHD DVD�رĤϷ���Ū���Ƿ��������ȸ����Ƥ��ޤ���
- Blu-ray�رĤ����������������ͳ�ϡ����ˡ������ҤΥ����ൡ�ץ쥤���ơ������3��PS3�ˤ˥֥롼�쥤��ǽ����ܤ������ȤǤ�����
- �Dz�ȳ��ο�Ʃ�����褦�˥�����ʬ��ˤ�Blu-ray��Ʃ������٤���̥��Ū�ʻ��ͤȲ��ʤ�PS3�����˽Ф��ޤ�����
- ����ˤ��Blu-ray�Ǻ���륲���ॽ�եȤ������ƹԤ��ޤ�����
- ����ʬ��Ǥ���������ޤä�2008ǯ�ʹߡ�����ԥ塼��ʬ��Ǥ�֥롼�ǥ���������ܤ�����ǥ뤬��¿���Ф�褦�ˤʤ�ޤ�����
- ��Blu-ray ���͡�
- ����Ͽ���̡���25GB�ʰ��ءˡ�50GB��2�ء�
- ����������Ĺ����λ = 405nm�Ŀ�ȾƳ�Υ졼��
- ����������������DVD�ϡ�λ=650nm�ֿ�ȾƳ�Υ졼����CD�ϡ�780nm���ֳ��졼����
- ������ʪ���N.A.����0.85
- ����������������������DVD�ϡ�N.A. = 0.6��CD��N.A. = 0.45��Blu-ray�����뤤���طϤ�ȤäƤ��롣��
- �����ǡ���ž��®�١���36Mbps
- �����ǥ���������������φ120mm��CD��DVD��Ʊ����
- �����ǥ�������������1.2mm
- �����ǥ�������������φ15mm
- ������ž������800 rpm �� 2,000 rpm
- ������®�١���4.917 m/s
- ������Ͽ�������������Ѳ�
- ����������Ĵ����1-7PP
- ���������ե����ޥåȡ���MPEG-2
- ���������ե����ޥåȡ���AC3��MPEG-1
�� ��- �����ϡ��ɥ����ƥ����Ѥ��Ω����TDK��-��DURABIS
- �֥롼�쥤�ǥ���������ȯ���줿���顢�ǥ�������MO�Τ褦�˥ϡ��ɥ��С���ʤ���Ƥ��ޤ�����
- �ǥ���������ʥ٥��ǥ������ˤǰ�����褦�ˤʤä��Τϡ�TDK����ȯ�����ϡ��ɥ����ƥ����ѤΤ��������ȸ����Ƥ��ޤ���
- ���ν����ˤ�äƥ֥롼�ǥ������⥫���ȥ�å��쥹�ˤʤꡢ��갷�����ڤˤʤäƲ��ʤ�¤��Ǥ���褦�ˤʤ�ޤ�����
- �ϡ��ɥǥ����������ƥ�������DURABIS = Durability + Shield�ˤ�2002ǯ�˳�ȯ���졢DVD�ǥ������˱��Ѥ���ޤ�����
- DVD�˺��Ѥ��줿�ϡ��ɥ����ƥ��ϡ�DURABIS1�ȸƤФ���Τǡ��֥롼�쥤�Ǥ�DURABIS2���������ѤΥǥ������ˤ�DURABIS3�ȸƤФ�륫�ƥ���Υ����ƥ����ʤ���Ƥ��ޤ���
- ���Υϡ��ɥ����ƥ����Ѥϡ��������뤿�路�ǥǥ������̤�100���äƽ���Ĥ��Ƥ��ɤ߽Ф��˱ƶ����ʤ��ȸ����Ƥ����ΤǤ���
- �ޤ������ν����ϻ���ʤɤα�����Ф��Ƥ���줬�դ��ˤ����������äƤ����ꡢ���ŵ��ˤ�����Ť������ˤ����ۥ�������夬�ˤ�Ƥ����ʤ���������äƤ��ޤ���
- ���Υϡ��ɥ����ƥ����ɤΤ褦���Ǻ��Ȥäơ��ɤΤ褦�ʼ�ˡ�ǹԤ��Ƥ���Τ��ϻ伫�Ȥ褯�狼�äƤ��ޤ���
- ����Disc��-��CD/DVD/Blu-ray���ΤޤȤ�������2009.09.17���ˡ�2011.07.13�ɵ���
- CD��DVD��Blu-ray����HD DVD�ˤϡ�Ʊ����Ĺ���ǿʲ���뤲�Ƥ�����ΤǤ��� Ʊ����Ĺ���ΰ�̣����Ȥ����ϰʲ��Τ�ΤǤ���
- 1.��ľ��12cm������1.2mm�Υݥꥫ���ܥ͡��ȱ��סʥǥ������ˤ�ȤäƤ��롣
- ������Ͽ�̤䵭Ͽ��ˡ�˰㤤�Ϥ��졢������Ʊ�쵬�ʡ�
- 2.���ǡ������ɤ߽Ф�����Ͽ�˥졼����ȾƳ�Υ졼���ˤ�ȤäƤ��롣
- 3.����ȯ�μ�ư���������ǥ������ڤӱDz襳��ƥ�Ĥ�Ͽ��/Ͽ�衦�����Ǥ��ꡢ
- ��������ԥ塼����ǥ����Ȥ��ƤǤϤʤ��ä���
- 4.��Ĺ���֤ˤ錄��Ϣ�ʤȤ����ǡ������ɤ߽Ф�����ħ��
- 5.���䤨����̸ߴ�������θ����Ƥ��롣 �ĤޤꡢDVD����ȯ����Ƥ�CD���ɤ߽��Ǥ��뵡ǽ����θ���졢
- ����Blu-ray�γ�ȯ�Ǥ�DVD��CD���ɤ߽Ǥ����б����ޤ��Ƥ��롣
- 3�ԤϺ��ΤȤ�����2010ǯ�����˸ߤ����������뵤�ۤ��ʤ���
- �桼���ϡ���Ū�˱����ƺ�Ŭ�ʥǥ���������Ѥ��뤳�Ȥ��Ǥ��롣
- ��
- ����3����Υ졼������
�嵭��3�ĤΥǥ������ϡ���̩�١���®�����Ȥ����������˱����뤿��˸������夨�Ƥ��ޤ�����
- �ĤޤꡢCD�λ������Ĺ780nm���ֳ��졼����Ȥ���DVD�Ǥ�650nm���ֿ��졼�����Ѥ���Blu-ray�Ǥ�405nm�λ糰�˶ᤤ�Ŀ��졼����Ȥ��ޤ�����
- ��Ĺ��û�����뤳�Ȥˤ��ӡ��ॹ�ݥåȤ����Ǥ���Ʊ���礭���Υǥ�����������˹�̩�٤˾�������뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ�����
- CD����ȯ���줿����ϡ��ֳ�ȾƳ�Υ졼�����ǻϤ�������п����Ŀ���ȾƳ�Υ졼���Ϥޤ�����ޤ���Ǥ�����
- CD����ȯ���줿1970ǯ���Ⱦ�ϡ�ȾƳ�Υ졼���˰��ꤷ�����ʼ��Τ�Τ��ʤ��ä��Τǡ��إꥦ�।����졼���Ȥ��������졼����ȤäƤ��ޤ�����
- ���饹�Υ��塼�֤ǤǤ������Υ졼���ϡ�ȾƳ�Υ졼������٤��礭�����ʤ�2000�ܰʾ夷�ޤ�����
- �졼��������ʲ����¸�����ʤ���С����ǥ��������Τ��Բ�ǽ�ʤΤ�����Ǥ�����
- 1960ǯ������ۤ��졢1970ǯ��˲ֳ�����1990ǯ����礭��ȯŸ��ߤ�ȾƳ�Υ졼����������Ŀ��ΰ��ȾƳ�Υ졼���μ��Ѳ����ʤ���С���Ϣ�Υǥ�������ǥ����������ʤϤʤ��ä����ȤǤ��礦���졼���ι��ܻ��ȡ�http://www.anfoworld.com/lasers.html�ˡ�
- ���ǥ��������ɤ������˰��̤���Ǯ�ŵ��Ȥä��Ȥ�����ɤ��Ǥ��礦����
- �����餯CD��DVD��BD����Ѳ��Ǥ��ʤ��ä����ȤǤ��礦��
- �졼�����ʤ�������ǥ����ˤʤ��ƤϤʤ�ʤ���ΤǤ��ä�������ͳ��ʲ��˽Ҥ٤ޤ���
- 1.���ظ�����ľ�������褤���� ������-����������Ȥߤ䤹�����������ݥåȤ����䤹�����������٤��夬�롣
- 2.����̩�٤Ǥ��뤳�� ������-����Ψ�褤���طϤ��Ȥ߾夲�䤹����;ʬ�ʸ�������Ф�ʤ��Τ�S/N���褯�ʤ롣
- 3.��ñ����Ĺ�Ǥ��뤳�� ������-�����������θ�����ˤ��ࡣ�ӡ��ॹ�ݥåȤ������˶ᤤ�ͤˤ��뤳�Ȥ���ǽ��
- 4.�����̤������äƤ��뤳�� ������-�����Ĥ����䤹�����ᡢ������Ѷ�Ū�� ���Ѥ�����Ĺ��٥��Ĵ�������Ф���ǽ��
- ���������������������������������ԥåȤι⤵����Ĺ��1/4�ˤ��ơ�S/N�����夵���Ƥ��롣
- 5.���и����äƤ��뤳�� ������-���и��ߤ����Ѥ��ƿ��渡�Ф���������夵���Ƥ��롣
- ��
- ��������¥�ʹ�NA���
- �ӡ��ॹ�ݥåȤ������뤿��ι��פȤ��ơ������������N.A. = Numerical Aperture�����礭�����ޤ�����
- N.A.�ϡ�����Ū�˶�����Ǻ���1�Ȥʤ�ޤ���
- �������äơ�Blu-ray�ǻȤäƤ���NA 0.85�϶ˤ�Ƴ��������礭����ȸ����ޤ���
- �ԥå����åץ�γ�ȯ��CD/DVD/BD��ȯŸ�˴�Ϳ���ޤ�����
- ��ϡ��Ȥ߹�碌���饹����顢ñ�������̥���ץ饹���å��ˤ��⡼��ɥ�������������Ѥ����ۥ�����������ޥ�ؤȿʲ����ޤ�����
- �������ơ�N.A.0.85�Ȥ�������¤�0.47um�Υӡ��ॹ�ݥåȤ������Ǥ��ޤ�����
- ����ˡ���Ĥ���ʪ���3����θ�����CD/DVD/BD�ѡˤ��б��������ץ�����ԥå����åפ����ʲ�����ޤ�����
- �����ǥ������ε�Ͽ��
- û��Ĺȯ���졼�����������Υ���о�ˤ�ꡢ3����Υǥ������Ǥϵ�Ͽ�̰��֤��Ѥ��ޤ�����
- ���ʤ����CD�ϥǥ������ȼ��̤�����˵�Ͽ�̤����֤���Ƥ����Τˡ�DVD��Blu-ray�ˤʤ�ˤ������äƾȼͤ����̤ζᤤ���֤˵�Ͽ�̤��֤����褦�ˤʤ�ޤ�����
- �ӡ��ॹ�ݥåȤ�������ˤϳ��������礭�����ơ����ľ�����Υ��û�����f = 1.5mm��2mm�ˤ�Ȥ�ʤ���Фʤ�ʤ��Τǡ���ȥǥ�������ʪ��Ū��Υ�ϼ�����û���ʤ�ޤ��ʾ�������ȡˡ�
- CD�ε�Ͽ�̤ϡ��ǥ��������̡ʥ졼�٥��Ž�äƤʤ��̡ˤ���1.2mm�ʤۤܥ졼�٥��̡ˤˤ���ޤ���
- DVD�ϡ����餫��2�̤ε�Ͽ�Ȥ����߷��ۤ����ä��Τǡ�0.6mm���Υǥ�������Ž���碌�빽¤�ȤʤäƤ��Ƹ��ߤ��濴��2�ؤε�Ͽ�̤�����ޤ���
- 2�ؤε�Ͽ�̤ϡ��ºݤ�30um���٤Υ��ڡ����ؤ�20um���٤�ȾƩ�����ؤ�ʬΥ����Ƥ��ޤ���
- 2�ؤε�Ͽ�̤ϡ��ߥ��������Ƕ�ư���륢�����奨�����Ǿ���Ĵ����Ԥä��ɤ߽�ԤäƤ��ޤ���
- BD��Blu-ray�ˤϡ��ǥ������̤���0.075mm��0.1mm�ΰ��֤˵�Ͽ�̤�2�ػ��äƤ��ޤ���
- ���ߤǤϡ�4�ؤ�8�ؤˤ�뵭Ͽ�̤����BD����ȯ����Ƥ��ơ������ε�Ͽ�̤Ϥ��ΰ��ֶ�˵�˺���Ƥ��ޤ���
- ��οޤ���狼��褦�ˡ�BD�Ǥϥǥ������̤ζˤ�ƶᤤ���֤˥�����֤���Ƥ��ޤ���
- CD����ȯ���줿�������ǥ��������ɤ���̤ˤǤ�����ˤ�äƥǡ������ɤ��ʤ��ʤ뿴�ۤ��ʤ���ޤ�������1.2mm�θ��ߤΤ���ݥꥫ���ܥ͡��Ȥα��˵�Ͽ�̤�����Τǡ�ɽ�̤Υ����ϥܥ�����Ƥ��ޤ��礭�ʻپ�ˤϤʤ�ޤ���Ǥ�����
- �ޤ������顼������ˡ��EFM��Ĵ�����ˤˤ�äƳμ¤˥ǡ������ɤ����Τǡ����ꤷ���ǡ������ɤ�꤬�Ǥ�CD��ڤ��礭�ʹ���̤����ޤ�����
- �����ݥꥫ���ܥ͡��Ⱥ��
- CD�ǥ������γ�ȯ�ˤ����äƤϡ������Ʃ���٤ȶѼ������ȤƤ�����Ǥ��ä������Ǥ���
- �Ĥޤꡢ�ݥꥫ���ܥ͡��Ⱥ�ζѼ����ǺबCD�ΰ��ꤷ���ǡ�����¸���礭���������ΤǤ���
- �ǥ������Ǻ�������ǡ��ݥꥫ���ܥ͡����Ǻ�˹Ԥ��夯�ޤǤ˥�������ݥꥨ���ƥ����إ��饹�ʤɤ����Ƥ��ޤ�����
- �������ϥ졼���ǥ������˻Ȥ��Ƥ�������ǡ��ݥꥫ���ܥ͡��Ȥ���٤Ƶۼ������礭����ǯ�Ѳ����礭���ä����ᡢ���Υǥ������μ�̿��10ǯ�ȸ����Ƥ��ޤ�����
- �ե��åԡ��ǥ�������ӥǥ��ơ��פȰ㤤�����ǥ�������Ʃ�᷿�ε�Ͽ���ΤǤ��뤿�ᡢ�����ƥߥ��������������ʾ�����ɤ߹��ि��ˡ�����Ū���ʼ�������������ޤ���
- ������Ͽ�Ǥ�����ˤʤ�ʤ��ä�Ʃ�������ȶѼ������ȤƤ�����Ǥ�����
- ����Ʃ��/ȿ�ͤ������˷�٤����ä��ꡢ�����ʥ��ߤ�ܥ��ɡʵ�ˢ�ˡ�̮���ʶ���Ψ�����Ȥʤ����̡ˤ�����ȡ��ǡ������������ɤ��ʤ��ʤ�ޤ���
- �ޤ��������ȿ�ä����Ĥ���ꡢǮ�ȼ��١����ˤ�ä����äƤ��ʼ����礭�ʱƶ���Ϳ���ޤ���
- �ݥꥫ���ܥ͡��Ȥϡ����ʤ�������¤�������������ʼ���������CD�κ���ˤ�äȤ�դ��路����ΤǤ�����
- �ݥꥫ���ܥ͡��Ȥϡ��ʸ塢DVD��blu-ray�ˤʤäƤ��Ǻ�Ȥ��ƻȤ��Ƥ��ޤ���
��
- �����3����Υǥ������ϡ������ɬ�פ˱����ƻȤ�ʬ�����Ƥ�����ΤȻפ��ޤ���
- �ǥ������ɥ饤�֤Ϥ��Τ���ˤ��٤ƤΥǥ�������CD��DVD��Blu-ray�ˤ��ɤ߽Ǥ���褦���б����ޤ��Ƥ��ޤ���
- ȾƳ�Υ졼���Ǥϰ�Ĥ��ǻҤ�3�����ȯ�����Ǥ����Τ���ȯ���줿�ꡢ��Ĥ���ʪ���3����θ����˾������֤˽�������ԥå����åפ���ȯ����Ƥ��ޤ���
- ��
- �� �� �� ��
- ↑�˥�˥塼�С�������ʤ���硢
- ←����å����Ʋ�������
- ��
- �� �� �� ��
- ȾƳ�Τˤ�뵭Ͽ
- �ڥե�å�������Flash Memory��Flash-EEPROM������2008.05.05���ˡ�201108.15�ˡ�2020.03.13�ɵ���
- ��
�ե�å�������Flash Memory�ˤϡ�����̾�� Flash - EEPROM = Flash - Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory �ȸ����ޤ���
- ȾƳ���ǻҥ�������ROM����֤����ꡢ�ŵ�Ū�˽�����ǽ��EEPROM�Ǥ���
- 2000ǯ�����꤫���®����ڤޤ�����
- 2011ǯ�λ����Ǥϡ�32GB���̤�USB���ƥ��å������פΥ��꤬10,000�����٤�����Ǥ���褦�ˤʤ�ޤ�����
- 2020ǯ3��λ����Ǥϡ�USB3.1���ͤ�256GB���꤬10,000�ߤ�����Ǥ���UDB2.0�б���16GB���̤�600�����٤β��ʤ˲����äƤ��ޤ���
- �ե�å������Ϥޤ���HDD�ʥϡ��ɥǥ������ɥ饤�֡ˤ����äơ������̤Υ���ɥ饤�����֡�Flash SSD = Solid State Disk) ����ܤ����ѥ�����Ȥ��ƻ��Τ����褦�ˤʤ�ޤ�����
- ȾƳ�Υ���ϡ��ե�å������˸¤餺ȾƳ���ǻҤ��Ǥ������餫�鸽�ߤ˻��ޤ��䤨���ʲ���뤲�Ƥ��ꡢ�Żһ��Ȥ���ˤ�ô�äƤ����ΤǤ���
- ȾƳ�Υ��ꤽ�Τ�Τϡ��ȥ�������Ǥ���1950ǯ���������饢���ǥ�������ޤ�����
- �ȥ��������ή��ή���Ṳ̋��ݻ���³����������̤��������Ȥ�����ΤǤ���
- ��������������ˡ�Ǥϡ��ŵ���ή���ʤ��Ⱦ���Ͼä��Ƥ��ޤ��ޤ��� �ŵ���ή���ʤ��Ƥ���ä��ʤ�ȾƳ�Υ���Τ��Ȥ��Դ�ȯ�������Non-Volatile Memory�ˤȸ����ޤ��� ���������Τ���˥���ǥ�¤��������ơ��������Ų٤��ݻ������ƥ��굡ǽ��������Ƥ��ޤ���
- �������������50ǯ����ˤ���ǿ�¿������Ƥ��ޤ����������ͤ˥������̤����ʤ��ơ�����/�õ�˻��֤������äƤ��ޤ����� ����λ糰���õEPROM��Erasable Programmable Read-Only Memory) �ϡ��ǡ�����õ��Τ�30ʬ���٤����äƤ��ޤ�����
�ե�å������ϡ����������Դ�ȯ��ȾƳ�Υ���η�����ʤ�������Τǡ��������Ƥ�쵤�˾õ�Ǥ����ΤǤ�����
- �ǡ����ξõ�ե�å���Τ褦�˾õ�Ǥ���Τǥե�å�������̾�դ����ޤ�����
- ���ä�����¸���줿�ǡ����ϡ�������10ǯ���٤��ݻ�����ޤ���
- ���Υե�å�������ȯ�����Τϡ��ʳ���������縦���θ�����Ǥ��ä������ٻ�ͺ ��ʤޤ������դ�����1943ǯ�����������̾�������ˤǡ�1984ǯ6����õ��д��1980ǯ�ˤΤ��ȤǤ���
- �ե�å��������õ����äƤϡ�2004ǯ�������Ǥδ֤��ʾ٤��������Τ�ͭ̾�ʤȤ����Ǥ���2006ǯ�²�ˡ�
- �ʤ��ʾٺ����ˤʤä��Τ��Ȥ����ȡ����ǻ����1980ǯ��ˤ�ȯ�Ƥ��Ƴ�ȯ���Ƥ�����������ǤϤ������ʤ��Ф����������ǤϤ���ޤ���Ǥ�����
- ȯ�����в������դ����ΤǤϤʤ����������Ƥ��ޤ�����
- ������DRAM����Ĵ�ǡ���������ʤȤ��Ƥϲᾮɾ���ˤ���ޤ�����
- ����ɤ��줬1990ǯ��Ⱦ�Ф�����Ū�ʥҥåȤȤʤä���Ǥˤ��礭�����פ����ޤ�뤳�Ȥˤʤä����ᡢ�������в�������˵��Τ��Ȼפ��ޤ���
- ��������Ǥ�����ȯ����ᾮɾ�������Τϡ�����ԥ塼��������DRAM��DROM�˼�ä��夨��ˤϱ���®�٤��٤������̥���Ȥ���HDD���֤�������ӥ�����̤��ʤ��ä��ΤǤ���
- ���դˤ���������1994ǯ����Ǥ�������ؤ˰ܤ�줿������Ծ�ε����Ϥ��ơ����ߤΥե�å������λ��夬���褷���ΤǤ���
- ��Υץ��������Ȥ����ޤ��Ԥ��ʤ��ä���������Υ����åդξ��ʤ���̿Ϳ�����Ǥ�Υ����ƹ�Intel�ҡ�Micron�ҡ��ڹ�Samsung�Ҥ˰ܤ�ޤ�����
- �äˡ��ڹ�Samsung�Ҥˤϡ�1992ǯ��NAND���ե�å������ε��Ѥ�Ϳ���Ƥ��ޤ���
- Samsung�Ҥϡ����ε��Ѥ��Ѷ�Ū�˼����ߵ�ۤ�����DRAM��ȼ�������Υʥ�С������������˻��ޤ�����
- ��ϡ����ߡ�2011ǯ�ˡ����ܥ�˥���ƥ������쥯�ȥ��˥����Ҥκǹ����Ǥ�ԤȤ��ơ�������ȾƳ���ǻҡ�3������¤ȾƳ�Ρˤγ�ȯ�˽�������Ƥ����ޤ���
- �ե�å�����꤬�ǽ�˺��Ѥ��줿�Τ�1985ǯ�γز�ȯɽ�θ�Τ��Ȥǡ��ƹ�ե����ɥ⡼���������ؿ��������������Ѥ�ȾƳ�Υ���Ȥ��ƻȤ�줿�ȸ����Ƥ��ޤ���
- ���ʴĶ����ǻȤ��������ι⤤�Դ�ȯ����Ȥ�������Ω�ä���ΤȻפ��ޤ���
- ���Τ褦�ˡ��ե�å������ϼ�갷�����꤬�����ɤ����Ȥ��顢�ǥ������������äΥ����SD�����ɡˤȤ��ơ������ơ��ѥ��������������Ѥ�USB�б��Υ��ƥ��å�����Ȥ���¿���Ȥ���褦�ˤʤ�ޤ����� ����������CD/DVD/BD��ο����HDD������ޤǤˤʤäƤ��ޤ���
- �ե�å�����꤬��®����ڤ��Ƥ�����ͳ�ϡ�CD��640MB���̡�DVD��4.7GB���̡�BD��25GB��½���ʤ��ǡ������̤���ĥ��ꥹ�ƥ��å����²��˽в��褦�ˤʤä����Ȥȡ��������äȥǥ�����ε�®����ڤˤ��ȸ����Ƥ��ޤ���
- �ե�å������λ��Ļ������Ӥ������ǥХåƥ꤬���餺�������ƴ�ñ�˥ǡ������ɵ�������õ�Ǥ��뵡ǽ�⡢��ڤ�¥���װ��Ȥʤ�ޤ�����
- �ե�å������ϡ��屦�ޤˤޤȤ�褦�ˡ��Ȥ�������ɤ������®�˼��פФ��Ƥ��ޤ���
- �����Ǥ����ѵ��������®�٤�����⡢ʬ�������ʥ�������٥�� = wear levelling�˼�ˡ��Ƴ�����������ˡ��Ƴ���ˤ�äƼ��ѥ�٥��ã����2011ǯ�λ����Ǥϡ�HDD���¤�ǥǡ������ȥ졼����ξͺ�Ȥʤ긽�ߤ˻�äƤ��ޤ���
- 2020ǯ�����Ǥ�2TB��SSD��PC��¢�ѡ�SATA III�����ե�������30,000�����٤����䤵��Ƥ��ޤ���
- �� ��
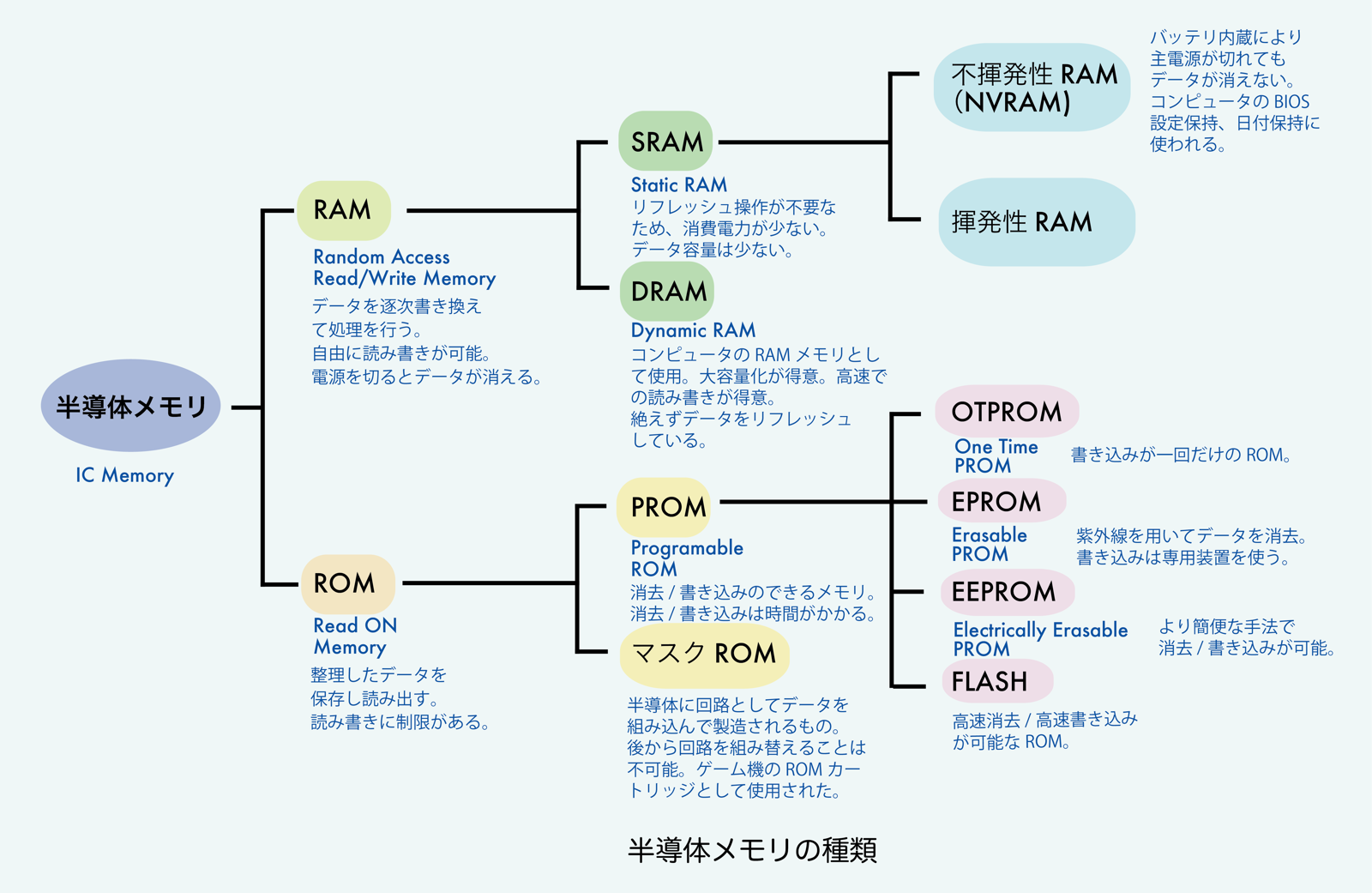
- ����ȾƳ�Υ���η���
��οޤϡ�ȾƳ�Υ���ΰ���������ΤǤ���
- ȾƳ�Τι�¤�ˤ�äƤ��Τ褦��ʬ�व��Ƥ��ޤ���
- ȾƳ�Υ���ϡ��ȥ������ȯ�����줿�����1950ǯ��ˤ��餢��ޤ�����
- ���������ǡ�����¸�ѤȤ��Ƥ�¸�߲��ͤ������ä��Τϡ���¤�塢�²��������̤Τ�Τ��Ǥ��ʤ��ä��ꡢ�Ÿ����ڤ�ȥǡ������ä��Ƥ��ޤ��Ȥ����������äƤ�������Ǥ���
- �ǡ�����¸���ΤȤ���˾�ޤ����ǽ�ϡ��Ÿ����ڤäƤ�ǡ�������¸��³�����Դ�ȯ������Ǥ�����
- �� ��
- ����ȾƳ���ǻҤ�Ȥä�����
- �����ǡ��ȥ������ȾƳ���ǻҡˤ�Ȥä�����δ��ܸ����ˤĤ��ƿ���Ƥ����ޤ���
- ���ޤϡ��ǥ������ǻҤ��Ѥ�������Ǥ���
- �ե�åס��ե��åס�Flip Flop�˲�ϩ�ȸ����ޤ������ǥ������ǻҡ�NAND�ǻҡˤ���ĻȤä�1�Ĥξ���ʥǡ����ˤ��ݻ����뵡ǽ���äƤ��ޤ���
- ���β�ϩ�ϡ��ǥ������ϩ�ǥǡ������ݻ����뵡ǽ�Ȥ��Ƥ褯�Ȥ��Ƥ��ޤ�����
- ����ԥ塼���˺��Ѥ��줿SRAM�ϡ����β�ϩ�Ǻ���Ƥ��ޤ���
- ���ޤΥե�åס��ե��åײ�ϩ�ϡ����åȥܥ���ȥꥻ�åȥܥ���ǹ�������Ƥ��뤿�ᡢR-S-FF��RS������ �ե�åס��ե��åס˲�ϩ�ȸƤФ�Ƥ��ޤ���
- �ե�åס��ե��åײ�ϩ�ϡ����Τۤ��ˤ�����फ������ޤ���
- RS�ե�åס��ե��åפǤϡ����åȥܥ�����Ȳ������Ȥ��������ݻ�����ޤ���
- ���ξ���ϡ��ꥻ�åȥܥ�����ޤ��ݻ�����³���ޤ���
- ���������ե�åס��ե��åפ�1�ӥåȤΥ���Ȥ��ƻȤä��Τ�SRAM�Ǥ���
- ����ˤϡ���˼������ȥ�����Ǿ��֤��ݻ����륿���פȡ��ǻ������˥���ǥʥ���ѥ������ǻҤ��Ȥ߹���ǡ�������ߤ���줿�Ų٤Ǿ��֤��ݻ����륿���פ�����ब����ޤ���
- �Ų٤����ŪĹ���ݻ��Ǥ����Τ�ROM�Ȥʤꡢû�����֤����ݻ��Ǥ��ʤ���Τϡ����٥�ե�å��夷�ƾ��֤��ݻ�������DRAM�Ȥʤ�ޤ���
- DRAM��SRAM�ϡ��̤ι�����DRAM��SRAM�����������ޤ���
- �� ��
- ��������ԥ塼����¿�Ѥ��줿����
- ����ԥ塼���Τ��⤽�������Ω���ϡ��ץ��������Ǽ�Ǥ������γ��ݤ�������ȤʤäƤ��ޤ�����
- ����ԥ塼�����礭��Ư���ϡ�����ʥǡ������®�ǽ������뤳�ȤǤ�����
- �ǡ�������¸��ץ�������¹Ԥ�������ˤ��������ڤʥ���ԥ塼�����ǤǤ�����
- �Υ��ޥ�ȯ�Ƥ����ե��Υ��ޥ���ԥ塼���Ǥϡ��ǡ�����ͽ�����줿�˽��äƽ������ʤ���Фʤ餺������ˤϥǡ������Ǽ�������֤�黻�����ζ�����֤��ʤ���Фʤ�ޤ���
- ����ԥ塼�������������ڤʥ���ݡ��ͥ�ȤȤ����ŻҲ�ϩ�ˤ�뵭�����֤���ȯ���졢���յ���Ȥ��ƥ����ɥѥ���������ơ��פʤɤ�ȯ�Ƥ���ޤ�����
- ȾƳ�Υ���ϡ��ȥ������ȯ���ȶ�����Ĺ��뤲�ޤ�����
- IC�ʽ��Ѳ�ϩ�ˤ�ȯ���ˤ�äƥ���⾮���ˤʤ����̤������ޤ�����
- ���ޤ˥���ԥ塼���˻Ȥ��Ƥ���ȾƳ�Υ�����ޤ���
- ȾƳ�Υ��꤬�ͤ��Ф�������ε������֤ϡ��������������Magnetic Core Memory�ˤ���ή�Ǥ�����
- ������������ϡ�1949ǯ�˥���ꥫ��ʪ���ؼ�An Wang�� Way-Dong Woo�ˤ�äƳ�ȯ���졢IBM����ԥ塼����Ƭ�ȶ��˥���ԥ塼���μ絭�����֤Ȥ� ��1960ǯ����濴��1970ǯ�Ϥ�ޤǻȤ��ޤ�����
- 1971ǯ���ƹ�ƥ�Ҥ���1k�ӥåȤ�DRAM����ȯ����ޤ���
- ����ƥ�ϡ����ߡ�2009ǯ�ˤΥѡ����ʥ륳��ԥ塼������ܤ���Ƥ���CPU�Υ������μ¤�80%����ĵ����ȤǤ��������ο���ĺ��ȾƳ�Υ���γ�ȯ��¤�ˤ���ޤ�����
- DRAM��Dynamic Random Access Memory�ˤ�SRAM��Static Random Access Memory�ˡ�ROM��Read On Memory�ˤʤɤۤȤ�ɤ�ȾƳ�Υ��꤬����ƥ�ˤ�äƳ�ȯ������¤����Ƥ��ޤ�����
- ����ƥ��ȯ������DRAM�νи��ˤ�äơ�ȾƳ�Υ���λ��夬�Ϥޤ�ޤ��� �����ơ�����ޤǼ�ή���ä����������������ष�Ƥ��ޤ��ޤ�����
- ������ͳ�ϡ�ȾƳ�Υ���λ��ĥ���ѥ��Ȥ���®����������®�١��㤤�������ϡ�����ʡ�������ʤɡ����٤Ƥ��ϤäƼ������������ο�路�Ƥ�������Ǥ���
- �����������������Magnetic Core Memory��
- ������������γ���̿���
- ��γ��Υե��饤�ȥ����ʥ�����ǿ������ǥ��깽¤���롣���٤Ƽ��Ȥ��ä���
- ���쥤������������ѡ�����ԥ塼����1964ǯ�ˤ���ܤ��줿64x64�ӥåȡ�4k�ӥåȡˤμ����������ꡣ�濴�����֤��ܤ������γ��Υե��饤�ȥ������ͤޤ롣�⥸�塼����礭���ϡ�106mm x 106mm��
- ��������Wikipedia commons
- 1950ǯ�夫��20ǯ�֤ˤ錄�äơ�����ԥ塼���μ絭�����֤Ȥ��ƻȤ��Ƥ���������������Ȥ����ΤϤɤΤ褦�ʤ�Τ��ä��ΤǤ��礦����
- ������������ˤϡ��������Ȥ��ƥɡ��ʥåľ��Υե��饤�ȥ������Ȥ��Ƥ��ޤ���
- ���Υե��饤�ȥ�����ľ��2���Υ��ʥ������������������֤���ξ��������ή�����ή�ˤ�äƥե��饤�ȥ����������ƥ������ŵ��������¸����Ȥ�����ΤǤ���
- �ե��饤�ȥ����ϡ����ߥ����٤�����γ���餤�����˾����ʤ�Τǡ�������̤����ʥ������ˤ�ƺ٤���ΤǤ�����
- �ե��饤�ȥ���1����1�ӥåȤξ���Ȥʤ�Τǡ�1k�ӥåȤΥ��������ˤ�1,000�ĤΥե��饤�ȥ�����ɬ�פǤ���
- ����˥��ʥ�������̤��Ȥ������ο�����ߺ�Ȥ�Ԥ�ʤ���Фʤ�ޤ���Ǥ�����
- �����Ϥ��٤Ƽ��Ȥ��ä������Ǥ���
- ���äơ���������ʤ�ΤǤ�����������������¤�ˤϡ������������ΰ²���ϫƯ�Ϥ����Ƥ����ƻ��β��Υ�ɤ��������������ڤ�ߤ������Ǥ���
- 1960ǯ����о줷��1k�ӥåȤμ�������������礭����50cm x 50cm x 20cm���٤Ǥ�����
- �������֤ϡ�100W�����Ϥ���Ƥ��������Ǥ���
- �緿����ԥ塼���Ǥϡ��絭�����֤Ȥ���10MB���٤�ɬ�פ��ä��Τǡ��������֤����֥��ڡ����ˤ�15m x 15m���١��Ĥޤꡢ�礭�ʲ�ļ����٤���ݤ��ʤ���Фʤ餺���ŵ�������6,000kW��2,000����ʬ�����������ˤȤ���������ʤ����Ϥ�ɬ�פȤ��ޤ�����
- 10MB�Υ�����Ư����Τˡ�����ǻȤ����Ϥ�ɬ�פ��ä��ΤǤ���
- 2009ǯ�����Υѥ�����Ƥߤ�ȡ�10MB��DRAM��ư����Τϸ�������ޤ���
- ���Х�ǻ������֥Ρ��ȥѥ�����ˤ����Ƥ�2GB���١�2,000�����١ˤ�DRAM����ܤ���Ƥ��ޤ���
- �Τδ������鸫���顢����Ͼ����ʥХåƥ�ǤȤƤĤ�ʤ��礭�ʥ����ư�����Ƥ��뤳�Ȥˤʤ�ޤ���
- 1993ǯ�˻䤬�Ŀ�Ū�˹��������ѥ�����ʥޥå���ȥå���LC III�ˤϡ�4MB��DRAM��ɸ�������Ǥ��������ޤȤ�˻Ȥ��ʤ���30,000�ߤ�8MB��DRAM���ɲä��ޤ�����
- 12MB�Υ���Ǥʤ�Ȥ�ư��������������ޤ���
- DRAM�ϡ�ǯ���ɤ���������̡�����ʲ����ʤߤޤ�����
- DRAM����ϡ�����ԥ塼������ˤ��Ѥ����ȸ��äƤ⺹���٤��ʤ��Ǥ��礦��
- ���Τ��Ȥϡ��դ˸���ȡ��絭�����֤�����ԥ塼��ȯŸ�������ȤʤäƤ������Ȥ�Ǥ碌�륨�ԥ����ɤǤ���
- ����ƥ�ϡ����Υ�������ڤ����ΤäƤ����Τǡ�ȾƳ�Υ����ȯ�����ҤȤ��ơ�1968ǯ����Ω����ޤ�����
- ��Ω�ˤϡ�����ȾƳ�Υ�����Ǥ��ä�Fairchild���ߥ�����������ҤμҰ��ʥ��С��ȡ��Υ����������㡼���ࡼ��������ɥ�塼���������֡ˤ���Ҥ��ƿ���Ҥ���Ω���ޤ�����
- ����ƥ�ϡ���Ω1ǯ���1969ǯ��64�ӥåȤ�SRAM��ȯ����1970ǯ��DRAM��1971ǯ��UV-EPROM��ȯ���Ƥ����ޤ���
- ���ȷݤ�CPU�ϡ�1971ǯ��4�ӥåȥޥ���������ܤ��褵��Υꥯ�����ȤǺ�ꡢ���줬������Ȥʤä�1974ǯ��8�ӥå�CPU 8080��ȯ���ޤ���
- ȾƳ�Υ���ϡ����θ塢���ܤ���Ǥ�����ʤ�Τ���褦�ˤʤäƤ��ä��Τǡ�����ƥ�ϼ���CPU�˰ܤ��ƹԤ����Ȥˤʤ�ޤ�����
- ��
- ����RAM��ROM
- ȾƳ�Υ���ϡ��礭��ʬ���ơ�
- RAM��Random Access Memory��
- ROM��Read On Memory��
- ����Ĥ�ʬ�����ޤ��ʾ�ޤ�ȾƳ�Υ������ɽ�ȡ���
- ξ�Ԥϡ���ȯ��������Դ�ȯ������ȸ��ʤ��Ƥ�褤�ۤ����ʤ��ۤʤ�ޤ���
- RAM���Ÿ����䤨��ɬ�פȤ����Ÿ����ʤ��ȥǡ�����̵���ʤäƤ��ޤ��ޤ���
- ROM�ϡ��Ÿ���̵���Ƥ�ǡ������ݻ����Ƥ��ޤ���
- RAM���ä˰²��������̤�DRAM�ϡ�����ԥ塼����CPU�ζ�����֤���ơ��ƥ�ݥ��ʡʰ��Ū�ʡ˥ǡ�������¸����������Τ˻Ȥ��ޤ���
- DRAM�Ϥޤ�����®�ǥǡ������ɤ߽��Ǥ���Τǹ�®�٥����ʤɤι�®�ǥǡ������Ͽ����Ͽ�����ΤȤ��ƻȤ��Ƥ��ޤ���
- �¤�����ȡ�DRAM��SRAM����٤���ǽ�����äƤ���Τ������Ǥ���
- �������ʤ��顢SRAM����DRAM���礭����ڤ��Τϡ���ˤ���ˤ���ʤ��ä������Ǥ���
- ����ʤǤ��뤳�Ȥ��������礭�ʼ��פ����ळ�Ȥ����Ͻ�ʬ�˸��ڤäƤ��ơ�DRAM�Υ���ѥ��������̲��˼���Ȥ�Ǥ��ä������Ǥ���
- ��
- ����RAM - DRAM��SRAM
- RAM�Υ��ƥ���ˤϡ�SRAM��Static Random Access Memory�ˤ�DRAM��Dynamic Random Access Memory�ˤ�2���ब����ޤ���
- SRAM�ϡ���ȾƳ���ǻҤ�Ȥä������ǾҲ𤷤��褦�ˡ�ȾƳ�Υ���κǽ�Τ�ΤǤ��� DRAM�ϡ���¤����ñ�ǰ²��ʤ�ΤȤ����о줷�ޤ�����
- ������ϩ�˥���ǥʥ���ѥ����ˤ��Ȥ߹���ǡ�����ǥ��Ų��ݻ��ˤ�äƾ������¸���Ƥ��ޤ���
- �ʲ���SRAM��DRAM�β�ϩ���ޤ���
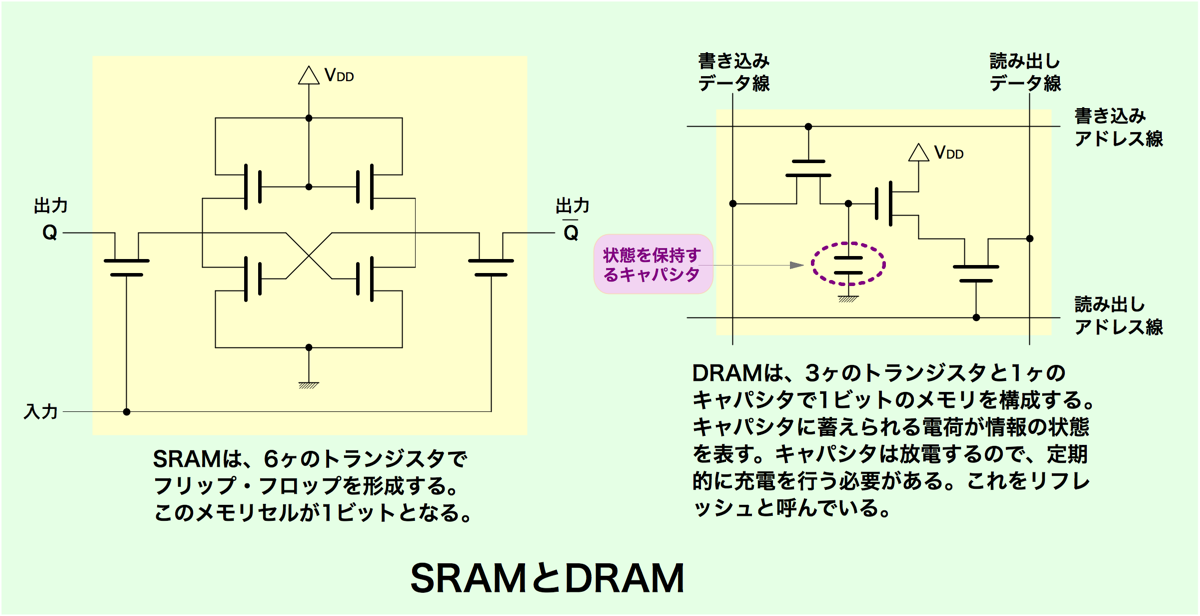
- �ޤκ��˼����Ƥ���SRAM�ϡ�6���Υȥ�����ǥե�åס��ե��åײ�ϩ���������1�ӥåȤε����ΰ����äƤ��ޤ��� SRAM�ξ��֤ϰ��ꤷ�Ƥ��ơ�����ǡ������ݻ���³���뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
- ���������Ÿ�����Ȥ��ȡ��ǡ����Ͼä��Ƥ��ޤ��ޤ���
- �����ޤα��˼�����DRAM�ϡ�3���Υȥ������1���Υ���ǥ�=����ѥ����ˤˤ�ä�1�ӥåȤε�����ϩ��������Ƥ��ޤ��� SRAM�β�ϩ����٤�ȡ��ȥ�����ο������ʤ�����ץ�Ǥ���
- ɬ��Ū�ˡ���¤�����Ȥ��ޤ����Ƥ��ơ�Ʊ�����ڡ����Ǥ���ʤ�Ф�������Υ��������Ǥ��뤳�Ȥˤʤ�ޤ���
- ��������DRAM�ϡ��ǡ������ݻ�������ǥ˥��㡼�����줿�Ų٤˰�¸���Ƥ��뤿�ᡢ���֤ȶ��˼������Ťˤ�ä��Ų٤��ʤ��ʤäƤ��ޤ��ޤ���
- ���Τ���ˡ����Ū�˥���ǥ˺ƥ��㡼����Ԥ���ե�å��夬ɬ�פȤʤ�ޤ������Υ���������ǻҤˤ�äưۤʤ�ޤ�������HZ�������Hz�Ǥ���
- DRAM��Dyamic�ʥ����ʥߥå� = ưŪ�ˤȸƤФ��Τϡ����Υ�ե�å����Ȥ�ؤ��Ƥ��ޤ��� SRAM�ϡ����κ�Ȥ��ʤ����ᡢStatic�� = ��Ū�ˤȸƤФ�Ƥޤ���
- ���ޤ�SRAM��DRAM����Ӥ��ޤ���
- SRAM���������Ϥ�����˹�®ư��Ǥ���ȿ�̡������Ȥ��⤯�����̲������Τ�����Ǥ��ޤ���
- ����������ͳ���顢DRAM�ϥ���ԥ塼���μ絭���ǻҤȤ��ƾ���ư��٤��������ŵ�����뤳�Ȥˤ��ܤ�Ĥ�äơ��²��������̤Ǥ��뤳�Ȥ�ͥ�褵��ơ�����Ф��Ƥ��ޤ�����
- �²��������̤�DRAM�ϡ��絭���ǻҤȤ��ƥ���ԥ塼����CPU�ζ�����֤���ơ��ƥ�ݥ��ʡʰ��Ū�ʡ˥ǡ�������¸��������Ԥ��Τ˻Ȥ��Ƥ��ޤ���
- DRAM�Ϥޤ�����®�ǥǡ������ɤ߽��Ǥ���Τǹ�®�٥����ʤɤι�®�ǥǡ������Ͽ����Ͽ�����ΤȤ��ƻȤ��Ƥ��ޤ���
- ���Ҥ٤��褦�ˡ�DRAM��SRAM����٤���ǽ�����äƤ��ޤ���
- �������ʤ��顢SRAM����DRAM�������礭����ڤ��Τϡ���ˤ���ˤ���ʤǤ�����
- ����ʤǤ��뤳�Ȥ��������礭�ʼ��פ����ळ�Ȥ����Ͻ�ʬ�˸��ڤäƤ��ơ�DRAM�Υ���ѥ��������̲��˼���Ȥ�ǹԤä��ΤǤ���
- DRAM�ϡ�����ԥ塼������μ��פ������γ����Ϥ��äƤ��ޤ�����
- DRAM��ȾƳ�λ��ȤΡ֥���פȸƤФ����ޤ�����
- 1980ǯ������ܤΥ����������2000ǯ�������ȴڹ�Υ�����Ծ���ʴ�����褦�ˤʤ�ޤ�����
- ����ROM����֡�-���ե�å������
- �ե�å������ϡ�����ηϿޤ��鸫��ȡ�ROM�Υ��ƥ������ξõ���ߤ���ǽ��EEPROM��Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory�ˤ���֤�����ޤ���
���衢ȾƳ�Υ�������ROM��RAM����٤ƥǡ������̤����ʤ����õ�˻��֤�����������֤��٤����Ȥ�����������äƤ��ޤ�����
- ���줬�ե�å������ˤ����Ƥϡ�����ξõ���ˤǤ��ƽ��ߤ⤽������®�����Ȥ�����ǽ�������碌�Ƥ��ޤ�����
- ����˲ä����ǡ������̤�ɤ�ɤ��礭����Τ���ȯ����Ƥ����ޤ�����
- ���פ��ե�å��������ɤθ岡��������®�������̡��²��ʤ�Τˤ��ƴ�����������ޤ���
- ȾƳ�Υ���ϡ��ȥ��������ή��ή�����Ṳ̋��ݻ���³����������̤��������Τ����ܤǤ���
- ��������������ˡ�ϡ��ŵ���ή���Ƥ����ʤ��Ⱦ��ä��Ƥ��ޤ��ޤ���
- �ŵ�����ή���ʤ��Ƥ���ä��ʤ�ȾƳ�Υ���Τ��Ȥ��Դ�ȯ�������Non-Volatile Memory�ˤȸ����ޤ���
- ����ϡ�����Τ���˥���ǥ�¤��������ơ��������Ų٤��ݻ�����������ˤ����굡ǽ�����������ΤǤ���
- ������������ϡ�50ǯ����ˤ���ǿ�¿������Ƥ��ޤ����������ͤ˥������̤����ʤ��ƽ��ߤȾõ�˻��֤��������ΤǤ�����
- �糰����Ȥä��õEPROM��Erasable Programmable Read-Only Memory) �ϡ��ǡ�����õ��Τ�30ʬ���٤����äƤ��ޤ�����
- ���줬�ե�å������ǰ�֤ˤ��ƥǡ�����õ�Ǥ���ΤǤ���
- �����ȯ��������֥ե�å���פ�̾�դ�����ͳ���褯����Ǥ��ޤ���
- �ե�å������δ��ܸ����ϡ����ޤ˼���ǡ�����Ų٤�Ĺ�����ݻ��Ǥ�����ͷ���������ʥ���ǥ����⤷���ϥ���ѥ������ˤ�MOS�ȥ�������˺�ꡢ�����������ƹ⤤�Ű�����20V�ˤ���ä����Ų٤��ݻ��������ΤǤ���
- 1�ӥåȤΥǡ����˥���ǥ�1�Ĥ��Ƥ����뤳�Ȥˤʤ�ޤ���
- �ǡ�������¸������ͷ���������ϡ��ݥꥷ�ꥳ����Ƿ������졢�����Ȥ��ŵ�Ū�������֤ȤʤäƤ��ޤ���
- ������ͷ���������˹��Ű����ơ��Żҡ�= �ۥåȥ��쥯�ȥ���ˤ��������Ų٤��ߤ��ޤ���
- �����Ű����⤤����ˡ���ͷ�����������ѵ���������ˤʤäƤ��ޤ�����
- ����NAND���ե�å�����ꡢNOR���ե�å������
�ե�å������ϡ����Ū�˸����NAND����NOR������Ĥ�ʬ����ޤ���
- NOR�Ȥ�NAND�Ȥ������դϡ��ǥ������ǻҤ�������ϩ���餭�Ƥ��ޤ���
- �ǥ������ǻҤǤϡ���AND�ס���OR�ס���NAND�ס���NOR�פʤɤ������黻��Ԥ��ǻҤ�����Ƥ��ޤ�����
- �ե�å������ˤ⡢�������������黻��ˡ�����������Ƥ��뤿�ᡢ���Τ褦��̾���Ȥʤ�ޤ�����
- �ե�å������ϡ�NAND��NOR��¾��AND�����פ�DI-NOR�����פⳫȯ���줿�аޤ�����ޤ���
- ���ߤǤϡ�NAND��NOR�����פ���ή�Ǥ��ꡢ�ޡ����å�Ū�ˤ�NAND�����פ����������Ƥ��ޤ���
- NAND���ϡ���Ǥ��濴�ˤʤäƳ�ȯ��ʤᡢNOR�����ƹ�ƥ�Ҥ���ȯ��ʤ�ޤ�����
- ξ�Ԥϡ����줾��˰�Ĺ��û�����ꡢ��ڤˤ��Τ����äƤ��ޤ����� ξ�Ԥΰ㤤���ñ�˽Ҥ٤�ȼ��Τ褦�ˤʤ�ޤ���
- NAND���ϡ���������Ĥʤ����˹�������Τǡ���礷���ɤ߽����դǤ���
- �Ĥޤꡢ�����ॢ��������Ǥ�դ˥ǡ������ɤ߽��뵡ǽ�ˤ��Ǥ������֥��å�ñ�̤Ǥ��ɤ߽����Ǥ��ޤ���
- ����������¤�彸�Ѳ����ưפʤΤǥ���ѥ��Ȥ������̲��˸����Ƥ��ޤ���
- NOR���ϡ�NAND���Ȥϵդ˥���1�Ĥ��ĥ��������Ǥ��빽¤�ȤʤäƤ��ޤ���
- ���Τ���Ǥ�դΥӥåȤ˥����������뤳�Ȥ��Ǥ������ॢ�����������դȤ��Ƥ��ޤ���
- ȿ�̡��ӥå�1�Ĥ�������ͭ���Ѥ�NAND��������礭���ʤ뤿�ᡢ�⽸�Ѳ������դǤϤ���ޤ���
- NOR���ϡ���®����ͥ��ơ�®�٤�SRAM�����˥ӥå�ñ�̤ǤΥ���������ǽ��ͥ��Ƥ��ޤ���
- NAND���ϡ����ꥹ�ƥ��å���SD�����ɤʤɤγ�������Ȥ�����ڤ���NOR���Ϸ������äʤɤξ���������������Ȥ߹������Ȥ��ƻȤ��Ƥ��ޤ���
- ��Ǥ�1988ǯ�˳�ȯ����4M�ӥåȤ�NAND���ե�å������ϡ��ǥ����륫���˻Ȥ��ޤ�����
- ��2011ǯ�ˤǤϡ����Ӳ��ں������֡�iPod��iPad�ˤ䥹�ޡ��ȥե�����ѥ��ȥǥ����륫���ε�®����ڤˤ�ꡢNAND���ե�å������μ��פ������ش�������Ƥ��ޤ���
- ����MCP��Multi-chip Package��-������⽸�Ѳ�����
�ե�å�����꤬�����ʤ�³���Ƥ������ε��ѤȤ��ơ�����ι⽸�Ѳ����Ѥ��夲���ޤ���
- ���ε��Ѥΰ�Ĥ˥��ꥳ����Ĥ��ؤˤ��Ѥ߾夲�ơ������ʥ��åפ˹⤤�����٤����������ز����Ѥ�����ޤ��ʱ����ȡˡ�
- 2004ǯ1��ˤϡ���Ǥ�9�ع�¤��ȯ���ޤ�����
- �ѥå������ϡ�11mm�ʶҡ�x 14mm��Ĺ��x 1.4mm�ʸ��ˤ��礭���ǡ�1.4mm�θ�����6�ؤΥ��åפ�3�ؤΥ��ڡ��������ؤ����Ƥ��ޤ���
- �����ϡ����Ĥθ�����70um�������ǡ����������ξ�˥�����ꤢ�����Ѳ���ޤäƤ��ޤ��� 70um����������ꥳ���ϡ��Ϥɤ���äƺ��ΤǤ��礦��
- �����ŻҸ������̿���ȡ�50um���٤κ٤�������180um�ԥå��ǥܥ�ǥ�����Ƥ���Τ��狼��ޤ���
- �磻�䡼�ܥ�ǥ��ε��Ѥ�ߥ�������������ǹԤäƤ��뤳�Ȥ�Ǥ碌�ޤ���
- �����������Ѥˤ��䤫�äơ�USB�ե�å������Ǥ�32GB�ޤǤ����̤���Ĥ�Τ����Τ����褦�ˤʤ�ޤ�����2011ǯ�����ˡ�
- �ޤ����ǥ������ѥ���Τ˻Ȥ���SD/SDHC�����ɤ�32GB����Ĥ�Τ����䤵�졢���������ʤǤ���SDXC��2009ǯ���ꡢXC = eXtended Capacity�ˤǤ�exFAT��extended File Allocation Table�ˤ���Ѥ���2TB�ʥƥ�Х��ȡˤޤǤ����̤���ݤǤ���褦�ˤʤ�ޤ�����
- ��
- ����NAND���ե�å�������¿�Ͳ����ѡ�MLC = Multi Level Cell��
NAND���ե�å������ι⽸�Ѳ����Ѥΰ�Ĥˡ�¿�Ͳ����Ѥ�����ޤ���
- �����ȾƳ�Υ���ϡ���Ĥ��ǻҤ��Ф���1�ӥåȡ��ŵ�����¸���Ƥ��뤫"1"�������Ǥʤ���"0"��2����ˤξ����������ޤ���Ǥ����������ε��ѤϤ������ͤ�4��٥�����ꤷ��2�ӥåȤξ����1�Ĥ��ǻҤ˻��������ΤǤ���
- ¿�Ͳ����Ѥˤ�ꡢ�⤤�����٤����뤳�Ȥ��Ǥ��������̲��ȥ�����¤���ʤ��㸺��¸������ޤ�����
- MLC���б�������դȤ��ơ������1�ӥåȥ��������Τ�Τ�SLC��Single Level Cell�ˤȸƤ�Ǥ��ޤ���
- MLC��SLC����٤�ȡ�MLC�Ͻ����٤��夬�ꡢñ�����Ʊ�����������ܤΥ������̤���Ĥ��Ȥ��Ǥ��ޤ���
- ȿ�̡�MLC�ϡ��ɤ߹��ߤ��ɤ߽Ф���ʣ���ˤʤ�ʬ���ɤ߽Ф�®�٤Ƚ���®�٤��٤��ʤ�ޤ���
- �ޤ����Ų٤��ߤ�����ͷ�����Ȥ���٤�������ʬ�����ߤΤǤ����������ʤ��ʤꡢSLC��100,000����Ф��ơ�MLC��1�徯�ʤ�10,000��ȸ����Ƥ��ޤ���
- ��
- �����ե�å���SSD��Solid State Drive��Solid State Disk�ˡ�����2011.08.12�ˡ�2020.03.10�ɵ���
- �ϡ��ɥǥ������ɥ饤�֡�HDD�ˤ�ȾƳ�Υ�����֤����������֤����ե�å������ˤ�볰���������֤Ǥ��ꡢ�����SSD�ȸƤ�Ǥ��ޤ���
- SSD�ϡ������ϡ��ɥǥ������ɥ饤�֤�Ʊ���٤Υǡ�����¸���̡�80GB��3TB�ˤ������ȾƳ�Υ������ħ��褫�������֤Ǥ���
- SSD�ˤϡ������ǥ������Τ褦�ʥ⡼���������إåɥ�����ʤɤβ�ư�����ʤ�����������Ϥǥ����ॢ��������®���������Ƶ�ư��®���Ȥ�����ħ����äƤ��ޤ���
- SSD�η����ϡ�����ɽ�ˤ⼨����ǡ��������ʤ��ȤǤ���
- �ޤ����ե�å������θ����塢�ǡ����ν����˹��Ű���Ȥ�����������Ǥ��륭��ѥ������ѵ���������꤬����10����λ��Ѥǥ��꤬�Ȥ��ʤ��ʤ뤳�Ȥ���Ŧ����Ƥ��ޤ���
- �����������뤿�ᡢSSD�ˤϥ���ȥ����餬��¢����Ƥ��ơ�����Υ��������ɤ߽����椷�ʤ��褦�˴������Ԥ��Ƥ��ޤ���
- SSD�ϡ��ǡ����ν��ߤ˻��֤�������ޤ���
- �����ե�å������θ����������Ǥ��ꡢ����ѥ��������ߤ���줿�Ų٤��ö������ơ����٥���˽���Ȥ���ư���ɬ�פ����뤫��Ǥ���
- ���Τ��ᡢSSD�Ǥν��ߡʤ��ɤ߽Ф��ˤϡ����ꥳ��ȥ�����ʥХåե��������������ˤˤ������Ū���ɤ߽�®�٤���Ƥ��ޤ���
- SSD�Τ⤦��Ĥη����ϡ��֥ץ��ե�פȸƤФ�븽�ݤǤ���
- �ǡ�����SSD�˽���Ȥ����ǡ����ν��ߤ����椹��ݤ˰��Ū�˥ե�����븽�ݤǤ��� ����ϡ�����κ���SSD��������SSD�˸������Τǡ����ꤪ����SSD�Ǥϥץ�ե��������浡ǽ������ȥ�����������ܤ���Ƥ��ޤ���
�ե�å���SSD���ǽ�˻��β����줿�Τϡ�2001ǯ�Τ��ȤǤ���
- ���ΥǥХ����ϡ�Adtron�ҡ��ƹ�ʽ��ե��˥å�����1985ǯ��Ω��2008ǯSMART Modular Technologies�Ҥλ����ˤ���ȯ������ǥ�S35PC�Ȥ�����ΤǤ�����
- �������ʤϡ��ʲ��λ��ͤǺ���ޤ�����
- 3.5����������ס�
- SCSI���ե��������ϡ�
- 14GB������
- �������ʤϡ�����42,000�ɥ����4,500,00�ߡˤβ��ʤǤ�����
- �������֤ϡ��̳����ĤΥѥ��ץ饤�����߹����θ��������˻Ȥ�����ԥ塼���Υǥ������ɥ饤�֤Ȥ��ƻȤ�줿�����Ǥ���
- �����ʼ����Ķ����Ǥλ��Ѥ��θ���ơ��������ι⤤SSD���ƥ�ǥ������Ȥ��ƻȤ����Ȥ�������Ǥ���
- Flash SSD�ϡ����θ�ʲ���뤲��2008ǯ�ˤ���Ǥ���512GB���̤Τ�Τ���ȯ���졢2009ǯ5�����Ǥ�PC����ܤ��������Ϥ��Ƥ��ޤ��� 2008ǯ��ȯ�䤵�줿�ե�å���SSD�ϡ��ʲ�����ǽ����ä���Τ�10���ߤ��ڤ���ʤ����䤵��Ƥ��ޤ�����
- ������������1.8����������ɥ����סʱ��̿�����ǡ�
- �����ǡ������̡���128GB
- ��������®�١���40MB/s max.
- �����ɤ߽Ф�®�١���100MB/s max.
- �������ե���������serial ATA
- 2011ǯ�λ����Ǥϡ��ե�å���SSD��256GB���̤Τ�Τ�60,000�ߤ���90,000�����٤����䤵��Ƥ��ޤ���
- SSD�ѥå������η����ϡ�HDD��Ʊ������դ�����������Ѥ��ơ�3.5�������2.5�������1.8��������������Ѱդ���Ƥ��ޤ���
- �ǡ����̿��Υ��ͥ����ϡ�SATA��Serial Advanced Technology Attachment�ˤ����Ѥ��졢�����HDD�ȸߴ������ݤĤ褦���߷פ���Ƥ��ޤ��� �ե�å���SSD���������ϡ������̲��Ȳ��ʡ�����˿������Ǥ��� ȾƳ�Υ���ϡ������ǥ���������٤�Ȥɤ����Ƥ���ˤʤ�ޤ���
- �ޤ�������ξõ����ߤ˥ۥåȥ��쥯�ȥ���Ȥ����⤤�Ű���Ȥ�����ˡ��ǡ�����¸�����������ƽ��߲���˸³�������Ȥ�������������Ƥ��ޤ���
- 2011ǯ�ˤ��äƤϡ��ʲ��˼����褦�����ʤ����β�����Ƥ��ޤ���
��
- �ե�å���SSD�Υ饤�Х�ϡ��ճ��ˤ�USB2.0��³�Υ��ꥹ�ƥ��å������פΥե�å������Ǥ���
- ���Υ����פ�32GB���١�10,000�����١ˤˤʤäư²��˻��Τ���Ƥ��ޤ���
- �������Ƥߤ�ȡ��ե�å���SSD��360GB���٤����̤��ʤ���̥�Ϥ˴����ʤ��ʤäƤ��ޤ���
- �����������̤ˤʤäƤ⡢Ʊ�����̤����HDD�β��ʤ�2011ǯ������1���ߡ�2�������٤ʤΤǡ���ڤ���ˤϤޤ��ޤ����֤������ꤽ���Ǥ���
- ����SSD�ȳƼ������ɤ߽Ф�/����®�٤����
���ޤˡ������̥�����ɤ߽Ф�®�٤Ƚ���®�٤���Ӥ��ޤ���
- �ե�å�������Ȥä���Τˤϡ�SSD��SD�����ɡ�USB���ꡢPCI Express�����ɤˤ��SSD�ʤɤ�����ޤ���
- �ե�å�������Ȥä���ǥ����ϡ��������ɤ߽Ф�®�٤�®����USB3.0���ͤ�USB������פ�70MB/s���ɤ߽Ф���Ԥ���USB-C 3.1���ͤι�®SSD�Ǥ�500MB/s���ɤ߽Ф����Ǥ��ޤ���
- ���̤�SSD�ϡ�������⥹�ԡ��ɤ�����ޤ���
- �ե�å������ǺǤ��®�ʤ�Τϡ�PCI Express���ʤˤ��ܡ��ɥ����פΤ�ΤǤ���
- ����SSD��2GB/s���ɤ߽Ф����Ǥ������ߤ�1GB/s����ǽ����äƤ��ޤ���
- ���⤽�⡡PCI Express�Ͻ����PCI���ʤ�16�ܤ�ž��®�٤��Ĥ�Τǡ�6GB/s��ǽ�Ϥ��äƤ��ޤ���
- �ե�å������ˤ����ޤǤ���ǽ�Ϥ���ޤ���SSD����ǽ��˸¤ޤǰ����Ф��뵬�ʤΤ�Τȸ����ޤ���
- ���إǥ�������CD��DVD��Blu-ray�ϡ�SSD����٤��2��ۤ��ɤ߽Ф�®�٤��٤��ʤ�ޤ���
- ���إǥ������ϡ������ܥ͡��ȱ��Ĥ��ž�����ƥ졼���������٤������줿�ԥåȤ��ɤ��Ȥ����������äƤ��뤿�ᡢSSD�Τ褦�ʹ�®�ɤ��ϤǤ��ޤ����ߤ��٤���������ʽ��ߤ�Ǥ��ޤ���
- ���إǥ������ϱDz�ʤɤ�ư��䲻�ڥե�����Τ褦�ʰ�Ϣ��Ϣ³�����ե�������ɤ߹��ߤ��ɤ߽Ф������դȤ��Ƥ��ޤ���
- �����ܥ͡������Υǥ�������100�ߤ���300�����٤Ȱ²��Ǥ��뤳�Ȥ��顢���̤����ۤ�����Ū�˻Ȥ��ޤ���
- HDD�ϡ�SSD���о줹��ޤǤϹ�®�����̤Υ�ǥ����Ȥ��ƥ���ԥ塼���μ����յ���Ȥ��Ʒ��פ��Ƥ��ޤ�����
- ���פ˱����Ʋ��ʤ�����ʤˤʤꡢ500GB��1TB��2TB�ⵤ�ڤ˹����Ǥ���褦�ˤʤ�ޤ�����
- ������������HDD�⺣��Ϥ������٤γ�������SSD�˾��äƹԤ���ΤȻפ��ޤ���
- HDD�ϡ�SSD����٤Ʋ��ʤ����̤�����̥��Ū�ʤ�ΤΡ��ɤ߽Ф�®�٤�SSD��Ⱦʬ����1/4���٤Ȥʤꡢ�����ƥ��Ω���夲�����ϡ��ɥǥ�������Ȥä��礭�ʥ��ץꥱ������եȤ�Ω���夲�����2�ܤ���4�ܤ������äƤ��ޤ��ޤ���
- SSD�β��ʤ������äƤ���С����Ϥ������ˤ����ħ���褫�������ӵ���˻Ȥ���褦�ˤʤ�Ǥ��礦��
- ��
- ����SD���ꥫ��������2020.03.13����
- �ե�å������μ��פ�����夲���Τϡ�SD�����ɤ��о�ȸ����ޤ��礦��
- SD�����ɤϡ��ǥ����륫����������äε�Ͽ���ΤȤ��Ƥ�������μ��פ������뤵��ޤ�����
- SD�����ɤϡ�NAND���ե�å���������Ѥ�����������ɤǤ���
- ̾����ͳ��ϡ���Ǥ����ۤ���DVD�θ��ǥ�������ή��������Super Density Disc�פ�����Ƥ��ޤ���
- ��������ǥ������οްƤ����ʤȤ����ޤ���
SD���ꥫ���ɤϡ�1999ǯ8��˾����ʸ����ѥʥ��˥å��ˡ�����ǥ������ʸ������������ǥ�����ˡ�����Ǥˤ��SD Group�ˤ�äƵ��ʲ�����ޤ�����
- SD�����ɤ����Ȥ˥���ǥ������ȥɥ��ĤΥ�����ҳ�ȯ����MMC�ʥޥ����ǥ��������ɡ�1997ǯ�ˤ�����ޤ�����
- SD�����ɤϡ�MMC�θ�ѵ���ȸ����ޤ���
- 1999ǯ�ȸ����з������ä���®����ڤ��Ƥ������ǡ�����ѥ��ȥǥ����륫������ڤ��Ƥ������Ǥ�����
- ��������ڤ˥ե�å��������礭������̤�����SD�����ɤ���®�˼���������ƹԤä��طʤ�����ޤ�����
- ���ʤߤˡ�SD�����ɤ���ȯ���줿�����˳�ȯ���줿¾�Υե�å�����ꥫ���ɤȤ��Ƥϡ��ʲ��Τ�Τ�����ޤ���
- �� �ޥ����ǥ��������ɡ�MMC�ˡ���1997ǯ���ɥ��ġ�������Ҥȥ���ǥ������Ҥγ�ȯ��
- �� ���ޡ��ȥ�ǥ�����SmartMedia�ˡ�1995ǯ����Ǥ����ǥ����륫���䲻�ڥץ졼�䡼��
- ������ѥ��ȥե�å����CF������1994ǯ������ǥ������ҡ�SD����緿��
- �� ������ƥ��å���MS�ˡ���1997ǯ�����ˡ�����ȯ��
- �� ��D�ԥ����㡼�����ɡ�xD�ˡ���2002ǯ�������ѥ����ٻΥե����ˤ�äƳ�ȯ��
- �� SIM������ :���������ä˺��ѡ�
- ��IC�����ɡ�ICC�ˡ������쥸�åȥ����ɡ��Żҥ������Ȥ߹���IC��
- ����鶥�����ʤ���٤ơ��ʤ�SD�����ɤ������������礭�ʥ�������������Ƥ��ä��Τ��ȸ����ȡ�SD�����ɤϥ饤��������²������ꤷ�����Ȥȡ�������micro�����ɤ��������Ʒ������ä˺��Ѥ������Ȥ��礭���ȸ����Ƥ��ޤ���
- SD�����ɤη����ϡ��庸�ޤ˼������褦����ˡ�ǵ��ʲ�����Ƥ��ޤ���
- �ޤˤ�SD��microSD��2006ǯȯ��ˤ�������ܤ��Ƥ��ޤ��������ʤǤϤ�����֥�������miniSD�⤢��ޤ���
- ������miniSD��2009ǯ�ʹߤε��ʤˤϺ��Ѥ���Ƥ��ޤ���
- microSD��miniSD�˼�ä����ä��Τǡ����������ޤ�����
- ɸ���SD�����ɤϡ�������PC �Υ���Ȥ��ƻȤ��Ƥ��ơ�microSD�Ϸ������ä䥫���ʥӥ�����������֤˻Ȥ��Ƥ��ޤ���
- ��ȯ���줿�����1999ǯ�ˤ�2GB���̤��ä���Τ���SD�����סˡ����̤γ��粽��ȼ�ä�32GB���̤�SD HC��2006ǯ�ˤ��Ǥ���2TB�ޤǤ�SD XC��2009ǯ�ˤ�Ф�128TB�ޤǤ�SD UC��2018ǯ�ˤ����ʲ�����ޤ�����
- SD�����ɤϡ�����ޤǤ�4��������ӳ�ĥ��Ԥä����Ȥˤʤ�ޤ���
- �ե�����ե����ޥåȤϡ������SD��FAT�ǥե����ޥåȤ��졢SDHC�Ǥ�FAT32��������SDXC��SDUC�Ǥ�exFAT�ǥե����ޥåȤ���ޤ���
- �����Υե����ޥåȤˤ�äơ�����դ�����ǡ����κ������̤���ޤ�ޤ���
- ����������̲���ȼ���ǡ����̿��ι�®����ޤ�졢�Х������ե�������6�٤��ϤäƸ�ľ����ʵ��ʥС������SD1.0��SD1.1 ��SD3.0��SD4.0��SD6.0��SD7.0�ˡ�����®�٤��夬�ꡢ12.5MB/s����985MB/s�ޤ��ʳ�Ū�˸��夷�ޤ�����
- ʪ��Ū�ˤϡ��ǡ���ž����Ԥ��ԥ�������ѹ����ʤ��졢�����ƥ����å����ԡ��ɤ�夲�ƹԤ��ޤ�����
- �ǡ���ž���Υԥ�������ѹ��ϡ�UHS-I��UHS-II��2��Ǥ���
- UHS�ϡ�Ultra High Speed��ά�Ǥ���
- UHS-II�ǥԥ���������䤷���ޤ����줾��Х������å���夲�ƺ���®�٤��ݾڤ��Ƥ��ޤ���
- ���οޤΥԥ�쥤�����Ȥ�ξ�Ԥ��ѹ����ޤ���
- �ԥ�쥤�����Ȥ�2���ढ�ꡢ����ʥΡ��ޥ��SD3.0�ǵ��ʤ��줿UHS-I�ˤΤ�Τ�1��������������ˤΤߤ�9�ԥ�Ȥʤ�ޤ���microSD�����ɤ�8�ԥ�ˡ�
- ����Τ�Ρ�SD4.0�ǵ��ʤ��줿UHS-II�ˤϡ�2�����������������������ˤȤʤäƤ��ơ����������8�ԥ��ɲä���ƥХ�����¿������®����ޤ�ޤ�������microSD�����ɤ�Ʊ���Σ��ԥ�����������ɲä���Ƥ��ޤ�����
- UHS-II�ϡ�UHS-I�ξ�̸ߴ��Ǥ���Τǡ�UHS-II���ʤ�SD�����ɤ�UHS-I�Υۥ��ȡ�PC��ǥ����륫���ʤɡˤ˻Ȥ����Ȥ��Ǥ��ޤ���
- �����USB3.0��USB2.0�δط��Ȼ��Ƥ��ޤ���
- UHS-III��SD6.0�ǵ��ʡˤϡ������Υ����å�����夵������Τ�ʪ��Ū�ʥԥ�쥤�����Ȥ�UHS-II��Ʊ���Ǥ���
- SD7.0�ʻ��͵��ʡˤǤϡ�PCI Express�Х���PCIe Gen.3�ˤ�ľ����³����SD Express�Х��ȤʤäƤ���ʤ��®�ǡ���ž������ǽ�ȤʤäƤ��ޤ���
- ��ޤ�SD�����ɤ�ɽ�̤Ǥ�����ǽ���٤���ɽ������Ƥ��ޤ���
- ����ɽ���ˤ�äƥ����ɤ���ǽ���Τ뤳�Ȥ��Ǥ����ǡ������̤�ž��®�٤��ǧ������Ū�˱�������Τ�Ȥ����Ȥ��Ǥ��ޤ���
- SD�����ɤ���ǽ������礭����ͳ�ϡ��ӥǥ������ε�Ͽ���ΤȤ��ƥˡ�������ޤä����Ȥ����ޤ���
- 2006ǯ11��ˡ��ѥʥ��˥å�����HDC-SD1�Ȥ���SD�����ɤ���ܤ����ǥ�����ϥ��ӥ����ӥǥ�����餬ȯ�䤵��Ƥ��ޤ���
- Ʊ�����ˤϻ��嵡HDC-DX1��ȯ�䤵�졢�����8cm�¤�DVD��Ͽ���Τˤ�����ΤǤ�����
- DVD�ǥ�������·�����ӥǥ��������������ä�2006ǯ����SD����������Υӥǥ�����鸵ǯ�ȸ����ޤ��礦��
- ���ԡ���ɽ���ϡ�SD�����ɤ���ǽ����ȤȤ�ˡ��ӥǥ������ε�Ͽ���Τ��ӥǥ��ơ��פ���SD�����ɤ˼�ä�������褦�ˤʤꡢ�桼���λ��ĥӥǥ������˺�Ŭ��SD�����ɤ��Ȥ���褦�˻ܤ����褦�ˤʤä���ΤȻפ��ޤ���
- ���̥�����ɽ�����顢HD�ӥǥ���4K�ӥǥ����ѻ����ܰ¤��狼�ꡢ�ӥǥ����ԡ��ɥ��饹�Ǥ�Ϣ³Ͽ��κݤΥǡ�����¸®�٤��ǧ���뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
- �㤨�С�V30ɽ���Ǥ�30MB/s�Υǡ�����¸���Ǥ��뤿��ʤ����Blu-Ray�ǥ�����4.5MB/s��6.7�ܤν���®�١ˡ�MPEG4�ʤɤΰ��̤���ư������SD�����ɤ���¸������ˡ�ư������30MB/s�ʲ��Υǡ����̤Ǥ���Х���������뤳�Ȥʤ���¸�Ǥ��ޤ���
- ���ʤߤˡ�V6����ǽ�Ǥ�4K��4096 x 3072���ǡˤλ��Ƥ���ǽ�Ǥ��ꡢV60�ʾ�Ǥ�8K��7680 x 4320���ǡˤλ��Ƥ���ǽ�Ȥʤ�ޤ���
- ��������������줿2����Υ��ԡ��ɥ��饹�ʡ�C��ʸ������˵����줿������ɽ�� = ���ԡ��ɥ��饹�ȡ���U��ʸ������˵����줿������ɽ�� = UHS���ԡ��ɥ��饹�ˤϡ��ӥǥ�����ʳ��Υǡ���ž���κݤ�®���ܰ¤�����ΤǤ���
- ��������뵡�郎UHS�б��Ǥ�����Ȥ����Ǥʤ�����®�٤��Ƥ��ޤ���
- Classɽ������륹�ԡ��ɥ��饹��4����ǡ�UHS�Υ��ԡ��ɥ��饹�ϡ����饹1�ȥ��饹3�������Ǥ���
- ������ɽ���ϺǾ��ǡ���ž��®�٤�����ΤǤ��ꡢ�ºݤϤ���ʾ����ǽ��ȯ�����ޤ���
- ���줬ɽ���Ρ��ɤ��®�١פǼ�����Ƥ��ޤ���
- ������������®�٤Ϥ��Ĥ�ã���Ǥ����ΤǤϤʤ����ˤ�äƤ�ã���Ǥ��ʤ����Ȥ⤢��Τǡ���Ĥ��ܰ¤Ȥ��ƤȤ館��٤����Ȼפ��ޤ���
- �ӥǥ������Τ��褽��Ͽ����֤ϡ�32GB���̤�SD�����ɤ�Ȥäơ�ɸ�������Standard Definition, SD��1024 x 576�ˤ���11���֡��ե�HDư���1980 x 1080�ˤ���5����10ʬ��4Kư���4096 x 3072���ǡˤ���60ʬ�Ȥʤ�ޤ���
- �����Ϥ����褽���ܰ¤Ǥ����о�ʪ�ΰ����ٹ礤�ˤ�ä��Ѥ��ޤ���
- ���δ����Ǥϡ�ư�谵�̤�1/100���٤Ȥʤ�ޤ���
- ��������ѥ��ȥե�å����CompactFlash, CF����2020.03.13����
����ѥ��ȥե�å���ϡ����������ɷ����ե������Ȥ��ε��ʤǤ���
- 1994ǯ�˥���ǥ������Ҥ���ȯ���ޤ�����
- ��Ͽ��ɸ�ʤΤǡ�¾������ϥ���ѥ��ȥե�å���Ȥ������դ��Ȥ����Ȥ��Ǥ�����CF�����ɤ�CF�ȸƤ�Ǥ��ޤ���
- �礭����PC�����ɤ�1/3�ȥ���ѥ��ȤǤ��ä����ᡢ����ѥ��ȥե�å���ȸ���̾�����Ĥ��������Ǥ���
- ���������嵭����������SD�����ɤ���٤�Ȳ������������٤��礭���ȤʤäƤ��ޤ���
- �����ɤξ������˥ǡ���ž�����Ÿ���50�ԥ�����Ƥ��ơ�����ޤǤ�68�ԥ��PC�����ɤ��ŵ�Ū�ʸߴ���⤿���Ƥ��뤿�ᡢPC�����ɤؤ��Ѵ������ץ������Ѱդ���Ƥ��ޤ�����
- ����ѥ��ȥե�å���ϡ���˥ǥ��������ե����Υ��ꥫ���ɤȤ�����ڤ�����ǽҤ٤�SD�����ɤϾ����Υ���ѥ��ȥǥ����륫���˺��Ѥ���ޤ�����
- SD�����ɤ��лϤ����ϡ�����ѥ��ȥե�å�������������̤Ǥ��Ĺ�®�ǡ���ž�����Ԥ��ޤ�����
- SD�����ɤι�®���������̲���ȼ���������������ĤĤ���Ȥϸ�����2020ǯ3������ι��ǥ��������ե�����Canon 1DX mkIII��Nikon D6�ˤˤϡ�CFexpress�����ɡ�type B�ˤ�ɸ��Ǻ��Ѥ���Ƥ��ޤ���
- ���ǥ��������ե����Ǥϡ�CFexpress�����ɤ�¾�ˡ����μ�Υ����ǻȤ��Ƥ���XQD��������ɤ���Ѥ���Ƥ��ޤ���
- ��
- �ե����ˤ�뵭Ͽ������2010.06.19�ˡ�2020.06.05�ˡ�2022.11.21�ˡ�2023.11.04�ɵ�����
- ���ε�Ͽ���� ����3 - - - 2������Ͽ�ʶ���ե�����
- ��
- ����1840ǯ�夫��180ǯ³������������ࡡ��2002.02.17�ˡ�2009.11.23�ˡ�2020.05.16�ˡ�2022.11.21�ˡ�2023.11.04�ɵ���
�Dz���35mm�ե���ࡣ�Dz�ۤǻȤ���ե����ϡ���Τ褦�ʥե����̤���������۵롢�ݴɤ���뎡�ե����̤ˤϥ����˴����줿�ե���ब���äƤ��ơ���ǻ��˱Ǽ̵��˼���դ��ƥե���������Ƥ�Ʊ�ͤʥ������Υե���ब���������Ƥ�뎡 - CCD/CMOS������Ȥä��ӥǥ�������ǥ���������������Ȥʤä�����ˤ��äơ�1900ǯ���̤ä��ե������������ϤɤΤ褦�ʰ��֤Ť��ˤ���ΤǤ��礦����
- �ե������������ϡ�140ǯ����ˡ�1879ǯ �� �ˤ����ޤ���
- �ʶ�������������Τ�Τϡ�1830ǯ���Ⱦ�����180ǯ��1839ǯ �� �ˤ���ˤ���äƤ��ޤ�����
- ���������λٻ��Τϡ��ǽ顢���饹���⤷���ϻ�Ǥ�����
- ���줬����������ե����ٻ��Τ��֤�������줿�Τϡ�1879ǯ�Υ�����֥åȡ�John Carbutt��1832 - 1905���ѹ�μ̿��ȡˤ��Ϥޤ�Ȥ���Ƥ��ޤ���
- ��������ɥե������������ˤ���Ϣ³���Ƥ�Ŭ������Τ˺��夲���Τ����ƹ�����硼�����������ȥޥ���George Eastman�� 1854 - 1932�ˤǡ�1888ǯ�Τ��ȤǤ���
- ��Ͼ��ͤˤ������ͤǡ���Kodak�סʥ����å��ˤȤ���ï�ˤǤ�ȯ���Ǥ��뾦ɸ�ʥ֥��ɡˤ��ꡢKodak�֥��ɤǥ�����ե������硹Ū������¥�ʤ��ޤ�����
- Kodak����Ĥ��礭���������������ˤ��̤��ơ������Ƥޤ�����ή�˾�ä��Dz�ȳ����̤����礭�ʥޡ����åȤΥ��˥������֤ꡢ�ե���ശ���������Ū��������������Ƥ����ޤ�����
- �Ƽ�ե����ѥå�����
- �塧��135�����ס��̾�Υե����ѥȥ�����
- ��������120�����ץ֥����ˡ�����Ƚ�������
- ��������4��5�����ȥե����
��
��
��
��
- ��
- �����ƥ�Ӥ���
- �Ҥ�ƥ�ӥ����ϥե����ζ�δ���٤�뤳����70ǯ��
- �ɥ��Ŀ�ʪ���ؼԥ֥饦���Karl Ferdinand Braun�� 1850 - 1918�ˤ��ƥ�Ӥμ����ɤθ����Ȥʤ�֥饦��ɤ�ȯ������1897ǯ��ƥ�Ӹ�ǯ���Ȥ��Ƥ��ޤ��������λ��������ϱǤ��Ф���Ƥ��ޤ���
- �ƥ�ӥ����ʻ��Ƶ��ˤ��ʤ��ä�����Ǥ���
- �ƥ�ӥ���餬�ʤ���ʤ�ˤ��Ȥ߾夬�äơ��ƥ�Ӽ¸������������Τ�1920ǯ�Ǥ���
- �ܳ�Ū�ʥƥ�ӥ���餬�Ǥ���Τϡ�1931ǯ���ƹ��ȯ���ȥե�����Philo.T.Fransworth�� 1906 - 1971�ˤ�������ǥ����������塼���ʥƥ�ӥ���黣���ɤΰ�ġˤγ�ȯ����Ǥ���
- ���θ塢�ӥ������Vidicon���ȸƤФ��ͭ̾�ʻ����ɤ���RCA�ҤΥ磻�ޡ���Paul.K.Weimer�� 1914 - 2005�ˤˤ�ä�1950ǯ�˳�ȯ����ޤ���
- ���Υ����ȥ֥饦��ɤγ�ȯ���ŻҲ�����������褦�ˤʤ�ޤ�����������ϥե�����������٤Ƶڤ֤٤��⤢��ޤ���Ǥ�����
- �ƥ�Ӳ�������Ͽ�Ǥ���ӥǥ��ơ��ץ쥳������VTR = Video Tape Recorder�ˤγ�ȯ��1953ǯ�Τ��Ȥǡ��ƹ�RCA�Ҥ�4�ȥ�å������Υ��顼TVϿ��θ���ȯɽ���Τ�ü��ȯ���ޤ���
- ����3ǯ���1956ǯ�ˡ��ƹ�Ampex�Ҥ�4�إåɥС��ƥ����륹�����������VTR��ȯ�������Ѥ��Ѥ���ӥǥ��ơ��ץ쥳�����δ����ޤ�����
- A��pex�Ҥϡ�����β�����Ͽ�Ǽ�ή�ˤʤäƤ��������إåɤ���ꤷ�Ƽ����ơ��פ����Ԥ�����Ȥ������������ơ������إåɤ��ž������Ȥ���ȯ�ۤǸ���إåɤν������쵤�˲�褷�ޤ�����
- Ͽ�衢�����إåɤ���ꤷ�Ƥ����ΤǤ�����ʿ��������Ǥ��ʤ��ä��ΤǤ���
- ���äơ���Ͽ�Ⱥ������Ԥ����ŻҲ�������ˤ�68ǯ���١�1956 - �ˤȤ������Ȥˤʤ�ޤ���
- �ӥǥ��ơ��ץ쥳�����γ�ȯ�Τ��ä����ϡ�1950ǯ���ƹ�ǻϤޤä��ƥ�������Ǥ���
- �ƹ������������Ȥ�TV�����������ä�����ʤȤ��ơ��ƥ�����Ȥ�Ͽ���������ͤ��Ф���ޤ�����
- RCA�ҡʥ����Υղ�Ĺ�ˤǤϡ�1951ǯ�����������������ܤΰ�ĤȤ��ơ�VTR��ȯ�λؼ����Ф������Ϥ����Videograph��̾�դ����ˡ�2ǯ���1953ǯ�˸������̤�ȯɽ���ʤ��줿�ȸ����Ƥ��ޤ���
- ���θ��50ǯ�֤ˤ�����ӥǥ���������ˡ��ä˥ǥ����������������ʤϤᤶ�ޤ�����Τ�����ޤ���
- �ӥǥ������ϡ����Τ˸����ȥ��ʥ��������ȥǥ����������2���ब����ޤ���
- ���⤹��ȥӥǥ������ϡ֥ǥ�����פȻפ�줬���Ǥ�����ξ�Ԥ������Ȱ㤤�ޤ���
- �֥ǥ�����פȡ֥��ʥ����פΰ㤤�ϡ���AnfoWorld����˥Х�����3��-���ǥ�����ˤĤ��ơ��Ȥ��Ƥ���������
- ��
- �����ƥ�ӱ����ȥե�����������������2023.11.04�ɵ���
- �ӥǥ������ϡ�¨�¤˸�����Ȥ�������������������ǥ����Ǥ���
- ���Ǥ�������������ħ�⡢2000ǯ�ޤǤϲ���Ǥϥե���������ͥ�̤�Ω�äƤ��ơ����Υե��������ϸ���������ɬ�פǤ�����
- ����ξ�Ԥ���ħ�ˤ�äƤ���ޤ�����ʬ�����ʤ���Ƥ��ޤ�����
- �������ʤ��顢���ޥ��奢�����������Ǥϰ²��ʥǥ�����ȥѥ����ץ�ˤ�륷���ƥब�ѥ��������Ƭ��1990ǯ���Ⱦ�ˤȤȤ�˼���κ¤�����褦�ˤʤꡢ�̿����ΰ��������ޤ�����
- 2007ǯ6�iPhone��ȯ��ϥǥ����������������쵤�˿�Ʃ��������̿Ū�ʽ�����Ǥ�����
- ����̿��ϡ�1860ǯ��ˤ��äƤϰ����˰��ټ̿��˼��ޤ뤫�ɤ����Ȥ�����ʪ�Ǥ�����
- 1950ǯ�夫������˼̿�������ڤ���1970ǯ�夫��Ϥ��ؿͤǤ�Ϫ�����ˤ��뤳��̵������å����������μ�ư�����ˤʤ�ޤ�����
- �����ƥ���ԥ塼�����������ȤȤ�ˡ�������CCD�����ǻҡ�CMOS�����ǻҤγ�ȯ�ȤȤ�˥ǥ����륫���λ���Ȥʤ�ޤ�����
- 1990ǯ���Ⱦ�ʹߤ����λ���ʥǥ���������λ���ˤȸ����ޤ��礦��
- 2007ǯ�ʹߤϼ�ڤ˥��ʥå̿����Ȥ��ñ�˥����ͥåȤˤ����ƽֻ���������˳Ȼ��Ǥ���褦�ˤʤ�ޤ������ä���ư��ʥࡼ�ӡ��ˤ��ñ�˰�����褦�ˤʤ�ޤ�����
- �ǥ����륫������ڤϡ��ʲ����װ��˰ͤ��Τ��ȹͤ��ޤ���
- 1. �ǥ����뵻�Ѥ���ڡ�CPU�Ƚ�����ϩ�ι�®��������ʲ��ˡ�1980ǯ��ʹߤΥޥ�����CPU�γ�ȯ��
- 2. �ǥ����뵭Ͽ���Τ���ڡ�1990ǯ��ʹߡ�CD��DVD��BD�θ������Τ���ȾƳ�Υե�å���������ڡ�
- 3. CCD��CMOS�����ǻҤι���ǽ������ڡ�2000ǯ��ʹߤ�CMOS�����ǻҤ���ڡ�
- 4. �ͥåȥ������ڡ�1990ǯ���Ⱦ�ʹߡ������ͥåȡ�̵���̿������饦�ɡ�Wi-Fi�̿���
- 5. ���ޥۤ���ڡ�2007ǯ�ʹߡˡʱվ��ǥ����ץ쥤��������।�������ӡ�
- �ǥ����륫���ϡ�����⤽�������ˤ��äơ�����ˤ�ޤ��ƴ��ؤǾ����Ǥ��뤿��ȹԤ������Ǥ���
- �ǥ����������1000 x 1000���Ǥ�Ķ����������1990ǯ���Ⱦ�ˤ��ե����̿�����ǥ���������Ѥ�äƹԤä������˥ݥ���Ȥ��Ȼפ��ޤ���
- ���ޥ��奢�������Ǥϡ��������²��Ǥ��뤳�ȤȴʰפǤ��뤳�Ȥ����ޤ�ޤ���
- �ݥ�����ɼ̿�����ɽ����륤����ȥե����ϡ����ؤǤϤ��ä���Τλפä��ۤɥ������Ф��ޤ���Ǥ�����
- ������ͳ�ϡ��ݥ�����ɥե����ϰ��礢����μ̿�������Ǥ��ꡢ���ξ�־Ƥ������פȤ����ץ��Ȥ��Ǥ��ʤ��ä��ΤǤ���
- �����˥ǥ�������������ä��ΤǤ���
- �ǥ�����ϡ�100�����Ǥ�Ķ���륫��餬5�����������Ǥ��뺢��2000ǯ�Ϥ�ˤ����®��ȯŸ�ޤ���
- �ץ��3������β��ʤǼ̿�����¤ߤΥץ��Ȥ�����褦�ˤʤ�ޤ�����
- Windows�ޥ���10������ǹ����Ǥ���Ҳ�Ķ�������2000ǯ���Ⱦ�ˡ�����ڤä��褦�˥ǥ��������������������礷�Ƥ����褦�ˤʤä��ΤǤ���
- 1990ǯ���Ⱦ����ڤ��������ͥåȤ������¿���ܤ�����褦�ˤʤ������ư��λ��夬�Ϥޤ�ޤ�����
- 2020ǯ�ˤ��äƤϡ��̿���ץ��Ȥ��Ƥ������������̤Υ��ޡ��ȥե���Υ�����ݴɤ����ꡢ���饦�ɤ�����ʲ�����ư�����¸���ơ����ٸ������Ʊ����Ǥ���褦�ˤʤ�ޤ�����
- ����������ǡ��ե����������Ĥ��ǽ���Ϥ���ΤǤ��礦����
- �ե�����2020ǯ�����ǡ��ʲ��Τ褦�ʱ��ѤǻȤ��Ƥ��ޤ���
- �������ޡ������ե��ȡ�-����������������ӥ��ʤɤμ̿����ơ�4x5���������Ƚ����顣
- �����Dz衡-�����Dz衣35mm�ե���ࡢ70mm�ե���ࡣ��IMAX����顣�֥��륯�ס֥ȥåץ���פʤɡ�
- �������ޥ��奢���ץ������ޥ�-�����ʡ��ɥ������
�饤��������������135�����ץե������4x5���������Ƚ����顣- �������ޡ�����뻣�ơ�-���ƥ�Ӥ����Ǥ��륳�ޡ�����롣35mm�Dz襫���ȥե���ࡣ
- �������ޥ��奢���ʥåס�-���ּ̥��Ǥ��ס�1986�ˡ�
APS�ե��������������1999�� ���� ��- ���ƹ�ˤ�����16mm�ե�����®�٥����Τ�������
���ס���˴����줿16mm�ե����������ǤΥ�������ƤǤ����Τǡ���®�٥����˻��Ѥ��줿��16mm�ե����ϡ��ե�����ξü�˥ѡ��ե��졼�����ʹ��ˤ���ޤ�Ƥ��ơ�����ǥե�������ä��������äƤ����� - ���ܤǤι�®�٥����θ����ϡ��ǥ������®�٥������濴�Ȥ����ǥ��������������Ū�ˤʤäƤ��ơ��ե���५����Ȥä��桼���Ͼ��ʤ��ʤäƤ��Ƥ��ޤ���
- �������ʤ��顢���顼���Ƥ�5,000���ޡ��ðʾ夬�ߤ����桼�����䡢35mm�ե�����Ȥä���������®�ٻ��Ƥ����Dz�ط��䥳�ޡ������ط�������˱��賫ȯ�ط��Ǥ�̤������¸�ߤ�ؼ����Ƥ��ޤ���
- ��
- 2002ǯ1��ƹ�Ρ�Photonics Spectra�פȤ������������������ФƤ��ΤǾҲ𤷤Ƥ����ޤ���
- ���ε����ˤ��ޤ��ȡ��ƹ�θ��浡�ؤǤϰ����Ȥ��ƥե�����Ȥä���®�٥���餬����dz������Ƥ��뤳�Ȥ��狼��ޤ���
- ���˶�̣���뵭�����ä��Τǡ�������ʲ��˺ܤ��Ƥ����ޤ���
- ���ܤǤϡ�2002ǯ�ˤ��äƤϤۤȤ�ɻȤ��ʤ��ʤä�16mm��®�٥����Ǥ������������ʤ�Τ���������ͳ����äƹ�®���ե����������¸�ߤ�ǧ�ᡢ��������Ȥ��ƺ��������Ѥ��Ƥ�����¤˴��ä�����ޤ�����
- ���ʤʤ����ե�����®�٥����Υȥԥå��ϡ���AnfoWorld����طʤȥȥԥå����Ȳ��������� ��
��
- CCDs vs. Film for Fast-Frame Impact Testing,
- ������������by Brent D. Johnson��pp.58- 60, December 2001, Photonics Spectra��
- ��������������- ���˻Ȥ��Ƥ����®�٥ե���५���ȹ�®�٥ӥǥ������ -
- ��ư�ְ����¸��Ǥϡ�1960ǯ�������®�٥���餬�Ȥ��Ƥ��롣
- Arlington�ˤ����®ƻϩ�����ݸ������The Insurance Institute for Highway Safety�ˤǤϡ�16mm�ե������Ѥ�����®�٥����Locam��Visual Instrumentation Corp. ���ˤ���Ѥ���500���ޡ��äβ�����ɤ����������Ƥ��롣
- �ޤ������λ��ߤˤϡ�������Weinberger�Ҥι�®�٥������ͭ���Ƥ��롣
- ��Locam�ǻ��Ƥ��������ϡ��ӥǥ����Ѵ�Ͽ�褷���ݤ˺ǹ�β�������Ƥ����� ��ô���Ԥ�Pini Kalnite�ϸ�äƤ��롣
- ���ζ���Ǥϡ�CCD�����פι�®�٥ӥǥ�������Ƴ����Ƥ���ʤ���⡢���ʤ���®�٥ե���५���λ��Ĺ����ˤ�����ꡢ�������ӥǥ��Խ��Ȥ�������ˤⴺ�����ܤ�Ĥ֤���Ѥ��Ƥ��롣
- National Highway Traffic Safety Administration's Vehicle Research and Test Center�ʥ��ϥ����� East Liberty�ˤǤϡ��֤ΰ������ͼ¸���12���16mm��®�٥ե���५����1,000���ޡ��äϡ�Photo Sonics�����Τ�Ρ�5,000���ޡ��äΥ����ϡ�Visual Instruments������ Hycam�ˤ�Ȥäƻ��Ƥ�ԤäƤ��롣
- �Ҷ���ʬ���Ǥϡ�NASA Langley Research Center�ʥ��������˥���Norfolk�ˤ�14��Υߥꥱ����Miliken�ˤ��Ҷ������ͻ�˻Ȥ��Ƥ��롣
- NASA�Ϥ��Υ�����1970ǯ���Ƴ���������ʺ�����30ǯ�ʾ�������ˡ����ɤ��ʤ��鸽�ߤ˻�äƤ��롣
- ���ϡ����ι�®�٥ե���५����ή�ˤʤäƤ���CCD�����פι�®�٥������夨��Ĥ��Ϥʤ��Ȥ�����
- ��ͳ�ϡ�CCD�����פι�®�٥����β����Ϥ������ԤΥե���५���ǻ��Ƥ���������2500x1500���Ǥǥǥ�����������Ѵ�������Τ���ٲ�������뤳�ȡ������ơ�CCD�����Υ��꤬2�ô֤λ��Ƥ����Ǥ��������������餦�¸����ȤƤ����ǥߥ���������ʤ����ᡣ
- ������פ�CCD��®�٥����Ǥϡ��ȥꥬ�����ߥ����줿���ε�Ͽ�ߥ�����̿Ū�ˤʤ�Τ�ͫθ���Ƥ��뤿�ᡢ�ȸ�����
- ��֤�æ�����ԤäƤ��륵��ǥ�����Ω������Sandia National Laboratory�ˤǤϡ���Ϥ�16mm�ե�����Ȥä���®�٥ե���५����ȤäƤ��롣
- ���θ����Ǥϡ�������ʪ�����������Υ��㥹����Cask�ˤDZ��ִط��塢��ֻ��Τ����ꤷ�ƥ��㥹���ξ���¥������Υ�ǥ����֤˺ܤ��ƻ��ԤäƤ��롣
- ��5ǯ���ޤǤι�®�٥ӥǥ������ϻȤ�ʪ�ˤʤ�ʤ��ä������Ϥ��ʤ��ɤ��ʤäƤ��뤬����������³���륳��ԥ塼����¿��ʥ����ɬ�פȤ���ΤǤޤ��㤤�����뵤�ˤϤʤäƤ��ʤ���
- �⤷�㤤������Ȥ���ʤ�С������Υե���༰��®�٥�����Ʊ���٤β����4�ܤ���5�ܤλ���®�٤��ĥǥ������®�٥���餬���줿���Ǥ��롣��
- �ȡ������Ȥ���絻�Ѱ���Mark Nissen�ϡ�����16mm��®�٥ե���५����Photo Sonics������16-1PL���ڤ�Visual Instruments������ Locam�ˤ��Ѥ���16���ޡ��ä���500���ޡ��äǻ��Ƥ�������ʾ�λ���®�٤��᤹�륱�����Ǥ�Hycam�ȸƤФ���®�٥ե���५����Ȥä�5,000���ޡ��äλ��Ƥ�ԤäƤ��롣
- ��
- ���ե����϶��ȤäƤ���
- ������Ͽ��������ǺǤ���ˤ����ꡢ���ġ��Ǥ���ľ�ʵ�Ͽ���ΤǤ��ä��Τ��ֶ�פǤ���
- �䤬�����ɤ�ȿ�����뤳�Ȥ��Τ���褦�ˤʤäơ����Ĵ����ब��ȯ���줿�Τ�1830ǯ��Ǥ���
- �ʸ塢160ǯ�δ֤˶�����������϶ä��ۤɤο����뤲�ޤ�����
- 1980ǯ��ʹߡ��ե����ν��μ����Τ�ʤ��Ƥ⤭�줤�ʼ̿�������륫��餬�в��ޤ�����
- ���ι�Ǥϡ�1990ǯ��ʹߵ�®�˰��̲������ӥǥ����ѤȤ���Ӥ�ǰƬ�ˤ����ʤ���ե���൭Ͽ�θ������������ޤ���
- Nikon��Pentax��Canon�ʤɤ�35mm�饤�������������ϡ����ե���������ۤ�����Ͽ���Τ�ȤäƤ��ޤ���
- �����Τˤϡ��ϥ�����γ�� = silver halide particles �����˺������������ۤ����������������ޤ��ơ���Ʃ���ե��������ۤ�����Ͽ���ΤǤ�����
- �桹�Ϥ����ñ�ˡإե����١�Film�ˤȸƤ�Ǥ��ޤ���
- �Τ����ޤ�ٻ�����١����˥��饹�Ĥ��Ȥ��Ƥ����Τǡ����ġ�photographic dry plate�ˤȸƤФ�Ƥ��ޤ������ʴ��Ĥ����ϥ����������� = collodion wet plate) ���Ȥ��ޤ���������ϡ����Ƥ����˼̿��� = ���ؼԤ��������Ĵ�礷�����ۤ�������δ��٤��⤯�ݤ����Ǩ�줿���֤ǻ��Ƥ��Ƥ��ޤ�������
- ���饹�ϳ��䤹���Ȥ�����Ⱝ���Τǡ���ˡ�������Τ褤����ե����γ�ȯ��˾�ޤ�Ƥ��ޤ�����
- ��������ɡʥ˥ȥ�����������ˡ�celluloid��nitrocellulose�ˤϡ���ˡ���������ɤ��Τǰ�����礤�˻��Ѥ���ޤ�������ȯ�������⤯������ȼ���Τ�1950ǯ������ȥꥢ���ơ��ȥ����������triacetate cellulose�ˤ��Ѥ���褦�ˤʤ�ޤ�����
- 1980ǯ�夫��ϡ���ˡ�����������ʳإե����ʹҶ��̿��ˤǤϥݥꥨ���ƥ�ե����ʥݥꥨ�����ƥ�ե��졼�� = polyethylene terephthalate��PET�ܥȥ�κ������ޥ��顼�ե���� = Mylar film�ˤ��Ѥ��뤳�Ȥ⤢��ޤ���
- �������������Ǻ�϶�����ʤ��ᥫ���ࡼ�֥��ȡ���������������Ƥ��ޤ������줬���ꡢ�����ơ��ȥե���फ���֤������ˤϤ�����ޤ���Ǥ�����
- 35mm���ե����Ǥϡ�0.13mm�� 0.15mm���Υȥꥢ���ơ��ȥե����١�����ˡ��ϥ���������γ�ҡ��礭��0.2um �� 6 um�ˤ�����gelatin�ˤ˺����Ƹ�����um �� 20 um�����ۤ���Ƥ��ޤ���
�������ۺޤ����ޡʥ��ޥ른���emulsion�ˤȸƤ�Ǥ��ޤ���
- �ϥ�����ϡ��̾���ǤȲ��礷������Ȥ��ƥ��ޥ른���˴ޤޤ�Ƥ��ޤ���
- ������ϸ����ͥ륮���������ȥ��ޥ른������ȿ�����䥤����Ƚ��ǥ������ʬ��ޤ���
- ���äơ�������ϥ��ͥ륮���ι⤤�糰����X���ˤ褯ȿ�����ޤ���
- ����������������û���糰����ۼ����뤿��200nm�ʲ��λ��ƤϤǤ��ޤ���
- �ϥ�����ϸ����ͥ륮�����������1�ʥ������٤Τ�����û�����֤Ǥ�ȿ������1�����٤ޤǤϥ�˥����������ޤ��ʸ��Υ��ͥ륮�� x Ϫ������ = ����ˡ�
- 1�ðʾ��Ϫ�Ф���ϡ�¿���ξ�硢���ͤ�������ͥ륮�����㤤���ᡢ�ϥ��������Υ�������Ϥ��夯��Ϫ���̤ϥ�˥��ǤϤʤ��ʤ�ޤ���
- �ޤ������Υ���������������Ǥ�Ĺ����Ϫ���ˤǤϡ���������˴ޤޤ����Ǥȿ�ʬ�Ҥ������ͥ륮����ۼ����Ƥ��ޤ�����¸����٤�����ޤ���
- ���줬��ȿ§�Ե��ʤ����Ϥ��դ��ˡ�reciprocity failure of film)�ȸƤФ�븽�ݤǤ���
- ���ˤ�ä���Υ���줿���������Υϥ�����ϡ������ʤ����ˡ١�latent image�ˤȸƤФ�Ƥ��ޤ���
- �����Ͽʹ֤δ�Ǥϸ��뤳�ȤΤǤ��ʤ������������Ǥ���Υȿ���Ǥ���
- ���ޥ른��������������ꤷ���Ļ벽���ˤ���Τ��ظ����١�image development�ˤǤ���
- �����ϲ���ȿ�������Ǥ��ꡢ��Υ��ionaization�ˤ����䥤������°��˴Ը����ƹ����ζ�����������ޤ���
- ���������Ǥϸ��������äƥ��������ϥ�����γ�Ҥ���Ը�ȿ�����Ϥޤꡢ�����˸������ޤ�������ʤ��ä����̤ˤ�Ը�ȿ����¥���褦�ˤʤ�ޤ���
- �������äơ�Ϫ���Ѥߥե������������դ�Ĺ���ֿ����ƴԸ�ȿ����¥�ʤ�����ȡ����٤ƤΥϥ����䤬�ʸ��������äƤ������̤������äƤ��ʤ����̤�˴Ը�����ƶ�°��Ȥʤäƹ��������Ƥ��ޤ��ޤ���
- �����ˤ����븽�����֡ʤ�ȿ����¥�������ղ��١ˤ����ڤ���ͳ�������ˤ���ޤ���
- �����դϥϥ������Ը������������ĥ��륫���ϱդǡ���ȡ����Metol��β���ѥ����륢�ߥΥե��Ρ��������ˡ��ϥ��ɥ����Υ��hydroquinone��C6H4(OH)2�ˤ��Ȥ��ޤ���
- �����������Ƥ⥨�ޥ른�����ˤϸ���ȿ���Ǥ���ϥ����䤬�����Ȥ��ƻ�¸���뤿��ˡ����������ɬ�פ�����ޤ���
- ���������ȸƤ�Ǥ��ޤ���
- �����photographic fixer�ˤϻ����ϱդ���ǹԤ��ޤ���
- ���ʤߤˡ������ϥ��륫���ϱդ���ǹԤ�졢���������������幩��������ݡ������Υ��륫���ϱդ����������ϱդ˻����ۤ���뤿������դ���ޤ�ޤ���
- ������ɤ�����ˡ��ݻ��ʿݡ��ϱդ���߱դǥե��������¤⤷���ϻ������������幩��������ޤ���
- �ե���������夵�줿�������blackened silver�ˤϤ����ư���ˤʤꡢĹ����¸���Ѥ����뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
- ��
- �ڿ�������ˡ�ۡ�Photographic hypersensitization��
- ����������ܤ����ե�����ŷ�δ�¬�ѤΥե����Ȥ��ƥ��ޥ��奢ŷʸ�Ȥδ֤ǻȤ��Ƥ��ޤ�����
- ���Υե��������ʷ�ϵ���ˤ��餷�Ƥ����ȼ¸����٤�10�����ٸ��夷�ޤ���
- ���θ����ϥե������˻�¸�������ʬ�Ҥȿ�ʬ�Ҥ������ͥ륮����ۼ����Ƥ��ޤ����ᡢ���٤�ͭ���ʤ�����ʬ�Ҥ���Ǥ��ִ������Ƥ��ޤ���ΤǤ���
- �������뤳�Ȥˤ�ꡢ�ϥ�����䤬��Ψ�褯����ȿ���Ǥ���褦�ˤʤ�ޤ���
- ��������ˡ��Ԥ����֤ˤϡ��ե����������̩���ƴ�ʿ��������ǥե����ߥ���������륳�å��ա��ǥ��������Ǥ�ή�Ѳ�ǽ�ˡ������ݥ�ס�50����ݤĥҡ���������8%������92%�Υե����ߥ�����ɬ�פǤ���
- ���ΤΥե�����̩���ƴ�����졢��ʬ�Ȼ��Ǥ��������������ޤ���
- Ⱦ�����ٿ��������������ǥե����ߥ���������ƻ��Ǥȿ�ʬ�Ҥ�ȴ���������̤ζ�˳����Ǥ��ִ����ޤ���
- �ִ���Ȥϲ��٤��⤤������Ψ�������Τ�̩���ƴ��50����դˤ��ƹԤ��ޤ���
- ��������ˡ��Ҳ𤷤���������ī����ʹ�ס�1981ǯ3��14���ˤˤ���ޤ����ΤǤ����Ҳ𤷤Ƥ����ޤ���
- ��
ŷʸ���Ƥ�����˹Ԥ�줿��������ˡ�⡢1990ǯ�彪��꺢������CCD���о�Ǥ��κ¤�å���ơ��Ƕ��1990ǯ��ˤǤϤ�������������Ԥ�ʤ��ʤ�ޤ�����
- ������������ �Ϥä���̤롡-����ڤ��Ϥ��������ˡƱ��Ϫ���Ǥ�10�ܤκ��⡡-��
- ���ޥ��奢ŷʸ�ե���ϡ��и����Ѥ�Ǥ����ŷ�Τ�̥�Ϥ�̿��˵�Ͽ�������ʤ�褦����
- ����ʻ����Ť�ŷ�Τ�̤��Τ˥ե����δ��٤���ʤ����Ȥ����뤬���Ƕᡢ���ǥ�����Ȥä���������������ǡ�2�ܤ�����ˤ�äƤ�10�ܤ�Ķ�����٤˥ե����������Ǥ��뵻ˡ����ȯ���줿��
- ����ꥫ�ǤϿ��Ǥ�����˻Ȥ�����Υ��åȤ⤹�Ǥ����Ф���Ƥ��ꡢ���ܤ�ŷʸ�ե������ˤ��������֤������ե�����Ȥ��Ϥ�ͤ⤤�롣
- ��������ˡ�ϡ�����Ū�ʥե�������Υ����å��Ҥ�T.A.�Х֥��å����T.H.�������ॺ�����ͤ�1975ǯ�˸��Ĥ����Ƕ�ˤʤä���ڤ�����
- ���٤������Τϡ��ե����δ������ޤ���ˤ���ľ��0.1��1�ߥ�����ν�����뾽�˿��Ǥ����Ѥ������Ǥȥ�����礷�Ƥ�����Ը���2���Ҥ�ñ�Τζ���뤫�����
- ���̤˥ե���ब��������ȡ������������ŻҤȥץ饹���ŵ��������ˤ����衢�ŻҤ������ä��䥤����ñ�ΤΥ�����ˤʤ롣
- ���줬�������κݡ����ޤ�Ư���ƹ���������Τ��������ǤǴԸ����줿ñ�Τζ䤬�ǽ餫�餢��ȡ���������Ǥ������Ψ���ɤ��ʤ뤿�����
- ŷʸ���ƤǤ�Ϫ�����֤�10�ä���1ʬ���٤ˤ��뻣�Ƥ�¿���Τǡ�Ĺ����Ϫ�������դ�cooled CCD�����������Ȥ����꤬�ɤ��ȸ����ޤ���
- ��®�٥����Ǥ�10us�Ȥ�1us��ɴ��ʬ��1�áˤ�Ϫ�Ф�ɬ�פʾ�礬¿���Τǡ����Ҥ٤��ե���������������ˡ��2000ǯ��ޤǤ�ͭ���ʼ�ˡ�Ǥ�����
- �� ��
- ��
- �����顼�ե��������2002.05.04�ˡ�2020.5.17�ɵ���
- �������������ե����ˤĤ��ƽҤ٤ޤ�����
- ���顼�ե���������ե����Ʊ�Ͷ����ȤäƤ��ޤ���
- ��������ե����Ȱ㤦�Τϥ��顼��������뤿��������̤��ġ��С��֤λ��ؤ��̤�Ƥ��뤳�ȤǤ���
- �ġ��С��֤γ��ؤˤϤ����ΰ�˴������������ǡ�sensitizing dye�� = ���ץ顼��coupler�ˤ��ޤޤ�Ƥ��Ƥޤ�������ȥϥ������silver halide��������˥襦���䤬�Ϥ�������襦��������Ȥ��������Ρˤ��ä����ۤ���Ƥ��ޤ���
- ���θ��εۼ��ˤ�äƥϥ�����γ�Ҥ�ɽ�̤������濴���Ǥ��ޤ���
- ������������γ�Ҥ��������Ǹ������ƴԸ�����γ�Ҥˤ����ޤ���
- ���δԸ�ȿ���ˤ�äƸ�����������������ƻ�������ʪ���Ǥ������λ���ʪ�ȥ��ץ顼��coupler�ˤ�ȿ������ȯ�����Ǥ�����ޤ���
- ���ΤΤ��ʥͥ��ե����Ǥϡ�ɺ��Ȥ���������Фơ�����ǥե������ζ䤬���٤�����ή����ȯ���������ץ顼�������Ĥ�ޤ���
- ���ץ顼��coupler�ˤȤϡ��ե��Ρ���ʥ�����ˡ������륢���ȥ��˥�ɡʥ��������ˡ�1-�ե��˥�-5-�ԥ饾����ʥޥ��ˤ���ɽ����벽�����ʤ�ȯ���θ��ˤʤ��ΤǤ���
- ���ץ顼�γ�ǰ�ϥ����å��dz�ȯ����ޤ�����
- ���顼�ե����Ϻ��Ǥ�������Ū�ˤʤäƤ��ޤ����ȤƤ�ʣ���ʻ��ȤߤˤʤäƤ��뤳�Ȥ��狼��ޤ���
- ���顼��������뤿��˻������θ�������Ѥ���3�ؤ����ޤ����ۤ��뵻�Ѥ䡢�������˴������������ޤγ�ȯ��ȯ����������ĥ��ץ顼�γ�ȯ�ʤɶ�̣���뵻�Ѥ����������߽Ф���ޤ�����
- ��
- ��3���������ء�����2005.11.20�� ��2020.05.17�ɵ���
- ���顼�̿��ιͤ����ϡ�1891ǯ��������ʪ���ؼԥ�åץޥ��Jonas Ferdinand Gabriel Lippmann�� 1845 - 1921�ˤ��Ϥ�ȸ����Ƥ��ޤ���
- ��åץޥ�ˡ�ϸ��δ��Ĥ�ȤäƸ��μ��ȿ���Ͽ���������Ǥ�����
- ���Ȥ��Ƥ�����λ������ˤ����ˡ�ǤϤ���ޤ���
- ���μ�ˡ��ɾ������ơ�1908ǯ�˥Ρ��٥�ʪ���ؾޤ���ޤ��Ƥ��ޤ���
- ��åץޥ����ˡ�����������Ǥʤ����Ȥ����ʤ��Ȥ������Ū�ˤϤʤ�ޤ���Ǥ�����
- ����Ū��3�����˴�Ť����顼�̿���1855ǯ�Υޥ����������James Clerk Maxwell��1831-1879�ˤ����T.Young�ˤ�3���������˴�Ť��������Τ��Ϥޤ�Ȥ���Ƥ��ޤ���
- �ޥ���������ϡ�1861ǯ����Ω������3�����˴ؤ��붽̣��������¸��Ƥ��ޤ���
- ��Ͽ����դ�����ܥ�μ̿������Υե��륿���ġ��С��֡ˤ�Ȥäơ����줾������μ̿��˻��Ƥ�ľ����3��μ̿��ʥݥ��ˤ���ޤ�����
- ���μ̿��Ƥλ��˻Ȥä��ġ��С��֤Υե��륿�˺��٤����ƥ�������Ƥ��ޤ�����
- ����3��μ̿���Ԥä���Ť�碌���Ȥ�������̿����ä������ϸ����ʥ��顼�̿��ˤʤä��ΤǤ���
- �ޥ���������Ͽͤ��ܤ�3���������ǥ��顼������뤳�Ȥ�¸��Ǽ������ΤǤ���
- �ͤλ��˦�ˤ�3�������Τ��뿧�μ����Τ�����ΤǤ���
- ����ϡ������ꥹ�Υȡ��ޥ�������ؤ�Ω�줫�����Ƥ������ȤǤ�����
- ����Ū�ʥ��顼�ե���ब�����Τϡ�1904ǯ���Dz����ȸ���줿�ե��ȯ���ȥ��ߥ����뷻���A.&L. Lumiere�ˤ��⥶������������Ȥä������ȥ������ഥ����Autochrome Lumière�ˤ�ȯɽ���ƾ��ʲ��������Ȥ���Ϥޤ�ޤ���
- 1928ǯ�ˤϲÿ�ˡ��°�����������顼ˡ��16mm�������顼�����ʲ�����ޤ���
- 1935ǯ�������å��Υޥ�ͥ���L.D. Mannes�ˤȥ��ɥ���������L. Godowsky�ˤ��ե����˻������λ������ޤ����ۤ�������������ȿžȯ������ˡ�ȸƤФ�븺��ˡ�ˤ���Υѥå�ˡ��ȯ�����ޤ���
- ���������Ǻ��줿�ե���ब�������������Kodachrome�ˤȤ�������̾�����䤵�졢���������ĤΥե�����¿�����ۤ��륫�顼�ե���ब����Ū�ˤʤ�ޤ�����
- ���ߥǥ����륫����ñ��CCD���������̤�Ž���դ����Ƥ���3�����⥶�����ե��륿�ϡ��٥��䡼��Bayer�˥ե����ޥå��ȸƤФ�Ƥ��ޤ��������Υե��륿�ϡ������å���Bayer��Τ����顼�ե����θ������ȯ��������Τǡ�CCD������ѤȤ��Ƴ�ȯ���õ����ä���ΤǤϤ���ޤ���Ǥ�����
- ���顼�ե����⡢�ͥ��ե���ࡢ��С�����ե���ࡢ�������ץ顼�������ⷿ���ץ顼������������ȥե������������ȯ��������ʲ�����Ƥ��ޤ���
- ��
- �ڹⴶ���ء��洶���ء��㴶���ء�
- ��ޤΥ��顼�ͥ��ƥ��֥ե�������̿ޤ��ϼ��ޤ�ȡ����顼�ե�����ʣ����¿�������ۤˤ�äƺ���Ƥ��뤳�Ȥ��狼��ޤ���¿����λ����ϥ���ˤ�äƤޤ��ޤ��Ǥ�������ɽŪ������ޤǼ����ޤ����ˡ�
- ���顼�ե����ˤ��ġ��С��֤�3�Ĥδ����ؤ���ʤ륳���ƥ����ܤ���Ƥ��ơ��ƴ����ؤϤ����3�Ĥ������ؤ��̤�Ƥ��ޤ���
- 3�Ĥ������ؤΰ��־�Ϲⴶ���ؤǡ������洶���ءʲ��������ؤȤ�ƤФ�Ƥ��ޤ��ˡ����ֲ����㴶���ؤǤ���
- �ⴶ���ؤϥϥ�����γ�Ҥ��礭����γ���ϹӤ�����ɸ����ɤ�������Ư��������ޤ���
- �㴶���ؤ���γ���ϥ����䤬���ۤ���Ƥ��ơ�������ʬ�ˤ���Х���κ٤������������뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
- ��֤����֤��줿���������ؤϹ��ߤ�Ư���ޤ���
- �����ؤ��������Ƹ��������Ȥ����ؤ˴ޤޤ�Ƥ��븽�������ޤ�ͷΥ���ơ����ؤιⴶ�٤���γ�Ҥ����ޤθ���������������γ�Ҥ˻ž夲�ޤ���
- ������Ϫ�����λ�����ִ����ؤ��ۤȤ�ɴ������ʤ����ᡢ���������ޤ����Ф���ʤ��Ǿ��ؤιⴶ�����ޤ��ե�˴��٤�ȯ�����ޤ���
- ���ξ���γ�������㲼�����̤Ȥʤ�ޤ���
- ��
- �ڲ����ե��륿�ء�
- ���顼�ե����Ǥϡ��Ŀ������ؤΤ������˥��������ե��륿�ؤ����֤���Ƥ��ޤ���
- ������ͳ�ϡ��ϥ�����Ϥ�Ȥ���Ĥ˴��٤���äƤ����ֿ��ΰ�ϴ��٤��㤤����ˡ������˴��٤�������뤿��˥ϥ������ʬ���������ǡʥ��˥����ǡ�������˥����ǡˤ���Ĺ��Ĺ�ˤޤǴ��٤�������ޤ�����
- ���äơ�ʬ�����Ǥ�Ż�ä��ϥ������Ĺ��Ŧ�ˤⴶ�٤���Ĥ褦�ˤʤ�ޤ���
- �������������Ȥ����Ŀ��ϥϥ����䤽�Τ�Τ������Ƥ��ޤ��Τǡ����顼�ե����Ǥϸ����ǽ�ˤ�������̤��Ŀ������ؤ����ۤ������β����ˤ��Ŀ���ۼ������Ф��֤�Ʃ�᤹�륤�������ե��륿�����֤��Ƥ���ޤ���
- ���Υ��������ե��륿�ؤϸ��������Ǽ�������Ʃ���ˤʤ�ޤ���
- ��
- �ڥ��顼�ɥ��ץ顼��
- ���顼�ͥ��ƥ��֥ե����ˤϸ������������ݤ����Τ�������ӤӤ��ž夬��ˤʤ�ޤ���
- ����ϥޥ���ȯ�����ץ顼���д����ءˤ������ǥ�����ȯ�����ץ顼���ֿ������ءˤ�ø�ȿ��Ƥ��뤿�ᡢ������������̤ȯ�����ץ顼����α���ƥ�������ä����ˤʤ�ޤ���
- ͽ�ῧ���դ��Ƥ������ץ顼�Τ��Ȥ顼�ɥ��ץ顼��colored coupler�ˤȸƤ�Ǥ��ޤ���
- �д����ؤ��ֿ������ؤˤʤ����顼�ɥ��ץ顼����Ѥ��뤫�Ȥ����ȡ�ξ�ԤΥϥ�������Ŀ��ˤⴶ�٤���äƤ��ꡢξ�Ԥδ����ؤǤ�ξ�Ԥθ������Ǥʤ��Ĥ�㴳�ۼ����ޤ���
- ��������֤��Ƹ�����������Ŀ��������ʤ�Τ�ͽ��ͭ�����ץ顼���Ŀ���ʬ���������ƿ��Ƹ������䤫�ˤ��Ƥ���ΤǤ���
- �� �� ��
- ��
- ���ե�������ޤ��������2002.02.03�ˡ�2006.02.06�� ��2020.5.15�ɵ���
- �ե���ശ�������ϥͥ��ƥ��� �ե���ब�濴�Ǥ�����
�����������۲褫�饹�����Ȥ��ޤ��������ץ��Ȥ�Ԥ�ɬ�פ���ͥ��ե����μ��פ������Ƥ��줬����Ū�ˤʤ�ޤ�����
- �桹�ξ��ع���������ʤλ��֤��ļ̿��μ¸���Ԥä����Ȥ�����ޤ���
- �ե����δ��������Ϥ���Ȼ��Ƥ��ޤ���
- �ļ̿��Ǥϴ�����ξ�˿�ʪ���դ��ڤ����֤��ơ����ξ�˥��饹��Τ���30ʬ�ۤ����۲��ˤ��餷�ޤ���
- ���θ塢����������դˤĤ���ȸ��������ä��꤬ȿž�����Ŀ������ޤ�ޤ���
- ���θ������ե���ശ����ˤ����ƤϤޤ�ޤ���
- ���������ä��Ȥ����������ʤ�ޤ���
- ���̤δ��ФǤϸ�������������뤯�ʤ�Τ��ʤꡢ�ե����Ǥ�Ʃ����ȴ���ʤ���Фʤ�ޤ����ͥ��ƥ��֥ե����ξ��϶�ȿ���ˤ�븽��������Фƹ�����Ȥʤ�ޤ���
- �Ĥޤꡢ�ͥ��ƥ��֥ե����Ǥ�ǻø����ȿ�Фˤʤ�ޤ���
- ���Υե�����˰����˾Ƥ��դ��ơ�����ȿž�����������������������ޤ���
- ���줬����Ū�ʥե���ࡢ�Ĥޤ�ե������ȥץ��Ⱥ�ȤǤ���
- �桹����Ź�ǥե������㤦�ե����ϡ��ۤȤ�ɤξ�礬�ͥ��ƥ��֥ե����Ǥ��ꡢ�����Ȱ��˥ץ��Ȥ����Ƥ�餤�ޤ���
- �����ե����˻Ȥ��Ƥ�����������ϡ��ļ̿��Ȱ�äƸ����Ф��ƴ��٤��ɤ����ʲ�����ħ����äƤ��ޤ��� ��
- ����û����Ϫ�����Ǥ��롣
- ���������γ����������������ǻ�١ˤ��ɤ��ΤDz�����ɤ����Ƥ������롣
- ��������줿ȿž�����ʥͥ������ˤϡ�Ʃ���ٻ��Τ�����Ǥ���Τǰ����˥ץ��Ȥ���ݤ�������
- ��������ε�Ͽ���ϡ���Ͽ�����ɤ�����

- ��
- �ڶ��silver�ˡ�
- �������夵���뤿��ˡʴ�����Ȥ��ơ˶䤬�Ȥ���褦�ˤʤä��Τ϶�̣�����Ȥ����Ǥ���
- ����Τ������Ǥ�����
- �����衼���åѤǤϡ���������������ͤΤ�����夬���ä��ȸ����Ƥ��ޤ���
- ����������ܤ������ˤʤäƳ����ޤ���ޤǶ�ȶ�Ȥ����в��ͤ϶�������⤫�ä��ΤǤ���
- ��ʾ���ֶ�פ��ܤȤ��ư층���������ܰ�����Ȥäư���ֶ�פ��ǹ�β��ͤˤʤäƤ��ޤ������Τϡ���ȶ�Τ��줾����Ω����ʣ�ܰ����Ǥ�����
- �����ꥹ�Ǥϡ���ʾ��ñ�̤ˡ֥ݥ�ɡס�pound�ˤȤ���ñ�̤��Ȥ�졢�Ť��ʤΤ���ʾ�ʤΤ��狼��ʤ�ñ�̤��Ȥ��Ƥ��ޤ���
- ���Ρ֥ݥ�ɡפ�������1�ݥ�ɤνŤ��β��ͤ��ä��ΤǤ���
- �����ꥹ�Ǥϡ����ζ�1�ݥ�ɤ�240��ʬ�ˤ櫓240��ζ�ߤ���ޤ�����
- ���ΰ��礬1�ڥˡ���ߤȤʤ�ޤ����� �ʥڥˡ����12�礬���ޤäƥ���Ȥ�����ߤ���졢20�����1�ݥ�ɤλ��夬����ޤ����� ���ʤߤ�1�ݥ�� = 4���饦��1���饦�� = 5����� = 60�ڥȤ�����ʾñ�̤�Ǥ����ꡢ�ϡ��ե��饦��Ȥ�����ʾ��Ǥ���1���ˡ� = 21�ڥȤ���ñ�̤�Ȥ��Ƥ��ޤ�������ˤΤʤ��뵻�Ǥ��礦������
- ���θ塢�����ꥹ��1813ǯ�˶��ܰ�����Ȥ�褦�ˤʤ�ޤ������֥ݥ�ɡפȤ���̾�������ϻĤ�ޤ�����
- ������ˤ��Ƥ��Ϻ����Τ��°���ä��ΤǤ���
- ��ϡ������������������ä���°�Ǥ��θ��������������鿩����������¿�Ѥ���ޤ�����
- ��������Ȱ�äƶ�ϻ������䤹����������ȹ����������������ޤ������Τˤϥ������ȿ�����ƻ�����Ȥʤ뤽���Ǥ���
- ��Ȼ��Ǥ��Ф��Ƥϰ��ꤷ�Ƥ��뤽���Ǥ��ˡ� ������������ᤱ�Фޤ���Ȥ��������������������뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
- ��϶�μ��˱������٤ߡ��ŵ���ƳΨ�϶�°�����Ǥ���
- ����������ħ�˲ä��ơ���ϸ��ˤ褯ȿ�����ޤ���
- ���θ����Ф���ȿ����ȴ���������ˤ����ο�ã����������Ĥ������Ȥ��ƶ��������ȯŸ�����ޤ�����
- ���ߡ�1990ǯ��ˤǤϡ���ξ����̤���Ⱦʬ���̿������ѤȤ��ƻȤ��Ƥ��뤽���Ǥ���
- ��϶ˤ�ư��ꤷ����°�Ǥ���������ȿ���������ξ�ϥ�����ˤϤ��䤹����������������äƤ��ޤ���
- ������Ĥ��Ȥ߹�碌�ˤ�äơ�������ȿ�������ƥϥ�����ȶ�äĤ�����Υ�����ꤷ������ȿ�������������ͷΥ�������夵����̿����Ѥ���夲�ޤ�����
- ��
- �ڥ���顦���֥�������
- ���α��Ƥ�̤��Ф��Ƶ�Ͽ���뤳�Ȥ��Ϥ��줿�Τϡ�1500ǯ���Υ���顦���֥�������camera obscura����ƥ���dark chamber���Ĥޤ��Ȣ�Ȥ�����̣�ˤ���ȸ����Ƥ��ޤ���
- ���Υ����ϡ��Ť��������ɤ˾����ʷ���������餽�η���̤������������ˤ�ä�ȿ��¦���ɤ˳������ʤ�̤��Ф����̤��Ф��줿����������ä��ͤ��ʥ��ä����ʤ��ϼ̤����ȸ����ޤ���
- ���줬�����θ����Ȥʤꡢ���θ�ԥ�ۡ��뤬������ꡢ�ҥȤ������ϼ̤�����˴���ʪ���DZ��Ƥ�Ϫ�����뵻�Ѥ�ȯã�����̿�������夬��ޤ�����
- ��
- �ڴ������
- ����ȿ������ʪ����ȯ�������Τϡ�1727ǯ���ɥ��ĤΥ�ϥ����ġ�J.H. Schulze��1687-1744�ˤȸ����Ƥ��ޤ���
- ��ϸ��ˤ�äƾ˻����AgNO3�ˤ��������뤳�Ȥ�ȯ�����ޤ�����
- ��ϡ��Ť��Ȥ����Ǿ˻����ϱդ����г���ˤ�ʴ���ƥ��饹�Ӥ�����졢�ӥ�β���ʸ�����ڤ�ȴ������������襤����������Ȥ������֤����Ȥ��������Τ����ä�����������ʤꡢ�Ĥ����ʬ���ޤޤǤ��ä��ΤĤ����ΤǤ���
- ���κ�����ȤäƱѹ�ͤΥȡ��ޥ��������å����åɡ�T. Wedgewood��1771-1805�ˤ�����顦���֥������ξ����̤ˤ��κ�����Ȥ��ޤ�����
- ������������Ϥ��ޤ������ޤ���Ǥ�����
- ��ϡ������Ǿ˻�����������ɤä���ʴ�����ˤ�ȤäƳ������������饹���ơ���ʬ�����������ƤƳ���̤���뤳�Ȥ��������ޤ�����
- ���ΤȤ��δ�����˼̤ä����Ƥϳ��Ȥϵդα���ʥͥ��ˤǤ�����
- ����
- �ڥ˥��ץ��ˤ��إꥪ����ե���
1822ǯ���ե��ȯ���ȥ˥��ץ���Joseph Nicephore Niepce�� 1765 - 1833�ˤϡ������ե���Ȥ������ʥƥ�ԥ����ˤ��ϲơ������ġ�Ƽ�ġ����Ǿ�����ۤ�����Τ�顦���֥�����������Ʒ����̤�����̤���뤳�Ȥ��������ޤ�����
- ����ϡ������å����åɡ�T. Wedgewood��1771-1805�ˤα���Ȥϵդ��۲�ʥݥ��ˤλ���ˡ�Ǥ�����
- ��Ϥ����إꥪ����ե�����heliography�ˤȸƤӤޤ�����
- ������˥����ե���Ȥ�Ȥä��Ȥ����Τ��̯�ʼ���碌�Ǥ���
- �����ե���Ȥˤϡ��������Ƥ�ȸǤ��ʤ�Ȥ�������������ޤ���
- �������������Ѥ��ơ��̿��Ѥ���ȯ����������������Ѥθ��Ĥ���ˡ�Ǻ�äƤ��ޤ�����
- ����ӥ����������ܱ��ǰ����θ����Ǥ��� �����̿��Ѥ˱��Ѥ����ΤǤ���
- ��ϡ����å�������°�Ĥ˥����ե�����ϱդ����ۤ������Ȥä�ʪ�������֤⤫���ƴ����Ĥ˷�Ф��ޤ�����
- ʪ�Τ�����ʬ�Ϥ�������θ���ȿ�ͤ�����̤������ˤ⤿������������Ĥޤ�Τǥ����ե���ȤϸǤ��ʤ�ޤ���
- �Ť�ʪ�Τϡ���������ȿ�ͤ��ʤ���ΤʤΤǡ��Ť�ʪ�����Ϥ�������θ��Ǻ���ʤ��Τǥ����ե���ȤϽ��餫���ޤޤǤ���
- �������������ե���ȴ����Ĥ���������ή�����塢�衼�ɾ����ˤ��餷�ޤ�����
- �������뤳�Ȥˤ�ꡢ���餫�������ե���ȡʰŤ����Τ������̡ˤ�ή����������뤤ʪ�����Υ����ե�������ϸǤ��Τ�ή������ˤ������ΤޤĤ�ޤ���
- ����������ʤ��ä���ʬ�϶䤬Ϫ�Ф��������˥衼�ɤ�ȿ����ø�����Υ襦���䤬�����ޤ���
- ���������äƹŲ������ޤĤä������ե���Ȥϡ����θ奢�륳������Ϥ����ƶ��̤�Ϫ�Ф����ޤ�����
- ������������줿�����ϡ�ǻø���ºݤηʿ���Ʊ���۲�ˤʤä��ȸ����Ƥ��ޤ���
- �������ʤ��顢���δ��������ϴ��٤����������Ƥ�10���������Ϫ����ɬ�פ��ä������Ǥ���
- ��
- �ڥ����쥪�����̿���
1839ǯ8��19�����ѥ�βʳإ����ǥߡ��ǡ��륤�����������Louis-Jacques-Mande Daguerre��1787-1851�ˤ������쥪�����פμ̿���Daguerreotype�����ļ̿��ˤ�ȯɽ���ޤ���
- Ʊ��ͥ˥��ץ����٤�뤳��17ǯ�Τ��ȤǤ��� �˥��ץ��ȥ����쥪�ϡ�������˼̿��θ����ԤäƤ��ޤ���
- ���θ����ȯŸ�����ơ�����˴��٤��ɤ��Ʋ�����ɤ�����̿�ˡ��ȯ�����ޤ�����
- �����쥪�����פϡ����Ĥ�褯�ᤤ�ơ��衼�ɡ����١˾�������Ѥ����ƶ���ɽ�̤˥襦�����AgI�ˤ�������������顦���֥�����������ƻ��Ƥ��ޤ�����
- ���ƻ��֤ϡ��˥��ץ���10���֤���20-30ʬ��1/20���礤��û�̤��졢�����ä��ۤ������Ǥ�����
- ���Ƥ������ĤϿ������Ǹ������졢�����ʸ�˥ϥ��� = ����β���ʥȥꥦ��ˤ����夵��ޤ�����
- �����˶���̿����ơ�������ˡ�θ���������夬�ꡢ�����μ̿����äȤʤ�ޤ�����
- ��������ϡ���Ȥ�Ȥ���������ʲ�Ȥǡ����ʲ���͡��ʿ��ξ��������Ƥ��촶��Ф��֥�����ޡפ�ȯ���ԤǤ⤢��ޤ�����
- �������뤬����̿��Ѥ��ĤǤ���Ȥ���Τ˰�¸���ʤ������ԥ����ɤ�����ޤ���
�������뤬�������������1800ǯ����Ⱦ�ˤϡ��ե�Dzʳص��Ѥ�������ˤʤ�Ф������ǡ����ؤ���ؤ�ȯã���Ƥ��ޤ�����
- �ʳإ����ǥߡ�����Ω���ʳص��Ѥ�¥�ʺޤˤʤäƤ����Τ��ݤ�ޤ���
- �������뤬�̿��Ѥ�ȯ��������������ȯ����ɤΤ褦�˳褫��������ŷʸ�ؼԥ��饴��Dominique Francois Jean Arago��1786-1853�ˤ����̤��ޤ����� ���饴�ϡ�����ͭ̾�ʳؼԤǡ��ե�ͥ�ʤɤ�äѤʳؼԤ�ȯ�������ͤǤ��Τ��Ƥ��ޤ��� ���饴�ϡ����ȯ�����õ��Ȥ�����ν�ͭ�ˤ���ΤǤϤʤ���ï�Ǥ⼫ͳ�˼̿�����褦�ˤ��٤�������Ƥ��ޤ����� ���Τ���ꥢ�饴�ϡ����������˥��ץ��λ�¹���ե�����ܤ���ǯ����館��褦�˼��Ϥ���ä��ΤǤ���
- ���������аޤ�Фơ�1839ǯ8��19�����ե�ػα��βʳؤ�������ѥ����ǥߡ��ι�Ʊ��Ĥ��ʾ�ǥ��������ȯ������ɽ���줿�ΤǤ���
- ���Υ��ԥ����ɤϡ����θ�μ̿�ȯŸ�ˤϤʤ��ƤϤʤ�̽�����Ǥ�����
- �����������õ��ϥ����ꥹ�Ǥ�̵���ȤϤʤ餺�����ѤΤ�����õ�����ݤ��������Ǥ���
- ��ͳ�ϡ��ʲ��˽Ҥ٤륿��ܥåȤ�ȯ���������������פδ�����ȵ��Ѷ����ȯŸ���Ƥ�������Ǥ���
- ��
- ��

- �ڥ��������̿���Calotype��
- �����쥪�����ļ̿���ȯ������2ǯ���1841ǯ�������ꥹ�ο��ؼԤǤ���ȯ���ȤǤ��ä�����ܥåȡ�William Henry Fox Talbot�� 1800 -1877�ˤ������������ס�Calotype�ˤζ������������ȯ�����ޤ���
- �����Ȥ����Τϥ��ꥷ����Kalos = �����������餭�Ƥ��ޤ���
- ���������פϡ�����ʥͥ��ˤ��äƤ��줫��¿�����۲�ץ��Ȥ�Ȥ뤳�Ȥ��Ǥ����Τǡ��桹��Ĺǯ�Ƥ�����褿�ͥ��ե����θ����Ǥ�����
- ����ܥåȤ�ȯ�Ƥ����ץ��ȤǤ��뵻�ѤϷѾ����졢���������פ���3����ۤɲ��ä����硼�����������ȥޥ��Kodak�ҡ��Υ�����ե������礭����ڤ�ߤޤ���
- ����ܥåȤ�ȯ�������ߤμ̿��λϤޤ���Ȥ�����⤢��ޤ���
- �����쥪�����פϡ��ץ��Ȥ��Ǥ��ޤ���Ǥ�����
- �ºݤΤȤ����������쥪�����פΥ����ϡ�����ܥåȤμ̿���ˡ���Ǥ��ƤΤ����Ѥ�Ƥ��ޤ��ޤ���
- ���������ס�Calotype������ܥ����� = Talbotype�ˤϡ����ݼ��λ�˾˻���ο��ϱդ����ۤ��ƴ��礵�������ξ�˥襦�����ꥦ��ο��ϱդ߹��ޤ��ƥ襦����������������Τ����ٴ��礵��������˾˻��䡢�ݻ������һ�������ϱդ˿����Ƥ���ƤӴ��礵������ΤǤ���
- ����Ǻ�ä��������6cm x 6cm�ˤ�饪�֥�����������ƻ��Ѥ��ޤ�����
- ���Ƹ�ϡ��˻��䡢�ݻ������һ�������ϱդǸ������ƽ������ꥦ��դ������Ԥ��ޤ�����
- ���������פ����ȿž�����ͥ������ʤΤǡ������⤦���٥���������˥ץ��Ȥ��ƥݥ��̿������ޤ�����
- �ͥ����ݥ����̩�夵���ƴ��������Ƥ����Τǥͥ���λ����ݤ��Ǥ���ߥ����쥪�����פΤ褦�ʥ��㡼�פ��ˤϤ����ޤ�����
- ����ܥåȤϡ����������פμ̿�����������ȯ������3ǯ���1844ǯ�ˡ������ǤϤ���Ƥμ̿������ʪ�ּ����α�ɮ�ס�Pencil of Nature�ˤ���Ǥ��ޤ����� ��μ̿��ϡ��ͥ����餿��������۲褬�ץ��ȤǤ����Τǽ���ʪ��Ŭ���Ƥ��ޤ�����
- �̿����ǽ�ʪ�����Ȥʤä���ΤǤ���
- �̿��Ѥϡ��ե�ȥ����ꥹ�ǿ������椵��Ƥ����褦�Ǥ���
- �̿��Ѥϡ�1839ǯ�Υե�Υ����쥪���ǽ���Ȥ���Ƥ��ޤ���������ܥåȤϤ��������̿��μ¸���Ϥ�Ƥ��ơ�1833ǯ���ब33�ͤλ��˥����ꥢ�˿���ι�Ԥ˽Ф������ݤ˻Ȥä�����饪�֥�������������¸����̿��Ѥ�פ��Ĥ��������Ǥ���
- ���ǻ��ľ�����ʤ�Ƥ��դ������֡ʼ̿��ˤιͰƤ˼���Ȥߤޤ���
- 1935ǯ�����������פμ̿���ͰƤ��ޤ���
- ��ϡ���������������Ǥ�������ܿ��ΰ�ĤǤ�����ظ�������ޤ�����
- �̿��Ѥθ����ƤӻϤ��Τϡ������쥪���̿��Ѥ����������Ȥ�������ʹ����ľ���1939ǯ�ˤǡ���Ω������Ф���4ǯ����ȯ���������������������ޤ�����
- �ޤ�����Ω����Υϡ��������John Frederick William Herchel��1792 - 1871�ˤ�¿���βʳؼԤ���ζ��Ϥ����Ƹ����ʤᡢ1840ǯ�ޤǤ˵��Ѥ��������ޤ�����
- ����ܥåȤϡ��������̿��Ȥ������դ�Photograph��Ȥ鷺 Photogenic drawing�ʥե��ȥ����˥å����ɥ��������ˤ�ȤäƤ��ޤ�����
- ����Ȥä����ʤ������Ȥ����ռ����������ä���ΤȻפ��ޤ���
- 1840ǯ��ʹߡ��礤�˼̿��Ȥ��ֶ����ޤ���
- �ե�Ϥ������Τ��ȡ��ѹ�ˤ��äƤ⤿������μ̿������ȤȤ��ƽ��������褦�ˤʤ�ޤ�����
- ���Ľ����Ρּ̿����Ȥε��ѳ��� - ����1�ס����ܼ̿��ز��2014ǯ77��2�桧 76 - 82�ˤˤϡ��̿����������ˤ��ӥ��ͥ���¦�̤���ܤ������ޤ�����̣������ɮ����Ƥ��ޤ���
- ��β���ˤ��ȡ�1841ǯ����������ɥ�˼̿��Ȥο�����Ϥʤ���1851ǯ��51�͡�1861ǯ��2879�ͤȵ��������Ȥ���ޤ���
- 1851ǯ�ϡ����������������ब�Ǥ���ǯ�Ǥ���
- �����������̿��ϡ��Ȥ�����ϰ����ä���Τδ��٤��褫�ä��褦�Ǥ���
- �����������ȯ�������������㡼���õ��������ʤ��ä��Τǡ���ͳ�˻Ȥ����Ȥ��Ǥ��̿��Ȥ����䤹���Ȥˤʤä��Τ����Τ�ޤ���
- ��
- ��
- �ڥ����������ļ̿��ۡ�Collodion process��
�����쥪�μ̿��Ѥ�ȯɽ���줿12ǯ���1851ǯ�������ꥹ��Ħ��ȥ����åȡ��������㡼��Frederick Scott Archer�� 1813 - 1857�ˤˤ�äơ�������������ˡ��Collodion Process�ˤ�ȯɽ����ޤ�����
- ��Ʊ����˥ե�ͤ�Gustave Le Gray��Ʊ�ͤ������߽Ф����Ȥ�����Ƥ��ޤ�����
- ���μ̿��ϡ������쥪�����פ��ⴶ�٤Ǥ�������Ϫ�����֤�5�á�15�á������쥪�����פ�30ʬ�����������פ�1ʬ����
- �ޤ��������������ļ̿��ϡ�10ǯ�ۤ�����ȯ�����줿����ܥåȤΥ��������פ���٤ƻٻ��Ĥ˥��饹���Ѥ��뤳�Ȥ��Ǥ������ᡢ��������������뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ�����
- �����������Ĥϡ����������פ�Ʊ�����ͥ����ƤǤ��ä��ΤǸ��Ǥ��鲿���ץ��Ȥ��Ǥ�������ϥ��������פ����ɼ��ǰ²��Ǥ������ʥ����쥪�����פ϶��Ǥ���ѡˡ�
- �ޤ����������㡼�����ȯ�����Ф����õ��������ʤ��ä����ᡢû���֤ǥ����쥪�����פȥ��������פ���ष�Ƥ��ä��ȸ����Ƥ��ޤ���
- ���������פ�ȯ����������ܥåȤϡ�1840ǯ�塢������õ����Ф��Ƥ��ʤ�ι�ۤʻ�������ݤ��Ƥ��ޤ�����
- ����ϡ��ե�Υ����쥪�˾��Ĥ����¿�ۤγ�ȯ��ɬ�פ��ä�������ȸ����Ƥ��ޤ���
- �����������ΰ���ǯ�֡�1854ǯ - 1860ǯ�ˤ����ܤ�͢�����줿�̿����ϡ����������������פǤ�����
������������ˡ�ϡ��襦�����ꥦ�����������ϲƥ��饹�Ĥ����ۤ���������礷����˾˻�����ϱդˤĤ���Ǩ�줿�ޤޤǻ��Ƥ�����������ˡ�Ǥ���
- Ǩ��Ƥ���֤�Ϫ����Ԥ�ʤ��ȡ����٤�����ƻ��Ƥ��Ǥ��ʤ��ʤ�ޤ���
- ���٤��ɤ������Τ�ޤ���Ǩ�줿�ޤޤν����Ǥ���ΤǼ谷�����ؤǤ�����
- ����������ϴ����Ƥ��ޤ��ȹŤ�����äƤ��ޤ��Τǡ����礷�Ƥޤ�20ʬ�δ֤˻��Ƥ��ʤ���Фʤ�ޤ���
- �����ƴ����ʤ����˸����������夵���ʤ���Фʤ�ޤ���
- ���Ƥ����塢¨�¤˸���������Ԥ�ʤ���Фʤ�ޤ���Ǥ�����
- �����������collodion�ˤϡ�ȾƩ��ΰ��Ƕ��Ϥ�����Ǥ���
- �˻�����������ʥ˥ȥ������������nitrodellulose�ˤ��Ρ��� - �����ƥ뺮���ϱ�����Ϥ�������Τǡ��Ϻޤ���ȯ����������������ޤ���
- �˥ȥ�����������ϡ��ʲ����Ȥ�ƤФ���Ф���ȷ㤷��dz���ޤ���
- �����θ����Ȥ�ʤꡢ�ޤ������ȥե�����ʥ�������ɡˤθ������Ȥ�ʤä���ΤǤ���
- �������줬����������ȸƤФ���Τǡ�����ˤ�ȾƩ������������뤿�ᥳ�����ɤθ���˻Ȥ��ޤ����� ����������ϡ�Ǵ�ꤱ�Τ�����ΤǤ����������ɤ���ѿ��������줬�Ǥ����ޤ��ɤ�ޥ˥奭���κ����Ȥ��Ƥ�Ȥ��ޤ�����
- �̿��Ȥ�Ǵ�ꤱ�Τ��봶���Ĥ������ʤ������˻��Ƥ��뤿�ᡢ�����������丽���ż��϶������륳����ǽ������Ƥ������Ȥ��������������ޤ���
- ����������
- �������ɤϡ������䡢�Ͻ���������������ʤɤ����Ū�礭��γ�ҡ����ˤ�������ǰ°פ����¤��ʤ����֤Τ��Ȥ�����ޤ���
- �ؽ�Ū�ˤϡ�����������Τ���礭����γ�ҡ�10-7��10-9m�ˤ�ʪ�����ʬ�������Ȥ����ϱդ�Ʊ���褦�˶Ž������¤��뤳�Ȥʤ�ʬ�����֤��ݤľ��֤����ɾ��֤ȸ��������������Τ��ƥ������ɤȸ����ޤ���
- �������ɤΰ���Ū�������Ȥ��Ƥϡ�
- ������1�ˡ��֥饦��ư�롣
- ������2�ˡ��ɻ���̤뤬ȾƩ����̤�ʤ���
- ������3�ˡ�������븽�ݤ���
- �Ȥ�������������ޤ���
- ����������ˡ�ϡ��Ȥ����꤬�����Ȥ����Τǡ�1864ǯ�������ȥܥ�ȥ�ˤ�äƴ��祳��������ʥ��������� + ������ˤ��ͰƤ���ƥͥ�������δ�����¤�˻Ȥ��ޤ�����
- ��������������٤ƴ��٤��������㤫�ä��Τ���ڤ�ߤ뤳�ȤϤ���ޤ���Ǥ�����
- �������Ѥ�봥�����������ʥϥ����䥼��������ޡˤ��������㡼��ȯ����21ǯ�Ǹ���ޤ�����
- ��
- ��
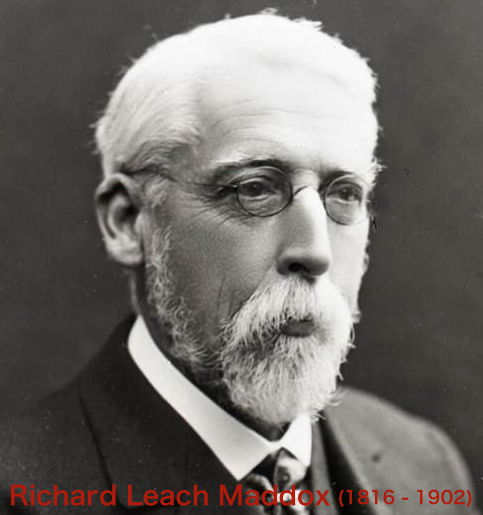
- �ڥϥ����䥼��������ޡ�
- 1871ǯ�������ꥹ�ΰ�դǼ̿��ȤΥޥɥå�����Richard Leach Maddox�� 1816 - 1902�ˤ�ȯ�������������ޤ����ʸ�ζ��������μ�ή�Ȥʤ�ޤ�����
- �̿�������ϡ����������ġ�wet plate�ˤ��鴥�������ġ�dry plate�ˤȤʤ�ޤ�����
- ����ȯ���ϡ�Maddox��55�ͤλ���ȯ���Ǥ����顢���ʤ���ǯ��ȯ���ȸ����ޤ���
- Maddox�ϡ���������������դȤ���̾���Τ��Ƥ��ޤ�����
- ���������Ƥ�ԤäƤ�����ǡ�����������������ǤϻȤ����꤬�����������Ƥޤ���������Ȥä�Ĺǯ�̿���ȤäƤ�����ϼ̿����Ѥ���ͭ�����������Ƿ��Ƥ������ᡢ�������Ǵ��ؤʴ���������νи���˾��Ǥ��ޤ�����
- ���ȯ����ȯɽ���Ť��ʤ�Τǡ����ػ����British journal of Photography�פ˥�������Ȥä����������ޤκ����쥷�Ԥ�ܤ����Τ��ǽ�Ǥ�����
- ���θ��Ƥ�̤�����Ǥ��ꡢͧ�ͤ��Խ�Ĺ�������������ǽйƤ��Ƥ��ޤä����Ȥ��ǰ�˻פ��������õ��ο����⤷�ʤ��ä������Ǥ���
- ���ȯ����������������ޤϴ��٤��㤯�ƥ��������������Ĥ��֤�������ۤɤˤϻ�餺�����������ƤΥץ졼��ʣ���˻ȤäƤ��ޤ�����
- ���������ꤹ��Τ����������Gelatin�ˤ��Ѥ����Τϡ����������ʡ֤Ĥʤ��פ�����̤�äȤ���ꤷ�Ƥ��Ƥ����ƶ�δ������Ѥ��˳����ʤ���Τ��ä����顢�ȽҤ٤Ƥ��ޤ���
- �ब����֤Ĥʤ������ϡ�����ʪ��Ǵ������ϰ� = ���������ޥˡ������ˡ��ơ����ԥ����������ʤɤǤ�����
- �Ǹ�ˤ��ɤ��夤���Τ�����������Ρ֥ͥ륽��Υ������ʴ�� = Nelson's Gelatine Granuals�פǤ�����
- ����������ޤϡ������γ�Ҥ�ϥ�����Ȳ��礵���Ƴ����������ơ������ˤ�ư���Ǥ����ϲ���ưפʥ������˺�������ΤǤ���
- �������ޤ��ٻ��Ĥ����ۤ�����Τ�������������ĤǤ���
- ��갷�����ɤ��ä����Ȥ���̿����������μ�ή�Ȥʤ�ޤ�����
- ������������������ޤν���δ��٤ϡ������������ĤΤۤ����褫�ä��褦�Ǥ���
- �ϥ����䥼��������ޤ�ȯ�����줿����ϡ������ޥ���Ĵ�礷�ƻ��Ѥ��Ƥ��ޤ�����
- �ޥɥå�����ȯɽ����2ǯ��Ф�1873ǯ���С���������John Burgess�ˤ������䥼������Ĥ��ʤȤ������䤷�ޤ�����
- ���λ��ޤǤˤϡ����٤����Ĥ��ɤ��Ĥ��Ƥ����Ȥ���Ƥ��ޤ���
- ����������ξ��ʤ��ʼ�����·���ǿ͵����Ǥ�������Ȥ����������ޤ���Ǥ�����
- ���줬��1878ǯ�����ꥹ�Υ�Хס��봥�IJ�ҡ�Liverpool Dry Plate Company�ˤΥ٥ͥåȴ��ġ�Bennett Dry Plate�ˤˤ�ä�������ȯŸ�ޤ���
- �����䥼��������ޤϡ����θ���ɤ��ä����ƹⴶ�ٲ�����ޤ�����
- �ޥɥå�������ȯ���������δ��٤�ASA/ISO 0.01���٤��ä��Τ�10ǯ�ۤɤ�ASA/ISO100���٤ޤǸ��夵�����褦�Ǥ���
- �����ꥹ�ˤ�����̿�������¤�ȼԤ��®�������Ƥ�����Wratten & Wainwright�ҡʥ���ɥ�åƥ�ե��륿����̾�����Ĥ롣���Eastman Kodak�Ҥ˵ۼ��ˡ�Britannia Works�ҡʥ���ե����ɡ������å������ˡʥ���ե����ɤδ��Ĥ�ͭ̾�����ܤǤι����ʼ���ɸ�ˤʤ�14�Ҥ˾�ä��ȸ����Ƥ��ޤ���
- 1873ǯ�Υɥ��Ĥμ̿��ȡ��̿����ؼԤΥե��������Hermann Wilhelm Vogel�� 1834 - 1898�ˤˤ��ʬ���������Ǥ�ȯ���ˤ�äơ�����ޤ��Ŀ��ΰ�ˤ������٤��ʤ��ä�������Ĥ��п��ΰ�˴��٤���ĥ��륽���Ĥˤʤꡢ������ֿ��˴��٤���ĥѥ����Ĥ���Ĺ���Ƥ����ޤ�����
- ��
- ��
�� ��ɽŪ�ե����ϡ����̸���35mm�ե�����135�����סˤ�ꥹ�ȥ��åס�����2001ǯ�����Ǥλ�����
- �ե����
- �ͥ�/�ݥ�
- ��������
- ��ħ
- ��ɽŪ�ե���ࡡ��
- ����ե����
- �ͥ��ƥ���
- �ե����
- ��
- �Ǥ����Ū�ʥե���ࡣ ȿž���Τ���ץ���ɬ�ס�
- ǻ�ٳ�Ĵ�ϥ�С�����ե������ҹ�����
- ���ե��ե���� �ͥ��ѥ�SS
- �������å�T-MAX��T400CN
- �������
- �ե����
- ��
- ���饤���ѡ�
- ���ޤ�Ȥ��ʤ���
- ��
- ���顼�ե����
- �ͥ��ƥ���
- �ե����
- �ǡ��饤��
- �Ǥ����Ū�ʥե���ࡣ ȿž���Τ���ץ���ɬ�ס�
- ǻ�ٳ�Ĵ�ϥ�С�����ե������ҹ�����
- ���̥��Ǥ����ٻμ̿��� ���ե����顼Superia 100 �ʥǡ��饤�ȡ� �������å� Gold 100
- �ʥǡ��饤�ȥե�����
- �����ƥ�
- �������
- �ե����
- �ǡ��饤��
- ���饤�ɱǼ��ѡ������ѡ� ���Ƹ������⤤�� ǻ�ٳ�Ĵ�ϥͥ��ƥ��֥ե������ �����Τǡ�Ϫ�����꤬����ƥ����롣
- �ץ��̿��Ȥ�����ǻ��ѡ�
- ���ե���������Provia 100F �ʥǡ��饤�ȡ� ���ե���������ץ��ե��å���ʥ� 64T ������II�ʥ����ƥ�� �������å��������������� ������
- EX100�ʥǡ��饤�ȥե�����
- �����ƥ�
- �������
- �ե����
- �ͥ��ƥ���
- �ե����
- ����
���פ��ʤ��������
- ��
- �������
- �ե����
- ��
- ����Ū�ʥ�����ȥե���ࡣ
- ���Ƥ������ξ�Ǽ̿��������롣
- ���ե�������ȥե���� ��FP-3000B�������Υ�����ס� ���ե��ե��ȥ�� FI-800GT ���ե��ե����Instax�ʥ������� ���ݥ������779 ���ݥ������SX-70TZ ���ƹ�ݥ�����ɼҤ�2001ǯ10��
- ����ҹ���ˡ��Ŭ�ѡ�������
- ����������Gelatin�� ��2020.05.16�ɵ���
- ���ޥ른�������ޡˤ˻Ȥ�������˥��������ޤ���
- ������֤Ĥʤ������Ǥ���
- ����ʤ���˽�����ˤ����˺����ƥ���������Υե��������ۤ����Τ��ե����Ǥ���
- ��������ˡ��ʤ�������Ȥ�줽�줬���ߤޤ������ĤäƤ����ΤǤ��礦����
- �̿������ˤ�Ҥ٤�ǡ��������ʥ����쥪�����סˤΤ�Τ϶���Ĥ˥襦�Ǥ�Ȥä��ϥ�����������Ĥ������������ʥϥ����ˤ����Ƹ���ȿ�������Ƥ��ޤ�����
- ���μ�ˡ�ϡ����Ƥ�ľ���˽�������ɬ�פ����ꡢ�����˺�ä���ΤǤϴ��٤��ʤ��ʤ껣�ƤϤǤ��ʤ��ʤ�ޤ���
- ���Υϥ�������������ˤ��ơ����Ƥ������ޤǼ��ä����֤ˤ����������ʤ��褦�ˤ����˥���������ˡ���Ԥ߽Ф��졢�ǽ�Ū�˥���������˶��γ�Ҥ�����������ब�Ǥ������ꡢ���줬���ߤޤ�������Ӥޤ�����
- �����Ϥ����ˤ�Ȥ����꤬�������������ޤ���
- ����������ޤϡ��Ȥ����꤬�ɤ��ƴ��١������ϡ���Ĵ��ͥ�줿����������Ĥä��Τ����������ޤ���
- ���ޤȤ��ƥ�����Ȥ���ޤǤˤϡ����Ҥ٤�����������䡢���Ȥ��ޤ�����
- �������ϡ�ưʪ�ι�����ʤɤ��������륳�顼������ȤȤ�˼�ʨ�����ÿ�ʬ���������륿��ѥ����ΰ��Ǥ���
- ���������������ϥ�����ˤʤäƤ��ޤ��������礷��ʴ���Ȥ�����¸���뤳�Ȥ��Ǥ���ɬ�פ˱����ƿ���ᤷ�ƥ�����ˤ��뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
- �������ˤϰʲ�������������ޤ��� ��
- 1�ˡ����ξ��֤Ǥ⿻Ʃ����̲᤹�뤳�Ȥʤ��������ɤǤ��롣
- 2�ˡ�Ŭ���ʻٻ��ξ�˥��åȤ��줿�Ȥ�����������ؤ�̵���Ƕʤ��뤳�Ȥ��Ǥ��롣
- 3�ˡ��̿������դ�ϥ�����뾽�Ȥ�ȿ�����ʤ���
- 4�ˡ�����ϱդ˿����Ƥ��Ϥ�������������ΤνŤ���10�ܤޤǤο�ʬ��ۼ����롣
- �������Τ��Τ褦��ͥ�줿�����ϡ��̿�������Ρ֤Ĥʤ��פȤ��ƺ�Ŭ�ʤ�ΤǤ��ꡢ�ϥ����������ޤ���Τ˺Ǥ�Ŭ���Ƥ����Ȥ����櫓�Ǥ���
- �������ϡ���ʬ��ۼ����ƽ��餫���ʤꡢ��ĥ���Ƥ�ϥ�����ʪ���뾽��ή�Ф��뤳�Ȥ⤢��ޤ���
- �ޤ������줬���礷�Ƥ⡢�����礭������˽̤�Ǥ��٤Ƥη뾽�䤽����б�����䡢���Ǥ⸵�ΰ��֤���뤿�ᡢ�������Ĥ���뤳�Ȥ�����ޤ���
- ����ˡ�����������ޤϷ����֤����餻���괥�礷���ꤷ�Ƥ⡢�����˷������줿�����˱ƶ���Ϳ���뤳�ȤϤʤ�������ɽ�̤�٤������뤳�Ȥ��Ǥ���ΤǤ���
- ���줬�����Ķ���ƥե�������ޤΡ֤Ĥʤ��פȤ��ƻȤ��Ƥ�����ͳ�Ǥ���
- ��
- �ڥ������ȴ��١�
- �������ϡ�Ĺ��³�����������Ρ֤Ĥʤ��פȤ���2000ǯ�ˤ�����ޤ�140ǯ���Ĺ���ˤ錄��Ȥ��Ƥ��ޤ�����
- ����������ޤˤ�봶���ब�Ǥ�������δ��٤Ϥ��ޤ�褤��ΤǤϤʤ�������ޤǻȤ����褿���������������������1��ʾ���ɹ��Ǥ�����
- ���������κǽ�Υ����쥪�����פΤ�Τϡ�1���륯�����٤β��������뤵�ˤ�����30ʬ�ۤɤ�Ϫ�����֤�ɬ�פǡ����줬����ܥåȤΥ��������פˤʤ��1ʬ��û�̤��졢����������������ˤʤ�Ȥ���ˤ���Ⱦʬ��30�äۤɤˤʤäƤ��ޤ�����
- ��������Ĥϡ��ʤ�ۤɻȤ����꤬�褤��ΤǤ����������٤ˤĤ��ƤϽ���Τ�ΤϤ���ۤ�˧������ΤǤϤʤ���1878ǯ�ѹ�Υ٥ͥåȤ���ȯ�����٥ͥåȴ��ĤǤ褦�䤯���٤�ASA/ISO 100�����ˤʤä��ȸ����Ƥ��ޤ���
- �ⴶ�٤Υ���������ޤ���ȯ�����ˤĤ�ơ����������������ˤ��̿��Ѥ���®����ڤ��Ƥ����ޤ�����
- ���ޤιⴶ�ٲ��ϡ����������ˡ���β�Ǯ��ˡ��Ǯ����ˡ = �����ȥ��ɽ����ˤˤ���ΤǤ�����
- ������ˡ�ϡ�����������ޤ���������Ǵ���Ҥˤʤ�ޤDz�Ǯ����������Ǥ��ꡢ���������˻��ߤ��Ƥ����γ�Ҥ��礭�ʲ��ˤ�����̤�⤿�餷�Ƥ����褦�Ǥ���
- �ⴶ�ٲ��ϡ����٤�32�����٤ˤ���1�������٤ν�����ܤ��Ȥ���˸��̤����ޤ�ޤ�����
- ��������������ˡ�Ǥϻ��Ȥ��ƥ���������ޤ����Ԥ��Ƥ��ޤ��Ȥ������꤬���������ᡢ�����˥����Ȥä�������������褷�Ƥ��ä��褦�Ǥ���
- �����������������ιⴶ�ٲ��ϡ�����κ������Ū��餫�ˤ��μ�ˡ����������Ƥ�����ΤΡ�Ʊ��¾�Ҥ���������ƶ�����������褦�ˤʤ��������Ȥ��ƴ����̩�ȤʤäƹԤ��ޤ�����
- ���ޥ��奢���ƹ�������������˽��ॢ�ޥ��奢�Υ��硼�����������ȥޥ����ζȳ�������Ϥ����1870ǯ��ˤϼ̿����Ѥ���餫�ǡ��ѹ�ξ���˿������������ץ�ˤ���Ƥ����Τ����Ū�ưפ˱ѹ�μ̿��Ѥ����뤳�Ȥ��Ǥ����褦�Ǥ���
- ��������ӥ��ͥ��Ȥ��Ƥ�̥�Ϥ�ޤ��㤯����̣Ū�ʰ��֤ˤ��ä��Ȼפ��ޤ���
- ����������ޤδ��٤�ASA/ISO 100���٤ˤʤä�����1882ǯ��Wratten & Wainwright�ҡˤ������������Ȥ��Ƥ��ϰ̤��Ω�������Ǥ�����
- ����ǯ�μ��Ĥȴ��ĤλȤ��������ϡ�����1���Ф��ƴ��Ĥ�140�ۤɤǤ��ä��ȸ����Ƥ��ޤ���
- 1880ǯ�夫��ϡ�������������Ѥ���ή�ȤʤäƹԤ��ޤ�����
- ���������ϡ�120ǯ���2004ǯ�ˤ��ٻΥե���फ��ASA/ISO 1600�����δ��٤����NATURA1600��Τ����β�����Ƥ��ޤ����ʤ�������2018ǯ3�����¤����λ���ޤ����ˡ�
- ��
- ����
- ���ϥ������Silver Halide��
- �ϥ�����ϡ��̿�����ʪ���μ�ή�Ǥ��� ���ߤ�������˽в�äƤ���ե����ˤϤ��٤Ƥ��Υϥ����䤬���äƤ��ޤ���
- ����ե����⡢���顼�ͥ��ե����⡢���顼��С�����ե����⡢���٤ƤΥե���ശ����ˤϤ��ζ�°��γ�Ҥ����äƤ��ޤ���
- �ϥ�����ϡ���ȱ��ǡ��襦�ǡ����Ǥʤɥϥ����鹽���������Ǥ���
- ���������ϥ�����ϡ���ȥϥ������ľ�ܷ��ˤ�äƷ������뤳�ȤϤǤ��ʤ��Τǡ��˻��˽����Ϥ����ƺ�ä��˻����AgNO3���ϱդȡ��������ꥦ���KBr�ˤ�����ʥȥꥦ���NaCl�ˤΤ褦�ʥϥ�����ʪ���ϱդ礷�ƺ���ޤ���
- ���β��ؼ��ϰʲ����̤�Ǥ��� ��
- AgNO3 + KBr��→��AgBr↓ + KNO3
���μ��Ǽ����줿����������ʪ��AgBr�ˤ���γ�ҤǤ��ꡢ����γ�Ҥ��礭���ˤ�äƴ��٤�����٤����ꤵ��ޤ���
- �ϥ���������դ��٤����Ȥϡ�����Ĥ����֤ޤǿʹ֤��ܤ�Ʊ���褦����Ĺ���٤���äƤ��ʤ����ȤǤ���
- �ϥ����䤽�Τ�Τϡ��糰�������Ŀ��ˤ������٤�����ޤ���
- ����ǤϺ��롢�Ȥ����Τ��ֿ��˴��٤�������뵻�ѳ����Ԥ��ޤ�����
- �̿��ν���Τ�Τϡֿ��աפ��ä��ΤǤ���
- ���ߤǤ⡢���˴ط����ʤ�ǻ�٤����Υץ��Ȥ���������ˤϡ��֤˴��٤�����ʤ��ϥ����䤽�Τ�Τ���Ѥ��Ƥ��ޤ���
- ���äơ��ż��Ǹ�����Ȥ����ֿ����פβ��Ǹ���������ԤäƤ⥫�֤�����ʤ��ΤǤ���
- �ϥ����䤬���Τ褦����Ĺ��¸���ä����������Ǥ��뤿��ˡ����ޤ�������ʬ�������ޤ�ź�ä����ֿ��ΰ�ޤǴ��٤�夲�빩�פ��ʤ���ޤ�����
- ����ͥ��ե����ϡ����Τ褦����ͳ���顢5����ۤɤΥե���ब��ȯ����ޤ�����
- �����ޤȤ��Ȱʲ��Τ褦�ˤʤ�ޤ��� ��
- 1.���쥮��顼��Regular�ˡ�
- ����δ�����ǡ�������non color sensitive�ˡ������������Ĵ�����blue sensitive�ˡ����������ʤɸƤФ�Ƥ��ޤ���
- ���Υե����δ����ΰ�ϡ��糰���硢�ġ��ڤ��Фΰ����Ǥ���
- ��˱Dz�Υݥ��ե���ࡢ������ɥե���ࡢ����ʣ���ѤΥץ������ե���ࡢX���ե����˻Ȥ��Ƥ��ޤ���
- ���δ������Υե����ϰ��̤λ��Ƥˤ��Ը����Ǥ������ż������뤤�ֿ�����������Ѥ��뤳�Ȥ��Ǥ���Τ� ��Ȥ����䤹���Ȥ������åȤ�����ޤ���
- �ޤ����δ��������¸������äȤ��ɹ��Ǥ���
- 2.�����륽����������Ortho chromatic�ˡ�
- �����ϰϤϡ��糰���硢�ġ��С������ޤǤǡ��ֿ��ˤϴ��٤���äƤ��ޤ���
- �����о�ʪ���ֿ��ΰ��ɬ�פȤ��ʤ����˻Ȥ��뤳�Ȥ�����ޤ��� ���δ������Ȥ��С����������ֿ���������Ȥ����Ȥ��Ǥ���ΤǸ����������°פˤǤ��ޤ���
- �����Ѥδ��Ĥ䥷���ȥե���������ƻȤ��뤳�Ȥ��ʤ��ʤ�ޤ�����
- 3.���ѥ�������������Panchromatic�ˡ�
- �糰�����ֿ��ޤǤ��٤ƤβĻ���ˤ錄�äƴ��٤���Ĵ�����Ǥ���
- ����ե����Ϥ��٤Ƥ��Υ����פΤ�ΤǤ���
- �ѥ��Ȥ��äƤ����ˤϣ���B��C�Ȼ��������̤��Ƥ��ޤ�����
- A���Ͻ���Υѥ��Τ��Ȥ��п����Ф��봶�٤��㤯���֤��Ф��봶�٤��㤤��ΤǤ�����
- B���ϥѥ��ΰ���Ū�ʤ�Τǿʹ֤δ����ˤ�äȤ�ᤤ��ΤǤ���
- B���Τ��Ȥ륽�ѥ��Ortho Pan�ˤȤ�Ƥ�Ǥ��ޤ�����
- C���ϡ��ʲ��ǽҤ٤륹���ѡ��ѥ�Τ��ȤǤ���
- 4.�������ѡ��ѥ��Super Panchromatic�ˡ�
- �ѥ�����Ǥ��ä��ֿ����˴��٤��ɤ�������Ǥ���
- ���ä��������ʥ����ƥ���סˤˤ��������μ������ʤλ��Ƥ�Ŭ���Ƥ��ޤ�����
- ���ΤΥե����Ǥϡ��ٻΥݡ��ȥ졼�ȥѥ��ʤɤ�����ޤ�����
- 5.���ֳ��ѡ�Infra-red sensitive�ˡ�
- �ֳ��ʥԡ�����Ĺ750nm�ˤ˴��٤��ä���������ü���Ѥ˻Ȥ��ޤ�����
- ���δ��������ħ����¸��̿��û�������֤��������Ǥ�����
- ��ư�֤�®�ټ����ѥ����Υե����Ȥ��ƻȤ��ޤ�����
- ��
- ����С�����ե�����Reversal Film��Negative Film��
- �̿��ե����θ���������ͥ��ƥ��֥ե����Ǥ�����������黺�Ȥ�ȯŸ���Ƥ��������Ǥ��������ʥ����פΥե���ब��ȯ������Τ���ޤ�����
- ���Ƥ����ե����Τޤ������Ȥ����ʤ虜�虜�ץ��Ȥ��˥ե�����ľ�ܸ������Ȥ�������˱������Τ���С�����ե����ȸƤФ���ΤǤ���
- �ޤ�������3����ʬ���Ƶ�Ͽ����ȥ��顼��Ͽ���Ǥ��뤳�Ȥ��顢���顼�ͥ��ƥ��֥ե���ब��ȯ���졢���θ奫�顼��С�����ե����ؤȿ�Ÿ���ޤ���
- �� �� ��
- ���ե����Υ���������2001.01.09�ˡ�2009.11.23�ɵ���
- �ե����δ��ܤϾ嵭�˽Ҥ٤��̤�Ǥ��������Υե����γ����ϼ¤��͡��Ǥ���
- ����������餬�ФƤ��뤿�Ӥˤ�����ʥ����פΥե���ब����ޤ�����
- �ǽ�ϡ����饹�ĤǤ��ä�������Ĥ��顢�����䤹������������ϤΥե������Ѥ�ꡢ����˰��٤ˤ�������μ̿��������褦�˥����Ⱦ������������Υե������Ѥ��ޤ�����
- �ǽ�Ū�ˤϡ��ѥȥ����������35mm�ҥ�����ե���ࡢ�����60mm�Ҥι�������줿�֥����ˡ���Brownie�˥����פΥ�����ե���ࡢ4 x 5 ������Υ����ȥե���ࡢAPS�����ȥ�å��ե���ब�Ծ�˽в��ޤ�����
- �����ե�����ֹ�
- �ե����Υ����פ��ֹ��ɽ���������ϡ�������ե��������˹���ƹ����ȥޥ����å���Eastman Kodak�˼Ҥαƶ����礭���褦�Ǥ���
- ���������ϡ����Ĥλ�����ƹ���⥤���ꥹ����������Ǥ��ä��褦�Ǥ�����1891ǯ���������ȥޥ����å��Ҥ��������ե���बȯ�䤵��ư��衢�ƹ�Υ����å��Ҥ����ΤȤʤä��罰���Ϥ����줿������ե���५��餬ȯ�䤵���褦�ˤʤ�ޤ�����
- �����å��Ȥ����ȡ��ե�������Ȥ������������������ޤ��������β�Ҥϼ̿����ƤΤ���Υ����ȥե���ࡢ����˸����ץ������Τ���Υ��ߥ�������äƤ��ޤ�����
- �����å��Ͽ������ӥ��ͥ��λ�ߤȤ��ơ��ޤ��ե�����ͤ������Ҥ����䤷���Ҥ����Ƥ����餽�Υ����������֤��Ƥ�餤���ե����θ����ȥץ��Ƚ����ơ�����˿������ե�����ͤ�ƥ桼���������֤��Ȥ��������ӥ��������ǽ��ƹԤ��ƹ�ǵ���Ĺ��̤����ޤ���
- �ޤ���������ʥ����פΥ������äơ��������٤��Υ����˻Ȥ��ե����뤷�Ƥ��ޤ�����
- ���塼�����Υ����ϡ��Dz��ѥե�����û���ڤäƥѥȥ����ͤ����줿�饤���������Υ���餬1925ǯ�˥ɥ��ĤǺ��졢���������ȶ��ˡ�������ή�줬�ɥ��Ĥ˰ܤꡢ������ܤ˰ܤäƸ��ߤ˻�äƤ��ޤ���
- �ե����ϡ��ƹ��å��Ҥ��Ǥ��϶����ȳ������ƤϤ�����Ρ��������ƥ��륫�����ä��ɥ��ĤǤϥ����ե��ҡ�Agfa: 1864���ȥ٥륮���Υ��Х�ȼҡ�Gevaert:1894 �ˤ��ե������äƤ��ޤ�����
- �ޤ����ѹ�Ǥϥ���ե����ɼҡ�Ilford: 1879�ˡ����ܤǤϾ���ϻ��1873�ˤ��ٻμ̿��ե�����1934ǯ��1919ǯ��Ω�������ܥ�������ɤ���ʬ�Ҳ���2006ǯ�ٻΥե����ˤ�����Ū�˥�����������������¤���Ƥ��ޤ�����
- �����å��ϡ�1890ǯ���ꥫ��顢�ե���ࡢ�������ץ��Ȥ���˰��������Ƥ��ޤ�������1910ǯ��ɥ��ĤΥ���餬����Ū������褦�ˤʤ�ȡ������˥ե�����ͤ�Ƥ��Ҥ��Ϥ����䤫�顢�ե������������䤹��ӥ��ͥ����ò�����褦�ˤʤäƹԤä�����������ޤ���
- �ѥȥ����͡�patrone�ˤȤ����Τϥɥ��ĸ�Ǥ��ꡢ�Ѹ�Ǥ�film cartridge�ȸ����ޤ���
- 1895ǯ�������å����ե�����ֹ�101�֤�Ϳ���ư��衢ǯ���Ȥ�1-3����Υե���ब���������졢20ǯ�֤���30����Υե���बȯ�䤵�줿�ȸ����ޤ���
- �����Ȥˡ���������Ф��줿�ե����μ���ϡ��ե���ब�ǽ�ˤǤ����ΤǤϤʤ�������餬�ǽ�ˤǤ��Ƥ�����碌��褦�˥ե���ब�Ǥ��Ƥ��ä�������Ϳ���ޤ���
- ����ۤɥե����γ�ȯ�ֹ�ȥ������ˤϤʤ��̮���⤢��ޤ���Ǥ�����
- �����ե����Υ�����������2009.11.23����
- �ե����Υ������ϡ��̿��������ꥹ�ȥ���ꥫ���濴�ˤ���1880ǯ�夫��1960ǯ��ޤǥ��Ū������̤����Ƥ����Τǡ�������Ǥ���ˡ�Ȥʤä��ΤϤ褯����Ǥ��ޤ���
- �����������ʤΤ��������˥�ȥ�å��ʥߥ���ˡ�ˤ��������줹��ΤǺ��𤷤ޤ���
- ����̿��ϡ���Ȥ��1830ǯ��˥ե��ȯ������ޤ������������Ȥȸ��ع��Ȥ�ͥ��Ƥ��������ꥹ�������ȥ����夲�ޤ���
- ����������ȯŸ�ϥ����ꥹ���ɤ��Ȥ������礭�����������Ȥ�ȯã���������ꥹ�ϥ����������ˤ��ꡢ�������ͥ���ʤ�Τ���夲�ޤ���
- ���������ϡ������̿��Ȥ���ʬ�Ǻ�äƤ��ޤ�����
- �̿������ʲ����ƥ����˹�碌�ƾ��ʲ������Τϡ�����ꥫ�Υ������ȥޥ��å��ҤǤ���
- �̿������̾���������������Τϡ������å��ҤΥ�����ե����Τ������Ǥ��礦��
- ��������ꥫ�Υ��������
- ����Ū�˺Ǥ�褯��줿�ե����ϡ�35mm�ҤΥ�����135�Ȥ����ѥȥ����ͥ������Τ�Τ��Ȼפ��ޤ���
- 35mm�Ҥϡ��������ȥޥ��������Τ���˺�ä��Dz�ե����1-3/8������ҡ� = 34.925mm�ˤ�����Ƥ��ޤ���
- �������ȥޥ�ˤϡ�������2-3/4������ҡ� = 69.85mm�ˤΥ�����ե���ब���äơ�ư�軣�Ƥ�Ȥ��ˡ����Υե����ҤǤ��礭������Τ�Ⱦʬ�ζҤˤ��ޤ�����
- ����˲ä��ơ�ξü�˥ե��������뤿��ι��ʥѡ��ե��졼�����perforation�ˤ��ߤ��ޤ�����
- �ʥѡ��ե��졼�����ϡ�����ϥ������ȥޥ�Ǥ����줺�˥桼�����ԤäƤ����褦�Ǥ���
- �ե���೫ȯ����ϡ���������Ҥ����Ƥ����ˤ���ԤäƤ����褦�Ǥ�����
- �ѡ��ե��졼�����ϡ�3/16������� = 4.7625mm�ˡʸ�ε��ʤ�4.750mm�˴ֳ֤Ƕ������ޤ�����
- 4��ʬ�Υѡ��ե��졼�����Υ��ڡ����˰���β����ʥե졼��ˤ�����褦�ˤ��ޤ�����
- 1��β��̥������ϡ���3/4������� = 19.05mm�� x ��1������� = 25.4mm�ˤǤ����� �IJ���3��4�Ǥ���
- ���줬�Dz�ե����ȱDz襵�����ε��ʤȤʤ�ޤ������ʤ����40ǯ��˻Ϥޤ�ƥ�ӥ����β��̤νIJ���Ȥ�ʤ�ޤ�������
- �Dz�ե����ϡ�1�ե�����Ĺ��64�ĤΥѡ��ե��졼���������줿�Τǡ�4��ʬ�Υѡ��ե��졼�����Ǻ����ե졼�� ��1�ե�����16��Ȥʤ�ޤ�����
- �����αDz�ϡ�16����/�äǻ��ƻ��Ƥ���Ƥ��ޤ������顢1�äλ��Ƥ��פ���ե�����1�ե����ȤȤʤꡢ�ե����ξ����̤Ȼ��ƻ��֤ϴ�ñ�˴����Ǥ��ޤ�������1930ǯ����ȡ������λ���ˤʤ�ȡ�����������塢����®�٤�24�ե졼��/�ä˾夲���ޤ�������
- �Ť������ޥ�ϡ����ƻ��֤Τ��Ȥ�ܿ��ʤ��㤯�����ˤȸƤ�Ǥ��ޤ�����
- �ܤϡ����ܤμܤǤʤ��ѹ�μܤ�1�ե����ȤǤ���
- �Dz�ե����ϡ�100�ե����ȴ���30.3m�ˤ�400�ե����ȴ���121m�ˤ���ή�ʤΤǡ����줾��100�á� = 1ʬ40�áˤ�400�á� = 6ʬ40�áˤλ��ƻ������̤��ä����Ȥ��狼��ޤ���
- ����
- �����ե�Υ�ȥ�å�����
- ����ꥫ�Υ��������Ʊ�����ˡʼºݤˤ�1ǯ�٤�ǡ˥ե���륤�����ߥ�������Ʊ�������פαDz襫���ȱǼ̵�����ޤ�����
- �ե�ϥ�ȥ�å��ι�Ǥ����顢��ˡ���ʤϥ�ȥ�Ǥ���
- ���äơ���餬��ä������ϥ�ȥ�å����ʤǺ���ޤ�����
- �ե����ϡ������ƹ�Υ������ȥޥ��å��ҤΤ�Τ��ʼ����ɤ��Ƥ�������в�äƤ����Τǡ������ή�Ѥ����Ȼפ��ޤ���
- ������������ˡ�ϡ���ȥ��ľ���ƽ�18mm x ��24mm��3��4�ˤȤ��ޤ�����
- ����������ͳ���顢�Dz軺�Ȥϡ����ϥ�����Ǥ���ˡ�ˤ�äƵ��ʤ������ʤ���⡢��������ˡ����˥�ȥ�å����Ȥ�줿�ꡢ������Ǻ��줿���ʤ���ȥ�å��Ǵݤ��줿�ꤷ�ޤ�����
- �ե���ब��ݵ��ʤˤʤä����⡢�䡼�ɥݥ��ˡ���ƹ�ȱѹ�ȥ�å�ˡ�Υե���ɥ��ĤǷ㤷�����Ȥ꤬���äơ������ϥ�ȥ�å��Ǵݤ��줿��ʥե����ζҡˡ������ʥѡ��ե��졼�����Υԥå��ˤϥ�����Τޤޤǵ��ʤˤʤä��褦�Ǥ���
- 35mm�Ҥ��Dz�ե�����������ή�Ѥ����Τ���1913ǯ�ǡ��ɥ��ĥ饤�ļҤ����������Х�ʥå��Ǥ�����
- ���Υ����β��̥������ϡ�8�ѡ��ե��졼������1���̤��������24mm x ��36mm�ʥ饤���������ˤȤ��ޤ�����
- ���Υ饤���������ǡ������̿����Υե�����120�֥����ˡ��ե���फ��135�ѥȥ����ͥ����פΥե������Ѥ�äƹԤ��ޤ�����
- ���� �� ��
- ���������ʥ�������ɡ�Celluloid��
- ������ե����˻Ȥ�줿��������ɡ�Celluloid�ˤϡ�1862ǯ�˱ѹ�Υѡ�������Alexander Parkes�� 1813 - 1890�ˤ��˥ȥ�륻��������� = NC��Cellulose Nitrate�ˤ���ˡ��ȯ�������õ���������Parkesine�ʥѡ�������ˤ�̾�դ��ޤ�����
- ���ؼ���κǽ�����ʤȸ����Ƥ��ޤ���
- 1869ǯ���ƹ��ȯ���ȥϥ���åȷ����John Wesley Hyatt��Isaiah S.Hyatt��1837 - 1920�ˤ���Ʊ��Τ�Τ�����ɤ�̾�դ�����������ƻ���ޤ�����
- �ϥ���åȤϡ��ӥ�䡼�ɵ���¤������ޤ˱��礹�뤿��˥�������ɤ�ȯ�������Ȥ����ޤ���
- �ѹ�ͥѡ������λ��Ȥ�2ǯ�ۤɤǼ��Ԥ������������Ѥ����ѹ�μ¶Ȳȥ��˥��롦���ԥ��Daniel Spill�� 1832 - 1887�ˤβ�Ҥ�1874ǯ���٤�Ƥ��ޤ��ޤ���
- ��ɡ��ϥ���åȤ���������ɹ���бĤ�����������ΤΡ��ݻ�������ҤΥ��ԥ�Ȥδ֤��õ��˴ؤ��ƺ�Ƚ�ˤʤä��ȸ����ޤ���
- ��������ɤϡ��˥ȥ�������������ɼ����������ݤ������������ˤ����Ȥ��Ƥ���˾�Ǿ������ޤȤ��ƾ˲�������Ǯ�������ץ饹���å��Ǥ���
- ��ˡ���������ɤ����ᡢ�٤ùä�ݲ������˻Ȥ��ޤ�����
- �䤬�Ҷ��κ���1960ǯ�塢�����������ʤ�������ץ饹���å��μ��ब�����ˤʤ��ä����ϡ����ؼ���ȸ����Х�������ɤ��١����饤�Ȥǡ���������ɤϲ��ߤ���ɮȢ���������ԥ�ݥ��ʤɤ˻Ȥ��Ƥ��ޤ�����
- �������������̤��ơ����ܤΥ����������������������ä��ȸ����Ƥ��ޤ���
- ��������ɤ������ɤ�dz���ơ����줿ɮȢ�䲼�ߤ���Фˤ������������褯dz�����Τ�Ф��Ƥ��ޤ���
- �� ��
- �����ǽ�Υե���ࡡ-��Geoge Eastman �ڥ��硼�����������ȥޥ��
���ο������������ܤ�Ĥ����Τ�����ꥫ�ͤΥ��硼�����������ȥޥ��Geoge Eastman��1854-1932�ˤǤ���
- ��ϡ��˥塼�衼����Watervile, New York�ˤ��Ϥ����Ȥ����ޤ�ޤ���
- 14�ͤǥ������������θ�Ω�ع���´�Ȥ��ơ��ݸ���Ҥȶ�Ԥ˶Ф�����ޤ�����
- ��μ���������ϡ���̳����ޤǤǤ�����
- ��ȼ̿��νй礤�ϡ��ɥߥ˥����¹�μ��ԥ���ȡ��ɥߥؤ�ι�Ԥ�ײ褷���ݤˡ�ͧ��������ι�Ԥμ̿���Ͽ��褦�ˤ������줿���Ȥ����ä����Ǥ�����
- ���ʤ饹�ޡ��ȥե���˥���餬�Ĥ��Ƥ���ΤDz��������ʤ��ΤǤ�����ɡ�1870ǯ����������������������������̿���Ȥ����Τ��¤�����Τ��ȤǤϤʤ��������ץ��åȤ�Ʊ�����餤�Τ����Ф뻣�Ƶ���ȴ���������Ĵ�礹�����ޤ丽�������ޤʤɰ켰���������ɬ�פ�����ޤ�����
- ��Ϥ��Τ��Ȥ������Ǽ̿��ˤΤ�����Ǥ����ޤ���
- ��Ϥޤ����̿��Ȥ�����Τ����ٶ���Ϥᡢ1����5�ɥ�μ�������ʧ�äƼ̿��Ѥ�ؤӤޤ�����
- ��Ϥ���Ф결�Ǥ⤢�ä��褦�Ǥ���
- ��ɡ��̿��ˤΤ����߲��ι�Ԥ뤪���̿����ٶ��˻ȤäƤ��ޤä��Τǡ�ι�Ԥ����ᤶ������ʤ������ˤʤäƤ��ޤ��ޤ�����
- �������ȥޥ�ϡ�Rochester Saving��Ԥ��������Ȥ��ƶФ��˵�顢�����ɥӥ��ͥ��Ȥ��ƶ�Ԥ���������壳��������ī��ī�����֤ޤǼ̿���������¤����Ƥ��ޤ�����
- ������1870ǯ��ˤμ̿��Ѥϱѹ��ǤƤ��ޤ�����
- ����ܥåȤ��ͥ�������ʥ��������ס���ȯ�����顢�������㡼���������������������ޥɥå������ϥ��������������������ˤ�����ޤǡ����٤Ʊѹ�ͤˤ�äƼ̿��Ѥ�ʲ������Ƥ��ޤ�����
- ����ȡ������ꥹ�ε������Ȥȸ��ص��ѡ�����˽��ǵ��Ѥ��礭�ʷкѵ����⤢�äơ������μ̿����ȤϱѹǤ⽨�ǤƤ��ޤ�����
- ����饤���ꥹ���Ϥˤ�äơ�����ʥ����ʤȥ�ˤ�����Ƥ��ޤ�����
- ���硼�����������ȥޥ�ϡ������ε��Ѥ���Ƴؤ�Ǥ����ޤ���
- ���������ȼ̿��Ѥ˴ؤ��Ƥϡ������μ��ν�������餫�ǡ�����ʪ����߱��������������Ѥ�������Ƥ����褦�Ǥ���
- ���ޥ��奢�Υ��硼�����������ȥޥ�ϡ���British Journal of Photography�פʤɤν�ʪ������μ���ۼ����Ƥ��������Ǥ���
- ���Τ褦�ˤ��ơ����硼�����������ȥޥ�ϡ����饹�Ĥ˥���������ޤ��ɤä����Ĥ���¤���������ޤǤ˼̿��ˤ������Ϥ���ޤ�����
- 1881ǯ���ब27�ͤλ�����Ԥ��Eastman Dry Plate Company����Ω���ޤ���
- ��δ��IJ�Ҥ��˾����ޤ�������Ʊ�ȼԤ�������ˤĤ쾭����Ф����¤�Ф���褦�ˤʤ�ޤ�����
- ��äȻȤ��䤹���̿����������˰㤤�ʤ���
- ��ϫ�ͤΥ������ȥޥ�Ϥ����ͤ��ޤ�����
- ��
- �ڥ�����������碌�Υե��������ӥ��ͥ���
- �����ǡ������Ӹ�����ӤƤ�����������¤����Υ�������ɤ��ܤ�Ĥ��ơ����饹����ȤäƤ��������ٻ��Τ����֤��������ʤ����ȹͤ��ޤ�����
- �����ơ���������ɤ˴���������ۤ��ƥ�������ˤ���������ե�����ȯ�Ƥ��������ɬ�פʥ������ä�1888ǯ���������Ϥ�ޤ�����
- ���饹�ǤǤ��������Ĥϻ������Ӥ����ؤǡ����������Ǥ�����
- ����ʥ�����Ȥä��̿����Ƥ�����ե�����ȯ���ˤ�ä��罰�λ���ʪ���Ѥ��褦�Ȥ����ΤǤ���
- ��������������ե�����ȯ�����Τ�ΤǤ���Υӥ��ͥ��ϥ֥졼�����ޤ���Ǥ�����
- ��Ϥ����ǡ��⤦�칩�פ��ޤ�����
- 100��ʬ���ƤǤ��������ե�����ͤ���������䤷�����Ƥ�����ä��饫��餴�����äƤ�餤�����ȥץ��ȤƺƤӿ������ե�����ͤ�����Ȱ��������֤��Ȥ��������ƥ��ͤ������ޤ�����
- ������礤��������ޤ�������ϡ� ��
- "You press the button, we do the rest"�� - �����ʤ��ϥ����Υ���å�����������ϻ�ã�����ޤ���
- �Ȥ�����������������ơ���Kodak Camera�פ��硹Ū�����������䤷�ޤ�����
- ���Υ����ȥե��������ץ��ȥ����ӥ���ά�����������������å���̾�������������Τ��Ϥ�褦�ˤʤ�ޤ�����
- ���Υ����ϿƤ��ߤ����ơ���the Kodak�פȸƤФ��褦�ˤʤ�ޤ�����
- ��Kodak�μ�̾��
���Υ����ƥ�������ά�κݡ���ϼ�ʬ�β�Ҥ�Ǥ�ɰ�������Ƥ�̾���Υ��˥�����K�٤��ꡢ�Ƥ��ߤ䤹��̾���Ρ�Kodak�٤Ȥ�����ɸ�ˤ��ơ�1892ǯ��������������Rochester, New York�ˤ��Ϥ� Eastman Kodak Company ����Ω�����Dz��ѥ�����ե����ޤǼ�ݤ���褦�ˤʤ�ޤ���
- �����å���̾������ư�Τ�Τˤ����Τϡ�1912ǯ�����Ф����٥��ȥݥ��åȡ������å��ʺ��̿���Vest Pocket Kodak�ˤǤ�����
- ���Υ����ȥե����������ˤ�ꡢ�����å���̾�������������Τ��Ϥ�褦�ˤʤ�ޤ�����
- ���Υ����ˤ�127�֤Υ�����ե���ब�Ȥ��Ƥ��ơ����Υե����Τ��Ȥ�٥��ȥե����ȸƤӡ����̥�������4cm x 6.5cm�Ǥ��ä����Ȥ��餳�Υ�������٥��ȥ������ʥ٥���Ƚ�ˤȸƤ�Ǥ��ޤ�����
- �٥��ȥ����ϡ����ɡʥ٥��ȡˤΥ����Ȥ�����̣�ǤϤʤ����٥��ȡʥ���å��ˤΥݥ��åȤˤ�ڤ�����Ȥ����Τ�̾�դ���줿̾���Ǥ���
- ���Υ����ˤ�äơ��̿��μ��פ���̤Υ��ޥ��奢�ޤǹ���ȸ����Ƥ��ޤ���
- ��
- ���õ���ġ�
�����å��Υ�����ե����ϡ������Τ��Ȥʤ����õ�����������䤷�Ƥ��ޤ�����
- �������������ԥ����ɤ�����ޤ���
- Eastman��ȯ������������ե����ϡ��¤�Kodak��������ե��������䤹��1ǯ����1887ǯ���һ�Hannibal Goodwin��1822 - 1900�ˤˤ�äƤ��Ǥ�ȯ������Ƥ��ơ��õ������⤵��Ƥ����ΤǤ���
- 65�ͤ��һ�Goodwin�ϡ����˳ع��ǥ��饹���Ĥ˽줿����������Υץ����������˱Ǥ��Ƽ��Ȥ�Τ�Ǥ��ޤ������������ݤ������Ȳ���Ū�μ��Τʤ��ޤ�����Ҷ��ǻ�Ժ�����̤��������Ʃ����������ɥե�������Ф��ޤ�����
- 1869ǯ�Τ��ȤǤ���
- ����õ���дꤷ�ޤ��������ν���ϲ���Ū�ʺ����⤿�ʤ������ޤ��ʽ�����ä��褦�Ǥ���
- �����å��Ϥ����õ����ΤäƤ��Τ餺������ȱ�����줺���õ��������ơ���¤�����Ω���夲���ȡ��ޥ�����������Dz��ѤΥ�����ե���೫ȯ����ʸ�ޤǼ����ƻ��Ȥ���礷�ޤ���
- ����Goodwin�ϡ�������ե�����������ˤ�������⤬�ʤ������ͤ�Ω���夲Ⱦ�Фǻ��Τˤ����Ǥ��ޤ��ޤ���
- ��λ�塢�˥塼�衼���ˤ���Anthony & Scovil�ҡ�1907ǯ��Ansco�ҡˤ��õ�������Ѥ��ǥ�����ե�������¤��Ϥ�ޤ���
- ��Ʊ���ˡ������å�������ä�1902ǯ����õ������ʾ٤�Ϥ�ޤ���
- �����ʾ٤�12ǯ��Ĺ�����Ϥä�³�����ǽ�Ū�ˤ�Goodwin���õ������������å�������������Ƥ������ȡ��õ����Ƥ��ˤ�ƹ�����Ƥ��뤳�Ȥ��饳���å������ʤ˽���ꡢ500���ɥ�������λ�ʧ����̿�����ޤ�����
- ��Ƚ���餱�������å��Ǥ����������κ��ˤϥ����å��ϻ��Ȥ����������Ƥ��ơ�������ե����ȸ����Х����å��ȸ���줯�餤�����Ȥ���Ĺ��������٤ߤ��ۤ��夲�Ƥ����Τǡ���Ƚ�˾��ä��������ˤ���Ansco�Ҥ������å��Υ饤�Х�ˤʤ뤳�ȤϤ���ޤ���Ǥ�����
- ��
- ��Kodak������
- ���Ҥμ�Ĺ�Ȥʤä��������ȥޥ�ϡ�����β�Ҥ�����ݸ����ǯ�⡢��̿�ݸ��ʤɤ�ʡ��������ɤ��β�Ҥ����Ƴ������¿���κ��ޥ����塼���åĹ�����ؤ��±��˴��դ��Ƥ��ޤ���
- �����¿���ΰ�ѻ��Ȥˤ�¿�ۤδ��դ�ܤ������餬�������ʤ��ä��ع������¿���οͤ˼����Ƥ�館��褦�ˤ��ޤ�����
- ��������ȿȤΤޤᤴ�����οꤨ����77�ͤ�ǯ��1932ǯ�ˡ�
- �ּ�ʬ�λŻ��Ͻ���ä�������ʾ�����Ĺ�館�ƻ���Ԥİ�̣���ʤ�����
- �Ȥ�������Ĥ����ԥ��ȥ뼫�����������ޤ�����
- ����
- �ڥӥ��ͥ��Ȥ��Ƥμ̿��ȡ� ��2020.08.26�ɵ���
- �ե����Ȥ�����Ū�ʰ�����Ȥ˲����夲���������ȥޥ�ϡ��̿��Ѥ����Ǥʤ�¿���̤ˤ錄��ӥ��ͥ��κ�ǽ��ȯ������ʬ�β�Ҥ�����Ȥ˲����夲�ޤ�����
- �̿��ϤȤƤ�̥��Ū�ʻ��Ȥǡ�1800ǯ���Ⱦ����1900ǯ����Ϥä�¿���ο�ã�����Υӥ��ͥ��˻������������ᤷ�Ƥ��Ƥ������Ȥ��������������ޤ���
- �������ȥޥ�Ϥ������������Ҥ��Ǥ����äơ������Ҥ��ɤ��Ĥ��ʤ��ۤɤ��ʼ��Ⱦ��ʤ�ȯ�����б�Ū�ˤ����Ф������������˿�������ƹԤ��ޤ���
- �ä˱Dz�ե����˴ؤ��Ƥϥϥꥦ�åɤΤ�ɨ���Ȥ������Ȥ⤢�ꡢ����Ū�ʻٻ������Ƥ��ޤ�����
- �䤬�̿����ܳФ20�ͤκ���1970ǯ��ˡ��ե������ʼ��ϥ����å������ȴ���Ƥ����褦�˴����Ƥ��ޤ�����
- �Ҳ�ͤˤʤäƲʳؼ̿��˷Ȥ��褦�ˤʤ�ȡ�Kodak�μ̿��˴ؤ��뵻�ѻ������ȤƤ⽼�¤��Ƥ��뤳�Ȥ˶ä��ޤ�����
- 1979ǯ��ȯ�����줿 Ensyclopedia of Practical Photography by Eastoman Kodak����14�����Ѹ��ǡˤϡ������å����ޤȤ�̿��˴ؤ���ɴ�ʻ�ŵ�Ǥ���
- ���ۤˤ��������Ω�����ۤˤ��줬���äơ����֤Ĥ��ƤϤ��ο�ۤ��̤äƤ��λ�ŵ���äƤ��ޤ�����
- ���λ�ŵ�ϱѸ��ǤǤ��ä����ᡢ���ܸ줬�Фʤ������Ԥ���ӤƤ����Ȥ�����1981ǯ�˹��̼Ҥ���̿���ɴ�ʡ���10������˰��ȯ�����ǽ�����1982ǯ5��ˤ�ȯ�����줿�Τǡ�������㤤���뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ�����
- ���ܸ��Ǥϡ��Ѹ��Ǥδ��������ǤϤʤ����ܤμ̿��Ȥ�ؽѸ���Ԥˤ�ä������˼꤬���������������μ̿����Ѥ˺��줿��Ǥ�����
- ��ˤȤäƤϱѸ��Ǥλ�ŵ�������Ż����������ΤǤ�����
- ���λ�ŵ��ޤ�Ż�������ꤷ���ե����˴ؤ���Kodak�ε��ѻ����ϤȤƤ⤷�ä��ꤷ����Τǡ��ƹ��ʸ���Ǥ����������ȤޤȤ�夲�����̤Ȼ���������ޤ�����
- �����å��ϡ����̿����Ѥ�ʳ�Ū��õ�ᤷ�ʼ��ζˤ�ƹ⤤���ʤ����̤�������������Ф��Ƥ��ޤ�����
- ��������μ���Υե���ശ����Τߤʤ餺�������˴ؤ������դ��ˡ�������ޤ�ɸ�ಽ���ޤ�����
- �����å������ʤϡ����Ľ����Ρּ̿����Ȥε��ѳ��� - ����1�ס����ܼ̿��ز��2014ǯ77��2�桧 76 - 82�ˤ˾ܤ�����Ƥ��ޤ���
- �����ʸ�ˤ��ȡ�
- �ֶ��������ο�Ÿ�ϡ�1860ǯ�夫��αѹ�μ̿������Ȥˤ����Ӥ��礭������餬ȯ���������ѳ��ο�����ȳ�����ˤ�����̵��ȯɽ����¿���ε��ȲȤ�������ɤ�ǻ��Ȥ�����夲�Ƥ��ä�����
- �Ƚ�Ƥ���ޤ���
- ����������ˡ�⡢�������ˤ�봥�����ޡ��襦����ν����ˤ��ⴶ�ٲ���ѹ�ͤ�ȯ���Ǥ�����
- �ƹ��쳤�ߥ˥塼�衼�����������������˽��ॸ�硼�� �������ȥޥ�ϡ�Ǯ���ʵ��ȲȤǤ��긦��ȤǤ⤢�ä��褦�Ǥ���
- �ƹ�ˤ����Ƽ��Ҥ��ܳ�Ū�˼̿����������¤�Ϥ�Τϡ�John Carbutt�ˤ��Keystone Dry Works�ҡʥե���ǥ�ե�����1879ǯ�ˤ�Gustav Cramer�ˤ��Cramer & Nordern�ҡʥ���ȥ륤����1879ǯ�ˡ�������George Eastman��Eastman Dry Plate�ҡʤΤ���Eastman Kodak�ҡˡʥ�������������1881ǯ�ˤ�3�ҤǤ��ä��ȸ����Ƥ��ޤ���
- ��������ˤ��ƹ��͢����ҡ�Anthony�Ҥ�Scovil�ҡˤ��������͢�����뤫����鼫����¤��Ϥ��ΤΡ����ʤ��ʼ����й��Ǥ�����ǰ�����аޤ�����ޤ���
- �ƹ��3�Ҥ��ƹ���μ��פ����ӤĤĤ�����ˤ��äƤ��������졢Eastman Kodak���Ĥ�ޤ�����
- Kodak�ηб���ά�⤵�뤳�Ȥʤ��顢������������¤���Ф��뿿���ʻ������ʼ�����Τ�������������դ�ʤ��ä�������ȸ����Ƥ��ޤ���
- �ե���ശ������������ϡ���������ʼ��ΥХ�ĥ��ˤ�봶���㲼�Ǥ��ä��ȸ����Ƥ��ޤ���
- �� ��
�����ե����١���������
- ��������ɡʥ˥ȥ�����������ˤϤ��ʤ�����ʺ����Ǥ���
- ���δ����ʥե���ब����Ĺ���ֻȤ��Ƥ����ΤǤ��礦��
- �Dz�ե����ϡ������������̤ä��塢�Ǽ̵��ˤ�����첿ɴ��Ȥʤ��Ȥ��ޤ���
- ���٤䲹�٤��Ф�����������ɤ���ˡ�Ѳ������ʤ��ä��ΤǤ���
- �����������������������кҤδ���������ޤ�����
- ��������ɤμ���ʬ�Ǥ���˥ȥ������������75��ˤϲ����ˤ�Ȥ���ۤɲ�dz���������������ޤǤ����Ǿ��25��ˤ��������������100��C �ʾ�����Ū�㤤���٤�ʬ�ơ�170-180��C ��ȯ�Ф��ޤ���
- �б������®�٤�®������Ф���ȶä����������DzФ����ޤ���
- 1984ǯ9��3���ʷ�ˡ�����������������Ω�������Ѵۥե���ॻ���Ҹˤ���νвФ�ͭ̾�ǡ�330�ܤˤ�ڤָŤ�̾��ե����ʥ�������ɥե�������ˤ��Ƽ����Ƥ��ޤ��ޤ�����
- ��������ɤϤޤ����ˤ�äƤ�Ǯ��ʬ������ͭ�Ǥ����ǻ���ʪ��ȯ�����뤿�ᡢ���Ǥζ���⤢��ޤ�����
- ��塢1955ǯ�ˤʤäơ�dz���ˤ����ݻ�����������ϥե����ʥȥꥢ���ơ��ȥ�������� = TAC�ˤ���ȯ���졢����˥ݥꥨ���ƥ�ʥݥꥨ�����ƥ�ե��졼�ȡ�PET�ˤȤʤ�ե����١����ˤ��ȯ�Фο��ۤϤʤ��ʤ�ޤ�����
�ݥꥨ���ƥ�϶��פʼ���Ǥ��뤿�ᡢ�����ե����ˤ��뤳�Ȥ���ǽ�Ǥ���
- �����ѤΥơ��פ䡢1980ǯ��˵���Ĺ�����ӥǥ��ơ��פˤ�Ȥ�졢�ե��åԡ��ǥ������κ���ˤ�Ȥ��ޤ�����
- �ڥåȥܥȥ��PET�ϡ��ݥꥨ���ƥ�ʥݥꥨ�����ƥ�ե��졼�ȡˤǤǤ��Ƥ��ޤ���
- �����å��ϥݥꥨ���ƥ�١����ե�����ޥ��顼��Mylar�˥١����ե����ȸƤ�Ǥ��ޤ�����
- �ޥ��顼��Mylar�ˤϡ��ƹ�ǥ�ݥ�Ҥ���Ͽ��ɸ�Ǥ���
- ����ե����Ǥϡ�4x5�����ȥե����˥ޥ��顼�١����ե���ब�Ȥ�줿��ΤΡ�35mm�ե�����֥����ˡ��ե����ǤϤޤ��Ȥ��뤳�ȤϤʤ��������������о줷�Ƥ����ȥꥢ���ơ��ȥե���ब�Ȥ��³�����ޤ�����
- ������ͳ�ϡ��ݥꥨ���ƥ�ե���ब����Ū�˶������뤫��Ǥ�����
- ������ե����ϵ�����ȤäƸ���������Ԥ����ᡢ������ե���ब��������Ǿ��夲�Ƥ��ޤä���硢�礭�ʻ��Τ����ꤵ��ޤ�����
- �ե���ब�������ᵡ��������Ƥ��ޤ��ΤǤ���
- 1980ǯ�塢������¬�Ѥˡ���˱��賫ȯ�Ѥ˥ޥ��顼�١�����16mm�ե���ࡢ35mm�ե���ࡢ70mm�ե���ब�����Ȥ��ޤ�����
- ������֤˥ե�������äƤ����ȥե������˻�¸���Ƥ����ʬ����ȯ���ƥե���ब���Ѥ�����ʤ�ޤ���
- �ޤ����ȥꥢ���ơ��Ȥ��㲹�ˤʤ���Ȥ��ʤ�ե����������ޤǥѡ��ե��졼������ˤ�Ƥ��ޤ��ޤ���
- ���Τ褦�ʲ��ʾ��ǻ��ƥե�����Ȥ������ޥ��顼�ե����Ϥ����ɤ���ȯ�����ޤ�����
- IMAX�˻Ȥ���70mm�ե����ˤϥ��������١����Υե���ब�Ȥ��Ƥ��ޤ���
- �ѵ������θ��������Ǥ���
- ��
- ��60mm������ե����ʥ֥����ˡ��ե����ˡ�
- 60mm�ҡ����Τˤϡ�2 1/2������Ǥ�����63.5mm�ҡˤΥ�����ե����ϡ����٤ˤ�������μ̿���²�������������饬�饹���ġ������ȥե��������äƹͤ��Ф��줿��ΤǤ���
- ���Ū�˸��ơ�������ե����Ϥ���60mm�ҤΤ�Τ��ǽ�Τ褦�Ǥ���
- �����ȯ�����������å��ϡ����顢�ե����Ҥ�2 1/2������ҤȤ���3����Υ����ס�117�֡�120�֡�620�֡ˤ�Ф��Ƥ��ޤ�����
- 117�֤ϡ����̤�2 1/4 x 2 1/4 �ʤ�����6x6Ƚ�ˡ�120�֤�2 1/4 x 3 1/4 �ʤ�����6x9Ƚ�ˤȤ������Ǥ���
- ���ߤǤϡ�1901ǯ��ȯ�䤵�줿120�֤�����Ƚ������Ѥ���ɽŪ�ʥ�����ե����Ȥ��ƥ֥����ˡ���Brownie�˥ե����Ȥ���̾���������ĤäƤ��ޤ���
�֥����ˡ��Ȥ���̾���ϡ����������å������Υե��������Ф������������˾��ͤ�ȤäƤ��ơ����ξ��ͤ�̾����Brownie�Ǥ��ä����Ȥ���̾�դ���줿�˥å��͡���Ǥ���
- ���Υե����ʥ֥����ˡ��ե����ˤϤ��θ�ϥå���֥�åɤ�ޥߥ䡢�ٻμ̿������֥��˥��ʤɤ���Ƚ�����˻Ȥ��Ǹ�ޤǻĤ�ޤ�����120�����ס�220�����פ�2���ब����ޤ���
- �桹�������ߤο����ѥȥ����͡�patrone���ȡϡ�film cartridge�������35mm�Ҥ�135�����פ���٤�ȡ��֥����ˡ��ե����Ϻ�Ĺ�Ǥ���
- �֥����ˡ�������ե����ϡ���62.75mm�κ�Ĺ��������Ǥ��μ���Ȥ��ơ������꾯��û��Υե�����61.5mm�ˤ���ˤ��Ƥ��Ĥ����ס���˴����դ�����¤�ˤʤäƤ��ޤ���
- �֥����ˡ��ե����ϰ�����������ǡ����Ƥ������Ƚ����ι��椬�ե��������褦�ˤ��ƴ����졢��ˤʤä����륹�ס���ϼ��Υ�����ե�������뤿��˴������¦�������ؤ��ƻȤ��ޤ���
- ñ��ʹ�¤�ʤΤǤ��������ι�¤�ϼ��������ä�����ݤơ����۸����β��Ǥ⥫���ؤνФ������Ԥ����Ȥ��Ǥ��ޤ���
- �ե����Ȱ��ˤʤäƴ�����Ƥ�������ؤˤϡ��ֹ椬�դ��Ƥ��ơ����������̤��֤��Фξ��뤫�餽���ֹ椬��������Υե����ä����狼��褦�ˤʤäƤ��ޤ���
- ��ǯ�Υ����ϡ����Ԥ��ե���ബ���夲�Υ֤�ơ����뤫��ե�����������ǧ�Ǥ���褦�ˤʤäƤޤ���
- �����Υᥫ���٤�夬�äƤ���Τǡ��ե������夲��ȼ�ưŪ�˥ե�������꤬���ȥåפ��뵡���ˤʤäƤ��ޤ���
- ���Υե����ˤϡ�35mm�ե����Τ褦�ʥѡ��ե��졼�����ʹ��ˤ��ʤ��������夲�Υ��ȥ����������ǥե���������褦�ˤʤäƤ��ޤ���
- �����60mm�ҤΥ�����ե����ϡ�60mm x 90mm ��������6�绣���1��������Ǥ����������θ塢�֥����ˡ�Ƚ�Ȥ�Ф��120�����������礵���褦�ˤʤ�ޤ����� 120�������ϥե�����Ĺ����825mm���ꡢ�����60mm x 90mm ��������8��λ��Ƥ��Ǥ���60mm x 60mm ��12�硢60mm x 45mm �Ǥ�16�礬��������̤ȤʤäƤ��ޤ�����
- 220�������Υե����ϡ��ե�����������������Ĥ��Ƥ��Ȥϥե����ΤߤȤ���120�������Υե������ܤ�Ĺ���Υե���ब��������Ǥ���ޤ���
- 220�����פ�120��2�ܤΥե����Ĺ�������ꡢ60mm x 90mm ��������16�硢60mm x 60mm ��24��λ��Ƥ���ǽ�ˤʤäƤ��ޤ�����
- �ϥå���֥�åɡ�Hasselblad�ˡ�2005ǯ �֥����ˡ��ե�������Ѥ�����Ƚ��������ɽ���¿���Υץ������ޥ�����Υ���顣 ���ݥ�11�椬��˻��äƤ��ä������Ȥ��ơ�ͭ̾�ˤʤä���
- ���ߤϡ��ǥ�����Хå���꤬���Ƥ��롣
- �ڥ������ˡ�� ��2020.05.14�ɵ���
- �����Υե���ॵ�����ϸ��ߤǤϥ�ȥ�å��ʥߥ�ɽ���ˤǸ���ɽ�路�ޤ��������ʤ��ä����ˤϥ�����Ǥ�����
- ����ꥫ�Ϻ��˻��ޤǹ������ʤ���������Ǻ�äƤ����ʤΤǡ�1890ǯ��������ȥ�ǵ��ʤ��뤳�ȤϤ������ʤ��ä��Ϥ��Ǥ���
- �ե����ζҤ�60mm�Ԥä���ε��ʤȤϹͤ��Ť餯��2 1/2�������63.5mm�ˤǤϤʤ��ä��������ȹͤ��Ƥ��ޤ���
- �Ť���Τ�Ĵ�٤���ˡ�������������٤ƥ�ȥ�����ƤϤ�����ˤ�������Ƚ�Ǥ��뤳�Ȥ����ʤ�ޤ���
- �ʤ���60mm�ҤΥե���ब�о줷���Τ����ȥ��ñ�̷Ϥǹͤ��Ƥ������νФ��褦���ʤ�����Ǥ���
- �������Ƹ����60mm�ե����Ȥ����Τ��������ʤ���2 1/2�������63.5mm�˶ҤȤ����Τ��������������Τ褦�ʵ������ޤ���
- ������ե���ब�Ǥ��ʤ������Υե����ϥ��饹���Ĥ��Ȥ��Ƥ��ơ�4x5�������8x10������ʤɤΥ�����������ޤ�����
- �����δ��Ĥϱѹ�äȤ�����˺�äƤ����Τǡ��ѹʡʥ�������ʡˤˤʤä��Τ�����Ǥ��ޤ���
- ������ե����ϡ�¿���ξ���Ԥ��Ϥ��ΤǤ����鵬�ʤ����ڤ��ڤ�Τ������������������ä��ȹͤ��Ƥ��ޤ���
- ���ߡ��֥����ˡ��Υե����Ҥε��ʤϡ�61.5mm+0/-0.2mm�ȤʤäƤ��ޤ���
- 61.5mm�Ȥ�����ˡ��������ƤϤ�褦�Ȥ���ȡ��ڤ���ɤ����ͤ����ƤϤޤ�ޤ���
- ��ȥ�ˡ�ϡ�10��ˡ��Ŭ�Ѥ��Ƥ���Τǡ�10.123�Ȥ����褦�˼�ͳ�ʿ��ͤ�����Ǥ��ޤ���
���䥤�����ˡ�ϡ����衢1/2��1/4��1/8��1/16��1/32�Ȥ�������Ⱦʬ���ĤǺ٤����櫓�Ƥ�����ʬ���2���ܿ��ˤ���ʬ�Ҥ�ʬ��ο��ޤ����Ƥ����������ȤäƤ��ޤ���
- �ʱ��ޤΥΥ����ˤϥ�ȥ�å��ȥ����ɽ����2�����¬��Ǥ���褦�ˤʤäƤ��ޤ����������ɽ����1�������16ʬ�䤷�С��˥��ϡ�8ʬ�䤵��ơ�1/128�����ñ�̤Ǥ�¬���褦�ˤʤäƤ��ޤ�����
- �Ĥޤꡢ1/8�η���ʤ�С�1/8��1/4��3/8��1/2��5/8��3/4��7/8��1�Ȥ�������ˤʤ�ޤ���
- ���ä�10��ˡ�Τ褦�ʼ�ͳ�ʿ���ɽ�������ΤϤ��Ǥ���
- ���Τ��Ȥ��顢�䤬���ꤷ�Ƥ���120�֥����ˡ��ե����Ҥϡ�2 1/2�������63.5mm�ˤǤϤʤ��������ȼٿ䤷�Ƥ��ޤ���
- �Ȥ�������JIS���ʤǤϥ֥����ˡ��������Υե�����61.5mm�Ҥȷ����Ƥ��ơ����κ���2mm�ˤ��ɤ����ƤǤ����Τ�����˶줷��Ǥ��ޤ���
- �����å�����ˡ����Ǥϡ�120������ե����Ҥϡ�2.41�������2.45��61.24mm��62.23mm�˥�������ϰ������¤���Ƥ���ȸ����Ƥ��ޤ���
- ���ο��ͤ�10��ˡɽ���Ǥ���Τǡ���������ŪŪ��2�ʿ���ʬ��ɽ����ľ����2 7/16�������61.9mm�ˤȤʤꡢ���줬�߷���ˡ�ʤΤ����Τ�ޤ���
- ������������Ǥ⡢���ߤ���ˡ��0.4mm�θ����������Ƥ��ޤ��ޤ���
- �ޤ����֥����ˡ��Ȥ��̤ˡ�35mm�� = 1-3/8������ҡ˥ե����θ����Ȥ�ʤä�70mm�ҡ� = 2-3/4������ҡˤΥ�����ե���ब����κ��ˤ��ä��Ȼפ��ΤǤ���������ʸ���⺣���ΤȤ�����Τ���������ޤ���
- ��������बȯ�����줿�Τ�1830ǯ�彪���Τ��Ȥǥե�Ƕ���ޤ�����
- �ѹ��������ɤ��ơʥ���������→������������→����������ޡˡ�Ʊ���˥����ʻ��ư�Ȣ�ȥ�ˤ�����ư��绺�Ȥˤ��ޤ�����
- ���θ塢1880ǯ����˿���Φ�ƹ�Υ����å���������ե�����ȯ����1890ǯ����ˤϱDz軺�Ȥ������ơ��礤������ˤʤäƤ��ä��Ȥ����аޤ�����ޤ���
- ��������ˡ���ʤˤ⸽�졢�ե����ε��ʤⶥ���ϤΤ����������Ƹ��äƤ��ä����������ޤ���
- �����ȥե�����Ȥ��ܥå��������ϱѹ���ǽ���ɤ���Τ�꤬�����Τǡ�������������Υ����ȥե���ब�Ǥ���������ե������ƹ�Υ����å�����ȯ�����Τǥ�����������Ȥʤ�ޤ�����
- �Dz襫�����ƹ�Ǥ�����ˤʤ�ޤ���������αDz�ϥե�ʥ��ߥ����뷻��Υ����ȥѥơˤ�Ǯ�����ä��Τǡ�������ȥ�ȥ�å�������ˤʤä����̤������ޤ���
- ��
- ���ե����Υ������Curling��
- ������ե�����������������0.1mm���Υ����ơ��ȥ١����˴������ޤ����ۤ���Ƥ��ޤ���
- ���Τ���ˡ�����Υե����Ǥ����������̤�ȿ��¦���Ѷʤ��륫�����Ǻ�ޤ��졢�ä˸�����Υե����Υ������Ƭ���ˤ�����Ǥ�����
- ���Υ�������ɻߤ��뤿�ᴶ�����̤�ȿ��¦��Ʃ���ʥ����������ۤ��ƻ��Ѥ��Ƥ��ޤ�����
- ���ߤǤ�ۤȤ�ɤΥ�����ե����ˤϥ��������Ǻ�Ȥ�����������ɻ������ؤ��ܤ���Ƥ��ơ�����������Ǥ�ۤ�ʿ����̤��ݤäƤ��ޤ���
- ��
- ��35mm������ե�����
- �̿�����餬�Ǥ������Υե������ڤǤǤ���Ȣ���Υ����˻Ȥ����ĥե�����4x5�����ס�8x10�ˤ䡢���θ��60mm������ե����ʥ֥����ˡ��ˤ���ή�Ǥ�����
- �����Ϥ��θ塢�������礭�ʥ���餫��������Ӥ䤹�������ʥ饤�������������Ф���ޤ�����
- �ե����ϡ��Dz��Ѥ�35mm�ҤΥե�����ή�Ѥ��Ƥ��ޤ�����
- �Dz��ѥ����ϡ�100ftĹ��30.5m�ˡ�400ftĹ��120���ˤʤɤ����ѤΥޥ����������ƻȤäƤ����Τǡ����������ˤ⤽���������ѤΥޥ�����ɬ�פǤ�����
- ����Υ����ˤϥե��������ѤΥޥ��������Ĥ��Ѱդ���Ƥ��ơ����ѼԤ�Ĺ�����ե�����٤����ڤäƥޥ�����˵ͤ��ؤ��ƻȤäƤ��ޤ�����
- 1913ǯ���ɥ��� Ernst Leitz�Ҥε��������������Х�ʥå����Oskar Barnack, 1879 - 1936�ˤ����Dz��Ѥ�35mm�ҤΥѡ��ե��졼������դ��Υե��������Ѥ������������֥饤���פ���ޤ�����
- ���Υ����λ��ƥ�������24mm x 36mm��8�ѡ��ե��졼�����ˤǤ��ä����ᡢ�ʸ夳�Υ������� �饤���������ȸƤ֤褦�ˤʤ�ޤ���
- �Х�ʥå���Ĺ�ܱDz�ե������ڤäƥե���५���åȤ˵ͤ��Ȥ�����γȤ���ξ�Ӥΰ�ҡʤҤȤҤ��ˤ�Ĺ���� = 137cm�ˤ�36�绣�ƤǤ������Ȥ��顢���줬�ե����36�绣���ɸ��Ȥʤ�ޤ�����
36�绣��ޥ�������Ū�ˤʤäƤ���ȡ��ե�����ޥ�����˵ͤ��ؤ���ɬ�פΤʤ��ѥȥ����͡�patrone���ȡϡ�film cartridge������Υե���ब���䤵���褦�ˤʤꡢ18�绣�ꡢ36�绣�������ȥ��顼�ե���ब�����褦�ˤʤ�ޤ�����
- ���줬135�����פΥե����Ǥ��������߰���Ū�˻Ȥ��Ƥ���135�����פΥѥȥ����������35mm�ե����ϡ�1934ǯ�˥����å��ˤ�äƺ���ơ����֤�135��Ϳ�����ޤ�����
- ���Υѥȥ���������ե����ϡ�35mm�ե���५���ε���Ĺ��ȼ�ä�1960ǯ�ʹߥե�������̾��ˤʤ�ۤɤ���ڤޤ�����
- ���θ塢���̤λ��Ƥ��Ǥ���12�绣�����Τ��졢18�绣���20�绣����Ѥ�ꡢ������24�绣��Ȥʤ�ޤ�����
- ���Ū�˥ե����λ������̤Ƥߤޤ��ȡ�36�绣�꤬�ǽ�ǡ�����Ⱦʬ��18�绣�ꡢ������36���1/3��12�绣�꤬�о줷�ޤ�����
- ���Ū�ˤϡ�12�绣����ܿ���24�硢36�绣�������夤���Τ϶�̣�����뤳�Ȥ��Ǥ���
- �ե����������������ˤ�����äƤ����Τ��褯�狼��ޤ���
- 20�����꤬24��������Ѥ�ä������Τ��Ȥ��ɤ��Ф��Ƥ��ޤ���
- ����ϻ䤬�2ǯ���ΤȤ��Ǥ�����1972ǯ���Ǥ���
- ���ܤΥե������������ϻ�ʥ��˥��ˤ�20�绣���24�绣��ˤ��ƥ������Ф����Ȥ��ޤ�����
- �����͵������ȤǤ��ä����ְܶ�ʥ����55��ˤ����֤ɤä����������褩�������ͤ��Ƥߤ褦���פȤ�������å����ԡ���ή�Ԥ餻�ޤ�����
- �����������Ҵ���ȿ�������Τ��ٻΥե����ǡ�������24�绣���Ф����������Ԥ��ä������å��Ͽ����ʤ���Ǹ��24�绣�����������褦�ˤʤ�ޤ�����
- �����ʤǤ���ե����ϡ�Ʊ�����ʤǤ���ʤ黣������ʤ�������ä������������Ȥ��ΤǤ���
- ��
- ���ѡ��ե��졼������Perforation��
35mm�ե����ϱDz��Ѥ˺��줿��ΤǤ����顢�ե��������Τ�����ɬ��ե�����ξ¦�˥ѡ��ե��졼�����ȸƤФ�빦���ߤ����Ƥ��ޤ���
- ���ι��Υԥå��ϡ�4.75mm��0.1870����� = 3/16������ˤȵ��ʤǷ����Ƥ��뤿�ᡢ����ե����Ǥ�8�ѡ��ե��졼������37.998mm��1 1/2������ˤǰ���β��̹����ˤʤ�ޤ���
- ���Υ��ڡ����˥饤���������Ǥϡ�24mm x 36mm ��1����� x 1 1/2������ˤ������ƤƤ��ޤ���
- 35mm�ҤΤ�����11mm�� = 35mm - 24mm�ˤ��ѡ��ե��졼��������˳�����Ƥ�졢������ʬ��2.08mm�� = 38.08mm - 36mm�ˤ��ե졼��֤Υ��ڡ����Ȥʤ�ޤ���
- ���������ѡ��ե��졼�����Τ�������60mm������ե����ǻȤ��Ƥ����褦����ˤ�����ɽ�������פȤʤ�ޤ�����
- 135�����פ�35mm�ե����ϡ��Dz��ѤΥե����Υѡ��ե��졼�������㴳�礭��˺���Ƥ��뤽���Ǥ���
- �Dz��ѤΥѡ��ե��졼��������Ѥ���ȡ��²��ʥ����Ǥϴ����夲���ץ����åȤ���̩�˺�뤳�Ȥ��Ǥ��ʤ����ᡢ�����夲�˸������ФƤ��ޤ������夲���ʤ��Զ�礬�ǤƤ��ޤ�����Ǥ���
- ��
- ��35mm�ե����Υ������Curling��
- 35mm�ե����ϡ�60mm�ե���������Ѥ�������������αƶ������ʤ����ᥫ����������ؤϻܤ���Ƥ��ޤ���
- �Dz�ե����ϸ�������������˴��������¸���ޤ��������������Ǥϻ��Ƥ����ե�����û���ڤä�û�����ˤ��ơ�������ޤˤ������¸���뤿�ᥫ������ٹ礤�����ʤ��ΤǤ���
- �� �� ��
- ����35mm�饤�����������������2005.09.04���ˡ�2023.09.28�ɵ���
�̿������ȸ����С֥饤���פȸƤФ��ۤ�ͭ̾�ˤʤä��饤���������Υ����ȤϤɤΤ褦�ʥ����Ǥ��礦��
- �饤���ϡ��ɥ��ĤΥ���ȡ��饤�ġ�Ernst Leitz�˼ҤΥ����Ȥ�����̣�ǡ�Leica�פȸƤФ�Ƥ��ޤ���
- �饤���ϡ�1913ǯ�˥饤�ļҤΥޥ��������ʿ��͡˥����������Х�ʥå���Oskar Barnack��1879-1936�ˤ���ȯ������ΤǤ���
- �������ɥ��ĤǤΥޥ��������ϡ���Ĥο����α�ޤä���ǯ������ޤǡ��ǻ����������Ȥ������ܤΤ褦���������٤ϤȤäƤ��餺�����������Ѥ���ƥɥ��Ĺ������鷺���ٽ�����Ϥ��⤤�Ƥ��ޤ�����
- �Х�ʥå��ϡ�1900ǯ����1910ǯ�ޤǤ�10ǯ�֡��ब21�ͤ���31�ͤδ֡˥����롦�ĥ��������Ĥ�Ư���Ƥ��ޤ���
- �������������Ǥ����Ư������ɮ���٤���ΤϤʤ���"�����Ĥξ夬��ʤ�"���ͤ��ä��褦�Ǥ���
- ���θ塢1ǯ��Ф�1911ǯ��32�ͤλ��ˡ��ĥ������Ҥ��⾮���ʲ�ҤǤ��륦���åĥ顼�ˤ��륨��ȡ��饤�ļҤ����Ҥ����Dz赡�����Ĺ�Ȥ���Ư���Ϥ���ޤ�����
- ����2ǯ���1913ǯ�ˡ��ǽ�Υ���顢Ur Leica�ʥ��롦�饤��������Ȥ����Τ�Urbild = ����Ȥ������դ�û�̡ˤ�2����¤���ޤ�����
- �Dz赡���λ�λŻ��ι�֤ˡ��Dz�ե�����Ȥäƥ�����������Ǥ���
- �Х�ʥå���̵��Υ���鹥�����ä������ǡ������ƾ����Ǥ�����
- �������ब��������Ȣ�����Ȥ�Ω�ƥ�����9x12����� = 90mm x 120mm����������껥Ƚ���饹���Ĥ��Ѥ�����ʢ�����ˤ��������ǡ����Ƥ���ΤϤȤƤ����Ѥ��ä��褦�Ǥ���
- ����ȡ��饤�ļҤΥ��˥� �����������Х�ʥå��������
- 35mm�ե���५��顢Ur Leica��1913ǯ��
- ���ʤߤˡ������ɥ��Ĥ�Ȣ����ʢ�����˻Ȥ�줿�ե����ϡ���ȥ륵�����Ǥ��ꥤ����������ǤϤ���ޤ���
- �������ƹ��Kodak�Ҥϡ�4�������5����������ȥե��������˹���Ƥ��ޤ�������ȥ�ˡ����Ѥ��Ƥ����Ϥ��Τ���ˤ����������б���;���ʤ�����Ƥ��ޤ�����
- �ʥ�ȥ륵�����Υե���Ȥȥ�����������Υե����˴ؤ��Ƥϰʲ��ε����Ȥ��Ʋ����� �֢�����ȥ�ե����ȥ�����ե����ס���
- �����ब���Ҽ�ǻ������٤ƴ�ñ�˻��ƤǤ��륫�������ܤ����Τ�Ǽ���ιԤ���Ǥ���
- �Х�ʥå��������˺��Ѥ����������������24mmx36mm�ˤ�饤���������ȸƤ�ǡ����θ��35mm�ե���५����ɸ�ॵ�����Ȥʤ�ޤ�����
- �Х�ʥå��ϡ��ǽ顢�Dz��Ʊ���������������18mm��24mm�ˡ�3/4����� x 1���������ȥ���ˡ�Ȱۤʤ뤬�ǽ�ε��ʤϥ�����ˤΥ�������ޤ����������Ū���ɹ��ʷ�̤������ʤ��ä��Τǡ�2�ܤΥ��֥륵������24mmx36mm�ˡ�1����� x 1 1/2������ˤȤ��ޤ�����
- ��������Ŷ����ե�����Ĺ���ϡ��ब�ӤФ���Ĺ���ʰ�� = �ҤȤҤ��ˤȤ������ᡢ36�绣���Ĺ���Ȥʤ�ޤ�����
- �ब��ä�2���Ur Leica�Τ�����1����Ĺ�Υ���ȡ��饤�İ������Ϥ��������Ǥ������饤�ļ�Ĺ�Ϥ��ޤ궽̣���ʤ��ä��餷�����ޤ������켡��������⤢�ä�˺�����Ƥ��������Ǥ���
- �����Ĺ�λ�塢���Ѥ�������ȡ��饤������������Υ����ƤȤƤⶽ̣����30��λ�����Null Leica�ˤ��餻�ޤ��� ����ϡ�1923ǯ�Τ��ȤǤ�����
- �̥��Null�ˤȤ����Τϡ���0�פȤ�����̣�ǡ�I����II���ΤǤ����������ʤ�������̣������ΤǤ���
- �̥롦�饤����ɾȽ�ϰ���������Ǥ����ʲ���ȿ�Ф�������¿���ä������Ǥ���
- ������ͳ�ϡ����ޤ�ˤ������ʥ����ǥ�����ˤ���ޤ�����
- ���ǤϤ��������̤Ǥ��ä��ɤ��Ȥ����פ���35mm�ե���५���λ��Ʒ��֡����ʤ������ʿ�Υ��������̤��˲����դ��ƥե���������ۤ�������Τ��ˤߡ�����ǥ�����٤��ʤ����������ǥ����Υ֥�����ʤ��饷��å����ڤ롢�Ȥ�������̯�˸������ΤǤ���
- �饤�ļҤϡ����������Υ���顢�饤��I�������䤹�뤳�Ȥ�Ƨ���ڤ�ޤ�����
- �ǽ�Υǥӥ塼�ϡ�1925ǯ4��饤�ץ��ҡ���å���Ÿ�����Ÿ�Ǥ������Ծ�˽Ф��Ƥߤ�ȡ��饤����ɾȽ�Ϥ������Ĵ�Ǥ�����
- �����Ѥ�ä�����餬�¤����˼���Ū�Ǥ��ꡢ���ؤʥ����Ȥ��ƻԾ�˼���������Ƥ��ä��ΤǤ���
- ����Ÿ����θ塢�饤�Ĥˤ�500�����ʸ�����ꡢ1ǯ��Ф��ʤ�12�����ˤ�1000�����ʸ��������ȸ����ޤ���
- �ʸ塢�ܡ��������Ͽ��ӤƤ��ä������Ǥ���
- ���Υ饤�Ĥ������˰���������褦�ˤ��ơ��饤�Х�Υĥ�������������Ҥ���ϡ֥��å����פ�ȯ�䤵�졢����¾�ˡ����ܤΥ�������⤳���äƥ饤�������ϤȤ����������߷ס�����ޤ�����
- �ʤ����饤����80ǯ��Ĺ�����Ϥäư�����³���Ƥ���ΤǤ��礦����
- ������ͳ�ϡ�����鹥���ο��ͤ����������ƻȤ����¦��Ω�ä��������ä����ˤ���Ǥ��礦��
- �饤���δ��ܹ�¤�϶ˤ�ƥ���ץ���ȸ����Ƥ��ޤ���
- ���������Υ���ץ뤵�ˡ������ο�������Ƥ���ȸ����ޤ���
- �ե����δ����夲�δ����ȳ�餫���ϡ��饤�������ˤ��ˤ�ʤ�ͥ�줿��ΤǤ�����
- �ޤ����ե�������ץ졼��å����κ�ư��������å��ξ��ʤ������Υ֤μ��������������å��νŸ������ɤ��Ĥ�ȤäƤ���ļԤ�����Ϳ������ʪ�Ǥ��ä������Ǥ���
- �饤���ϡ��ʤ�������ե������äƤ��ޤ���
- ����ե�������Ƭ�ȤȤ�˥饤���������ϵ�®�˿ꤨ�ơ�1970ǯ��ʹߡ�35mm�ե���५���ȸ����а���ե����ȸ�����褦�ˤʤꡢ����������餬���������ʴ�����ޤǤˤʤ�ޤ�����
- ������ե����ϡ��饤���Τ褦�ʥ�ե�������������Ǥʤ����ե���������������ޤޤλ�����ƤǤ��������ͳ�˻Ȥ��ƶ��ܻ��Ƥ⼫ͳ�ˤǤ����Τ��ä��Τǡ��饤�����Υ�ե������������ष�Ƥ��ä��ΤǤ���
- ����ˤ��ȡ�1960ǯ��ޤǤϥ饤�������ޤ�ˤ���ǽ��ͥ��Ƥ�������ˡ����ܤΥ����������ɿ魯��Τ�����ơ������������ΰ���ե�å��������˿���Ф���������ʤ��ä��ȸ����Ƥ��ޤ���
- �����Ȥˡ�1977ǯ�Υ��㥹�ԥ˥������ڤ�Ȥ���1980ǯ�夫�饪���ȥե�����������餬��Ƭ�������줬�²��ʥ����ˤޤdz��礵���ȡ��饤����������Ǥ����ե�������������Υ���餬��������������ڤ��Ƥ����ޤ�����
- �� ��
- ��2000ǯ��Υǥ����륫���˱ƶ���Ϳ�����ե���५����������2012.02.23���� ��2022.04.09����
- 2012ǯ���ե���५���������Ϥʤ�����ᡢ���ä�CMOS���λ����ǻҤ�Ͽ�ǻҤȤ����ǥ����륫��餬���������Ӥ��Ƥ��ޤ���
- ��̣����Ȥ����ϡ���Ͽ���Τ϶�������फ����λ����ǻҤ��Ѥ��ޤ������������Ȥ�ޤ������η������������֤�¿���ϥե���५����Ƨ�����Ƥ��ޤ���
- �㤨�С�����å����ڤ륷��å����ϡ��ᥫ�˥��륷��å�������ʤ��Żҥ���å��Υǥ����륫���ˤ�̵����ΤǤ������ե���५������Υᥫ����å��˻����Ƶ�������Ф��Ƥ��ޤ���
- ������ϡ��ե���५������Τ�Τ��Ȥ�졢�����δ��٤�ɽ����ISO����������ɽ����Ƥ��ޤ���
- �ǥ��������ե����Ǥϡ��ե�������ץ졼��å��Τޤ��Ѥ�������ǻҤδ֤˥ߥ顼�����֤��ڥץꥺ��Ǹ�������ե����������Ƴ��������������äƤ��ޤ���
- ���Τ褦�˥�������ˤƤߤƤ⡢���������Ѥ��Ԥ߽Ф��줿�Ȥ����ΰ��ڤ�ΤƤ�ΤǤϤʤ��������ɤ���Τ�������ʤ����Ȥ߹�碌�Ƥ����Ȥ�����ˡ�����������Ƥ��ޤ���
- �������������ʤ��鿷������Τ��Ǥ����Ȥ�����������Ƥ�����Τ⤢��ޤ���
- �ǥ����륫���ξ��ˤϡ�����ե���ब�ޤ��������졢�����ȼ��������������Ƥ��ץ��ȹ�����ä��ޤ�����
- ���äơ�HDD��IC�����SD�����ɡˤ�CD��DVD��BD�ʤɤ��Żҵ�Ͽ���Τ˼̿�����¸���ܤꡢ�վ���˥��DZǤ��Ф��Ƹ���Ȥ������֤��Ѥ�äƤ��ơ�ɬ�פ˱����ƥ������åȥץ��졼���ץ�ǰ�������褦�ˤʤäƤ��ޤ���
- ��������ή��ˤ�äơ�����ե����ȶ�����Ȥä��������Ƥ������μ�ˡ�������Ĥ�;�Ϥ��ʤ��ʤ�ޤ������ʤ���Ǥ�2022ǯ04��ߤ�ե�����ȤäƤ����ã��¸�ߤ��ޤ���
- �ǥ��������ˤʤäƤ�ե���� = ������������Τ�����̤�̥�Ϥ��Ƥ���ͤ����������ʤ���⤤�ޤ�����2022.04.09�����ˡ�
- �� ��
�� �� ��
- ������
- �ƾΡ��ֹ�
- ������������
- 35mm�ե����
- 126
- 35mm�ե���५���ȥ�å��������ޥ��å��ѥե���ࡣ
- 1963ǯ��135�����פΥ����ȥ�å��ǡ������ޥ��å��ե����˸Ť��Ȥ��Ƥ����ֹ�����蘆������
- 135
- ���̤�35mm�ե���५����ѥե���� �ѥȥ���������12�� ��
- �Dz��ѥե���फ�����1934ǯ��
- 35mm��
- 30.5m��100ft�˴�����
- ��ԥå�
- ��ԥå������ѥȥ��������ꡢ12�绣��
- APS
- ��IX240
- �ե�����24mm���ѥȥ��������ꡣ
- 1996ǯ
- ������ե����
- 127
- �����ȥ�å����ꡢ16mm�ҡ���Ĥ�
- �����ޥ��å��ѡ�12��20�绣��
- 120
- �֥�����Ƚ��61.5mm x 830mm����Ĥ� ���Ǥ����Ū�ʥե���ࡣ
- 6 x 6��12�绣�� ��1901ǯ��
- 620
- �֥����ˡ�Ƚ��Ʊ�塢�ټ� ��1932ǯ - 1995ǯ
- 220
- �֥�����Ƚ��6 x 6��24�绣��
- ��������ȥ졼�顼�դ� ��1965ǯ��
- 828 616
- 116
���ܤǤϻ��Ѥ��줺 ��
116�� 70mm�ҡ�2 1/2 x 4 1/4 ��6.5cm x 11 cm�ˡ�1899 - 1984
- ���֥ߥ˥��奢
- 16�������
- 16mm�ҡ��ѥȥ���������
- �ߥΥå�����
- ��
- �ѥå��ե����
- ��̾�ɡʼ껥�� 9 x 12
- 4 x 5
- �����Ⱦ��ե���������Ф���ΤĤ������Ž�դ���12���10�硢16��ˤ��������줿���
- �����ȥե����
- ��̾�� �껥 4 x 5 ����ӥ� Ȭ���ڤ� 8 x 10
- �ͤ��ڤ�
- 62 x 88mm��̾�� JS��2 1/2 x 3 1/2�� 81 x 106mm��̾�� JS��3 1/4 x 4 1/4�� 100 x 125mm��̾�� JS��4 x 5�� 118 x 163mm��̾�� JS��4 3/4 x 6 1/2�� 165 x 215mm��̾�Ρ�JS��6 1/2 x 8 1/2�� 200 x 250mm��̾�Ρ�JS��8 x 10��
- 251 x 302mm��̾�Ρ�JS��10 x 12��
- 70mm�ե����
- 70mn
- 70mm�� �Dz��ѥե����
- ������ȼ̿�
- ��
- �ݥ�����ɼ�
- �ٻμ̿�
- �����ȥ�å��ե����
- 110
- �����ȥ�å����ꡢ16mm�ҡ���Ĥ�
- �ݥ��åȥ�����ѡ�12��20�绣��
- 126
- �����ȥ�å����ꡢ35mm�ҡ���Ĥ�
- �����ޥ��å��ѡ�12��20�绣��
- �ǥ������ե����
- ��
- 2.5��������ġ�15���ǥ����������;��˻���
- �Dz��ѥե����
- 8mm
- �����ȥ�å�
- 16mm
- 100ft��400ft
- �������������ס��봬����ξ�ܡ�����
- 35mm
- 100ft��200ft��400ft��1,000ft
- ��������
- 70mm
- 100ft��200ft��400ft��1,000ft
- �����������ѡ��ե��졼�������I��II
- �ھ����ե������б����������ȥ�å��ե�����
��126������ �ѥȥ����͡�patrone���ȡϡ�film cartridge������Υե�������Ŷ�κݤ˴������¦��������ޤʤ���Фʤ�ޤ���
- ������Ŷ��Ȥ��������Դ���ʿͤ䤴�ؿͤˤȤäƤ��ʤ�Υ���륮�������������Ǥ��뤳�Ȥ��Τä��ե�������ʥ������ȥޥ����å��ҡˤϡ������Ѥ路�����鳫�����٤���1963ǯ�˥����ȥ�å����Υե�����ȯ�������ޥ��å������Ȥ���ȯ�䤷�ޤ�����
- ���Υ����ȥ�å���35mm�ҤΥե�������Ѥ���������������26mm�ֳ֤Υѡ��ե��졼����ܤ���Ƥ��ޤ���
- ���Ʋ��̤��礭����26mm x 26mm �Ǥ����顢�����1�ѡ��ե��졼�����Ȥ������Ȥˤʤ�ޤ���
- ���Υ����ȥ�å���12�绣��⤷����20�绣���2���ढ�äơ�����ñ�ʤ��Ȥ�������������ȯŪ�����Ԥ����������Ǥ���
- �錄���ϻ�ǰ�ʤ��餳��126�����פΥե�����¸�ߤ⥫�����Τ�ޤ���
��110������ 110�������Υ�����1972ǯ��ȯ�䤵�졢1980ǯ�ޤ����ޤ�����
- 126�����פν̾��ǤȤ�������Τǡ�16mm�ҤΥե�����Ȥä������ȥ�å��ǥѡ��ե��졼��������¦�������ߤ����Ƥ��ޤ�����
- ���̤��礭����13mm x 17mm �Ǥ�����
- ���������126�����פ�Ʊ���ǡ�12�绣���20�绣���2���ढ��ޤ�����
- �֥��ƥ�פȸƤФ�Ƥ��ޤ줿���Υ����ϡ��ݥ��åȤˤ���ʤ������礭���ȴ�ñ�������罰���������ä���Τǡ��������ٻԾ�˿�Ʃ���Ƥ����ޤ�����
- �����������Ū�ˤ�ű���;���ʤ�����ޤ���
- ���Ԥθ����ϡ��ץ��Ȥ��줿��������ޤ�˧�����ʤ������Υ���餬���䤵�줿��Ʊ�����ˡ���ư��������ưϪ�С���ư�����夲�Υ�������ɽ�����ϥ���Υ����ȥܡ����ˤ���®����Ƭ���Ƥ��ơ����Υޡ����åȤäƤ��ޤä��ΤǤ���
- ��ⲿ�٤�����110�������ե���५��������Τ˼��ޤꡢ�ץ��Ȥ������ޤ�������γ�����Ӥ�����ȥ饹�ȤΤĤ��ʤ�����ˡִ��ؤʤ�ΤϤ���ʤ�Τ��ʡפȻפä���ΤǤ�����
���ǥ������ե�����Disc Film�� �ǥ������ե�����1982ǯ�˥����å�����ȯ����2.5������¤��������ľ��Υե����Ǥ���
- �ե���ब�ǥ��������β֤Ӥ���ˤʤäƤ��ơ����β֤Ӥ��15��ͥ��ե���ब�����ž���ʤ���15��λ��Ƥ��Ǥ����ΤǤ�����
- �����ե���५���ȥ�å���Ȥ����ᥫ����ѥ��ȤˤǤ��ޤ������������Ӥ������ˤʤ뤳�Ȥ���ȯ�������Ȥ��Ƥ����褦�Ǥ���
- �ޤ������������ι��������ޤ�����åȤ⤢��ޤ�����
- �����������ε��ʤΥե����⡢�����ܤ���ű���;���ʤ�����ޤ�����
- ��ͳ�ϡ�110�������ν�Ǥ�Ҥ٤ޤ�����135�����פΥ����ξ������ȼ�ư���ˤ�äƲ�����ɤ��̿�����ڤˤǤ���褦�ˤʤä�����Ǥ���
- �ǥ������ե����Υ�����������ϡ�11mm x 8mm��������ޤ���Ǥ�����
- �ޤ�1990ǯ����Ⱦ������β����줿��ѥå������λȤ��Τƥ����ּ̤��Ǥ��ס��ٻμ̿��ե����ˤνи��ϡ����������ȳ�����Ѥ�����������Ǥ�����
- �Ȥ�����Τ褤���ץȤȤ��������˼̤��ɹ��ʲ�������������������Ծ���ʴ����Ƥ����ޤ�����
- �ǥ������ե����ϡ�1998ǯ����¤����ߤ��ޤ�����
- ��
- ��APS������2012.02.23�ɵ���
- APS�ϡ�Advanced Photo System��ά�Υե����ե����ޥåȵ��ʤǤ���
- �����������������ʤϡ����٤��ƹ�Υ����å��Ǻ���ޤ���������⥳���å��������������ȥޥ��å����ٻμ̿��ե���ࡢ����ΥߥΥ륿���˥���ƼҤ���Ʊ��ȯ���ơ�1995ǯ4��饵���ӥ��Ϥ��ޤ�����
- APS�ϲ������������Ȥ����ȡ��ޤ����褫�����Ū�˻Ȥ��Ƥ���35mm�ե��������äơ���60%�Ҥζ����ʤä�24mm�ե�����IX240�˻ȤäƤ��뤳�ȤǤ���
- ��������ϡ�15�硢25�硢40���3���ब����ޤ�����
- �ե���ब�����ˤʤä����Ȥ������äơ����ޥ��奢�桼�����ץ��ȥ�������ۤ��礭�����ʤ����Ȥ�������֤Υ���ѥ��Ȳ��������ʺ������ޤ���Ʊ�����ʤ����Ȥ������¼�Ū���;夲�Ȥ������ä������⤢�롩�˥��������������褦�Ǥ���
- ��Ͽ���ΤΥե����⽾���35�ߥ�ե��������뿷�����ե�������Ѥ������̥�������30.7×16.7�ߥ�ȥ���ѥ��Ȥǡ����դ䥿���ȥ�ʤɤξ��������Ȥ������ǻ��Ƥ�Ʊ���˥ե����˵�Ͽ�Ǥ��ޤ���
- �ե����ϥץ饹���å��ޥ�����˼�Ǽ����Ƥ��ơ��ե���५���ȥ�å��������������δ�ñ�μ¤��߷פˤʤäƤ��ޤ���
- ���Υ����ȥ�å��ե����ϡ������35�ߥꥫ���Ȥθߴ����Ϥʤ��Τǡ��ְ�äƹ������Ƥ�APS�ѤΥ�������äƤ��ʤ��Ȼ��Ѥ��뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
APS�Υ����ƥ�ˤϡ����̤��礭����C�����ס�H�����ס�P�����פ���ޤ���
- ���Ƥϡ����̥�����30.7×16.7mm��16:9�ˤǻ��Ƥ����ץ��Ȼ��˰ʲ��Τ褦�ʥ���������ꤷ�ƥץ��Ȥ�ž夲�Ƥ�餤�ޤ���
- C�����ס���89×127mm���ʽIJ���/2��3��
- �����������������35mm�ե���ॵ�����ʥ饤���������ˤȽIJ��椬Ʊ��
- H�����ס�89×158mm���ʽIJ���/9��16��
- �ϥ����졼�� P�����ס�89×254mm���ʽIJ���/1��3�ˡ��ѥΥ�� ��
- �ե���ॵ����������H�����פǤ���Τǡ������H�����פ������ɹ��Ǥ���
- ��Υ������ϻ��Ƥ��줿�ե��������β����ڤ���Ȥ�����岼��ȥ�ߥ��ư�����Ф��ƥץ��Ȥ��뤿�ᡢɬ��Ū�˲��������ޤ���
- APS�ˤϤ⤦����礭�ʵ�ǽ���ɲä���Ƥ��ޤ���
- ����ϥե�����Ʃ���ʼ����ؤ����äơ������˻��ƥǡ����䥳���Ȥ�Ͽ���Ƥ��뤳�ȤǤ��ʤ����IX����Ȥ����ޤ��ˡ�
- ���ξ���ϸ�ǥ���ԥ塼�����ɲþ�����Ǥ�������ꡢ�ɲõ�Ͽ���Ǥ���褦�ˤʤäƤ��ƥե����δ�������ñ�ˤǤ���褦�ˤʤ�ޤ���
- ���Ԥ��ä��о줷��IX240�ե�����APS���ʡˤϥǥ����륫���ζ�δ��ȼ����ϩ�ξ�ä����䤬�פ��褦�˹Ԥ�����2011ǯ���ä���¤��λ���ޤ�����
- 16ǯ����ˤȤ������Ȥˤʤ�ޤ���
- �� �� ��
- �ڥ�����ȼ̿��ۡ�Instant Film��
1948ǯ���������������3ǯ�塢�ݥ�����ɼҤ�������ȼ̿��ȥ�����ȯ�����ޤ�����
- ȯ�������Τϥ��ɥ���������Ρ�Edwin H. Land��1909 - 1991�ˤǤ���
- ��Τϥϡ��С�����ؤ����ष�Ƥ��ޤ���
- ����������и����ݤ˷��ݤ�������塢�˥塼�衼����Ω��ۤˤ�����������ȳؼ����Τ����и��˴ط��Τ���ʸ�����Ҥ�ü�������ˤ��֥ݥ�����ɡ��и��ե��륿���ʲ����ޤ���
- �������ǡ�������ȥ����ϼ�ʬ�λ��Фˤʤ뤪���μ̿���̤���ľ��ˡ֤����ä��̿��������ơפȤ����ޤ줿���Ȥ��餳���ȯ�ۤ���Ȳ����������Ǥ���
- �ʰ���ˤϥݥ�������и��ե��륿���Υӥ��ͥ����פ路���ʤ����Υӥ��ͥ���ͤ��Ƥ���������ä��Ȥ�����Ƥ��ޤ�����
- ���������Υե���५���ϻ��Ƥ���1ʬ�Ǽ̿����Ǥ���Τǡ�1ʬ�ּ̿��פȸƤФ�Ƥ��ޤ�����
- �ݥ�����ɼ̿��Ϻǽ饻�ԥ�Ĵ�Υ�Υ�������Ǥ�������1950ǯ�˰��̤μ̿���Ʊ�ͤι�Ĵ�ˤʤ�1960ǯ�ˤϥ��顼���ɽ����1963ǯ��ȯ��Ϥ��ޤ���
- 1972ǯ�ˤϤ���ޤǤΡ֥ԡ��륢�ѡ��ȼ��סʥͥ��ȥݥ��ڡ��ѡ��������������ˤ��夨�ơ�SX-70������ȯ���ޤ���1975ǯ�ˤϤ��������ˤ�륫�顼��ȯ�䤷�ޤ�����
- �������ȥޥ����å��Ҥ�1976ǯ��Ʊ�ͤΥե����ȥ�����ȯ�䤷�ޤ���
- ����ˤ��ݥ�����ɤȤ�������̾����֥�����ȥե����פȤ������դ�����̾��Ȥ��ƻȤ���褦�ˤʤ�ޤ���
- �ٻμ̿���1981ǯ��Ʊ�ͤΥե�����ȯ�䤷�ޤ���
- ������ȥե������äƤϥݥ�����ɼҤȥ����å��Ҥδ֤ǥѥƥ�����꤬������1976ǯ���ʾ٤���������㤷����Ƚ���ɤ���1990ǯ�˥ݥ�����ɼҤ����ʤ��������å��Ҥ�1200���ߤ�����Ȥ���ʬ����ű���;��̵������ޤ�����
- �ٻμ̿������ܤ��Ф��ƤϤ��������ѥƥ�ȿ����Ƥ��ʤ��ä��ݥ�����ɼҤ�ˡŪ���Ϥ������äơ����ܤ˸¤äƤ������ԤäƤ��ޤ���
- �����ܤǤ��Կ͵�
- ������ȼ̿��ϡ��ƹ�Ϥ����Τ餺�����ܤˤ����Ƥϲ����ˤ��ޤͤ���Ʃ�����Ȥϸ��������ʤǤ�����
- ����ꥫ�Ǥ���������Ⱦ�����ݥ�����ɥ�������äƤ����Τˡ����ܤǤϤʤ�����ꥫ�ۤ���ڤ��ʤ��ä��ΤǤ��礦��
- ��θĿ�Ū�ʻפ��Ȥ��ưʲ�����ͳ�ˤ���Τȹͤ��ޤ���
- 1.�������ܤǤΡ˥ݥ�����ɤϥե���ब�⤫�ä���
- ������1970ǯ���2000ǯ�塢1��150�ߤ���200�ߤ�����
- ������1500�ߤ���2000�ߤ�Ф���1�ѥå�����äƤ�10�����٤�������ʤ���
- 2.���Ƥ��������Ǥ���������̿��ʤɤ����Ѳ��ͤ��㤫�ä���������Ф���Ǥ��ʤ��ä���
- 3.��135�����פΥե�����DPE�ʸ������ץ��ȡ��Ƥ������ˤΥ����Ȥ�ǯ�������ä�
- ����1���֥����ӥ���в��褦�ˤʤꡢ�ݥ�����ɤβ��ͤ������ä���
- 4.��������ȥե����β�������夹��Τˤ��ʤ�λ��֤������ä���
- �����Τ��Ȥ����ܤǤ���ۤ���ڤ��ʤ��ä���ͳ�ȻפäƤ��ޤ���
- �������ʤ��顢������ȼ̿��ϴ�Ȥ�����θ����ʤɤλ�����浡�ؤˤϤ��ʤ깭���Ԥ��Ϥ����Ѥ���Ƥ��ޤ�����
- ��������1995ǯ�ʹߡ��ǥ������®����ڤ��뤳�Ȥˤ�äơ�������ȥե����μ��פ��㸺���Ƥ��ޤ��ޤ���
- ��
- ������������Cheki��Instax mini����2020.04.14�ɵ���
1998ǯ�������ٻμ̿��ե����ǿ����������פΥ�����ȥե����֥������פ�ȯ�䤵��Ƥ��ޤ���
- ��������¯�Τ�����̾��Instax mini�ʥ����å������ߥˡˤǤ���
- �̿��������Ͼ�������Τμ�Ԥδ֤Ǽ�����������ɹ�������Ƥ���Ȥλ��Ǥ�����2004ǯ�ޤǤ��á��ˡ�2020ǯ���ߤ������³���Ƥ��Ʒ�Ĵ������Ƥ��ޤ�����
- ���Υ�����ȥե����ϥǥ����륫������Ƭ�ǻ�̿������ä��ȻפäƤ����ΤǤ������ǥ����륫���ǻ��ä������Υ�����ȥե��������Ѥ��ƥץ���ѻ�Ȥ��ƻȤ����פ굯�����ޤ�����
- ���Υץ�Τ��Ȥ�������ץ�ȸƤ�Ǥ��뤽���Ǥ���
- �ѥ������Ȥ鷺�˥ץ��ȤǤ���Τǡ���ñ�˼�갷�����Ǥ��뤳�Ȥ�����ҹ����δ֤ǿ͵�������褦�Ǥ���
- �桹��¬��ʬ��ǤϤ��ޤ�ߤ����ޤ���
- ����������ȥե�����
- ������ȥե����ϸ�����ɬ�פȤ������ե����Ȥϰۤʤä���������äƤ����Τǡ��Ծ�ΰ�������ݤ��뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ�������ή�ȤϤʤ�ޤ���Ǥ�����
- �ޤ���1995ǯ�����Ծ����������Ϥ�ǥ����륫���ζ�δ�ˤ�äư쵤�ˤ��λԾ�����å���Ƥ��ޤ��ޤ�����
- 2001ǯ10��ƹ�Polaroid�Ҥϲ�ҹ���ˡ��Ŭ�Ѥ������˻�äƤ��ޤ���
- �ǥ����륫���ε��ѳ��ˤ�äơ�������ȥե���५��餬ô�äƤ����Ż��٤�������äƤ��ޤä��ΤǤ���
- ������ȥ���餬�ǥ����륫���˲��ζ��व�줿�Τ��Ȥ����ȡ��ʲ�����ͳ������Ȼפ��ޤ���
- 1.��2000ǯ������1,000x1,000���ǥ��饹�Υǥ����륫��餬3�����������Ǥ�����
- ����2.�������ͥåȤ���ڤ���ޤäơ������˥���ԥ塼������������ �ǥ����륫���ˤ��
- �����ǥ������������ñ�˼�����ꡢ�ݴɡ��ɤ߽Ф����Ǥ���褦�ˤʤä���
- ����3.������ˡ��������åȥץ������̿�����ʾ�ΰ������Ǥ���ץ��
- ����������3������Ƕ��뤹��褦�ˤʤä��� �� �� ��
- ��
- �ڱDz��ѥե�������2020.04.06�ˡ�2020.05.09�ˡ�2023.10.23�ɵ��� ��
- ��35mm�ե����
�Dz��������Ƨ�߽Ф����Τϡ��ƹ�ȡ��ޥ�������С����������Thomas Alva Edison: 1847 - 1931������θ����μ�Ǥ����������ꥢ�ࡦ���ͥǥ����ǥ��������William Kennedy Laurie Dickson��1860 - 1935�ˤȸ����Ƥ��ޤ���
- ���ϡ�1894ǯ�ˡ֥��ͥȥ���աס�Kinetograph�ˤȸƤФ�뻣�Ƶ��ȡ֥��ͥȥ������ס�Kinetoscope�ˡפȸƤФ��Ǽ̵���ȯ�����Ƥ��ޤ���
- ����˻��Ѥ���ե���ब��������ɥ١��������ޤ����ۤ���������ե����ǡ��ѡ��ե��졼������Ϥܸۤ��ߤ�Ʊ���������Τ�Τ�������Ƥ��ޤ������ʥѡ��ե��졼�����ϥե���ඡ���Kodak�ǤϤʤ��ơ����Ѥ���¦�Υ�������ǹԤ��Ƥ����褦�Ǥ�����
- �ࡼ�ӡ��Ѥ�Ĺ�ܥե���ब���줿�Τϡ����硼�����������ȥޥ�1885ǯ�˥�����ե�����ȯ�����Ƥ���9ǯ��Τ��ȤǤ���
- ���������Υǥ�������ϡ�Kinetoscope��ȯɽ����5ǯ����1889ǯ�˥������ȥޥ�Ҥ˥�����ե����λ���Ф��Ƥ��ޤ�����
- ���Υե����Ҥ���1 3/8�������34.925mm�ˤǡ�Ĺ����50ft��15.2m�ˤ��ä������Ǥ���
- ���ε��ʤϥ����å���70mm�ҡ�2 3/4����� = 69.85mm�ˤΥե���ब���ä��Τǡ������Ⱦʬ�ˤ���ξ�����ɤ˥ե���������ѡ��ե��졼�����ʹ��ˤ��ޤ�����
- ����ʹߡ��Dz�ե����δ���Ū�ʶҤ�35mm�ȷ���졢�饤�ļҤΥ����������Х�ʥå������Υե����ή�Ѥ��ƥ饤����ȯ���Ƹ塢�����Ż߲襫���ʥ饤���������ˤǤ�ɸ����Ѥ����褦�ˤʤ�ޤ�����
- ��
- ������ȥ�ե����ȥ�����ե����
- �ե����Ҥ�35mm���ڤ�Τ褤���ͤˤʤä��Τϡ���ȥ�ˡ��ȯ����Ǥ���ե�αƶ��������ä��褦�Ǥ���
- �ƹ�Ǻ��줿35mm�ե����Ҥϡ��ǽ�1- 3/8�����±0.001�������34.925mm±0.025mm�ˤȤʤäƤ��ơ����줬��ݵ��ʤˤʤä����ϡ�34.975mm±0.025mm�Ȥʤ�ޤ������ե��������0.05mm�礭���ʤ�ޤ�����
- 35.00mm�Ҥ��¤Ȥ��ơ�0.05mm�ޤǾ��������ͤ���Ƥ��ޤ�����
- ���Υե����Ҥε��ʤ��ɤ߲ȡ�������������ε��ƺ�±0.001������ξ�¤Ǥ���34.950mm�Ȥ��ơ���ȥ�å����ͤβ��¤�34.950mm�Ȥ��ƹ�դ�ߤ�����������ޤ���
- �ߤ�����ߴ�ä��ȸ������ݤǤ���
- �ե�ϼ̿����Ѥ��ܲȤǤ��ꡢư���Ǯ���˸��椷�Ƥ��ޤ�����
- ����αDz�ۥ�������ˤ��ʰ����ʤ�ä������˿ͤ�ƱǼ̵���ư����Ǥ����˱Dz軺�Ȥϡ��ե�ǻϤޤ�ޤ������ʥ���ꥫ�ǤϤ���ޤ���
- ����Φ�Υ��硼�����������ȥޥ�ȥ�������ϡ��ե�ǻϤޤä��Dz���ܤ��ˤߤʤ��鶥���ϤΤ���Dz襫���ȱǼ̵����Ǽ̾������ۤ��ư��绺�Ȥˤ��褦�Ȥ��Ƥ��ޤ�����
- �Dz����ϥե�����ߥ����뷻���ȸ����Ƥ��ޤ���
- ���ϡ��ǽ顢���ޤ����ۤ��벼�Ϥ˻��ȤäƤ��ޤ�����
- �ѡ��ե��졼������1����1���Ǥ�����
- ��������Υ��ͥȥ������פƤ���ͤˤ��ơ��õ��˿���ʤ��褦�ˡˡ���ʬ�����αDz襫���ȱǼ̵�����ޤ���
- �鷺��1ǯ��Ǥ���
- �ե����ε��ʤ�1909ǯ�˹�ݵ��ʤȤ��Ʒ���줿����35mm�ե����ҤȤʤä��褦�Ǥ���
- �ե����ε��ʤ���ˤ�ɳ�ȡ��ֱDz�ե����ε�����ˡ�������������ι���ƹѹ�ˤȥ�ȥ�å��������ι��ʩ���ȹ�������������ʼ�ĥ�ơ����η�̡��Ŷ��λ�ʪ�ǽ���夬�ä��פȵ����Ƥ��ޤ���
- �ե����Ҥϥ�ȥ�å��ʥե�ˤ���Ƴ�����ѡ��ե��졼�����Υԥå��������ȥѡ��ե��졼�����η�˴ؤ��Ƥϥ��������������ƹ�ˤμ�ĥ���̤�ޤ�����
- 1900ǯ����Ⱦ���ե�������ˡ���ʤ�¿�������Ĥ��ʤ���ơ���ˡ���ʤ����Ū�˷����ޤ�����
- �ƹ�Dz軺�Ȥο�ã�ϡ������������ʤ��桹������줺����餬�������Ƥ���1900ǯ���ᤫ��αǼ̵����ץ������Ѥ�³���������å��ؤΥե������ʸ��������ˡ����ʸ���Ƥ��ޤ�����
- �������ʤ˲����ȡ��ޤ������˱Dz赡��������ʤ���Фʤ�ޤ���Ǥ�����
- ����35mm�ե�����Ȥä������������
�����Ĥ����������ե�������ǡ�35mm�ե����Ҥ�������������Ƥ�����Τ��Ȼפ��ޤ���
- ���Υե���ॵ�����ϡ����塼���ѤΥ�����Nikon����ե����ʤɡˤ˻Ȥ��ޤ��������Dz����Ѥ�¿���Υ���餬35mm�ե�����ȤäƤ��ޤ�����
- ���ޤ�35mm�ҤΥե����Υ�����ե����ޥåȤǤ���
- 35mm�Ҥ�ξ��4�ѡ��ե��졼�����Ȥ�������Ϥ����ΤΡ�������ե����ޥåȤ����Ū��ͳ�˷����Ƥ���Τ��狼��ޤ���
- �������ǥ��������ߥ����뷻�郎�Ϥ1890ǯ��Υ������������0.98����� x 0.735������Ǥ�����������������1930ǯ��Ǥϥ�����������������˴�äƾ������ʤ�ޤ�����
- ��¬�ѥ����ϡ��IJ���3��4�ǹ⤵�ʤ��äѤ��˼�äƤ��ޤ���
- �饤���������Υ����ϲ��ˤ���8�ѡ��ե��졼������3��4�β��̤ȤʤäƤ��ޤ���
- �����ե����ΰ���
- ��ϡ�Ĺǯ�Dz�ȳ����Ҷ��ǥե������������Ф����̤��������Ƥ��ޤ����Τǡ��ե������Ф��륫���ޥ�ο��ФλȤ������Ҿ�Ǥʤ����Ȥ��ΤäƤ��ޤ���
- �Dz���륫���ޥ����ĤˤȤäơ��ե�������������̿�������äƤ��ޤ���
- �������ޤä��黣���ѤαDz�ե�����쵤����ʸ���ޤ���
- 3�������٤λ��ƤȤʤ��16,000ft�ʥե����ȡ�ʬ�Υե���बɬ�פǤ���
- 400ft�ե�����40�̤ۤɤǤ��ʤ��褽320���� - 2000ǯ�����ˡ������ե����ȼԤ˰�����ʸ���ޤ���
- ������ʸ����Τϡ���¤���åȤΰ㤤�����ޤ�Ĵ�礬�Ѥ�ꡢ�����Ѥ��Τ��������Ǥ���
- ���åȤǹ��������ե����ϡ�����줿���١����ٴ��������ݴɤ���ޤ���
- �����ƹ���ʻ��ƥ��åȤ�������֡���ͥ�����·���Ƽ��ľ���Τ����ʤ����Ƥ�����ޤ���
- ���ϻ��ƻ���1��24���ޤΥե���������Τ������Ф��椵���ޤ���
- �ե����β��̤˽�������ʤ����������Ȥ��������ϥ��ࡼ���˲�äƤ������������Ȥ������Х�ϥ���������Ѥ�äƤ��ʤ����������Ȥ������Ƹ���϶��������ۤɤζ�ĥ������ޤ���
- �������٤�С��ӥǥ����Ƥϥե�����夬������ʤ��������ޤ������Ƹ��̤������狼��ΤǶ�ĥ���������Ǥ��礦��
- �ե����DZDz��Ȥ����Τϡ������åդ���ͥ�֤ο��ꤪ���붦Ʊ��Ȥξڤ��Ȥ�����ޤ��礦��
- �ƥ�ӥɥ�ޤǡ��Ǹ�ޤǥե����Ƥ�ԤäƤ����Τϡ��ե��ƥ�ӤΡֵ�ʿ�Ȳ�Ģ�סʼ�顧��������¼�ȱ������1944 - 2021�ˡ��ǽ���Ͽ2016ǯ12��ˤǤ���
- �Ǥ����顢�ե����뤹��ե��������ե�������¤��������ˡ���٤ˤĤ��Ƥ��ʤ�ο��Ф�ȤäƤ��ޤ���
- ��2023ǯ6�����¼�ȱ�����θ��Ѥ��DZ��ξ��ܹ���Ϻ�������˵�ʿ�Ȳ�Ģ�λ��Ƥ����ä��Ȥ�������ˤ��ޤ�������������̤����ե�����Ȥä�����黣�ƤǤ��뤫�ɤ����Ϥ狼��ޤ��� - 2023.10.21������
- �����ѡ��ե��졼������perforation���������ε��ʲ�
- �ѡ��ե��졼�����ʥե��������빦�ˤ���ˡ���٤϶ˤ�Ƹ��������ʲ�����Ƥ��ޤ���
- �ѡ��ե��졼�����ι��������٤�0.1mm���äƤ�����ɤ��Ǥ��礦��
- 18mm x 24mm����3/4����� x 1������ˤΥ��ͥ������β��̤�6m x 16m�Υ������˱Ǥ���Ψ�ϡ���������333�ܤǤ���
- 0.1mm�Υ����ϡ����������33cm���ɤ�Ȥʤä���Ƥ���ޤ���
- 20mΥ�줿�ѵҤϤ����ɤ��0.47�١�ξ�֥��0.94�١ˤǤȤ館�ޤ���
- �ʹ֤��ܤϡ�1/2000�����٤�ʬ��ǽ������ޤ����顢6m�Υ�������Ǥ�3mm�ο����ǧ��뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
- �Ĥޤꡢ330mm���ɤ�Ͽʹ֤θ��и³���110�ܤ��礭���ɤ�Ȥʤ�Τ��Բ��˱Ǥ�ޤ���
- �����ɤ�������3mm������ޤ���ˤϡ��ѡ��ե��졼���������٤������18mm��1/2000���Ĥޤ�0.01mm���٤����٤��ޤ��ʤ��Ȥ����ʤ����Ȥˤʤ�ޤ���
���Τ褦����ͳ���顢�ե����ˤϤ��ʤ����ˡ���١����������٤��ᤵ��Ƥ���ΤǤ���
- ���Τ褦���طʤ��顢1900ǯ������ƹ����ǵ��Ȥ����٥롦�ϥ�������ϡ��������٤��Ѥ����뤵���ʥѡ��ե��졼���ˡ��ץ���������߷������ˤ�����ޤ���
- �ե����Υѡ��ե��졼�����ϡ��ե������¤��Ҥ������ƾ���Ԥ��Ϥ����ΤȤФ���פäƤ��ޤ����������������ʻ������ɤ�Ǥ����ȡ�����Υ�����ե����Ϸꤢ��������Ƥ��ʤ��ƥ�����桼������ʬ�����Ƿ곫���Ƥ������Ȥ��狼��ޤ�����
- �ե�Υ��ߥ����뷻��κ�ä��Dz襫���ϡ�1����1���ξ������1��ǹ��2��ˤǤ�����������������Υ����̲�Ҥ��ä�Dickson��Biograph�����ϡ����ƻ��˥������ǥѡ��ե��졼�����η곫����Ԥ���¤�Ȥ��Ƥ��ޤ�����
- ����������õ����뤿��Ǥ���
- ����������ǡ���������Bell & Howell�Ҥ�������ޤ���·���ǵ��ʤΤȤ�ʤ��ե����Υѡ��ե��졼�����˰��Ф��ꤸ����̩�ʹ���������Peerforator�ˤ���������Ϥ�ޤ�����1909ǯ�ˡ�
- ���������줿�ե�����Ŭ�礷��������Bell & Howell 2709����1912ǯ������ޤ���
- ���Υѡ��ե��졼�������ˡ�ȥѡ��ե��졼��������Ǥ��ä����ᡢ�ե����������Kodak����Ѥ��ᡢ��ݵ��ʤȤʤäƤ����ޤ�����
- ���ޤΥѡ��ե��졼�����ϡ�1934ǯ���Dz赻�ѼԶ����SMPE = Society of Motion Picture Engineer, 1916ǯ��Ω�����SMPTE = Society of Motion Picture and Terevision Engineer�ˤǷ���줿���ʤǤ���
- SMPE�ϡ��ѡ��ե��졼�����η�����2��ǧ�ᡢ�ޤ����ѡ��ե��졼�����ֵ�Υ��2����ǧ��ޤ�����
- 2����Υѡ��ե��졼�����ϡ�BH�ܤ�KS�ܤǡ�BS�ܤ�Bell & Howell�Ҥ����Ѥ��Ƥ�����Τǡ�KS�ܤ�George Eastman��Kodak�˼Ҥ����Ѥ�����ΤǤ���
- �ѡ��ե��졼�����ԥå��ϡ����ԥå��ȥ��硼�ȥԥå������ꡢ�Dz����Τ�Τ����ԥå��ǡ���ǯ�ˤʤäƥ��硼�ȥԥå������Ѥ���ޤ�����
- �������̯�ʰ㤤�����μ�«�����˵������ꤵ�줿���ȸ����ȡ������ȵ������Ǥ����ޤäƤ����褦�Ǥ���
- �ե����Υѡ��ե��졼�����ϡ��ǽ�αDz�˥�������ʤȽ����Dickson�ˤ�ȯ�Ƥ����õ���������ޤ��ˡ��ݷ��φ0.110����� = 2.794mm�ˡ������ƹ��ֵ�Υ0.187�������= 4.750mm�ˤǻϤޤ�ޤ�����
- �ݷ��������ǽ�ʤȻߤޤ����١ˤ�˧�����ʤ��Τǡ��ߤ���Ȥ��ޡ�pull down claw�ˤ�ե����ߤ�ԥ��registered pin�ˤ����ä���ۡ���ɤǤ���褦�����������ξ岼��ʿ�ˤ��ޤ�����
- ���줬BH�ܤȸƤФ���ΤǤ���
- ���ι������ϡ�1909ǯ�٥�ϥ�����Ҥ��ե���व����Perforator�ˤǺ��Ѥ����ե�����Ҥ�Kodak�����Ѥ������Ȥ����ƹ�Ƕȳ�ɸ��Ȥʤ��������ʤޤǤˤʤ�ޤ�����
- ���θ�20ǯ���٤�Фơ�Kodak��KS�ܤ���Ѥ��Ϥ�ޤ�����
- BS�ܤϡ����ץ����åȤ�쥸���ȥ졼�����ԥ�ä���ȥۡ���ɤ��������Ϥ��ä���ΤΡ����ä��ꤷ������Ĺ���ֲ����Ǽ̵����̤��ƥե�����Ȥ��ȥѡ��ե��졼������ˤ����꤬�����Ƥ��ޤ�����
- �ޤ����ѡ��ե��졼��������ˡ�����ä��ꤷ�Ƥ��뤬�Τ˥��ץ����åȤ���ե���बΥ���ݤβ����礭���ơ��ե����ˤ�������Ϳ���뤳�Ȥ��狼�äƤ��ޤ�����
- ������Kodak�Ҥϥѡ��ե��졼�����˵���������ʤ������ʡ���ݤ�빩�פ����������ζҤ���ˤ���礭����Ρ�KS�ܡˤˤ��ޤ�����
- ���κ���0.005������� = 0.127mm�ˤǤ�����
- �ޤ�����������ɥ١����Υե����ϡ���������ǯ�Ѳ��ǥե���ब�̤ळ�Ȥ�ǧ����Ƥ��ơ��ͥ��ե����ȥץ��ȥե����������̤��碌��Ϣ³�ץ�����̤��ȡ����ץ����åȶ�Ψ�ˤ�ä�ξ�Ԥζʤ���Ⱦ�¤˺����Ǥ��ե����Ʊ�Τ�����礦���꤬�����Ƥ��ޤ�����
- ��������������뤿�ᡢ���ꥸ�ʥ�ե����ʻ����ѥͥ��ե����ˤˤϽ����BH�ܤ�0.187������ֳ֡ʥ��ԥå��ˤΥե�����Ȥ����ץ���ѵڤӥ�С�����ե����ˤ�KS�ܤ�0.186������ֳ֡ʥ��硼�ȥԥå��ˤΥե���ब�Ȥ���褦�ˤʤ�ޤ�����
- ���줬1934ǯ�����ꤵ��Ƹ��ߤ˻�äƤ��ޤ���
- ��
- �����ե��������
- 35mm�Dz�ե����ϡ�100ft��30.5m�����̡�200ft��61.0�������̡�400ft��122m�����̡�1,000ft��305m�����̡�2,000ft��610m�����̤�����Ū�Ǥ���
- �Dz軣�ƤǤϡ�100ft�⤷����400ft���̤Υե���ब����Ū�ǡ��Dz�ۤǤαǼ̤Ǥ�2,000ft������Ū�Ǥ�����
- �Dz��Ǥˤ�2000ft���̤�6�̡���2���֡˻��Ѥ��Ƥ��ޤ�����
- �Dz�ե����ξ�硢1��α����ޤȸƤӡ�1ft������16���ޤλ��ơʱDz�ν����̵���Dz�Ǥλ��ƥ���®�١ˤ�Ԥ��ޤ���
- �ʲ�����Ʊ���˵�Ͽ����ȡ������λ���ˤʤäơ�16���ޡ��äǤϲ����������Τ�24����/�äˤʤ�ޤ����������ϥե����¦���˸���Ū�˵�Ͽ���Ƥ��ޤ�������
- 1���ޤˤϡ�4�ĤΥѡ��ե��졼�����ʬ�Υ��ڡ��������Ƥ�줿���ᡢ�ѡ��ե��졼�����ֳ֤ϡ�1ft/��16���� x 4�ѡ��ե��졼�����/���ޡ� = 4.7625mm�ʼºݤε��ʤ�4.750mm��/�ѡ��ե��졼�����Ȥʤ�ޤ���
- 1ft�Υե�����16�����Ƥ��Ǥ���Ȥ������Ȥϡ������������λ���®�٤�16���ޡ��äǤ��ä��Τǡ�1��1�ե����Ȥȸ����狼��䤹���ܿ��ˤʤ�ޤ�����
- �������Ƥߤ�ȡ�100ft�Υե�����100�á�1ʬ40�áˡ�400ft��400�á�6ʬ40�áˡ�1000ft��16ʬ40�äλ��Ƥ��Ǥ��ޤ�����
- ���ߤǤ�1�ô֤�24���ޤαǼ̤����ʤȤʤäƤ��ޤ����顢�嵭�Υե����Ǥϡ�100ft��1ʬ7�á�400ft�Ǥ�4ʬ27�á�1000ft�Ǥ�11ʬ7�äȤ������ˤʤ�ޤ���
- 2���֤αDz��ǤǤ�10,800�ե����ȤΥե���बɬ�פˤʤ�ޤ���
- ���ƻ��ˤϤ���1.5�ܤ��餤�Υե���बɬ�פǤ��礦���顢16,000�ե����ȤΥե�������ݤ��Ƥ����ʤ���Фʤ�ޤ���
- �ե����β��ʤ�100�ե�����20,000�����١�2000ǯ�����β��ʡˤȤ���ȡ�3,200,000�ߤΥե�����夬ɬ�פȤʤ�ޤ���
- ��
- �����Dz襫���
- �Dz軺�Ȥϡ���ˤ�Ҥ٤��褦�ˡ�1894ǯ�ƹ��쳤�ߤΥ��������Υ�������Ȥ��ε���Dickson����New York���������������ˤ���Eastman Kodak�Ҥ�35mm�ҥ�����ե�����ȯ���������Ȥ���Ϥޤ�ޤ���
- �����Υ�������αDz�ۤȱDz軺�Ȥϡ���ǯ���1895ǯ���ե�Υ���Υ��ߥ����뷻���Auguste Marie Louis Lumière��1862 - 1954��Louis Jean Lumière��1864 - 1948�ˤ���ä��Dz襫���ȱǼ̵������������αDz�ۥ������뤬�ǽ�ȸ����Ƥ��ޤ���
- ��ޤ����֤�����������ʤ���θ����ε���Dickson�ˤˤ�ä�ȯ�����줿�ǽ�αDz襫���Ǥ���
- ���֤��礭���ϡ����ե������˾�뤯�餤���ꡢ�Ť���100kg��ۤ��Ƥ��ޤ�����
- �������Ӥ�����̵������ʪ�ǡ���äѤ饹����������Ǥλ��ƤȤʤäƤ����褦�Ǥ���
- Kinetograph�ϡ�Ϣ³�������������ƤǤ���褦�˥�����ե�����Ȥ���������֤��ˤ�����ư�⡼������ľή�ˤǶ�ư�����Ƥ��ޤ���
- �Ÿ��ϥХåƥ���Ѥ��ޤ�����
Dickson��Kodak��ȯ�������ե����ϡ�50ftĹ��15.2m�ˤǡ����Kinetograph�μ̿���Ȥ������٤��礭���Υե����ޥ������ޤäƤ��뤳�Ȥ��狼��ޤ���
- �Dz襫�����ŵ��⡼������Ȥä��Τϥ�������ʤ�ǤϤȻפ碌�ޤ����ʥ��������ȯ�ŵ�����������ȯ�������ΤǤ����顢���ȥ١����Ǥ��ŵ�����Ǥ�����
- ��ʪ������ˤϲ�ž���ĥ���å������Ȥ߹��ޤ�Ƥ��ơ��ե�����������˱��ĥ���å����ι�̣���蘆�ä�Ϫ������ߤ����ե�������꤬��ߤ��������DZ��ĥ���å����γ�������������Ϫ������ޤ���
- ���ΰ�Ϣ��ư���ϡ��ַ��ߤ���Ȥ���ư��intermittent movement�ˤȸƤФ���Τǡ��Dz軣�ƤȱǼ̤δ���ư��Ȥʤ�ޤ�����
- ��������λ��Ƶ��ϡ�40����/�ä���50����/�äǻ��Ƥ����ȸ����Ƥ��ޤ���
- ������ͳ�ϡ��������٤ˤ��ʤ��ȱ��ĥ���å����ǤΥե�å����������Ƹ���˴������ʤ��ä�����������Ǥ���
- ���ߥ����뷻��ϡ������к��Ȥ��ƱǼ̻��ˤϱ��ĥ���å�����1���̤�3���ڤäƥե�å������ޤ������ᡢ16����/�äλ��Ƥ���ǽ�Ȥʤä������Ǥ���
- ������������ʤ��������ƻ��֤�Ĺ��������Ѥ�¤��夬��ޤ���
- �ºݤνꡢ�Dz襫��餬��ư�������ΤϤ��äȸ�Τ��Ȥǡ�����αDz襫����1920ǯ��ޤǡˤϼ�ư�����ȤäƼ�ǥե��������ä�ư�軣�Ƥ�ԤäƤ��ޤ�����
- �����ϡ��ŵ��������ˤʤ��ä�������ƻ��μظ��Τ褦���ŵ�����Ȥ˥ץ饰��ؤ��ƴ�ñ���ŵ�����櫓�ˤϤ����ʤ��ä��ΤǤ���
- ��������ҤǤϡ�������Kinetograph�ˤǻ��Ƥ����ե������˼����褦�ʱǼ̵���Kinetoscope�ˤˤ����ơ���������褦��ư������֤�ȯ���ޤ�����
- 1894ǯ�Τ��ȤǤ���
- Kinetoscope�ʥ��ͥȥ������סˤϸ���ʪ�����ʥ��ͥȥ������ס��ѡ��顼�ˤ˲�����֤��졢�ѵҤ�Ƥӹ����ư����붽�Ȥ˻Ȥ��ޤ�����
- ʣ����Υ��ͥȥ������פˤϤ��줾���15�äۤɤ�û��ư�褬���Ƥ�Ƥ��ơ��Ҥϥ������25����ȹŲߡˤ������������˴���Ť���ư��ޤ�����
- ���ͥȥ������פϥ���ɥ쥹�Υե�����Ȥä�Ϣ³�Ǽ̤�ԤäƤ��ޤ�����
- ���ߤαǼ̵��Τ褦�ʴַ祳������ǤϤ���ޤ���
- ���ͥȥ������פ�Ϣ³�ե��������ˤ��Ǽ̤ǡ�������������������֤��褿�Ȥ��ˤ��Υ����ߥ˹�碌�Ʋ�ž���ĥ���å��Υ���åȤ������ơ����ȥ��ܸ��̤Τ褦�˱Ǽ̤Ƥ��ޤ�����
- ���αǼ������ϡ�Zoetrope�ʥ����ȥ����ס���ž�Τ������ˤ˻��Ƥ��ơ���������ҥ�Ȥ����Ƥ���褦�˴����ޤ���
- ��
- ��
- �������ߥ����뷻��
- ��������αDz�ζ��Ԥ��ե������Υ��ߥ����뷻��ϡ�1ǯ���1895ǯ����ʬ�����ǻ��Ƶ�����ޤ���
- ���βȤϥե�Υ���ˤ��äơ��̿����ĤȰ���桢���ꡦ���ι����Ĥ�Ǥ��ơ����ߥ����뷻���������Ѥ��Ǥ��ޤ�����
- ���륤�����ߥ�����34�ͤλ����㥢��ȥ�̤�����˻������ä���������Ρ֥��ͥȥ������ספơ���餬���ۤ��Ƥ�����Ǽ�ư��Ȥϰ㤦���Ȥ˰��´���Ф��ޤ���
- ���������ȯ���������Ƶ���Kinetograph�ˤȱǼ̵���Kinetoscope�ˤϡ��礭�����꤬��������ϸ�ȴ���ޤ�����
���ߥ����뷻�郎��ä����Ƶ��ϡ��ͥ��ե���फ��ݥ��ե�������ץ�ȥե�����Ǽ̤���Ǽ̵��ε�ǽ���������Ƥ��ޤ�����
- �Ǽ̵����ظ�˹�٤Υ��פ����֤��ơ�������Ǥ��Ф������ϰŤ����Ĥ館�ơ��Ǽ̵��������ˤ��礭�ʥ�������ĥ�äƴѵҤ��Ʊ�˽���ƥե������Ǥ��ޤ�����
- ���ߥ�����η���ζ��Ȥͥޥȥ���ա�Cinématographe�ˤȸƤ���Τǡ��ʸ�Dz�ϥ��ͥޡʥ��ͥޥȥ���ե����ˤȸƤФ��褦�ˤʤ�ޤ�����
- �ʸ��ή�ˤʤ�Dz�ۤθ������ä��Τǡ����ϡֱDz����פȸƤФ�Ƥ��ޤ���
- ���Υ����ϥ������ǥ�������γ�ȯ�������ͥȥ���դ���٤�ƤȤƤ⥳��ѥ��ȤǷڤ����������ŵ��Τ���ʤ����������Ȣ�����Ǥ�����
- �ե����ϡ���������λȤäƤ�����Τ�Ʊ����Τǡ�Ʃ�����������35mm�ҥ�����ե����ǡ��������18mm x 24mm���������ե���������ѡ��ե��졼�����ϡ��ݷ��ξ�����ɤ˰�ĤŤķ�2���Ȥ���1�ô֤�16���ޤλ���®�٤�50�ô֡�800��ˤλ��Ƥ�Ԥ��ޤ�����
- �ե�����Ĺ����50ft��15.2m�ˤȤʤ�ޤ���
- �ʻ�����ȡ��ե�����Ĺ����17��ȥ��55�ե����ȡˤǡ���Ǥ�46�äȽ�Ƥ���Τ�¿���������ޤ����ե�������Ƥ���ʬĹ���θ�����ͤ��⤷��ޤ���
- ���αDz�ۤǺǽ�˾�Ǥ��줿�Τϡ��ֹ���νи���Workers Leaving the Lumière Factory�ˡ��Ȥ���46�ä����̵��û�ԱDz�Ǥ�����
- ���αDz�ϡ����ߥ����뤬��ͭ���빩��ǤλŻ������Ұ�����Ҥ����ͻҤ��Ĺ���餬���Ƥ�����Τ������ǡ����̤ο�ã�ξ�ʤǤ���
- �ե�ο�ã�ϡ���ʬ�Ȥ�ޯ�����������������äƤ����Τ��ʤȻפ碌�ޤ���
����û�ԱDz��1895ǯ���ѥ�Υ�����ե��ϳ��Υ����ʥ�ǥ�����ˤ�ͭ���Ǹ������ޤ�����
- ���ߥ����뷻��ϡ����鳫ȯ����������ô�������������ꡢ��̣�������ʤ�͡��Ƥ��Ƥ������Ǹ������ޤ��������ܤ����ʡ���礤�ξ�ʡ����Ԥ�����⤢��ޤ��ˡ�
- �����κ��ʤϡ�46�äΥե�����50�ե����ȡˤ˼���Ƥ��ޤ������顢��������ѥ��Ȥʼ������Ȥ������������ä���ΤȻפ��ޤ���
- ��
- ��
- �����ѥƷ���
- ���ߥ����뷻��ϥ����ȱDz����֤�1902ǯ��Ʊ��ΥѥƷ��ᆭ���Pathè Frères�ˤ���Ѥ��ޤ�����
- �ѥƼҤ�1896ǯ��4�ͤη�����߲����ʥե��Υ���ե쥳���ɡˤ����䤹���ҤȤ��ƽ�ȯ�����Dz�ȳ��˿ʽФ��Ƥ���ϱDz襹���������Dz�ۡ�����顢�Ǽ̵��������ʰ��ڤ�꤬������켡���������1914 - 1918��ľ���ˤϥ衼���åѱDz軺�Ȥ�Ⱦʬ�ʾ�Υ����������Ƥ����ȸ����Ƥ��ޤ���
- ���ΥѥƼҤ���켡�������郎��λ���������꤫����Ӥ������������ᡢ�Dz������Ϣ�������Ѥ��Ʒ����۵����ǰ����褦�ˤʤ�ޤ���
- ���ߥ����륫���ʸ�Υѥƥ����ϱ��˼����褦�ʤ�Τǡ��ѥƥ��������ȸƤФ�ޤ�����
- �����γ��Ѥ������ǡ����μ�����ĥ�ꤷ400ft�ʥե����ȡ˥ޥ���������夷�ƻ��ƻ��֤�8�ܤ˿��Ф��ޤ�����
- ���Ƥϼ�ư����ˤ���Τǡ��������ȱDz�Ǥ�����
- �����β��ˤϥե�����������դ����Ƥ��ޤ���
- ���Υ�����Ȥä�1,700�ܤκ��ʤ����줿�ȸ����Ƥ��ޤ����顢1900ǯ����1920ǯ��ޤǼ�ή�Υ������ä��ȸ����ޤ���
- 1890ǯ�夫��1900ǯ����ˤ����ơ��ƹ�����Ҥ��꤬�����Dz襫���ȱDz�ۤϤɤΤ褦�ˤʤäƤ����ΤǤ��礦��
- �ե���ѥƼҤαDz襫���ϡ��ƹ��쳤�ߤǻȤ��Ƥ���������¿������������Ҥϥ������¤�˴ؤ��ƤϤ��ޤ��Ϥ�����Ƥ��ʤ��ä��褦�˴����ޤ���
- ȿ�̡��緿�Ǽ����֤��äƱDz�ۤ�Ĥ��ꡢ1900ǯ����Ⱦ�������������DZDz軺�Ȥ���δ���ƹԤä��褦�Ǥ���
- ��������Ҥ��ǽ�˺�ä�Kinetoscope�ϡ���ͤ����αǼ̵����������ߥ�������������Ƹ�������Ǥ�����
- ����Ǥϰ��٤ˤ�������δѵҤФ��ޤ���
- ���ߥ����뷻��αDz���������Τä���������ϡ�1896ǯ��Kinetoscope���夨�Ʒ��Ǥ�������δѵҤ�������Ǽ̵�Vitascope��ȯ���ޤ���
- �������������Υӥ��ͥ��ץ��ϡ�Kinetograph��Kinetoscope����¤���䤷���٤���ͽ��Ǥ���������Ǥ���ե���������ƾ�Ǵۤ��Ϥ��������ƥ������������Ϥ뤫�����פ��Ф�Ȥ��ơ��Dz�����˥ӥ��ͥ��γ���ڤꡢ������Ǽ̵��γ�ȯ��³�����Τ���¤�ˤ��Ϥ�����ʤ��ʤꡢ�ѥƥ�Ȥ����˸Ǽ�����褦�ˤʤ�ޤ�����
- ��ϡ�1908ǯ�˥ѥƥ�Ȥ����������Motion Picture Patents Company�ҡ�MPPC�ˤ���Ω���ơ��Ǽ̵��䥫�������羮�β�Ҥ˥������ƥ�����Ω�Ƥ�褦�ˤ��ޤ�����
- ���줬ȿ�ȥ饹��ˡ������Ȥ����礭�ʺ�Ƚ�Ȥʤꡢ���η�̡����ʤȤʤ�1918ǯ��������ϱDz�ȳ�����ű��뤳�Ȥˤʤ�ޤ�����
- ��
- ��
- ����Bell&Howell 2709����2020.04.08�ˡ�2023.10.23��
- �ƹ�Ǥϡ�1912ǯ��Bell&Howell������Bell & Howell2709�Ȥ�������餬���졢1960ǯ���ޤǻȤ��ޤ�����
����ޤǤϡ���˽Ҥ٤��ե�Υѥƥ���餬�Ȥ��Ƥ��ޤ�����
- Bell & Howell2709�νи��ˤ�ꡢ�ƹ�αDz軺�Ȥ��ƹ����֤������褦�ˤʤ�ޤ�����
- Bell & Howell2709�ϡ��ϥ��������Ŵ���ˤ����Τ���ɮ�Ǥ�����
- ����ˤ���ϴ�ǿ������Τ��뻣�Ƥ��Ǥ��ޤ�����
- ��ޥ���������2������̤Ϫ���ե������Ǽ���������Ȼ��ƺѥե�������������ˤǡ����줾��˴ݷ��Τͤ����߳����ߤ��Ƹ��̤˳�������褦�ˤ��ޤ�����
- ����������ˤϡ�32�����礭�ʥ��ץ����åȤ��ߤ��Ƽ����ϥ�ɥ��ľ�뤵�����ϥ�ɥ�1��ž��8���ޡ�32�ʻ�/��ž��/4�ʥѡ��ե��졼�����/���ޡ� = 8����/��ž�Ϥλ��Ƥ�Ԥ��ޤ�����
- �����αDz��1�ô֤�16���ޤλ��ƤʤΤǡ������ޥ��1�ô֤�2���ϥ�ɥ�����Τ˲����Ȥˤʤ�ޤ���
- �ե����Υѡ��ե��졼�����ϡ�1�ե����ȡ�30.48cm��Ĺ��64���� = 16���� x 4�ѡ��ե��졼�����ˤ��������Ƥ����Τǡ�1�ô֤�1�ե����ȤΥե��������Ȥʤ�ޤ���
- ���Υ����Ǥϡ��ե��������Τ��ߤ���Ȥ��ޡ�claw�ˤ˲ä��ơ��ե�������꤬����ä���˥ե�����������ߤ����ơ��ʤ����ĥե��������������֤˸��ꤹ�뤿��θ���ԥ��fexed pin, registration pin�ˤ����빩�פ��ʤ���Ƥ��ޤ�����US�ѥƥ�ȡ�1,038,586 Set.17,1912�ˡ�
����ԥ�ϥ����ɥץ졼�Ȥ˸��ꤵ��Ƥ��ơ��ե������ޤ���ץ�å��㡼�ץ졼�Ȥ�Ϫ�����˥ե������Ĥ��ƥ����ɥԥ�ǥե�������ꤵ���ޤ�����
- �ե��������κݤϡ��ץ�å��㡼�ץ졼�Ȥ��ˤ�ǥե���������䤹�����Ƥ��ޤ�����
- ����ԥ�ǻ��ư��֤����줿������ե�����α����ϡ�1��1�礷�ä���Ȳ������֤����ꤵ��뤿�ᡢ���Ƥˤ���֥��˸¤ޤ��ޤ��뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ�����
- �ץ�å��㡼�ץ졼�Ȥϴַ籿ư�ǰ�������ԤäƤ���Τǡ����ƻ������ϥХ��Х�����ȼ���礭����ΤȤʤ�ޤ�����
- ���줬�ȡ������Dz�ʲ���Ͽ���ˤλ���ˤʤ���礭������Ȥʤ�ޤ�����
- ������ϡ����Ѥ���˾��ޤ�4����Υ����ñ���夨����褦��4Ϣ��ܥ�С���������åȤˤʤäƤ��ơ�������ˤϥ�ա��ɤȥե��륿���������Ǥ���ޥåȥܥå�������������Ƥ��ޤ�����
- ��β��Ĵ���ȥե���������碌�ϼ��Τ褦�˹ԤäƤ��ޤ�����
- ����������夹�����̤�4Ϣ������åȤˤʤäƤ��ơ�4�ĤΥ������Ǥ�90�٤��IJ�ž�Ǥ���褦�ˤʤäƤ��ޤ���
- �ե��������Ȳ��Ĵ����Ԥ��ˤϡ�4�ĤΥ�Τ����λ��Ƥ˳��������Ƥ�����֤���180��ȿ�Ф˻��ä���ޤ���
- ���ΰ��֤ˤϥե����Ϥʤ�����ɤ⡢�ե��������ѤΥ롼�ڤ����֤���Ƥ��ޤ���
- �����Ǿܺ٤ʲ�Ѥȥե���������碌��Ԥäơ�����180�٥�����åȤ�ƥ���ᤷ�ޤ���
- ���Τޤ��Ƥ������180�٥�������ʬ�����ѥ��å������ǤƤ��ޤ��Τǡ���������Τ�ʬ�������������ˤ��餹�����������������Ȼ��Ӥδ֤��ߤ����Ƥ��ޤ�����
- �ե��������Ȳ�Ѥ�Ĵ���Ϸ빽���ݤʤΤ����ˤ˥������֤��Ѥ��뤳�ȤϤǤ��ޤ���Ǥ�����
- �����ޥ���֤��鸫�ƥ����κ����ˤϥե�����������դ����Ƥ���Τǡ�������Τ����褽���ȼ��ʲ�ѡˤϳ�ǧ�Ǥ���褦�ˤʤäƤ��ޤ�����
- ���λ���ϡ�ͥ���ʥ������Ϥ���ޤ���Ǥ�����
- ������ƥ����Ѥ�ʤ��ä��Τǡ���������¿���������ϻ��Ѥ��Ѥ��ʤ��ä��ΤǤ���
- ����˥���߷פ�ʣ���ʤΤǡ�����ԥ塼����ȯã���Ƥ��ʤ��ä�1900ǯ��Ƭ�ϥ�������˾��٤��⤢��ޤ���Ǥ�����
- ���Υ����ϡ��������ȱDz������礤�˼��������졢���㡼�륺������åץ����Υ������ȱDz�˻Ȥ��ޤ�����
- ��
- ��
- ����Bell & Howell�ҡ���2020.04.08�ˡ�2020.04.19�ˡ�2023.10.23�ɵ���
- 1900ǯ���Ƭ�Υ������ϡ��Dz軺���濴�ΰ�ĤȤʤäƤ��ޤ�����
- ���Υ������˥٥�ϥ�����Ҥ�2�ͤ��о줷�ޤ���
- Donald Joseph Bell��1869 - 1934�ˤϱDz�ۤαǼ̵��դȤ��ƺ�ǽ�֤��������饤�ɱǼ̵���Kinodrome��Ÿ���ۡ���䥷�硼���ǻȤ��Ǽ̵���ˤβ��ɤ�꤬���Ƥ��ޤ�����
- ���˲�Ҥ�Albert Summers Howell��1879 - 1951�ˤȤϱǼ̵���������¤��Ҥǽв��Ȥˤʤ�ޤ���
- �٥�Τۤ����ϥ�������10��ǯ��ǡ�ξ�ԤȤ�ѼԤǤ���
- �٥뤬�Dz����Τ��Ϥ����Τ��Ф����ϥ����������ε������ѼԤǡ��ᥫ�˥�����߷פ�������ɤκ�ǽ���ˤ�Ĥ����ä��Ȥ������Ȥˤʤ�ޤ���
- Howell�ϥߥ��������ޤ�Ǥ��ꡢ���θ奷�����˰ܤ�Ǽ̵�����¤���������빩���Ư���Ф��ޤ���
- 1906ǯ�ˤ�Kinodrome�Ǽ̵��β��ɤǺǽ���õ���������Ƥ��ޤ���
- �٥�αǼ̵��դȤ��Ƥκ�ǽ�ȥϥ�����ε������դȤ��Ƥ�ŷ��κͤ�ߤ���ǧ���ä�ξ�Ԥϡ��Dz軺�ȳ��ǰ���Ȥ��褦��1907ǯ�˼�ʬ�����β�Ҥ���Ω���ޤ���
- �����Ω���ϱDz��Ϣ�������¤�ȥ���������Ǥ�����
- ��Ω����λŻ��ϱǼ̵��ν���������Ⱦʬ�ʾ�����Ƥ��ޤ�������10ǯ�δ֤˼��Ȥε���������褦�ˤʤ�ޤ���
- �����αǼ̵���ȯŸ�Ӿ�ε����Ǥ⤢�ä����ᡢ�ե�������Ԥΰ�����������ȱǼ̾�Υ���ĥ��ʥե�å����ˡ������Ƶ����ɸ�ಽ�����꤬����ޤ�����
- �����Ϻ����Dz赡���˥Х�ĥ������ä��ΤǤ���
- ���ϡ�35mm�ե�����ư�赡��˽��椷�Ƶ��ʤ�������ɸ�ಽ��ޤ�ޤ���
- 35mm�ե���ൡ��ʳ��ˤ��ܤ⤯��ʤ��ä�����������ޤ���
- ��餬���椷���Τ�35mm�ե����Υѡ��ե��졼�����������ɤ�������Perforator�ʥѡ��ե��졼�������ӹ����ˤ�35mm�Dz襫��顢�����ƥͥ��ե���फ���ǥե�����Ƥ��դ���ץ�Ǥ�����
- ����3�Ĥε����ɸ�ಽ��㤭�٥�ϥ�����Ҥ������뤲�Ƥ����ޤ�����
- ��餬�ǽ��35mm�ե����Dz襫�����ä��Τ�1910ǯ�ǡ���Ȣ�ȳ�ĥ��Υ����Ǻ���ޤ�����
- ����ϥե�ΥѥƼҤΤ�Τ��Ѥ��ޤ���
- ��������������ĥ��Υ���餬��������ޤ���
- ����Ӥˤ�äƥ�����»����Ϳ���Ƥ��ޤ��ޤ�����
- �桼�����ʱDz���ĤȽ�ͥ���ء�Martin and Osa Johnson�ˤ�������Ȥ��ƥ��եꥫ�˥����ʱDz����̾�ϡ�I love Adventure�סˤ˹Ԥä����ˡ��������꤬ȯ�������ΤǤ���
- �����ǥ٥�ϥ�����Ҥϡ������Υϥ�����ߥ������㥹�Ȥ��夨�ޤ�����
- �����˶�°���Dz襫��餬���ƴ������ޤ�����
- 1912ǯ�����Υ�����Bell & Howell 2709��̾�դ����ޤ�����
- ��°�ϥ��������ä������������ζ�ư�ᥫ�˥�������̤Ȥʤꡢ����ޤǺ��줿�Dz襫������ǺǤⴰ���٤ι⤤��ΤȤ���ɾȽ�ˤʤ�ޤ�����
- �Dz軺�Ȥ������ߤ˰ܤäƤ����Υ�����ɾȽ�ǡ�1919ǯ�ޤǤˤϥϥꥦ�åɤǻȤ��륫���ΤۤȤ�ɤ�Bell & Howell 2709�ˤʤ�ޤ�����
- Bell & Howell 2709�����������˹���ǡ�����������ͭ�Ǥ����ΤϸĿͤǤϥ��㡼�������åץ��Τߤǡ���Ϥ��٤ƥ��������ʱDz�����۵��ҡˤ���ͭ�����ȸ����Ƥ��ޤ���
- ����åץ��Ϥ��Υ����˿�ʬ�Ȥ������ǡ�̵���Dz褫��ȡ������λ�����Ѥ�äƤ�����Ǥ�Ŀͽ�ͭ��Bell & Howell 2709�����³������ϥ�ɥ�ˤ��Dz軣�Ƥ�³���Ƥ��ä��ȸ����Ƥ��ޤ���
- ���Υ����ǻ��Ƥ�����κ��ʤˤϡ���A Dog's Life��1918�ˡס���The Kid��1921�ˡס���The Gold Rush��1925�ˡס���City Lights��1931�ˡס���Modern Times��1936�ˡפʤɤ�����ޤ���
- ����
- �٥�ϥ�����Ҥ�2709������¾�˷����Ѥ�������16mm�ե�����ѥ����Filmo�ʥե���⡢1923ǯ�ˤ�35mm�ե�����ѥ����Eyemo�ʥ����⡢1925ǯ�ˤ���¤������ƻ�Dz��Newsreel�ˤ䥢�ޥ��奢���������䤷���ۤ���16mm�ҥե�����ѱǼ̵���8mm�ե���५���ڤӱǼ̵���1934ǯ��1935ǯ�ˤ�꤬���ޤ�����
- ��
- ��
- �����ϥꥦ�åɡ�1900ǯ����Ⱦ����
- �ƹ�αDz軺�Ȥϥ������ȥޥ��å��䥨������ꡢBell & Howell�Ҥʤɡ��쳤�ߤDz�����ȯŸ���ޤ�����
- ���λ䤿���δ��Ф��鸫��ȡ��Dz軺�Ȥ��ܻ��������ߤΥ������륹�ˤ���ϥꥦ�åɤ������ޤ���
- �ƹ�αDz軺�Ȥ��쳤�ߤ��������ߤ˰ܤä��Τϡ�1910ǯ��Ǥ���
- ��
- ��
- 1908ǯ���������Dz�ζ��Դ�Ϣ���õ����������MPPC��Motion Picture Patents Company�� = Edison Trust�ʥ�������ȥ饹�ȡˤ���Ω������ʬ�����������������Ȥ��Ƥ��ޤ�����
- �ĤޤꡢMPPC������ʤ��ȼԤ��Ф��Ƥϻ��Ѥ˺ݤ���ˡ���ʻ��������ᤷ���ΤǤ���
- ���Τ������ȿ�Ф����澮�αDz軺�ȶȼԤϡ��˥塼���㡼������˥塼�衼�����������ʤɤ��쳤�ߤ������Ϥ��ʤ������ߤ�ƨ�����Ω�����Dz軺�Ȥ��ޤ�����
- ʻ���ơ�MPPC�����������ʤ��ƺ�Ƚ�����ޤ�����
- �������ȥޥ��å���ǽ��MPPC�˲��������궡��������Ǥ��ޤ�������1911ǯ��MPPC�������ʤ����Τˤ�ե�����Ǥ���褦�ʷ���˲����줿���ᡢ����ʸ塢�ƹ���DZDz�ۤ��������Ƥ��ä������Ǥ���
- MPPC��ȿ�ȥ饹�ȤǤ��롢�Ⱥ�Ƚ���Ƚ�Ǥ������졢�ʾ٤���1917ǯ�˾��Ǥ��ޤ�����
- ��
- �����ߤˤϡ���ͳ������ޤ�����
- �����ⲹ�Ȥǡ�ǯ���ɤ������ΤDZDz軣�ƤˤϤ��äƤĤ��Ǥ�����
- �����ߡʥϥꥦ�åɡˤǤαDz軺�Ȥ��夲���Τϡ������ͤǤ�����
- �����ͤϡ��쳤�ߤ�����������Ƥ����Τǡ���ŷ�ϤǤο������ӥ��ͥ��������Ѷ�Ū�ǡ��Dz襹������������Ω���ƹԤ��ޤ�����
- �ѹ��ե�⡢�����ƱDz��Ϣ�ȼԤ�ϥꥦ�åɿʽФˤ��Ѷ�Ū���ä��ȸ����Ƥ��ޤ���
- MPPC���Թ����ʶ���˶��Ǥ˰ۤ����Τϡ������ͤΥ����ꥢ�ࡦ�ե��å�����William Fox�ˤǤ�����
- ��ϡ�1915ǯ���ϥꥦ�åɤ�Fox Film Corporation�ʸ��20�����ե��å����ˤ�Ω���夲�ޤ���
- �ޤ�����˥С�����Dz�ҡ�1912ǯ�ˡ��ѥ�ޥ���ȱDz�ҡ�1916ǯ�ˡ���ʡ����֥饶�����ҡ�1923ǯ�ˡ�������ӥ��Dz�ҡ�1924ǯ�ˡ�MGM����������1924ǯ�ˤʤɸ��ߤ�������Ƥ���ϥꥦ�åɤαDz��ҤϤۤȤ�ɤ��٤ƥ����ͤˤ����Ω�ȷбĤǤ�����
- ��
- ��
����Mitchell�ʥߥå��������2020.04.08�ˡ�2020.04.19�ˡ�2023.10.23�ɵ���
- Bell & Howell 2709�����θ���о줷���Τ��������ߥ���ե���˥��Ǻ��줿��Mitchell�ʥߥå�����˥����Ǥ���
- ���Υ�����1920ǯ�夫��1960ǯ��ˤ������ƹ�Dz軺�ȤǺǤ��ɤ��Ȥ�줿35mm�ե�����ѥ����Ǥ�����
- Mitchell����餬�о줹�������Bell & Howell�����ϡ���ϴ�ǿ��������⤯�Ȥ�������ɤ���ΤΡ��ե������ư���������礭����Clipper������åѡ��ˡ��ޤ�����ѹ�碌��ե����������Ѥ路�����ʤ����ġ��ե���������������岼��ž�α����ȤʤäƤ��ޤ�����
- �����ޥ�ˤȤäƤ�����Ĥ���ɾ�Ǥ�����
- �ߥå����륫���Ϥ������褷�����ġ�����̵��Υե�������굡������äƤ������ᡢ�Dz襫���˾������ФΥᥫ�˥���ȸ���졢��¿���λٻ���ƹԤ��ޤ�����
- �ޤ���Υȡ������λ���ˤʤä�Ʊ��Ͽ��������줿���Ƹ���Ǥϡ����Ʋ��ξ��ʤ��ߥå����륫���ϴ�äƤ�ʤ��������ä��˰㤤����ޤ���
- �ߥå�����Υե�����ư�ࡼ�֥��Ȥϥߥå����륫���ʸ��Movicam��Panavision�����ˤ���Ѥ��캣���˻�äƤ��ޤ���
- ����
- ����Mitchell Camera Corporation����2020.04.08�ˡ�2020.04.19�ɵ���
- ��
�å����륫���ҡ�Mitchell Camera Corporation�ˤϡ�1919ǯ�˥إ����ܥ�����Henry Boeger�ˤȥ��硼��������ե�åɡ��ߥå������George Alfred Mitchell�� Feb. 1889 - Apr. 1980�ˤ���ͤˤ�ä������ߥ������륹�ʥϥꥦ�åɶ�١ˤ���Ω���졢1985ǯ������������Ǥ�����ҤǤ���
- ���硼�����ߥå������ʼ��������1911ǯ��22�ͤλ��ˤ˥������륹��Frese Optical Company�˵������ѼԤȤ������Ҥ����Dz�ȳ�������ޤ���
- ������Frese���ؼҤϡ�¬�̵���α��ѡ����ƥʥ���̳�Ȥ��Ƥ��ơ�����¾�ˡ������Ϥ˶��ä��Dz軺���ѤΥ����ȱǼ̵��Υ��ƥʥ�꤬����褦�ˤʤꡢ�ߥå�����Ϥ������̤˺�ǽ�֤����Ƥ����ޤ���
- 1911ǯ��������˽Ҥ٤�MPPC��Motion Picture Patents Company��Edison Trust���αƶ��������ơ������ߤȤ����ɤ�MPPC��°���Ƥ��ʤ���Ҥˤ��õ������ʤ������Υ���餷���Ȥ��ʤ����ᡢFrese��ϥߥå������̿���ƥե���ѥƤΥ�����ѹ��The Williamson�����ԡ������Ƥ��ޤ�����
- ���줬�ߥå����뤬�Dz襫���˴ؤ��ǽ�ν�������ä��ȸ����Ƥ��ޤ���
- ��ϡ������Υ���������˻��ޤ����Τ˥��ԡ�����ʣ���������ä��ȸ����Ƥ��ޤ���
- �ߥå������1916ǯ��27�ͤλ��ˤ˥�˥С�����Dz�Ҥ˰ܤꡢ�Dz襫���Υ��ƥʥ��װ��Ȥ���Ư���Ф��ޤ���
- ��˥С�����ҤǤλŻ��ϥߥå�����ˤȤäƤȤƤ�̥��Ū�ʤ�Τǡ�¿���Υ����ޥ�Ȱո����路�ʤ���Dz襫�����θ���Ƥ����ޤ�����
- ��������˥С�����Ҥϥ����������Prevost�ʥץ�ܥ��ȡ˥�����ȤäƤ��ơ�����¾�˾����ʤ���Bell&Howell������ȤäƤ��ޤ�����
- �ʤ����餯Bell&Howell2709�����Ϲ�����ä��Ȼפ��ޤ�����������αDz���ʤ�Bell & Howell������Ȥ���Τϸ¤�줿��ã���Ĥޤ�ͽ����������äƤ����ã�������ä��Τ������Ȼפ��ޤ�����
- ��������������ݻ��������ƹԤ���ǡ�John E. Leonard�Ȥ��������ޥ����߷פ����������ˤ�äƤ��ޤ�����
- ����鼫�Τϴ����٤ι⤤��ΤǤϤ���ޤ���Ǥ�������Leonard�Υ����ǥ���������ޤ줿��å������С������Υե�������������ϤȤƤ�¿��Ǥ�����
- ��å������С���rack-over�˼��Υե���������Ȥϡ���������Τ��ץ졼�Ȥ�ʬΥ�Ǥ���褦�ˤ��ơ���å����������ǥ�������Τθ������ñ���ڤ�Υ���ƥ������ե�����������ڤ��ؤ����ΤǤ���
- ��å��ԥ˥���ǥ�������Τ������ʿ�Ԥ˰�ư�����ƥե���������θ������碌��������λ���ȥե���������ե���������dz�ǧ�Ǥ����ΤǤ�����
- ��å������С����ϡ�Bell & Howell 2709�ˤ⤢��ޤ�������������ޤ뤴��ʿ�Ԥ˰�ư�����뤿�ᥫ�����֤��Ѥ��ޤ���
- �ޤ����ե���������Ԥ��ݤˤϡ��������������4Ϣ������åȤΥ��180�ٲơ��ե�����̤�̵�����֤���¢�ե���������ʥ롼�ڡˤ�Ȥäƥե����������碌�Ƥ��ޤ�����
- �ʻ�����ϥ���̤��������ǧ�ϤǤ����������ɥե���������Ǥ��褽�λ�����ǧ���Ƥ��ޤ�������
- �ߥå�����ϡ�Leonard�λ�������������ε�ǽ�ˤ��������ä��������¸�Υ����˲�¤��ܤ����Ȥ��ޤ���
- ����������ζФ�Ƥ�����˥С�����Dz�ҤϱDz�����β�ҤǤ��ꡢ�������¤�ˤ϶�̣��̵���ä�������μ�ĥ���̤�ޤ���Ǥ�����
- �����ǡ����Ʊ�Ҥ����1919ǯ��Mitchell 30�ͤλ��ˤ˲�Ҥ���Ω���ޤ���
- 1920ǯ��Mitchell��Mitchell Standard 35mm Camera����¤�����䤷�ޤ���
- ���Υ����ϡ�Leonard�Υ����ǥ���ʬ���Ȥ����줿��Τǡ��礭����ħ����˽Ҥ٤���å�&�ԥ˥��ǥ�������������������ľ�Ѥ˰�ư�����ƥ������ľ�ܥե�������������褦�ˤ��Ƥ��ޤ�����
- �ߥå����륫���ϡ�����¾����ħ�Ȥ��ơ�4�����Υޥåȥܥå��������ݡ��ȥ졼�������֤���ͥ��Ǵ�ñ�����Ǥ���褦�ˤ������Ȥ䡢����ظ�ˡʥե����ȥ�δ֤ˡ˥����ꥹ���֤����濴���Τߤʤ餺��ͳ�ʰ��֤�Ĵ���Ǥ����ü���̵�ǽ��������Ƥ��ޤ�����
- �ޤ����ե��륿��������åȤ����ظ�����֤�����ñ�˼���ؤ�����褦�ˤ��ޤ�����
- ��ư����å�����ǽ��Ĥ���170°����å������٤���μ�ư�ե����ɥ���/�ե����ɥ����Ȥ��Ǥ���褦�ˤ��ޤ�����
- �����Υ����ǥ���¿���ϡ���ȿƤ������Ƥ���ϥꥦ�åɤΥ����ޥ�������ä���Τǡ��ߥå������������˾�����տ���Ƚ�Ǥ����߷פ�ȿ�Ǥ����ޤ�����
- ����
- ��
- ����Mitchell high speed movement����2020.04.10�ˡ�2023.06.12�ɵ���
- �ߥå����륫������ɮ���٤��礭����ħ�ϡ���ˤ�Ҥ٤��ե�������굡���Ǥ���
- Bell & Howell 2709������ե��������Ϲ�̯�����̤ʤ�ΤǤ��������ߥå�����Ϥ����õ��������äơ����������Ū�ʥ����ǥ�����ߡ�������̤��Žͤʤ�Τˤ��ޤ�����
- ������Žͤʥ�������Ƥ��ޤ�����������ɻ���ʥȡ������ˤ����äƤ����ΤǤ���
- �ߥå����륫���ϲ��ޤ˼����褦�˥쥸���ȥ졼�����ԥ��ưŪ�ʹ�¤�Ȥ�������˱�ư����ȴ��������¤�Ȥ��ˡ��ե����ѡ��Υե��졼�����ʹ��ˤ��ޤ���¤�Ȥ��Ƥ��ޤ���
- Bell & Howell 2709�����Υ쥸���ȥ졼�����ԥ����Υ��ѡ����㡼�����Ȥ˸��ꤵ��Ƥ���ΤȤϰ�äƤ��ޤ�����
- �ե���������ޡ�Pull down cla���ˤȥ쥸���ȥ졼�����ԥ��Registration pin�ˤϡ�Ķ��̩�ʥ����ȥ����Ϣư�����ޤ��ե������ߤ���Ȥ�������Ż��ѥԥ����äƥե������Żߤ����ޤ���
- ��ž����å�����������Ϫ���������ȡ��Żߥԥ�ȴ�����ߤ���Ȥ��ޤ��Ƥӥե����ѡ��ե��졼���������ꡢ4�ѡ��ե��졼�����ʬ��������Ȥ��ޤ���
- ��
- ��
- �쥸���ȥ졼����ԥ��ľ�ʡ�����˱�ư�Ǥ�����ǽ�ˤ��Ƥ���Τϻ��ѥ���ʥ쥸���ȥ졼�����եȡ�����ˤǤ���
- �ץ�����������϶�ư�����륮���β�ž�濴���Υ�줿���֤˸��ꤵ���Ƥ��ޤ��ʥ�������ȥ�å����֡ˡ�
- ���ι�¤�ˤ�äƻ��Ƥ�ȼ����ư�Υ������������㸺��Ʊ��Ͽ�����ǽ�ˤ��ޤ�����
- ��������ʤ�0.0001�������2.54μm�ˤε����ϰϤ���̩�ù�����ޤ�����
- 1920ǯ��Ϥ��������ߥ����������βù����ǽ�ˤ��Ƥ����ΤǤ���
- �쥸���ȥ졼����ԥ�ϥե�������¤���ʤ��ϰϤ�ۤ��ơ�0.0005�������12.7μm�ˤε��ƤȤ��ơ���ù����ʤ���Ƥ��������Ǥ���
- �������Ƥߤ�ȡ��ƹ�ε������Ȥ϶ˤ�ƹ��٤ʵ��Ѥ���äƤ������Ȥˤʤ�ޤ���
- ��
- ��
- ����Mitchell�ҤΤ��θ�
- �ߥå�����Ҥϥߥå������Υ�����߷ԤȤ��Ƥ�ŷ��κͤ�ȯ��������ҤȤϸ���������ȿ��Ȥ��Ƥ�äѤ˱��Ĥ��ʤ������Ĺ��뤲���褦�ˤϸ��������ޤ���
- �ߥå����륫����̾���ϥϥꥦ�åɱDz�˾廸���ȵ���¸�ߤǤϤ��ä�����ɡ�1970ǯ����Ť���©�������ä�����������ޤ���
- 1970ǯ��αDz襫���ϥɥ��ġ��ߥ��إ����Ĺ��뤲�Ƥ���ARII�ҡ�Arnold & Richter�˼Ҥ��ƹ�ե���˥���Panavision�ҤΥ���餬��Ƭ����ξ�Ԥ��ե���५���Υ��������Ƥ��ޤ�����
- ���ܤǤ�1960ǯ��ʹߤαDz�����ϡ�Panavision��ARRI�Τ����줫�Υ������Ѥ��ƺ��ʤ�����Ƥ��ޤ�����
- 2000ǯ������äƥǥ����륫��餬��ڤ��Ϥ��ȡ�Panavision��ARRI�˲ä���RED��Sony��Canon���ǥ�����Dz襫���˻�������¿���Υǥ����륫����ݥ��ȥץ�����������������ƺ��ʤ���Ϥ�Ƥ��ޤ���
- ���������ϥꥦ�åɱDz��ή�����ǡ�George Mitchell���1950ǯ��˰��������भ��1980ǯ��89�ͤ��������Ĥ��ޤ�����
- Mitchell�Ҥζ��Ӥϲ����Ω�λ����餽��ۤ�˧�����Ϥʤ��ä��褦�Ǥ���
- �ҤȤ��ӱDz������Ҥ˥�����Ǽ�ʤ���С����θ����ǯ��Ȥ�³���������ʤ������塢¿�������פ���ʸ������Ǥ���ȼ�ǤϤʤ��ä��褦�Ǥ���
- 1929ǯ�����������κݤϡ�FOX�ҡʸ塢20����FOX��2019ǯ���20�������������ҡˤ�FOX�Mithcell�Ҥ�¿���γ���������ƥߥå�����Ҥ�٤����ȸ����Ƥ��ޤ���
- ����FOX�Ἣ�Τ����������Τ�����Ǻ��ʤ�����20�����ҤȤι�ʻ��ФƤ����ޤ���
- �ߥå�����Ҥ���ȯ���������ϰʲ����̤�Ǥ���
- ��1920ǯ��Mitchell Standard 35mm Camera��
- �ǽ�Υ���顣
- ��1929ǯ��Mitchell FC 70mm FOX Grandeur Studio Camera��
- 70�������������緿�����
- ��1932ǯ��Mitchell NC/BNC Camera��
- News Reel�ʥ˥塼�����˥���顣
- BNC�ϡ�Brimped News Reel �ʥ֥��ץ����סˡ�
- Ʊ��Ͽ�����θ���ƻ��Ʋ��νФʤ������ʥ֥��פ����줿�����ˤ����
- ��1932ǯ��Technicolor camera��
- 3������ե���५�顼����顣
- ���顼�����Ѥ�����ե����3�������Ʊ����ư���륫����ȯ��
- ��1940ǯ��Mitchell GC��
- ��®�ٻ����ѡ�128����/�á�
��1940ǯ�塡Mitchell SS Camera��
- Single System ����顣
- ������������ƹ�Φ���Ѥ˳�ȯ��
- NC�β��ɵ���
- ��1956ǯ��Mitchell VistaVision Camera��
- �ѥ�ޥ���ȱDz�Υӥ����ӥ�����ѥ���顣
- �ӥ����ӥ����ϡ�35mm�ե����8�ѡ��ե���36mm x 18.3mm��1.66:1������ư��
- ������ɻ����б���
- ��1962ǯ��Michell R35 Camera��
- �ե�����������ե�å��������פˤ�����Ρ�
- 1965ǯ��Mark II��ȯ�䡣
- ��1967ǯ����Mithcell NCR/BNCR��Camera��
- �ե�����������ե�å��������פˤ���NC/NCR��
- �ʸ塢���Υ����ϡ��ѥʥӥ�����Panavision�˼Ҥ�
- �ѥʥե�å�����PnaFlex�ˤ˰����Ѥ��줿����
- ����
- ��
- ���� Panavision�ʥѥʥӥ�������2020.04.08�ˡ�2020.04.19�ɵ���
- �ѥʥӥ����ҤϱDz赡��Υ���ҤȤ��ƥ������Ȥ��Ƥ��ޤ���
- �ѥʥӥ�����Υࡼ�֥��Ȥϡ��ߥå�����Τ�Τ����Τޤ�Ƨ������Ƥ��ޤ���
�ߥå����륫�����õ����ɤΤ褦�ʷ��ǥѥʥӥ����˰Ѿ����줿�Τ���Ĵ���ڤ�Ƥ��ޤ���
- ���Υߥå�����Ҥ�1960ǯ���Ⱦ����ߥå����륫���Ȥ��Ƥγ�Ū�ʻŻ��Ƥ��ޤ���
- ����ϡ�1950ǯ���Ⱦ�˥ߥå��������ष�������ȵ����ˤ��Ƥ��ޤ���
- ��������夹��褦��Panavision����餬�о줷�ޤ���
- 1960ǯ���Ⱦ����Υϥꥦ�åɱDz�ΤۤȤ�ɤϡ�Panavision�����ȥ磻�ɥ�������ѥ���Ȥ���褦�ˤʤ�ޤ�����
- Panavision�Ҥϥ��С��ȡ����åȥ���륯��Robert Gottschalk��1912 - 1982�ˡ˻�ˤ�äơ��Dz軺�ȤΥ�뤹���ҤȤ���1953ǯ�ƹ�ե���˥����������륹����Ω����ޤ�����
- ��ϡ��ƹ������������´�ȸ塢�Dz軺�ȤǿȤ�Ω�Ƥ뤿��ϥꥦ�åɤ˰ܤꡢ20�����ե��å����ҤΥ磻�ɥ������Dz�����˷Ȥ��ޤ���
- ��������ǥ��ʥ�ե��å����anamorphic lens�ˤ�꤬���ƥ��ͥ������ס�������갷����ҡ�Panavision�Ҥ���Ω���ޤ���
- Panavision�Ҥϳ���Ǽ̸��إ����ҤȤ��ƥ������Ȥ����ޤ���Υ磻�ɥ������Dz�ζ�δ�ȤȤ�˶��ӤФ���1970ǯ�夫��ϡ��Dz軺�ȵ���Υȥåץ֥��ɤˤޤǤʤ�ޤ�����
- Ʊ�Ҥϡ��磻�ɥ���С�������Υӥ��ͥ���¾�ˡ��ե���५���ⰷ���褦�ˤʤ�ޤ�����
- Panavision���������Ф��Τϡ�1962ǯ�Ǥ���
- MGM���꤬�����Dz�ʥޡ����֥��ɼ�����ϥХ���ƥ��סˤ��������Ѥ�����ʤ�ΤˤʤꡢMGM�λ��ĥ�����Panavision����Ѥ��줿���Ȥ��饫�����Ȥ��Ϥޤ�ޤ�����
- 1967ǯ�����ϥߥå�����35mm������Ѥ��ɲ��֥��פ��߷���������줬Panavision Silent Refrex Camera��PSR�ˤȤʤ�ޤ�����
- �ѥʥӥ����Υ����ϡ��ߥå����륫�����ä��ΤǤ���
- 1970ǯ��ʹߤΥϥꥦ�åɱDz襫���ϡ��ߥå����뿧�����������Panavision�����Ȥ��ƤΥ֥��ɤ����夷�Ƥ��ä��褦�˴����ޤ�
- Panavision�Ҥϥ�ˡ����ʲ�Ҥǡ��Dz���������˰��������ʤ��顢�����������������ϹԤ鷺���٤ƥ���ԤäƤ��ޤ���
- ������⡢�����⻰�Ӥ⤹�٤ƥ��Ǥ���
- �Dz������Ҥ˥�������뤳�ȤϤ��ޤ���Ǥ�����
- ����ҤǤ���ʤ��顢ɬ�פʤ�ΤϺ��夲�������⼫�Ҥ����ʤ�Ű��Ū�˥��ƥʥ�ܤ��桼�����������������äƤ��ޤ���
- ���⤷�������Ȥˡ�Panavision�Ҥκ���Υ饤�Х�ϥɥ��ġ�ARRI�ҤǤ���ʤ��顢ARRI�Ҥ��礭�ʤ����ͤǤ⤢��ޤ�����
- �ĤޤꡢPanavision�Ҥϥ���̳��Ԥ������ARRI�Ҥ��餿������αDz赡���������Ƥ���ΤǤ���
- �̾�ϡ��饤�Х��ҤǤ���Х������������������ΤǤ��礦����Panavision�Ҥ��ϥꥦ�åɤǤ������ʥ͡���Х�塼����äƤ��뤳�ȤȤ䡢�磻�ɥ�������ѤΥ���С��������ҹ����꤬���Ƥ��뤳�ȡ�65mm/70mm�ե���५������äƤ��뤳�ȡ������ӥ����������ä��ꤷ�Ƥ��뤳�Ȥʤɤ��顢�ϥꥦ�åɤǾ����ʤ��Panavision�Ҥȶ�¸�����ۤ����ä��ȹͤ����Τ����Τ�ޤ���
����ꥫ�罰�������ߤΥϥꥦ�åɤζBurbank�˷��������ȸ����αDz襫�����äƤ����� Photo Sonics�������ꡢ1940ǯ�夫��ե���५������¤���䤷�Ƥ��ޤ�����
- Photo-Sonics�Ҥγ�ȯ���������ࡼ�֥��Ȥϡ�Mitchell�ҤΥ����ࡼ�֥��Ȥȶˤ�Ƥ褯���Ƥ��ޤ��ʱ����ȡˡ�
- �����餯�����������γ��襤�ǤϱDz軺����֤ǵ���Ū�ʸ�ή�����äơ�����ή�����ǥե�������굡��������褦�ʹ�¤�Τ�Τ�Ƨ������Ƥ����ΤǤϤʤ������������ޤ���
- Photo Sonics�Ҥ�Michell�Ҥǥ饤����Ϳ�����ä��Ȥ������Ѳ��ΰ�ư�����ä����ɤ����Ϥ褯�狼��ޤ���
- �伫��1978ǯ����2000ǯ�ޤǤ�22ǯ�֡����ι�®�٥����ΰ����䵻��Ū�ʻŻ��Ƥ��ޤ�������ɡ����Υ�����Mitchell�����δط����狼����������Ȥ�����ޤ���
- ����Arriflex�ʥ���ե�å�������2020.04.12�ˡ�2020.04.29�ɵ���
�����ARRI��Arnold & Richter�˼Ҥϥɥ��ġ��ߥ��إ�ˤ�����Ҥǡ�August Arnold��1898 - 1983�ˤ�Robert Richter��1888 - 1972�ˤ���ͤ�1917ǯ����Ω���ޤ�����
- ��켡��������塢���鵢�ä���ͤϾ����ʲ�Ҥ������¿�ʥ�����ץ�ʥե����Ƥ��դ����֡ˡ��������֤ν�����ԤäƤ��ޤ�����
- ���Ϥޤ������ޥ�Ǥ⤢��Dz���ĤǤ⤢�ꡢ����ʱDz���ʤ��Ĥ��Ĥ��ޤ�����
- �Dz襫���Ͼ�ˤ�Ҥ٤��褿�褦�˥ե���ƹ��쳤�ߤ�ȯ�����졢���Ϥζ����ƹ�Τ��Ȼ��ȤȤʤäƤ��ޤ�����
- �ƹ��쳤�ߤϱDz軺�Ȥ�����������ҡ��Dz�ե�������¤���륳���å��ҡ��ץ�ȥ�������¤����Bell &Howell�Ҥ����ꡢ�ƹ������ߤ��쳤�ߤ���ϥꥦ�åɤ˰ܤä������αDz襹�������������Υߥå�����ҡ����䥢�ʥ��Υѥʥӥ����Ҥʤɤ�����ޤ�����
- �ƹ�αDz軺�Ȥϵ��Ϥ������ȤϤޤ�ǰ㤤�ޤ�����
- �ɥ��ĤΥ���ҤϤ��������Dz軺�Ȥο�������ǡ��϶�7ǯ���1924ǯ����������ѥ��Ȥ�KINARRI35�����ʼ��100ft�ե�����Ǽ�ˤ�ȯ���ޤ���
- ���Υ����ϥϥꥦ�åɤμ�ή�ȤʤäƤ����ߥå����륫���Ȥ��о�Ū�ʤ�ΤǤ�����
- ����1937ǯ�������ǽ��Ƥβ�ž�ߥ顼�ˤ���ե�å��������ARRIFLEX35�ʼ̿� ���ˤ�ȯ��������Ϥ��ޤ�������ϱDz襫���ȳ��ΰ���ե����Ȥ�Ƥ֤٤���ΤǤ�����
- ���Υ�������ħ�ϽŤ���6.1kg�Ⱦ������̤ǡ����ġ�������Ǥ�ºݤλ��Ʋ��̤�������³�����ޤ�����
- ��ž���ĥ�ե�å�������å����ե���������ϡ������ޤγ�ǰ�ޤǼ������褦�˲�ž���ĥ���å����α������˥ߥ顼��Ž�äơ��ߥ顼����ȿ�ͤ��줿����ե�������������������Ȥ��Ƥ��ޤ���
- ��ž���ĥ���å����ϱ��Ĥ�Ⱦʬ��1����ʬ���������Ƥ����Τǡ�16���ޡ��äλ��ƤǤϱ��Ĥϻ���®�٤�Ⱦʬ���Ĥޤꡢ8��ž/�äȤʤäƤ��ޤ���
ȿ�ͥߥ顼�ϻ���®�ٴֳ֤�Ⱦʬ�ʥ���å������봹����180°�����ĥ���å����γ����٤�90°�ˤ����Ƥ���Τǡ����λ��ְʾ��Ϫ���ϤǤ��ޤ���
- ��ž���ĥ���å������ե�����̤�ʤ���蘆�äƤ��������ǥե������ߤ���Ȥ��ޤ���
- ���β�ž����å����ϲ��Ѥμ����Ĥ��ߤ����Ƥ��ơ����μ����Ĥ��Ĥ��Ƥ�����Ϫ�����֤�û���ʤäƤ����ޤ���
- ���ĥ���å�������Ѥ�������ҤΥ�ե�å����ե���������ϡ�������Bell &Howell�����ˤ�Mitchell�����ˤ�ʤ��礭����ħ�Ǥ�����
- ����ҡ�ARRI�ˤΥߥ顼��ե�å���������Mirror Reflex Camera�ˤȸ������Ȥ��顢����ե�å�����Arriflex�ˤ�̾�դ����ޤ�����
- ���Υɥ��ĤΥ���ѥ��ȥ�������������������˰��Ϥ�ȯ�����ޤ���
- Ϣ���ꥫ��Bell & Howell�Ҥ�Eyemo��Ȥ��Ƥ��ޤ�����
- ��塢ARII35���ᄀ��������ʤȤ���Ϣ���������졢��ե�å����ե����������ǽ���ᄀ��Τ�ΤȤʤ�ޤ�����
- ARRI�ҤΤ���ߥ��إ����Ф���ˤ���ޤ�����������ϥߥ��إ�ٳ��ˤ��ä��������Ƥ��Ȥ졢1956ǯ�ˤ�ARRIFLEX II��ȯ���뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ�����
- Arriflex�ϥߥ顼��ե�å����ե�����������礭����ħ�Ȥ��Ƥ��ơ����ġ��������⥳��ѥ��Ȥ������ʵ������ʤȤ⤢���ޤäơ��Ÿ�Ĺ��ʥ���ꥫ�Υ����Ȥ��о�Ū�����ʤȤ��ư��֤Ť����ޤ�����
- ��
- ���μ̿���1964ǯ��������ԥå��Υɥ�����Dz����������ԥå��סʻ����´��ġ�����κݤ˻Ȥ�줿����餬��·��������ǰ�̿��Ǥ���������ǥ��Х���ä��ƻش��Υݡ�����ȤäƤ�����Τ�������49�ͤλ����´��ġ���
- �����ΤۤȤ�ɤ�˾���� ��= �������Ĺ���ˤ�����դ����Ƥ���Τ��狼��ޤ���
- 3��7000���ߡʸ��ߤ�37���������ˤ�����������ɥ�����Dz�ϡ�556̾�Υ����åդ��ʤ������ƥ����ޥ��164̾������ޤ�����
- ���Ѥ��������Ϲ��104��ǡ�����ե�å�����Arriflex 35 II�ˤ�46�椬�Ȥ��ޤ�����
- ����¾�ˤϡ�Bell&Howell�Ҥ�Eyemo�ʥ������47�桢��®�٥����ʥե�� �����졼��ҥ���ե�å�����Eclair Cameflex��3�桢�ߥå�����ޡ���II 2�桢�����ƥߥå�����NC��1��Ȥ��ޤ�����
- ���Ѥ����ե�����40���ե����ȡ�400ft�ե����1000�̡����Ͽ�����74���֡ˤ˾��ޤ�����
- ���κ��ʤ�˾����¿�Ѥ���Ƥ��ơ���Υ�줿���֤˥������֤��������©�Ť�����˾�����ɤ������ޤ�����
- 100m���Υܥ֡��إ�����Robert Lee Hays������䡢�ޥ饽��Υ��٥١�Abebe Bikila������Υ����������åץ���åȤˤϡ�˾���˲ä��ƥ������⡼����ơʥϥ����ԡ��ɥ����ˤ��Ȥ��ޤ�����
- ����ե�å���35II����餬�ʤ�46���Ȥ�줿�Τ��ȸ����С��ɥ�������Ƥ˺�Ŭ����ǽ�����ʤ����ե�å����ե���������ȷ��̤Ƿ�ϴ�ʥܥǥ������������Ƥ�������Ǥ���
- ��Ĺ������Υ����⤷���ϥ������������夷��ư����®�����ݡ���������ɤ�������ˤϡ����Υ����ʳ��ˤϤʤ��ä��פȡ����μ̿���ʪ��äƤ��ޤ���
- ����ե�å���35II��Ʊ������Ȥ�줿Bell&Howell�Ҥ�Eyemo�ϡ��������̤Ǽ괬������ޥ��λ��Ƶ��Ǥ�����
- �Хåƥ��ɬ�פ���ޤ���Ǥ�����
- 1960ǯ��Ⱦ�ФˤʤäƤ⡢��������Eymeo���Ȥ��Ƥ������Ȥ�����Ǥ��ޤ���
- ���Υɥ�����Dz�Ƥ��������ޥ�ϡ�������ɤϵ�ȸ����Ƥ����˥塼���Dz�˷Ȥ�äƤ����ե���५���ޥ�Ǥ�����
- ���ϥƥ�ӥ˥塼�������̤ˤʤäƤ��ʤ��ä�1930ǯ�夫��1960ǯ��˳�����������ǥ˥塼�����Ƥ�����Ȥ�����ʹ�ҽ�°�Υ����ޥ�ǡ��Dz������Ҥ˽�°���Ƥ����Dz襫���ޥ�Ȥ��о�ʪ���ɤ���������äƤ��ޤ�����
- �Dz襫���ޥ���礭�ʥߥå����륫��������ơ��������֤����������������������ۤ��ƶ˾�β����뤳�Ȥ�ݤȤ��Ƥ��ޤ�����
- �˥塼�������ޥ�ϡ����Ȥ�ȿ�Фǡ������˽Фƹ�Ѥ�뻣���оݤη���Ū�ִ֤뤿��˿Ȱ�ĤǽФ������ã�Ǥ�����
- �������������˽Ф�����褦�ʿȷڤʤ�Τ�����줿�Τǡ�Arri35��Eymeo�����μ��Τ褦�ˤʤäƻ��Ƹ������äƤ��ޤ�����
- ���������˥塼�������ޥ��ӥǥ�����餬ȯŸ����ȤȤ���������졢1980ǯ�ʹߥ˥塼������ƻ�˸���κ¤���äƹԤ����Ȥˤʤ�ޤ�����
- �����Υ��&��ҥ����Ҥ�65mm�Ҥλ��ƥ����ˤϤ���ۤ����Ϥ��Ƥ��ʤ��ä��褦�ǡ�35mm�ե�����16mm�ե���५��餬�ᥤ�����ʤǤ�����
- ��������1970ǯ���Ⱦ�ϥꥦ�åɤǤ�65mm�ե���५�������ޤꡢƱ��Ͽ���Ǥ�����Υ����ե���५�����ᤫ�顢ARRI765��1983ǯ�˳�ȯ���ޤ�����
- 1960ǯ��Υϥꥦ�åɤϡ�Panavision��65mm�ѡ�35mm�ѤΥ磻�ɥ�������ǰ����Ȥ������������ݤäƤ��ޤ�����������ե�å��������ε�ư����Ż뤷�����ʤ�����褦�ˤʤꡢ�������Ф��Ƥ����ޤ�����
- 2000ǯ�ʹߡ��ǥ����륫��餬�ϥꥦ�åɤǤ���ڤ���褦�ˤʤ�ȡ��ǥ����륫����Arri Alexa�ˤؤΰܹԤ���������¿���Υ�����������褦�ˤʤ�ޤ�����
- ��
- ��
- ����16mm�ե������ ��2020.03.14�ˡ�2020.04.20�ɵ���
- 16mm���Υե�����1923ǯ�˥������ȥޥ����å��Ҥ���ȯ���ޤ�����
- �����å���16mm�ե�����Ȥä�ư���Cine-Kodak�ʥ����ˤ�����ޤ���
- 35mm�ե����Ϲ�����Ȥ��륢�ޥ��奢�桼���������ˡ�35mm�ե�����Ⱦʬ�ζҤ���ĥե������ä��Τ��ӥ��ͥ���ư���Ǥ���
- 35mm�Ҥ�Ⱦʬ��17.5mm�Ǥ�����16mm�ҤȤ�����ͳ���褯�狼��ޤ���
- �������ˡ�17.5mm�ҤΥե�����¸�ߤ��Ƥ��ޤ�����
- Ĵ�٤Ƥߤ�ȡ�17.5mm�ҤΥե�����1898ǯ�ˤ�¸�ߤ��Ƥ����褦�ǡ��ѹ�μ̿��Ȥ�ȯ���Ȥ�Birt Acres����ʬ�Ѥ�����������Ǥ���
- ���θ塢11mm�ҡ�1902ǯ�ˡ�28mm�ҡ�1912ǯ�ˡ�22mm�ҡ�1912ǯ�ˡ�9.5mm�ҡ�1922ǯ�ˤ��͡��ʥե����ޥåȥե���ब����ơ�������б����륫���ȱǼ̵������ޤ�����
- ������¿���ϥ��ޥ��奢�ΰ��ФƤ��餺����������Ū�ˤʤäƤ�������������Ǻ��35mm�ҤΥե�����ή�ѡ��ù����ƻȤäƤ��ޤ�����
- �Ŀ���Ū�ǤϤʤ�����ȿ��ǥӥ��ͥ��Ȥ��ƾ����Dz襫����������Τϡ��ե�ΥѥƼҤǡ�1912ǯ��28mm�ҤΥե�����ѥ����ȱǼ̵������ޤ���
- ���Ϥ��Υե���ॲ�����ǥ��ޥ��奢�����Υե��������ӥ��ͥ��ʥѥƥ������ס��饤�֥��ˤ�Ÿ�����褦�Ȥ��Ƥ��ޤ�����
- �ƥ�������Τʤ�����β����Ѹ�ڥӥ��ͥ����ۤ��ޤ�����
- �����å���Ʊ���ӥ��ͥ����褷�ޤ���
- ���������طʤ�ͤ���ȡ������餯�����å��Ҥϡ��ѥƼҤΥե���ॲ�������ơ�����28mm�ե�����ꥳ���Ȥ��㤤��17.5mm�Ҥ˶ᤤ��16mm�Ȥ����Τ������ȹͤ��ޤ���
- Kodak��16mm�ե���൬�ʡ�gauge�ˤ�ȯ����ˤ����äơ��ѥƥ������ס�����ꥫ�ҡ�Pathescope company of America�ˤ���Willard Beech Cook���ۤäơʤ����餯����ȴ���ơ˥����������ץ饤�֥���Kodascope Library�ˤ���ޤ���
- 16mm�ե�����Ȥä���ڡ������Ǻ���ꡢ������뤹����Ȥ�Ϥ�ΤǤ���
- ��켡�������郎�����ޤǤϡ��ѥƼҤ�28mm�ե����ʥ饤�֥����ȡˤϲ����Τߤʤ餺�ƹ�Ǥ⤱�ä�������ڤƤ����褦�Ǥ���
- �����å��Ϥ�����Ǥ��ˤä����Ȥˤʤ�ޤ���
- �����å��Ҥϥ��ޥ��奢�����˳�ȯ����16mm�ե����˰ʲ�����ħ��������ޤ�����
- 1.���ե�����Ǻ�˲�dz���Υ�������ɤ��夨�ƥ����ơ��ȤȤ�����
- ������������ɤϲкҤ�褯�������ƴ�������ޤ�ʤ���������Ű�줷�ʤ������Ѥˤ��Ը������ä���
- 2.���ե����ϥͥ��ƥ��֤ǤϤʤ���С�����Ȥ��Ƹ�����ľ���˱Ǽ̤Ǥ���褦�ˤ�����
- 3.�����ε��ʤΥե����ȴ�Ϣ����ʻ��ӡ��ץ�����������������ե�����Խ��ݥץ饤�����ˤ�
- ��������ʤ��ߤ��Ф����������������Ƥ˵������֤�����β�ҤǤ��٤�������ä���
- �����å����礭�ʻ��ܤ��Ϥˤ�äơ����ޥ��奢���������ե���५��餬��������ڤ��Ƥ����ޤ�����
- �ʸ塢16mm�ե�����2000ǯ�ޤǤ�80ͭ;ǯ���ɥ�����ȱDz��˥塼���Ѽ�ࡢ�ƥ�ӥɥ�������®�٥�����ѥե��������Ѥ���ޤ�����
- ���Υե����ϡ�����Ū�ˤ�ξ¦�˥ѡ��ե��졼������ߤ����Ƥ��ơ�1ft������40���ޤλ��Ƥ��Ǥ��ޤ�����
- ��ˤʤäơ��ե�����̤˥�����ɤ�����륹�ڡ�������ݤ���ط��塢�ѡ��ե��졼�������¦�����Υե������о줷�ޤ���
- ����®�٤ϡ�35mm�ե�����Ʊ��̵���Dz�λ����16����/�äǡ��ȡ������λ���ˤʤäƤ����24����/�äȤʤäƤ��ޤ���
- ���Υե����β̤��������Ū�����ϡ������礭����ΤǤ��ä��Ȼ�ϻפäƤ��ޤ���
- ���Υե����ϡ��ɥ�����ȵ�Ͽ�Ѥ���������ޤ�����
- ������������Ǥε�Ͽ�ϡ������Ƿȹ�����ͥ�줿�Dz襫��餬ɬ�פȤ���ޤ�����
- �ƹ��٥�&�ϥ������Bell & Howell���Ҥϡ�������˱����뤿�ᡢ1923ǯ��Filmo�ʥե���⡢���̿��ˤ�ȯ���ޤ���
- Bell & Howell�ҤϤޤ��ե����η��參���Ȥ���1925ǯ��Eyemo�ʥ������������ȯ���Ƥ��ޤ���
- ������ϡ�35mm�ե�������Ѥ����괬�������Ǥ�����
- Filmo��3�ܼ�������åȥ�ʥ����������3�ܤ�ñ�������Υ������դ����ܥ�С����������Υ��ܥ�С��Τ褦�ʤ�Ρˤ��Ĥ��Ƥ��ơ�������Ū�˱����ƥ������Ƥ��ޤ�����
- �ե������������������ˤʤäƤ��ơ��������åȤ�Ȥ���˱������б�����ե����������������ư�ǥ��åȤ���ޤ�����
- ���Υ������Ҽ�ǻ������١������夲���Υ���ޥ��ǥե�����ư��Ԥ����Ȥ��Ǥ��ޤ�����
- Filmo��1970ǯ��Υӥǥ��˥塼��������ENG�����ˤ���Ƭ����ޤǡ��ƥ�������ɡ���ƻ���ؤ�¿���Ȥ��ޤ�����
- �ޤ����ɥ��ĤǤϥ����Υ�ɡ���ҥ����Ҥ�Arri 16ST�ʲ��μ̿��ˤȸƤФ����������ɤ���ե�å����ե��������������16mm�ե���५����ȯ�����²��ʱDz軣�Ƥ��Ǥ��륫���Ȥ��ƻȤ��ޤ�����
- ��������Ǥ��¿�����Ѥ��줿�Ȼפ��ޤ���
- �ʤ��μ�Υ��������Ǥ�35�����ե���५����Arriflex35��¿�������������ΤΡ�16mm�ե���५���Τ�Τϸ��Ĥ����Ƥ��ޤ���
- Arri16ST�ϡ������˺��줿�����Ǥ�����Ʊ�����16mm����餬�����ˤ⤢�ä��Ȼפ��ޤ���
- �������ε��郎�ɤ�Ǥ��ä���Ĵ���ڤ�Ƥ��ޤ���
- ��
- �ʲ��μ̿��ϡ�ARII�ҤΥۡ���ڡ����ʡ�The History of ARRI in a Century of Cinema�סˤ��餪�ڤꤷ�Ƥ���̿��Ǥ���
- ��μ̿���1960ǯ��Υ����ԥå�����ƻ�����ޥ��λ������ʤ��Ȼפ��ޤ���
- ���������Arri16ST���Ȥ��Ƥ��ޤ�����λ��Ƥ�Ԥ�����˾��������դ����Ƥ��ޤ���
- ���Υ����ϰ���ե�å����Ǥ��ä����ȡ�����ѥ��ȤǤ��ä����ȡ��ᥫ�˥��ब���ä��ꤷ�Ƥ������ȡ���ư��ư�������ȡ�ɬ�פ˱�����400ft�ե����ޥ���������Ǥ������ȡ��ʤɤ���ħ����äƤ��ơ��ʤ����Ĺ��ʼ��ǻȤ����꤬�ɤ��ä�����ˤ�����������ܤ�̾����Τ��Ȼפ��ޤ���
- �����ϥӥǥ�������̵���������ѤΥƥ�ӥ������礭���ä����ợ�Ƥ��¤��Ƥ��ޤ������ʾ嵭�μ̿��ϡ��ƥ����ƻ�Ѥε�Ͽ�Ȥ���16mm�ե���ब�Ȥ�줿�Ȳ�ᤷ�Ƥ��ޤ���16mm�ե���५���ǻ��Ƥ��ƥƥ쥷�ͤ���������ޤ������Dz��Ѥˤ�16mm�ե����ǤϤʤ���35mm�ե���ब�Ȥ��ޤ��������ɥ�����Dz� ��������ԥå��סˡ�
- ����¾����ƻ�Ѥ�16mm�����Ȥ��Ƥϥ�������Bolex�ʥܥ�å����ˡ��ܥ�塼���ե�Υ����졼�롢���ܤǤϥ���Υ�Υ���Υ� �������ԥå���Canon Scoopic16 _ 1965�ˤ�����ޤ�����
- ��������������̤���1980ǯ���Ⱦ�ޤǤΥ˥塼���ϡ��ۤȤ�ɤ�����16mm�ե���५������Ѥ��Ƥ��ޤ�����
- 35mm�ե����ϥ����Ȥ������ꤹ����Τǡ��ƥ�Ӥ�ή���˥塼�����Ϥ��٤�16mm�ե���ब�Ȥ��Ƥ��ơ��Dz�ۤ�ή���˥塼���ե����ˤϲ�����ɤ�35mm�ե���ब�Ȥ��ޤ�����
- �ӥǥ��ơ��ץ쥳������ENG = Electoronic News Gathering�ˤ���ڤ���Τ�1980ǯ���Ⱦ����ǡ��˥塼�����ह�륫��餬���ˡ��Υ١����������ɽ�����ӥǥ��������֤������ȡ�������ڤϤ����ޤ�����2000ǯ�ʹߤϤۤȤ�ɤΥ˥塼������ƥ�ӥɥ�ޤ��ӥǥ��������֤�����äƹԤ��ޤ�����
- �ե���५���ϸ������������뤿��¨���������꤬����ޤ���
- �ӥǥ�������¨�����Ϥ���ۤ�̥�Ϥ����ä��Ȥ������ȤǤ���
- ��®�٥����Ǥ�1930ǯ�夫��1990ǯ��ޤǤ�16mm�ե������Ѥ�������餬�ۤȤ�ɤǡ�16mm�ե������®������ʤ���10,000���ޡ��äޤǤλ��Ƥ�ԤäƤ��ޤ�����
- �ܺ٤ϡ���®�٥���������طʤȥȥԥå����ַ��ߤ���Ȥ����ե���५����פȲ�������
- ��ɽŪ�ʹ�®�٥����Ȥ��Ƥϡ��ƹ�Photo-Sonics�ҡʥե��ȥ��˥å����ˤ�16-1PL��16-1B���ƹ�Photec�ҡʥե��ƥå��ҡ����ߤ�Visual Instruments�ҡˤ�Photec�����ܤΥʥå��Ҥ�E-10��1975ǯ��������Ω��Hitachi 16HS��16HD�ˡ��������磻��С������Ҥ�STALEX�ʤɤ�����ޤ���
- �ޤ����ƹ�Ǥ�Redlake�Ҥ�Hycam��Locam��Fastax���ե������㥤��ɼҥߥꥱ���Miliken�ˤʤɤ�����ޤ�����
- 16mm�ե����ϡ�100ft��30.3m�ˡ�400ft��121m�˥����פ���ή�Ǥ���
- ����¾�ˡ�200ft�����ס�1200ft�����פ⤢��ޤ�������Ū�ʰ����Ȥʤ�ޤ���
- �ޤ��������Υե����ϥ��ס��봬���ȥ�������������ब���äơ���®�٥�����ѤΥե����ϼ��Τ���Υ�������ΥĥФ��դ���줿���ס����������Ŷ�ˤ����Ѥ���ޤ�����
- ��
- ��
- ��
- ��
- ����8mm�ե������2020.04.18����
- �ӥǥ����ॳ������8mm�ǤϤ���ޤ���
- �ե�����8mm�Ǥ���
- ���Υե�����1932ǯ�˥������ȥޥ����å��Ҥ���ȯ���ޤ�����
- 16mm�ե����ǤϤޤ�����Ǥ���Ȥ��륢�ޥ��奢�桼�������ˡ�16mm�ե�����Ⱦʬ�ҤΥե������ä��Τ��Ϥޤ�Ȥ���Ƥ��ޤ���
- ����ϥ��֥�8�ʤȤ��쥮��顼8��R-8�ˤȸƤФ�Ƥ��ޤ�����
- �����16mm�ե����ΤޤȤ���Ϫ�����륢�ѡ������Ⱦʬ�Υ������ˤ�����¦�Ť�2�ȥ�å��ˤ��ƻ��Ƥ��Ƥ��ޤ�����
- ����������˥ե�����������ڤ�Υ����2�ܤȤ���8mm�ҤαǼ̥ե����Ȥ��ޤ�����
- 16mm�ե�����ξ�ܤΥե�����Ȥä���Ĥ��ڤ�Υ���Τǡ��ѡ��ե��졼��������¦�����Ȥʤ�ޤ���
- �ޤ��ѡ��ե��졼�����ι���ˡ��Ʊ���ǡ��ѡ��ե��졼�����ι��ο����ܡʥѡ��ե��졼�����ԥå���16mm�ե�����Ⱦʬ�ˤ������Ƥ��ޤ�����
- ���֥�8�η�����16mm�ե�����ή�Ѥ��ä��Τǡ��ѡ��ե��졼������礭��ͭ����ˡ���̤��ե����Ҥ�60%�����Ȥ��ޤ���Ǥ�����
- �ե�����˥�����ɥȥ�å����ߤ��褦�Ȥ���ȡ�����˲�����ˡ�������ʤ���Фʤ�ʤ��Ȥ�������������Ƥ��ޤ�����
- ����������褹�뤿��ˡ�1965ǯ��8mm�ե�����33ǯ�֤�Ʊ�����ʤ��ä���Ǥ��͡��ˡ�16mm�ե����Ҥ��夨��8mm�ե����ҤȤ��ơ�8mm�ե�������ѤΥѡ��ե��졼�������������Τ������å���ꥹ���ѡ�8�Ȥ���̾����ȯ�䤵��ޤ�����
- �ޤ����ٻΥե����Ǥϥ���8�Ȥ���̾�����о줷�ޤ�����
- ���Υե����ϥ�����ɥȥ�å��ѤΥ��ڡ��������ݤǤ����Ф���Ǥʤ���ͭ��������ˡ���礭���ʤä�����Ǽ̲��̤μ������뤵�����夷�ޤ�����
- ���Υե�����ͽ�ᥫ���ȥ�å��������졢8mm�ե���५�������������ǻ��Ƥ��Ǥ���褦�ˤʤ���ؤʤ�ΤȤʤ�ޤ�����
- �����å��ǤϤ���¾�ˤ�Ϥ�16mm�ե������Ѥ��ơ��ѡ��ե��졼�������ˡ���������ˡ�������ѡ�8����Ʊ���ˤ������֥륹���ѡ�8�Ȥ����ե�������Τ��Ƥ��ޤ�����
- ��̣���뤳�Ȥˡ�35mm�ե���ࡢ16mm�ե�����ѤαDz襫���ˤϿ���Ф��ʤ��ä����ܤΥ������������8mm�ե���५���ˤʤ���ٻμ̿��ե����䥭��Υ���⡢���������륳���䥷�������ܸ��ءʸ����˥���ˤ����ʤ�������䤷�ޤ������ʥ���Υ��16mm�ե���५����Ȥä���ƻ�ɸ����Ѥ�Canon Scoopic 16 = ����Υ� �������ԥå�16������1965ǯ������¤���Ƥ��ޤ�������
- ���塼�ޡ��Ѥ����ʤ���������������������������Τǡ����ܤΥ�����Ϥ����������ʤ��Ф����Ѷ�Ū�˿���Ф����Ȥ����Τ��Ȥ��������Ǥ��ޤ���
- 8mm������������ܤΥ桼���ϡ�1960ǯ�夫��1980ǯ����̤��Ƥۤ�ΰ찮��Υޥ˥������Ǥ������ʳ����������������䤬���ԤǤ��ޤ�������
- 1980ǯ�彪���˥ӥǥ��ơ��ץ쥳��������Sony Handycam CCD-TR55�ˤ�ȯ�䤵��ޤ��������줬�����罰���礭�����������줿���ޥ��奢�ࡼ�ӡ������Ǥ�����
- �����ơ�1990ǯ����꤫��2000ǯ�Ϥ�ˤϥǥ����륫��餬��ڤ���褦�ˤʤäơ�8mm�ե���५���μ��פϤ����Ȥ���ޤ���礭�ʥ������֤��뤳�Ȥʤ����äƤ����ޤ�����
- ��
- ��
- ��
- ��
- ����70mm/65mm�ե������202004.029���ˡ�2023.06.12�ɵ���
- 70mm�ե������緿����ѤΥե����Ǥ���
- �Dz�ե����ϡ�1890ǯ���溢��35mm�ҤΥ�����ե����ǻϤޤ�ޤ������������ܤζҤ�70mm������ե�����Ȥä��Dz���������餢�곫ȯ���ʤ���Ƥ��ޤ���������������ä��褦�Ǥ���
- ���硼�����������ȥޥ�����ե������ä����顢���Ǥ�70mm�ե�����¸�ߤ��Ƥ��ޤ�������������ʤȥǥ�������ˤ�70mm�ե�����Ⱦʬ�ˤ���35mm�Υ�����ե��������ȥޥ����ʸ�����Ȥ����������Ĥ�����ޤ���
- �������ѡ��ե��졼�����Τʤ��Ӿ��Υ�����ե����Ǥ������ʥѡ��ե��졼�����ϥ�������¦�Dzù��Ƥ��ޤ�������
- �Dz�ϡ�35mm�ե���५��餬��ή�Ȥʤ�ޤ�����
- �ܳ�Ū��70mm�ե����Dz褬�����Τϡ�40ǯ�Фä�1930ǯ��Ȥʤ�ޤ���
- ���θ�����Фơ�70mm�ե����ε��ʤ�3�ĤȤʤ�ޤ�����
- ����ܤϡ�1930ǯ��Υ�����I�ʥ������������4�ѡ��ե��졼�����ˤǡ�����ܤϷ����ѤΥ�����II�ʥ������������10�ѡ��ե��졼�����ˡ�������3���ܤϡ�1950ǯ���Ⱦ�θ�ڱDz軺�Ȥ�65mm/70mm�ե���൬�ʡ�5�ѡ��ե��졼�����ˤȤʤ�ޤ���
- 65mm/70mm�ե����ˤϤ⤦��ġ��ʲ��˽Ҥ٤Ƥ���IMAX������ޤ���
- �����15�ѡ��ե��졼�����β�����αDz�Ǥ���
- ��1930ǯ���70mm�ե����Dz��
�ܳ�Ū��70mm�ե������Ѥ����Dz衦��Ǵۺ�꤬�Ϥޤä��Τϡ�1928ǯ��FOX�Dz�Ҥ��ϻϤ���William Fox��꤬������Fox Grandeur�ʥ����ǥ奢�ˡס� = grand cinema�ˤ���Ȥʤ�ޤ���
- 70mm�������ߥå��������ȯ�����졢1929ǯ��Mitchell FC����餬�����ޤ���
- FC�����Ȥ�Fox-Case��ά�ǡ�����餬Fox-Case�Ҥ�����ʸ���줿���Ȥ�����Ƥ��ޤ���
- Case�Ȥ�Theodore Case��Τ��Ȥǡ���ϲ���������ǥե����˸���ǻ�ټ��Υ�����ɥȥ�å���ȯ�������ͤȤ����Τ��Ƥ��ޤ���
- ���Fox��ȶ�Ʊ�Dz�ҡ�Fox-Case�ҡˤ���������ɥȥ�å����Ȥ����줿70mm�ե����Dz����Ϥ�ޤ�����
- ��������1929ǯ�������������Ϥޤä�ǯ�ǡ��礬����ʷײ���ܺä���FOX�Dz�Ҽ��Τ�бĤ��������ʤ�ޤ�����
- 1930ǯ������70mm�ե����Dz���Ǥ���Τϥ������륹�ȥ˥塼�衼����2�ۤ����Ǥ�����
- ���λ��κ��ʤ�����ߥ塼������ǡ�Fox Movietone Follies of 1929�פǤ�����
- 70mm�ե����Dz��1930ǯ�夫��1950ǯ����Ⱦ�ޤǤ���ۤ��礭�����ʤϤʤ��դ����Ų����Ƥ�����������ޤ���
- �����ˤ��ȡ�70mm�ե����Ϥ��δ�˺�����Ƥ��ơ��Dz軺�Ȥϡ�35mm�ե�����Ȥä����顼����������ɥȥ�å���ʣ����Υ�����Ȥä��磻�ɲ��˿ʤ�ǹԤä��Ȥ���ޤ�����
- ˺����줿70mm�ե���ब���ٸ�ľ�����Τϡ�1940ǯ���Ⱦ���ƥ�����������ʤ���Ǥ���
- �ƥ�Ӥ��о�ˤ�äƱDz�ȳ��Ϥ��ʤ�δ���������ä��ȸ����ޤ���
- �ƥ�Ӥˤʤ�̥��Ū�ʱ���������졢���ΰ�Ĥ�����̾�Ǥ��Ǥ���65mm/70mm�ե����Ǥ��ä��ȸ����Ƥ��ޤ���
- ��1950ǯ�夫���70mm�ե����Dz��
- 70mm�ե���५���ˤ�뻣�Ƥ��Ƴ����줿�Τϡ�1955ǯ�Ǥ���
- Michael Todd��1909.06 - 1958.03�˻��American Optical Company�ˤ�äơ�Todd-AO�ʤȤäɤ��������ˤȤ����֥��ɤ�70mm�ե����磻�ɥ������Dz褬����ޤ�����
��American Optical Company�ϡ�1869ǯ�˥ޥ����塼���åĽ����϶Ȥ����������������ѤΥ��饹���������롢�Ż����֤ʤɤ�꤬�����褿Ϸ�ޡ�Todd-AO�γ�ȯ�ϡ��Хåե����� NewYork��Ʊ�ҤǹԤ�줿�褦�Ǥ����濴��ʪ�ϸ��ؤ���̾��Dr. O'Brien����
- Todd-AO�ϡ�������ȯ���줿���ͥ�ޡ�Cinerama��3���35mm�ե����Ǽ̵���Ȥä�145°�磻�ɥ�������ǡ����κ�ޤϴѵҤ���Υ������λ���ѡˤ��й���������̤ξ���ѤȤ��Ƴ�ȯ����ޤ�����
- ���ͥ�ޤ�35mm�ե�����3�ܻȤ��Τ��Ф���70mm�ե����1�ܤ���������Ū�˴�ñ�������Ȥ������ʤΤ褦�Ǥ������ʼºݤ�3��Υ�������ߤΤĤʤ��ܤΥ���䡢Ʊ�����ơ�Ʊ���Ǽ̡�������Ʊ���ʤɵ���Ū�ʲ����¿�����ä��褦�Ǥ�����
- Todd-AO�����ƥ��ȯ����ˤ����ꡢ�磻�ɥ������ˤ��������θ����Ѳ��������Ķʤ��褹�뤿�ᡢ������̾�ʥ��֥饤������Τȷ��ơ��ºݤθ������������American Optical Compnyn�˰������ޤ�����
- ������1930ǯ��˳�ȯ�����ߥå������70mm������Mitchell FC�����ˤ�65mm���Ѥ˲������ޤ�����
- ����Τ�Τ�30���ޡ��äǻ��Ƥ���ƾ�Ǥ���ޤ������̾��24���ޡ��äǤ�����
- ���ƻ��ˤϥ�����ɥȥ�å�����ɬ�פʤ��Τǡ������ʤ����Ҥ�65mm�ҤΥե����ǻ��Ƥơ��ץ��Ȼ��˺���2�����ͥ�ʥե����ξü��2.5mm x 2 = 5mm�ζҡˤȥѡ��ե��졼��������¦�˺������줾��1�����ͥ�ι��6�����ͥ�β������ʥ�����ɥȥ�å��ˤȤ���70�����ե����ˤ��ƾ�Ǥ��Ƥ��ޤ����ʾ���ȡ���
- ���äơ�70mm�ե�����1930ǯ��Τ�ΤȤϰۤʤäơ��ѡ��ե��졼�����η�����ԥå�����֤��ä���ΤȤʤ�ޤ�����
- ���Ƥ�65mm�ե�����Ȥ��Ȥ����Τ���1930ǯ���70mm�ե����ƤȤ��礭���ѹ����Ǥ�����
- Todd-AO�Υ�����ɥȥ�å��ϡ�����������6�ȥ�å��ˤʤäƤ��ޤ���
- Todd-AO�ˤϤ⤦�����ħ�����äơ�70mm�ե������˵�Ͽ���줿������ɥȥ�å��Ȥ��̤ˡ�35mm�ե����Τ��٤Ƥ˼��������ƥ���ܤ���Ͽ���ե������Ѱդ��ơ�����˥�����ɤ�����ƾ�ǻ�������Ʊ�������Ƥ��ޤ�����
- ���ˤ�����������ä������ƥ�Ǥ�����
- Todd-AO���ǽ�κ���̾�ϡ��ߥ塼������Dz�Ρ�Oklahoma�סʥ�����ۥޡ�1955ǯ�������ǥߡ����ھ��ޡˤǤ�����
- Todd-AO�Ϥ��θ��80������������ס�1956ǯ�������ǥߡ����ʾޡˤ�꤬���ޤ�����
- Todd��ε��¡����Ե����Ρ˸奫��饷���ƥ���ѥʥӥ������������Ѥ����ˤʤꡢTodd-AO�Ҽ��Τϥ�����ɥȥ�å������Ϥ���褦�ˤʤ�ޤ�����
- Panavision��Panavision�ǡ�Ʊ������MGM�Ȱ���MGM Camera 65�ʤΤ���Ultra Panavision 70�ˤ�ȯ���Ƥ��ޤ�����
- MGM��бĤ��פ路���ʤ���MGM65��1960ǯ�ʹߡ�Panavision�����Ȥ����Τ���褦�ˤʤ�ޤ���
- Panavision�����⸵��MGM���ߥå�����˺�餻��70�����ե���५���Ǥ�����
- Todd-AO�����ˤ��Dz��1960ǯ�ʹߤ�֥�����ɥ��֥ߥ塼���å��ס�1965ǯ�������ǥߡ��ޡ����ʾޡ����ھޡ�¾�ˡ��֥ѥåȥ�����ַ��ġס�1970ǯ�������ǥߡ��ޡ����ʾޡ����ľޡ�¾�ˤ�³���ޤ�����
- ��MGM��Panavision�ۡ�
- Todd-AO��70mm�ե�����Ȥä��磻�ɥ������ʤ�Ƥ����Τ�Ʊ�������ˡ��Dz��۵���MGM��Panavision���ȶ�Ʊ����70mm�ե����Dz����Ϥ�ޤ�����
- Todd-AO���磻�ɥ���������ʤˤ�������̤��Ǥ�����ˡ��ȤäƤ����Τ��Ф���MGM�ϥե�åȤʥ������˲�Ĺ�β��̾�Ǥ�����ˡ����Ѥ��ޤ�����
- MGM���ѥʥӥ����Ҥ��Ф��ơ������̻��Ƥ��Ǽ̻��˸����ᤷ�ƱǼ̲��̤�磻�ɲ������Ϥ���������ΤǤ���
- Todd-AO��1958ǯMike Todd��ιҶ������Τˤ����������塢Panavision�Ҥ˵ۼ�����ޤ�����
- Panavision�ҤϤޤ���1962ǯ�ʹߤ�MGM����ͭ���Ƥ����ߥå�����Υ�������������褦�ˤʤäơ����ҥ֥��ɤ˼�����ǹԤä��褦�˻פ��ޤ���
- �����Υ�����Super Panavision70��Ultra Panavision70�Ȥ��ƹ��ۤ���70mm�ե����Dz�μ�Ƴ���äƤ����ޤ�����
- ����饫���ο�¡���ʥե����ࡼ�֥��ȡˤ��ߥå����륫����Ǥ��ꡢ���̤κ����̤��ƻ��Ƥ���������֡ʥ��ʥ�ե��å����Anamorphic lens�ˤ�Panavision�Ҥΰ�����ΤǤ�����
- �������֤ǡ��֥٥�ϡ��ס�1959�ˡ��֥���ӥ��Υ�����ס�1962�ˡ��֥ޥ��ե�����ǥ��ס�1964�ˡ��֥�����ɥ��֥ߥ塼���å��ס�1965�ˤ�꤬���ƹԤ��ޤ�����
- 70mm�ե����Dz�ϡ��Ȥˤ������⤬������ΤǤ�����������뤳�ȤϤǤ��ޤ���
- ǯ��2��3��ʿ�Ѥ�����Ȥʤ�ޤ�����
- ���Υڡ����ϸ��ߡ�2020ǯ�ˤǤ�³�����Ƥ��ơ�������������65mm�ե���५���ȤϤ��������֤���������Ȥ����ϥǥ����륫���ǻ��Ƥ����Խ����Ƥ�����ˡ���Ȥ��Ƥ��ޤ���
- �ޤ���¿���αDz�����Ū�²���35mm�ե����ǻ��Ƥ��졢70mm�ե����Ǽ̤ΤǤ���Dz�ۤˤ�35mm�ե����→70mm�ե����˳���ʥ֥������åס˥ץ��Ȥ��줿��Τ��۵뤵���褦�ˤʤ�ޤ�����
- 65mm�ե����ǻ��Ƥ���Τ����Ѥʤ��⤬������Τǡ�35mm�ե���५���ǻ��Ƥ��ơ�70mm�ե����˳���ץ��ȡʥ֥������åסˤ��ƾ�Ǥ��뤳�Ȥ�1970ǯ�夫��Ԥ��ޤ�����
- 35mm�ե�����Ȥ����γ�����ϸ��夹��Τǡ�����̱Ǽ̾�Ǥϰ���θ��̤�⤿�餷�ޤ�����
- ��
- ��
- ��¬�Ѥˤ�70m���ե���५��餬�Ѥ�����ƹ�ιҶ����軺��ʬ��ǻȤ��Ƥ��ޤ�����
- ��ޤ��ƹ�Photo-Sonics�Ҥ�70mm�ե���५���70-10R�ϡ���¬�ѤΥե�����Ȥä������ǡ��Dz��ѤΥե���൬�ʤȤ��̤Ǥ�����
- �ե����Ϸ�¬�Ѥ˺��줿70mm�ե���� Type II�Ȥ�����Τ��Ȥ�졢�������Υ������������10�ѡ��ե��졼�����ˤǤ�����
- ����IMAX ��2020.04.29�ˡ�2020.06.28�ɵ���
IMAX/OmniMAX�ʤ����ޤä��� / ����ˤޤä����ˤ�70mm�ե������Ѥ����礭�ʥ�����������αǼ̥����ƥ�Ǥ���
- ��
- ���Υ������������130ǯ�αDz�˾����Ǥ�äȤ��礭�ʥ������Ǥ��ꡢ����ʾ���礭���αDz�Ϻ���Ϻ���ʤ��������ȸ����Ƥ��ޤ���
�礭�ʥե�������Ѥ���Ȥ������������꤬�����ޤ���
- ���������Υե���ॵ�����Ϸк�Ū�ʴ����ʥե�����塢�������ץ�����ˤ��������ƾ�����������礭�ʥ����α��ѡˤ⤢��ޤ���
- ����Ū�ʴ������鸫��ȡ�IMAX���礭�ʥ������Υե��������Ԥ������ư�����꤬����ޤ���
- 1�ô֤�24���Υ��ȥå�&�������֤��ե����ϡ����ʤ����٤��餦���Ȥˤʤꡢ����6��ǯ240���1500��λ��ѡˤζ��ȤDzݤ�����ե����ؤ���١ʻ�����ȥѡ��ե��졼�����ξ��סˤ�ͤ���ȡ�IMAX�ե����αǼ̥����ƥब��ˤǺǸ�Ǥ���Ȼפ虜������ޤ���
- IMAX��OmiMAX�ΰ㤤�ϡ�IMAX�������ʿ�̥���������ͤ��������Ǥ���Τ��Ф��ơ�OminiMAX��Ⱦ�ɡ�����ε��̱Ǽ������ǡ���ŷ�Ǽ̤ȤʤäƤ��ޤ���
- IMAX�����ƥब���Ѥ���ե�����70mm�ե����ʻ��Ƥ�65mm�ե����ˤǡ�15�ѡ��ե��졼�����ʬ��1���̤ˤʤ�ޤ���
- 70mm������ե��������������������Ȥ��ơ��ե����ζҤ�ĥ������ʲ�2.772" x 2.072"��70.4mm x 52.6mm�ˤˤ��Ƥ��ޤ���1970ǯ�Υ������ˡ�
- ����αDz�ե���ब�о�ʪ�˸����äƻ��ƥ�����ե���������������餻�Ƥ���Τ��Ф���IMAX�ϲ����������餻�Ƥ��ޤ���
- ���Υ����̿������狼��褦�˥ե����ޥ�����ϲ����֤ˤʤäƤ��ޤ���
- ��
- ����
- ��
- �� IMAX�ҡ�Multiscreen Corporation��1967����2023.06.09�ɵ���
- ����������ȯ�����Τϥ��ʥ����ȥ���ȶ�٤�Mississauga�ˤ��ä�IMAX�ҡ����Ȥ�Multiscreen�ҡ����ʥ����ꥪ��Galt��1970ǯ�˼�̾���̾�ˤǡ�1967ǯ�����ߤ���ޤ�����
- IMAX�����ۤ��Τ�Roman Kroitor��1926��2012�ˤǤ���
- ���ȥꥪ��������������'67�Υ��ʥ��ۤα���Ÿ���֥�ӥ�� = In the Labyrinth�פ˴ؤ�ꡢ35mm�ե�����70mm�ե�����Ȥä��ޥ����������꤬�������ˡ�IMAX��פ��Ĥ��������Ǥ���
- ��Ϥ������ۤ��Ȥ˹�����ͧ�ͤ�Ʊ���Ż��Ƥ���Greeme Ferguson��1929��2021�ˤȡ��ӥ��ͥ����������̤����뤤Robert Kerr��1929��2010�������ȡˡ�����˵��ѼԤ�William Shaw��1929 �� 2002����Ford�Υ��˥��ˤ�4̾�����ä�Multiscreen�Ҥ���Ω����ޤ�����
- �ǽ��IMAX�ζ��Ȥ�1970ǯ�����������ٻΥ��롼�ץѥӥꥪ��ǹԤ��ޤ�����
- ��19m x ��13m�ε��祹�����ˡ�17ʬ�֤Ρ�Tiger Child�סʸפλơˤ���Ǥ���ޤ�����
- ����������������Ǥ������ڤ�κŤ���Τ��ٻΥ��롼�ץѥӥꥪ��Ǿ�Ǥ��줿IMAX�ȥ���ꥫ�ѥӥꥪ��η���Ф��ä����Ȥ����3ǯ�����ä���Ϥ褯�Ф��Ƥ��ޤ���
- IMAX�α����Ϥ����ϤǤ�����
- ��
- ��
- ��������� - �ٻΥ��롼�ץѥӥꥪ��ſ����
- IMAX�ҡ����Ȥ�Multiscreen�ҡˤ���Ω���줿1967ǯ����������IMAX�����ƥ�Ϥޤ��������Ƥ��ʤ��ä���
- ��餬���Ƥ���Ÿ����ˡ���Ϻ���³������ǡ����ܤ��饰�åɥ˥塼�������ӹ������
- �������'70�λ뻡�Ĥ����ȥꥪ��������˽и�������Ƥ��ơ��������̤�����
- ������ǡ��ٻζ�Ԥ��Ƭ�Ȥ���36�Ҥ����ޤ��ٻΥ��롼�פ�Ʊ�Ҥε��Ѥ�⤯ɾ��������������ٻΥ��롼�ץѥӥꥪ��α���Ÿ��������Τߤʤ餺���ϡ��ɥ������γ�ȯ���ޤ��Ѱդ�����Ƥ��������
- ���Ϥ��ο����Ф˾����ꤷ���Ȥ�����
- �緿������Ǽ̤���Ǽ̵��ϡ����λ����Ǥϻ�Ժ����빽������ʳ��Ǥ��ä���
- 36�ҤΥ��롼�פ���ΰ�ҥ���Υ�ϡ��緿�Ǽ̵��ѤαǼ̥�����߷ס���¤���뤳�Ȥ���«���Ƥ��줿��
- �Ǽ̵����߷פ�줫��Ϥ�Ƥ������ˡ�������������褿��
- �������ȥ�ꥢ�Υ֥ꥹ�٥�˽���Ǽ̵���������Ron Jones�Ȥ�����ʪ������Ū�ʥե�������굻�ѡ�Rolling Loop�סʥ�����롼�סˤ��õ�����äƤ��뤳�Ȥ��狼�ä���
- ���������ϡ�����Υե�����ߤ���Ȥ��Ȱ�äơ��ե��������Ǥ����Ƥ���Ⲥ���Ф��ƥե���������Ȥ�����ΤǤ��ä���
- ���ϥ֥ꥹ�٥�����ӡ��ѥƥ�Ȥ��Ĥ���Ǥ������ϥꥦ�åɤζ�������ݤʤ��Ȥˤʤ����ˡ�Ron Jones���õ����㤤��ä���
- ���ε��Ѥν����ˡ���ư�ֲ�ҤΥ��˥��Ǥ��ä�������ͧ��William Shaw�˥��Ȥ��ư������졢Rolling Loop���ѤҤΤ�ΤȤ��ƿ������Ǽ̵���ȯ������
- �����Թ�����Shaw�ˤϱǼ̵��κ��ܵ��Ѥ��ʤ��ä����᤹�٤Ƥˤ錄������Ū�ʿ������Ǽ̵�����夲�뤳�Ȥ��Ǥ�����
- ������롼���ν���߷פȥץ��ȥ����פϤǤ�����ΤΡ����ϥȥ�ȥ���ҤˤϤ��������ࡼ���ʥե�������Ԥ�����ˤϤۤɱä�����Ϥ���ꥪ���ϥߥ�ȥ����ظ��漼�˻������ߡ����Ի��Υե������ϤΤ����������ȼ¸��ˤ����Ф�����ο����������ǥ����������ǡ��Ǽ̵��κ�Ŭ���������뤲�Ƥ��ä���
- ��
- ��
- IMAX����顧
- 65mm�ʻ��Ƥ�65mm�ե���ࡢ�Ǽ̤�70mm�˥ץ��ȡ˥ե�����Ȥäơ�15�ѡ��ե��졼����������Ԥ������⿷������Ǥ��ä���
- MGM��Robert Gaffney��1931���ˤ��顢�ǥ�ޡ������������Υ�����߷ס���¤�Ԥ����뤳�Ȥ�ʹ���������Ȥ����줿��
- ���Υ��˥��ϡ��Υ륦�����ͤ�Jan Jacobsen��1919.12 �� 1998.06�ˤȸ��ä���
- ��ϡ��Dz�������Ǥ�̾���Τ줿��ʪ�ǡ��������̥������߷���������դȤ����ʥ������դ����ü쵡����¤��꤬���Ƥ�����
- ��Ҥ��ƥӥ��ͥ����礭�����Ƥ��������פǤϤʤ��ä��褦�ǡ����륿���Ū�ʻŻ������ȤȤ��Ƥ����褦�Ǥ��ä���
- Jacobsen�ϥΥ륦�������ޤ�ǡ��ƥ��������㡼�κ�������αDz蹥���Ǥ��ä���
- �ɥ��ġ��ϥΡ��С�����ؤ�̵�����̿���ؤ������´����ʸ�ϡ�16mm�ե����ˤ�������ز����Ǥ��ä���
- ´�ȸ塢�Υ륦�����Υ���������겻�����ѻդȤ���Ư������������1945ǯ��26�ͺ����ƹ���Ϥ�Dz��Ϣ�ε���Ū�Ż��˷Ȥ�ä���
- ���θ塢�ѹ���Ϥäƥ��ʥ�ե��å���ʲ��̺�����̾����Ƥ��ƱǼ̻����绣�Ƥ���������̥�ˤ��߷���¤�˷Ȥ�롣
- ���θ塢�ɥ��ġ��ߥ��إ�˰��ۤ��������ARRI�˼ҤȤ�ط����ʤ����ȼ��λŻ��Ƥ��ä���
- 1968ǯ4���Jacobsen48�͡ˤ˸������줿�����������塼�ӥå����ĤΡ�2001ǯ�����ι�פ�����Ǥϡ��û��ε���Ū�ʶ�Ϳ���Ȥ���Ƥ��롣
- ��ο�������ǺǤ��礭�ʻŻ������ʥ�����ˬ��롣
- 1968ǯ��Multiscreen�Ҥ�Graeme Ferguson��1929.10.07��2021.10.07�ˤ��ߥ��إ��ˬ�졢Jan Jacobsen�����̤�65mm�ե�����Ȥä��緿���������β�ǽ�����ù礤����ä���
- Multiscreen�ҡ�IMAX�ҡ�¦�ΰո��ϡ�15�ѡ��ե��졼������γ�ȯ�Ǥ��ä���15�ѡ��ե��Υ���餬�����Բ�ǽ�Ǥ���С������8�ѡ��ե��Υ����Ǥ�褯�������15�ѡ��ե��˳���ץ��Ȥ��ƥ��ꥸ�ʥ���������줫������ץ��Ȥ���ʢ�Ť��Ǥ��ä���
- Jacobsen�β����ϡ���������ݤʤ��Ȥʤ��Ƥ�15�ѡ��ե��Υ����Ϻ��롢�Ȥ�����ΤǤ��ä���
- Jacobsen�ϡ����ڥ�ϡ�������οͤκ�Ƚ�˰ܤä�4����ǥ�������夲����
- 15�ѡ��ե�����ο�¡���ϡ��ब���ĤƼ꤫����7- 1/2�ѡ��ե��Υࡼ�֥��ȤǤ��ꡢ�����ǥ�ˤ�����ߤ�7.5�ѡ��ե����ߤ���Ȥ��ƹ��15�ѡ��ե������빽¤�Ǥ��ä���
- �������������ϡ�1968ǯ��12��˥��ʥ������ꥪ����Galt�ˤ���Multscreen�Ҥ��Ϥ���줿��
- ���ΰ����塢���եꥫ�Ǥ�����ưʪ�Ƥ�������ե���ब�夬�ä���
- ���������Ǿ�Ǥ���Dz�ָפλơפ������Ǥ��ä���
- Jan Jacobsen��IMAX�����ƥ�ؤθ��Ӥ��礭����
- ���ä�4����ǥ������߷ס���¤���������⥫�����̤�25kg�������ʾ�η��̤˻ž夲����
- ���ξ����κ�ä������Ϸ�ϴ�Ǥ��ä���
- ��浡�Υ����ϡ������������ӥλ�����˻��Τˤ��ä��˲����Ƥ��ޤä���ΤΡ����θ��12���ۤ�������30ǯ�ʾ��ФƤ�Ȥ�³����졢16��Υ���餬���ڡ�������ȥ��ͳ�DZ��������Ω�äƤ��ä���
- IMAX�β����ϡ����ߤΥǥ���������˴��������18K����������ȸ����Ƥ��ޤ���
- IMAX�ϡ���ȯ���顢�Ƽ�Υ��٥�ȤǤ��̺ܶŤ��Ȥ��ƾ�Ǥ���Ƥ���Τߤǡ�1970ǯ���������������ʹߤξ��ߴۤ��ϸ��ȥ���Ȥȥ亮��ȥΥ��ݡ������Spokane�ˤʤɿ�����ۤɤ�������ޤ���Ǥ�����
- 1990ǯ�����������ϤǥܥĥܥĤȾ��ߴۤ��֤����褦�ˤʤꡢ��Ǥ�����ʤ������ƹԤ��ޤ�����
- IMAX���������ϡ�2020ǯ���������Ƥ��濴��450�۰ʾ夢�뤽���Ǥ���
- ���ܤǤ�36�ۤ��ꡢ�Ĵۤ���25�ۤ�ޤ��߷�61�ۤ˾��ޤ���
- ���ߤǤϡ�70mm�ե����Ǥξ�ǴۤϾ��ʤ��ʤäơ����ܤǤξ��ߴۤϼ������Ω�ʳشۤ�IMAX DOME�ΤߤȤʤꡢ¾��35�ۤϡ��ǥ����륷��������4K�����Υǥ�����ץ������������ˤȤʤäƤ��ޤ���
- �ե����Ǥξ�Ǥϡ������촶�����ϤϤ����ΤΡ��ե�����Ǥ�ݻ����Ƥ����Τ����Ѥʤ褦�Ǥ���
IMAX�����ƥ��Ȥäƺ��줿�Ƕ�αDz�ϡ�Christopher Nolan�ʥ��ꥹ�ȥե������Ρ����1970.07.30 - �˴��Ĥ��꤬����2017ǯ���ʡ�Dunkirk�סʥ��륯�ˡʥ�ʡ��֥饶�����۵롢�����ǥߡ����Խ��ޡ�Ͽ���ޡ������Խ����ޡˤǤ���
- �Ρ������Ĥϡ�IMAX�ˤ��Dz���������ǡ���μ꤬�������ʡ��������ʥ��ȡ�2008�ˡ��������ʥ��ȥ饤����2012�ˡ��������ƥ顼��2014�ˡ�TENET �ƥͥåȡ�2020�ˡ����åڥ�ϥ��ޡ���2023�ˤϡ�IMAX�����ǻ��Ƥ��줿��ΤǤ���
- IMAX�����ƥ�ˤ��Dz�����ϻųݤ������Ѥǡ���Dunkirk�פǻȤ�줿���̥���� = IMAX MkII LW�νŤ���25kg���ꡢ��¡���������硢�������֡����Ѥ���ե�����塢�����塢�ץ������ͤ���Ȼ��Ƽ��Ԥ⸷�������Ȥ��顢�����ش�����ץ��ǥ塼������Ĥ�65mm/70mm�ե����Ǥλ��Ƥ���IMAX�ǥ�����˰ܹԤ��뷹��������ޤ���
- �Ρ������Ĥϡ�������������65mm�ե����ˤ�������ݤȤ���CG�ʥ���ԥ塼������ե������ˤ������������Τ��Ƥ��ޤ���
- IMAX������Ȥ������ޥ�ϡ������˶��������Ϥ˼���������ͤǤʤ��ȶФޤ�ޤ���
- �����餯���ܤǤϤ����Ȥ����ʤ��륹���åդ⡢���Ĥ⡢�����ƺ��Ϥ�ʤ��ΤǤϤʤ����Ȼפ碌�ޤ���
- �����ϡ�����Ū����¤����ϹԤ鷺���ΤߤΤ褦�ǡ�����������Υ�������120���ߤۤɤʤΤ�1���ߤλ��ͤΤ��륫���Τ褦�Ǥ���
- 65mm/70mm�Dz�ե������륳���å��Ҥϡ��Ρ������Ĥ���Ĺ���ե���ඡ��η�����魯���Ȥ��Ǥ����Τǡ��ӥ��ͥ���³�ΰ���λ��ʤ��Ǥ�������ƻ����ޤ������ٻΥե����ϡ�2012ǯ�˱Dz�ե������¤��λ����ű�ष�Ƥ��ޤ�����������135�����פΥե�������¤���³���Ƥ��ޤ��ˡ�
- IMAX�˻Ȥ���65mm/70mm�ե����κ���ϡ�Estar�ʥݥꥨ���ƥ�١����ե���ࡢ�ޥ��顼�ե����ˤ��Ȥ��Ƥ��ޤ���
- ���Υե����ϤȤƤ�פǤ����ڥåȥܥȥ�˻Ȥ��Ƥ���PET�ʥݥꥨ�����ƥ�ե��졼�ȡˤ���֤�����ޤ���
- ���κ���Υե����Ȥ��ȥ������ߤ���Ȥ���������쥸���ȥ졼�����ԥ��ޤ�Ƥ��ޤ��ȸ����Ƥ��ơ����̥桼���ˤϤ��ޤ�Ȥ�����ޤ���Ǥ�����
- ���������Ф��Ƥ�ե���ब��������Τǡ��ե���ब�ͤޤ�ȸ������Υᥫ���Υ�������礭���ȸ����Ƥ��ޤ�����
- ��������70mm�ե���������̲�����Ȥʤ�ȡ��Ǽ̤Ǥ��ѵ���������Ȥʤ뤿�ᶯ�פ�Estar�١����ե���ब���Ѥ��줿��ΤȻפ��ޤ���
- IMAX�����ˤϡ�1000ft�Υե����ʽ���5.3Kg�ˤ����Ƥ�Ǥ���3ʬ��λ��Ƥ��Ǥ��ޤ���
- �ޤ���2022ǯ5��ˤϡ�6���IMAX����Ѥ��������å���Ʈ���αDz��Top Gun Meveric�סʥȥࡦ���롼�����ˡʥץ��ǥ塼�������������ॺ���֥�å����ޡ������ġ����祻�ա����������ˤ���Ǥ���ޤ������ʤ�������6���IMAX�����ϥե���५���ǤϤʤ���SONY�Υǥ����륫���Ǥ�������
- ���αDz�ϡ�1986ǯ�˸������줿��Top Gun�פ�³�ԤȤ������٤���Τǡ���Ʈ����F/A-18E/F �����ѡ��ۡ��ͥåȡ��ޥ��ɥͥ롦�����饹�����ˤ�IMAX������ܤ��ơ���ͥ���餬��Ʈ�������Ȥ����������ʤ����Ƥ�ԤäƤ��ޤ���
- 1986ǯ�κ��ʤϡ�35mm�ե���ब�Ȥ�졢��Ʈ���Υ��åץԥåȤˤ�35mm��®�٥�����4�ѡ��ե�200���ޡ��á�Photo-Sonics 4ML�ˤ��Ȥ�줿���Ȥ����Ƥ��ޤ���
- IMAX�β����ϡ�1�ե졼��70mm x 52mm�Ǥ���
- �����ǥ���������˴���������ե����ξ���濴���β����٤�70��/mm���٤���Τǡ����������70mm�Υ�����������Dz����٤���Ф��ȡ�
- 70�������/ mm�� x 2 ����/����� x 70 mm x 2 ��baye������r = 19.6k ����/1��ʿ�饤��
- �ȴ�������ޤ���
- bayer�����ʥ⥶���������ˤ�2��ݤ����Τϡ�ñ��CMOS�ǻҤ�RGB�Υ⥶�����ˤʤäƤ��ơ�ʣ���β��Ǥǿ��������Ƶ��پ�����������Ӥˤʤ뤿�ᡢBayer�����ǻҤϲ��ǿ�ʬ�β����Ϥ������碌�Ƥ��ʤ����ᡢ�ե���������2�ܤ�ݤ���碌�Ƥ��ޤ���
- �ºݤϡ��������濴���Τߤ��������٤Υǥ�������ǿ��˴������졢�������Ϥ�������β����Ϥϻ������ʤ���Ƚ�Ǥ��ޤ�������ϥե���������ǤϤʤ������Ѥ�������ǽ���餦�Ȥ����Ǥ���
- ���������Dz�վ���濴���˥ե�����������äƤ���м������Ϥ���ۤɤβ����ϤϽŻ뤵�줺���������ϲ��������Ƥ�ͤ�ư�λ��Ϥδط����礭������ȤϤʤ餺�����뤷�Ƥ������̤�����٤��Ǥ���м������ϥܥ��Ƥ��Ƥ��礭������Ȥʤ�ޤ���
- ���ƥ�ϼ������β����Ϥ��濴���������������������Ƥ��Ƥ����������ƥ����ǽ�䥹������ĥ����ǥܥ����ĤߤϽФޤ���
- IMAX�Υ�ϡ��ϥå���֥�åɥ����ǻȤ�����Ƚ����Ȥ��Ƥ���褦�Ǥ���
- 1970ǯ���������dz�ȯ���줿�����Υ�ޥ���Ȥϡ�Bronica�ޥ���ȡ����ܤ���Ƚ�����Ǥ���֥��˥��Υޥ���ȡˤ����Ѥ���Ƥ��ޤ�����
- �������λ��ѤϤ�������̵���褦�ǡ���Ƚ������ǥ�����������Τ�ʹ�������Ȥ�����ޤ���
- IMAX���Ƥ⡢�������äơ�ñ�̥�λ��Ѥ��ۤȤ�ɤǡ����f40mm�Ȥ�f30mm�ι��ѥ���Ȥ��Ƥ���褦�Ǥ���
- �����Υ�λ��ƻ���Ѥϡ��г�����94�٤���110�٤Ȥʤ�ޤ���
- IMAX�ǥ����륫���ˤϡ�Arri�Ҥ�Alexa IMAX��6560 x 3102���ǡˤ��Ȥ��Ƥ��ޤ���
- IMAX 3D�Ǥϡ�Vision Research�Ҥ�Phantom65��4096 x 2440���ǡˤ�2��Ȥ��ޤ�����
- 18K�����Υե����β������٤�ȥǥ���������봶�����ݤ�ޤ���ɡ�����Ū�˹ͤ���ȥǥ�����Τۤ������Ѥ��䤹���Ȼפ��ޤ���
- �����Υǥ����륫���ϡ�35mm�ե����Dz�Ǥ��֤������ƻȤ��Ƥ��륫���ʤΤǡ������4K���٤Υ����ˤ�Ȥ��ΤǤ����IMAX�������Ϥ��ޤ�ʤ��ʤ�ΤǤϤʤ����Ȼפ��Ƥ��ޤ��ޤ���
- IMAX�ǥ�����Ǥϡ��ݥ��Ƚ����Dz�����֤�Ԥä�4K�����β�����8K�����ʾ�ˤ��Ƥ���褦�ˤⴶ���ޤ���
- ����2023ǯ���ߤαDz�ե������¤����2023.06.09����
- Kodak���ƹ�˥塼�衼����Rochester�˼ҤǤϡ�2023ǯ���ߤ�Dz�ե�������¤���Ƥ��롢�Ȥ����٤�������YouTube�˺ܤäƤ��ޤ�����
- ��Eastman Kodak�Ҥϡ�1892ǯ�˥˥塼�衼����Rochester���϶Ȥ��������ե���������Ȥ���������ε��ϤǷбĤ�ԤäƤ��ޤ�����2000ǯ�夫��Υǥ���������֡���Ǥϡ���Ƭ�����äƤ����ˤ�ؤ�餺�Ȥ˾�뤳�Ȥ��Ǥ�����2012ǯ��Chapter 11���˻������ޤ�����2013ǯ�ˤ�Kodak�Υե�������礬���ԥդ��ơ�Kodak alaris�Ҥ���Ω��������ե������¤�ȥǥ�����������եȥ�����/�ϡ��ɥ����������³�����Ĥ��뤳�Ȥˤʤ�ޤ�������
- �����å��Υե������¤���ͻҤ�ܤ����Τ륯��åפ��ʲ��Τ�ΤǤ������Υ����Ȥϡ��ʳر������ä˥ϥ����ԡ��ɥ�����Ȥä���®���ݤƤ����ʬ��Ƕ�̣����ȥԥå������Ƥ��륵���ȤǤ���
- ��
- �����å��ϤɤΤ褦�˥ե�������ΤǤ���?�ʥ����å��ե����ȥ�ĥ������ѡ���1/3�� - Smarter Every Day 271��2022��
- ��
- �����å��ϤɤΤ褦�˥ե�������ΤǤ���?�ʥ����å��ե����ȥ�ĥ������ѡ���2/3�� - Smarter Every Day 275��2022��
- ��
- How Does Kodak Make Film? - Smarter Every Day 286��2023��
- ��
- Kodak Film Factory Tour ��2017��
- ��
- ��
- ����IMAX�αǼ����� - Rolling Loog����
- IMAX�αǼ̵��ϡ��̾�Υѡ��ե��졼������ߤ���Ȥ������Ȱۤʤ������롼�ס�Rolling Loop�˼����Ѥ��Ƥ��ޤ���
- 70mm�ե������礭�ʥ������ǡ�����������15�ѡ��ե��졼�����Ȱ���70mm�ե����Dz��3�ܰʾ�����Ѥ���ĥե���������IMAX�Ǥϡ��̾���ߤ���Ȥ����ˤ�äƲ��٤�ե������Ǥ��Ƥ���ȡ��ߤ���Ȥ��ޤˤ�äƥѡ��ե��졼������������ˤʤäƤ��ޤ��ޤ���
- �ѡ��ե��졼������Ȥ�ʤ���ˡ���ͤ��Ф���ޤ������ե����١����϶��פʥޥ��顼�ե����ʥݥꥨ���ƥ�١����ե����ˤ��Ȥ��Ƥ��ޤ���
- ������롼�פȤϡ����Ի��˥ե������ȤΤ褦��"���ͤ�"�ʥ롼�סˤ��ꡢ����"���ͤ�"�ˤ�äƥե��������������������Ǥ���
- ���������ϡ�������̤��Ф����ѡ����㡼��ľ���ˤ��ͤ�ʥ롼�סˤ��뵡�����ߤ������ѡ����㡼���̲ᤷ����Ϥ��Τ��ͤ���������빽¤�Ȥ��Ƥ��ޤ���
- ���ѡ����㡼��ʬ�ϡ����꤬ͤ�̲ᤷ�Ƥ�����ϤޤȤ�˸����ʤ��Ĥ�������ˤʤ��ΤΡ����꤬ͤ�̲ᤷ���塢���Τ��꤬ͤ���ޤǤϥե�����ư���ʤ������Ż߾��֤�³���ޤ���
- �����Ż߾��֤λ��˥���å������Ƹ����̤���Ǥ��ޤ���
- �Ǽ̵��ˤϡ��Ż����٤���뤿���registration pin �ʥ쥸���ȥ졼�����ԥ�ˤ�ѡ��ե��졼����������Ƥ��ޤ����ʥ쥸���ȥ졼�����ԥ�ϡ��롼�פ����Ǥ����ڤ�Ư���Ƥ��ޤ�����
- �ե���ब���ѡ����㡼����Żߤ��Ƥ���֤˱Ǽ̥���å������Ƹ���ե������̤�����������ͤ����ޤ���
- �롼�פ����ѡ����㡼���̲᤹��Ȥ��ϡ�����å������Ĥ��Ƥ��Ʊ�������ͤ��ʤ��褦�ˤ��Ƥ��ޤ���
- ���������ϡ�������ߤ���Ȥ��ޤ�Ȥä��ե�����������ե����˥��ȥ쥹���ä˥ե����ѡ��ե��졼�����ˤ��ʤ����ᡢ70mm15�ѡ��ե��졼���������굡���Ȥ��Ƥ��ɹ��ʷ�̤Ȥʤ�ޤ�����
- ���ѡ��������ϡ��ե���ब��ư���Ƥ��ʤ��Ż���ϥե�����̤�ե�åȤˤ��뤿������֤ǥե����ѡ��������˵��夵�����ʤ�����������������褦�˥쥸���ȥ졼�����ԥ���������ư������٤���Ƥ��ޤ���
- ��������1�ô֤�24���֤��ƱǼ̤Ƥ��ޤ���
- ���ޤ����ºݤ�IMAX�αǼ����֤ο�¡���Ǥ���Rolling Loop�������Ǥ���
- ��ޤ�����������Τ�ʿ������Ǥ������������ǤǤϲ�ž���굡���ʥ���������ˤ��Ȥ߹���Ǥ��ޤ�����������ʤ���롼�פ���Τǡ�������롼�פȸƤ�Ǥ��ޤ���
- ��ޤϡ�IMAX�αǼ̵���ȯ����William Shaw�1970ǯ�˽Ĥ������ѻ������Ȥ˺Ʋ������ʤä���ΤǤ���
- ���οޤϻ���ʤΤ褦�ǡ�1970ǯ���������������Ǽºݤ˻Ȥ�줿��Τϡ������������礭����37.5"��952.5mm�¡ˤǡ������8����åסʥ롼�פ������̡ˤ����֤���180��ž/ʬ��24���ޡ��äαǼ̤�ԤäƤ��ޤ�����
- ��ޤ�4����åפȤʤäƤ��ޤ�������������¤��������Τ�Τ��2�ܤۤɾ�����������ʬ���������β�ž����2�ܤ��ä��Ȼפ��ޤ���
- ���ε�����ȡ��ե���ब�����������������̤Ƚи���2�Ĥ˥��ץ����åȤ����ꡢ�ե���ब����˳��߹�äơʤ��ä���Ȥ������ꥹ�ԡ��ɤǡ˥������������ꡢ�����ƽФƹԤ��ޤ���
- �����������塼���ȥ��ơ������졼��ˤϡ��ե���ब�̤뤹���֤��ߤ����Ƥ��ޤ���
- �������Ƥ��������ƥե����˥�����Ĥ��ޤ������������Ƥ�������˥ե���ब�٤äƤ��ޤ����ԤǤ��ʤ��ʤ�ޤ���
- ���ơ������졼��ΰ�ü�ʾ�ޤˤ����벼¦���ˤˤϱǼ̸����˱�äƳ������ʥ��ѡ����㡼�ˤ��ߤ����Ƥ��ơ���������ե������������������ͤ����褦�ˤʤäƤ��ޤ���
- ���γ�����ʬ�ǥե������Żߤ�����ɬ�פ�����Τǡ��쥸���ȥ졼�����ԥ��ߤ����Ƥ��ޤ���
- �������ץ����åȤ���������ޤ��ե����ϡ���ή�ˤ���쥸���ȥ졼�����ԥ�ʾ�ޤλ���������û��6���ˤ�ư�������ȥåפ��뤿�ᡢ�����ߥ��碌�Ʋ�ž���Ƥ��륮��å����Υ����������塼���ʾ�ޤλ���������û��8��30ʬ�ˤˤ������ƥ롼�פ���ޤ���
- ����åפ�Ⱦ����������ž�ȤȤ�˥���åפ�������ä��ե����롼�פ���Ĺ���Ƥ������쥸���ȥ졼�����ԥ��ȴ����ȡʾ����������û��5��30ʬ����3���˾������ʤäƤ����ޤ���
- �쥸���ȥ졼�����ԥ�˥ѡ��ե��졼������μ¤����줱��Фʤ�ʤ����ᡢ�롼�פ�Ĺ���������ɤ���������ʤ���Фʤ�ޤ���
- �롼�פ��빽¤��롼�פι⤵���������ʤɤ����Ť������ʤ���ˤ����äƤϡ��٤����¸��Ȼ�Ժ��������ͷ����Ԥ�줿�褦�Ǥ���
- �äˡ��������ץ����åȤ��饮��åפ�����ե����ο������٤Ƚ���λ��ʤ�����Ͻ��פǡ������ǥ롼�פ���Ĺ���礭�����Ѥ�äƤ��뤿�ᡢ�ե���������������ʤη����䥸���åȥ�����Ȥäƥե��������פ��ʤ���ޤ�����
- �ޤ����쥸���ȥ졼�����ԥ���������ʳ��������ѥ����åȥԥ�����֤��ơ��ѡ��ե��졼������μ¤���������빩�פ�ʤ��줿�褦�Ǥ���
- ���������ˤ�äơ��ե����Ǽ̻������λߤޤ����٤�0.03%�������������ɤ��0.003����� = 0.076�����ˤȶˤ�����٤ι⤤��Τˤʤꡢ���ġ��ե����ؤ����ԥ������ˤ�ƾ��ʤ��ʤꡢ5000��ʾ�αǼ̤ˤ����ƥѡ��ե��졼������»���ϺǾ��¤Ǥ��ä��ȸ����Ƥ��ޤ���
- ���ѡ���������
- �Ǽ̤�Ԥ����ѡ��������ʥ쥸���ȥ졼�����ԥ��볫��������ޤλ���������6���ˤˤϡ�����Ǥ��Ф�����Υ��ѡ�����ץ졼�Ȥȥե����ѡ�����ץ졼�Ȥ˵۰������뤿��ο������֡�����ȵ��������Τ����2���Ȥ��������������Ȥ߹��ޤ�Ƥ��ޤ�����
- ���ѡ���������ʿ�̤ȤϤʤ餺�����������ζ�Ψ�˹�碌����¤�Ǥ��뤿�ᡢ�������˱Ǥ�������������طϤ�ɬ�פ��ä��褦�Ǥ���
- ����å����ȸ�����
- �ե����롼�פ��륮��å����ϼ����ʥᥤ��å����ˤ��⤦�����Ƥ��ơ��Ǽ̥��פ���θ������ե�������ͤ���ʤ��褦�ˤʤäƤ��ޤ�����
- �ᥤ��å�����90�٥��줿���֤ˤ⤦��ĤΥ���å��ʥե�å�������å������ˤ����äơ��������̤ϱǼ̸����θ����̤�����å��ȤʤäƤ���褦�Ǥ���
- ���������ե�å�������å����ϳ������ȼ�������ߤ�2�Ȥ����ߤ���졢����å��������������β�ž�ˤ�ä���ͳ������ʥ��ѡ�����ˤ��ڤ�Ȥ���2��å������ڤäƤ��ޤ�����
- �Τ���24����/�ú����αǼ̵���1����2��Υ���å������ڤä�1�ô�48��Υ���å�����ԤäƤ��ޤ�����
- 24Hz�Ǥϥ���ĥ����礭���ΤǤ���
- IMAX�⤽���Ƨ������48��Υ���å�����ԤäƤ��ޤ�����
- ����ɤ��Υ���å�����48��ʬ���ФǤϤʤ���1/48�ô֤�1���ޱǼ̤�2ʬ�䡢�Ĥޤ�96Hz�ǥ���å������ڤäƤ��ޤ����ʲ����ȡˡ�
- 1���ޤ�1/24�äǤϤʤ��ʤ�1/48�äʤΤ��ȸ����С��ե��������뤿���1/24�ä�Ⱦʬ���Ĥޤ�1/48�ä����Ƥʤ��ƤϤʤ�ʤ��ᡢ�������Ƥ�Τ�1����1/48�äȤʤꡢ���λ��֤�2��Υ���å������ڤ�Τ�24Hz�ֳ֤�2����å���@96Hz�αǼ̤Ȥʤ�ޤ���
- ��
- ��
- ����å�����Ư���ȸ��������֤Ϥ��οޤ�����ɤ��ޤ���
- ������IMAX�αǼ̵��αǼ̥��פϡ�20kW��25kW��30kW��3����Υ����Υ硼�ȥ��������פ��Ѱդ���Ƥ��ޤ�����
- 500�פ�1kW�Υ����Υ���פϸ������Ȥ�����ޤ�����25kW�Υ��פϸ������Ȥ�����ޤ���
- �ȤƤ⤿����������Ϥ���ޤ���ȯǮ�⤹�����̤Ǥ���
- 10��åȥ��10kg�šˤξﲹ�ο��7�ä�ʨƭ�����Ƥ��ޤ��ޤ���
- ����Ū�ˤϡ���������ο��۴Ĥ����ƥ��פ���䤵�ʤ���Х��פϿ�ʬ�Ȼ����������餬��»���Ƥ��ޤ��ޤ���
- ���θ�����Ȥäơ���������������25 lm/ft2�ʥա��ȡ����٥�ȡˡ�86 nt����1,500�륯���ˤǾȼͤǤ��������Ǥ���
- �����ʥ����Υ���סˤϡ����ʿ�̿ޤξ��������濴���������ͤ���ȿ�ͥߥ顼��90���ޤ�ʤ����Ƴ�������Ƴ���졢�ե�����ȼͤ��ޤ���
- ����̤�����ȥ���Υ�γ�ȯ����f=150mm��f/2.0���Ȥäơ��ٻΥ��롼�ץѥӥꥪ���43' x 62' (13.1m x 18.9m�ˤΥ���������Ƥ���ޤ�����
- ������롼�������ϡ��ե�����̵������٤�������ʤ��ɹ����������Ȥ��ơ�IMAX�������ʹߤ��������ʿ�ã���Ǽ̵��˸¤餺�����ѥ����ˤ���Ѥ��褦�Ȥ��Ƥ��������ʻ�ߤ��ʤ�����褿�褦�Ǥ������õ����ڤ�Ƥ���⤽�μ�Υե���ൡ�郎����뤳�ȤϤ���ޤ���Ǥ�����
- �����ǥ��Ϥ��Ф餷������ɡ����Ѳ��ˤ����������꤬���Ѥ��Ƥ��뤳�Ȥ����������Τ�ޤ���
- ��
- ��
- ���������ʰ���������� ��1998.09.07��
���μ̿��ϡ�1980ǯ�夫��1990ǯ��˻ȤäƤ������ե��������Ǥ����ʼ̿���1985ǯ�˻��ơˡ�
- 16mm����ͥ��ե�����ѤΤ�ΤDZѹ������ä��ȵ������Ƥ��ޤ���16mm�Dz�ե����θ����ȸ�������ΤϤޤ��Ȥˤ�ä����ʺ�ȤǤ���
- 30m��100ft�ˤ��Ĺ���ե�����ż��Ǹ�������ΤϷ빽�����ޤ���ȤǤ�����
- ��������������ϥ���ѥ��Ȥ�400ft��120m�ˤޤǤ�����ե�����ưŪ�˸������Ƥ���ޤ��ơ�
- �����2��åȥ�Υ��ǰʲ���5�����äƤ��ޤ�����
- ��������→��������→���奿��→��������→����
- �Ÿ���AC100V15A��
- ��ƻ�Τ����ˤ����Ƹ����������Ǥ��ޤ���
- ��������2��åȥ�Ⱦ������ΤǴ�ñ�˸����դ��Ϥ����Ȥ��Ǥ��ޤ���
- �������֤ϡ�100ft��30m�ˤ���1���֤Ǥ���
- 30m/1hr = 8.3mm/�äΥե��������Ȥ������Ȥˤʤ�ޤ�����
- ��
- ��
- ��
���ȥåפ����
- �ڥե�������������1998.09.07�ˡ�2020.05.13�ɵ���
- ��
- ����
- ��
- ���顼�ե�����Ĺ����¸������붲�줬���� ����ե����ϡ���°�䤬�ĤäƤ��뤿�����˰��ꤷ����¸�Ǥ��ޤ�������С�����ե����ϡ����幩�������Ƥζ䤬���٤�����ή���졢��������2��ȿ������ȯ�����ץ�������Ĥ�ޤ���
- ����ȯ�����ץ顼�ϡ��糰���ʤɤζ������˼夯�����۸��ʤɤ�Ĺ���֤��餵��������ޤ���
�ե�����Ĺ����¸�ˤϡ������Ȳ��٤���Ǥ��ż�����¸����ɬ�פ�����ޤ���
- ��
- ��
- ǻ�پ��� �ե�������ε�Ͽǻ�٤ϡ��ͥ��ե�����10�ӥå� = 1:1000���١��㤨�С�100 �륯����10,000 �륯���ˡ���С�����ե�����7�ӥå� = 1:100���١��㤨�С�100 �륯����10,00 �륯���ˤ�Ͽ���뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
- ��Ͽ���ΤȤ��Ƥϵ�Ͽ®�٤�®�������ʥߥå������Ȥ�ޤ���
- �ե����Ǥϡ�ǻ�٤�ɽ��ñ�̤�D1.0�ȸ���ɽ������������Log�˴ؿ�ɽ���Ȥʤ�ޤ���
- D��Density��ǻ�١ˤ�ά�Ǥ���
- Dǻ�٤ȥե������Ʃ��ΨT��%�ˤδط��ϼ����̤�Ǥ���
- ������T = 1/10 D x 100
- ����������������T: �ե������Ʃ��Ψ (%)
- ����������������D���ե����ǻ�� (������ʡ�ǻ�١ˡ�
- D0.0��ǻ�٥����ˤϡ��ե����˲���ǻ�٤�̵�����ȤǤ����������̤äƤ��ʤ���ȴ����Ʃ���ե�����Ʃ��Ψ100%�ˤ�ɽ���ޤ��� D1.0��10%�θ���Ʃ�᤹��ǻ�٤�ɽ���ޤ��� ����ϡ�ǻ�٤�1�������Ʃ��Ψ��1/10�˸��ꡢ0.3���1/2���ĸ���ޤ��� �ե����ǻ�٤ϡ��ե����ǻ�ٷפ�Ȥä�D�ͤ��ɤߤȤ�ޤ���
- ��
- ���ޤ�������Ū�ʥե�������������Ǥ���
- �����̤��Ф��ƶ�����ɤΤ褦��ǻ�٤�Ȥ�Τ��Ȥ������������Ǥ���
- �ޤβ������ե����˾ȼͤ����������ˤ��̤ǡ�Ϫ����E�ʾ��٤Ȼ��֤���碌�����ͥ륮���̡ˤ��п���ľ�����ͤǤ���
- �ļ��ϡ��ͥ��ե�����ǻ�٤��п��ͤ�ɽ���Ƥ��ޤ���
- ���οޤ��顢�ȼ�Ϫ���̤��Ф���ե����ǻ�٤ϡ��ʤ��餫�ʻ��ʤ�ζ����ˤʤäƤ��뤳�Ȥ��狼��ޤ���
- Ϫ���̤ϡ������������Ƥʤ��ȥե�����ǻ�٤Ȥ��ƾ�餺���ޤ�ɬ�װʾ��Ϫ���̤�Ϳ����Ȥ���ʾ��ǻ�٤��������Ȥ��Ǥ������֤ä�ǻ�٤����äƤ��ޤ����Ȥ��Ƥ��ޤ��ʥ���ꥼ�������ˡ�
- Ϫ����E�ϡ��ե�����̤���������٤�Ϫ�����֤��Ѥǡ������ͥ륮���̤��������ޤ���
- �����Log�п������ƤƤ��ޤ����顢LogE = -3���ϡ�1/1000�륯�����ä�ɽ����LogE = 3.0���ϡ�1000�륯�����ä�ɽ���ޤ���
- �������Ƥߤ�ȡ��ե��������������ξ�п������Ȥʤ�ޤ���
- ���ɽ��γ�ʥ���ޡˤȽ�Ƥ���ޤ���������ϡ�Ϫ���̤��Ф���ե����ǻ�٤η�����ɽ���Ƥ��뤳�Ȥ��狼��ޤ���
- γ=1�Ȥ����Τ�Ϫ���̤�ǻ�٤�1:1���б����Ƥ�����ˤʤ�ޤ���
- ����Ū�ʥե����ϡ�γ��0.8�ˤʤ뤳�Ȥ��ᡢ�����ˤ����Ƥ�γ=0.8��ɸ����Ȥ��ơ������λ������ե�����������Ҳ𤷤Ƥ��ޤ���
- γ��0.8�Ȥ����ȡ��ºݤ�����Τ�ǻø����٤ƥե�������α��Ƥ�0.8�ܤν��餫����Τ��Ѥ�뤳�Ȥˤʤ�ޤ���
- �ʳؼ̿�������ˤϡ�Ϫ���̤ȥե����ǻ�٤δط����ɤ��狼�ä������褤�ΤǶ�����ľ����ʬ��Ϫ��������褦��Ϫ�л��֡���ʤꡢ����Ĵ�ᡢ����Ĵ����Ԥ��ޤ���
- Ϫ���ϡ����֥�ǻ�٤ζ��դΡ������䡢ǻ�٤�ǻ���ָ���������Τ�����Ū�Ǥ���
- �ºݤ�����Τ����뤵���ϰϡʤ���������塼�� = latitude�ˤȸƤ�Ǥ��ޤ���
- ASA100�Υե����Ǥ��ȡ��������LogE��3.0�ʾ�Ȥ�ޤ��Τ�����Τ����뤵��1:1000�˵ڤ����뤵���ϰϤ�ե�������˵�Ͽ���뤳�Ȥ���ǽ�Ǥ���
- �Ĥޤꡢ�ե���ॹ����ʡ������ե��������ǻ�٤�1:1000�ޤ��ɤߤȤ��С��ե��������1:1000�ξ�������뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
- ���γ�Ĵ��ԥ塼���Ѹ�ΥӥåȤ�ɽ����10�ӥåȤޤǤξ������Ĥ��Ȥˤʤ�ޤ���
- ���ʤߤˡ��ե�������ǤϤʤ�CCD������ŷ�δ�¬�Ѥ�CCD�����ˤϡ�ǻ�٤�16�ӥåȡ�1:65,000�˳�Ĵ�����Τ����Τ���Ƥ��ޤ���
- CCD�ǻҤδ��Ĥϥ��ꥳ��Ǻ���Ƥ��ơ����ꥳ��ϸ����Ф����Ҵ��ǡ�Ǯ�ˤ���CCD���ȯǮ�ʤɤˤ��Ǯ�ΤФ�Ĥ��˥Υ�����ʬ���ޤ����1:100,000���٤Υ����ʥߥå��������ޤ���
- X����ؿ��ǤǤϡ����Υե�����Ȥä�X���̿��ꤳ��X���ե���फ�鴵�Ԥο��Ǥ�ԤäƤ��ޤ���
- ������ɱơʤɤ������ˤȤ����ޤ�����X���������ե�������������Դ����Υǡ�����ͽ��Ƭ������Ƥ��������������٤��Ѳ���Ȥ����ޤ��줿�и��ȴ���ȯ�����ޤ���
- �ä˥�������ȯ���ˤϡ��ۤ�Τ���äȤ����۾��X���ե���फ���ɤߤȤ�ʤ��ƤϤʤ餺��CCD������Ϥ���Ȥ����Żұ�����X���ե�������ǽ���ɤ��Ĥ�2010ǯ������ޤ�X���ե���ब�Ȥ��Ƥ��ޤ�����2020.05.11�ɵ�����
- �� ��
- ��
- ��ASA���١�ISO���١ˡۡ�ASA��ISO�˴��٤�����ˤĤ��ƽҤ٤ޤ���
- �ե�������ˤϸŤ��Τǡ����ޤǤ��������ʴ��ٵ��ʤ��Ѥ����Ƥ��ޤ�����
- ���Ȥ��С��ɥ��ĤǤ�DIN���١����ܤǤ�JIS���١��ѹ�Ǥ�BSI���������Ǥ�GOST�ȸ������Ǥ���
- ���ʤ���������Ȳ��������ؤʤΤǡ���ݵ��ʤ�ISO�����줵���˻�äƤ��ޤ���
- ISO���٤ϡ�ASA���١�American Standard Association�����ε��ʤ�ANSI = American National Standards Institute�����ȤǤ���ˤ⤫����餺���ʤ����ե���ശ�٤����ϸŤ�ASA�������ĤäƤ���ˤ����Τޤ��������ޤ�����
- ���äơ��ե���ശ�٤�ISOɽ���ϡ������ASA����ɽ����Ʊ���Ǥ���
- ISO��=ASA�˴��٤η�����ϡ��ɤΤ��餤�ξ��ʤ����̤ǥե����ǻ�٤������뤫���ܰ¤�ɽ���ޤ���
- �Ĥޤꡢ����Τΰ����Υǥ��ơ���ʤ�Ϫ�Фǵ�Ͽ�Ǥ��봶���ब���٤��⤤���ȹͤ��ơ���ޤ���������������ʬ�Ρ����֥����ʬ�����̤��Ϥä��ꤹ��ǻ�١����ʤ�����١���ǻ�� + ���֥�ǻ�� + 0.1�� = 0.1D�ˤ����������������Ϫ����Ea�εտ��Ǵ��٤�ɽ�����Ȥˤʤ�ޤ�����
- �ե����ˤ�äƤϡ�����Ϳ���Ƥ�ʤ��ʤ�ȿ������ǻ�٤��Τ�ʤ���Τ�����ޤ�����0.1Dǻ�٤ˤʤ�Ȥ��θ��̤��ե���ശ�٤ˤʤ�Ȥ����Τ����ݥ���ȤǤ��� �ե����ϡ������ˤ�ä�Ϫ�����Ф���ǻ�١ʤ��ʤ���áˤ��Ѥ�äƤ���Τǡ�����Ea������⤦������̩���������ɬ�פ�����ޤ���
- a����LogEa���1.3�礭�����ʤ����LogEb�ˤȤ�����������ǻ�٤�0.8�ˤʤ�褦�˸������ޤ���
- ��������γ�����ˤ��Ƥ�����Ea���ͤ����ꤷ��ASA���٤���ޤ���ASA���٤ϡ�
- ������������ASA��ISO�˴��� = 0.8/Ea����������������Rec -47��
- ���������ޤ���
- ���ä�ASA100�Υե����ϡ�Ea��1/125��=0.008�ˤλ���ASA100�ȸƤ֤��Ȥ��Ǥ��ޤ���
- ����ϡ�0.008�륯�����ä�ɽ���ޤ���
- �ĤޤꡢASA100�Υե�����̤�0.008�륯�����äθ��̤�Ϳ�����0.1D��ǻ�٤����뤳�Ȥˤʤ�ޤ���
- �� ��
- ����
- �����ե����β�����
- �ե���༫�Τβ����Ϥϡ�100�����/mm �� 200�����/mm���٤���ǽ������ޤ���
- ����ϡ�1/200mm��1/400mm��2.5μm�ˤ�ʬ��ǽ�����������ե�������Ѥ������������ȤʤäƤ��ޤ���
- ���β����Ϥ����ˤ����٤Τ褤���㡼�Ȥ�ե�����̩�夵����Ϫ�������������ޤ���
- ���������ե�����ǻ�ٷפǷ�¬���ƺ٤����Ȥ�����ɤ��ޤ�ʬ��Ǥ��Ƥ��뤫��Ƚ�Ǥ��Ʋ����Ϥ���Ƥ��ޤ���
- �ޤ����ü�ʤ�ΤǤϡ����饹�Ĥ�Ȥä��ۥ�����ե��Ѥδ�����Ǥ�1,000�����/mm���٤���ǽ����äƤ��ޤ���
- ����Ū�ˤ����Υե����λ��IJ����Ϥ����°����Ф����ȤϺ���ǡ������ǽ�䥫���Υե����������١��ե�����ư�����ΰ��������ե�����̤ΰ�������Ƨ�ޤ�����������ϤȤ����������ǥե���५���β����Ϥ���Ƥ��ޤ���
- �����β�����ɾ���ˤĤ��Ƥϡ�����ˤĤ����ס�http://www.anfoworld.com/Lens.html#Resolving Power�ˤȤ������ܤˤ�ܤ�������Ƥ��ޤ��ΤǤ����ͤˤ��Ʋ�������
- ��
- ��MTF�ۡ�Modulation Transfer Function�ˡ� �ե����β����Ϥ�ɽ������Ū����ˡ��MTF������ޤ���
- �����Ϥ�100�ܤ���Ȥ��äƤ⡢�٤����������ä���ȵ�Ͽ����Ƥ��뤫�ɤ���������ˤʤ�ޤ���
- �ե����ˤ�äƤϤ鷺���˸����뤫�����ʤ������餤���������ĤäƤ��뤫���Τ�ޤ���
- �̤Υե����ǤϤ��ä���Ȥ��줤�˼̤äƤ��뤫���Τ�ޤ���
- ��������������β����Ϥ�ȥ饹�ȡ�ǻ�١ˤǼ����������˲����Ϥμ��ȿ����ļ��ˤ��Υ���ȥ饹�Ȥ�ɽ����������MTF�ȸ����ޤ���
- ���̤˲����Ϥ��⤯�ʤ�ȡʼ��ȿ����⤯�ʤ�ȡ˥���ȥ饹�Ȥ��㲼����Τ�����Ū�Ǥ������ե������ˤ�äƤ��ζ������Ѥ�äƤ��ޤ���
- �����Τϡ��⤤���ȿ��ǵ�˥���ȥ饹�Ȥ�������ꡢ�٤Ĥ�ΤϽ����˥���ȥ饹�Ȥ��㲼�����ꤷ�ޤ���
- ����������Ϥ��⤤���֤ޤǥ���ȥ饹�Ȥ�������˿��ӤƤ����Τ⤢��Ǥ��礦��
- ���Τ褦�ˡ����Ū�˼��ȿ��������ĤȤ������⡢MTF���Ѥ���Ф��ܤ����ե������β������������狼�äƤ��ޤ���
- �� ��
- �������������
- �ºݤ��ɤ��Ȥ��Ƥ����®�٥�������������ϤˤĤ��ƿ���Ƥߤޤ��� 16mm�ե���ॵ�����ι�®�٥����ϡ���ư�ְ����¸��Ѥ˻Ȥ���500����/ �û��Ƥ��Ǥ���16mm�ե�����ߤ���Ȥ�����®�٥���� ��ǥ�16-1PL���ƹ� Photo Sonics�ҡˤ䡢������ǥ�������dz�Ƹ���˻Ȥ���10,000����/ �äΥ�������ץꥺ�༰��®�٥����ʥ�ǥ�E-10���ʥå��ҡˤ��ɤ��Ȥ��ޤ���
- �����Ϥϡ�����������˸������ʤ�̵��ʬ�ե�����ߤ���Ȥ�����®�٥�����1PL�ˤ�����ͭ���ǡ�TV�ܤ˴�������Ȳ�1,200�� x ��840�����٤ˤʤ�ޤ���
- E-10�ϡ�����������˻��Ƥ��®�ˤ��뤿��β�ž�ץꥺ����졼������뤿������Ϥ�����������700�� x ��500�����٤ˤʤ�ޤ���
- 35mm�ե�����®�٥����ϡ�200����/ �äޤǻ��Ʋ�ǽ���ƹ� Photo Sonics�Ҥ�35-4ML������ޤ���
- ��������줤�ʤ��Ȥ���ƥ�ӥ��ޡ������ǥ������⡼����Ƥ˻Ȥ�줿�ꡢ�Dz軣�Ƥ��û�����������Ǥ��夲�����åȤ������Ƥ˻��Ѥ���ޤ���1970ǯ���2000ǯ�ˡ�
- ���μ�Υ����β����Ϥϡ�TV�ܤ˴�������Ȳ�2,200�� x ��1,600�����٤ǥϥ��ӥ����α�����ɤŨ���ޤ���
- �������Ϲ�®�٥����Ǥ��äǤ��äƱDz��Ѥ˻Ȥ���Dz襫��顢�ɥ��ġ������Υ�ɡ���ҥ����Ҥ� ARRI Flex 35 BL�ʤɤϡ��ե������®�˶�ư���ʤ������ե�����������١������٤��ɤ��ϥ��ӥ����ʾ�β�������Ƥ���ޤ���
- Nikon��Pentax�ʤɤ�35mm�饤���������Υ����ϡ��Ǥ��ڤǺǤ�����Ϥ���Ĥ�ΤǤ���
- ���β����Ϥϡ�TV�ܴ����Dz�4,300�� x ��2,900�ܤ���������16mm�ե�����Ȥä�E-10������36�ܤξ����Ϥˤʤ�ޤ���
- ���Τۤ���70mm�ե�����Ȥä���®�٥���� �ƹ� Photo Sonics�Ҥ�70-10R�ϡ��������������56mm x 56mm����TV�ܴ�����5,000�ܰʾ���������ޤ���
- ���Υ����ϡ�������ϥ��ӥ�����ƥ�ɾ���ѥ������Ȥ��ƻȤ��Ƥ��ޤ���
- �� �� ��
- ��
- ���˥�˥塼�С�������ʤ���硢
- ������å����Ʋ�������
- �� �� �� �� ��
- �������ε�Ͽ���� ����4 - - - �������������֡ʥ��������ƥե����� = Image Intensifier��
- ��������Ƥˤϡ���®�٥����˹ⴶ�ٸ������������֡ʥ��������ƥե����� �� Image Intensifier�ˤ����դ�����100��10,000�����٤δ��������������ˡ������ޤ���
- ����−������ƥե��������̾�I.I.�ᥢ�������ˤϡ��ŻҴɤΰ��Ǹ��������Ż������Ѵ������Ż�����ָ��̤ǺƤӲĻ�������Ѵ��������ͤ������ʾ�θ���������Ф���ΤǤ���
- I.I.�ǹԤ��������ϡ�����Ū�˰ʲ��μ��ǵ����ޤ���
- ������Ψ = �����Ѵ���Ψ x �����Ű� x MCP�Ż����� x �ָ���Ψ ��������������Rec -48��
- ��
- ��
- ���������̡�Photo Cathode��
- �弰�ϡ�I.I.�θ����������������Ż������Ѥ�������̤��̻Ҹ�Ψ���ŻҤ���®����ָ��̤ޤ���ã���뤿��ΰ����Ű����ڤ��ŻҤ��ָ��̤DzĻ�������Ѥ�뤿��ηָ���Ψ���ѤǷ�ޤ뤳�Ȥ�ɽ���Ƥ��ޤ���
- �����̤��̻Ҹ�Ψ��ָ��̤ηָ���Ψ�ϡ����Ѥ������ˤ�äưۤʤꡢ�����̤κ����ָ��̤κ����1940ǯ��ʹߤ��������ȳ�ȯ����ޤ�����
- �����̤κ����ɽ����1���20�ʤɤϡ����襢��ꥫEIA ��Electronic Industories Associ-ation�ˤ���Ͽ���줿���ťǥХ�����ʬ�������������դ���줿�ֹ�Ǥ��ꡢ���줬������ʬ��������������̾��Ȥ�������Ū�˻Ȥ��Ƥ��ޤ���
- �����̤ǺǤ��ɤ��Ȥ���S20�ޥ�����륫������̤ϡ�����ꥫ��A.H.���ޡ���Sommer�ˡ� = 1930ǯ����1970ǯ��˳�������¿���θ����̤�ȯ���ˤ�1960ǯ��˶�����ȯ�����������̤ǡ������Ȥ��ƤϲĻ�����Ф����˹ⴶ�٤���ǽ����äƤ��ޤ�����
- �ⴶ�٤ϼ��Ĺ��Ĺ�ؤδ��٤ο��Ӥˤ�äƤ��ޤ���
- ���θ����̤ϡ����Ѥ������˥ʥȥꥦ�ࡢ���ꥦ�������륫���°��¿�����Ѥ������ᡢ�ޥ�����륫������̤ȸƤФ�Ƥ��ޤ���
- S25�ޥ�����륫������̤ϡ�1971ǯ����ꥫRCA�Ҥdz�ȯ���줿��Τ���̾��ERMA��Extended Red Multi-Alkari�ˤȤ�ƤФ�Ƥ��ޤ���
- ����ϡ��̾��S20�̤�������5��6�ܡ���150nm�˸�����Τǡ��³���Ĺ��900nm��ã���Ƥ��뤿��I.I.�Τߤʤ餺�졼���������Ѹ��Ż����ܴɡ�����ȥ�ʥå��ʥ��������С�������®�٥����ˤ˻Ȥ���ʤɽ��פʸ����̤ˤʤäƤ��ޤ���
- ��
- ����������
- ���塼����˰��ä�����Ű��ϸ����̤��ȯ���������ŻҤ��Ϥ�Ϳ���ŻҤ��®�����ޤ���
- ��®���줿�ŻҤϷָ��̤˾��ͤ��ָ���ȯ���ޤ���
- �ָ����ŻҤ�®�٤ˤ�äƵ��٤��Ѥ��ޤ���
- ���äơ��ָ��̵��٤�Ʊ�������ŻҤ���������ˤϲ�®�Ű������㤷�ޤ���
- �̾��I.I.�β�®�Ű���15,000��17,000V���٤ǡ����˽Ҥ٤�MCP�ʥޥ����������ͥ�ץ졼�ȡ���¢��I.I.��6,000��7,000V���٤ˤʤäƤ��ޤ���
- �Ű���夲����Ż��������⤯�ʤ�ޤ�����ɬ�װʾ���Ű���夲�Ƥ���塼����ο������ٹ礤���θ���ʤ��ȥޥ��ʥ����̤ˤʤ�ޤ���
- �Ĥޤꡢ���塼����˻�α���Ƥ���ʬ�ҡʥ�����ˤˤ⥨�ͥ륮����Ϳ�������Υ����ָ��̤˾��ͤ��Ƹ����̤˸������ͤ��Ƥ��ʤ��Τ˷ָ��̤��Υ����ˤ�ä�ȯ���������꤬�����ޤ���
- ����ϥ��塼�֤μ�̿�ˤ�ƶ�����Τߤʤ餺���������Σ�/�ΤⰭ���ʤ�ޤ���
- �����ͤ�EBI��Equivalent Background Illumination�ˤȸƤӡ��ָ���ñ����������θ�«�ʥ롼���/cm2�ˤ�ɽ���ޤ���
- EBI �ϡ��̾��I.I.��4 x 10-11�롼���/cm2���٤Ǥ��ꡢ���塼�֤��礭���ۤɤ����ͤ������ˤʤ�ޤ���
- ��
- ����MCP�ʥޥ��������ͥ�ץ졼�� = Micro Channel Plate��
- MCP�ʥޥ����������ͥ�ץ졼�ȡˤϡ�I.I.���塼������Ȥ߹��ޤ��0.5mm���٤��������饹�Ĥǡ������φ10��12μm�ι���̵���˶�������φ25mm�ǿ�ɴ���ġˡ�ξü��100V��900V���Ű��������̤���θ��ŻҤ�1,000�����٤�2���ŻҤ����䤹��ΤǤ���
- MCP�ϡ����Ū���������Ѥǽ����I.I.�ˤϤ��줬��¢����Ƥ��ޤ���Ǥ�����
- MCP��Ƴ���Ǹ�����������Ū�˸��夷���Ѥ⥳��ѥ��ȤˤǤ���褦�ˤʤ�ޤ�����
- �ޤ�����3�����I.I.�ϡ����������������ʤäƤ����������Żҥ����������ʤ��������Ĥߤ�����ޤ���
- MCP�η����ϡ��ָ��̵��٤������Ȥ�ʤ�I.I.����⤯�ʤ�ʤ����Ȥȡ�MCP����¢����Ƥ���ʬ���������ϡ���Ĵ = �����ʥߥå�����㲼���뤳�ȤǤ���
- �ָ��̵��٤ϡ�����Ū�˥֥饦��ɡ�CRT�ˤηָ������٤����뤵��10,000�륯�����١ˤ�Ф����Ȥ���ǽ�Ǥ���MCP����¢�����1/300���٤�30�륯�����٤˸��äƤ��ޤ��ޤ���
- ����ϡ�MCP�Σ����ŻҤ��ָ��̤�10,000�륯�����٤ޤ����뤯����������ФǤ��ʤ����Ȥ��Ƥ��ޤ���
- ���ä����뤤�����᤹���®�٥�����MCP��¢��I.I.����³���Ƥ⻣�ƤϤǤ��ޤ���
- MCP����¢�������β����Ϥϡ�MCP�������Ф�����ŻҤ�MCP�γ���Ψ��ȯ�����Ʒָ��̤���ã���뤿�ᡢMCP�ȷָ��̤ε�Υ��Ǥ���������դ��ʤ��ȷָ��������ܥ䤱�Ƥ��ޤ��ޤ���
- ��������;���Ť���ȹ⤤�Ű��������äƤ��ޤ��Τ�������ɤ������Ƥ��ޤ��ޤ���
- ���Ű��������äƤ���ָ��̤�MCP��1/100mm���٤����٤�����뵻�Ѥ���Ω����1970ǯ��ˤʤäƲ����ϤΤ褤I.I.���Ǥ���褦�ˤʤ�ޤ�����
- ��
- �����ָ����Ѵ���Ψ
- �ָ��̤ϡ��ָ�����ƥ�Ӽ������Τ褦���ŻҤ��ָ��̤˾��ͤ��Ƹ���ȯ�������Τ�ȯ�����١�ȯ���ο���ȯ���Υ쥹�ݥ�ȿ�������Ǥ��������ʷָ��Τ���ȯ����Ƥ��ޤ���
- �̾�ָ��̤κ����Ƥ֤Ȥ��ϡ�EIA (Electronic Industrial Association�ˤ���Ͽ����Ƥ����ֹ��Ȥ�����11�Ȥ���20�Ȥ����Ƥ����ޤ���
- I.I.�ˤ褯�Ȥ���ָ��̤ϡ���20�ȸƤФ���Τȣ�11�Ǥ���
- ��20�ϲ��п��ηָ��Τǡ�������ָ��̤���Ǥ��٤ǻ��������Ūû����ħ���äƤ��ޤ���
- ��11���Ŀ��ηָ��Τǻ��������ʤ�����ǤϰŤ����������ޤ����̿����ƤǤϣ�20���ⴶ�٤������ޤ���
- I.I.���®�٥�������³���ƻȤ���硢���ηָ��̤ε��٤Ȼ���������ˤʤ�ޤ���
- ��®�٥����ϡ�10,000����/�äλ��ƾ��ǡ�����ȥ�ʥå��ʥ��������С�������®�٥���顢���Ū�ⴶ�٤Υ���顢1990 - 2000�ˤ�Ȥ����30,000�륯����16mm�ե���५���E-10��1980 - 1995�ˤǤϡ�150,000�륯�����٤ηָ��̵��٤�ɬ�פǤ���
- 150,000�륯�������뤵�ϼ���ָ��������뤵���������ޤ���
- ���ä�E-10��®�٥����ϡ��ָ����Τ褦�����뤵����I.I.��Ȥ�ʤ���л��ƤǤ��ʤ����Ȥˤʤ�ޤ���
- �ָ���ϡ����뤤��Τۤɻ�����¿������������ޤ���
- �����ȤϷָ��̤��ŻҤ�������ʤ��ʤäƤ⤷�Ф餯�δַָ���ȯ���Ƥ��븽�ݤΤ��Ȥǡ��졼���ʤɤϤ����������Ѷ�Ū�����Ѥ��Ƥ��ޤ�������®�٥����Ǥϡ����Υ��ޡʱ����ˤ��������������ۤ���Ƥ��ޤ�����Ū�Τʱ��������뤳�Ȥ��Ǥ����礭������ˤʤ�ޤ���
- �äˡ���ʰʾ���ŻҤ��ָ��̤������ä��Ȥ��ϻ�������ü��Ĺ���ʤ뤿�ᡢ���ξɾ���������������뤤����ΤǤλ��ƤǤ����դ�ɬ�פǤ���
- �դˡ��ָ��̤�û���֤������餻�����λ����ϡ�Ϣ³ȯ������ٶä��ۤɲ����Ǥ��뤿�ᡢ��4�����I.I.��Ȥä�MCP��û���֥���å������P20�ηָ��̻�����100μs�ʲ����ޤ��뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
- ����������4�����I.I.����ˤ�Ҥ٤��褦�˷ָ��̤���¤�����뤯�Ǥ��ʤ����ᡢ���뤯�Ǥ�����1�����I.I.���Ȥ߹�碌��2�ʼ��Ȥ��ƹ�®�٥�������³���ޤ���
- 1996ǯ���ѹ�Imco�ʢ��ѹ�Hadland�Ң�DRS�ҡˤγ�ȯ����ILS��Intensified Lens System�ˤ�����®�٥������I.I.�Ȥ��Ƥϲ��Ū�����ʤȤʤ�ޤ�����
- ILS�����Ѥ��Ƥ���I.I.�ϡ�����Ū���������Υ����ȼ����ܷ����������ƥե��������Ѥ��Ƥ��ޤ���
- �����̡��ָ��̤θ��¤�����φ40mm�������ǹ⥯�饹�Υ������������������ָ��̤���®�٥������Ѥ������ٹ�¤�ˤʤäƤ��ޤ���
- ���Υ��ץȤˤ�ꡢ����ȥ�ʥå����������С������������������ϥ����ԡ��ɥӥǥ���Kodak HS4540��MEMRECAM�ˡ�16mm�ե���५���E-10�Ǥ����夬��ǽ�ˤʤ�ޤ�����
- ��
�� �� �� ��ɽŪ�ʷָ��̺������ħ
- ��
- P1
- P11
- P20
- P22
- P31
- ����
- �졼����
- �̿�����
- �������
- �ηָ���
- ���顼�ƥ��
- ������
- �ָ���
- ����
- ��
- ����
- ��
- ��R.G.B.��
- ����
- �ĸ���10%��
- 24ms
- 60us
- 200us
- 25ms
- 600us
- �ָ��̺��統��
- �ʴ������١�
- 7,400�륯��
- 3,600�륯��
- 12,400�륯��
- 17,800�륯��
- 21,000�륯��
- ȯ����Ψ��K1��
- ��lumen/W��
- 520
- 137
- 480
- 520
- 230
- ȯ���θ�Ψ��K2��
- ��%��
- 5
- 17
- 9
- 6
- 22
- ���ͥ륮���Ѵ���Ψ
- ��K1 x K2��
- 31
- 26
- 43
- 31
- 51
- ��ħ
- �Ǥ�Ť��ָ���
- �ʥ���������ɡ�
- �Ŀ��˴��٤��뤿�� �̿����Ƥ˸��̡�
- P20����2��
- ������ɤ� ����Ū�ָ��̡� ���١���Ĵ��
- �Ȥ���ɹ�
- ���ٺǹ⡣ ����Ĺ����
- �ָ�������
- �������ΰ���Ū�ָ��̡����ٺǹ⡣
- ������
- ��
���ȥåפ���� ��
�� - ����������奤�������ƥե�����
- ��������I.I.�ϡ����������������1940ǯ�塢�����ѤΰŻ����֤��ᤫ���ƹ�RCA�Ҥdz�ȯ����ޤ�����
- ��¤�⥷��ץ�ǿ����� I.I. �����Ϥ˸����̡����Ϥ˷ָ��̤��ۤ��������ˤ��Żҥ���֤�������̤������Ф��줿���ŻҤ��Żҥ��������ǥ��������Ʒָ��̤���ã���ޤ���
- ���������ȷָ���������Ω���ˤʤꡢ��ʪ����Ȥ߹�碌����Ω�������ޤ���
- ������Ψ�ϡ�x 10��x 200 ��300�륯�����٤˷ָ��̵��٤�⤯���뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
- ��®�٥�����Ѥ��߷פ��줿��ΤǤϷָ����¤ε��٤���Ĺ��I.I.�������Ƥ��ޤ���
- ��ǯ�Τ�Τϸ����̤ȷָ��̤˸��ե����С���Ȥ��������Ѷʤ˽������Ƽ��դα����ĤߤȲ����Ϥ���夵���Ƥ��ޤ���
- I.I.����Ǥϰ²��ʤ��ả�Ǥ�Ż����֡ʥʥ��ȥӥ奢�ˤȤ��ƻ��Τ���Ƥ��ޤ���
- ��
- �����������奤�������ƥե�����
- ��������ϡ���������I.I.��MCP����¢�����������٤�����Ū�˸��夵������Τ�1960ǯ�夫��1970ǯ��ˤ����Ƴ�ȯ����ޤ�����
- φ10μm�Υե����С�����¤���뵻�Ѥ���Ω����Ƥ��Υ����פ�I.I.�δ����ޤ�����
- ������Ψ�ϡ������������1,000�ܤۤɸ��夷����ʸ��Ф���ƻ��������ޤ�����
- �������������������MCP��ȤäƤ��뤿��ָ��̵��٤�1/3���٤ȰŤ��ʤꡢ�����Ϥ�����ޤ���
- ��
- �����軰���奤�������ƥե�����
- 1970ǯ��ˤʤ�ȡ��ߥ�����������¤���Ѥȿ������Ѥ�ȯã���������̤ȷָ��̤�Ǥ��������Ť��� �ʶ��ܤ����ơ����֤�������ܷ�I.I.����ȯ����ޤ�����
- MCP��¢ ���ܷ�I.I.�ϡ����������I.I.�ι��������Żҥ������������Τ�Τǡ����˥���ѥ��Ȥˤʤ������٤���������Τޤޤǡ������Ĥߤ����˾��ʤ��ʤ�ޤ�����
- �Żҥ�����Ѥˤʤä���������̤��������Τޤָ������Ȥʤ���Ω���ˤʤ�ޤ�����
- �����̤������ͤ��줿���ŻҤ�MCP���̤ꤽ�Τޤָ��̤���ã���뤿��MCP��ޤ������-�ָ��̵�Υ��Ǥ������û�����ʤ��������ܥ��Ƥ��ޤ������Ϥ˱ƶ���Ϳ���ޤ���
- ����ѥ��Ȥʤ�����������I.I.�ȶ��������ɤ��Ȥ��Ƥ��ޤ���
- �ָ��̵��٤ϡ����������Ⱦʬ���٤�10��50�륯���ȰŤ���CCD�����Ȥ���³�ϲ�ǽ�ʤ�ΤΡ�35mm���ƥ��륫���Ǥ�ISO 400�Υե������Ѥ��Ƥ���1/2�ä�Ϫ����ɬ�פ����뤵�ǡ�����I.I.ñ�Τǹ�®�٥������Ȥ߹�碌��Τ��Բ�ǽ�Ǥ���
- �ޤ���1,000����/�ðʾ�λ��ƤǤ� 600μs��1ms ���٤λ�����ͽ�ۤ���뤿�����դ�ɬ�פǤ���
- ��
- ����������奤�������ƥե�����
- ��������I.I.�ϡ��軰�����MCP�ΰ����Ű���ѥ륹�⡼�ɤˤ���˾�������ʬ�Υ���å����Ԥ����ΤǤ���
- ���Υ����פθ�������¤�ϡ��軰����Τ�ΤȤۤȤ��Ʊ���ǡ��㤤��MCP�ؤΰ����Ű���DC��Ϣ³�ˤ��ѥ륹�⡼�ɤǤ��뤫�����Ǥ���
- 1980ǯ����MCP�Ű����å����뤿��Υ��硼�ȥѥ륹���Ű������å����ǻ�/��ϩ����ȯ����ƻ��β�����ޤ�����
- ���ߤǤϡ��ʥ��äΥ����ȥѥ륹����������ⰵ��ϩ�䡢2MHz�ι���ȥ�����ȯ������ǽ�ʹⰵ�ѥ륵������ȯ����Ƥ��ޤ���
- ��������I.I.�ϡ�CCD�������Ȥ߹�碌����å������Ȥ����ɤ��Ȥ��Ƥ��ޤ���
- ��
��
- ��
- ���˥�˥塼�С�������ʤ���硢
- ������å����Ʋ�������
- ��
��
��Anfoworld �����ޤ���